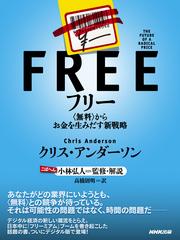
総合評価
(528件)| 140 | ||
| 210 | ||
| 99 | ||
| 9 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログタダより高いものはない! とはよく言ったものだが、まさにその通り。 この書籍にはタダのカラクリが多数まとまっています。 2025年の今、この本を読んで感じるのは『そーだねぇ』と同意するだけの浅いものになるかもしれません。 しかし、この本が書かれたのは2009年。今から16年前です。 その頃に読んだ読者はきっと『そーだねぇ、え?いやいやまた大袈裟な。。。!』みたいに感じてたんじゃないかなと。未来をある程度、当てにいく内容になってます。 緻密な調査と先見の目で書かれた名書、ぜひ読んでもらいたいです。
0投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「電子ブック戦争 日本の敗北」 https://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51312798.html
0投稿日: 2025.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログよく調べられた大作のWEB記事。 無料であることをテーマにした様々なビジネスモデルがまとめられている。テーマやイデオロギーありきな解説が目立たなくもない
0投稿日: 2024.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
評価はちょい甘め。日本語訳のせいなのか結構途中がしんどかったですが、ビジネスを考える上でのいろいろな示唆に富んでいて全体的にはまあまあ感。
1投稿日: 2024.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ1ビットでもデジタルに触れるビジネスマンにオススメ デジタルビジネス×無料のメカニズムがわかりやすく説明されている 行動経済学の要素もあるよ
0投稿日: 2023.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 無料という戦略。一度競争が始まれば無料がデフォルトになる。問題はそこから。顧客が料金を支払うように誘導できるか。魅力的なサービスの提供。
0投稿日: 2023.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年の本にも関わらず、メタバースの話や書籍の無料化の話など今のビジネスのマーケっぽい話しがかなり書いてある。2009年7月でデジタル書籍を無料化、30万ダウンロード、有料書籍もベストセラー入りなど、この時から今っぽいマーケ手法を使って結果が出ているのがすごい。 https://docs.google.com/presentation/d/1cS13Ni2UIg1i31FbNr9l_GgDQo47ngWFbNj-AMhFh-A/edit#slide=id.p ・無料のものと有料のものを見極め、常に無料にできるものを探す ・お金を支払うには様々な理由がある(時間節約、リスク、好き) 周辺でお金を稼ぐ方法はある ・コストがゼロに向かっていくならば、最初から無料にする
1投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年前〈2010年)に読了。 当時としては、無料のサービスは理解できなかった。 ネットに関わるECを含めて固定費無料が定常化になりつつある。
1投稿日: 2021.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ現社会におけるフリーサービスについての仕組みを解説している。あらゆるものが無料で便利になっていく中、その収益モデルと成り立ち、またその対抗策を述べている。
1投稿日: 2021.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料やフリーの存在って もう当たり前の存在ですよね? 無料登録、無料アプリ、無料期間、、、 色々あるんですけど、あらゆるサービスが無料化していっています。 たぶん今の時代ほとんどのものが無料で使えます。 じゃあなんで無料のサービスなんてするの?ってことですよね。 僕もブログで無料で誰でも努力すれば3ヶ月で月利11万円を稼ぐことができて、 その後も資産化されるコンテンツを公開しています。 無料メルマガに登録すれば、 マニュアルも無料で配布しています。 「それも有料化すればええやん?」ってよく言われますが、 僕はギブの精神でやっていて 来るものは拒まず、去るものは追わないスタイルでやってます。 そこから個別指導をして欲しいとなると仲間になって、全力でサポートするし、 努力に助力するようなことはします。 あくまで、個人の独立を尊重しているので、 全部やってあげる、全部教えるような指導はしません。 無料でサービスは提供するのが当たり前の時代の中で大事なのが、 パーソナリティですよね。 誰から教えてもらいたいか、 誰から情報を得たいか、 無料だからいいとか悪いとかそういう問題ではなく、 無料社会だからこそできることはなんなのかをぜひ、この本を読んで考えて欲しいです。 まぁでもなかなかのボリュームです。 自分がサービスを提供する側になるのであれば、読んでおいて損はない本ですよ(^^)
1投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこの連休を利用して読み切った! 10年ほど前に出た本なので古さを感じる箇所もあるが、豊富なエピソードは読み応えがあった。また様々な人のコメントに対する反論が、そこまで話してきたことに対するまとめにもなっているのは、良い構成と思った。
1投稿日: 2020.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日垣隆氏が強くお勧めしていたので読んでみる。 本書が書かれたのが2009年。そんなに昔ではないけれど、インターネットを取り巻く環境は大きく変化していて、既に古くなっている部分もあるが、本質は今でも変わらない。今まではお金になっていたビジネス(デジタル)も、いずれは無料化されてしまう。 無料化されてしまうものに拘るのではなく、それを手子にして新たな価値の創出出来るか否かが今(現代)のビジネスに問われている。 過去のビジネス展開における成功例・失敗例については詳細に触れられているが、価値創出の具体的手段迄は、まだ著者も試行中のご様子。読者の工夫に委ねられている。
1投稿日: 2020.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかった。 世界はこのような場所に向かっているのだと、 私も思う。 内容としては「2011年新聞・テレビ消滅」とかぶっていて、おかしかったけれど。
1投稿日: 2020.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログネットを中心とした無料(フリー)のビジネスについて書いた本でなかなかおもしろく説得力のある内容でした。 帯には「2010年代を生き抜くのに欠かせない一冊だ」とあります。そんな本を2010年代の最後に読んでいる自分はどうかと思いますが、後から読んだからこそ、この本で言われていることが概ね当たっていることも分かります。
2投稿日: 2019.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ★避けられない売り方★2009年の出版から10年たっても無料を巡る根本的な状況は変わっていない気がする。デジタル化できる情報・サービスの限界費用はゼロに近づき、供給はどんどん潤沢になる。それだけ先を見通せていたのだろう。雑誌という衰退産業にいる人物だけに、それを回避するために個人としては講演で稼ぐという実践をしている点も含めて、説得力と実践の重みがある。 ウェブ関連のサービスやコンテンツは無料なのが当然だと思って育った世代にとって、有料は受け入れられないだろう。ライブなど希少(な体験)がカギとなるものにしかおカネを払わない。供給側としてはフリーを入り口としたビジネスを考えるしかないのだろうか。 著者が付録として挙げているフリーを取り込んだ形態は3つ。<1>直接的内部相互補助(ハードは無料、ソフトは有料・・)、<2>三者間市場あるいは市場の二面性(ある顧客グループが別の顧客の費用を払う。広告や、発行無料で店から決済手数料を取るクレジットカード・・・)、<3>フリーミアム(一部の有料顧客がほかの顧客の無料分を負担する。後から課金するゲーム・・・)。ただ入り口を無料にしたからといって、その後の有料顧客を必ず得られるとは限らない。その橋渡しのカギはなんだろう。サービスやコンテンツにどれだけ希少さを打ち出せるかなのか。
0投稿日: 2019.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ池袋 ブックオフ 2/19発売 『ビジネスモデルを見える化する ピクト図解』の見本が届きました! 2010.02.14 Sunday :ビジュアルシンキング 『ビジネスモデルを見える化する ピクト図解』 板橋悟(著) (ダイヤモンド社) 2010年2月19日発売 新刊の見本が出版社から送られてきました。 我が家に到着! 刷り上がった本を見るのはこれが初めて。 どんな仕上がりだろう? ドキドキしなながらダンボールを開けると、 編集担当の常盤亜由子さんのお手紙が添えられていました。 お心使いありがとうございます。 著者見本として10冊頂きました。 スリップに「見本」の文字が! 感動のご対面! ティファニーブルーの表紙がお洒落です。素敵です。 今回の本はタイトルからして、一見図解の本に見えますが、 実はビジネスモデルの入門書です。 ベストセラーの『フリー〈無料〉からお金を生みだす新戦略』を 読むときの補助教材にされると理解が深まると思います。 前作の『記事トレ!』同様、「3W1Hメソッド」に基づく ビジュアル思考力を駆使した直感的なトレーニング方法です。 この本を読むと ?ビジネスモデルの見抜き方 ?ビジネスモデルの発想の仕方 が学べます。 読者ターゲットは、20代後半から30代半ばの若手ビジネスパーソン。 (ガンバレば大学生にも読めます。就活の企業研究に使えます) 女性の方にも是非とも読んでいただきたかったので このような可愛いデザインにしました。 帯を外すとデザイン書?と間違うほど スタイリッシュな装丁です。 こんなビジネス書はなかったと思います。 売り場で目立つだろうな。 本文は2色です。深緑とスミ。 装丁はべストセラーを連発しているTYPEFACE 渡邉 民人さんにお願いしました。 さっそく4面出し。 書店でもバッチリ!目立ちそう。 楽しみ楽しみ。 ゲラを読んでいただいた書店員さんの評判もよく 早くもツイッター上で話題になっています。 ありがとうございます。 「ピクト図解」でツイッター検索(http://twittell.net/search.php) してみてください。 発売まで、あと5日!
0投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構ボリュームがある! 様々な事例が豊富に掲載され、分析されている。 例:タダの医療ソフト プラクティス・フュージョン社の電子カルテ →患者の情報を収集して、必要な医療機関などに売ることで収入(←これもどうかと思うが、、、)
0投稿日: 2019.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの例を出したり,あるいは反論に答えたりしながらの分析には,驚嘆するばかり。これからやって来る厳しい世界を早く受け入れて,自分の/自社の立ち位置を見つけたい。あわせて,本書のモデルと異なるモデルを信じているように見える日本国がどういう政策を出していくのか,その結果どうなっていくかも注目したい。
0投稿日: 2019.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅の驚異的なペースでの低コスト化により、21世紀のビット経済(デジタル社会)ではコンテンツの流通にかかる限界費用が、ほとんど気にならないくらいに安くなっている。 それゆえに、20世紀のフリー・ビジネスとは大きく性質を異にする「無料」を生かしたマーケティング戦略により巨額の富を生み出すビジネスが登場している。 ここでは、無料経済を4つの類型に分けています。 1.直接的内部相互補助 無料または極端に安い値段の商品で客を呼び、利益を出せる魅力的な他のモノを売る。 例)携帯電話の端末を無料にして通話料で稼ぐ。 ドリンクは無料だがショーは有料。 駐車場無料でショッピングモールに客を呼ぶ。 2.三者間市場 二者が無料で交換をすることで市場を形成し、第三者がそこに参加するために費用負担する。 例)テレビ・ラジオの無料放送、広告主が媒体料を払う。 クレジットカードの発行は無料、加盟店が手数料を支払う。 子供は入場無料、大人は有料。 3.フリーミアム 一部の有料顧客が、他の多くの顧客の無料分を負担する。 例)無料のウェブサービスで付加サービスを利用するためには有料。 基本ソフトウェアは無料、機能拡張版は有料。 広告付きは無料、広告を取り払うには有料。 4.非貨幣市場 金銭以外の評判や関心が動機となり成立する贈与経済。 例)ウィキペディアの編集。 知らないうちに無償の労働力を提供している。 例)検索するたびにグーグルのアルゴリズム向上に貢献している。 限界費用ゼロの世界での不正コピーの受け容れ。 例)ミュージシャンが無料で楽曲配信し、ライブで収入を得る。 1.と2.は、20世紀のアトム(=実物)経済でも存在したのに対し、3.と4.は21世紀のビット経済であればこそ急激に拡大している。 特に、3.のフリーミアムという概念が新しい。 そこでは無料ユーザーが圧倒的多数であり、それを全体の1〜2割くらいしかいない有料ユーザーが支えている。 それが可能になるのは、デジタル化により莫大な数の母集団を低コストで集めることができる(そのための手段が「無料」)ようになったから。 母集団の数が膨大な一方、ユーザーを集めるコストは低いので、割合が低くても有料ユーザー分で全体の費用を賄い、かつ利益を出すことができる、というわけです。 このあたりは非常にわかりやすい。 頭の整理という点で、非常に有用でした。 一方で、ちょっとショッキングなくらいに刺激的な見方を教えられた点もあります。 著者によれば、フリーへの考え方は(現在の)30歳を境にした上の世代と下の世代で全く異なる。 20世紀型のアトム経済で育った30歳以上の世代は、モノやサービスにはコストがかかっているのでムダにすることは悪徳だという感覚がある。 それに対して、小さいころからビット経済に慣れ親しんだ30歳以下の世代は、デジタル世界では製造・物流コストが無視してよいほど小さいことが感覚的に分かっており、デジタルなモノやサービスをムダにしたりタダでコピーして楽しんだりすることに抵抗がない。 それから、海賊版について。 中国やブラジルでは音楽ソフトやブランド品の海賊版が横行している。 先進国に暮らしている人間の感覚からすると許し難いように思えるが、中国人やブラジル人もニセモノとホンモノの価値の違いはちゃんと分かっている。 それを利用して、あえて海賊版を許容してプロモーション手段としてファンを増やし、ホンモノで儲けるビジネスモデルが生まれている、といいます。 そんなこと自信をもって言っちゃっていいのかな、と何となくドキドキしちゃうあたり、自分も「旧世代」であることの証明かもしれません…
0投稿日: 2019.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ險?繧上★縺ィ遏・繧後◆繝吶せ繝医そ繝ゥ繝シ縲ゅう繝ウ繧ソ繝シ繝阪ャ繝医↓縺翫¢繧九ン繧ク繝阪せ縺ョ縺ソ縺ァ縺ェ縺上?√h繧贋ク?闊ャ逧??豁エ蜿イ逧?↓辟。譁吶ン繧ク繝阪せ繧呈侍繧贋ク九£縺ヲ縺翫j縲∵悄蠕?サ・荳翫↓闊亥袖豺ア縺剰ェュ繧薙□縲 縲後ワ繝シ繝峨?螳ケ驥丞宛髯舌r螳医k縺ケ縺上?∽ク崎ヲ√ヵ繧。繧、繝ォ縺ョ蜑企勁繧偵&縺帙※縺?k莨夂、セ縺ッ譎ゆサ」驕?l縲阪→縺ッ縲∵ュ」縺ォ蟆冗函縺ョ蜍、繧√k莨夂、セ縺ョ縺薙→?
0投稿日: 2018.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ気付きのポイント ・情報発信者の価値は上がる ・信用をお金に変える ・スーパーの商品の1/4はトウモロコシ ・Wikiの歴史、集合知 ・根本的にビジネスモデルを考え直す ・プロとアマの垣根は低くなる ・読書会は無貨幣価値の提供 ・お金にできなかったものをお金に換える仕組み
0投稿日: 2018.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログFree(ただ)を武器とする企業がなぜ成功するのか、たとえば、無料の検索サイトgoogleがなぜ大儲けできるのか、無料の百科事典ウィキペディアの運営方法、無料ダウンロード、無料雑誌、無料試供品のからくり等について述べたもの。内容は、納得できるし、よくまとめられていると思うが、著者のようにFreeが成功の鍵になるかは未だ疑問に思う。Freeにまつわるサービスを駆使して成功した企業に学ぶことに視点をおいて読むべきなのだろう。
0投稿日: 2018.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてある事例は比較的平易でわかりやすいのだが、全体を通して読むと、何が書いてあったのか考え込んでしまった。この本を読むと、19世紀からフリーを導入することにより成功した事例が存在していることが分かる。そして、現在ネットの普及に伴って、より激しく変化・進化を遂げている最中であり、Googleなどの限られた例を除いて成功している企業も少なく、まだ評価や分析が十分になされていないことから、成功事例を羅列したという趣きがある。読みながら取ったメモに、「フリーの意義は、間口を広く低くすることにより、これまで知られていなかった潜在的ニーズ(ロングテールに属する顧客層等)を掘り起こすということか?」とあるが、常識の枠に縛られている気がする。 ところで、この本では、知的財産は'物事がフリーになろうとする動きを押しとどめる方向に作用する'と本質を喝破している。「ビジネスにおいては企業は知的財産権法を利用して、人為的にアイデア不足を生みだすことでお金を儲ける。それが特許や著作権や企業秘密だ。つまり、アイデアは多くの人に伝わるのが自然だが、その流れをしばらくせき止めて利益を上げようとしているのだ。(中略)だが、最後には特許が切れて、秘密は外に出る。アイデアを永久に止めておくことはできない。(111ページ)」となると、特許屋の仕事って・・。フリーになろうとするアイデアを堰き止めて、エネルギー差を人為的に作り出そうとするダムのような仕事だろうか、などと考え込んでしまった。ただ、このあたりは自然に逆らうことなので、うまくやらないと面倒なことになる。ブラジルで欧米の医薬品メーカーが持っているHIVウィルスの薬の特許に対して、国が強制実施権の発動をほのめかせて、薬価を大幅に値引きさせた事例も書かれていた。いずれにしてもパラダイムシフトを考える上で大変参考になる面白い本だと言える。
2投稿日: 2018.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ350ページのハードカバー単行本。 通勤電車で読むにはちょっと辛いので、海外出張の機内で一気読み。 明快な論理と説得力十分の書きっぷりに舌を巻いた。 本書を手に取るまでは、今の時流にのったあまり良くない意味での”ノリノリ”の一冊だろうという勝手な印象をもっていたが、実はフリーという形態を活かしたビジ ネスの歴史は長いということを丁寧に書いているところから始まる。 ここでまず好感度アップ。 そこから、テクノロジー(情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅)の限界費用がどんどん下がっているネットと、フリーの関係へと展開する。 説得力十分でお見事。 途中引用する様々な例え話や、フレーズも興味深いものばかり。 米や小麦と違って、育てやすくタンパク質が豊富なトウモロコシを主食とする文化は、近隣の部族を頻繁に攻撃していたという「トウモロコシ経済」を例にした説明は至極明快。 さらに、その明快な例え話の中に「無料の本当の魅力は恐れと結びついている」なんていうフレーズが出てくるなど、読者のハートをがっちりつかむ術にも長けて いる。この著者は本当に筆が立つ。 このフリーを活かして成功している企業の一つにグーグルがあるが、ヘタなグーグル本を読むより本書を読む方がグーグルのすごさがよく分かる。特に「注目経済」と「評判経済」から成る「非貨幣経済」について触れた第12章が象徴的。 それにしても、こういう本はやっぱりアメリカ発なんだな。
1投稿日: 2018.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーにしたことで利益を得られた事例を集め、紹介している。ちょっと古い本と思っていたが、日本人にとっては新しい本かも。最近始まったと思っていたサービスがあたりまえのように解説読み終わったで出てくる。最後に、シェアまで同梱されていたとはびっくりした。電子書籍のフリー版を読了。
0投稿日: 2018.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ多くの人に読まれたのか分からない。 それまで誰も口にしたことがないことを本にまとめてくれたから、皆あたまの中にあったモヤモヤが解消されたのかな。
0投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年近く経ってから読んでみると、 既にネットフリックスの存在に言及しているくだりがあり、 その先見性にちょっと驚いた。 ちなみに、申し訳ないが、和訳が読みづらい。
0投稿日: 2018.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル経済では、アトム商材と異なり、ビット商材はあたかも万有引力にしたがうかのごとく価格はフリー(無料)に向かう。,潤沢と稀少の狭間で、いかに利益をだすかが課題。,「フリー」は必ずしも法則といったものではなく、成功者ばかりがいる訳ではない。,しかし、今後のフリーに対応していくことは必須となるだろう。,,図書館で借りました。,
0投稿日: 2018.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログワイヤード・ベスト5(以下引用):「ロングテール」の言葉を生み出し時代の寵児となった現『WIRED』編集長の目下の最新作。「フリー」「フリーミアム」など、時代を読み解くキーワードをつくるセンスは何をおいても抜群。 ※全体で5位 ※ワイヤード文化1位 ◆ユーザーからのコメント 「フリー」からは無料より自由というイメージ。無料はむしろ縛られそうで怖い/iPhoneで無料で読んだけどなかなか面白かったよー/この本は、WEBを生業にするうえで凄く勉強になりました/ビジネスに対してのサードアイが開く書。(多分言い過ぎだ)/「人はお金よりも感謝を重視する」とか、よい指摘が沢山/やはりこの本はエポック/現代は単に共通の価値があるのではなく、多様な個人に対して価値を創造していく理由付けの時代 ¥ mmsn01- 【要約】 ・ 【ノート】 ・
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み応えあった。 前半はアメリカの昔の話なので取っ付きにくいけど終盤は最近の話なので身近に感じられて勉強になった。 また自分のビジネスにも参考になった。
0投稿日: 2018.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料をビジネスにどう組み込むかについてはまだまだ高度な戦略思考が必要とされる。気になっていたが、やはり読んでおいてよかった。
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ店頭に並んでいることきにはなったものの、その当時はBtoBがメインだったのであまり関係ないと思って読まなかった。今更ではあるが、BtoCには大きく関わってくる内容ということで、読んでみた。 ところで本書の著者は、「ロングテール」の著者だったのね。知らなかった。 「どうしてグーグルではフリーがあたりまえなのだろう。なぜなら、それが最大の市場にリーチして、大量の顧客をつかまえる最良の方法だからだ。シュミットはこれをグーグルの『最大化戦略』と呼び、そのような戦略が情報市場の特徴になるだろうと考えている。その戦略はとても単純だ。『何をするにしても、分配が最大になるようにするのです。言いかえると、分配の限界費用はゼロなので、どこにでもものを配れるということです。』」 「お金を稼ぐ方法として、ウェブの発展に合わせて成長するやり方をみつけているからだ。…そのため、グーグルのつくり出すほとんどの製品は、無料の無線アクセスから無料の記憶容量まで、多かれ少なかれインターネットの使い道を広げようとするものだ。 こうした関連製品を、経済学者は『補完財』と呼ぶ。…グーグルにとって、オンラインにあるものはなんでも、メインビジネスの補完財と見ることができる。…そのすべては、グーグルが新しい製品を開発し、広告を売るときに役立ちうるのだ。」 このような縦につながるストーリーを戦略として構築したいものである。もちろんオンラインではないものは難しいし、一朝一夕に思いつくものでもないだろうが、このような「フリー」は常に意識されるべきテーマであると思う。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ発売当初に、父に購入してもらったものの、 長きに渡り積読状態だったものを読了。 ものすごく面白い一冊。 若干時間が経っているものの、今にも通じるエッセンスが詰まっている。 もっと早く読んでおくべきだった。 日本語版解説のところに、 本書のポイントがコンパクトにまとめられており良い。 また、外国語の本の訳書にも関わらず、 冗長になり過ぎず非常に読みやすかった。 ~メモ~ (1)貨幣市場 ①直接的内部相互補助 ②三者間市場 ③フリーミアム (2)非貨幣市場
0投稿日: 2018.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長らく本棚に埋もれて居た同書を今更ながら手に取り、読み終えた。いわゆるフリー戦略の歴史から始まっており、手を変え、品を変え、フリー戦略というものがあった事がわかる。ただオンライン上のビットと物理的なアトムの商品には違いがあり、アトム商品は価格が安くなるには限界があるが、ビット商品は無料になりたがる、という話が様々な事例を持って語られていて面白かった。 以下、興味深かったところの抜粋。 P.47 デンマークにあるスポーツジムは、会員が少なくとも週に一度も来店しなければ、その月の会費を全額納めなければならない。その心理効果は絶大だ。毎週通う事で、自身がつくし、ジムも好きになる。いつか忙しいときが来て、来店できない週が出てくる。そうすると会費を支払うが、そのときは自分しか責められない。行きもしないジムに会費を支払うというありがちな状況とは異なり、このジムの会員は脱会したいと思うよりも、もっとジムに通おうという気持ちを強くするのだ。 P.51 イギリスの数学者アルフレッド・ノース・ホワイトヘッドは一九一一年に次のように記した「ゼロについて大事なことは、日常生活ではそれを使う必要がないことだ。誰も魚をゼロ匹買いに行かない。ある意味でゼロは基数の中でもっとも洗練された数字で、洗練された思考のために必要となるにすぎない」 P.56 クロボトキンは一九〇二年の著作「相互扶助論」の中で、ある意味では、今日のインターネットという<リンク経済>を支配するいくつかの社会的な力を予想していた。人に何かをあげることは、お金のためではなく自己満足のためだと彼は言ったのだ。その満足をコミュニティや相互扶助や支援に根ざしている。すすんで他人を助けることで、相手も同様にふるまうようになる。「原始社会」はそのように動いていたとクロボトキンは主張した。贈与経済は市場経済よりも、人間の自然の状態に近いのだと。 しかしそれを知っ戦しようという試みはあらゆる規模で失敗した。集団の人数が一五〇人を越えると、そうフォフジョを監視する社会的絆がゆるみはじめるのが主な原因だった。(一五〇人という数字は「ダンバー数」と呼べれる。それは経験則により割り出された数字で、人間のコミュニティで各メンバーが強い絆で結ばれたままでいられる構成員の上限数だ)したがって一国規模の大きさを持つ集産主義がうまくいかないことはほとんど運命付けられていた。 P.63 私が子どもの時、アメリカの貧困層の問題と言えば飢えだったが、今日では貧困層の肥満が問題になっている。 P.67 (人口学者/生物学者のポール・エーリックと経済学者のジュリアンサイモンの賭け:サイモンが民間がコントロールする穀物と原油を含む原材料の価格は長期的に上昇しないに賭け、サイモンが賭けに勝った) なぜサイモンは賭けに勝てたのだろうか?理由の一つは彼が優秀な経済学者で、代替効果について理解していたからだ。これは、ある資源が希少となり、価格があがりすぎると、人々は潤沢に供給できる代替品を見つけようとするので、希少な資源の需要が減ることだ。 P.86 「予想通りに不合理」の中で、ダン・アリエリーは、「無料」という言葉がなぜ強い影響力を持って居るのかを知るために、彼と同僚がおこなった実験を紹介して居る。「価格ゼロは単なる価格ではない。ゼロは感情のホットボタン、つまり引き金であり不合理な興奮の源なのだ。(トリュフチョコを卸売価格の約半分の15セント、キスチョコ1セントという値をつけ学生に売った際、73%がトリュフチョコを選んだ。次に前者を14セント、後者を0戦ととした場合、69%が後者を選んだ。価格差は変わらないが、無料が持ち込まれたとたんに被験者の好みが逆転した) P.238 情報が豊富な世界においては、潤沢な情報によってあるものが消費され、欠乏するようになる。そのあるものとは、情報を受け取った者の関心である。つまり、潤沢な情報は関心の欠如を生み出すのだ。(社会科学者ハーバード・サイモン) サイモンの観察は、最古の経済原則のひとつを表明したものだった。それは、「あらゆる潤沢さは新しい希少性を作り出す」という原則だ。私たちは、自分たちがまだ十分に持っていないものに高い価値をつける。例えば、職場で無料のコーヒーを好きなだけ飲めることで、よりおいしいコーヒーの需要を呼び覚まし、よろっ混んでそれに高い料金を払う。 P.240 「経済」の定義はなんだろうか。一八世紀中頃まで「経済」という言葉は政治と法律の分野で使われて居た。しかし、アダム・スミスが経済学を「市場を研究する学問」と定義することで、その言葉に近代的意味を与えた。現在、経済学は簡潔に「希少な資源をめぐる選択の化学」と言われている。 P.269 不正コピーは事実上、中国のすべての産業に及んでいる。それはこの国の発展状況や法制度も関係して居るし、さらに儒教では、他人の作品をまねることは敬意の表明であり、教育の基本となるという知的財産に対する考え方がある(アメリカで学ぶ中国人留学生に模倣の何が悪いのかを説明するのに苦労することは多い。師のまねをすることは、中国で学ぶことの中心にあるからだ) P.282 古代ギリシアのアテネとスパルタの文明がその答えになる。ふたつの都市国家は、膨大な数の奴隷に支えられた基本的に潤沢な世界だった。フォースターの小説の機械や、マジック・キングダムのビッチャン世界に似て、肉体を使う作業はすべて奴隷にさせていた。運良く正しい階級に生まれれば、生きるために働く必要がなかった。 それでもアテネとスパルタは、目的がないことで立ち往生したり、進歩を止めたりはしなかった。アテネ市民は芸術家や哲学者になり、観念の世界に目的を探した。一方、スパルタ市民は軍事力と勢力を拡大することに集中した。物質的豊かさは、生きる目的を奪ったのではなく、生きる意義の欠乏状態をつくり出したのだ。アテネ市民はマズローの要求段階を登っていき、化学と創造性を探求した。では、スパルタ市民が戦いを求めたのはなぜだろうか。マズローならば、自己実現欲求の一種だと言うだろう。 P.305 親の世代に価値があったものでも、子の世代になればあってあたりまえのものになるのはこの世の常だが、だからといって、新しい世代が何もかも評価しなくなるのではない。評価の対象が変わるだけだ。私たちはもはや夜明けに起き出して牛の乳搾りに行かないでもすむようになったが、仕事への意欲そのものを失っていない。 その他、同書内で紹介されており、面白そうだった本 * E・M・フォスター 機械が止まる * アーサー・C・クラーク 都市と星 * コリイ・ドクトロウ マジックキングダムで落ちぶれて
0投稿日: 2018.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ===引用ここから== 二一世紀の無料(フリー)は二〇世紀のそれとは違う。アトム(原子)からビット(情報)に移行するどこかで、私たちが理解していたはずの現象も変質したのだ。「フリー」は言葉の意味そのままに「無料で自由」であることとなった。 ===引用ここまで=== 「アトム(原子)からビット(情報)に移行」。このくだりが大好きなのです。 本著では、IT技術の飛躍的な革新により、モノの価値を図る概念の変化が起きた結果、経済活動(”稀少な資源をめぐる選択“と呼べる)の在り方を変える必要性を説きます。 巻末付録では、フリービジネスを以下の3つに大別し、50個の例を挙げています。 フリーその1。直接的内部相互補助(例えば、製品は無料・サービスは有料。その逆も然り。サンプル配布、駐車無料など) フリーその2。三者間市場あるいは市場の“二面性”(ある顧客グループが別の顧客グループの費用を補う) フリーその3。フリーミアム(一部の有料顧客が他の顧客の無料分を負担する) また「無料のルール」として、以下10個の原則にまとめています。 1.デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる 2.アトムも無料になりたがるが、力強い足取りではない 3.フリーは止まらない 4.フリーからもお金儲けはできる 5.市場を再評価する 6.ゼロにする 7.遅かれ早かれフリーと競いあうことになる 8.ムダを受け入れよう 9.フリーは別のものの価値を高める 10.稀少なものではなく、潤沢なものを管理しよう 顧客からお金や時間を確保するために、古典的な広告収入やキックバック、無料サンプル、アイテム課金などあらゆるビジネススキームが開発され、我々の生活に浸透している事実を再認識しました。 一つ一つのビジネスがどう成り立っているか図式化すると、なるほどこんな方法で儲けることができるのか、と驚くものが多くあります。柔軟で、目先のキャッシュにとらわれない思考が求められますね。豊富な資源によりリスクが低下されている現実を再認識し、まず挑戦してみて早めに失敗してみることが重要ですね。
1投稿日: 2018.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1.ガソリンスタンドの無料空気入れは補完的商品 2.情報処理能力と記憶容量、通信帯域幅がはやくなり、性能が上がり、安くなる三重の相乗効果をオンラインは享受している。 3.コンピューターで解放された人間の価値を再提供できるかが社会の役目。 4.価値の変遷をとらえ、利用する。 5.ムーアの法則。 ゼノンのパラドックスは原始の反発作用が原因。ニュートンは微積分で解決。 6.コモディティ化した情報は無料に、カスタマイズされた情報は高価になる。 コモディティとは、競合の中で機能、ブランド力の差異がなくなり、低価格化し、普及すること。 7.ダンバー数である150人以上になると、集産主義が緩む。 8.フランスの経済学者、セーの法則。供給はそれに等しい需要をつくる。なにかを作れば、世界がその使い道をみつける。アップル、ジョブズ→これが欲しいんだろ。 9.ハッカーはMiTの鉄道模型クラブの回路作成チームからうまれた。潤沢な情報は無料に、稀少な情報は高価になる。パラドックスと矛盾はちがう。前者は常に前進し、他方を捕まえれば他方の背中を捕まえる。パブも電話も内容は関係ない。ただ方法と場を提供した。 10.好きなだけ遠くにいけるが、好きなだけスピードはだせない。 11.ほぼ0の限界効用をしらない。私たちはフリーの世代。情報タダは当たり前。 12.替え刃、ネットゲーム、プリンターのインク、それらは本体を買って終わり、から、継続収益確保のビジネスモデルとして成功した。 無料のルール 1デジタルのものはいずれただになる アトムも無料になりたがるが、ゆっくりである フリーは止まらず、利益を出せる。 市場を再評価する。その周辺で儲けよ。 コストが0に向かうならいずれ無料になる。であれば、早く無料にして注目を集めよ。 あなたが出している商品もいずれ誰かが、フリーにする。100%無料は強い。あなたも無料 にして別のものをうるか、価格の違いを埋めるだけの差別化をはかるしかない。 「容量がない」は希少さに基づくビジネスをしている今際の声。 無料にするとモノやサービスは高次のレイヤーに向かう。 デジタルを使ってビジネスをすると母艦が沈むことを恐れずに、早めに失敗しろ、という企業文化に代わる フリーのタイプは時間制限、機能制限、人数制限、顧客タイプによる制限の4つ。 時間制限は、実行しやすいが、低価格競争で共倒れのリスクが小さい。本気の客がすくない。 機能制限は最大のユーザーをえることができる。有料版に移るときは忠実なユーザーとなっている。 無料ユーザーの価値 従来の試供品とは違うフリーミアムを説明している。従来は95パーセントを売るために5%を無料。しかし、今は逆。これがなぜ成り立つか、それはデジタルの限界費用が限りなく0に近いため、95%の製品を作るコストが少なく、大きな市場にアクセスするためのコストを容認できるからである。オンラインゲームは有料ユーザーが5~10%いれば破綻せず 利益も出せる。ペニーギャップと格闘する会社は3~5%が有料ユーザー。有料ユーザー10%がどれだけ無料にして潜顧客をつかまえるか、のポイント。 3つのビジネスモデル フリーのビジネスモデルは大きく分けて3つ。直接的内部相互補助(マックのタダのコーヒーや携帯端末タダ。アマゾンのいくら以上で送料無料など)二つ目は市場の二面性。例えば子供は無料、大人は有料、コンテンツは無料、広告主から掲載料をとる。三つめはフリーミアム。顧客のだれか別の顧客の負担をする。例えば、雑誌や本などの印刷物は有料、デジタルは無料、 デモ版は無料、完全版は有料。など。
0投稿日: 2017.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ-シェアハウスの本棚にあったので読んでみた。 -古くはレシピを無料にしてゼラチンを売った「ジェロ」、カミソリ本体を無料にしての替え刃を売った「ジレット」の話とかはやっぱりインパクトある。要はこういうフリーを使ったビジネスモデルを生み出せるか。 -何気に残ったのは「アンカー」の考え方。「朗読を聞く」という行為に「何ドルなら払うか」と聞くのと「何ドルもらえるなら我慢して聞いてもいいか」と聞くのでは全く違った答えが返ってくるという話。facebookのシェアとか、amazonのレビューとか、タスクのようであって人が喜んでやっていることっていうのは、そもそも前提として人は金を払ってでもやりたいことになりうるのかもしれないと思った。 -ペニーギャップの話も面白かった。人は無料の状態だと思考停止して「とりあえず」もらったり、登録したりする。ただそこに1セントでも料金が発生すると、選択をするというコストが発生する為、一気に心理的ハードルが高くなる。「売上を五ドルから五〇〇〇ドルに増やすのは、ベンチャー事業にとってもっとも難しい仕事ではありません。ユーザーになにがしかのお金を払わせることがもっともむずかしいのです。」 -タダのものは大切にしない。グーグルの無料スナック菓子はみんな残すし、慈善活動で無料であげたバスの乗車パスもバンバンなくす。ただそこに1ドルでも課金すると人は大切にしてなくさないようになる。フリーというのも本当に使いようなんだなというストーリー。 -この考え方には色々なビジネスチャンスが隠れていると思う。「あるもののコストがゼロに向かっているならば、フリーは可能性ではなく、いつそうなるかという時間の問題だ。それなら真っ先に無料にすればいい。それは注目を集めるし、注目をお金に変える方法は常に存在する。」 -「私のアドバイスは、ユーザー全体に対する有料ユーザーの割合は五パーセントを損益分岐点にすることだが、望ましい割合は一〇パーセントだ。それ以上の有料ユーザーがいる場合は、無料版の性能を絞り込み過ぎていて最大数の潜在顧客をつかまえていない可能性がある。一方、割合が一〇パーセント未満のときは、無料ユーザーを支えるコストが高すぎて利益をあげられない恐れがある。」 -「企業が創業まもないときの買い手は、数年後の買い手よりも価値が高い。」
0投稿日: 2017.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料からお金を生み出す新戦略として、いろいろな無料で儲けてる事例などを挙げながらこれからの経済取引を考える本。 これまではアトム経済、物質のやり取りが中心だったが、これからはビット経済、情報のやり取りが中心だ。情報は費用ゼロで取引先を増やせるから必ず”無料”と戦わなければならない。といった始まり方をするのだけれど、内容はアトム経済ビット経済の区分けがそれほどはっきりとしてるわけでもなく、きちんとまとめられた考え方とは言い難い内容。 様々な事例をもとにいろいろと書いてあるが、「費用」と「利益」が直接つながらなくなっているという話に集約できると思う。 今後ますますこの”フリーミアム”が深化してき経済活動が複雑化していくのは避けられないと考えたほうが良いと思わされる一冊ではあった。
0投稿日: 2017.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログすべてがF(ree)になる。 とは別に言ってるわけではないんだけど笑 無料についてこんなに考えたことはなかったので、ゆっくり考えることができる骨太の一冊。 タイミング的には自分がいま関わっている部分もあり、メモしながら読んだ。 無料とは向き合わ合いといけない。 どう無料を使いこなし、創造性を持たせるか。が大事なんですよね。
0投稿日: 2017.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ物質の時代からデータの時代へ変わっていく現在の世界での価値観とその対価に対する新たな考え方が示されている。 自分には新鮮で面白かった。
0投稿日: 2017.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「潤沢な情報は無料になりたがる。希少な情報は高価になりたがる」「フリーの周辺でお金を稼ぐことが、ビジネスの未来になる」 ①直接的内部相互補助(無料と有料の抱き合わせ)②三社間市場(スポンサー)③フリーミアム(無料版+有料版)④非貨幣市場
0投稿日: 2017.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料の商品(サービス)を提供し、それを起点にして、ほかのもので稼ぐ 無料は潤沢なものが望ましい。コスト0に近いやつ。 ビット経済によりコスト0で無限湧きするものが増えた 従来のアトム経済はコスト0無限湧きしない。 パターンは4つ。 ほかの商品を売る スポンサー狙い フリーミアム 非貨幣市場の評価(コミュニティ協力、承認欲求、注意経済など) フリーミアムのパターンは4つ。 時間制限:30日無料など 機能制限:アップグレード 人数制限:ライセンス 顧客タイプ制限:企業規模、法人個人などの違い。Unityとか
0投稿日: 2017.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
グーグル、ユーチューブ、種々のフリーペーパー等の収入獲得方法を知っていれば、本書の記述内容はそれほど新奇ではない(アマゾンの分析もないし)。スポンサーがどこかに居るか、ある種のダンピングの一方法か。それより、①製造業・農業等何かから何かの物産を生み出すケースは射程外、②ある種のソフト開発が本当に個人だけの力によるのか。個人の力でない場合、それを適正に評価して利益の配分ができるか。利益や開発に対する寄与度が正しく確定できるのか。結局、労働時間×時給以上の方法はないのでは?等多くの疑問が湧く書であった。 さらには、無料化は限界費用が限りなくゼロに近づくことでも実現できるというが、それは労働者が取得できる利益を剥奪して実現していないか。あるいは③介護・医療・対人サービス産業も限界費用がゼロであるはずはないが、記述の射程外。本書の所与の前提の幾つかが何の疑問もなく正しいと言えるかに疑義。2009年刊行。情報流通の限界費用の逓減化は首肯するにしても、多様な情報の流通媒体を握る者が、流通情報の選別をしないか。流通情報の埋没による無意味化の懸念も(ただし現代のネット環境に功もある点は否定しない)。
0投稿日: 2017.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大盛り無料も同じ理屈だろうか? ちょっと違うきがするのだが・・・・ オーダーの時に「無料で大盛りにできますが」と言われると、つい「お願いします」と言ってしまうが、大盛り無料を期待して店を選んでいるわけではない
0投稿日: 2017.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料にすれば商売がうまくいくという内容はどこまで本当なのかさっぱりわからないが、音楽の世界では一部の有名なアーティストしか成り立たないのではないだろうか?
0投稿日: 2017.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や当たり前に利用されるフリーサービスについて、歴史、経済、心理などあらゆる観点から分析、解説されている。
0投稿日: 2016.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、一時期ブームなっていた。 そこで手に取って読んでみたが、意外と内容は面白い。 かなり前に読んだので、内容が間違っているかもしれないが、FREEというなかでどうするかが書かれていたと思う。 今でも、この本の考えを利用することが多い。 特に、日本は規制が厳しくなっているので、それを否定する時の理論に使える。
0投稿日: 2016.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログIT革命と言っていたのは、はるか昔のことのようだ。パラダイムシフトがITに限らずすべての社会事象で起こっている。自分自身も含め人々が気づいていない。過去の成功体験(価値観)を捨てたくないのだ。
0投稿日: 2016.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フリーによって得た評判や注目を、どのように金銭に変えるかを創造的に考えなければならない」まあ,そうですね. (p311)
0投稿日: 2016.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今さらという感じのタイミングではあるが、一時期話題となった本書を読んでみた。出版から時間が経ったため、当時日本にないサービスで、注が付されていたものが、今は当然のものとしてあって、そのギャップが新鮮に感じられた。 本書を大胆に要約すると、情報(ビット)はモノ(アトム)と異なり、生産・再生産・コピーの限界費用が限りなく低いので、万有引力の法則のように無料(フリー)になっていくが、だからといって誰の利益にもならないというものではなく、付加価値のある有料バージョンをそれを求める少数の者に売るフリーミアムなど工夫次第でマネーに変えることができるというところか。このほか、かつては希少だったもの(例えば記憶容量)が無料ではないもののタダ同然で潤沢に使えるようになることによる変化など、潤沢と希少という2つの状態でいかに人々の対応や行動が異なるかということの冷徹な指摘など、鋭い洞察が随所に見られ、今さらながらではあるが、読んでよかった。
0投稿日: 2016.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「万引きしようと思わないが、ファイル交換サイトから音楽を不正にダウンロードすることについては何もためらわない。」 CDの海賊版やファイル交換ソフトによる音源の獲得は被害者がいない犯罪だと著者は言う。万引きと違い現物が減るわけではない。しかし、収入は減るだろう。形がないからこそそれを盗んでいるという意識が希薄だ。 固定料金により、見えざる料金メーターを気にしなくなる。7GBも使わないのに、それにお金を払い続ける。安心するからだ。 フリーの市場では勝者が多ければ多いほどよい、グーグルはそれによって新たな広告収入を得られる。 お金を払わないために時間をかけるのは、最低賃金以下で働いている。 どんなに安くても課金形式にすれば利用者は減る。金額が問題なのではなく、わざわざ払うのが面倒なのだ。
0投稿日: 2015.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスを考える上で、 その物自体がフリー(無料)で利益と直結しなくても、 利益を作り出すことができる。 ビジネスのしくみや世の中の流れの変化を感じる。 分厚い本だけど、中身はわかりやすく、 ビジネスのヒントがたくさんあるので、 ビジネスチャンスの手がかりが見つかりそう。
0投稿日: 2015.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネット上ではFREEになりたがる。という言葉が印象的でした。 これからのnet時代を生きていくにはお勧めの本です。 #インターネット #free
0投稿日: 2015.11.15フリービジネスに興味があれば。
タイトルやテーマには強い興味を覚えたが内容はイマイチぴんと来なかった。刊行から時間が経っているからかもしれないが。 グーグルに代表されるフリービジネスの台頭を予言していて、今でも違和感を感じないということはおおよそその予言は的中していたのだろう。 もしかして起業を志している人が読めばもっと多くのことが吸収できたかもしれない。私には少々退屈な読書だった。
0投稿日: 2015.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
4割タイムマジック、残りはふつうの速読で通読。 いまさらで済みませんという感じ。 とはいえ内容そのものは面白い。数学としてのゼロの発明の話やたびたび引用するSFの話は無駄だと思うが。 evernoteについては俺自身ばっちしフリーミアムにやられてら。 ところで、09年に既にドローンに投資している先見に感心。 別件だが、ダンバー数やマズローの欲求段階、最近よう聞くなあ、不思議だな、と思うが全然不思議じゃない。 俺の読む本と関心に偏りがあるから目に入るだけであって、スピリチュアルでもなんでもない。
0投稿日: 2015.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ロングテール」を世に知らしめたワイアード誌編集長、クリス・アンダーソン氏の著書です。 本書は、旧来のフリーの説明に始まり、現在のフリーについて順に解説する内容になっています。 物やサービスをフリー(無料)で提供し、 その売り上げ以外の方法で収益を稼ぐビジネスモデルがこれほどの力を持つとは・・・ インターネットは本当に革命ですね。 ハイスピードな現在進行形の内容を解説しているので、めまぐるしく感じるほどテンポが速く感じます。 また、どんどん新しい価値が生み出されていくので、一定の法則性もなく、その寿命も短いために余計に全体像を掴みにくい感じがします。 ただ、直感的に感じるのは、インターネットの発展とデジタル化の流れの中で、旧来の商業ベースの価値感が大きく根底から変化していることです。 諸行無常ですね。
0投稿日: 2015.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ劇的に世の中を変えてきたWEBの世界を「タダ」というキーワードで切り取った本。著者はWIREDの有名な編集長だけあって、読み応えあります。 クリス・アンダーソンの一連のシリーズは、日本語訳が出るたびに、同じテーマの和書がフォロワーのように発行されるので影響力の強さは感じていたのですが、著者の本を読むのはこれが初めて。 現在進行形で発展しているフリーの世界を描くにあたり、歴史と背景の解説がとても丁寧で面白いこともすごいのですが、相当な批判が来ることも覚悟の上で発行されることに、アメリカ出版産業の底力を感じます。
1投稿日: 2015.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ今までなんとなくしかわからなかったり、あるいはまったくわからなかったりしたフリーの仕組みについて、なんとなくわかるようになった気がします。
0投稿日: 2015.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人気だったので手に取って見た。Hot pepperとか、1か月間無料の戦略に背景にどんなことがあるのかがまとめられている1冊。 【無料の価値を考える】 ・価値が低く見積もられ、大切にされない。 ・有料→無料の選択が、質の低下、と見られることがある。 ・無料が進むと、ちょっとした贅沢を求める人、有料の希少性が出てくる。 キーワード:無料がもたらす、有料の意味を考える
0投稿日: 2015.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2010.9.23 私が印象的だったのは、ここ。 フリーは魔法の弾丸ではない。無料で差し出すだけでは金持ちにはなれない。フリーによって得た評判や注目を、どのように金銭に変えるかを創造的に考えなければならない。 私は、フリーフレンドリーだと思う。大学に入った年にWindows95が発売されて、PCに初めて触ったのとWindows95に触れたのがほぼイコールで、PC普及前のことも普及後のことも両方知っている。Yahoo!やFC2のフリーのサービスをずいぶん使っていたし、この楽天ブログもフリーだし、gmailやyoutubeやWikipediaにも毎日のようにお世話になってるし。だから、お金を払うなら納得した理由がないと払いたくないって思うの、よくわかるなあ。当たり前にいろんなフリーがあるから。 フリーの普及によって、「自分がなぜこのモノ/サービスにお金を払うのか?」について、人はもっと自覚的になるんじゃないかな。でもって、お金をかけるところとかけないところにその人の価値観が今以上に顕著に反映されるようになるのではないかしら……
0投稿日: 2015.05.02これはおもしろい
無料で提供する事によって、有料販売する以上の儲けが得られる場合があることを分かり易い例で書いてあった。とてもおもしろかったです!
0投稿日: 2015.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアイデアや情報という形にならない商品は、デジタル革命によって限界費用がほとんどゼロになるため、価格はおのずとフリーに近づいていくとのこと。 しかし、である。コンテンツを作る上ではバカにならない費用がかかっている。 市場をリードする大企業ならば、対象とする顧客も巨大なため、コンテンツにかかる費用をそれほど気にしなくてもよいかもしれない(グーグルにいたっては他者の作った情報を自社の強みとして取り込む仕組みができている)が、中小企業の多くはニッチな市場の中で生きており、費用全体に占めるコンテンツ制作費の割合が高いため、複製と配信における費用が大幅に減るからといってフリーを販売戦略の核にするには一筋縄ではいかない。 コンテンツ費用をある程度カバーできるだけの柱となる販売手段を持った上で、その埋め合わせ、あるいは利益の上乗せの方法としてフリー戦略を採るというのが圧倒的多数ではないだろうか。 ただ、フリーは大企業だけに恩恵をもたらすものではない。 フリー戦略に関するさまざまな概念や原理、そして多くの具体的事例を知る。 その上で、自社にとって「何が潤沢で、何が稀少か(何を稀少にできるか)」を理解し、その稀少さをお金に換える適切な戦略に落とし込めれば、フリーを生かすことは十分に可能であろう。 「どこで顧客を引きつけ、どう回収するか」。それを考える上で、本書は一読の価値ありと言える。 少し残念だったのは、ツイッターやYouTubeが今なお見出せていない有効な収益モデルに関して、「~すべき」と言い切らないまでも、どのような方法が考えられるかくらいは提示してもらいたかった。
0投稿日: 2015.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年に出版されたにもかかわらず、現在でも十分に通じる書籍です。著者の視点、情報収集力、整理の仕方がとても素晴らしいです(特に、フリーの分類と事例が秀逸です)。
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
料金を取らないことで、大金を稼いでいる人々がいるのだ。 デジタルの流通システムでは、限界費用(流通に必要なハードウェアにかかる固定費ではなく、商品のコピーをもう一つ作って送信するときにかかる追加費用の子と)がゼロに近いので、どんな目的にでも使えるし、流通させるものに価値があるかどうかをいちいち判断する必要もない。 ムーアの法則が言うとおり、情報処理能力ノコストは二年ごとに半分になり、通信帯域幅と記憶容量のコストはそれ以上のペースで下がっている。 今日の最も興味深いビジネスモデルは無料からお金を生み出す道を探す所にある。遅かれ早かれ、全ての会社がフリーを利用する方法や、フリーと競い合う方法を探さざるをえなくなる。 私たちがブログを訪問するたびに何かしらの価値が好感されている。 本当に無料以下の者は少ない。ほとんどの場合で、遅かれ早かれ、利用者は財布を開くことになる。だが、この方法で面白いのは、本当はタダでもらったお金ではないのに、消費者がしばしばそうだと考えることだ。 コモディティ化した商品は安くなり、その価値はよそに移っていく。 人はどうして、場合によって無料を質の低下だと考える時と、考えないと気があるのだろうか。それは無料に対する感情が絶対的なものではなく、相対的なものだからだ。それまでお金を払っていたものが無料になると、私たちは質が落ちたと考えやすい。でも、最初から無料だったものは、質が悪いとは思わないのだ。 消費者からすると、安いことと無料との間には大きな差がある。 タダで手に入れた者にはあまり注意を払わないから、大切にしないのだ。フリーは暴飲暴食や取りすぎ、考えなしの消費、無駄、罪悪感、貪欲さを奨励する。 フリーは信用を広めるのに役立つ。 デジタル市場ではフリーはほとんどの場合で選択肢として存在する。 近いうちに、太陽光パネルや電気自動車と電気をやり取りして、需要を調節できるようになるだろう。 私たちが報酬なしでも喜んですることは、給料のための仕事以上に私たちを幸せにしてくれる。私たちは食べていかなければならないが、マズローの言うとおりで、生きるとはそれだけではない。創造的かつ評価される方法で貢献する機会は、マズローが全ての願望の中で最上位においた自己実現に他ならず、それが仕事でかなえられることは少ない。ウェブの急成長は疑いなく無償労働によってもたらされた。人々は創造的に為り、なにかに貢献をし、影響力を持ち、なにかの達人であると認められ、そのことで幸せを感じる。 もしも自分のスキルがソフトウェアにとってかわられたことでコモディティ化したならば、まだコモディティ化されていない上流に上って行って、人間が直接かかわる必要のある、より複雑な問題解決に挑めばいい。
0投稿日: 2014.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ巻末のsummaryが理解を助けてくれた。いわく、デジタルは無料になりたがる、フリーは止まらないがフリーからもお金もうけはできる。遅かれ早かれフリーを競いあうことになることを覚悟し、自社製品をfree にするか、free品に負けないだけの差別化をするかが課題。 フリーは別のものの価値を高める。潤沢さは、新たな希少さをもたらす。100年前と今との時間と娯楽に関する違いを考えれば明白。フリーミアムのモデルは 時間制限 機能制限 人数制限 顧客タイプによる制限
0投稿日: 2014.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ・フリーミアム戦略とは、表で課金をするのでなく、カスタマーからはみえにくいポジションでお金を生み出すこと。これが同時に、心地良いUXを届けることにもつながっている。UXがなければ、フリーミアムの戦略そのものが成り立ちにくい。 ・フリーミアムを実行するのは、多くのファンを獲得することにも繋がる。そのファンに対し、誠実な態度を取り続けること、コミュニケーションを取り合うことがフリーミアムの強みをより引き出していくことになる。資金源はなにかと合わせて考えると、まずはなにを優先するのかというサービスの設計にも大きく影響を及ぼしてくる。 ・フリーミアムが実現できたときの副次的産物として、ブランド力のアップが挙げられる。収益が出せる程にまで成長させたフリーミアムサービスならば、存在そのものが市場価値として高く、中にはインフラとして重宝される域まで届くものもある。サービス設計の際、どこまでの世界を見ているかがその後を左右する。 ・自分たちがフリーミアムとしてサービス提供できるもの、また、他のフリーミアムサービスの恩恵を受けて自分たちのサービス活性化に応用できるもの。これらを知ることが、新たな事業創造へと繋がる気がする。
0投稿日: 2014.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ- today the most interesting business models are in finding ways to make money around free - A typical online site follows the 5% rule, 5% of users support all the rest. - Free brings more liquidity to any markety place, and more liquidity means that the market tends to work better. - Company culture can shift from "Don't screw up" to "Fail fast"
0投稿日: 2014.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ書籍内容 まず、プロローグに、本書の目的が書いて有ります。引用すると、 ーー 無料にはパラドックスがある。料金を取らないことで、大金を稼いでいる人々がいるのだ。すべてとは言わなくても、多くのものがタダになっていて、無料か無料同然のものから一国規模の経済ができているのだ。それはどのようにして起こり、どこへ行こうとしているのだろうか。これが本書の中心となる疑問だ。 ーー 自分が一番最初に頭に浮かんだのは「グーグル」。あとは、「メイプルストーリー」といったオンラインゲームとか、最近台頭してきた「USTREAM」辺りですね。自分の脳内インスピレーションですが。 これらのビジネスが成立する理由を、本書は数多く挙げているのですが、 解説の中で個人的に興味が湧いた箇所を挙げておきます。 それは「内部相互補助」「フリーの心理学」「非収益化」の3つです。 ○内部相互補助 これらのビジネスを成立させている一つのシステムとして「内部相互補助」という形態があります。 内部相互補助の本質は、「この世にタダのランチはない」という言葉で表されており、引用すると ーー 実際にランチを食べた者がお金を払わないとすれば、それは結局、その人にランチを提供しようという誰かが払っているにすぎないのだ。 ーー つまり、無料を他の有料がカバーしているというのが「内部相互補助」です。 これには 「無料のものを提供して、他の有料のものも買わせようとする」直接的内部相互補助。 「二者が無料で交換することで市場を形成し、そこに第三者(広告主など)がそこに参加するために費用を払う」三者間市場。 「平均約5%の有料プレミアム会員が無料会員を支えている」フリーミアム。 といった種類に分かれています。ここを読んで、FREEのお金の流れのフレームワークがはっきりしました。 ○フリーの心理学 人々が「無料」という言葉に弱いのは、「失うという選択をしなくて良い」事が大きいようです。 ーー 人間は生来、怠け者なので、できるだけ物事を考えたくない。だから、私たちは考えずにすむものを選びやすい。 ーー 何かが無料になると、人間が本来持っている「失うことの恐れ」の心理から、失わないというだけで価値があると思ってしまうという。確かに自分も「無料」というだけで、美味しくないお菓子を試食してしまったりしますしね。試食に数円かかるならおそらく食べませんし。そういうことを言っているんだと思います。 ○非収益化 非収益化というのは「人々が欲するものをタダであげて、彼らが必要とするときだけに、有料で売るビジネスモデルを作れば良い」という考えです。 これが上手くいった例が、中国で海賊版被害にあったマイクロソフトの戦略です。 ーー 「中国では1年に300万台のコンピューターが売れているにも関わらず、人々は私たちのソフトウェアにお金を払ってくれません。」「でもいつの日か払ってくれるようになるでしょう。だから、どうせ盗むのならば、わが社の製品を盗んで欲しい。彼らがわが社の製品に夢中になっていれば、次の10年でお金を集める方法を考え出せるはずです。」 (中略) 中国は以前より豊かになり、コンピューターは安くなった (中略) マイクロソフトは当時流行のネットブック用OSを、通常版の4分の1以下の約20ドルで提供。不正コピーによってユーザーはマイクロソフトの製品を使っているので、新しい製品を選ぶときも、必然的にマイクロソフトを選ぶようになった。 ーー この場合は海賊版被害が例になっていますが、先にネットワークを構築してからトリガーを引くという戦略は、SNS(突然の有料会員募集)やオンラインゲーム(有料のレアアイテム)など至る所で見受けられ、FREEの基本的な戦略の例として挙げられています。
0投稿日: 2014.09.15「フリー」 ・・・ 現代のITビジネスでは避けて通れない
前半では19世紀以来の「無料」ビジネスの歴史について詳しく説明されています。 後半では、現代のITビジネスでの「無料」サービスが述べられます。 前者と後者では、質的に大きく変わった、というのが筆者の主張です。 そして現代では、「フリー」の動向を無視しては自社の商品・サービスを守ることさえ危ういことを踏まえ、本書の一読をお勧めします。
0投稿日: 2014.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更ながら、目を通してみました。この書が書かれた時よりもさらに事態は進展しているはずですよね。まだ、頭にしっくりきてません、もう一度、読み返すべきなのだろうと思います。
0投稿日: 2014.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料で提供するビジネスについて、数多い事例を交えて紹介し解説している。概ね知っていることだったり、推測できることだったりするが、改めて網羅されているのを読むと頭の中が整理できて良い。初犯から5年たっているのでそろそろ改訂版を出したら良いかもね。
0投稿日: 2014.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書や経済学の本というよりは、様々なフリーの事例を紹介して、現代(2009年ごろ)の金の流れをレビューしている、という印象。 オンラインゲームや制限つきのフリーウェアなど、身近な例が多いのでとっつきやすく、訳文も読みやすい。 読了後、日本のサブカルチャーで同じようなテーマを書いてる本がさらに読みたくなった。そういった本は探せばありそう。
0投稿日: 2014.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
●起業家とか、自分で仕事をやっている人がビジネスモデルを考える際には参考になる本という印象。 結局フリーは「最大の市場にリーチして大量の顧客をつかまえる最良の方法」 ・富が蓄積していた産業を駆逐して、市場価値を大きく減らす(価格・売り上げ上は)。しかし、その富はどこかに再配分される(人間の集合知、利便性など)。かつてのブリタニカ百科事典が、マイクロソフトが産み出したCD-Romの格安百科事典で市場が6分の1になり(マイクロソフトは市場規模を縮小させたが、自らは新たな富を獲得した)、その後、ウィキペディアの登場により、市場が0になった(富は、我々の集合知という計測できない価値を大きく増やすことになった)ことで見ることができる。結局、市場はより効率的になる。 無料経済は、おおざっぱに見積もって、3000億ドル。(アメリカで1160~1500億ドル。2008年) フリー経済の中には、バージョン化したものに一部の人がお金を払い、それいがいは無料というシステムを一つの類型としている。従来は、これも「フリーライダーの問題」という経済学で有名な概念を使用したかもしれないが、もはやフリー経済の下では、フリーライダーの問題は消失するのではないかという気もする。ウィキペディアがそれで、フリーライダーする大量の読者のために、一部の人が内容を書き、一部の人が寄付をする。フリーライダーがいて事業が成り立っている一例。 ●この本も5年ぶりくらいに読んだのだが、なるほど、昔はあまり気にしていなかったが、色々と気づきを与えてくれる本であろう。自分の視点が新たに追加される気がする。いや、視点というよりは、再確認、といったほうが正しいのかもしれない。 ・グーグルのページランクは、どれだけ人に見られているか。これは、論文の価値を測るときに、どれだけその論文が引用されているか、で価値を決めることと近いアルゴリズム。 ・大学の授業がオンラインでタダになっている、という最近の事実が示すのは、大学教育の価値は講義だけではなく、教師に質問し、学生とコミュニティをし、その場に生でいられる、ということ。学校側は、授業を提供することはマーケティング手段になる。さらに、無料に開放して人気が出れば、教授が有名になり関連書籍が売れるということもありえる。こう考えると、メリットは多く、デメリットは少ない。開かれた教育は、その教育を閉鎖的な空間で受けていた特権階級の価値を減じない。だから、塾は無料開放しない。塾は、教育だけが価値だから。学校とは違う。 テレビとネットの違いは、消費⇔生産の違いだ。生産によって、「コミュニティ」「個人の成長」「助け合い」というマズローの欲求段階で上位のものが得られる可能性があり、それがタダでも人を動かす原動力ともなる。 この本は、意外と概念を再構築する。ユーチューブは、「映像を無駄に」することで動画の可能性を探っている。何も考えずに動画をアップロードするという大規模な集団実験を行っている。確かに。「無駄」は個人によって異なるので、その無駄があったとしても、需要は存在しうる。 海賊版も、市場の基礎を作り、その者が富裕層になったときには、お金を産み出す源泉となる。マイクロソフトは、懐柔策に出て、中国が市場拡大したときに、利益を生み出すことができた。つまり、ブランド力は海賊版であっても向上する。 SF小説の面白さは、ルールが変わったときに人がどう振舞うかにある。SF作家にはひとつの不文律があり、物理学の法則を破るのは、ひとつの小説につき一つが二つまでである。こう考えれば、SF小説はひとつの思考実験として、人類の未来における思考体系を検討させる要素として興味深いものとなろう。 温暖化について、人々が義務を負うべきと考えたのは、これまで外部化されていた経済を内部化し始めたらからともいえる。コストを埋め合わせる。 本書のポイントとしては、アトムの世界ではなく、ビットの世界ではあらゆるものが無料化の傾向に進む。今後のビジネスを考える上では、フリーを周辺においたビジネスモデルを考えようというもの。 フリーの種類は、広告収入によるメディア運営等、既存のものを含めて大きく4種類存在。まず前提としてフリーで利益を得るのは、「内部相互補助」の役割がキー。 ①直接的内部相互補助(1枚買えば2枚目ただ、など。要は釣り。携帯電話は無料、通話は有料、ショーは無料、ドリンクは有料も同じ。) ②三者間市場(伝統的。メディアはこれ。コンテンツの消費者の分の料金を広告主が払う。女性は無料、男性は有料、売り手から料金とって顧客に安く売る、もそう。) ③フリーミアム(ウェブでは一般的。非伝統的。バージョンアップしたものを買う人だけお金を払う。有料ユーザーが残り大半の無料ユーザーを支える構図。スカイプ、ウェブコンテンツは無料、印刷したものは有料。) ④非貨幣市場(これは、マズローの欲求でいうところの「自己実現欲求」を満たすこと(注目・評判)で無償労働をする概念に近い。ウィキペディア、博物館等) ちなみに、本書は解説だけ読めばだいたい内容が分かる。 ・競争市場では、価格は限界費用まで落ちる →テクノロジー(情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅)の限界費用は年々ゼロに近づく →低い限界費用で複製、伝達できる情報は無料になりたがり、限界費用の高い情報は高価になりたがう →フリーの万有引力については、抵抗するよりもむしろ生かす方法を模索せよ(フリーは破壊者でない、うまく使いこなせ)
0投稿日: 2014.05.06タダとは何なのか?を考える
情報やサービスの享受が限りなく「タダ」になることの仕組みがよくわかる本。 おおかた納得して読めるんだけど、音楽の違法コピーや、中国を中心としたブランド品の模倣品の話は、結果としてプロモーションとして成り立っている部分もあるとはいえ、それでいいとはけして思えない…。そのあたり、著者には賛同できない部分かもしれません。
1投稿日: 2014.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログーFREEー ネットにはフリーで提供されるものが溢れている。 しかし、それらの全てがお金を生み出さないわけではない。 フリーはその周りにお金を生み出すシステム・あるいは生態系を作りだすことができる。 何故あれは無料なんだろう?といった疑問や、発見を促してくれる本だった。 自分は『MAKERS』の著者で『WIRED』編集長でもあるクリスアンダーソンの著書ということで読んだが、これから起業を目指す人にも一読の価値があるだろう。
1投稿日: 2014.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料で売る戦略についての事例紹介と、どのようにフリーの戦略を行えば良いのか解説もあります。事例紹介が読んでいてわくわくします。何回読んでも面白い本です。
0投稿日: 2014.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ持たざるものとして、なぜインターネットサービスを無料でサービス(webサービス、オンラインゲームなど)をこうも快適に受けていられるのかがクリアになった
0投稿日: 2014.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長年積ん読だったものをようやく読了。 2014年の今読むと多少事例が古めかしく思えますが、事例の豊富さに理解を助けられます。 「潤沢な情報は無料になりたがる。稀少な情報は高価になりたがる」というのが印象的な一節。
0投稿日: 2014.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ潤沢になったものを「無駄遣いする」という概念が新しかった。例えばトランジスタを無駄遣いすることを思いついたから今日のコンピュータがあるといったような。
0投稿日: 2014.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ高知大学OPAC⇒ http://opac.iic.kochi-u.ac.jp/webopac/ctlsrh.do?isbn_issn=9784140841048
0投稿日: 2014.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料で何かを提供するビジネス<Free>についての本 Googleなど最近のサービスだけではなく、伝統的なFreeについての紹介が面白い。たとえば新聞を買えば必ずもらえる景品、フリーランチなど。今は誰でもFREEを当然だと思い、無意識に利用する時代。誰にでもオススメできる本。
0投稿日: 2014.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ロングテールの提唱者 Chris Andersonの新書。 辞書みたいに分厚い本で 著者自身が小説を書いているようと 記載していた通り、冗長的な部分をものすごく 感じた。(全ての小説が冗長とはいかず、この表現は 小説に対しての私自身の固定概念の表れですが) 最初のフリーに関するスキームと 最後のまとめだけをよめば十分。 本の構成的に フリーのスキーム→歴史→デジタル世界におけるフリーの定義 →無料経済学におけるフリーの定義→フリーの反対意見における彼の反駁 →まとめ ということで、正直、冗長的。 本書のために調査しましたとという 著者の自己満足な内容をつらつらと書いている。 読みながら途中で飽きました。 下記が本書の概要。 フリーのスキーム ①直接的内部相互補助 →剃刀メーカ「ジレット」の例はなるほど!と思いました。 ②三社間市場 ③フリーミアム 日本ではmixiがぴったりではありませんが 当てはまるかと。 ④非貨幣経済 日本語版wikiがこの論理にぴったり 当てはまってますね。 --- ミュージシャンが、フリーでの販売を拡大し CDなどのライセンスフィーではなく フリーからの相乗効果による ライブなどの収益で、著作権者の権利、収益を 守れというロジックは、あまりにもライブという収入源に 絞った、ミュージシャンが一本足の自身の音楽の経営を 続けろという視点の狭い提唱をしていたり フリーにより、プロとアマの障壁がなくなり アマの出現により、講演などでプロの収入が 増えると書いていた部分も極端かと思うなど 疑問に思う点はタタありました。 --- ・価格はコストではなく、心理学から設定される ・マイクロソフトのビジネスモデルを明確にかつ論理的に 批判している点→このロジックすげー。 ・デジタルの限界費用は、限りなくゼロと定義づけ コストほぼゼロからのビジネスの可能性を提唱した点 ・行動経済学の観点から、フリーのユーザの動向を 考察した点などは参考になりました。 あと、読み終わって思ったこと。 「それで?」 フリーがお金を生み出すとまで、本書の 題にしているのだから、youtubeの収益モデルを どのように構築したらいいかを 提唱をしたりとかしたらと思いました。 ただ、フリーは、こういうスキームがあって、 それに反対する意見もあるけど、 フリーにはこういうメリットがあって、だから反駁しています ブラブラブラ。そうですね。それで? うーん、正直、350ページ読むのは時間の無駄です。 ロングテールで期待しすぎたのかな。
0投稿日: 2014.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログまずは、フリーとは何か? フリーというビジネスはない。その通りである。 副題にもあるように、無料からお金を生み出す戦略についての一冊。 そして、Freeの語源がFriendだというから、その本質を想像することができないだろうか? 商売がモノを売ることではなく、ヒトの生活活動に関わることであるというミカタから フリーという戦略を考えてみる1つのミカタになるだろう。 ところで、特にインターネット産業において”新”しさが相乗しているとはいえ、 副題の”新”戦略というのではなく、新しい目でこれまであった戦略を見直してみようというモノだ。 無料と有料のビジネスモデルの事例からフリーに見えるビジネスを説明している。 興味深い視点の1つは、 インターネットという「いつでも、どこでも、誰とでも」コミュニティーをつくる技術によって、 「注目経済」と「評価経済」というマズローの5段階で言えば自己実現を価値化するようなビジネスモデルという考え方である。 世界には稀有な情報や人材が在って、 そのコンテンツを共有することが、報酬なしでも喜んでしたくなるヒトの幸せであり、 それをインターネットが実現してくれるということ。 最後に、フリーは止まらない。そして、コンテンツはコピーされるがコミュニティーはコピーできない。という・・・ これがインターネットビジネスの、或いは、モノに満たされた社会でビジネスを考えるときのキーワードの1つになるのでは?と思うのである。
0投稿日: 2013.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ音楽について書かれていることには少し疑問が残りましたが、それ以外は普通に納得できるかなって思ったり。 2009年に本書が発売されてもうすぐ5年目。フリーに対する考え方はそんなに外してない気がするし。でも10年後に本書を読んだ時の感想は今と全然違ってるだろうな、と期待。 面白かったです。
0投稿日: 2013.12.07フリーからはお金を生み出せない
結局のところ、フリーからはお金を生み出せない、ということが書いてある。 実際、登場企業はまだまだ収益化に喘いでいる。 しかし、引き続き積極的に使われるビジネス戦略である。 本書にあるよう、フリーを用いた戦略は勝者総取りのゼロサムゲームになりやすく、自らフリーを使わなくても無関係ではいられない。 活用するにも対抗するにも知らないことには始まらないので、フリーの歴史、様々なビジネスモデルを解説する本書に目を通して損はない、と思う。
2投稿日: 2013.11.30フリーとは何者なのか?
なぜ無料なのか?なぜフリーなのか?分かる本である。 人間は、無料すなわちフリーに関しては皆弱いのである。 無料なのはなぜかと考えてしまうものも多い。 例えばスマホのゲームなど、いろいろなものの無料の仕組みが分かる本である。 フリーがあふれている、この世の中に住んでいる皆さんに読んで欲しい。
2投稿日: 2013.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フリー すなわち無料に関するビジネスモデル、世の中の流れ、その考え方について知ることができる本。限界費用に関する話しなど世の中の流れに根拠があり、わかりやすい。 <メモ> ・無料で配って、その後のランニングで使用料をとるジレットや携帯電話など ・ビジネスモデル①直接的内部相互補助 DVD1枚買えば2枚目ただ ・価格は原価ではなく、心理学をもとに決められる。 ・企業はあるものを無料かそれに近い値段にし、それで客を読んで健全な利益を出せる他の魅力的なものを売ろうとする。 ・賢い会社は通常のお金の流れを逆にする。モノやサービスを無料にしたり、他の会社が料金をとるものに料金を支払ったりする。 ・フリーの敵は無駄。 ・供給は需要を作りだす。 ・無料にすることによりユーザーのデータを集め、そのデータを売って収益とすることもできる。 ・無料にすることによって、プール資金を増やし、その運用益で儲けたり、有料サービスや広告で収益につなげることもできる。 ・ユーチューブが表れることによって、子供はスターウォーズより素人の投降動画に興味を持つようになった。 クオリティは低いが、アマチュアに無限の可能性をもたらした。 無駄が許されることにより、参加のハードルが大きく下がった。 テレビや新聞などは資源が希少で限られているから、編集など源泉が必要になり、クオリティは保たれるが、敷居は高く、自由度が低い。意思決定もトップダウン。 WEBは逆であるというわけである。 ・偽物は本物を助けている。本物であるからの良さは当然そこにあり、本物ではなく、偽物ではいいと元々思っている人が偽物に流れる。 また、偽物が普及することで本物含めた認知もあがり、市場が二局化し普及に一役かっていることになる、
0投稿日: 2013.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ初月無料や初回無料、ティッシュ配りやサンプルなど、無料<フリー>がいかに経営に関わってくるかを知るきっかけになる
0投稿日: 2013.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーの裏側がわかる。なぜ無料で儲けられるのか、Googleやyahooのサービスなどの仕組みも説明されている。無料と1セントの差(ペニー・ギャップ)、稀少なものではなく潤沢なものを管理しよう、などが心に残った。 サービスを考えるときに、フリーを選択肢に入れ、別の側面で収益を得る仕組みを考えるのも面白いかも。
0投稿日: 2013.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後にかかれている、解説がすばらしい。 フリーは”必殺技”に納得。 今後としては、ビットの世界においてフリーを考えなければいけないのは間違いない。 観光戦略 写真などの素材をフリーで提供。その後、実際にきてもらうことで儲ける。 ガス ガス栓をダイニングか部屋(暖房用)に一口無料にする。 無料はムダではない。 ビットの世界では、貨幣的ではないもので”評判”や”承認”が取り引きされている。
0投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フリーのビジネスモデルは内部相互補助であり、必ず誰かがお金を支払っている。1.有料商品で無料商品をカバーする、2.将来の支払が現在の無料をカバーする、3.有料利用者が無料利用者をカバーする。 ビジネスモデルを具体化すると4つで、1.直接的内部相互補助(一部無料だが、一部は消費者から直接徴収する)2.三者間市場(広告、その分の値段が添加された商品等を通して間接的に聴衆する)3.フリーミアム(一部の有料会員から徴収する。複製の限界費用がほぼゼロであるWEBだから可能)4.非貨幣市場(Ⅰ,贈与経済{評判や関心を与えるかわりに無料で製品を提供する}、Ⅱ,無償の労働{無料の製品を提供する代わりに労働力を提供する}、Ⅲ,不正コピー)。そして、それとは異なる第三の価格が「マイナス」である。アンカーとなる最初の質問をうまく使い、通常とは真逆の支払プロセスを生み出す。 潤沢なものは目につかないが、希少なものは目につくため、悲観的になりやすい。また、ものが希少になると希少性の低い(=安い)ものを代わりに使おうと試みるため、希少にならなくなる。 フリーとそれの品質に対する考えは相対的に決まる。初めからフリーだと質が悪いと思われない。雑誌は広告があるためフリーでも料金回収可能だが、読者に財に対する希少性を感じさせる、と広告主に感じさせるため有料にし、それと読者獲得曲線の交点が料金になる。それ以外では、価格がつくと「検討」しなければいけなくなるというコストが生じる。ただそれは無駄にしない、ということを意味する。 アイデア移動はコストを必要としないため、生産コストにおいて物質の占める割合がとても小さい場合、速くものは安くなる。フリーだと、分配は最大になる。無料で稼げなくなった分は一見消えるように見えるが、実際は色々なところに分配されている。 従来は、コンテンツと広告を並べて掲載しないのが基本だったが、WEBでは当然のことになった。また、広告収入で運営されるフリーのモデルは、新聞を衰退させた。コンテンツの価値が下落しているのは、1.WEBでの過剰供給、2.物理的形状の消滅(複製の容易さ)、3.入手しやすさ、4.(主にWEB上の)広告収入で運営するコンテンツへの移行、5.(ハードが売れるようになるため)コンピュータ業界のコンテンツ無料化への願望、6.デジタルネイティブ世代への移行、である。オンラインでは競争が厳しいため広告単価は極端に低いが、Googleが配信するテキスト広告の価値は非常に高い。 WEBの世界とは、メディアのビジネスモデルを他の産業へ無限に拡張するものだ、ということが可能である。オンライン広告には、インプレッションモデル(CPM=掲載数1000回あたりの料金)、クリック単価(CPC)、成果報酬(CPA:アマゾンアフィリエイトなど)がある。他にも、リードジェネレーション広告(無料コンテンツに興味を示した見込み(リード)顧客の情報にお金を払う)、固定報酬、SEO、プロダクトプレイスメント(劇中での商品提示)。 かつてはディスプレイ広告やクラシファイド広告(ターゲットを地域などでセグメント分けし、出稿のハードルが低く安価な(一般に)小さい広告)ばかりであったことを考えると、驚異的な成長である。 ゲームでは特に様々なビジネスモデルが展開されている。例えば、1.バーチャル製品の販売。満足した顧客だけ購入するので、不満に繋がりにくい、2.会費(ゲームの全機能を使うための会費)、3.広告(プロダクトプレイスメント)、4.不動産(あくまで賃貸である点が1と異なる)、5.商品(オフラインのぬいぐるみ等の商品がオンラインでも使えたり、逆もしかり) 音楽では、衰退速度を遅らせるためにフリーが用いられている。CDからの売上は放棄し、コンサートやフェスの売上で稼いだりしている。書籍では、章の続きを売ったり、紙の書籍に波及させたり、知名度向上後のコンサルティング料に払わせたりしている。 「価格が限界費用まで下落する」という理論はあるが、ネットワーク外部性(直接的:電話、間接的:補完財)があるので限界費用=価格=0にはならないことがある。また、市場にあるのは同一製品ではないので、限界効用の高さでも決まるし、独占によっても変わる。ちなみに、限界価格が0に近いビジネスでは、顧客は気分よく消費ができる。 WEB上ではフリーライダーは問題にならない。それは、資源コストが0なことと、参加者の異常な多さによるものである(1%でも支払えばビジネスとして成立するし、承認欲求という報酬は参加者が多ければ多いほど満たされる) 潤沢さは新しい希少性を創造する(例:職場の無料のコーヒーは、よりおいしいコーヒーの需要を喚起する)。また、マズローの欲求階層説は情報にもあてはまる(例:娯楽への欲求が満たされると、知識を性格に把握できるようになり、自信の娯楽へのインセンティブを学び、創作に対する精神的報酬を求めるようになる)。 消費者市場には、資本的経済だけでなく注目経済と評判経済がある。例えば、グーグルは一種の評判市場であり、ネトゲ上の金銭は注目経済と言える(時間と金銭がトレードオフ)。贈与経済も自己利益(注目を集めたいから、など)に沿っている。分業の進展で物質・情報余剰になり、思考の余剰が発生した場合、仕事では満たしきれない精神面や知性面の欲求を満たすべく、無償労働する、ということは大いにある。 革新と満足は潤沢と無駄から生まれる(例:トランジスタを無駄にして作ったGUI、YouTubeの動画群→テレビ枠は希少なので冒険できない)。これは自然界にも見られ、局所的最大値から大域的最大値を模索する試みであると言える(例:マンボウ)。中国の偽物は産業を破壊するのではなく、ブランドを浸透させ、いずれは本物の購入を促す。物質的欲求が充足されると、精神的欲求を求めるようになることは長年指摘されている。 よくある指摘としては、1.フリーランチは存在する(自分が払う必要はない、ただ時間を費やすことになるので機会費用は払うかもしれない、あるいは高度に分散している 例:Wikipediaを使う→GoogleはWikipediaに寄付をする→Googleの広告単価がわずかに上がる→製品の値段がわずかにあがる→とはいえ無視可能)、2.プロバイダは有料だがコンテンツは無料、3.無料≠無価値。注目と評判がありビジネスモデルを変えればいい、4.フリーが外部不経済を発生させるのは、限界が存在するものに無限のもののような値付け(=フリー)をするときである、5.フリーが海賊行為を助長するのではなく、海賊行為がフリーを助長する、6.デジタルを当然フリーだとみなすからといって、アトムをフリーだとみなすわけではないから、何に対しても価値を認めない世代を作るわけではない、7.フリーと戦うには、フリーが喚起した需要に沿ってフリーよりいいものを作ればいい、8.フリーで儲けられないのはやり方が悪いからだ 無料に関する思考法:1.デジタルは遅かれ早かれ無料になる、2.アトムの無料になりたがる、が厳しい、3.フリーは止まらない、4.フリーからも儲けられる、5.市場を再評価する、6.とりあえずフリーを前提にする、7.遅かれ早かれフリーを競争する、8.無駄を受け入れる、9.潤沢さは新たな稀少さを生み出す、10.稀少なものでなく潤沢なものを管理することで、失敗を許されない文化から早めに失敗する文化へ移行する フリーミアムの戦術:1.時間制限、2.機能制限、3.人数制限(小規模事業者向けなど)、4.顧客のタイプによる制限。また、フリーミアムを使うときは、無料ユーザーの価値を意識すべき。例えば、初期の顧客はさらなる顧客を呼び生涯支払金額も高いので価値が高い。
0投稿日: 2013.10.24フリーの恩恵を受けつつも深く考えさせられる一冊。
類似本や関連本が出版されるほど話題になったフリー経済についての解説本。 著者はワイアードという雑誌の編集者であり、優秀な記者でもあるが、反対論をはねのけながらフリーの時代の到来を高らかに歓迎する。インターネット関連企業だけでなく、音楽や新聞といった著作権が絡むものについても考察を行い、無料にすることによる有効性を説く。さらに、フリー経済の先駆者として中国の模造品をあげ、消費者は本物と偽物を識別する目を持ち、裕福でないものが模造品を、裕福になれば本物を買うとする。 しかし、これらは余りにも楽観すぎないだろうか。ホンダの工場で生産される部品を盗み、あるいはその工場自身がその部品でコピー商品を作り、格安で売る強かさを前にしても同じことが言えるのだろうか。 あるいは、音楽などはCDやファイルベースでほぼ無料同然で売り、コンサートや関連グッズで売れば良いとするが、コンサートといった手段の取れない小説家などが果たして作品をフリーで配布できるのだろうか。 いずれにせよ、世の中はフリーへと進んでいる。自分たちのビジネスは今後どうあるべきか、深く考えさせられる。
3投稿日: 2013.10.20タダにも理由がある
タダより怖いものはない、ということもない。そこにはちゃんと理由がある。読みながら自分でもフリーのビジネスモデルを考えてみたりしました。しかしなかなか難しい。巷に溢れるフリーはよく考えられてるんだなと実感。ボリューム多くて読み応えあり。
1投稿日: 2013.10.01無料を謳うビジネスはどのようにして存続できるか
会社や学校の帰りに、定期券の範囲で途中下車して買い物をしたり映画を見たりする。 休日に、定期券を利用してデパートや遊園地や野球場に足を運ぶ。 定期券を持っている人はこのような行動をとることが多いのではないだろうか。 定期券は、期間内であればどんなに乗り降りしても自由。実際には購入時に費用を払ってはいるのだが、感覚としては無料の乗り放題きっぷである。 そして、無料と思わせるがゆえに、仕事や学校以外にのるときにためらいを抱かせない。それどころか、乗らないともったいないとさえ思わせる。 一方、交通機関の立場で見るとどうか。 定期券を通勤や通学以外に利用されたら、電車やバスに乗るために特別な出費をしてはいないことになる。これで交通機関の利益は出るのだろうか。 鉄道やバスの単体で見ると利益にならない。 しかし、デパートや、映画館や、遊園地や、野球場は利益をあげる。そこまでの交通費は無料でも、落としていく金額はかなり大きい。 電車やバスは無料でも、そこに行ったあとで金を落としてくれれば、グループ全体で見れば利益を残すこととなる。 これがビジネスモデルとして成立する理由である。 人間は、無料に弱い。 実際には無料でなくても、無料と思わせることでビジネスを生み出すことがある。 この視点を活かせるか否かが、ビジネスマンとしての才覚の一つとなる。
4投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログFREE: The Future of a Radical Price ― https://www.nhk-book.co.jp/shop/main.jsp?trxID=C5010101&webCode=00814042009 , http://www.freemium.jp/ , http://www.thelongtail.com/
0投稿日: 2013.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ小さい頃からタダより高いものはないと教えられてきたが、現代においては本当にタダのものもある。ビジネスモデルも変化し、この激動の中に身を置くのはやはりスリルがあるし、忙しいけれど楽しい。
0投稿日: 2013.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい。 タイトルも表紙も怪しいのでずっと敬遠していたが、こりゃ名著だわ。 なんとなく理解しているつもりのGoogleやYoutubeといった“フリー”のビジネスをより理解するのは当然のこと、なぜこうしたビジネスモデルが成り立つのかという深い分析に関心してまう。その分析は歴史や心理学まで非常に幅広く惹きつけられた。ビジネスの事例も豊富だ。 これを読むまでは“悪徳”としか思っていなかったAKB商戦も納得してしまうし、むしろフリー時代の流れを読み取った儲け方の素晴らしい事例の1つではないか、とさえ思ってしまった。 今存在するインターネットビジネスの根本にあるものが書かれているような気がして、多くのことに実践・応用できる思考がこの本には詰まっている・・・ような気がする。
0投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自宅で半年以上熟成させていました。日本語版ですら4年も前の本ですので、目新しさはありませんが、無料コンテンツ、無料版ソフトなど、ネット、ウェブを利用した無料サービスについてその基本となる部分を解説した良書です。モノやサービスを貨幣軸以外の価値基準で測ることで、結果として貨幣価値として無料(のように見える)ように思います。単なる金儲け話以上の内容が埋まっている本のように思います。
0投稿日: 2013.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「料金を払う必要はないが、払いたくなるかもしれない」という考え方には、ハッと来るものがありますね。 無料でコンテンツやサービスを提供していて、アフターケアや情報の管理もしっかりとしている企業には、こちらもなにかを提供したくなりますよね。 それがお金なのか「もっとこうした方が良い」というような意見なのかは人それぞれだと思います。 顧客が評価している企業や個人には、なにかしてあげたいという一種のファン心理みたいのが働くんだと思います。 例えば、野外で弾き語りをしている人がいるとします。その人の演奏する曲を聴くのに、お金を支払わなくても良いので無料ってことです。別に演奏が良くも悪くもお金を払わなくても良いんです。 でもバンドマンのちょっとしたトークがおもしろかったり、ふと見せる態度が謙虚だったりすると、少しでもお金を置いてあげたくなります。もともと無料なのにお金を払うということは、そのバンドマンのファンになったということだと思います。ファンだから少しでも貢献したい。そんな想いからボクたちはお金を払ったり、感想などの意見を送ったりするんだと思います。 意見を送るということは、バンドマンで言うとフィードバックが得られるということです。誰かからも意見や感想がなければ、バンドマンは改善のしようがありません。やっぱり演奏をしたら、良かった所、悪かった所などの反応が欲しいですよね。 反応がないと、世間から無視されているような感じがして長続きしません。
0投稿日: 2013.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログんー、今だとフリーミアムも当たり前になっているからなあ。もちろんそれだけで稼げるわけじゃないのだけど。結局は質のいい製品、サービスを届ける、という普通のところに帰着するのかなと。
0投稿日: 2013.07.31
