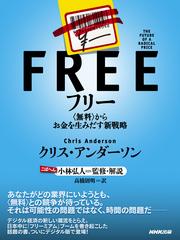
総合評価
(528件)| 140 | ||
| 210 | ||
| 99 | ||
| 9 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーとは、人間の行動心理科学に基づいた仕組みだと感じました。 フリーとプレミアムの差別化が重要でバランスが大事だと感じました。
0投稿日: 2010.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログロングテールの概念を提唱した人の本。2009年。グーグルの検索から音楽配信をはじめとした、いわゆる無料のものを経済的な観点から説いている。著者の表現として、アトム(物質)は有料であり、ビット(情報)は無料になりたがる傾向にある。ハードとソフトという言葉に置き換えても良いかもしれない。デジタルのコンテンツとしてネットワークにのった途端に、それは無料への道を歩み始める。特に、コピー商品のあふれる中国ではその傾向が顕著である。一方で、無料でコンテンツを配信することで、本来の商品を売り込むことに成功している事例もある。たとえば、youtubeでフリーの音楽PVを提供し、より画質の良いDVDがこれまで以上の販売数を記録するようになったという話。無料で配信しまずは多くの人に認識してもらう。そして、興味を持った人に製品を購入してもらうといった構造であり、これまでのサンプル提供とは違ったマーケティング手法といえる。有名大学がウェブ上で講義を配信しているのも、同様の手法だろう。 今後の企業経営を考える上で、フリーとの付き合い方は従来よりもずっと重要になる。そういった意味で、指南書のひとつとして本書を携えるのが良さそうだ。
0投稿日: 2010.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログITの進化によって商品の無料化を劇的に進めているが、その現象に対し、無料に関する歴史、現在のマーケティング手法を述べている。 無料経済に関する予備知識が薄かったため、なかなか頭に入ってこない部分もあったが、情報やコンテンツに関しては、今後も限りなく無料に近づくことをふまえ、そこから利益を生み出すことを考えていくことが重要であると強く感じた。
0投稿日: 2010.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ競争市場では、価格は限界費用まで落ちる。テクノロジーの限界費用は徐々にゼロに近づいている。低い限界費用で複製、伝達できる情報は無料になりたがり、限界費用の高い情報は高価になりたがる。これらについては抵抗するよりも生かす方法を模索せよ。ということ。潤沢になってしまった商品の価値はほかへと移ってしまうので、新たな稀少を探してそちらを換金すべき。
0投稿日: 2010.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル情報は無料に近づく(気にならないくらい小さい コストになる為)というのは、Google世代と言われる 若年層には当たり前のように受け入れられるというのは、 ある種の驚き。頭では理解しているつもりでも 既得権益を壊すモデルであると、防衛本能が働いてしまう。 どうすれば、無料にしてもビジネスとして成り立つのか? 無料にすることで、集客ができ、且つ広告以外の方法で 収益を獲得できるモデルを考えないと。。。 音楽アーティストが無料で音楽を配信し、知ってもらう事で ライブを満員にすることで刈り取る。 これって、今はパッケージでもライブでも儲かる状態である という点で、片側をあきらめるように見えるから進みにくい んだろう。(特にパッケージ制作に携わる人の権益が減るから)
0投稿日: 2010.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ受益者負担というフレームを外して考えると、様々なものが見えてくる。昔からあるビジネスモデルもフリーの一部として捉えられているが、その本当の効果が現れるのはネットを活かしたフリーミアムと言われる戦略をとれるビジネス。この考え方は、工夫次第で様々なビジネスに展開できると思う。
1投稿日: 2010.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. フリーの流れはとまらない。 2. フリーをうまく利用することが重要 3. ただし、フリーをうまく利用するには、注目(トラフィック)と評判(リンク)を高めることが必要。
0投稿日: 2010.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログフリービジネスの類型化は参考になった。 ビットの世界だけでなく、アトムの世界でも不正コピーが本物を助けうるという観点は新鮮だった。(誘発された陳腐化) ウェブの通貨がトラフィックとリンクである、ってのはよいとして、それを「金銭に変えるのはとても簡単」ってのはどうかな。 かなりの量のトラフィックとリンクでないと、金銭的価値には結びつかないように思う。
0投稿日: 2010.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログビットの世界においては、潤沢さゆえコストはどんどん下がる。従来のように稀少なものを管理する必要がなくなる。新しいビジネスモデルが必要。 ネットの世界ではその通りだが、これを製造業などの「アトム」の世界とごっちゃに語るところは強引。 アトムの世界でのフリーは、この本が語るまでもなく従来どおりのマーケティングで説明がつく部分。目新しい話ではない。つまるところ、コピー天国のデジタルの世界は、どういった経済原理が働いているのかにテーマに絞ったほうが焦点がはっきりする。 フリーというタイトルゆえ、アトム経済の「フリー」まで含めた解説をしつつも、対象はネット経済を前提としているので、ちぐはぐとした感じ。 「ネット経済」というタイトルで、ネット経済におけるフリー戦略を解説、という流れのほうがしっくりくる。 タイトルのインパクトに、うまく乗せられた印象。
0投稿日: 2010.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログクリス・アンダーソンは、ロングテールの次に、フリーミアムという言葉を生み出した。 歴史的な無料戦略から、現代のクラウドサービスに代表されるフリーミアム戦略まで、網羅的に解説された本。 新しいフリーについてこれほど簡単に、わかりやすく説明してくれる本は、これ以外ないだろうし、必要ないだろう。 たぶんこれからの基本書。
0投稿日: 2010.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ今、市場でたくさんの無料のビジネスモデルが展開されているなかで、一体この『フリー』というものは何なのかを検証した本。 本書は『フリー』の歴史、心理、有用性などの説明から始まり、後にGoogleなど、具体的に企業がどのように『フリー』を使用して事業を展開しているかが書かれている。 個人的に、『フリー』自体に対して肯定も否定も意見はないけれども、これから切っては切れない『フリー』を捉えていくのは有意義だし、読み応えのある一冊でした。
0投稿日: 2010.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログあるものをタダであげることで、別のものの需要を作り出す モノの経済である原子経済→情報通信の経済であるビット経済へ ムーアの法則 情報処理能力のコストは2年ごとに半分になる フリー① 直接的内部相互補助 ex. 無料サンプル、無料購読機関 フリー② 3者間市場(ある顧客グループが別の顧客グループの費用を払う) ex. 広告収入で運営されるメディア、クレジットカードの発行は無料で、商店から決済料を取る フリー③ フリーミアム オンラインゲームは無料、さらに楽しめる会員登録は有料 フリー④ 非貨幣市場 物々交換 さかさまにできるビジネスモデル ex. 休むと会費を払わなければいけないフィットネスクラブ 潤沢な情報は無料になりたがる。希少な情報は高価になりたがる ex. 「FREE」を無料で配布するのと、講演をすることの別 ビットとその意味する内容はまったく別物。ビットは少なくとも経済的にはタダに等しいが、それが意味する内容は受け取る側次第で、無駄なものから値段をつけられないほど価値があるものまでさまざま ex. 電話会社は利用することに料金を課すだけ。コンテンツは関係ない。 パブはコミュニティとおしゃべりのための場所を提供するが、それについては料金を取らない。潤滑油となるビールの代金を取るだけ →ビールのジョッキなり電話の発信音なり、料金を請求できる何かほかのものを見つける。常に情報以外のもので料金を取れるようにする必要がある グーグルの「最大化戦略」(by エリック・シュミット) グーグルでフリーが当たり前なのは、それが最大の市場にリーチして、大量の顧客をつかまえる最良の方法だから はっきりしているのは、オンラインでは広告の在り方そのものが違うこと。従来のメディア広告は、その商品に関心がありそうな10%の視聴者に届けるために、関心がない残り90%の視聴者をイライラさせる(フットボール中継で流れる入れ歯のCM)。グーグルの広告は正反対だ。ソフトウェアを使うことで、内容をもっと関連がある人にだけ広告を見せる。関心がないわずか10%の視聴者をイライラさせても、商品に関心がありそうな90%の視聴者に届けられる コンテンツとの強い関連性があれば、訪問者はそれをコンテンツの一部とみなす ex. 飛行ロボットのサイトでの三軸加速度計 アップルは売り上げを音楽ファイルの販売からではなく、iPodの販売で上げている グーグルが売っているのは広告スペースではなく、ユーザーの意思。検索リクエストという形でユーザー自身が表明した興味そのものを売っている vs. 1日に「バークレーのドライクリーナー」と入力する人の数はごく限られている 従来の広告手法がオンラインでは限界がある一方、広告というものを再定義したグーグルの手法=表明された欲求と製品を結びつけるは、いまだに急成長している 限界費用経済学 配布コストがかからないものを無料で配り、店舗で売る利益率四割の商品の価値を高める 作者の敵は著作権侵害ではなく、世に知られないこと(ティム・オライリー) 非貨幣経済の価値は、「評判と注目」 ウェブは、注目(トラフィック)と評判(リンク)という二つの非貨幣単位で構成されている ダンバー数 個人が維持できる人間関係の限界数、150人 競争市場において、価格は限界費用まで下落する バージョン化 支払い能力に応じて→必要に応じて フリーライダーは問題にはならない オンラインでは参加者がはるかに多いので、全体の1%でも協力してくれれば、ほとんどのコミュニティではうまくやっていける →マズロー「人間の動機に関する理論」五段階欲求 もはやお金が市場におけるもっとも重要なメッセージではなくなる 「注目経済」と「評判経済」 経済学とは、「希少な資源をめぐる選択の科学」 貨幣市場の研究から、行動経済学や神経経済学へ プロとアマチュアが同じ注目という市場に立つことになった 人々が無償で何かをするのはほとんどの場合、自分の中に理由がある。それは楽しいからであり、何かを言いたいから、注目を集めたいから、自分の考えを広めたいから.. ユーチューブでもっとも人気のある動画でさえ、標準的なハリウッド映画の質にはまったく及ばない。解像度は低く、照明は下手で、音声も聞き取りにくく、話の筋など存在しない。しかし、そんなことは関係ない。なぜなら、もっとも重要なのは「関連性」だからだ。私たちが選ぶのはいつでも、自分が求めていない「質の高い」動画ではなく「質がく」ても求めている内容の動画なのだ 偽物のグッチは、マイナスとプラスの効果を持つ。マイナス面は代替効果。プラス面は刺激効果(偽物があふれることによって、そのブランドを認知させる) フィクションは、大量にあるものを私たちがうまくイメージできないことを教えてくれる。私たちの脳は、希少性にとらわれていて、時間やお金など、自分が充分に持っていないものに心が向きやすい。それが私たちを突き動かす。足りなかったものを手に入れれば、私たちはすぐにそれを忘れて、自分がまだ持っていないものを見つけて追い始める。私たちは、自分が持っているものではなく、持っていないものによって突き動かされている 非補償型の外部不経済 実際には希少な限界のあるものを、潤沢な本質的に無限なもののような値付けをすると起こる悲劇 ex. 二酸化炭素を値付けすることで、内部経済に取り込む 無料のコーヒーの横を素通りして、スターバックスで4ドルのコーヒーを買うには理由がある。おいしいから。小さな楽しみであり、ちょっとしたぜいたくで自分を甘やかしたいから 。スターバックスは無料以上のものを提供する フリーと競争するには、潤沢なものを素通りしてその近くで希少なものを見つけること ex. ソフトウェアが無料ならサポートを売る。電話が無料なら、遠くの労働力と能力をその無料電話を使って届ける(インドへのアウトソーシング) クレイグズリスト、グーグルはコンテンツの仕入れはほぼゼロに近いからこそ、通信帯域幅や記憶容量を浪費できる 「潤沢さを価値にして伸びる企業」と「新たな希少を価値にして伸びる企業」。メディア企業は後者に属する 無料のルール ① デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる ② アトムも無料になりたがるが、力強い足取りではない ③ フリーは止まらない ④ フリーからもお金儲けでできる ⑤ 市場を再評価する ex. ライアンエア ⑥ ゼロにする あらゆるもののコストがゼロに向かっているのならば、フリーは可能性の問題ではなく、いつそうなるかという時間の問題 ⑦ 遅かれ早かれフリーと競い合うことになる ⑧ ムダを受け入れよう あなたの留守番電話の録音はいっぱでいすというメッセージは、潤沢な記憶容量を持つ世界で希少さにもとづくビジネスモデルに固執する業界の今際の声 ⑨ フリーは別のものの価値を高める あるモノやサービスが無料になると、価値は一つ高次のレイヤーに移動する ⑩ 希少なものではなく、潤沢なものを管理しよう ビジネスの機能がデジタルになると各ビジネスのリスクは小さくなるので、母艦が沈む危険を考えずに独立して多くのビジネスができるようになる。企業文化は「失敗するな」から「早めに失敗しろ」に変わる フリーミアムの戦術 ① 時間制限 ② 機能制限 ③ 人数制限 ④ 顧客のタイプによる制限
0投稿日: 2010.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料より高いものはない とよく言ったもので、フリーであることを分かりやすく解説してくれている本。 フリー=無料ではないということがよく分かります。 この本を読むと無料とか割引とかいう言葉が本当に得しているかどうか疑いを持つようになりました。
0投稿日: 2010.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【ポイント】 プロローグ 14/あたらしいフリーを理解するものが今日の市場を粉砕し、 明日の市場を支配する。 過激な価格の過去と未来について・・ 20/(ジレット)無料で配った安全カミソリが、やがて替え刃の需要を作った。 20世紀にフリーは強力なマーケティング手法になったが、21世紀にはフリーは全く新しい経済モデルになる。 モノの経済である原子経済(アトム)ではなく、情報通信の経済であるビットの経済へ 39/「フリーミアム」: 香水サンプルは実費がかかるので生産者は少量しか配布できなかった。 一方、デジタル製品では、5%の有料ユーザーが95%の無料ユーザーを支えている 46/「予想どおりに不合理」 行動経済学が「アンカー(錨)」と呼ぶもの 72/(フリーの歴史)20世紀に特筆されるべきことは、潤沢さがもたらした大きな社会的、経済的変化。 20年前のフォーチュン誌TOP100は地中から何かを掘り出すか、天然資源をモノに変える会社だった。 現在は、モノを作る会社は32社しかなく、アイデアを加工したり、サービスを提供する会社だ 77/今まで有料のものが無料になると「質が落ちた」と考えやすいが、元から無料だったら、質が悪いとは思わない。 85/消費者からは安いことと無料の間には大きな差がある。 ものをタダであげれば、バイラルマーケティング(口コミ)になるが、1セントでも請求すれば、全く別の苦労して顧客をかき集めるビジネスの一つになる。 「無料はひとつの市場を形成し、いくらであろうと有料になると別の市場となる」 89/行動経済学は、フリーに対する我々の複雑な行動を「社会領域」おける意思決定と「金銭領域」における意思決定に分けて説明する。 95/有料のもの選ぶ理由は、目当のものがえられないリスクを下げるため。 有料には保証がつくが、フリーには保証がない。 102/コンピューターの情報処理能力、デジタル記憶容量、通信帯域幅は「安すぎて気にならないレベル」にある 104/★今日のコストをもとに決めるのではなく、明日に要するであろうコストから価格を決める。 110/半導体は、物質よりも智恵がはるかに重要となる製品。 アイデアは事実上コストを要せず、無制限に伝わっていく。 アイデアとは究極の潤沢な商品で、伝達のための限界費用はゼロなのだ。「ミーム」 169/「流動性」という言葉は金融用語だと思われているが、テクノロジーでは「規模」と呼ばれる。 「インターネットは誰もが自由、無料にアクセス出来る流動性のマシンだ」 174/ブリタニカ→WIKIPEDIA 価値収入という計測できる価値を縮小させて、我々の集合知という計測できない価値を増やした。 「冨は計測しにくい形で再分配される」 240/お金が市場での重要なメッセージではなくなり、「注目(トラフィック)経済」と「評判(リンク)経済」という、非貨幣要因が浮上する。 244/ページランクは、「評判を扱う金本位制なのだ」。 ラリー・ペイジはグーグル経済の中央銀行。 彼らは、通貨の価値を保つように、ページランクのアルゴリズムを微調整している。 307/(タダと闘う)フリーと戦うのは簡単。単純に無料のものよりよいもの、少なくとも無料版と違うものを提供すればよい。 (日本語訳解説) 343/「競争市場では、価格の限界費用まで落ちる」 「テクノロジー(情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅)の限界費用は年々ゼロに近づく」130 「低い限界費用で複製、伝達できる情報は無料になりたがり、限界費用の高い情報は高価になりたがる」 「多くのアイデア商材の価格は、フリーの万有引力に引っ張られる。それは、抵抗するよりもむしろ生かす方法を模索せよ。」 「潤沢になってしまった商品の価値は他へ移るので、新たな稀少を探して、換金化すべき」 348/「潤沢さを価値にして伸びる企業」と 「新たな稀少を価値にして伸びる企業」
0投稿日: 2010.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ(読み始め:3/22、長い中断を経て、2010/12/14読了)当たり前だが、本当に徹頭徹尾フリーだったら食っていけない。『フリーによって得た評判や注目を、どのように金銭に変えるかを創造的に考えなければならない。その答えはひとりずつ違うはずだし、プロジェクトごとに違うはずだ。その答えがまったく通用しないときもあるだろう。』(P310)ということで、単に言われた通りにコツコツまじめに働けばOKだった20世紀とは違う世界に我々は住んでいるのである。
0投稿日: 2010.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからのサービスのあり方を考えさせられる一冊でした。研修ビジネスをやっているものとして、今後どう活かしていけばよいのか考え中です。
0投稿日: 2010.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料ビジネスの仕組みが書いてある本 新しいビジネスモデルの形が見えてくるかも 僕はこの本を読んで、これからのビジネスモデルを考えるヒントのようなものを貰えたと感じました 読んでから数日間はビジネスモデルがいくつかでてきたから、なにかが刺激されたのかも と、青二才は言ってみる
0投稿日: 2010.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ従来の経済モデル、価格モデルとフリーであることを詳しく分析している。行動分析と経済をうまく結びつけたところが新しい視座だと思う。これからの経済は潤沢さの中に稀少性を見いだしていくことに価値がつくという視点は素晴らしい。これは言うまでもなく、ITの力で1)コストがグローバルなレベルで分散化されたこと、2)コスト転化が容易に行えるようなビジネスモデルが生まれていること、そして3)ビットの力でコスト最小で新しいコンテンツやサービスが生み出せることにあると思う。個人的にはこういう経済学をもっと体系化すべきだし、そういう経済学(行動経済学?)があるのなら勉強したい。また、ソーシャルなコンテンツの連携も考えてみたい。
0投稿日: 2010.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今売れているので読みました。 本書で挙げられている「FREE」という考え方は昔からあった。 その最たるもので、身近なものがテレビであろう。 ネットの普及によって、「FREE」の性質や特徴が変わってきており、 そもそも「FREE」の与えるインパクトの大きさははかり知れず、 ビジネスとして活かしていくべきであると書いてある。 但し、完全に「FREE」のものなどなく、 誰かしらが負担しているというのはよくわかる話で、 それを3つに分類しているのはわかりやすい。 ①直接的内部相互補助 一昔前の0円携帯はこれ。ハードは無料だが、その分通話料を余分に 支払っており、結局ハードの支払いもしている。 ②三者間市場あるいは市場の二面性 先にあげたテレビや、フリペなどが代表例。 ③フリーミアム(一部の優良顧客が mixiアプリにように、有料でないと良いアイテムが買えなかったり、 一部の優良顧客がほかの顧客の無料分を負担するもの。 歴史を繙きつつ、様々な事例を出しているのは、 本来は分かりやすくする意図であろうが、 そもそも英語の本であり、事例が全て国外のもの。 また、内容があちこちに飛ぶため結果として理解しにくい。 最後のまとめだけ読んでも、それなりに理解できるのではと感じるが、 使い方次第では、ビジネスにおいて、きわめて有力な武器になりえる ということは十分に理解できた。
0投稿日: 2010.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ今、ネットまわりでいろいろと起きている環境変化をきっちりとらえて、解説してくれている。 現状を分析する上で非常に役に立つ! また、いまのクラウド・ネットをどうつかってビジネスを成立させるのか?という考え方の整理にも使える!
0投稿日: 2010.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいて非常に楽しく、未来をわくわく想像できる本である 是非、楽しく読みつつ自分の生活に置き換え どう利用出来るか? を考えたい。これは未来を語るための本である http://twilog.org/tweets.cgi?id=haniwa0705&word=%23free
0投稿日: 2010.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フリーによって得た評判や注目を、どのように金銭に変えるかを創造的に考えなければならない。」妙に印象に残りました。考え方を見直してみよう。
0投稿日: 2010.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題だったので読んだ。長くて大変だったけど面白かった。今までどうしてただなのかな?と思ってたもののからくりがわかった気がする。
0投稿日: 2010.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログオンラインとオフラインのハイブリッドモデル:ぬいぐるみのタグコードを入力してバーチャルのぬいぐるみを所有する→フリーを利用して「有料」の儲けを増やす。
0投稿日: 2010.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログコンシューマ向けサービスをやっている人は読んでおいたほうがいいかもね。特に新しい何かがあるわけではないけど、よくまとまっていると思います。
0投稿日: 2010.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ95%に無料で提供し、5%で収益を上げるビジネスモデル……としてもてはやされている本書ではあるが、昔からサンプル配布などでやられて来た、従来のFREE(コストは掛かるんだけど、無料にした分をどこかで価格に分配している)とは異なり、そもそも無料にするためのコストが0、あるいは0に近い。 従来は何かを提供するためにはコストがかかったり、希少なものを奪い合ったり管理しあうのだが、FREEでは、潤沢なもの(たとえばサーバーの容量サイズだったり、通信コストだったり)を管理し、そこから生まれる新たな価値に視点を置いているようである。 もいちどきちんと読み返したくなる。面白かった。
0投稿日: 2010.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ米のテクノロジー雑誌「ワイアード」の編集長にして、「ロングテール」が大ヒットしたクリス・アンダーソンの新作。 CPUのコスト、メモリのコスト、ネットワークのコストが時間とともに劇的に低下している現代、ネットにおいては極一部の有料課金ユーザからの収入によって他の大多数のユーザに対しては無料でサービスを提供するというフリーミアムというビジネスモデルが成立する。フリーミアムとは、無料のフリーと、有料会員を意味するプレミアムを合成した造語。 とはいえ、このモデルが成立するためには相当な規模のユーザを集めないと成立しないだろう。 それに加えて、このモデルとはユーザが参加することによってコンテンツの提供が事業者側からユーザサイドに移行した新しいモデルともいえる。 ユーザが情報発信するこの時代にプロシューマーとしてのユーザの立場はこれまでとは違った役割を持つようになるのではないかという予感を提示していると感じた。
0投稿日: 2010.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ分厚いので巻末付録から読まれることをお薦めする。付録を読み、日本語版解説を読み、それでも内容がピンとこない場合は「どうして○○がタダになるのか?」という各コラムを読もう。 おそらく35歳以下(PCを使いこなしているなら40歳以下)なら、この時点で本書の内容を「当たり前じゃん」と思うはずである。つまり潤沢さが経済成長の原動力だということ、そして評価が通貨になるということ。 不幸にもこれを理解できない人は本文を最初から読もう。読み進めてフリーに懐疑的になったら第16章を熟読しよう。あなたの疑念に筆者が丁寧に答えてくれている。今読んでおけば、あと10年くらいは役に立つ本。
0投稿日: 2010.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料の仕組み 無料をえさに客を集める方法 フリーに関するビジネスについて かいてあったがもう少しボリュームを おさえてまとめてほしかった。
0投稿日: 2010.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログためになりました。 コンシューマー向けだけかなと思いましたが、 そうでもなさそうですね。 この本、結構まわりに貸してます。
0投稿日: 2010.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん良かった! 自分達のビジネスがFREEで書かれているスタイルだと確認できたことの収穫は大きかったです。 そして、非常にヒントも得ることもできました。 やはりFREEと言えでも価値あるモノを提供していきたいですね。 ただ、ちょっとボリュームはサービスしすぎですよね(汗)
0投稿日: 2010.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログブルームーンの夜、散歩途中に立ち寄った本屋さんで手にした一冊。読んでおくといいな、と率直に思います。ビジネスモデルが「変革するものである」ことを前提に、事象を読み解く力を身につけること。その覚悟と能力が問われるこれからの10年になると思っています。
0投稿日: 2010.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーの周りでどう稼ぐか,ってことですね。稀少と豊穣という概念の対比は分かりやすい。弁護士業にどうつなげるか。
0投稿日: 2010.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう仕組みになってたんか! なぜ無料にできるのかを知り、消費者は踊らされているなと思った。 もっとこのような本を読んでいきたい。
0投稿日: 2010.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーからどういう収入が得られるのか、思わぬところで思わぬ人が設けたり、フリーによって得られるブランド力で収益を上げるのか?まだ良く理解できていないと思う。
0投稿日: 2010.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネット業界に身を置く一人としての意見をいうと、本書で述べらていることは、既知の事実の整理と体系化の色あいが強いと感じている。 しかしながら、googleが行うビジネスはなぜ無料なのか? たとえば日本でいうと、グリーやモバゲーがなぜ収益を上げているのか? このような質問や疑問に対し、端的で皆が共通認識をもてる言葉がなかった。 クリス・アンダーソンは、まさにそれを実行した。「ロングテール」のように。 利益の構造を分解すると、 「(A)ひとりあたりの利益 ×(B)顧客数=利益」という公式で整理できる。 FREEは、この(B)を最大化できる極めて破壊的かつ圧倒的なツールである。 ただし、当然のことながらそこには大きな必要要件が存在する。仮にその要件を押さえずに、FREEを実施すれば確実に失敗に終わる。 本書の中でも引用されているが、今後すべての商売において行動経済学的発想がより求められていくと考えている。 消費者がより賢くなり、そして商行為における主導権をもつ形態は今後さらに強くなるだろう。 そのような時代だからこそ、いかに消費者の行動や心理を科学的に分析し、イマジネーション豊かな商売をできるかが、成功のカギとなるのだろう。 いやいや、本当に大変な時代である。「とりあえず」は許されない。。 「潤沢さを価値にして伸びる企業」、「あらたな希少(オリジナリティ)を価値にして伸びる企業」だちらの極に身を置いたとしても、その道程は楽しくまた厳しいものである。 商売を行うものは、必ず脳全体を使って、生きなければならない時代が来たということであろうか。 (行動経済学に興味のある方は) 本書の中でも引用されている。 「予想どおりに不合理」がおすすめです。
0投稿日: 2010.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログケナ、ッ、マ・ォ・゚・ス・熙ホ・ク・?テ・ネ、ホーkーク、キ、ソ・モ・ク・ヘ・ケ・筵ヌ・?ォ、鬣ーゥ`・ー・?「twitter、ハ、ノ?。ゥ、ハ・ユ・?`、ハ・モ・ク・ヘ・ケ・筵ヌ・??ツタ?、?サ、ィ、ニマオスyチ「、ニ、ニスBス鬘」キヌウ」、ヒ、ェ、筅キ、?ォ、テ、ソ。」、゙、ソ。「ーk箇、ネヘャ瓶、ヒPDF、?oチマ、ヌケォ饑、ケ、?ハ、ノリ怏モキスキィ、ヒ、筵ユ・?`・゚・「・爨?。、???ニ、ェ、熙ウ、?ォ、鬢ホウ?譏Iス遉ホ我サッ、?雕ミ、オ、サ、?」
0投稿日: 2010.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本は重量があり、分厚く、1800円と比較的高額なのに「フリー」だなんて…と読まず嫌いを決め込んでいたが、あまりに話題になったので読んだ。内容は単純で面白い、アメリカ人(?)らしいユーモアと語り口が小気味よく、文章のセンスも秀逸です。自分の仕事がフリーになったら…少し怖い。
0投稿日: 2010.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨今Webを介したサービスで、無料(フリー)で使用できるものは本当に 増えたなぁと感じることが多い。 特に、個人的に実感するろころだと、 昔(約10年前)、DTPの仕事をしていた頃に使っていた画像処理、イラストソフトと同等の機能を持ったソフトが無料で手に入る。 Office系ソフトの無料で使える種類は増えたなぁ。 ソフトウェア開発者向けのツール(IDE、ソースのバージョン管理など)は普通に良いものが無料で使える。 テキスト、音声だけぢゃなく、映像によるコミュニケーションツールだってそう。 本の内容だってザクザク無料で読めたりする。 映像も公式に無料で著作権者が流してるものはどんどん増えてきた。 んー、ユーザは本当にお金を使わずに多くのことができるようになった ものだ。 デジタルの世界においては・・・ この状況を当然のこととして育った世代がマーケットの主力プレイヤーになる頃、 果してどんなビジネスが強いのだろうか••• これから考えるビジネスは、そー言うことを考えないとダメなのだろうな。 その一方で、モノ・コトの価値がわかりづらくなってきていると感じる今日この頃でもある。 本書の「アトム」と「ビット」の話は、その辺をいくらかすっきりさせてくれた。 「アトム」と「ビット」、この棲み分けをしっかりできずに語られた話は怪しいなと、 そう判断することはできるようになりそうだけど・・・。 価値観、自分の価値観。 価値実態を見極めながら生きていくのは確実に困難になっている。 紙のお金と金属のお金。 物質的にはコインの方が価値があるんだろうけど、 実際には紙きれの方が価値が高い。 ダメだ、自分はやっぱり翻弄される側で終わりそうだ・・・。
0投稿日: 2010.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーはクオリティを犠牲にして、アマチュアの肩を持ちプロを排除する。- フリーはプロとアマチュアを同じ土俵にあげる。本当に”タダ”のものはなく何かしらの方法で代金を払うことになる。海賊行為は人間と文化の解釈により重力のような自然の力になる。
0投稿日: 2010.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の価値はフリーのビジネスモデルについて体系的にまとめたことにある。 フリーのビジネスモデルは大きく、①リクルートが提供していたような就職情報誌の無料モデル、②インターネットの普及によるビット経済モデルに分けられる。 いずれも今や目新しいものではないが、体系化されることで、新たなビジネスの気づきが得られるかもしれない。
0投稿日: 2010.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタルものはフリーに向かう。アトムのものもそれにむかう。フリーはとまらない。フリーでもお金儲けはできる。価格は限界費用まで落ちる。 今の社会はネットへの関わらないものはなくなっている。ネットと絡んでくる以上 フリーのおきてはすべてに課かわってくる。 フリーから生み出されるお金儲けの新しい世界はまだまだ工夫の世界であるが、フリーの流れはもはやとまらないであろう。
0投稿日: 2010.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段なにげなく使っているFree製品のビジネスモデルを分かりやすく書いた本。 商品を提供する側からすると、売上を直接的ではなく間接的に享受する形なので、商売の予想がたてにくいビジネスというイメージです。 一方人件費以外のコストはかからないので、たくさんアイデアを出して色々やってみるのが一番の早道かなぁと感じました。 日本だと競合も少ないので、中国人とかのアイデアをパクれば以外と成功するかもなぁ。
0投稿日: 2010.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログレストランのケースでは、ビール一杯につき、ランチが無料のケース。ネットではDropbox等のように、より付加価値の高いサービスを利用する人が、無料ユーザーの分を負担するという戦略。 面白かったが内容を理解したので手放す。
0投稿日: 2010.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ考えされられることが多いですね。 Freeを受け入れることは難しい勇気のいることですが、思い切って受け入れたときに何が起こるのかを考える必要があるし、出来るだけ早く実践してみる必要があると思います。 ただ、ここに書かれていることは、決して斬新なことではなく、昔から有った考え方、実証済みです。 この流れは誰も止められないのでしょう。
0投稿日: 2010.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーのビジネスモデルは4つに分けられる。 1:直接的内部相互補助 2:三者間市場 3:フリーミアム 4:非貨幣市場 色んな事例を交えながら、丁寧に解説されており判りやすい内容だった。 また、フリーに対する疑問、批評に対してもきちんと回答しており理解を深める事ができた。 何をフリーにし、何から収益を得るか、その奥深さを学んだ気がする。
0投稿日: 2010.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本自体への感想、ではないのだけど、 是非言っておきたいこと。 止めた方がいいですよー 悪いこと言わないから、止めた方がいいです。 フリー戦略を自分もやってみようかと思うこと。 この本で書かれてることは正しいとは思う。 でも、その戦略を、あなたがやっても損するだけです。
0投稿日: 2010.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ・消費者の心理を理解をすれば、無料と有料の線引きはもちろんある ・「安物買いの銭失い」とは異なる無料サービスが存在する とりあえず、φ(..)メモメモ
0投稿日: 2010.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ巷で話題が過ぎ去るまでになんとか読み終えた。 本書ではフリーミアムをはじめとするFree Economyを純粋に真っ正面から分析する。なんというか、自分はいわゆるGoogle世代(Free世代)なのでこうしたIT業界の潮流というものを至極当たり前に受け止めてきた。なので以前どこかで見た「Freeを読んでいない人とはこれからの経営や経済を語れない」という言葉はあまりしっくりこない。それでも、もし「Free」に無用に懐疑的になったり批判的になるような人がいたとしたら、確かにそのとおりなのかも知れない。なので厳密には「Freeを読んでいない非Google世代の人とはこれからの経営や経済を語れない」といったところか・・・。 これからは躍進する企業の多くがIT企業であることが益々多くなり、それ故にバーチャルであるものを売るこうした企業が感覚的に自身の生活に深く関わってくることを実感することも増すと思う。そしてそうしたIT企業の多くが本書の説く「Free」を活用しているはずだ。そうした時代の潮流を汲めば、やはり本書は必読といえるのかもしれない。
0投稿日: 2010.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ“フリー”経済の研究ってこれまでなかったのですね。 お金(資本)が関係して初めて経済になるわけなので、そりゃそうかという感じではありますが・・・ 学ぶことの多い、面白い本です! アメリカの当たり前に今後の日本が透けて見えるのも勉強になります。
0投稿日: 2010.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋をぶらぶらしていて買った本です。見た目が目立っていて、しかも「フリー」という分かったような分からないようなタイトル。試しに中を見てみると、自分の仕事に関係のあるウェブ関連の本だと分かり、でも暇つぶしのつもりで買いました。著者が「ロングテール」という、ウェブ界では有名な造語を作ったクリス・アンダーソンだとは、しばらく気づきませんでした。 内容的には、ウェブで展開される「フリー」ビジネスについてなのですが、「フリー」とは何か?ということに話はおよんでいますから、ウェブ関連にあまり興味のない人でも無視できない内容になっています。「フリー(無料)」ビジネスというのは、別に新しいわけでもなく、昔からありましたが、21世紀型の「フリー」は何かが違う。20世紀型の「フリー」は、何か紐付きでしたが、21世紀型は、「フリー」なものは最初から最後まで「フリー」でいます。GoogleのG-Mailが最初の10日だけ無料ということはありませんね。ずーっと無料です。どうしてそれが成り立つのか?そして、そのユーザとしての20代の人は、その無料の考え方を自然に受け入れらるそうですが、30代以降は受け入れられないそうです。確かに私は20世紀型の「無料」が潜在意識の中に染み付いていて、「無料」と聞くと懐疑的になっていることに本書で気づきました。その点は、この本を読んでいて、良い意味でカルチャーショックでした。ウェブ業界という時代の先端にいるはずの自分が、実は着実に「おじさん」となって時代に取り残されつつあったのです。そんなことに気づかせてくれる思想的な意味でもとても良い本です。また、たぶんクリス・アンダーソン自身が文章能力のある人で、読んでいて次を読み進めたくなるので、楽しい本でもあります。
0投稿日: 2010.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ参照元:まなめはうす http://homepage1.nifty.com/maname/ 3月17日
0投稿日: 2010.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本に興味を持っている方も少なくないと思いますが、 まず、ハッキリいって長い。読むなら覚悟が必要です。 あと、やたら目立つカバー。 これは、カバーを取るといいと思います。 結論から言うと、会社でも個人でも、 新しいサービスを立ち上げて、仕事にできる立場なら 見ておいて損はない本だと思います。 この本には、明確な結論はありませんが、 フリーで出回るコンテンツを客観的に見直すことができます。 内容ですが、前半は過去の事例を説明する感じで、結構ダレます。 めんどくさい人は飛ばしてもいいかも。 中盤は、わりと現代の事例が出てるので取っ付きやすいです。 最後のほうは、フリーやビジネスを通して、 やや思想的なところに行き着きます。 自分の知らないような世界各地のビジネス事例があって、 結構ためになります。 しかし、日本のビジネス事例がほとんど無かったのは悲しかった。。 あと、デジタルコンテンツなどが タダ同然で出回ってしまうことを“重力”のようなものだ。 と、言っていたのが個人的には面白かったです。 テレビやラジオは、無料で提供され第三者の広告で収益を得る。 オンラインゲームは、無料で提供され一部のユーザーからの課金で収益を得る。 また、ミュージシャン(著書ではブラジルのテクノ音楽のようなものを例に)さえも、 無料で楽曲を提供し、コンサートで収益を得る。 まあ、馴染みのあることなんで改めて言うことではありませんが、 無料であるべきサービスは無料にして、 マネタイズ(収益化)は、また別の方法ということです。 パソコンやインターネットなどのデジタルの発展は、 価格と著作権を破壊し続けています。 それは、資本主義の破壊でもあると言えます。 思いっきり端折るのでわかりづらいかもしれませんが。。 例えば、ミュージシャンがコンサートを開催するとして、 昔だったら、その収益でご飯を買って生活してたかもしれませんが、 無料が当たり前の時代になると、無料でコンサートを開催して、 満足したお客さんがご飯をおごってくれるみたいな。 こうなるとお金の価値がなくなってきます。 精神的なやり取りに比重が置かれるわけですね。 このあたりは、もう少し掘り下げて 改めて書こうと思います。
0投稿日: 2010.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深かったけど、鵜呑みにしちゃダメだなとも思った。 あくまでマーケティングの手段であってコンテンツ軽視につながらないように気をつけなきゃなー、と。
0投稿日: 2010.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ価格への主観的評価、 次に無料無限になるもの、 航空会社フリーと茨木空港、 コストフリーな資源を無限潤沢につかって実現できるももの、 承認、感謝、感動、をwebで見える化したい
0投稿日: 2010.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログう~ん、衝撃的であった。 フリー(無料)の仕組みさえ分かれば、理解できる。しかし、人間が古いのか貧乏性なのか、「タダほど高いものはない」と心の底では理解できていない。 とくに中国のコピー製品のを認め、そのコピー商品を含めた商売を確立してるには驚く(@_@;) フリーには、1直接内部相互補助(他の物を買わせて採算を合わせる)、2三者間市場(双方間では無料だが、別の三社が費用を支払う。双方であるが、初期は無料でその後使%用したりバージョンをあげると有料)、3フリーミアム(5%の有料のユーザーが、95%の無料ユーザーを支えている)、4、非資弊市場(体力や情報の作業をお金として換算し、情報提供を無料とする) 潤沢な情報は、無料になりたがる。希少情報は高価になりたがる。
0投稿日: 2010.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログWEB全盛の時代に一口に無料といっても、いろいろな仕組みの無料が存在していることを再認識しました。 日本にも「ただより高いものはない」といいますが、 無料のからくりさえ抑えておけば、サービスに流されずにすみます。
0投稿日: 2010.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ検索サイトのグーグルをはじめ、無料という中でお金を生み出す手法が書かれている。使い捨てカミソリの無料配布を行い、替刃の購入で利益を得るビジネスモデルや、You tubeで音楽配信を行い、そこからサイトに飛んでもらい曲を購入してもらうモデルなどが書かれている。途中からはネット関連の話になった。グーグルのビジネスモデルやSNSの広告収益、ネット配信と著作権の問題など。 ・金融商品から携帯電話のお得プランまで、どんなモノやサービスでも、えてして価格は原価ではなく心理学をもとに決められることは初めて知った。 ・今日、市場に参入するもっとも破壊的な方法は、既存のビジネスモデルの経済的意味を消滅させることだ。つまり、既存ビジネスが収益源としている商品をタダにするのだ。→ラジオがテレビに移ったり、写真のフィルムがデジタルデータになったり、パソコンのOSがオープンソースになったりすることから考えるとこれは一番の肝だと感じた。 ・技術者の仕事はどんなテクノロジーがためになるかを決めることではない。テクノロジーを安く、使いやすくし、誰もが使えるようにユビキタスなものにして世界中に普及させ、あらゆる場所に届けることだ。それをどう使うかはユーザーが決めればいい。一人ひとりが異なるニーズや発想や知識や世界とのかかわり方を持っているからだ。→技術者になる以上どういう発想を持つべきか考えたことがある。参考にしたい。 ・潤沢な情報は無料になりたがる。希少な情報は高価になりたがる。 ・マイクロソフトがでかすぎて、目立たないが、モジラ財団はものすごい賢い収益の仕組みを持っていることがわかった。Firefoxの検索バーをクリックすると、グーグルの検索結果ページに飛ぶようにすることで、グーグルから広告収入の一部をもらって開発費用としている、とのこと。そのため、スタッフは100人足らずだが、MSのブラウザチームを楽に打ち負かしている、ということは驚いた。
0投稿日: 2010.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログもう語りつくされている感があるが、新しいビジネスを考える時には必ず立ち戻って読みたい本。いろいろなことを考えさせられる本。
0投稿日: 2010.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ要再読。とりあえず読み終わった。どういうことなのかはなんとなく理解できたが、結局「フリーは魔法の弾丸ではない。無料で差し出すだけでは金持ちにはなれない。フリーによって得た評判や注目を、どのように金銭に変えるかを創造的に考えなければならない。その答えはひとりずつ違うはずだし、プロジェクトごとに違うはずだ。その答えがまったく通用しないときもあるだろう。それは人生そのものとまったく同じだ。」p.310ということだというのはよく分かった。 要するに、今向き合っているものをどう市場に出して行けばいいのか、というのはそれぞれに考えるしかない、ということだ。当たり前だが。。いままでのマーケティングと同じにはできないということで…
0投稿日: 2010.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこの「Free」という観点で物事を整理する、という視点にまずびっくりです。確かに何で無料でやっていけるんだろう、という疑問があったことはありましたが、わかりやすく整理されています。しかもとても読みやすい。
0投稿日: 2010.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログとにかく良かった!勉強にもなるけど単純におもしろい!デジタル世代のモノの価値観とか興味深い内容もりだくさん!モノを作り出すにはお金がかかるしタダのものなんてないと思ってたけど、これを読むと考え方が180度変わった。フリーのものはお金が直接やりとりされないだけで、見えないもので取引されてその見えないものとどれだけうまくつきあっていくかが大事という事なのかなと。
0投稿日: 2010.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからのマーケティングあフリーミアムがスタンダードになるのでは。これを学んでおいてよかったと思う。要・再読。
0投稿日: 2010.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログフリー(無料)と聞いて、よくあるweb2.0関連の本と侮っていたのが第一印象。 しかし、この本を読み終わった後には、全ての経済圏に関わる人に薦めたくなる力を持った本と感じます。 とは言っても、この本に正解はなく、あくまでも「現在の状況」をなるべく正確に書き記そうとし、現在の経済圏に起こりつつある事を確認出来るという点でのみ正しい評価となる気がします。 既にフリーミアムという言葉については他の方が散々語っていると思いますので、別の点で。 この本が優れている点は、過去に「無料」のマーケティングが起こって以降、人々と商品との関わりについて触れている点です。それは本書の中で繰り返し語られる「競争市場において価格は下がり続ける」「情報は無料になりたがる」という事です。 現代において最も重要と感じるマーケティング手段の一つが「行動経済学」を基礎とした「どのように人々はお金を払うか?」という疑問に対する解であり、有名なウォルマートの例を持ち出すまでもなく、様々な売り方、もしくは売り方のヒントが開発されPDCAサイクルによって運営されています。 そういった試行錯誤の先にあるものとは別として、限界費用が「ゼロ」に近い、あるいは著者の言葉を借りれば「気にならないほど安い」モノを販売する際には、このフリーミアムという概念が今後も重要なキーワードとして流布するのではないかと思います。 現実の経済圏に置き換えても、限界費用がゼロに「なりたがる」商品についてはこの概念が必須となり、競争優位性を得るための手段として用いられていくものと思います。反対に限界費用を無視出来ないモノ、つまりは「高付加価値商品」の必要性は従来ポジションとして考えられがちですが、むしろそれらは関連性を伴っているのではないかとも感じました。 限界費用がゼロに近い商品でも「高付加価値商品」の発生が確認出来る。つまりはパレートの法則よろしく、2割ではなくそれ以下の5%程度のユーザーが利益をもたらすという構造は非常に興味深いところであり、ウェブ世界では当たり前と思う事でも改めて活字にされると納得してしまうところがあります。 従来の「高付加価値商品」については、それではもっともっと価値を付けられるという事も考えられます。モンティ・パイソンを例にあげていましたが、リスクリバーサルなんて面倒な用語を持ち出さずとも、今後は「返品する事が当たり前」の世界に移行しても利益を残せる仕組みが求められていくとともに、今以上に販促コストが下がる事によってそれが容易になっていく世界が見えてきます。 本書はマーケティングの本であり、行動経済学を含む経済学の本であり、ウェブの本であり、また優れた経営書でもあると思います。 web2.0なんて中身の伴わない言葉ではなく、新しい経済圏の潮流を確かめるために読むべき本という印象です。
0投稿日: 2010.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年12月30日現在、アマゾンので最も売れている本のようです。 この本の読んでみて、コンキチの感想を一言で言えば、 フリー(無料)とは、マーケティング・ツールだ ということでしょうか? <フリー>を活用したマーケティングの歴史は古く、それ自体は目新しいものではありません(この本でも、その歴史が解説されている)。重要なのは、ビット経済において、そのウェイトが、アトム経済とはくらべものにならないほど極めて大きいということに対する認識だと思います。 本書で何遍も述べられている「限界費用がゼロに近いモノは、フリーに近づく」というアイデアには、実際、具現化している事例がかなりある(本書でも例証されている)と思う。で、その中でもコンキチが特に注目したいのは、限界費用=(nearly) Zeroの違法なデジタル・コピーです。 コンキチが院生だったころ、インターネットは比較的黎明期だったと思います。我が国ではブロードバンドなど全く普及しておらず、貧弱な回線だったにもかかわらず、邦楽mp3ファイルがサイバー空間の至る所に並べられていた。法治国家の体裁を成す我が国では、やがて違法mp3ファイルの流通(ダイレクト・ダウンロード)は下火になったが、デジタルデータの違法コピーは、Torrentや中華サイト、韓国サイト、ロシアサイトなどに引き継がれている。ついでに違法コーピーファイルの入手法を指南する雑誌もある(日本で)。さらに細かいところまで数えあげると、多くのWebユーザーはなんらかの形で著作権を侵害している可能性が高い(そういった違法行為が許されるのは、ビットワールドがあまりにも広大で、権利者の対応コストが莫大となり、相当悪質でなければ、親告罪なるが故に黙示の許諾が適用されているに過ぎないのだと思う)。物理的な犯罪にくらべて、著作権にかかるデジタル犯罪に対する人々の罪の意識は極めて低いといわざるを得ないというのがコンキチの実感です。 さらに、非物質的な犯罪においては、損失がはっきりと認識することができず、犯罪や被害のあったことを確認する術もないからだと思います。結果、犯罪の結果として生じる苦痛が具現化しにくく、犯罪としての意識が希薄化しているんだと思います。 コピーが簡単で、犯罪であるという意識の低い違法デジタル・コピーが、<フリー>への道を進もうとするのは、水が高いところから低いところへと流れていくのに近しいほど技術的・心理的障壁がなく、当然の帰着なのかもしれません。 こういった不正コピーを犯罪としての局面から捉えると、著作権者の機会損失のみがフィーチャーされがちですが、本書では不正コピーでさえもマーケティングの一環として捉えるべきであるという画期的が提案されています。つまり、本来の価格では購買意欲の湧かない層にまでリーチすることができ、有効なプロモーションとなりえるというものです。その結果、多くの顧客の需要が喚起され、実は不正コピー品の流通の結果生じるのは機会利益であったなんてこともあるわけです。 感想終了 あと、ここで挙げた話題の他にも、機知に富んだアイデアがこの本の中で展開されており、オススメの一冊に仕上がっていると思います。さすが、アマゾンで一番売れている本と思います。
0投稿日: 2010.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ+++ ヒットしたフレーズ +++++++++++++++ ●5%の有料ユーザーが残りの無料ユーザーを支えている。 ●4分類:①無料サンプル型、②広告収入型、③高機能有料型、④無償労働型 ・有料だったものが無料になると質が落ちたと思うが、最初から無料だと質が悪いと思わない。 ●潤沢な情報は無料になりたがる。稀少な情報は高価になりたがる。 ・「儲かるか?」ではなく、「クールか?」。(グーグル) ・限界費用の低いデジタル書籍は、限界費用の高い講演やコンサルティングのためのマーケティング。 ・作家の敵は著作権侵害ではなく、世に知られないでいること。 ・フリーライダーは問題にならない。資源コストが限りなくゼロであるため、および参加母数があまりにも多いため。 ・価値のものさしは、金銭だけでなく、注目(トラフィック)と評判(リンク)。 ・海賊行為は教育や法律でなくせるたぐいの社会的行為ではなく、自然の力のようなもの。 ・フリーの周辺でお金を稼ぐことがビジネスの未来。 ●フリーと戦うには、無料のものよりいいものを提供すればいい。潤沢なものを素通りして、稀少なものを見つけること。 ●コンテンツはコピーされるが、コミュニティーはコピーできない。
0投稿日: 2010.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ気になって手に取り、いまは積んである。 目次をぱらぱらして、さらに興味を覚える。 まずはロングテールを読んでから。
0投稿日: 2010.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ警鐘!FREEのパラドックス。コストをかけ創り出すコンテンツを、収益を出せないモデルでインデックス化しFREEで提供。創る側は持続する対価が得られず消えていく。そしてインデックス化するものも減っていく。残るのは駆逐され尽くしたマーケットと失った雇用。 #freemiumjp
0投稿日: 2010.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本ではリーマンショック、金融バブル崩壊以後、ネットビジネスも暗雲が垂れ込め、すっかり元気がなくなりました。 それで、これからはネット=無料ではなく有料化していくということを言い出す始末。(俺様キングダムの切込隊長こと山本一郎氏『ネットビジネスの終わり』『情報革命バブルの崩壊』) でもアメリカは違いました。『ロングテール』でネットビジネスの本質を見抜いたクリス・アンダーソン氏が書いたのが『フリー』です。 冒頭のモンティ・パイソンの話から説得力があります。 -------------- 自分たちのビデオがデジタル世界で大々的に著作権侵害に遭っていることに圧倒されていたが、2008年11月にユーチューブに登場して、反撃ののろしをあげた。・・・われわれ自身がユーチューブにモンティ・パイソンのチャンネルを立ち上げる。 もはや君たちが投稿してきた質の悪い映像は用なしだ。われわれは本物を届ける。そう、金庫室から持ち出してきた高画質の映像だ。さらに、人気の高い過去の映像だけでなく、新たに高画質にした映像も公開しよう。さらにさらに、それらはまったく無料だ。」 ・・・ 3ヵ月後、この無鉄砲な無料映像配信の試みはどんな結果になっただろうか。モンティ・パイソンのDVDはアマソンの映画とテレビ番組のベストセラーリストで二位まで上がり、売り上げは230倍になった。 -------------- その成功のメカニズムがこの本に書いてあります。 しっかり読むととても参考になります。
0投稿日: 2010.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料からお金を生み出す大きなウネリを、まとめあげた一冊。ロングテールの法則で、なるほどと思わされる視点を持っている人だと思っていたが、さすが次の着眼点はやはりネット。市場に参入する際にもっとも破壊てきな無料にするという方法は、コストの限りなくゼロに近いネット業界には頻繁に起こりうる。使用料を無料にすることで、付帯取引をとっていくやり方は、これから様々なシーンで当たり前になり、またそれを利用すれば商売が成り立つと説く。確かに、無料で配布される雑誌や、無料でできるゲーム、そしてソーシャルネットワークシステムに至っては、使っている本人でさえ無料という考え方が起きないくらいの自然さで我々の行動を飲み込んでいく。要は、パイの囲い込みを可能にしているとうことだ。 また、経済学上の需要と供給曲線を、潤沢な市場と枯渇している市場に分けて考えることで、圧倒的過多市場においては供給が需要を大きく上回り最終的にはコストぎりぎりまで到達するというところがポイントだろう。さらに一歩先を行く議論として、ネットであればそもそものコストがゼロに等しい、つまり売値はゼロに近いということを表すということだ。
0投稿日: 2010.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ● 航空会社のライアンエアは、自分たちの産業は航空機の座席を売ることではなく、さまざまなサービスをおこなう旅行会社であると位置づけたことで業界の常識をくつがえした。 ● フリーミアムのモデルは、有料版を利用するユーザーひとりに対して、無料の基本版のユーザーが19人もいる。それでもやっていける理由は、19人の無料ユーザーにサービスを提供するコストが、無視できるほどゼロに近いからだ。 ● 作家の敵は著作権侵害ではなく、世に知られないでいること。 ● ウェブには主にふたつの非貨幣単位で構成されている。注目(トラフィック)と評判(リンク)だ。両方とも、無料のコンテンツとサービスにおいてとても重要なものだ。 ● フリーは魔法の弾丸ではない。無料で差し出すだけでは金持ちにはなれない。フリーによって得た評判や注目を、どのように金銭に変えるかを創造的に考えなければならない。その答えはひとりずつ違うはずだし、プロジェクトごとに違うはずだ。その答えがまったく通用しないときもあるだろう。それは人生そのものとまったく同じだ。ただひとつわからないのは、失敗の原因が自分の貧困な想像力や失敗への恐れにあるのに、それをフリーのせいにする人がいることだ。
0投稿日: 2010.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる角度からこれでもかと「フリー」について語っている。「フリー」について学びたければ、本書で十分な知識を得ることができるだろう。コラムは面白く、巻末付録は頭の整理にとても役に立った。本編は、表現が冗長な部分も多々あり、もう少し簡潔でもよい気がした。ただ、「フリー」が当たり前の世代にとっては、特に驚くべきことは書かれていないかもしれない。「フリー」はあらゆる業界の根底を覆すパワーを秘めている。「フリー」は避けて通れない道であり、ビジネスモデルの再考は必須となる。いかに「フリー」と上手く付き合えるかが、今後の成否の鍵を握るだろう。決して乗り遅れるわけにはいかない。
0投稿日: 2010.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ20世紀が知識の世紀としたナラバ 21世紀は、知識の価格破壊が起きる が、ボクのジロン ソノ萌芽は既に現れてイル ってコトを紹介してくれる一冊。 情報は高価になりたがる なぜなら貴重だからだ 一方で、情報はフリーになりたがる。 なぜなら情報を引き出すコストは下がりつづけているからだ そして、情報を引き出すコストは 安くて気にならないほど技術が進化し 潤沢な量を活かしてRedundancyをタクワエル ソノ「ムダ」から新しい需要が産まれるのでアル と、いうのが本書の論調 知識の価格破壊はすでにはじまりつつアル ボクのビジネスモデルも ナニを「Free」にするか 考えさせてくれる一冊でシタ
0投稿日: 2010.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログワイヤードの有名編集長による一冊。 新鮮な内容も、既出の難しい内容も興味深く書かれていました。 自ら内容を証明するために、オンライン上にFREE版をアップした。 それにも関わらず本はヒットした。 この日が書いた本だからこそ売れたのかも知れないですが、説得力のある本です。
0投稿日: 2010.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログもうそこにあるFREE、デジタルでは無料と言う意味で脊髄反射してしまう言葉だけれど、リアルワールドでは自由と言う意味でとることが多いのではないだろうか。 フリーからお金を生むと言うのがどういうことかを書いてある本。出だしで触れるアトムとビットと言うのが世代によって理解し易かったりしにくかったりと言うことであるが、それ故にこれからの時代を生きるために身にしみていた方がいい感覚でもある。 デジタルはどんどん無料になっていくのは止められない、だからそれを上手く利用することで利益を得ようとした方が賢いと、まあ端折って言えばそんなところだろう。これは所有に馴染んだ旧時代の意識だとシフトは難しい。 もちろん、そこらたしにフリーの波は来てるわけだけど。その点に関しては自分で体感していても気付いていない部分があるかもしれない。これを読んで気付き、確認して活かせるようにしないといけない。
1投稿日: 2010.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ全体を通して満足です。 個人的にはコラムが一番面白かったかな!!! 「フリー」についての説明も面白いんだけど、実際に「フリー」がどのように使われているのかがよく分かった。
0投稿日: 2010.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前から、無料と言うのは、その集客力により数のパワーを得て、そのうえで広告収入から収益を得ているということだ、と思っていました。その手法もあるのはあるのでしょう。 しかし、ここで述べられているのは、さまざまな無料の形であり概念です。 貨幣経済だけを中心に無料の考えを思うのは20世紀型なのかもしれないけど、ネットに少しでも携わると貨幣経済だけでなく、注目経済(トラフィック)と評判経済(リンク)などもあると言うことをおぼろげながらわかってきます。 つまり必ずしもお金のためだけに動くわけではないということです。このあたりに21世紀型の無料の考え方があるのかもしれません。 原料を仕入れて加工して販売するような場合は、デジタルの世界とは違い、コストが限りなくゼロに近づくことはあまりないのです。しかし、価値はゼロに近づく可能性が大いにあるし、もうすでにそうなっている(そういう方向に進んでいる)でしょう。その時に、価値観の軸足をどこに移動するのか、そんなことを考えさせられる内容でした。
0投稿日: 2010.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい顧客を捕まえたり、より多くの人にアピールするには、フリーは確かに効果的。なんだけど、そっから顧客をどう繋ぎ止めて、どうお金を払ってもらうかが、いつもの課題なんだよなー。 内容的にはフリーのビジネスモデルを再整理しただけで、分かりやすいけど目新しさは感じられない。でもまあ、ビジネスモデルを検討するにあたってのヒントは落ちてそうだから、またつまみ読みしてみよう。 『フリーミアム(Freemium)とは、基本的なサービスを無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能について料金を課金する仕組みのビジネスモデルである。 wikipediaより』
0投稿日: 2010.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログネットがフリーな理由は、インフラの維持が容易で、 リアルな世界では不可能なほど沢山の人が、容易に情報に リーチできるため、その費用は無視できるほどだからだ。 と言うネットの世界の常識を事例を使ってもっともらしく、 そして難解な言葉で綴った本。 ネットで利益を生む仕組みについて分かりやすく書かれている。 知らないこともあったので勉強にはなったが、 ある程度予想できることだったり知っていることが多く そういう面ではあまり目新しさを感じなかった。 正直現状を分析をした後に、これからの事を予想して 書いていることを創造していたので、期待はずれだった。 本の表紙は綺麗だ。
0投稿日: 2010.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ儲け方の新しさ。 ○「まちがっている」と「自明のことだ」というふたつの意見にわかれる話題は、どんなものであれ、いいテーマに違いない(14頁)
0投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログワイアード誌編集長のクリス・アンダーソン著の本。 無料のサービス(表面上は)を分析し、サービスの裏側にある仕組みを解説している。 無料のサービスとはGoogle系サービスやウィキペディアなど、最近でこそ目立ってはいるが、結構古くからあるマーケティング手法とのこと。 特にWeb上でのサービスでは、一般ユーザには無料で、ページ内の広告によって利益を出すもの、一般ユーザの言動によって付加価値を作り、それを元に別の有料サービスに展開するなど、様々だ。 普段生活をしていると無料で便利だと思っているサービスも、実はこの本に書かれているような仕組みが採用されているものばかりかもしれない。 これからサービスを展開しようと思っている人に、参考となる一冊だ。
0投稿日: 2010.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ翻訳なので、全体的な文章は多少固くて読みづらい。 書かれている内容は非常に参考になった。 ネットでビジネスする時の、ビジネスモデルの参考になる。
0投稿日: 2010.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログFREE(無料)とは? そのフレーズからのイメージは、どこか魅力的であり、どこか怪しげであり・・・。 そんな得たいの知れない「FREE」を歴史に遡り現在の動向まで体系的に多面的に説明している力作。 著者のパワー感じます。 「競争市場では価格は限界費用まで落ちる」 「テクノロジーの限界費用は年々ゼロに近づいている」 「低い限界費用で複製、伝達できる情報は無料になりたがり、限界費用の高い情報は高価になりたがる」 自分の関わる業界もこれまでのビジネスモデルを再考が必須。 この本は、再考するのに必要な視点を与えてくれている気がします。
0投稿日: 2010.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料ビジネスについて興味があり購入。 引用が多く、この一冊でfreeについて大体の概念が分かるのはありがたい。
0投稿日: 2010.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログマーケティング戦略の新しいタイプの指南書になります。 ケーススタディがとても多く参考になるのです。 ただ、私のようなデジタル世代だと、 書かれている内容に革新性を感じることはできませんでした。 しかしそのことも含めて、十分に興味深い本であったと思います。
0投稿日: 2010.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本の価値は豊富かつ具体的な事例の紹介にあると思います。 「フリー」なモデルを導入してなぜ商業的に成功したのか、をGoogleを始めとした多様な事例で紹介されています。 コラムを読むだけでも目から鱗。おもしろいと感じるはずです。 「そんなこと知ってるよ」と思うかもしれませんが、一読すると圧倒的かつ体系化された情報量の前に世の中がフリーに支配されていく足音が耳元で聞こえてくるかもしれません。 立ち読みする方は、巻末付録の1~3と本文中のコラムに目を通すだけでも良いと思います。 きっと5人に1人は、この本を手にとってコーヒーを飲みながらゆっくり読みたい、という衝動にかられるはず。。。 なぜかこの本をあちゃこちゃで薦めまくってる気がしてますが、きっと気のせいです(^^; ただ、自分がずーっと気になっていた事象があまりにきれいに説明されていたので、衝撃を受けてるだけです。。 ◆無料のルール 1.デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる 2.アトム(物質的な物)も無料になりたがるが、力強い足取りではない 3.フリーは止まらない 4.フリーからもお金儲けはできる 5.市場を再評価する 6.ゼロにする 7.遅かれ早かれフリーと競い合うことになる 8.無駄を受け入れよう 9.フリーは別なものの価値を高める 10.希少な物ではなく、潤沢な物を管理しよう ◆フリーミアムの戦術 1.時間制限 2.機能制限 3.人数制限 4.顧客のタイプによる制限 ◆フリーの4形態 1.直接的内部相互補助(DVDを1枚買えばもう1枚無料、みたいな) 2.三者間市場(放送局x視聴者x広告主、みたいな関係) 3.フリーミアム(無料版と、有料版のプレミアム製品) 4.非貨幣市場(寄付や不正コピー、他社の評価・評判) <現在すでにうまくいっているフリー・ビジネスモデルの例> フリー① 直接的内部相互補助 ・サービスは無料、製品は有料(アップル・ストアのジーニアスバーの技術サポート) ・製品は無料、サービスは有料(銀行口座を開くと景品がもらえる) ・ソフトウエアは無料、ハードウエアは有料TBMやHPのリナックス版製品) ハードウエアは無料、ソフトウエアは有料(XbOX360などのゲーム端末を原価を大きく下まわった価格で提供する) ・携帯電話は無料、通話は有料(多くの携帯電話会社) ・通話は無料、携帯電話は有料商じく携帯電話会社の夜間や週末の無料通話プラン) ・ショーは無料、ドリンクは有料(ストリップクラブ) .ドリンクは無料、ショーは有料(カジノ) ・商品が無料(小売店の特売品) ・ひとつ買うと、もうひとつは無料(スーパーマーケット) ・無料のおまけ(シリアル) ・二五ドル以上の注文で送料無料(アマゾン) ・無料サンプル(新しく母親になった人へのプレゼントや、スーパーマーケットの試供品) ・無料購読期間(雑誌の定期購読) ・駐車無料(ショッピングモール) ・無料の香辛料(レストラン) フリー② 三者間市場あるいは市場の〝二両性〞 (ある顧客グループが別の顧客グループの費用を補う) ・コンテンツは無料、視聴者へのアクセスは有料(広告収入で運営されるメディア) ・クレジットカードの発行は無料で、商店から決済手数料をとる ・学術論文の閲覧は無料、著者が投稿するのは有料 ・PDF文書の閲覧ソフトは無料、作成ソフトは有料(アドビ) ・女性は入場無料、男性は有料(バー) ・子どもは入場無料、大人は有料(博物館) .プロフィール作漂無料、くわしい検索は有料(マッチ・ドットコム) ・リスト掲載は有料、検索は無料(クレイグスリストのニューヨークの不動産案内) ・旅行サービスは無料、レンタカー会社や應テルからキックバックを受ける(旅行サイト大手のトラヴュロシティ) ・売り手から料金をとり、顧客に安く売る(スーパーマーケットが売り手から棚賃料をとる) ・物件リストは無料にし、住宅ローンを売る(不動産情報サイトのジロー) .コンテンツは無料にし、顧客情報を売る(プラクティス・フュージョン) ・コンテンツは無料、ユーザーが小売商を使うと紹介料が入る(アマゾン・アソシエイト) .コンテンツは無料で、モノを売る(スラッシュドット、シンクギーク) ・コンテンツは無料、広告主から掲載料をとる(プロダクト・プレイスメント) ・プロフィールの一覧は無料、くわしい検索は有料(リンクトイン) ・-般消費者がコンテンツやデータを利用するのは無料、企業がAPIを使ってコンテンツにアクセスするのは有料(イーベイ。リサーチツールのテラピークなどを使い、大規模な分析をおこなう企業に対して) ・環境にやさしいエコハウスの建築プランは無料、そうした建築を請け負う業者として登録するのは有料(フリーグリーン・ドットコム) フリー③ フリ-ミアム(一部の有料顧客が他の顧客の無料分を負担する) ・基本情報は無料、くわしい情報を利用しやすいフォーマットで提供するのは有料(映画調査会社のボックス・オフィス・モジョ) ・一般的な経営アドバイスは無料、個別のアドバイスは有料〈マッキンゼ一社とマッキンゼー・ジャーナル) ・連邦税計算用ソフトウエアは無料、州税用は有料(ターボ・タックス) ・低品質のMP3は無料、高品質のCDは有料(レディオヘッド) ・ウェブコンテンツは無料、印刷したものは有料(雑誌や本) ・お得意さん以外には高く売って、お得意さんに安く売る赤字分を補填する(コストコなどの会員制チェーン店) ・オンラインゲームは無料、そのゲームをさらに楽しめる会員登録は有料(クラブ・ペンギン) ・ビジネス・ディレクトリヘのリスティングは無料、その企業に〈お墨付き〉を与えるのは有料(ブラウンブック・ネット) ・デモ版は無料、完全版は有料(ほとんどのテレビゲーム。最初の数ステージをプレーでき、好き嫌いがわかる) .コンピュータ同士の通話は無料、コンピュータと電話の通話は有料(スカイプ) ・画像共有サービスは無料、追加の保存容量は有料(フリッカ) ・基本ソフトウエアは無料、機能拡張版は有料チップル社のクイックタイム) ・広告つきサービスは無料、広告をとりはらうのは有料(SNS作成ツールのニン) ・一部抜粋は無料、本は有料(グーグルのブックサーチを利用する出版業者) ・バーチャル世界の探索は無料、その世界の土地は有料(セカンドライフ) ・音楽ゲームは無料、追加楽曲は有料(タップ・タップ・レボリューション)
0投稿日: 2010.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログフリー~〈無料〉からお金を生みだす新戦略 図書館から”無料”で借りて読んだ。P.319でTwitterを”俳句のようにつぶやくサービス” と書かれているのだけれども、原著でもこう書かれていたのだろうか?俳句って知ってるの? http://bit.ly/bB2ZaY
0投稿日: 2010.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ■概要 世の中には、(一部の人に)無料でサービスを提供することで 莫大な利益を得ている企業がたくさん存在しています。 海外に目を向ければ、グーグルの検索、Gmail、Docsや アマゾンの無料配送サービス。 日本でも、リクルートのフリーペーパーはパッと思いつく ところですよね。 そんな、<フリー>で設けるための考え方や 世の中の<フリー>サービスの分類方法などについて書かれています。 海外の書籍らしく、単に無料サービスについて説明するだけでなく、 周辺領域の経済史等、含蓄に富んだ内容で読み応えがあります。 ■仕事に役立つ点 ・ビジネスモデルを検討する際の切り口として、 、<フリー>を前提としたビジネスが出来ないか、 視点が増えます。 ・会社の仕組みについて理解のバリエーションが増えます。 <あし>
0投稿日: 2010.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料と有料の狭間で揺れ動く、思慮することってかなりあるけど、今におけるフリーについてよくまとまっていると思う。経営学云々と硬さはあるけど、これから先を考えるにはいいきっかけになるのではなかろうか。持ち運ぶには重いからね!
0投稿日: 2010.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ長いスパンで経済史を見れば、価値は常に相対的である。往来が不自由だった時代は関所や橋の通行が有料だったりするが、それらを無料化して往来が活発になると、次の時代にはフリーに通行できることが当たり前になる。付加価値の高い産業というのもやはり入れ替わっていき、花形産業はいつか陳腐化と価格破壊に見舞われる。その時には限界費用が低下しているから、供給過剰と過当競争を避けるのは本質的に難しい。 ただビットの世界ではこれらの変化が暴力的なほど素早く訪れる。基礎技術の革新が早く、ボトルネックから開放されれば限界費用はゼロに近い。さらにフリーウェアの開発者のように無報酬で奉仕する者が現れる。そもそもネットの世界は地理的制約から解き放たれ市場参加が自由・・・と、考えていけばフリーは必然であり、既存の付加価値にしがみつくことなくフリーを前提にビジネスを設計することが必要、となるだろう。 ただこの本の書き方はあくまでジャーナリスティック。グーグルやオンラインゲームの成功例を見れば、確かに高い市場占有や成長を背景に、広告効果や規模の経済性を換金するビジネスは成り立ちうる。ただそんなに上手く行くのはごく一部であり、例えば音楽業界でもフリーのプロモーションで成功したアーティストはまだ一握り。まぁ大きな流れとしては、情報とかソフトウェアとか知的財産とかいったものを私有財産として直接囲い込むことが難しくなり、一種の公共財的に活用するというふうに発想の転換を迫られていくのは間違いない。
0投稿日: 2010.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログテクノロジー(情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅)の限界費用は年々ゼロに近づいているため、ネット市場の価格は限界費用まで落ちていく。 bizモデルとしては、 ・潤沢さを価値にして伸ばす ・新たな稀少を価値にして伸ばす の方向性。 フリーのいろいろ。 <貨幣市場モデル> ・直接的内部相互補助 →フリーでないものを販売し、そこからフリーを補填 →DVDを1枚買ったら2枚目タダ ・三者間市場 →第三者(スポンサー)がお金を支払い、多数がフリーとして提供 →TV、ラジオ、ポータルとか ・フリーミアム →フリーで人をひきつけ、有償版を用意(5~10%の比率が大事) →flickrとか <非貨幣市場モデル> ・贈与経済 →wikipedeia ・無償の労働 →digg、OKweb ※根底にあるのは、注目(トラフィック)、評判(リンク)
0投稿日: 2010.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の中でも「若い世代はビットの限界費用による、アトムとの決定的な違いを感覚として知っている」というようなことが指摘されている。私はかろうじて若い世代に含まれていたらしい。本書についても、指摘の半分くらいは目新しさを感じなかった。例えば、一部の有料会員により大勢の無料会員がサービスを受ける〈フリーミアム〉についても「何を今更、説明してる」の感。「限界費用が限りなくゼロで、人々の注目こそが稀少となる、オンラインの経済」は、私が自らの金銭の使い道を考えられる年齢になった時には、もう始まっていた。 本書の貢献は、そのような感覚的に理解されていた違いを明文化して整理したこと。彼は、フリーについて、歴史を意味づけて振り返り、現状を整理してくれた。おかげで、感覚を共有していない世代とも議論を始められるようになった。 このタイプの経済の最終的に向かうところについての展望は本書にはまだ足りない。しかし議論のスタート地点が整備されたという、マイルストーン的論考となりそうだ。
0投稿日: 2010.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネスにおけるフリーを体系だてて明快に説明している。「ただ」をビジネスに取り込んでいる企業がいかに多く、これからも増えるだろうことがよくわかる。自分自身のビジネスについて考えさせられる。
0投稿日: 2010.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログビット(情報)経済で発生しているフリー(自由かつ無料)である経済のやり取りに関する考察。冒頭に、経済を原子(アトム)経済と情報(ビット)とに分割し、後者の限界費用(コスト)は潤沢な為、限りなくフリーに近接するから、フリー以外の価値のある物で利益を上げていくことが必要になるというのが主張。換言すると、95%の無料から5%の有料でビジネスが成立し得る例をgoogleより、また産業転換の事例として、プロダクション化した中国のレコード会社等の事例を挙げている。フリーの分解、(1)直接的内部相互扶助(ex.公的機関における起業支援教室…税収増)、(2)三社間市場(いわゆるマスメディア)、(3)フリーミアム(スカイプ)、(4)非貨幣市場(webのQ&A等。贈与経済)が分かり易い。価格決定権を失いつつある産業の価値は、非収益化により価値は別の形で配分される、という言葉が印象的。注目と評判を、別の事柄と結びつけ収益にすべき、ゼロとそうでないものとの需要の動きに関しての違いを行動経済学の視点も交え、分かり易く説明されていた。
0投稿日: 2010.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ話題の新書で題名に惹かれ買ってしまった。 読むべきところは非常に限られた部分であり、目新しい論理はあまりない。 話題負けしている感が非常に強い。 この手の本で失敗したのは久しぶりで ランキングだとか、口コミとかを当てにしすぎてもいけないのだなと実感しました。
1投稿日: 2010.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログひたすら面白い。現象も見る角度によって異なるように、モノの売り方も視点を変えれば違うということだろう。 何でもFree(無料)になるわけではなく、必ずどこかに儲けの仕組みが存在しているところが大事。 けど、やはり消費者は無料という言葉に弱いからなぁ。。。
0投稿日: 2010.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ本日は、『FREE 無料からお金を生み出す新戦略』 (著者:クリス・アンダーソン 監修・解説:小林弘人) をご紹介します。 ≪本の内容は≫ ************************************************************************** 『ロングテール 』の著者として有名な、Wired 誌編集者の クリス・アンダーソンが「無料」をテーマに書いた本です。 本書で紹介されている彼の"フリー"理論には以下のような ポイントがあります。 ・デジタル時代には、「アイデアで出来ているもの」 (音楽や映像、情報など)には強い値下げ圧力がかかり、 防ごうとしてもやがては無料に近づいていく。 ・技術の進歩により、デジタルコンテンツを配信するコストは 限りなくゼロに近くなった。 ・消費者は無料に弱い (例えば『予想どおりに不合理 』のキスチョコ実験が引用されて います)。 ・"フリー"はすなわち、クオリティの面から取捨選択を行う必要が なくなることを意味する (例えば YouTube ではビデオ(動画)をアップするのも見るのも 無料なので、コンテンツのクオリティが問題にはならなくなる)。 ・"フリー"をテコにして、別の部分で儲けることができる (ミュージシャンがCDセールスを諦め、コンサートの入場料で 儲けるなど)。 アイデアを商品とする私たちとしては非常に興味を持つ内容が 記されています。 このフリー理論については賛否両論様々な論議がされておりますが、 今一度、「何が商品となり、何に対して対価が支払われるか。」 そんなことを改めて考えるきっかけを作ってくれることには間違いない 1冊です。 ≪この本との出会いは≫ ********************************************************* 広告(アドバタイジング)を勉強するため、現在アメリカに留学している 妹より紹介してもらいました。 実際には本の紹介というよりは、発売に先駆けての『ウェブで本文全文の無料公開』といった広告について一報をもらいました。↓ http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20403606,00.htm 米国での7月の刊行時に、「freemium」(フリーミアム)戦略として、 デジタル形式で無料公開した際に2週間でダウンロード数が30万件を 記録し、「NewYork Times」紙のベストセラーにランクインしたそうです。 妹の大学のクラスでは、公開された翌日には「まだ読んでないの?!」と 言われてしまうくらいの注目度だったようです。 新しい物や考え方に対して「拒絶」ではなく「興味」を持つ。 改めて学生の積極性に感化されました。 妹よ…そんな気付きをありがとう。 ********************************************************************* 本は、誰からどのタイミングで紹介されるかなどで 受ける影響力が変わってくると思います。 どうぞ今回のトクマガが少しでも皆様の中に残りますように…。
0投稿日: 2010.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ従来の商品そのものを売ることで、儲けるのではなく、付随するもので利益を出すなどといった、従来のビジネスモデルとは異なる手法のビジネスモデルが今後増えてくるだろう。 というか、既にたくさんのフリーという戦略は行われている。
0投稿日: 2010.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ経済理論の基礎は、競争状態では「価格=限界費用」が実現することにある。デジタル革命で限界費用が限りなくゼロになれば、価格もつかない無料になる、というのは理解できる。その周辺で儲けよ、というのも理解できる。 しかし、その周辺というのが難しい。フリーミアムというが、プレミアム版も限界費用は限りなくゼロに近いはず。この部分で対価を払うという差別化はどう生み出されるのだろう。また、携帯電話無料のモデルが出てくる。これはアトムである携帯電話をゼロ円にして、ビットである通信料金で回収するということになるが、ビットのフリー化が進むとすれば、維持可能なビジネスモデルではない、と言えるのではないだろうか。 いずれにせよ、本書はいろいろな議論を巻き起こす。著者もフロー理論を押し付けようとはしていないように思える。議論のスタート台として大変優れた著作だ。翻訳もとても読みやすい。
0投稿日: 2010.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2010年を象徴しそうな「フリーミアム」。 面白過ぎる本で350ページ一気に読んだ。 構造転換を身近に感じられる刺激的時代。TSUTAYAのスタバで無料で読書しながら思う 2010年5月の読書会課題本。
0投稿日: 2010.01.10
