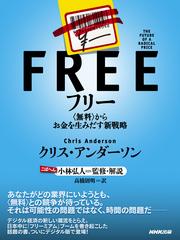
総合評価
(528件)| 140 | ||
| 210 | ||
| 99 | ||
| 9 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フリーと呼ばれているビジネスモデルの仕組みを理解できる良書。インターネットの内側世界を利用したビジネス改革を考える上では必要なアイデアが紹介されている。実体(本書で言うアトム)を扱う業界へいかに適用するかが商機だろう。
0投稿日: 2011.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
google, Facebook, myspaceなどのSNSをはじめ、デジタル時代ではほとんどのものがフリーになりつつある。 なぜフリー(無料)から利益を得ることができるのかがこの本を読めばわかるだろう。 本の構成としては、はじめフリーに関するビジネスモデルを紹介し、中盤ではハード面の半導体の技術向上から今日のソフトウェア開発にいたるまでの歴史を紹介しながらどのようにしてフリーが育っていったのかを解説している。そして最後にフリー経済についての疑問点をQ&A形式で筆者の意見を述べている。 はじめの章のモデルを事例と照らし合わせて裏付けていく形をとっているので、フリーのビジネスモデルを知りたい人ははじめの部分のみ読めば十分にその仕組みを理解できるだろう。 巻末にフリーのビジネスモデル事例50例を紹介しているのが面白いかった。
0投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ・12/16 これもiTunesストアでその名のとおり無料で出ていたので即ダウンロード.こういう企画は大歓迎. ・10/10 ようやく読了.なんとほぼ10ヶ月かかった。無料で儲ける仕組みは今後ビジネスをやっていくためには知識として必要な概念だということがよくわかった.
0投稿日: 2011.10.10 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーミアム戦術は、ネットの中のあらゆるところで使われている。頭では分かっているが、言葉で整理してあるので助かった。 故に益としたい。
0投稿日: 2011.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料ビジネスについて、具体例を多く含みながら説明。筆者のブログはなかなか面白いし、英語の勉強にもなるから一石二鳥だ。この本を読むきっかけは、少し前に読んだ無料ビジネスの時代という本にFREEを参考にしたところが多かったからだ。「無料ビジネスの時代」という新書でざっくりと無料経済について学んでいたので、この本はいまいち面白くなかった。厳密にいうと、すらすら読めなかった。これはマイケル・サンデルの「正義」の本も同じことが言える。翻訳の本と相性が悪いのかな?
0投稿日: 2011.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「ロングテール」の概念を紹介した著者による、インターネットによる事業環境の変化解説。 「高尚」なパートが多く長いのがネックですが、事例豊富で足許の変化をよくまとめています。 まず、デジタルの世界は限界費用が低いので、競争が進展すると必然的に無料になりやすい。 逆を言えば、リアルの世界とは異なり、デジタルならサービスを無料にできる。 このサービスの無料化は、圧倒的な規模の顧客へのリーチを可能とする。 圧倒的な規模の顧客へのリーチは、その周辺分野(Googleの広告事業、Linuxのサポート業務、 ライブ等のリアル事業への接続etc)や製品差別化(フリーミアム戦略、 機能限定版のみの無料化etc)で収益化(マネタイズ)のチャンスを提供する。 多くの「無料」ビジネス事業者は、既存ビジネスの収益源(OS、音源、ゲームプログラムetc)を 無料化することで一気に見込み客を獲得し、別なところで収益を稼ぐ 「既存ビジネスモデルの破壊」で躍進している。
0投稿日: 2011.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局価値を何に見いだすのは世の中に足りないって思って自分で創ろうという行動力がある人。 結構当たり前のことを淡々と書いてたけど、読み応えはあった。がなげぇよ!
0投稿日: 2011.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネットの発達で限界費用がゼロに近づく世界が拡がる。 昔ながらのフリーランチのようなものだけではなく、様々な形で「無料」が届けられるようになる。今までになかった規模の人を巻き込み、一人ひとりが気にならないほどのお金を負担するというモデルが成り立つ。 最近起っていることの理解をする、頭の整理をするのに役立つ。 でも音楽業界の話は違う気もする。注目と評判だけで人間食えるのか?そんなにコンサート収入は大きいのか? この世の中の流れを受け入れて戦略をとるのか、抗ってプライドや体裁やそういったものを守る戦略をとるのか、日本の音楽業界はどうするんだろうな、とふと考えさせられた。
0投稿日: 2011.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス書の類いは好きではないけど、そうではなくある種のエッセイくらいのつもりで。 それよりなにより実験的にiphoneアプリで、電車内のみで読破。 この哲学に共感できるかどうかは、Appleが理解できるのか? SONYとの違いがわかるのか? ということなのかな。
0投稿日: 2011.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本書は、2009年に発行されたベストセラーであり、内容については、様々な場面で取り上げられたこともあり、わかった気になっていたが、改めて手にとってみた。 フォトリーディング&マインドマップで1時間を費やした。 どの程度頭に入っているかは不明だが、理解したことを文字に起こしておこうと思う。 著者は、あの世界的ベストセラー『ロングテール』の著者であり、「ワイアード」誌の編集長でもあるクリス・アンダーソン。 インターネットが生み出したビジネス「無料化」の潮流と、その成 功事例を取り上げた一冊。 アトム(リアル)の世界では難しい無料化が、ビット(ネット)の世界では、簡単に(ノーコスト、ローコスト)で可能となる。 フリーとは、文字通り「無料と自由」である。 「無料」と「ビジネス(金儲け)」。 以前であれば結びつかないワードであるが、近年、非常に多く見かけるマーケティング手法となっている。 フリーは「ビジネス(金儲け)」と敵対するものではない。 フリーからお金を生み出す方法を考えなくてはならない。 フリーの期限は古い。 例えばゼラチンをジェロとして食べるようになったのは、「無料」でレシピブックを配布したことによる。 ジレットは、ホルダーを無料で配布したことで、替え刃が売れた。 (ジレットはホルダーの無料配布をしたことはなく、都市伝説という噂もある) 紳士服店の「2着目は無料」。本当は50%OFFの見かけフリー戦略 グーグルの提供するサービスは無料。 グーグルはサービスを非収益化することで、最大市場にリーチして大量の顧客をつかみ(最大化戦略)広告価値を上げることで収益を挙げている。 無料ゲームのGREEやモバゲーは、無料なのに凄い利益を挙げている。基本部分は無料だが、レベルアップしたり、より楽しむためには有料のアイテムなどを買う必要があるというビジネスモデル。 マイクロソフトは、無料で何でも提供するグーグルを自ら築いたビジネスモデルを脅かすものとしているが、過去においては、インターネット・エクスプローラーをPCに無料バンドルすることで、ネットスケープを駆逐している。 無料は、責任からの自由を意味する。 無料のランチは食べ散らかすことができるが、少額でもお金をとると残さず食べる。しかし、有料にすることで、食べる人は極端に減ることになる。 {確かに、バイキングで、フリーの食事やドリンクはと残したり、食べ散らかしたりするけど、料金が発生するアルコール類は残さないよな。(ちょっと違うか)} 潤沢な情報は無料になりたがる。稀少な情報は高価になりたがる 有料メディアの終焉は近い。他で稼ぐ必要がある。 中国やブラジルはフリーの先進地域。コピー天国でそれを許す。例えばCDをコピーされても、メジャーになる方が重要。メジャーになれば、コンサートで稼ぐことができる
0投稿日: 2011.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめて「自炊」した本。猫がおしっこをかけてしまい、読めなくはないけど臭いがひどくてやむを得ず捨てることに。でも捨てる前に、いっそのこと裁断してスキャンしてみよう、と思ったわけです。本書は電子書籍アプリとして一部フリーで提供されていたりしましたが、それと自炊を比べることが出来たのも何かの縁でしょうか。自炊も専用アプリの電子書籍も、どっちもまだまだ使いやすいとはいえず、その後積極的にはやっていません。 一応レビューも書いてみると、少し前の本ですが、厚いけど難しいことは書いてないので、フリーミアムって何?という人も必読です。自分の仕事がそういう仕事ではないと思えても、それでもひょっとしてそういうモデルがあるかもしれないと頭をひねるのは楽しいものです。
0投稿日: 2011.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯にある 「本書は間違いなく2010年代を生き抜くのに欠かせない一冊だ」はうそではないだろう。生活のあらゆる部分にインターネットを通した情報が関与している今、その情報の流れがどのような思考の元で流れているのかを知るのは必須だ。特に企業、マーケティングにかかわる部署の人たちは今後の展開において参考となること多し。 デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる、というのは生活の中でなんとなく実感できるところだ。これが進んでいくスピードによって企業の盛衰は左右されるかもしれない。 勤める企業が、部署が沈む前に転換を図れるように読んでおく必要がある本のようである。
0投稿日: 2011.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ『第1章 フリーの誕生』 ・フルーツゼリーの基、ジェロ。レシピ本を無料で配り、売上を伸ばした。こうして、20世紀でもっとも強力なマーケティング手法のひとつが誕生した。すなわち、あるものをタダであげることで、別のものの需要をつくり出すことだ。 ・今日のもっとも興味深いビジネスモデルは、無料からお金を生み出すところにある。遅かれ早かれ、すべての会社がフリーを利用する方法や、フリーと競いあう方法を探さざるをえなくなる。本書は、その方法について記してある。 『第2章 無料とは何か?』 ・フリーは4種類に大別することができる。これらは、一歩下がってみると、「内部相互補助(ほかの収益でカバーすること)」という点で同じだ。 ①有料商品で無料商品をカバーする。 ②将来の支払いが現在の無料をカバーする。 ③有料利用者が無料利用者をカバーする。 フリー①:直接的内部相互補助 フリー②:三者間市場 フリー③:フリーミアム フリー④:非貨幣市場 『第3章 フリーの歴史』 ・今日、市場に参入するもっとも破壊的な方法は、既存のビジネスモデルの経済的意味を消滅させることだ。つまり、既存ビジネスが収益源としている商品をタダにするのだ。すると、その市場の顧客はいっせいにその新規参入者のところへ押しかけるので、そこで別のモノを売りつければいい。 『第4章 フリーの心理学』 ・心理バイアスに関しては(すべての経済活動は心理学に根ざしている)、「これはそれだけの値打ちがあるのか?」という疑問の旗を揚げさせない方法があれば、うまくいくのだ。 ・靴の通販のザッポス。「唯一の問題は、たくさんの靴を注文して返品することに、いまだに多くの人が罪悪感を覚えていることです。返品をもうしわけないと思うがゆえに、はじめから注文しないことが問題なのです」 ・フリーが及ぼしうる悪い影響の一つ。タダのものは大切にしないのだ。 ・時間とお金の方程式:子供のときはお金よりも時間を多く持っているために、手間がかかっても無料を優先する。だが年をとって時間とお金の関係が逆になると、フリーミアムの世界においてお金を払う顧客になる。 『第5章 安すぎて気にならない』 ・もし電気がタダなら、どうなっていただろう?熱交換率など考えられず、電気が関わるほとんどすべてのものは、変化しただろう。すなわち、「安すぎて気にならない」は世界を変えたかもしれないのだ。 『第6章 「情報はフリーになりたがる」』 『第7章 フリーと競争する』 ・フリーに関して昔からよくある問題。既存企業よりも新参企業のほうがフリーを利用しやすいのだ。 『第8章 非収益化』 ・ほとんどの者はフリーを利用して、自分のアイデアがうまくいくかどうか、消費者をひきつけられるかどうかを確かめる。消費者をひきつけれられれば、次は彼らが何にお金を支払うか、あるいはほかにどうやって収益をあげるのかという質問に移るのだ。 『第9章 新しいメディアのビジネスモデル』 ・はっきりしているのは、オンラインでは広告のあり方そのものが違うことだ。従来のメディア広告は、その商品に関心がありそうな10%の視聴者に届けた。グーぐるの広告は、ソフトウェアを使うことで、内容ともっとも関連がある人にだけ広告を見せる。 『第10章 無料経済はどのくらいの規模なのか?』 『第11章 ゼロの経済学』 ・ちょっと待ってほしい。ソフトウェアは限界費用がゼロに近いはずだ。なぜマイクロソフトの製品は、数百ドルで売れるのか?答えはモデルの中の「競争市場」という部分にある。マイクロソフトは、独占状態をつくれたのだ。 ・限界価格(限界費用とは異なる)がゼロに近いビジネスは身近にいくらでもある。バイキング方式の朝食、インターネットの使い放題のプランなど。固定料金は限界価格の持つ負の心理的要素を取り除くので、消費者は気分良く消費ができるようになる。 『第12章 非貨幣経済』 ・あらゆる潤沢さは新しい希少性をつくり出す。私たちは、まだ充分に持っていないものに高い価値をつける。たとえば、職場で無料のコーヒーを好きなだけ飲めることで、よりおいしいコーヒーの需要を呼び覚ます。 ・私たちは自分が重要だと思う領域で無償労働をすることによって、尊敬や注目や表現の機会や観客を得ることができる。要するに、私たちが報酬なしでも喜んですることは、給料のための仕事以上に私たちを幸せにしてくれる。マズローの自己実現である。 『第13章 (ときには)ムダもいい』 ・カーヴァー・ミードはトランジスタを無駄にすることを説き、アラン・ケイがそれに答えて視覚的に楽しいGUIをつくり、それによってコンピューターがつかいやすいものになった。それと同じで今日の革新者とは、新たに潤沢になったものに着目して、それをどのように浪費すればいいかを考えつく人なのだ。 ・だがおもしろいのは、ムダというのは常に、稀少だと人が思うものと結びついていることだ。 ・私たちはムダに関して非常に発達した倫理観を持っていて、気に入らないおもちゃや食べ残しを捨てることに罪悪感を覚える。その感情にちゃんとした理由があるときもある。浪費によって社会的コストが増えることを理解しているときだ。だがたいていは、たんに私たちの哺乳類としての脳が、罪悪感を覚えるようにプログラムされているからだ。 『第14章 フリー・ワールド』 『第15章 潤沢さを想像する』 ・物質的豊かさは、生きる目的を奪ったのではなく、生きる意義の欠乏状態をつくり出したのだ。アテネ市民はマズローの欲求段階を登っていき、科学と創造性を探求した。 『第16章 お金を払わなければ価値のあるものは手にならない』 『結び 経済危機とフリー』 ----------以下感想---------- ウェブのビジネスについて曖昧に理解していた点がはっきり理解できた。
0投稿日: 2011.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ一回読んだ。深く理解するため、仕事でのビジネスモデルを考えるときにフリーを取り入れるためにもう一度精読したい。
0投稿日: 2011.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ“フリー”について、歴史、実例、理論、反論と網羅的に書かれている。 それぞれ切り口は、明確で分かりやすいのだが、読み進めるリズムが掴みにくいのは、翻訳の問題なのだろうか? 産業革命になぞられるビット世界の登場が、パラダイムシフトであり、その大きな特徴がこの”フリー”のように感じた。 新しい大きな流れ、傾向が、”フリー”に象徴されているのだが、昔からあった手法が、ビット世界により拡大されたものであるという話ではあるが、さらに価格・貨幣ではない、人々の新しい動機を生みだしている点には納得。 ぼやけた頭のネジを締めるまでには至らないが、改めてネジが錆びつきかけている事を認識させてくれた。
0投稿日: 2011.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1章 フリーの誕生 第2章 「フリー」入門 第3章 フリーの歴史 第4章 フリーの心理学 第5章 安すぎて気にならない 第6章 「情報はフリーになりたがる」 第7章 フリーと競争する 第8章 非収益化 第9章 新しいメディアのビジネスモデル 第10章 無料経済はどのくらいの規模なのか? 第11章 ゼロの経済学 第12章 非貨幣経済 第13章 (ときには)ムダもいい 第14章 フリー・ワールド 第15章 潤沢さを想像する 第16章 「お金を払わなければ価値のあるものは手に入らない」
0投稿日: 2011.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ印象に残った言葉、”あるものやサービスが無料になると価値はひとつ高次のレイヤーに移動する”。 アテンションを集める非貨幣経済、そしてそこから貨幣を生み出す方法に注意をしよう。
0投稿日: 2011.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ流し読みした部分も多かったけど、こういう種類の本をあまり読まないので面白かった。なんとなーく、わかったような気になっていたことの理解が深まりました。なんとなーくかもしれませんが…。
0投稿日: 2011.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「無料ビジネスの教科書」 そんな肩書きを贈りたい1冊である。 書籍として、無料ビジネスを体系的に扱ったものは 私の記憶している限りでは、本書の登場まで意外と少ない。 とくにネットビジネスにおけるメディア戦略が話題の中心となっており、従来の広告ビジネスに留まらない解説が嬉しい。 直接的内部相互補助、三者間市場、フリーミアム、非貨幣市場といった現存する無料ビジネスの分類の解説はとくによくまとまっている。 ジャーナル等ではすでに紹介されている事実が多いため、 勉強熱心なビジネスマンや、この手の仕事に付いている人には とくに目新しいわけではないのが本書の欠点かもしれない。 だからこそ、「教科書」なのだと私は考える。 また、解説されている事例が妙に多い。「話題が豊富」というよりも散漫な印象が拭えない。もう少しテーマを絞って、テンポのよい文章にした方がリピーターは増えるのでないか。
0投稿日: 2011.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ随分前に読み終わった本。いちおう棚においておこう。シェアよりは全然よい。カリフォルニア哲学の現在みたいなきがするんだよね。
0投稿日: 2011.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料ビジネスの変遷から、 様々なビジネス形態、 そして、これからの展望までわかりやすく書かれています。 海外発の作品なので、具体例がちょっととっつきにくかったりしますが、これからますます増えていくであろうフリービジネスに関して理解の深まる良書だと思います。 買うのはなぁっと思う人に対しては、 iphoneのアプリでも無料で読めたはずです。
0投稿日: 2011.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログapp storeで購入し読了。Googleの考え方や当時のLinuxとWinの戦いが記載されてて参考になったかな?
0投稿日: 2011.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログボリュームが多く余分な部分が少々かったるいが非常にためになる。 WEBを中心とした収益モデルの今昔、いろはが詰まってます。 これからの時代のビジネスモデルの引き出しを増やすアイデアのヒントになる。 印象深いのは、コピー大国とバカにされていた中国が、音楽の流通に関して言えば実は合理的で世界の最先端なのもしれないという事実を受け止めなければならない状況を知ったことだ。 2011.7.1-26 図書館
0投稿日: 2011.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料という撒き餌を軸にしたお金を稼ぐ様々な手法に感心させられ、とても勉強になった。しかしまだ読みきれてない…。
0投稿日: 2011.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ正直、読みにくい。 それは、自身の読解力がないのか、 それとも、内容が複雑すぎるからなのかは不明ですが、 もっと簡潔に書いてもいいのでは?と思ってしまいました。 ま、電子書籍で、「フリー」で買ったから良しとしよう。
0投稿日: 2011.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、参考になる話が満載。読み終わるのが楽しみです。 以下、学習院大学学生さんよりの紹介文 高校の卒業研究のために読んだ本。「タダより高いモノはない」という言葉はネガティブでなくポジティブな意味。「無料のものに価値がある?!」⇒価値のないものなどない! <まさにその通り!>
0投稿日: 2011.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の分厚さからいくと、もっと従来のフリービジネスについて多く取り上げてくれるのかと思ったが、思ったよりもオンラインの事例がメインで取り上げてあったので、その分野にそれほど詳しくない自分にはちょっと難しかったかも。 事例を豊富に挙げていて、力を入れているなとは思う。著者がフリーについて思いついたこと、考えること、言いたいことを全て取り込んだ感。もうすこし的を絞って一冊にまとめることもできたかも。 フリーに関する他人の意見への反論を一つずつ丁寧に列挙しているあたり、著者の力の入れようが半端なく伝わってくる。これがいいか悪いかは判断が分かれるところ。
0投稿日: 2011.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログフリー(無料)の歴史にはじまり、フリーの形態を説明し、なぜフリーがこれほど浸透したのか、なぜフリーが成り立つのかを分かりやすく解説している。なぜGoogleがビジネスアプリを無料で提供できるのかなど読むと納得する。デジタルの世界ではフリーは止められないと著者は言っている。ビジネスに携わる身であれば一度は読んでおくべき。
0投稿日: 2011.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログもうちょっと短くまとめてくれたら、もっと評点を高くしたいところ。 ビジネスの視点を変更させる事での可能性をインスパイアしてくれる、ちょっと古いけれども良書。 事例も豊富でどれも面白い。 キャッシュポイントを変える事を検討したくなったかも。
0投稿日: 2011.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非常に面白い。 フリーによるビジネスモデルを探求しているとだけでよむと 普通のビジネス書。 だけどそれを超えて、 21世紀の社会が産業革命以来の大変革を迎えて、 経済学から人の価値観、政治や人の倫理観まで、 全てが変革していく、その一断面を切り取っていると考えると、 とてつもない深さをもてる可能性のある本だと思う。
0投稿日: 2011.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ今流行の一冊。よく平積みされてます。 「ただより高いものは無い!」とよく言いますが、 この本を見ると最近は必ずしもそうでもない状態になっている事に気がつかされます。 この本を読んで今後の新たなビジネスモデルに「FREE」がカギとなるのは間違いなさそうです。 新たな発見も多く、流行っているだけのことはあって、数多くの事例は興味深く読み進められます。 個人的には海賊版とFREEの関係がおもしろかった。 しかし、その分中身はあるものの、300ページ以上あるので読むのに結構時間がかかります。 内容自体は大変おもしろいので、簡易版なんかが今後出るのに期待。
0投稿日: 2011.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
情報やサービスの享受が限りなく「タダ」になることの仕組みがよくわかる本。 おおかた納得して読めるんだけど、音楽の違法コピーや、中国を中心としたブランド品の模倣品の話は、結果としてプロモーションとして成り立っている部分もあるとはいえ、それでいいとはけして思えないんだよな…。そのあたり、著者には賛同できないかも。 あと、全体的に日本語訳がちょっとわかりづらく、同じ文章を何度も読み返すことがありました。
0投稿日: 2011.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ「この商品本当にタダで大丈夫なの」と思うビジネスの数々。その裏にはこういう収益構造があるのか、と非常に勉強になった。フリーを切り口とし、その周辺のビジネスで利益を出す。インターネットの発達し、タダが日常化した現在ではこの発想は常に必要なのかも。
0投稿日: 2011.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっと古い本だけど、一応読んでおいた。 特に目新しい「フリー」の形が提示されてるわけではなかった。(というか、そもそも無料の例ですらなかった。Wikipediaやオープンソースは無料かもしれないが、どちらもそもそも商売じゃないしね) 「ビットの世界では価格は0になるんだ!」とだけ言われても、作ってる人は困っちゃうよね。(まぁ、「フリーミアム」は別に無料じゃないんだけど)
0投稿日: 2011.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「タダより高いものはない」その価値観を崩される自体がおきている。 何故なのか、何なのか、知りたい方はこの本を。 『SHARE』もオススメ。 件名:eマーケティング
0投稿日: 2011.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ新しい商売のあり方を衝撃的に示した本。 これからのビジネスはフリーをいかに有効に使えるかで決まってくるようだ。しかし、従来の経済にフリーが割って入ることで経済の規模全体が縮小して、うまくやったところに金が流れるという現象が起こることについては、どう考えればいいのだろう。これまでの経済が肥大化しすぎていたのだとしても、急激な変化は市場に混乱をもたらす感じがする。 それはそれとして本書はこれからのマーケティングの革新的なあり方を具体的に示した快著であり、きわめて価値の高い1冊であることは間違いない。何度も読み返し、自分の仕事や投資行動に活かしたいところである。
0投稿日: 2011.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際の経済で起きている事象と、学術論を、うまく結びつけている名著。なにげなく利用しているいろいろなフリーなサービスを、いろんな観点から解説していて目からウロコが多かったです。これから起業しようと思うと一読しておいて損はないでしょう。 いくつか覚書をしておきます。フリーのビジネスの4パターン、①直接的内部相互補助(本人が違うところで支払う)、②三者間市場(広告関係など本人以外が支払う)、③フリーミアム(基本は無料、アップグレードは有料)、④非貨幣市場(実はうすくひろく負担)。あとおもしろいと思ったのは、「行けば無料、行かなければ有料のスポーツジム」とか、いくつかあるコラムとか。ICTの世界ではリソースの限界費用が0に近づくため、無料で大量消費が可能であり、それをいかにビジネスに結びつけるかが問われているということですね。ビジネスも、時代に合わせていろいろ挑戦していく姿勢が重要なんでしょう。
0投稿日: 2011.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログITにより、情報やツールの流通コストが劇的に低下していること、流通スピードや流通規模が劇的に上がっていることなどから、商品の生態系を根本から考え直すヒントをくれる本。 しかも、今は本書「Free」の無料版がiPhoneでダウンロードできる。ここには、次作のサンプルが付いている。本書の内容を自ら実践しているところがニクい!
0投稿日: 2011.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
感想は以下。 http://masterka.seesaa.net/article/209300472.html
0投稿日: 2011.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのたぐいの本は初めて読んだ。元々はフリーペーパーに興味を持ち始めて読んだもの。ビジネスを考える上でも参考になるし、日常がいかにビジネスに密接に結びついているかという視点からも割と面白い。 内容はフリーの歴史から始まり、心理、ビジネスモデル、経済学など多岐にわたるので興味のあるとこだけ読む感じでいいと思う。著者の網羅的な知識に驚いた。 ダンバー数など聞いたこともなかった。フリーということで潤沢さと稀少さが注目されておりしばしばでてくる。 デジタル世界、21世紀に入ってアトムからビットへの流れがすすみ、供給が圧倒的に増えた(潤沢) 潤沢になってくるとものの値段は安くなるという性質を帯びてくるので無料というものが出てくるのは必然だった。それは過去の経済学者も(当時は異端な考え方として認められなかった)予測していた。さらにフリーが潤沢していくことによって、デジタル世界ではお金ではなく、新たな通貨に価値が見いだされるようになった。非貨幣経済圏の誕生である。具体的には評価と注目である。これらはデジタル世界(ハイパーリンク)を通じて計測することが可能になった。大まかにまとめるとこんな感じ。googleやapple、Microsoftやフリーを使ったビジネスで成功している失敗している企業についても述べているのでそっち系にきょうみがあるひともおすすめ!
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「フリー」に関するビジネスを述べた本。 「フリー」は分かりやすくいえば無料の商品を提供しているビジネスを指している。無料のWebサービスを想定していただければ良いと思う。 簡潔に分かりやすくまとめられている。経済学や心理学を用いて「フリー」を分析している。 twitterやFacebook当の無料のサービスの恩恵を受ける一方、楽曲の違法ダウンロードや違法コピーの問題を孕む「フリー」。 その「フリー」の起源や今後の「フリー」のあり方を知ることができる。 「フリー」を体系的に学べるので「フリー」の入り口としてはいいんではないでしょうか?
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ今後、ビジネスを検討するにあたって、必ず意識をしなければならないフリー。特にコンテンツを製作するモノにとっては、避けては通れない。読書前の印象としては、フリーはコンテンツのチープ化の極めであり、良く言えばロングテール、悪く言えばコンテンツの氾濫を招くものだと考えていた。しかし、本書を通して感じたのは、むしろ逆だった。フリー経済で勝ち残るには、本当に質の高いコンテンツを作らなければならない。なぜなら、音楽にしても、ゲームにしてもコンテンツの質が低ければ(興味をひかないコンテンツならば)、フリー以上の関係にならないからだ。フリーは、課金をするテクニックに目がいきがちだが、勝つのは質の高いコンテンツを製作し、ユーザーと信頼関係を築いたモノだろう。
0投稿日: 2011.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ身近な「フリー」の理由がよくわかった 経済のことは知らないことが多いけど、ああこうやって儲けるのかと知った
0投稿日: 2011.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーミアムの考え方、事例をわかりやすく理解できる。新しくサービスを立ち上げる時、どこで稼いでどこは諦めるかは経営的な観点で必須。後半は若干冗長。AppStoreで無料で入手可能だったのは面白い試み。
0投稿日: 2011.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ雑多でまとまりのない印象を受けた.目新しい情報はなかったかなと思ったのは,自分がその分野の人だからか,本当に新しい情報がなかったからなのかはよくわからない.
0投稿日: 2011.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーミアムに集約されるコンセプトは、身近な素材であり、驚きを感じた。具体例が多いので、非常にわかりやすい。 本を読むようになって以来、ベストセラー翻訳本の素晴らしさを感じた。それ以来原書でも読むため、英語を自習している。
0投稿日: 2011.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ主旨から外れるが、 「テクノロジーの声を聞く」は 私に新しい視点を与えてくれた。 あと、ハッカー倫理、が全ての元ネタなのか、 と気づいた! そして、ブラジル…
1投稿日: 2011.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料で提供されるサービスがどのようにビジネスとして成り立っているのか? 「広告収入でしょ?」という単純なことではない。
0投稿日: 2011.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログWeb業界で働いてる人はみな体感してるであろうフリーという時代の流れの感覚。 具体的な言葉や事例を持って語られています。
0投稿日: 2011.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読んでる途中です。通読はきつい内容ですね。 2010年に出て話題になった本。2011年の5月に読んでいる。 “フリー”というものについて歴史的なことも踏まえて俯瞰。過去・現在・今後におけるフリーのあり方を一気に述べています。 読むまでは現代の状況をプラグマティズム的に書かれているのかと思ったら、概論のむちゃくちゃ大きい部分から述べているので意外な印象があった。 この人は理科系の人のようで、アダム・スミス、マルクス、現在に至るまでの貨幣・社会形成についての俯瞰に文学的なところがなくばっさりと切り取っているので、違和感ありつつも新鮮に読めてます。 いろんな要素がてんこ盛りなので、いろんな角度から読み方ができると思うのですが、結構ある一面からだけ語られてる本なのでは。 というのが途中の感想です。 ただ、いえるのは 「目次は細かくしてほしい!」 項目立てを細かくして目次にしてくれれば もっと読み込みと俯瞰した理解が楽になるのに。 本文で小見出しは立ててるのだから反映してほしいです。 通読ではなんとなく読んでおしまいになりがちな本なので出版社はそのあたり配慮すべき。
0投稿日: 2011.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
会社関係で用事があって読んでみました。 最近よく見かける“フリー”の仕組みが分かりやすく書かれていると思います。 要するに、“フリー”と言っても、本当に無料なわけではなく、どこかで誰かが何か(お金だけじゃなく、情報だったり、労働力だったり)を払っていることで成り立っているんですね。 言われてみれば「そりゃそうか」となるのですが、こういうことを一からビジネスモデルとして考える人がいるのはすごい。
0投稿日: 2011.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログボリュームがちょっと多いけど、楽しく読めた。「無料なコンテンツからどうやって収益を獲得しているのか」ということをテーマに、現代のマーケティングを丁寧に解説した内容だった。
0投稿日: 2011.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューを観て購入。本書で全体像を掴むことで、あらゆるフリーミアムを意識して考えることができる。だが成功するビジネスモデルを練るのは緻密な計算が必要な印象。余談だが、監修の小林氏があの「サイゾー」創刊者と知って納得。
0投稿日: 2011.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構大作だった。 後半、だらけ始めたが、まとめ的なもので、ふりかえりがあってよかった。 フリービジネスは、頭使うなと実感。
0投稿日: 2011.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ■図書館に行ったら真っ青な背表紙が見えたので、夏休みの宿題よろしく借りてきて熟読。ふーん、なるほど。って感じだったんだけど、この手の和訳ビジネス本は相変わらず読みづらいよなぁ...。 ■いや、言いたいことはよくわかりました。はい。
0投稿日: 2011.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログすんなり理解できるのは無料のコンテンツやサービスを使うのに慣れているからだろう。 音楽そのものはフリーでもライブ代金やグッズを売るビジネスはこち亀の両さんだ!ライブDVDをその場で販売とか
0投稿日: 2011.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的に非常に共感出来る本でした。一年前から読みたかったのでやっと念願が叶いました。 特に、無線ブロードバンド環境では、wi-fi技術および環境が最も「限界費用0」に近いと感じています。そういう意味でもとても参考になりました。 また、万能ではないと思いますが、飛び道具としての「フリー」も機を見て再挑戦したいです。 読了して改めて「限界費用0」および「フリー」への思いを強くしました。 改めて挑戦します!
0投稿日: 2011.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ110409*読了 いわずと知れた爆発的ベストセラー。図書館で予約していたので、遅ればせながらやっと読むことができました。 アトムのフリーとビットのフリー。これからもビットの世界では無料化が進む。フリーコノミクスやその他のフリーを利用した収益モデル。金銭での儲けだけがフリーのもたらす利益ではなく、知名度を高め、別の商品を売るために利用できることなど。例えば、海賊版はアーティストのCDの販売には貢献しないが、知名度を高め、コンサートの集客力を高めるので、結果的にはアーティストに利益をもたらしている。私は小さいときから、インターネットのある環境で育ったので、インターネットの世界のフリーを自然と受け入れてきた世代です。よって、その面では柔軟にフリーについて、もっと考えを巡らせることことができるのでは、と思います。インターネットの世界ではフリーであることは年々当たり前になってきているので、当時は読者にとって得るものが多かったのかもしれませんが、現在では当たり前のことも多かったです。時代はどんどん進んでいくのですね。
0投稿日: 2011.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ今現在社会で起きている現象は、すべてが新しい。 今の時代しか知らない自分たちにとって、このFREEな現象というのはごく当たり前にしか映らないのかもしれない。 けれど、これはとても斬新で新しい社会構造の始まりでもある。 そういう時代に生きている人にとって、このように時代を切り取り、未来を予測するための本はとても面白い。 ただあまり内容に感動を覚えなかったので評価は低めです。多分これは世代で評価が分かれる気がします。 途中にはさんでくるコラムはすごく面白かったです。
0投稿日: 2011.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々なフリー戦略に対する疑問を分かりやすく解説している名著。ウェブ上でのブランディング等の意味合いがますます重要度を増して行く中で、どのようにフリーという武器を効果的に使いこなせるかが鍵になっていくのだろう。
0投稿日: 2011.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ満足な内容。Webの中の人って、フリーなのが当たり前なシステムを作る・使うのはフツーに日常だと思うし、言われずとも体感していると思う。そんな人にとっても、いまのムーブメントを明確に整理された理屈で吸収しやすくまとめてくれている。 フリーの形態の整理のあと、このムーブメントは既存産業の敵ではなく、むしろ共存共栄をはかることで武器にもなりえる、という論脈。中国を中心にしたニセモノ文化や、ソフトのカジュアルコピーでさえ、その理屈にあてはめて「フリー」の亜種として語る(推奨してはいないけど)。 ものの見方はいろいろあるよなー、と改めて実感。結局人に受け入れられるものを、公共の福祉に反しないような流れ、フリーでもビジネスとして成立させるための努力を正面から全力でやる、そんなスタンスが今いろんな分野で求められているんだろうな。新聞とか雑誌とか…そういう流れだってことに気付いたほうがいいんだろうね。
0投稿日: 2011.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「SHARE」発売記念の電子書籍がフリー(無料)だったので購入して読む こういう自らの身をもって示す感じは素敵だ ネットをあまりしたことがない人にとってはフリーというのは大体以下のような反応をされると思う 「え~、無料?なんか怪しいし、私はいいや」 「無料より高いものはない」 という言葉があるように、通常何かを手に入れるためにはお金と交換しないといけないと考えている私たちにとって「無料」で何かを手に入れることが出来ることは、 「きっと自分の知らない所で何かを負担させられているに違いない」 という気持ちにさせてしまう しかし本書はその無料の概念は20世紀までのものだと看破する それを説明するために無料における数多くのビジネスモデルを本書は初めに紹介している 例えば、 「一つ買えば、もう一つはタダ」(二つ買うと半額) 「おまけ付き」(商品価格に送料含む) 「無料サンプル」(撒き餌=マーケティング手法) 「お試し無料」(使用期間が有限。解約しにくいことがある) 「タイヤの空気入れ無料」(補完的商品=場所への誘導=マーケティング手法) 「テレビやラジオ」(広告費でまかなわれている=三者間市場(消費者ではない他のものがお金を支払う)) といったものだ これらを経済学者は「内部相互補助」と呼んでいる しかし、本書の紹介する「無料モデル」はそのどれにも当てはまらない 当てはまったとしても進化したものだ デジタル技術が大きく進歩したことで可能になったことで、大きく分けて以下の4つに分けられている 直接的内部相互補助 無料:消費者の気を引き、他の商品を買わせられるもの 対象者:最終的に皆が喜んでお金を払う (要約:入口を魅力的にすること。結局、有料の物を買う) 三者間市場 無料:コンテンツ、サービス、ソフトウェア 対象者:誰でも (要約:魅力的なものを支援する誰か(広告主)を応援しよう。広告主の商品にコストが分散されて上乗せされる) フリーミアム 無料:基本版(プレミアム版は有料) 対象者:基本版のユーザー (要約:5%の有料版ユーザーが全体を支える。サービスコストが無視できるほど小さく、利用者が多いので可能) 非貨幣市場 無料:対価を気にせずにあげるものすべて(このブログとか) 対象者:誰でも いくつかパターンあり 贈与経済:貨幣の代わりに評判や関心を求めて為される共有 無償労働:無料サービス利用そのものによって生じる労働(グーグル検索はグーグルのターゲット広告のためのアルゴリズムを洗練させる) 不正コピー:楽曲やマンガ、小説など(デジタル技術進歩の宿命) 本書を有名したのが3つ目の「フリーミアムモデル」で、Evernoteなどのアプリで利用されていて、ネット上では特に有効だ 「ムーアの法則」によってデジタル技術は進歩し続けており限界費用は下がり続ける するとそれまでは気にしないといけなかった額の費用が急激に安くなり、0ではないが気にする必要がないほど少なくなる そして、インターネットでは評判さえ手に入れられれば現実世界とは違い、圧倒的多数の消費者が気軽に購入できる 1万人の消費者のうち5%が月額350円の有料版を買えば、それだけで17万5千円の収入になる これが10万人なら170万5千円、100万人なら1750万円になる しかもこの金額が(月額の場合)毎月入ってくるのだ これは、革新的なアイデアを持っている者たちにとっては画期的なことではないだろうか 人件費以外はそんなに多くの費用はかからないし(PC代とかの初期費用くらいだろう。後は場所代くらい。それも初期は自宅でも良い)、評判を集められれば何と魅力的なモデルだろう しかし、このフリーミアムモデルにも他のビジネスモデルと同様に弱点がある あくまで「評判を得られれば」なのだ しかもその評判を得る方法というのはサービスによっても違うだろうし、サービスがどんなに秀逸でもタイミングなどその他の要因が関わってくるだろう だから、このモデルは「サービスを乱立させるがその中からサービスをふるいにかけ秀逸なサービスが残る」という市場原理を有効に機能させる上で有用かもしれない その他、「無料」の歴史とか、インターネットにおける無料文化についてとか、フリーの心理学とか、メディアのビジネスモデルとか、非貨幣経済とか を無料経済について多面的な視点から説明しており インターネットが浸透した21世紀におけるフリー(無料)が与えるインパクトについて説明した良書だと思う 最後に本書の中で論師からは少し外れるが印象的だった内容 「儒教の文化では模倣することは尊敬を表す行為である」(要約なので間違っていたら申し訳ないです) 中国や韓国で違法コピーが多いのは、こういう事情もあるのかもな 確かに善かれと思っていることを(しかも主観ではなくて思想上の倫理として)直せと言われても困るよな
0投稿日: 2011.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「無料」という戦略でいかにお金を生み出すかがテーマ。 デジタル時代の現代社会において、おそらくこの無料化の流れは止まらないだろうというのが筆者の見解です。 今後、生活の様々な場面で「無料戦略」が仕掛けられ、魅力的なインセンティブを提供して収益に繋げる方法が次々と考案されていく と思われます。この本では「無料戦略」の儲けの仕組みがいろいろ紹介されていますが、これを知ると安易に無料戦略に乗ってしまう とマズイのかなと思ってしまいます。企業の「無料戦略」を上手く利用できる賢い消費者になりたいものです。 久し振りにビジネス書を読んで見ましたが、普段からメディアを通じて知っていた事も多かったように思います。 経済やビジネス情報は、世間の関心が高いだけに情報の賞味期間も短く、本になるときには古新聞のような印象になってしまいます。
0投稿日: 2011.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白い! 無料が金を生む新時代のビジネスモデル。 CDは売れないがライブやグッズで稼ぐ、フリーソフトの有料版で稼ぐ、広告で稼ぐ、などなど。 もう無料には抵抗するのではなく、ポジティブに取り入れるべきなのかも知れない。 -- p34 フリーのビジネスモデルは大きく4種類に分けられる。 ①直接的内部相互補助 ②三者間市場 ③フリーミアム(5%ルール) ④非貨幣市場 p56 150人という数字はダンパー数と呼ばれる。人間のコミュニティで各メンバーが強い絆で結ばれたままでいられる構成員の上限数だ。
0投稿日: 2011.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ2011 3/14読了。筑波大学図書館情報学図書館で借りて読んだ。・・・こんな状況(地震)だがこれ、いつ返せばいいのかね・・・? 今手伝っている研究プロジェクトに関連するかと思ったこともあり、いまさらながら読んでみた。 そして読んでみて「フリーミアム」の意味を全然勘違いしていたことに気付いたw やはり結構関連しそう(フリーのビジネスモデルについては特に)。
0投稿日: 2011.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ事例集、といえばそれまでなのかもしれないけど 時代の移り変わりを理解できないという人への入門書としてはいいのかなと思う。結構語り口も面白くて好き。 電子書籍で読んだらその凄まじいページ数(おまけ含む)に笑えてくる。 電子版のUIは秀逸。気になる場所をタップしてマーカー塗ったりtwitterでシェアしたりできる。電子書籍が全部この形式になればいいのにとすら思えた。
0投稿日: 2011.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ今後音楽をやっていく上で既存のビジネスモデルは大幅に変わることを実感した。やみくもにフリーを使えば良いというわけではなく、その使い分けとタイミング、また使う前の入念な準備と調査が必要だと思った。 音楽、ネットサービスに携わっていく上で非常に参考になった。
0投稿日: 2011.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーミアムという言葉が現在をよく表す言葉だが、どうして無料で経営が成り立つのかという事を海外の実際に成功した事例をもとに紹介している。すごくためになりました。
0投稿日: 2011.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログビジネス マーケティング クリス・アンダーソン フリーミアム FREE フリー 無料 経済 web twitter
0投稿日: 2011.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログネットによって経済はどのように変化したのか、 あるいはこれから変化していくのか、 これからの経済の趨勢を語るのであれば、 この本を読まずしては語れない。 アトムとして持っておきたい一冊。
0投稿日: 2011.03.03 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーミアムビジネスはどうすれば成功できるか?というようなビジネスノウハウ本ではなく、20世紀型貨幣経済の中で現れた「フリーミアム」とは、どのようにして可能となるのか?という一種の経済思想本。貨幣経済と非貨幣経済の差異、フリーミアムの生まれ方、フリーと相対したときの人間の心理などがまとめられていて、とても興味深く読み進めることができた。いい意味で予想を裏切られた感じ。iPhoneアプリで通読したが、マーカー機能やフォントサイズの調整が備え付けられていて使い勝手も良好。
0投稿日: 2011.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今、YOUTUBEなどでは、ほとんどのアーティストの曲が無料で見られる。 これじゃぁ、CDが売れなくなるのは当たり前だよなぁ、 これからの時代、アーティストはどうやって作品を現金化するんだろう、 そんな疑問に答えてくれるのがこの本。 (成功例ばかりなので、丸ごと信じるわけにはいかないが…) 例えば、レディオヘッドは新曲を無料で配信した。 多くの人が無料で彼らの曲に親しんだ結果、CDも売れ、ライブの動員も上がった。 ファンが増えれば、グッズの売上もあがる。 楽曲以外のところで現金化するシステムがあれば、フリーは大きな広告になる。 同じことが作家にも言える。著作をネット上でフリーにすることで、今まで読んだことのない人が読むことになり、 結果、過去に書いた著作が更に売れることにつながる。 「作家にとって、本は読んでもらわないと意味がない」と割り切れる人はフリー道を進めるだろう。 更に、講演などで儲けている人にとっては、著作は一種の宣伝材料なのだから、フリーでも読んでもらえるに越したことはない。 ポイントは、 *コンテンツに1円でも課金すれば、人は欲しがらない。 *無料でも人に知ってもらうことが新たにお金を産む。 なるほどな。
0投稿日: 2011.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログただ。だからお金が生まれる。 一見逆説的なこの論理。 その背後にはデジタルという領域がある。 無料のルールを作者はこう説く。 ①デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる。 ②アトムも無料になりたがるが、力強い足取りではない。 ちなみに「アトム」とは、原子の意味でモノの経済を指す。 ③フリーは止まらない。 ④フリーからもお金儲けはできる。 ⑤市場を再評価する。 ⑥ゼロにする。 ⑦遅かれ早かれフリーと競い合うことになる。 ⑧ムダを受け入れよう。 ⑨フリーは別のものの価値を高める。 ⑩希少なものではなく、潤沢なものを管理しよう。 一番気になるのが 無料からどう儲けるかであろう? ビジネスであれば ボランティアをし続けているわけにはいかない。 いちばん身近なフリー戦略の例は グリーやモバゲーなどのフリーゲームだろう。 無料でゲームができる。 しかし、より有効なアイテムなどを 手に入れるためにはお金が必要となる。 本書で注目したいのが 物語性という言葉だ。 情報は、デジタルは 無料になりたがる。 その流れに逆らえないとすれば 無料にする意味は何だろう。 それはコミュニティの成立であり そのためには 物語性が強く要求されるのだ。 そして、コミュニティができれば そこにビジネスチャンスは おのずと生まれる。 であれば! 注力すべきは 物語性の創出なのだ。 それを波及するためにこそ 「無料」が力強い。
0投稿日: 2011.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタルな世界に移行するに連れて、潤沢なものと稀少な物が何であるかが変化している。その変化に気付き、逆らわずに新たなマーケティングの方法を思いつくことが今後の成功へとつながる。今日では「評価」というものの価値が非常に高まっているようだ。コピーにより不満を漏らすよりも、それを逆手に取らなければうまく生存できていけない。また認識が世代間によって違うため、先輩にあれこれと聞いてはいはいというよりは、自分で考えて動くことの重要さが増して来るだろう。その点でホリエモンは先駆者のような(日本では)存在ではないか。また無料であることの裏側で、本当に自分はどんな価値にお金を払っているかを考えるべきだ。例えば、大学の無料講義がyoutubeで放送されているが、私たちは大学にお金を払ってまで行くということにどんな価値があるかを考えるべきだ。本書で私が重要だと思ったことは、潤沢さと稀少さを意識すること、オンラインにおける評判を重要視しうまく資金へと変えていくと言うことだ。
0投稿日: 2011.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報は高価になりたがる。なぜなら貴重だからだ。正しい所に正しい情報があれば、私達の人生さえ変わりうるのだ。他方で情報はフリーになりたがる。なぜなら情報を引き出すコストは下がり続けているからだ。
0投稿日: 2011.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルはおそろしいです。既存の市場に破壊的に参入しようと思えば、タダは強力すぎる武器になります。当然ですが、タダに人々は飛びついてきます。グーグルはさまざまなものでタダを実現しています。インターネットのようなデジタルな世界は、複製に費用がかからないし、劣化もしません。そういう世界ではタダをばらまくことができます。 昔は「タダほど高い物はない」といわれ、詐欺・マルチまがいの商法がありましたが、グーグルなどのインターネットの世界では、本当にタダが存在します。基本的に利用する側は無料で、広告費で儲けるというテレビと同じスタイルのビジネスです。(しかし、OSのアンドロイドはどのようにして収益を上げるのだろう?宣伝効果のみ?) これからは物を売って直接お金を得るのではなく、間接的に儲けるビジネスを考える必要があります。「消費者側には無料で使用できている感覚をあたえて、間接的にお金を払っていただく」といったビジネスです。 考えはじめると無料で人を集めて、その他で利益を上げることがいろいろできそうです。しかも集められた人々は無料で利用している感覚しかない。何かできそうです。
3投稿日: 2011.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ今世の中で起きていることが説明されており納得した。 サービスをフリー(無料)で提供し、これまでとは別の手段で収益化するビジネスモデルは、スゴい発想。 この動きが加速すると世の中がとんでもないことになる予感がする。
0投稿日: 2011.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ電子書籍にて読了。要約版を読んでからだったため、スムーズに理解することができた。要約版以上のものが得られたかと言われると微妙。フリーミアムのメカニズム自体は知っておく価値あり。
0投稿日: 2011.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ短く言えば、様々なフリーのモデルについて紹介した本(笑)。ケースバイケースであり、直接の何か転用というわけにもいかないであろう。 人の一歩先に行くには、もっと複雑にいろいろ絡めたり、もっとシンプルに大胆な発想をする必要があることを僕は知っている。
0投稿日: 2011.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初はiPhoneで読んでましたが、途中から書籍に切り替え。 内容は良いけど、操作性が悪すぎ、そしてやっぱり画面も小さいですね。 なるほど、これが戦略か…、ただ操作性の悪さはソフトの問題ですし画面の小ささはiPadなら大丈夫なのかもしれませんよね。 脱線しましたが、ネットを多用している人(していない人はここにいない気も、、)にとって目新しいことは無いのではと思います。ただ、フリーの歴史を振り返り、フリーを分類してくれていますので、最近の無料化の流れを整理する良い機会にはなりました。
0投稿日: 2011.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログすべてのコンテンツがデジタル世界に移行していこうとする昨今、クラウド化もどんどん進むコンピューター。僕たちの生活は劇的に便利になっていく反面、伝統的な企業にとっては色々と不都合なことも起こってくる。 『FREE』の台頭である。本来なら課金されてもおかしくないようなサービスがどんどんと無料で提供されていく。 パッと思いつくだけでも、yahoo、googleなどの各種free mail、FC2やアメーバなどの各種Blogサービス、facebookをはじめとする各種SNS、他にもtwitter、flicker、、、、など、山ほどあって数限りない。今ではそのフリーの波も音楽業界にまで及んでいます。 この無料への流れは、水が高いとこから低いところへと流れるように、デジタルテクノロジーの発達にともなっては抗うことのできないものである。言い換えるとそれは新たな段階への自然な移行で、今のデジタル社会は新たな転換点のひとつに差しかかっているということを意味しているようです。 コンテンツがフリー化するということは、企業にとっては収益の源泉の枯渇を意味し、企業活動の存続が危ぶまれる問題となってくる。 しかし、そんな新たなキーワードの「FREE」ですが、今の時代、先端的な事例でイノベーションに成功している企業は、収益の源泉をまったく違う他の新しい場所に見つけているのである。 世界がクラウド・コンピューティングで繋がるデジタルな方向に進みつつある中、FREEに振り回される企業とFREEを最大限活用する企業では明暗が分かれる。 この好機を掴めるか掴めないかの裏表は、迫りくるデジタル化によるフリーコンテンツの跋扈を自らの業界のピンチと捉えるのか、それとも新しい時代のチャンスだと捉えるかの違いにかかっています。 デジタルテクノロジーの黎明期を迎える今の時代、数々のテクノロジーが新しく生まれ落ちるのにともなって、自らの既存サービスも新しいビジネスモデルへとどんどんイノベーションをとげていかなきゃいけない。 読みごたえのある奥が深いオススメの本です。
0投稿日: 2011.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料化による様々なビジネスモデルを示していて今後うまくこれらを使っていかなければならないのだろうなと考えさせられた。ただ、電子書籍により読んでおり、こういったしっかりした本はまだ電子書籍より紙の本のほうが読みやすいなっていうのを感じた。(iPhoneだったため、電子書籍用リーダーなら別なのかもだけど。)
0投稿日: 2011.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーミアムの構造と歴史がよく理解できた。ページはやや多いけど、途中にコラムを挿んでいて読者を飽きさせない。GoogleやAmazon、Facebookなどの具体的な事例から儲けのカラクリを説明しているので、説得力があった。
0投稿日: 2011.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタルのものは、遅かれ早かれ無料になるという考えがよくわかる。本来であれば、世の中のものはビットになった瞬間に無料になるのが、(ビットの)性質なのだろう。音楽しかり、新聞しかり、メディアしかり、これからの時代は新しい価値を見出し、パラダイムシフトを図らなければならないのかもしれない。また、さまざまなビジネスモデルの説明がわかりやすい。フリーミアムの考え方は日本のケータイゲーム会社もよく使っている手法。新しい経済やビジネスモデルの勉強にはちょうど良い1冊だが、情報の特性などを前もって理解しておくと良いかもしれない。
0投稿日: 2011.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネットというインフラによってビジネスのルールが変わってくるという現実を事例を基に語られています。本書に出てくるフリーミアム戦略など、今後のインターネットというチャネルを活用したビジネスを考えていくうえで、頭の中や現実を整理するツールとして非常に有益だと私は思います。具体的な数値であるフリーからプレミアムへの誘導率は5%などを事例などから展開しており、すべての事例において適用されうるわけではないにしても、数値イメージを持つのにも参考になりました。 ネットの普及がビジネスをどう変えていくのかを考える良書だと思います☆
0投稿日: 2011.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ウェブの世界には、貨幣経済以外に、評判(トラフィック)経済と注目(リンク)経済がある ・無料で使ってくれる顧客をたくさん獲得すれば、その中の顧客が有料の商品を買ってくれる可能性が高くなる ・稀少性を発見し、そこを換金化する ・フリーをどのタイミングで、誰が、どのように使うかによって、その結果は大きく分かれるだろう
0投稿日: 2011.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ私のブログ ”Tatsuya's blog”へ http://pub.ne.jp/TakeTatsu/?entry_id=2722293
0投稿日: 2011.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ初めての電子書籍『FREE』読了。 電子書籍のメリットを感じられた。 メリット:持ち運び楽、いつでも読める。 デメリット:利便性 改良点:検索機能、メモ機能、タグ機能、共通して同じ機能がすべての電子書籍につけば絶対ほしくなるのに。 本の内容はフリーは戦略的に使えばかなり有効なツールってこと(笑) 0の威力を感じる。グローバル化、IT化した世界だからこそできる戦略。
0投稿日: 2011.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ興味深い内容。 読み始めるまでは、洋書のため日本に置き換えて成り立つものかなと思ってたものの、間違ってた。 ネットで繋がってれば国内も国外もないわな…
0投稿日: 2011.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「自由」と「無料」 そしてお金を払ってでも手に入れたいもの....etc 凄い!そして面白い! 発想の転換、目から鱗、そしてある意味 あらゆるビジネス の参考になると思う。 メモを取りながら読み込んでしまう。
0投稿日: 2011.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログクリスアンダーソン著「フリー」NHK出版 *新しいモデルを象徴する真の無料がある。その大部分は限界費用がゼロに近いオンライン上のデジタル経済に存在する。グーグルのサービス、ウィキペディアなど、金銭以外のインセンティブによって成り立つ経済である。 *生産において物質の占める割合がとても小さい場合には、生産量を増やすにあたって物質的問題はあまり障害にならない。半導体は物質経済の崩壊を示している。つまりアイデアは事実上、コストを要せず無制限に伝わっていくのだ。 *物質からではなく、アイデアからつくられるものが多くなれば、それだけ早くものは安くなっていく。これがデジタル世界のフリーにつながる贅沢さのルーツだが、強固の現象は簡潔にいムーアの法則と呼ばれている。 *ミードは、無料(コストを気にしない)経済効果が必然的にある論理上の規範にかかわってくることを理解していた。トランジスタが安くて気にならないものになるのなら、私達は実際に気にするべきではないし、そのコストについて考えるのをやめるべきだ。希少な商品として節約するのではなく、贅沢にあるものとして取り扱えばよい。いいかえれば、無駄にしはじめるべきなのだ。 *贅沢な情報は無料になりたがる。稀少な情報は効果になりたがる。 *知的財産に関する議論では、保護に賛成反対のどちらの意見もまったく筋が通っているのでそれはパラドックスだといえます。
0投稿日: 2011.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログGQやBRUTUSでプッシュされていた書籍。 ITがいかに世界の価値観をゆらしているのかが分かる。 これを読めばその「新しい常識」に少し馴染めるかも。 個人的な興味に本書の内容を当てはめて考えてみたのだけれど、 ダミアン・ハーストが作品をネットで無料販売したり、 村上隆が自社の画廊で学生でも買えるような安値でアートを売っているのは、 アートを物質ではなく情報・コンセプトとして扱っている=フリーミアムの範疇とみなしているからなのかも。 注:アメリカのこういったタイプのビジネス書に概して述べられること。 ・文章がシンプルで読みやすい ・噛み砕いた具体例をまじえるので理解しやすい ・しかし、その具体例が無駄に多い ・そのため、長い ・よって、物質的に厚いので携帯しづらい ライアンエアの航空ビジネス再定義に関心 格安航空券の内訳は、 チケット価格+二個目以降の預かり荷物の料金+水ボトル+優先搭乗権+クレジットカード取扱手数料+高額チケットからの内部相互補助+一時間の飛行における乗客一人当たりの広告収入 だそう。なるほどー フリーランチ/贈与経済
0投稿日: 2011.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログコモディティ化した情報(誰もが同じものを得られる)は無料になりたがる。 カスタマイズされた情報(その人にだけ与えられる特別なもの)は高価になりたがる いま、これからのビジネスの仕組みを理解するうえで読んでおくべき内容、ただ内容は冗長なので400ページまででいいかな、、 20 Feb, 2010
0投稿日: 2011.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ多少なりともインターネット、ソーシャルネットワークに興味を持っている人なら、早めに「インストール」しておいた方がいい考え方、アイデアが詰まっている。
0投稿日: 2011.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の意義は2つ。一つ目はフリーミアム(基本的なサービスを無料で提供し、さらに高度な機能や特別な機能について料金を課金する仕組みのビジネスモデル、Wikipediaより抜粋)を体系的に定義したこと。二つ目はFreeの潮流が世の中の主流になりつつあること(少なくともそのほう芽は十二分に感じられること)を書き記したこと。 一つ目は古くからの事例を元にFreeというマーケティング手法が結して奇抜や犯罪的ではないことを示している。更に幾つかのFreeビジネスモデルを提示することで、今後取るべき手法の指針としても非常に有効な本となっている。 二つ目はGoogleやYouTube、果てはMicrosoftまで例示しながら、今後のビジネスにおいてFreeという概念/手法の重要性を示している。時としてそれはベターからマストになるだろう。また音楽/出版業界で言われているような著作権侵害によるマーケットの衰退が杞憂(期節業者の保身だろう)ということを示している。特に黎明期のラジオの話は今のFreeに対する反感と同じで、今後どちらになっていくかは自明に感じられる。 ロングテールの時にもそうだったが、著者が挙げる例が他の企業にも適用可能かどうかは疑問が残るが、未来を的確に読んでいる資料としては最適だろう。
0投稿日: 2011.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ2010.12.20-2011.01.04 iPad APP(無料版)にて。 SHARE(20.12.15発売)のイントロダクション、4章、5章が後半に載っている。
0投稿日: 2011.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「無料」からお金を生み出すとはどういう仕組みなのか、4つのタイプに分けて説明をしている。主に無料のモノを提供する側の視点から書かれている。巻末には「無料のルール――潤沢に根ざした思考法の10の原則」も掲載されていてフリービジネスを展開する上での参考になりそうだ。ただひとつ忘れてはならないのは、フリーだからと言って必ずしも成功するわけでもなく、フリーだから失敗したということにもならない点だ。金儲けとして「フリー」を利用しようとする姿勢が間違っているように思う。主にB2Cについて書かれているが、B2Bの世界でのフリーの例はないものだろうか。
0投稿日: 2011.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ事例が多く非常に分かりやすい。ただし長すぎる。いったりきたり。 さっきも同じようなこと言ってなかったっけとなる。 あと、成功した理由はわかるけど、じゃあこれをどう適用するかってのは難しいと思う。同じやり方だと先行者には勝てないし。 無料になりたがるって言い方と、著作権侵害を擁護しているような物言いは嫌。
0投稿日: 2011.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料キャンペーンの時にGetした電子書籍なのでホントに"フリー"。キャンペーンの無料配布にも、この本の"フリー"の考え方が取り入れられている。ビジネスを考えている人にはおススメかも。
0投稿日: 2011.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは刺激的な本だ。 ブリタニカ→エンカルタ→ウィキペディアの例で「10億ドル産業を100万ドル産業に変えてしまう。だが、富が消滅するわけではなく、計測しにくい形で再分配される。」と言う。確かにそうだ。 米国に無料の広告「craigslist」があることも知った。 カナダでは5歳の子供でも知ってるそうだ(Webの「カナダ生活案内」による) 取り上げられている例がとても分かりやすい。 これからの起業家は必見だ。 さて、自分はどうするのか、だ。
0投稿日: 2010.12.30
