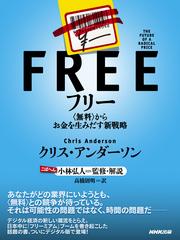
総合評価
(528件)| 140 | ||
| 210 | ||
| 99 | ||
| 9 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ある日、旦那に「ポートフォリオサイトはtumblrでいいんじゃない?無料だし、クオリティの高いテンプレートもたくさんあるし。」と持ちかけたことがあった。すかさずあった返答は「無料?なんで無料なの?」。その後も「どこがやっているのか」「どこで収益をあげているのか」といった純粋な疑問をいくつかぶつけられたが、自分はそんなこと考えるまでもなく使おうとしていた。 ■ フリーが当たり前すぎる20代 プロローグにもあるように、フリー(無料)については、年代が上にいくにつれて懐疑的になり、若い人ほど疑うこともなくホイホイ使うものだと思う。しかし、続けて「無料の周りに世界規模の経済がつくれるというアイデアは、彼ら(20代のグーグル世代)にとっては自明すぎる事実であって、わざわざ書くまでもないことなのだ。」とあるが、これはそうでもないと思う。少なくとも自分はそうだった。無料であることが当たり前すぎて、無意識に使うあまり、そこでどんな経済効果が生まれているのかについては意外と超・鈍感だったりする。LINEやFacebook、あるいはtwitter、google、youtube...これらを使っている20代で、自分が「経済効果をもたらしている」なんて思いながら使っている人なんて稀なんじゃないだろうか。 そういう点でも、フリーがどんな力を持っているのか、そこでどれだけのお金が動いているのかを知る、とても面白い本だった。 ■ 他人の手によってフリー(無料で自由)になっていく世の中で youtubeで人気のアーティストのMVを、公式チャンネルから綺麗な画質で楽しめることも当たり前になってきた。情報がすぐさま、他人の手によってフリー(無料で自由)になっていく世の中で、クリエイター自らが作品をフリーにする。ちょっと前までは考えられなかったことだけど、気持ちのよい太刀打ちの仕方だなと思う。 本書の中でも、成功したフリーの事例がいくつか挙げられている。古くはレシピを無料にしゼラチンを売った「ジェロ」の話や、カミソリの替え刃で儲けた「キング・ジレット」の話。その他、現代での新しい「フリー成功事例」と法則がまとめてある。 シェアやいいね!が当たり前の今、ものを作る人達の側が、生み出した作品をどう扱うかが問われている。これから先、何か新しいことを始めようと思ったとき、たくさんの人に見てもらいたい作品ができたとき、出方を考えるためにこの本を開いてもいいかもしれない。 ■ ブラよろの事例もあるわけですし、 ちなみに、経済の本なんて普段滅多に読まない私ですが、おもしろい実例がたくさん挙げられているので、苦なく読めた。フリーに対しては、日本ではこんなすごい事例もあるし、やはり人ごとじゃない気持ちがあったのだとも思う。 「単行本80万部のヒットと同等」 ブラよろ2次利用フリー化効果で月650万円の利益、佐藤さん明かす | ITmedia ニュース http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1304/22/news128.html 「ブラよろ」二次利用フリー化から半年でいくら儲かったか? | 少年 佐藤秀峰 http://ch.nicovideo.jp/shuhosato/blomaga/ar204961 知り合いのライターさんに勧められて読んだけど、すごく実になった一冊。鉄板通り、続けて「MEDIA MAKERS」を読みます。
3投稿日: 2013.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読み終わって改めて考えるとシンプルなことをただ述べているだけなのだが、情報を商品として考える新しい時代がくるまでの流れや背景がよくわかる本。 ブグログはじめ、無料で使えるサービスを支えるためには、たった1割のユーザーがお金を払うだけで十分ということに一番おどろいた。そんな少ない割合だとは。それだけ、かかるコストに対して抱えることができるユーザーの数が、従来の商品と比較して桁違いな世界が展開されているのだと実感した。
0投稿日: 2013.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今更ながら読んどいた。 2009年の本だから今読むと目新しさはないが、無料経済の仕組みがよくわかる一冊。 身近でわかりやすいものだと、GoogleやFacebook、Lineのような無料サービスが成り立つ仕組み。 うちの父親もそうだけど、世代によっては、無料サービスがどうしても信じられず、後で何か請求されるんじゃないか?とか思って敬遠してしまうらしい。 逆に若い世代だと、無料が当たり前で、有料とかあり得ないと考えているらしい。 そんな方々はこの本を読んでみると、なるほど(・∀・) となります。
1投稿日: 2013.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ・フリーを謳い文句→他サービスで儲ける ・5%の有料会員から儲ける(無料会員へのサービスのコストほぼゼロ) ・フリー→注目、評判
0投稿日: 2013.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ成功事例の中にはすでに頓挫しているものも見受ける。 死屍累々のFREE戦略、果たしてみんながハッピーになれるのだろうか。 ごく一部の富豪を生み出すだけならもうお腹いっぱいだ。 そのFREEはダンピング、寡占、独占を経て、やりたい放題の本性を現してこないのか。
1投稿日: 2013.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ潤沢な情報は無料になりたがる。希少な情報は高価になりたがる。 (低い限界費用で複製、伝達できる情報は無料になりたがり、限界費用の高い情報は高価になりたがる。)
0投稿日: 2013.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログとても参考になった。 少なくとも、よくわからなかったFREEの世界を 地図なしで航海しなくても良くなったことに感謝している。 私たちは今、まさにiTunesでオリジナルのアルバムを販売しているし、 オフラインでやってきた仕事の一部をオンラインへも移行しようとしている。 そのようなとき、まさにこの本はFREEの取り扱い説明書になってくれている。 初めてインターネットで物を買ったとき、 今までとは違う習慣が、私たちの生活に加わる予感がたしかにしたように、 ネットで物を売るという側になったときにも、 フリーの存在は私たちのビジネスにおいて、ますますたしかな習慣として あたりまえの存在になっていくことだろう。 そして、FREEはもうすでにオンラインの世界にまで広がっている。 これまでもFREEの世界はそこかしこにあったが、 まるで氷山の一角のように見えていただけで(まるで見えていなかったともいえる) 一角からは想像もつかないほどの巨大なFREEが 情報社会(海)の下に顕在化してきたということだ。 著書の後のほうに、著名人の発言したFREEについての苦言に 著者が一つ一つ答えている(反論している)部分があるが、ここを読むだけでも いくら顕在化してきたとはいえ、それぞれの分野でそれぞれの立ち場にある人間が FREEについて口を開けば、まるで違う捉え方をそれぞれがするものだ、 というのがよくわかる。 それくらい、FREEは図りにくいものだし、量りにくいものだからだ。 だからこそ、私たちは自分の豊かな創造力を使って、 心から楽しみながらFREEを活用しなければならない。 まさにFREEは無料という意だけでなく、自由という意もあるのだ。 先ほども、この本はよくわからないものの存在を知らしてくれる 地図にはなるという話をさせてもらった。 あとは、自分がどういうルートを通って新大陸を目指すか、 それはクルー達と頭と頭、顔と顔を突き合わせて、思う存分、 創造力を発揮すればいい。 だれも正しい航路なんか知らない。 私の好きな漫画、ワンピースじゃないが、まさにこの世は大海賊時代。 自分たちの本当にやりたいことをやるために、FREEという大海原へ 堂々と船を走らせて行けばいいだけだ。 ぐるぐるとコンパスを失った船を運航していたように感じていた私には、 とりあえず、自信を持って、次の島へ迎える ログポーズを手に入れたような、そんな気さえする。
1投稿日: 2013.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2013/5/5読了。ブックオフで安く買ってから2年以上積ん読してあった本。ハードカバーで350ページという見た目に何となく読む気が起きなかったんですが、GW中ということもあり読んでみた。オンラインゲームやGoogle、SNSなど特にネットサービスは無料が当たり前の時代。なぜ無料なのか?どういう仕組みなのか?疑問に思いつつユーザーとして利用していたが、その仕組みや裏側が、様々な事例とともに行動経済学や心理学も使いながら解説している良本。印象に残った言葉は、「思い出に残る経験こそが最も希少価値がある」「フリーと競争するには、潤沢なものを素通りしてその近くで希少なものを見つけること」。読み終わって、私もIT企業に勤める1人として、フリーとどのように向き合っていくのか、色々と考えさせられた一冊だった。
0投稿日: 2013.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「情報はフリーになりたがる」という印象的な言葉が出てきます。 きっと情報だけでなくあらゆるものがフリーに近づいていく。 世の中全体がフリーを求めている。 それはフリーに価値がある事を意味しているのだろう。 価値を創造する事がビジネスの常識であったのに フリーに価値を見出す事に多くの企業や人が躍起になっている。 フリーの価値とは何なのだろうか。 そもそもフリーに価値があるのだろうか? 答えはNoだろう。 フリー自体に価値は存在しない。 フリーを価値あるものに変えるのが21世紀のビジネスなんだろう。 それを実行し成長し続けているのがGoogleだ。 基本的に一般ユーザーはGoogleにお金を払う事はない。 ネット検索しようがGmailを使おうがストリートビューを使おうが。 Googleは優れた機能を絶え間なく生み出しているが そこから収益は得ようとしていない。 IT企業らしく広告収入がほとんどらしい。 でもGoogleの成長は鈍化するどころか加速しているように見える。 フリーを最大限利用してユーザーを増やしている。 それが広告のアクセスを増やし利益を生んでいく。 フリーをもっとも賢く戦略的にしかもシンプルに利用しているようだ。 ビジネスの世界だけではなく日常にもフリーは溢れている。 それにより密接にフリーと付き合っていかなければならないのだろう。 この先、僕たちの生活にフリーがどんな変化をもたらしてくれるのか楽しみだね。
1投稿日: 2013.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から気になっていた本だったのですが、ようやく読みました。 これは予想に違わぬ、というか、予想以上のおもしろさでした。 インターネットの世の中になって、ものすごく質の高いプロダクトが無料で提供されることが非常に多くなり、一体なぜ、そしてどうやってそれを可能にしているのか、前々から気になってはいたのですが、この本で分析してくれている各種ビジネスモデルや、「注目と評判」という非貨幣評価モデルというのは、自分にとって非常に納得度の高いものでした。 しかし、この本が著されて、すでに4年が経過しているのに、いまだに日本の現実の企業活動には、ものモデルを十分うまく利用できているところがあるように感じられないのは、かえって不思議な気がするくらいです。やはり意識や習慣というのは、そう簡単には変わらない慣性力というのがあるのでしょう。 でも、デジタル化によってこれまで希少だった様々なものがますますコモディティ化し、別の希少性を次々に探して行かなければ経済競争に勝ち抜けなくなるというのは、僕には間違いなく真理のように思えました。これからの世の中の変化に対応できるようにするため、この本の情報は、さらにしっかりと自分の中に落とし込んでおきたいところです。
0投稿日: 2013.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログMAKERSが面白そうだったので借りに行ったらこちらが置いてあったので先に読了。「ビットの限界費用が限りなくゼロに近い→フリーの流出は避けられない→ビジネスモデルを変えろ」というだけの話ですが、事例や論旨が上手で面白いですな。 しかし、音楽データの複製は避けられないからライブや物販で儲けるモデルにシフトしないといけないとかそれで儲けてる人がいると言われても「グレーン・グルードはどうするねん?」とはやはり言いたい。グルードでなくても、スタジオミュージシャンとか録音技師などミクロで悪影響を受け、技術が廃れていって取り戻せない物事はやはりある訳でして。 マクロの話としては総論賛成、一部各論反対ということで。 にしても、こういう本は発売後時間たって評価確立してから読まないと当りハズレが大きいですな。
0投稿日: 2013.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう経済関係の本にしては、とても読みやすく分かり易かった。 バイブル的な意味合いで1冊持っておいてもいいかも。 良い本だと思う。
0投稿日: 2013.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で。仕事に活かせるかな、と思い読んでみました。色々勉強になりましたし、面白かったです。 ビット世界での「無料」と言う概念に疑惑を感じる30台以上とそれを当たり前と捉える20代とか、コモディティは限りなく値下がりし、希少性やニッチなものに値がつくなど非常にすとん、と納得できました。が、これを実際に活かすのは大変だろうなあ。結局タダだから気安く利用しているモノを有料化した際に財布の紐を緩ませるにはなかなかの決断力が必要だということだなあと思いました。 ネットの世界にはお金だけでは無い一種独特のステイタスと価値観があり、アマチュアとプロフェッショナルが同列に並び、玉石混交の情報が存在する。面白いです。ただ、ネットでの情報は明らかに偏るなあと思ったことはあります。楽な分だけ流されやすいと言いましょうか。簡単にネットで調べてその情報が正確かどうかを確認することなく何となくわかった気になってそのうち忘れてしまう。何が正しい情報なのか。それを吟味するのはこれからの世代なのかもしれません。 そのうちネット検索代行サービスとか出てきそうだなあ。雑多な情報の中からあなたの求める情報を適切に正確に迅速に提供しますとか。もうあるかもしれませんが。
0投稿日: 2013.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ潤沢さと稀少さの考察に基づく、パラダイムシフトを促す、の書。 フリーがなぜ必然なのか、そのなかでどう考えるべきかの指針を示してくれる。 個人では辿りつかないその洞察は、知っておくべきことだろう。
1投稿日: 2013.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2009年に出版されてからかなり時間がたつが、内容と現実に齟齬はない。 FREE(無料・自由)の可能性については、本当にそこまですごいのか疑問は残る。 しかし、フリーミアムというモデルが素晴らしいことは疑問の余地はない。 昨年、大ヒット漫画「ブラックジャックによろしく」が無料で公開ダウンロード・二次利用自由ということになった。これがどれくらいの利益をもたらしたのか。 作者のブログ(http://bit.ly/ZpbDhE)によると、他の作品の売上が上がり、新しい仕事もたくさん舞い込んだそうだ。 おそらく十分に一番出汁をとった作品を利用することにより、新しい読者を獲得し利益に結びつける。 ひとまず成功ではあるのだが、どうも未だ実験の域を出ていないような気もする。 モデルとして有効であるならば、追随する者も多く出そうなものだ。 このあたりがひっかかるところ。 本書はハードカバーで352ページ。結構なサイズだけど、紙自体が軽いのか持ち歩くのも全く苦じゃない。 実はこの本を図書館で見かけて、読んでいなかったことを思いだし、読みだすと思い切り引きこまれた。 早速、Kindle版を購入。かつてはデータ版は無料ダウンロードできた時期もあったようだが、現在は有料。でも、紙版の半額である。Kindleの商品の値頃感としては、やはりこれくらいと思うのだが。 整理するためにいろいろと書いたほうが良い「テキスト」だと思うが、これくらいで止めておく。 Kindleで持ち歩いて10回くらいは読んでみよう。それだけの値打ちあり。
0投稿日: 2013.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日々日常で思っていた疑問、 「どうしてこんなにすごく便利で使えるものが「無料」なの?しかもネット上ではそんなサービスがたくさんあって、みんなが普通に使えるのこの社会って実は凄いことなんじゃない?」 こんな疑問をこの本では、たくさんの具体例をもって書かれているます。 最近僕のまわりで「無料」のものが増えたよな、と思っていました。 例えば、基本的にネットの中の情報は無料ですね。 そして、ネットに関わるサービス全体がほぼ無料。 僕の例で言えば、僕はメールの送受信では「Gmail」というアプリを使っています。 このアプリ、ほんと便利で使いやすい。 こんな便利なアプリを開発しようとしたら、どれだけの人と労力がかかったんだろうと思うと、このアプリが「無料」というのが信じられない。。。 だけど、もう今ではこれぐらいのアプリやサービスって、「無料」があたりまえなんですよね。 僕の職業は「設計」なのですが、Gmailを開発するのと同じだけの時間と労力を設計の仕事に置き換えたら、絶対に無料ではできないよな。。。 この本では、世の中に潤沢にあるものはどんどん「フリー」、いわゆる無料になっていく。 それはもう世の中の本流の流れで、特にデジタルの世界ではその流れが逆らいきれないストリームのように、周りの環境を飲み込んでいっている。 そのことが、ネットの世界で活躍する世界的なIT企業の名前と共に、実感として理解できるような本の作りになっています。 「フリー」という考え方。 これを僕の仕事でどう活かすかを考えだすと、どんどんこの本を読むのが難しくなっていくけど、こういう世界の先には、誰もが自由に「ビット」という情報を介して、自分の生活自体を「フリー」にしていって、 何者にも縛られない、真の「自由(フリー)」を得ることができたら、自分の嫌いなことをしてまでお金を稼いだり、仕事をしたりしなくてもいい世の中になっていくのかな? そんな楽観的な気分にもさせてくれるこの本は、今、現在を切り取る歴史書としてもうまく表現されていますね たいへん刺激的で面白かったです
1投稿日: 2013.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ積んでた「MAKERS」読もうと思ったら、最初の50ページ読んでほったらかしてたこの人が寂しそうだったので、おとなしくこっちから片付けマス。ごめんフリー。 タダで成り立つビジネスの仕組みを、貨幣経済だけやなくて、ぱっと見分かりづらい行動経済学の観点から説明。Webコンテンツ系の会社の時価総額が適当な理由も、何となく腑に落ちました。貨幣に換算した価値って、誰も正確なところは分かってへんのやろね、たぶん w インパクトあったんは、Webに飲み込まれた既存業界の成れの果てやなあ。例に上がってたのはアメリカの百科辞典市場。 ・1990年代までは、訪問販売のセールス部隊が中心(市場規模12億ドル) ・1990年半ばから、CD-ROM(MSのエンカルタ)が中心(規模は6億ドルに縮小) ・で、今はWikipediaとGoogle先生。 コンテンツの複製コストはほとんどタダやから、市場がほとんど消し飛んでしまうんやね。。。使てる人間は便利になって幸せやけど、既存業界にとってはまさに破壊的イノベーション(-_-;;; わたくし組み込みソフト屋さんの端くれですが、ローコスト側からはオフショアが順調に勢力拡大中。別方面からは「MAKERS」で思う存分語られるに違いない、オープンソース・ハードウェアの流れ、そしてプログラマいらずのモデル駆動開発。。。(デンソーでは既に実践されてるみたいやし) 10年先どころか5年先も読めへん世の中やけど、、、備えよう。
1投稿日: 2013.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フリー」という(特に貨幣的フリーの)テーマで綴られる洞察はとても面白く、Webとそのコンテキストで生まれた新しい産業や社会の形(経済圏)に対するひとつの視点を提案している良書だと思った。 特に非貨幣経済と貨幣経済の変換における考え方と、そのアプローチの分析はとても面白く、これまで分散的に提案していたいくつかのビジネスモデルを評判や注目といった経済活動という形で再認識することができた。 また後半の章であったSFの「ルールを1つ変えたときに人間がどのような行動をとるか?」という見方はとても印象的で、個人的に好きなサーバーパンク系の作品なども、そういった視点で面白いと感じている部分があるのかと、別の客観的視点での考えをはせるきっかけになった。
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料からお金を生み出すビジネスモデルについて、多くの例を挙げながら説明している。これには二通りあり、「潤沢さを価値にして伸びる企業」と「新たな希少を価値として伸びる企業」がある。
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログタダほど安いものはない? だから、タダにしてしまえば、それ以上安くすることはない? この本、「\-」と印刷してある。さすがに「\0」ではない。1800円もする。 無料のルール ①デジタルのものは遅かれ早かれ無料になる。 ②アトム=モノも無料になりたがるが、そのスピードは遅い。 ③フリー=無料はとまらない。 ④フリー=無料からもお金儲けはできる。 ⑤フリー=無料は市場を再評価する。 ⑥ゼロにする。 ⑦遅かれ早かれ無料と競い合うことになる。 ⑧ムダと思うものも価値がある。 ⑨フリーは別のものの価値を高める。 ⑩希少なものではなく、潤沢なものを管理する。 もう、CDの会社は儲からない。 アーティストにとっては録音された曲は無料でもいい。 ライブやグッズで儲け、その宣伝に無料の音源を使えばよい。
0投稿日: 2013.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
わかりやすい議題を取り上げているせいもあり、 論旨がつかみやすく、あっという間に読めた。 内部相互補助:一枚買ったら、一枚ただ。無料の恩恵を受けた人が払う 三者間市場:利用者はフリーの恩恵を受けるが、そこにある広告のものを買った人が払う。広告収入 フリーミアム:一部の有料会員がお金を払う。オンラインゲーム。時間のない人がお金で時間を買う。 非貨幣経済:無料で提供し、評判を買う。 無料で提供することで、知ってもらう。→ コンサートチケット、グッヅ販売などで収入を得る。 ビットの世界は、コストが限りなくゼロになるからこそできる。 ロングテールの世界では、商品棚は無限にある。 選択する必要はない。すべて載せることができる。 お金を払うというのは、選択を必要とするので、大きな障壁である。 たとえ1セントであれ。 無料情報の周りにコミュニティーを作り、ここのトピックスに助言する 人々が求めているものを設計し、基本機能を持つものは無料に 時間、技術、リスクに対する許容度よりもお金を払う人には、有料版を売る 海賊版はフリーの強制である。デジタルの世界では、もはやフリーにならざるを得ない。だからフリーで戦うモデルになる必要がある。 ビットの世界は、18ヶ月で半額にコストが下がる。 規模の経済が強く働くため、一人がちになる。 先に無料にしたものが市場をとり、規模を獲得できる。 リナックス:無料にすることで、会社などたくさん必要なところでは大きな差になる。 しかし、実際にはメンテナンスなどでお金がかかる。そこでお金が生まれる →メンテナンスが進む、機能が上がる。 オンラインゲームの世界 バーチャル製品の販売、会費、広告、不動産、商品 タンポポの種。 限界費用がゼロに近い場合は、種をまきまくる戦略の方が、勝つ可能性が高い。 海賊版のパラドクス 偽者が出回れば、商品は、コモディティー化して、 ブランドの価値がなくなり、新しいものを買う。 潤沢さから、新しい希少さが生まれる テキスト検索は、検索している人が何を求めているかわかる→テキスト連動広告を打てる。 一方、動画は、何を求めているかわからないので、広告収入かできない。 Huluは、テレビ番組を無料で提供している。 しかし、それは、何を放送しているかわかる→見たい人が何を診ればいいかわかるから、広告を特定できる。 1.デジタルのものは、遅かれ速かれ無料になる。 競争市場では、限界費用まで落ちる。 2.アトムも無料になりたがるが、力強くはない。 しかし、無料にすることでひきつけ、別の収益源を作り出すことはできる。 3.フリーは止まらない 法律や使用制限によってフリーを食い止めようとしても、 不正コピーなどが出回る、それをガードすることは正規の客への不評に つながる。フリーを取り戻す。 4.フリーからも稼げる 時間を節約するため、リスクを避けるため、 自分の好きなもの、ステイタスにに、お金を払う人がいる。 5.市場を再評価 何を売るビジネスか。席を売るのか、旅行ビジネスをするのか 6.ゼロにする 注目をお金に変える方法は必ず存在する。 7.遅かれ早かれフリーと戦う。 フリーになるか、価格差を埋められるだけ差別化するか 8.無駄を受け入れる 限界費用がゼロになっているものに気を払わない 9.フリーは別のものの価値を高める 潤沢さは、希少さを生み出す。 10.希少なものではなく、潤沢なものを管理する 資源が希少な世界では、資源は効果になるので、慎重に使う必要がある →従来型のマネジメント 資源が安い世界では、リスクは小さくなるので、沈む危険を考えなくていい。 むしろ速く失敗しろ!! フリーミアム ・時間制限:実行しやすい。そもそも使われない可能性がある ・機能制限:二つの製品が必要。バランスが難しい・ ・人数制限 ・顧客タイプによる制限 5%が負担すれば、回るようにコスト構造を目指す。 スポーツクラブは、「お金を払って、来ない人が多いほど儲かる」 くれば繰るほど、お金を返すようにしたら、一回の単価は飛躍的に下がる。。
0投稿日: 2013.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し前にはやった本。でも読み応え十分。本来の目的はボランティアは対価の払われないFREEの経済という分野に入るかなと思い、卒論のヒント探しに読んでみた。 ボランティアを経済学的に考えるうえで、マズローの欲求に関しては何となくヒントがあるのでは?と思って考えていたけれど、かなりすっきりした形で整理されていてよかった。 あとは、あのソーシャルゲームの会社がなんで5%とかの有料利用者で成立するかもいまいちわからなかったけどすっきり!!クリス氏あた良すぎ。すごい!!! そして自分でもフリーの経済、実験したくなってきました!!!
1投稿日: 2013.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログフリー。僕にとって特に身近なのはyoutubeかな。 今までアニメとか映画とかDVD借りて見ていたものが無料でアップされている。すると、レンタルビデオ屋さんも客が減るし、テレビの視聴率が下がることでテレビの広告費も減りテレビ屋さんも収入が減る。おいおい、無料なんて誰にメリットがあるんだって思った。 でも結局タダのものなんてなくて、テレビを広告に使っていた企業が、youtubeなどの広告にシフトしただけの話。その広告費でフリーになっている。しかも動画の種類がわかれば視聴者をある程度特定してCMを流すことができるし、リンクを押せばすぐに買ってもらうこともできるから企業にとっては投資する価値があると考えられる。 マーケティングの手法が変わりつつある時期に自分はいるんだなって思う。これをどう利用するか。
0投稿日: 2013.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ潤沢と希少が相対する構図の中で、潤沢がフリーへと落ちていくことを万有引力の影響になぞらえて説いている。いわゆるビットに属するデジタルコンテンツがCPUやストレージ、ネットワークなどの際限のないコストダウンにより、その限界費用が限りなく0へ近づく原動力となっている。ビジネスは新たな希少を拠り所にしなければいけない(もしくは非貨幣価値から貨幣価値の錬金術を見つけなればいけないのだろう)。そういう意味で存在自体が希少であるところがアップルの強みなのかなとこの冬の読書シリーズを振り返り思った。
0投稿日: 2013.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「時間とお金の方程式」が特に良かった。大抵、若いころはお金が自由に使えずその代わり時間をたくさん持っており、年をとるに連れてだんだんとそれが逆転していく。直感だが、その需供曲線に似た線が重なる所に、大きな可能性があると思う。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログKindle PHで初読了。デジタル・ビジネスの世界は2009年の本でも「今さら」感が出ちゃうのはしょうがないね。個人的には、FREEは一つのワザで、効果の出るTPOを選ぶと思う。
0投稿日: 2013.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終えた。電子書籍は視野に飛び込んで来て「読まなきゃ」って気持ちにさせる物がないのでついつい放ったらかしにしがちになっちゃうね。とても面白い本だったんだけどね…新しい価値観や思考方法を丁寧に見せてくれる本です。非常に面白くて紙媒体だとサラッと読み終えてたはず…
1投稿日: 2012.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ一度読んだけど、そもう一度読んでみる。そのとき時で、人間は視点が異なるから、こういう本は何度読んでもおもろい(^-^)
0投稿日: 2012.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料についていろいろな考えがあること、フリーにも種類があり時代の変遷があることを知りました。 既得権益にしがみついてはだめ 常に新しいほうへ という印象 タンポポの種組織を考えます
0投稿日: 2012.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログその筋ではベストセラーになった一冊。 まず、2012年のタイミングで読んでみると目新しさが減耗してしまう点はやむをえないものの、単なる表面的な事象だけでなく過去のネット以外のビジネスモデルと照合しながら記述されているという点において優秀であると言えます。 若干ボリューム過多な気は否めません。たぶん日本だったら新書ですむレベルでしょうね。
0投稿日: 2012.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーの文化に対して、アトムとビットで分けて考えて、 ビットは限りなく費用がフリーである、という発想。 漠然と認識していたアトムメインの世界とビットメインの世界との違いを記載している。 ビット世界でいかに認知されアトム世界に人々を移行させて金を得るか、であったりという部分にいろいろ考えさせられたように思う
0投稿日: 2012.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容は面白くとても勉強になる。 しかし、個人的には読みづらく途中飽きてしまった。 やはり、翻訳本は若干苦手だ。。。 何回も同じ内容が出てくる気がするし無駄に分厚いし。。。
0投稿日: 2012.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ言っていることは、ビジネス化するよりも評判を得る方が難しいんだから、まずフリーで評判を得た結果、ビジネスにしようということ。 自分もビジネスをまずフリーにしたんだけど、それは間違ってなかったし、読む中でビジネスモデルが浮かんだので、それだけでも良かった。 また、「潤沢な(低い限界費用で複製、伝達できる)情報は無料になりたがる。希少な(限界費用の高い)情報は高価になりたがる」はとても参考になった。これからの指針にしていきたい。 ちなみに、フリーに対する批判に対して返答しているが正直あまり説得力はない。フリーは、まず評判を得るものであるから、本当に良いものを提供することが大切なる訳です。 フリーに対する批判をしている人は、この良いものをまず提供することに対して恐怖感があるんだろう、たぶん。でも、ビジネスって、そういうものだと思うんだけどね。
0投稿日: 2012.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年にクリス・アンダーソンがリリースした「フリー」は今読んでも十分役に立つ、再読してみるとかなり新鮮だった。あれ?こんな文章あったっけ?僕の読書は軽薄だった(笑)、あと5~6回読まなければ。 以下は308頁からの抜粋 フリーと競争するには、潤沢なものを素通りしてその近くで希少なものを見つけることだ。ソフトウエアが無料なら、サポートを売る。電話が無料なら、遠くの労働力と能力をその無料電話を使って届ける(インドへのアウトソーシングがこのモデルだ)。もしも自分のスキルがソフトウエアにとって代わられたことでコモディティ化したならば(旅行代理店、株式仲買人、不動産屋がその例だ)、まだコモディティ化されていない上流にさかのぼって行って、人間が直接かかわる必要のある、より複雑な問題解決に挑めばいい。そうすればフリーと競争できるようになるだけはない。そうした個別の解決策を必要とする人は、より高い料金を喜んで支払うはずだ。 (「フリー」より) 「ワークシフト」を彷彿とさせるくだりである、まさにフリーやテクノロジーがある日突然、そうだいきなり、我々の技術や知識を陳腐化させる。そして、グロバリゼーションの波は怒涛のように襲い掛かり、この津波から逃れることはできない。 であるならばフリーやテクノロジー、グロバリゼーションを逆手に取るのが正解だ。組織に依存する羊を卒業して、個の力を見つめ直す。そして、鍛えるしかない。そうすることで新しい世界へのパスポートを手に入れることができる。世の中はこれから面白くなる、恐れることはない淡々と準備をするのだ。 準備ができていない僕の言葉には信憑性や重みがないのだが(笑)、クリス・アンダーソンやリンダ先生の論文に疑う余地は無さそうです。21世紀の産業革命に備え「MAKERS」もまた必読の書である。
0投稿日: 2012.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログネットにおける現在うまくいっているフリー戦略は大きく分けて3つある。 ・一つ目は直接的内部相互補助である。 簡単にいって無料のコンテンツを餌にして有料のものも買わせるという戦略だ。 「この世にフリーランチはない」という言葉の本質を表している。 ・二つ目は三者間市場である。 これは全てのメディアの基本形である。主に広告がそうだ。 ・三つ目はフリーミアムである。 この言葉は初めて聞く言葉だ。 この意味は少数の有料ユーザーが他多数の無料ユーザーを支えているという構図だ。 この有料ユーザーが10%を切るとこのビジネスモデルは厳しくなるそうだ。 これはニコニコ動画や天鳳などのオンラインゲームがまさに当てはまる。 無料のルール ・競争市場では、価格は遅かれ早かれ限界費用(ゼロ)まで落ちる。 ・フリーは止まらない ・フリーからもお金儲けは出来る。”
0投稿日: 2012.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログロングテールという言葉を流行らせた著者の「フリー」の考察。 ハードカバーで300ページ近くある本だが、例え話等が多くわかりやすかった。特に、2部についてはPCやネットについての話なので、その方面に阿カル人には簡単にわかると思う。 1部は、カミソリのジレットの話からフリーの商売がどのような歴史をたどってきたかを説明し、心理面からも説明している。2部では、デジタル時代として主にネット環境などのITのフリー戦略について説明している。3部では、非貨幣経済や巻末でフリーについてのまとめをしている。 デフレ時代に、フリー戦略が当たり前になっている現在、いろいろな戦略を例え話をいれながら最後にまとめているのはよいと思った。
0投稿日: 2012.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログI learnt a new business model, free、from this book. I could understand how to earn money for SNS ,for example facebook and twitter. I think the business model "free" will expand all over the world from now. You should read this book to keep up with sudden changes in the world.
0投稿日: 2012.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ副題は「<無料>からお金を生みだす新戦略」。これは「freemiumフリーミアム」と呼ばれていますが、「大辞林」には以下のように解説されています。 〔free(無料)とpremium(割増金)の合成語〕 基本サービスを無料で、付加的なサービスを有料で提供するビジネス・モデル。主にネット上のサービスについて言う。 著者のクリス・アンダーソンは、「ロングテール理論」で有名になった「ワイアード誌」の編集長。 どんな商品にもコストがかかっている以上、その受益者が負担すべきではないかと、僕は思います。しかし、無料化の流れは今後、経済の中で止まることはないでしょう。 消費者的には「無料」は歓迎なのですが、労働者的には「無料」というのは困ったものです。しかし、21世紀のビジネスは、この<無料>と対峙していかなければいけない。 かくいう僕も、無料で読めるブログの売り上げで得たアマゾンのポイントで、しかもマーケットプレイスで定価よりも安く、同書を購入。フリーミアムの恩恵を受けているわけです。 同書ではフリーミアムがいかに生まれたのか、という歴史の解説から始まり、デジタル世界のフリーでは、グーグルのビジネス、さらに、コピー天国の中国での報告、最後はフリー経済への疑念に応えるという構成。「どうして講演会をオンラインでタダで配信しても、高額なチケットが売れるのか」などのコラムは興味深いです。 この「フリー」がネット上で話題になっているのは知っていたのですが、最寄り駅近くにある書店でも、売り上げ第1位。無料について書いた「有料」の本が相当な金を稼いでいる…。面白いですね。まさにフリーミアムを実践しているような本です。
0投稿日: 2012.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強になったのは覚えているな。こっそり入っていくというのはわかるけど、なかなか難しいところでもあるんだとは、読んだあとさらに思ったな。 マイクロソフト対リナックス、グーグル対ヤフーの話は面白かった。
0投稿日: 2012.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料(フリー)は敵ではなく、使いこなせれば利益も出せる。 例えば音楽は無料配信にすればCDの売上は落ち込むけど、ファンが増えてコンサートチケットやグッズが売れると言ったふうに。 本書はそんな内容。
0投稿日: 2012.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログもう旬は過ぎてると思いますが、読んでみました。HD容量を食うソフト、掃除ロボット・ルンバの無限の時間・・・気にならないくらい潤沢なものを無駄に消費する時代が来ているのですね。
0投稿日: 2012.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログビットの世界でお金以外の新たな価値基準が生まれ、それを軸にお金が回る仕組みが形成されるようになることがわかる。 16章でフリーに対する有名人の見解を引用し、バッサバッサと切っていく様はお見事。 フリーは止まらない。
0投稿日: 2012.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログiphone版でやっと読了!こういう商法は昔からあるのだな。インターネットがさらにそれを加速させた、ということか。日本はこういう分野では遅れてる、と感じる。
0投稿日: 2012.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログit was pretty interesting to read. I was studying in college when i met this book. it tells you the logic why free could be free. i read one in Japanese too but i recommend reading in English. the example that they give in the book is better.
0投稿日: 2012.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ流通するすべての商品がコモディティ化すると、人に与えられた有限の時間が価値を生む。なので、時間の短縮にはお金を払う人がいるわけだ。これは、無料ゲームソフト会社が球団を買えた理由のひとるなのである。また、インターネットを贅沢に利用できる時代では自己のブランディング化をすすめることで、企業ではなく個人をより前面にだして売ることができるようになった。すべては贅沢に利用できるネット環境がなせる業なのである。 巻末付録に『無用のルール』と『フリーミアムの戦術』の要点を箇条書きに記載あり。このページだけでも読む価値がある。
0投稿日: 2012.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほど、web上に無料のサービスがいろいろあるけどweb上に限らず昔からあるビジネスモデルだったのね。web上であってもなくても、いかにフリーのあとに儲ける仕組みを作れるかが決め手だな。しかもこの本によると世の中みんなフリーに向かっていくらしい。競合より先に手を打てるかな?
0投稿日: 2012.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔にクライアントの方からいただいた一冊。曰く「これからの時代の考え方には必須のため見ないとやばい」とのこと。確かにフリーミアムの考え方を把握しておくことは重要。 以下レバレッジメモ フリー③フリーミアム 無料なもの―有料のプレミアム版に対する基本版 無料対象者―基本版のユーザー フリーミアムはベンチャーキャピタリストのフレッドウィルソンの造語でウェブにおけるビジネスモデルとしては一般的だ。それは多くの形態をとりうる。無料から高額のものまで様々なコンテンツをそろえるところもあるし、無料版にいくつかの機能を加えてプロ用の有料版をそろえるところもある。(無料のフリッカーと年間25ドルを払うフリッカープロがその例だ。)皆さんはそれなら香水売場から街角までいたるところで配っている無料サンプルがこれにあたるんじゃないかと思われるかもしない。確かにそうだが、フリーミアムはそこに重要なひねりを加えている。従来の無料サンプルは販売促進用にキャンディバーを配ったり新米の母親におむつを送ったりするものだ。そうした試供品は実費がかかるので生産者は少量しか配れなかった。少量で消費者を引き付けてより多くの需要を生もうとしたのだ。一報デジタル製品においては、無料と有料の割合は全く異なる。典型的なオンラインサイトには5パーセントの有料ユーザーが残りの無料ユーザーを支えているのだ。フリーミアムのモデルでは有料版を利用するユーザー1人に対sh知恵無料の基本版のユーザーガ19人もいる。それでもやっていける理由は19人の無料ユーザーにサービスを提供するコストが無視できるほどゼロに近いからだ。
0投稿日: 2012.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログGoogleやYoutubeなど無料のWebツールを使ったマーケティング方法についての本。初心者にもわかりやすく各項目が説明されています。 Webマーケティングの参考書として使いたい本です
0投稿日: 2012.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ従来は優秀なエンジニアを雇ってソフトウェアを開発していたが、いまはオープンソースという手法がある。IT革命によって形のない「情報」はどんどん無料になっている。 また、形があるものも無料になっている。例えばR25のような雑誌がそうだ。 この無料の経済がどうなっているのかを知りたくて読んだ。 マズローの5段階欲求説の一番上は、「自己実現の欲求」だ。社会が成熟してくると、人は自己実現を欲する。この原理の上に成り立っているのが、オープンソースプロジェクトだ。 さらに、ものを売る側、買う側という二者ではなく、もう一つの存在をかませることで三者の関係にする。その結果、消費者には無料で商品を提供するというのが、R25を無料で提供する手法だ。 社会が複雑になるにつれて、物を売る手法も進化している。 経営の神様・松下幸之助は、「無税国家」を作れると主張した。サービスを提供する役所とサービスを購入する市民という関係の中で、そのサービスを無料にできると訴えた。 企業は知恵を発揮して無料のサービスを生んだ。役所も市民にとって無料の行政サービスを提供することができるはずだ。
0投稿日: 2012.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書中の良書。巻末付録は必見である。この本のFREE版があるのは買った後に知ったが、それでも払うだけの価値アリ。
0投稿日: 2012.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2009年に発行。ちょっと古いですが読んでみました。 勉強の為とか仕事に活かそうとかいう気はないです。 あるのは好奇心のみ。 アトムは無料になりにくく、ビットは無料になる。 本書ではフリーをうまく利用したビジネスが多数紹介されてます。 多分、本題とあまり関係ないところでおもしろいなと思った部分↓ ●フリーは対象者のパイを極端に増やすことができる。なので、1000人のうち一人にお金を出してもらえれば良しとする。オンラインではもともとコストがかからないので問題ない。フリーにすることでとにかく注目度があがる。ある意味、数打ちゃ当たる戦法。 これを自然界の生き物の話と絡めていたところがおもしろい。 人間の脳はムダに対して抵抗を感じるようになっている。なぜならほ乳類であり、ほ乳類は動物の子供の数が少なく、子供が大人になるまで膨大な時間と手間を費やす。食べ残しや浪費に罪悪感を覚える。しかし自然界のほとんどの生き物はそうではなく、マグロは1回の産卵で1000万個の卵を生むが、成体になるのはそのうち10個。 うんぬんかんぬん〜長くなりました。すいません。 フリーは膨大な量から、少なくはあるけれど価値ある対象者を検索するのにもってこい。フリーが世の中に多くなったからといって、無駄に感じる必要はないのではないのかという話。 これだけフリーが多くなると世の中の経済って大丈夫かなと心配してましたが、著者はフリーを随分前向きにとらえていて安心しました。売れない音楽もライブやグッズその他で商売にできることはいくらでもあるんだなと。 何より、創造が好きな人がアピールできるステージがたくさん用意されたことが嬉しい。 それがフリーの一番の恩恵じゃないかと思ってます。
0投稿日: 2012.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ長い積ん読期間を経て、ようやく読み切った一冊。俺らの世代はデジタルネイティブとイミグラントの狭間だと思うから、一番読む価値のある世代かも。 本書によれば、複製にかがるコストが実際の価格と比べ圧倒的に安いものは、その価格タダになる力が働く。イメージとしてはPDF化された本やmp3の音楽をコピーすることに近い。 おまけにこれらはヴィトンの偽物とは違って、本物と何も変わらない完全なコピーなのよね。 これは倫理的な問題が潜んでいるかを議論することも出来るが、どんな結論が出るにしてもこの流れをせき止めることはおそらく出来ない。これはリンゴが重力に引かれて落ちる物理学の問題に近い。 その結果、フリーへの引力は社会に変化を要請する。実際、中国やブラジルではCD販売ではなく、ライブやその注目度を利用した他企業の広告出店料をメインの収入とするアーティストも多いとのこと。 俺の場合この手の不正コピーの話は医学書が頭に浮かぶんだけど、そういう専門書も複製されて、いずれはフリーになっていくのかな。そうだとすれば、著者は新しいビジネスモデルに乗った方法を考える必要があるのかも。 手っ取り早いのは機能を上乗せしたフリーミアムモデルだと思う。学生は無料、医師は有料とうまく棲み分けができるような。 「不正コピーは犯罪です」を念仏のように繰り返すこともひとつの手段だとは思う。 だけど、もしかしたらそれって、船の進路上にある灯台の光に向かって進路変更を要請し続けるようなものかもしれない。 いろいろと考えることの多い本でした。俺は結構保守的なとこもあるのでw得るものも多かった、おすすめです!
0投稿日: 2012.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ1ヶ月分の新聞を読んだような気分である。要素要素は面白かったものの、読んでいて苦痛だった。アメリカ人ってなんでこんなに編集能力がない人が多いんだろう。書籍である必要も、個人が書く必要もないような内容だった。
0投稿日: 2012.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ物が無料で儲かるのか? そこには驚きと納得の人間の心理が働いているというそうです。 マーケティングに興味のない人も、読むと仕組みが分かって得します。
0投稿日: 2012.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
00年代のベスト書籍と評判の本。 確かにデジタル時代に台頭してきてる GoogleやFacebookが採用する<無料モデル>を 実によく解説している。 従来型企業が採用してきたマスコミ型広報ではなく、 新種のオンライン上のバイラル型広報(PR2.0)が 新規ビジネスモデルのメインになっており、 そこは無料の世界だと指摘する。 そして、無料からお金を儲ける新たな錬金術を授けている。 <要約> 「潤沢な情報は無料になりたがり、希少な情報は高価になりたがる」 フリーの戦略はデジタル時代のいまに始まったことではない。 いつの世でも潤沢な情報と希少な情報があり、それは取引されてきた。 いまなにが違うのか、それを明確にした点でこの本は重要なのだ。 オンライン上でデジタルになり、フリーのビジネスモデルが ビットの世界のあらゆるモノに拡大していることが新しいのだ。 ここまでビット世界のフリーモデルが拡散する理由は、 ビットの世界では、今までのアトム(原子)の世界と比べて、 限界費用が圧倒的に小さいことに起因する。 まず基本としてビットの世界では 商品のコピーを作っても、ほとんど費用がかからない。 そして製品以外の限界費用であるコストも比較にならないほど安い。 アトムの世界では、人件費や配送費、店舗コストなどが 限界費用を規定していたのだが、 ビットのロングテールの世界には 人件費も配送費も店舗コストも「無視できるくらいに安い」のだ。 デジタルテクノロジーの3つの限界費用は限りなくゼロに近づいている。その3つとは、情報処理能力と記憶容量、通信帯域幅である。 それはムーアの法則によって予言されていたが、 「競争市場において価格は限界費用にまで下落する」という ベルトランの競争原理がビット世界でのフリー化に拍車をかけている。 アトムの世界では限界費用はある程度に抑えられていたが、 ビットの世界では「無料」が可能なほどに「無視できる」のだ。 そして、「無料」の価値は、想像以上に大きい。 フリーの心理学で考えれば、「値段がつくことで、人々は選択を迫られる」。選択すれば、選ばなかった後悔と選んだ末の不満に苛まれる。 無料のものには期待がないので、後悔も不満も存在しない。 では、無料でいかにして設けるのか? この最大の疑問に答えているのがこの著作である。 (ネタバレになるので詳細は控える) ①フリーの戦略を4つに規定 ・従来アトム型 直接的内部相互補助 ・従来アトム型 三者間市場 ・ビット経済型 フリーミアム ・ビット経済型 非貨幣市場 ②フリーミアムのタイプを分類 ・時間/期間制限 ・機能制限 ・人数制限 ・顧客タイプ別による制限 ③適切な有料と無料の移行の割合を決め 無料からお金を引き出す新しい戦略を導くとある。 いわゆる「ガチャゲー(Gree,DeNA)」が取っているのも このフリーミアムの戦略である。 大量にいる多くの「無料」の顧客と それを支えるプレミアムの「有料」の顧客。 これらの事例をふんだんに紹介し、 巻末には50のビジネスモデルを掲載している。 このところ「PR2.0」→「キュレーション」→「フリー」と 読み継いできた。 次に「リーンスタートアップ」の予定だが、その意味では 「フリー」のなかにも以下の文面があった。 「失敗せよ!もっとはやく失敗せよ!」 たぶん、これがビットの世界の成功の法則なのだと思う。
0投稿日: 2012.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在躍進している企業(Google、日本ではDeNAやGREE)の儲けの原理が分かる本で、本書終盤のまとめはビジネスモデルの構想に役立てることもできる。しかしあくまでも現在の方程式を説明した本であるので、次の時代に何が訪れるのか、想像する力が必要。
0投稿日: 2012.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログいまさら読んだ。 図書館で借りてただで読んだ。 潤沢なものを売るのか、希少なものを売るのか。 潤沢なものは無駄に使え ということが一番記憶に残っている。 キャッチーな概念化や分類が得意な人なんだと思う。 厚い本だけどさっと読めて楽しい本
0投稿日: 2012.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか読み切れなかったけど、やっと読み終えることができた。 本書は世の中のフリーなものを具体例を通して、わかりやすく説明されていた。 デジタルなものは遅かれ早かれフリーになる。 身近な例でいえばCD,航空料金など。 おおまかにCDをフリーにしてファンを増やしライブで収益を上げるなど、今までメインで売っていたものはフリーになり、フリーによって得た顧客から違った形で収益を得ていくというものだった。 確かにこの本を読んでいると、普段自分が使用しているものでも、フリーなものが多いことに気付いた。 フリーの流れは止まらないし、止めることはできないと思う。 そういったフリーの流れをもろにくらう業界は、今までの価値観では戦っていけなくなるのだろう。(まぁこの本出版されてもう2年半くらい経ってるけどw) 全然関係ないが、レディオヘッドやナイン・インチ・ネイルズなどのアーティスト名が出てきたのはびっくりした。さすがトレント様(笑)
0投稿日: 2012.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログFREEが当たり前の世代と、 そうでない世代、 理解できなかったことが、 とてもよく理解できました。
0投稿日: 2012.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ厚いわりにはページ数が少ない。 でも最後まで読み切れなかった。 フリーで金儲けはできることはわかるがその先は自分で考えなければならない。
0投稿日: 2012.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ・フリーの仕組み4種類 ・コモディティ化>安くなる>他への価値の転換 ・雑誌がフリーにしない理由>広告主への心理学 ・モノを獲得する時の影響、金銭的影響、社会的影響
0投稿日: 2012.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
印象的だったのは「無料メディア自体は新しくない。そのモデルがオンライン上のあらゆるものへと拡大していることが新しいのだ」、「ウェブの教訓=毎年価格が半分になるものは、かならず無料になる」等の言葉。
0投稿日: 2012.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログアトムの世界におけるムダを排除して原価を下げる活動と ビットの世界におけるムダを蔓延させて価値を生み出す活動。 アトムの世界が無くならない限り、前者のアプローチもなくならない。莫大な固定費がかかる世界では、自己否定とも言えるアプローチは合理的だし、日本人の性にも合うため(=もったいない)、未だに「モノづくり」が神聖視されるわけだが。 他方、後者は世の中をムダで溢れさせて、もっと魅力的なムダを生み出すために知恵を絞る。しかもそれを利用する何億人もの人の脳みそを借りて。それが利益を生み出す。 前者は衣食住に関わるインフラ産業と、後者はより快適な余暇を過ごすためのエンタメ産業と結びつきが強い。 連続的に捉えることが難しい両者の違いに稿を割いているところが良かった。 単なるフリービジネスの見本市に留まらず、一読の価値はある。
0投稿日: 2012.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログわたしが受験生だった頃、学校でやった問題集に、横浜国立大学の入試の英語長文で、ジレッドの話がでてきた。この本自体は日本語で読んだけど、文章がほぼ一致したので、この元となった雑誌か何かから取ってきたんだろうなあ、とちょっと嬉しかった。 難しかったです。初心者向けではないのかな。というのも、専門用語がいっぱいでてきて、うまく頭に入ってきませんでした。ビットとか…。 だけど物を売るにあたって、商品の性能の良さは前提として、やはり売り方ってのがかなり重要になるんだとわかった。 ちょっとした工夫、フリーをうまく使って、商品を普及させることができるんですね。 しかもフリーってのが鍵で、限りなく安くしても、やはりフリーには適わないし。お金を払うときの決断ってのもはっとなった。
0投稿日: 2012.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
半分くらい(しかもななめ読み)しか読めませんでした。 今までこのような切り口に関するフリーの研究はなかった、ということです。 サンプル配布による広告だけでなく、ジレッドによる替刃ビジネス、amazonの送料無料、OSSといった様々な形態があることに改めて気づきました。それぞれ、一番最初に考えた人は偉大ですね。
0投稿日: 2012.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログさまざまなフリーのビジネスモデルを学べました。 なぜ世の中に溢れかえってる試供品や無料版が成立つのか素朴な疑問に、深い視野、考察から答えてくれました。
0投稿日: 2012.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ無料のビジネスについて書かれた本。よく分析されており面白い。 無料は今や一つの大きな「戦法」になっているのだと痛感した。 自分が戦略を立てる時に逆転の発想として、「タダ」にしたらうまくないないかを考えてみるようにしよう。 (今やもうそれは逆転の発想ですらない、普通の戦略の一つになっているが。) 周りの無料のものはどこからお金を設けているかを考えても面白いね。
0投稿日: 2012.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フリーの例として、アマゾンの書評があるかもしれません。 本の宣伝広告をしようと思ったら、 お金を支払わないといけません。 それが無償でできるのです。 それがウェブの仕組みです。 あたりまえのことが、お金を生み出す新戦略といわれてもピンときません。 ウェブがはじまったころからの話だし、 もともとインタネットはネットワークの相互接続で、無償が原則でした。 原理を知らない人が読むと驚くかもしれないが、 原理を知っている人にはあたりまえのことが書かれているだけなのかもしれません。
0投稿日: 2012.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログFREEとは何か?、その歴史、現在経済に及ぼす影響、FREE対する誤った見解、などFREEについて他面的に書かれた本。デジタルはその物性と人間の性質により無料になりたがりいずれはゼロと競い合う、という内容が印象的。詳しく且つ分かりやすいので、フリーペーパーやフリーウェアくらいしか頭になかった自分としてはかなりイメージが広がった。ただ、サブタイトル「無料からお金を生み出す新戦略」というのはあくまでもFREEを提供する側の視点。最近は無料コンテンツだと思っていたら有料だったというようなトラブルもあるので、顧客視点の章もあればもっと良かった。
0投稿日: 2012.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、いかにして仕組みを作って利益を上げるかを知りたくなり、対価の取り方の中でもエンドユーザーを無料にするものに興味があったので、こちらを買いました。 何年か前に書店で平積みになっていて、そのときから気になっていたのですが、因果は巡るというか、昔気になっていてそのときは買わなかったものって、なぜか必ず後で読むことになります。 これは面白い。R25やフェイスブック、民放テレビのように広告収入でエンドユーザーが無料のものから、費用負担が薄く広く分散されていて事実上無料に見えるもの(実は公共サービスはこれに近いかもしれません)まで。さらに、そのサービス自体ではもう対価を取るのをあきらめ、サービス自体は純粋にプロモーションとして使い、周辺に作り上げた世界で稼ぐモデルもあります。例えば、音楽のコピーやYouTubeへのアップはもう止められないので、曲の提供自体はもう商売としてあきらめ、増えたファンをコンサートに繋げて稼ぐとか。 原則、デジタル情報に変換できるものは無料になっていく強い力が働くようです。情報は複製コストが限りなく低いので。 このあたり、著作権は今後どうなるのかという話と関係して実に面白そう。情報自体はフリーにしつつ、原作者に正当な対価が払われるような新しい枠組みが必要になってきていると思います。 この作者の前作、『ロングテール』もいま読んでいますがこれも抜群に面白いです。
0投稿日: 2012.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
"There's no such thing as a free lunch" 「内部相互補助」p31 【三者間市場】 無料なもの・・・コンテンツ、サービス、ソフトウェア メディア、消費者、広告主 p37 【フリーミアム】 5%の有料ユーザーが残りの無料ユーザーを支えている。(5%ルール)p39 「ペニー・ギャップ」p84 「ゼノンのパラドックス」p118 「複合学習曲線」p124 【クラウドのありか】 オレゴン州ダラスで、ポートランドから130キロ離れたコロンビア川沿いに行けば、少なくとも外からその建物をみることができる。そこはGoogleのデータセンターのひとつで、大きな工場のような建物に、数万台のコンピューターボードとハードドライブが、移動可能なラックに数十台ずつ収められている。すべてがネットワーク・ワイアで接続されていて、建物からインターネットへは光ファイバーケーブルの太い束で結ばれている。p160 「ダンバー数」:個人が維持できる人間関係の限界数。(150人)p219 フリーが世界に生み出す経済規模は少なくとも3000億ドルになる。p223 【中国の模倣文化】 「欧米の報道では、中国の模倣品は犯罪以外の何物でもない。だが中国では、模造品は別の価格帯の別の商品であって、市場が求めたバージョン化のひとつなのだ」p269 「機会費用」:ランチに費やした時間でほかのことをしていたら生じたであろう価値のこと。p287 ウェブは主にふたつの非貨幣経済単位で構成されている。注目(トラフィック)と評判(リンク)だ。p296 【インターネットを動かす3つのテクノロジー】 情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅。p322
0投稿日: 2012.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログパクりだなんだというけれど、著作権をふりまわすのも実は一面的な見方なのかもなぁ…と関連して思ったりもした。ずっと積読だったのをようやく読破。
0投稿日: 2012.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本屋に通う人は一度は見たことのある表紙と思います。 2年前くらいに売れていた本作が、地元の図書館にあったので 読んでみました。 フリー(無料サービスから収益を生み出す)方法について 様々な成功例や作者の意見を織り交ぜて紹介しています。 確かにmixiやFacebook、googleとかは大体が無料ですが、 一部の機能を使うがために有料会員になっている人もいます。 また店や道端で無料でもらったのをきっかけに、 リピータとなり、商品を買い始める人もいます。 このあたりがフリーから収益を生むコツなんでしょう。 こんな話が終始展開されています。 ちょっと話が長いですが、現代的な話なので納得できる作品です。
0投稿日: 2012.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フリー」という、経済学においてもまだ明確に説明されていない新しい概念をわかりやすく説明してあり、思ったよりあっさりと読めた。ただ、例としてあげられる説明の一部が適切でなかったようには思った。とても興味深いマーケティング手法として読めた。
0投稿日: 2012.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者のクリス・アンダーソンは、あの「ロングテール」を世に発表したWiredの編集長です。今回も、大きな波をキャッチしたようです。 ロングテールの時には、ネット店舗の陳列コストが下がったことによる、既存のスキームの店舗ではリーチできないニッチな客を捕まえることができるようになったことを、見事に捉えました。確かに、米国に出張の度に、リテールのCDショップが潰れていくのを見て、これは実際に起きていることだと、目の当たりにしていました。 今回は、ネット上での無料で行われているビジネスのからくりを明らかにして、いわゆる 『ただより怖いものはない』は、 もう存在しないことを見事に証明してくれる。 とにかく、ケーススタディが満載で、なぜ無料のスキームが成り立つのかの、彼の観察が、あまりにも斬新で、そっか、その視点からは考えたことがなかったと、思わずうなってしまいます。序盤の「無料」の歴史論は、ちょっと授業チックで退屈ですが、中盤からのケーススタディのオンパレードは、こんな本が1800円で世の中に出て良いのかと思うほど、今後のWeb社会を予見させます。 そしてキャッチがまた素晴らしい!! あなたがどの業界にいようとも、 無料との競争が待っている。 それは可能性の問題ではなく、時間の問題だ。 そのときあなたは、創造的にも破壊的にも成り得る このフリーという過激な価格を 味方につけることができるだろうか? まさに、この問に見事に答えてくれる、一冊です。 悩むより読むべし!!今年の必読書です!!!
0投稿日: 2012.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログフリー1 直接的内部相互補助 顧客が何か買う事を見込んでいる フリー2 三者間市場 メディアなど 広告収入で賄う フリー3 フリーミアム 5%ルール プレミアム版ユーザーの割合 無料と有料のバージョンがある フリー4 非貨幣市場 えてして価格は原価ではなく心理学を元にして決められる。 行動経済学
0投稿日: 2012.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログまずは、アトム(物質)経済の20世紀に存在する旧来型のフリーについて 説明すべくフリーの歴史から紐解き、フリーを四種類に分類。 ・直接的内部相互補助:フリーでない他の物を販売し、その売り上げをフリーに補填。 ・三者間市場:第三者がお金を払う。 ・フリーミアム:フリーで大多数の人を惹きつけ、有償バージョンを用意する。 ・非貨幣市場:フリーを提供してもらう代わりに無償で労働する、情報を与える等。 そしてビット(情報通信)経済の21世紀である今日においての著者の見解は、 ・競争市場では、価格は限界費用まで落ちる。 ・テクノロジー(情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅)の限界費用は年々ゼロに近づく。 ・アイデアからつくられる割合が大きいほど物は速く安くなる。 であり、そのため「低い限界費用で複製・伝達できる情報は無料になりたがり、 限界費用の高い情報は高価になりたがる」という フリー版万有引力の法則がはたらいていると著者は説く。 これからはデジタル化できる商品は潤沢化を促され、稀少さはますます目減りする、 この流れに抵抗するよりも、単にフリーを駆使するのではなく、 稀少性を発見しそこを換金化して活かす方法を模索せよ というのが著者からのメッセージではないか。 身の回りにあるフリー(無料)についてわかりやすく書かれていて、非常に面白い。 できれば各章ごとに重要点をまとめてほしかった。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログフリーをとりまく経済がわかりやすく様々なケースで取り上げられているので、ためになった。もう一度読んで理解を深めたい。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書籍化されて少し経ちますが、一読しておくといいかもしれません。 職業とはあまりかかわりが薄いところではあるのですが、このフリー自体の概念の再固定するにはとてもよい本のように思います。 はじめ僕がそうでしたが、「この本でのフリーの定義」を理解しておかないと読みづらいのかもしれません。 フリーミアムのことだけでなく、極限に最小化されるコスト、プレミアムの置き所、とても参考になると思います。 フリーミアム、アトムとビットの価格形成について、収益化されたビジネスモデル、例示やグラフが多く、読みやすいです。
0投稿日: 2012.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログいやあ、フリーにもいろんな都合があるもんだなあ。 フリーの理由、強さといったものが解説されてるが、 その中でも中国・ブラジルの不正コピー社会は興味深い。 不正コピーが横行する中で利益を上げるコンテンツは、 年々フリーに近づいていく社会の末路に違いのかも。 そういう意味で中国は強い。どこよりも先を行ってるのかもしれない。
0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最近、とある理由でスマートフォンをAndoroidからiPhoneへ変更しました。何が言いたいかというと、Andoroidでは無料だったようなアプリケーションが、iPhoneでは有料だったり、広告付きだったりしているわけです。有料とはいえ、ロングテールのさらに最後尾のような価格なので、がっつかれているというわけではないですが。 昔、PalmOSを使っていたころは、有料のソフトがあるの?と思うくらい、無料で質のいいソフトがそれこそハッカーたちによって開発されていました。その時代がよかった、というわではななく、そうしたハッカーたちの善意が、それこそPalmOSの限界であり、その後の衰退につながったのかも知れません。PalmOSにしろスマートフォンにしろ、それなりに垣根が高かったシステムに市民権を与えたのは、確立した課金のシステムと、程よい無料と有料のハイブリッドのソフトウェア群なのかもしれません。
0投稿日: 2012.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと読みたかったが故に卒論のテーマにまでなった本。 面白かった。漠然としていたフリービジネスに対して4つの分類という枠組みを与えてくれているので、フリービジネスがより理解しやすくなったと感じる。 個人的に良かったと思うのが次の視点。「潤沢な情報は無料になりたがる。稀少な情報は高価になりたがる。」「フリーと競争するには潤沢なものを素通りしてその近くで稀少なものを見つけること」フリービジネスの収益モデルを考える上で無視できないことばだったと思う で、なぜ評価4か。完全にはしっくりこなかったからということと卒論に追われて読んだからかと思われる。
1投稿日: 2012.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書会の課題本。300ページほどの本ですが、紙質によるものなのか、かなり分厚いです。■フリーの仕組みを分類して説明「なぜ無料という価格設定が可能なのか?」という問いに対して、4タイプに分類して解説しています。フリーミアム、という言葉もここで登場します。■非貨幣経済についても言及刮目すべきは、非貨幣経済似ついても言及されていることです。金銭だけで完結する現在の貨幣経済から、社会的評判と言ったファクターも重要視される非貨幣経済が今後興隆するのではないか、という示唆があります。最近の有識者の著述の中には、この種のパラダイムシフトに関する言及が増えてきているように感じます。■なぜ無料という価格が成立するか、疑問な人は読むべき!わりとボリューム感のある本ですが、良書です。これからの社会のトレンドを理解するためには、一般教養として読んでおくべき本であると思います。得に「なぜ無料という価格設定が成立するのか」と不思議に思ったことがある人は、一読してみることをおすすめします。
0投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言で要約すると、オンラインコンテンツ、情報処理能力、記憶容量、通信帯域幅は年々限界費用(ゼロ円)に近づいているという話。 最初の方は既に一般的に知られてる内容で、18ヶ月で単位面積当たりの半導体の数は2倍になるという、ムーアの法則から派生している話。様々な実例を元にフリーの歴史、分類も事細かに書かれている。後半はコンテンツ事業者のあるべき姿、評判•注目自体を価値とする非貨幣経済にまで話が及んでいる。 デジタルコンテンツはゼロに向かっているのは万有引力のように避ける事ができない、というのは真理を突いてる様に思った。 コンテンツ関連事業者は、フリーを拒絶するのではなく、コントロールする事が必要だ。ただ、Google、Facebookのように、市場がほぼ独占された中で他の事業者がこれを敷衍することは非常に難しいと思う。タダが当たり前の市場では、価格による優位性はもはや出せないからだ。他事業者よりも価値のあるコンテンツを、既存業者以上に頭を捻って絞り出す事が必要だ。 著者はかつて「ロングテール」で一世を風靡したクリス・アンダーソンという人。 物理学を学んでいただけあって内容は緻密かつ論理的なので、難解ではあるが、非常に納得できる。 テレビ、新聞、出版社、ラジオ、映画、音楽等、デジタル化可能なコンテンツを売り物にしている事業者は一度は読んでおきたい。
0投稿日: 2012.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログみんながなんとなく漠然と理解してる「フリー」の効果・効能をデータや学説などを交えてわかりやすく整理してくれる本。おもしろかった。 有料の「プロ版」と、それの廉価版的な無料版を用意して、有料ユーザーが10%くらいいれば収益があがるという話、自分はその手の無料版と有料版があるサービスとかアプリで10%のユーザになったことがない=有料版を購入したことがないんで実感がないんだが、実際お金払う人って結構いるんだな。 この手の訳書の読みづらさって、翻訳者の力でなんとかならんのだろうか。多少表現を変えても、日本人に馴染むようにしてもいいと思うんだが嫌がる人が多いんだろうか。 あと、アマゾンで買ったんだが、届いて手に取って、本のデカさにやってもうたと思った。通勤カバンがパンパンだった。あとがきにもあったけど、ネットでダウンロードできるフリー版に対するプレミアム版的な意味があるっていう、本文の内容を体現してるのはおもしろいと思うが。
0投稿日: 2012.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ書評は下記で公開中。 http://yokochan-y2.com/bookreview/free/
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ挫折した。。。 Freeというタイトル通り、資料の出典がwikipediaなところがちょっと愉快。
0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
表紙が何かのパッケージみたいで目を引く。山積みになっているのをよく見かけたので購入。特に期待していなかったのだが、商品を販売している身としては、新しいネタの宝庫だった。また、大学で研究していた意思決定についても参考になることが多くあった。キャッチーに、多くの事例を出してかかれているので、とっても読みやすい。 無料のビジネスモデルは頭の体操みたいで、色々なアイデアがあり、すばらしい。一方、それでそれできちんと儲かっている企業は一握りなのだと思う。身の回りから一例をあげると、ブログで口コミをしてもらうために、サンプルを配る試みなどがされているが、最近は消費者の方が賢くなり、このような口コミに敏感になってしまった。 同じようなシリーズでSHAREやPUBLICが出ている。こちらもいつか読んでみたい。
0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからもドンドンFreeの経済は拡大していくのだろう。 消費者としては大歓迎だが、メイカーとしては大変だ! デフレは続くどこまでも。
0投稿日: 2011.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔から試供品を最初に配布して知名度を上げてから通常の販売をするという販売促進方法はありましたが、現代は通信固定費はあるものの、いくら検索しても無料という検索サイトでじ十分にコトは足りる時代になっています。 この本には、最終的な消費者は支払う必要はなくても、そのコストを他の人が負担することで、多くのサービスを無料にすることができる実例が示されています。ポイントは低価格ではなく、無料だそうです。 モノを売って収益をあげている会社に勤めている私にとって、無料のサービスを増やすことにどうしても抵抗を感じてしまいますが、無料でサービスを提供することで収益が得られるというビジネスモデルが数多く成立している世の中に驚いてしまいました。 以下は気になったポイントです。 ・レシピ本は無料で配るので、セールスには当たらなく、戸別訪問販売を禁じていていたルールに反していなかった、製品を買った時だけ必要となる情報を、消費者に無料で提供した(p18) ・無料サンプルは売上に貢献したが、それ以上にジレットを助けたのは、無料で配った安全カミソリが替刃の需要をつくったこと(p20) ・自分たちの楽曲をオンラインで無料配信することで、多くの人々に音楽を届けてファンを獲得できる、一部がコンサートに来てくれて有料でグッズを買ってくれるので収益が上がる(p23) ・デジタル製品においては5%ルールがある、つまり5%の有料ユーザーが残りの無料ユーザーを支えている、それができるのは無料ユーザーにサービスを提供するコストが無視できるほどゼロに近いから(p39) ・日常生活に見られるフリーの分類として、4種類(直接的内部相互補助、三者間市場、フリーミアム、非貨幣市場)がある(p44) ・見知らぬ人との取引では、社会的絆では評価できないので、お金が価値をはかる共通の基準となった(p52) ・今日、市場に参入するもっとも破壊的な方法は、既存のビジネスモデルの経済的意味を消滅させること、つまり収益源としている商品をタダにする(p60) ・農作物を育てるのに必要な材料は5つしかない、太陽・空気・水・土地・労働力である、農作物の価格の大半は労働力と土地と肥料であるp63) ・コメはタンパク質が豊富だが育てるのが難しい、小麦は育てやすいがタンパク質が少ない、トウモロコシは育てるのが簡単でタンパク質が豊富(p65) ・今日の1ドルは100年前に比べて、25分の1の価値しかない(p70) ・無料が持ち込まれた途端に、被験者の好みが逆転することがある(p86) ・慈善活動の場合においても、ほんのわずかな金額でも課金することによって大きく参入者を減らすことができる(p91) ・中国では海賊版市場と並べて有料市場も巨大になってきた、無認可ソフトを手にいれるための面倒を我慢できなくなってきたから(p137) ・グーグルは多くのものをタダで与えて、少ないものからお金をとっている、ひとにぎりのコアプロダクトの広告料から大金を稼いでいる(p157) ・上位35組のバンド収益を合計すると、CDや音楽著作権の収入よりも4倍以上も多い(p208) ・個人が維持できる人間関係の限界数は、この1000年間の文明において常に150人と一定であった(p219) ・人々は固定料金を支払えばあとは無料になるほうを好む、見えざる料金メータにビクビクしたくないから(p221) ・中国において、不正コピーは自分たちの作品をもっとも多くの潜在的ファンに届けるためのコストのかからないマーケティングと考えている(p265) ・自分のEブックをいくらで買うかを読者に決めさせる方式(標準価格:5ドル)において、平均4.2ドルでありそれによる売上は2000ドル程度であったが、講演収入が5万ドルであった(p310)
0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこれからのビジネスを考える上ではフリーの概念は、シェアと並び不可欠な存在になると思う。本書はフリーの歴史から、世界中のフリーのサービスを分類整理し分かりやすく説明している。さらに、フリーに関して世間が持っている誤解に関しても丁寧に解説している。これからのビジネスを考える上で非常に参考になる本だと思う。 以下では、特に重要だと感じた無料のルールと、フリービジネスの分類に関して記載している。 ◆無料のルール 1.デジタルのものは、遅かれ早かれ無料になる 2.アトムも無料になりたがるが、力強い足取りではない 3.フリーは止まらない 4.フリーからもお金儲けはできる 5.市場を再評価する 6.ゼロにする 7.遅かれ早かれフリーと競い合うことなる 8.ムダを受け入れよう 9.フリーは別のものの価値を高める 10.希少なものではなく、潤沢なものを管理しよう ◆フリーのビジネスの分類 (1)直接的内部相互補助 企業があるモノ・サービスを有料にするが、別のものは無料にする。「DVDを一枚買えばもう一枚はタダ」が代表的な例。 (2)三者間市場 製造者、広告主、消費者間からなる市場。ラジオやテレビなどのメディアが広告主から広告スペース料を取るが、コンテンツを消費者に無料で提供し、消費者は広告をみて広告主のモノ・サービスを買う、関係が代表的な例。 (3)フリーミアム 多くの消費者には基本製品・サービスを無料で提供するが、一部の消費者に有料のプレミアム製品を売る。フリッカー、スカイプが代表的な例。 (4)非貨幣市場 製造者は消費者で無料なモノ・サービスを提供し、消費者は注目や評判を製造者に提供する。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ロングテール」の著者であるクリス・アンダーソンの著書。 「ロングテール」とは「長い尾」を意味し、マーケットにおいて、「大きな、少数のニーズ」(本体)とは別に、「ひとつひとつは小さな、けれど多様なニーズ」(尾)がある、ということを表す。 例えば、ポテトチップスでいえば、コンソメ味という大量に売れる商品がある一方で、梅しそ味という少数ニーズもある、といった形だ。 けれど、現実問題として、多様なニーズに応えるには限界がある。それは、店舗の販売スペースによる制限などがあるからだ。 ところが、ネット書店のアマゾンは、インターネットという「無限の販売スペース」を使うことによって、この多様なニーズに応えることに成功した。つまり『ロングテール』を支配したわけだ。 では、なぜ、アマゾンは「無限の販売スペース」を手に入れることができたのか。それは、インターネット上の販売スペースは、どれだけ増やしてもコストがほぼ「無料(フリー)」だからである。 (サイトへの商品登録にかかるコストは、テナントを借りて、開店することに比べればほぼ無視できるくらい安い) 本書は、この「無限=無料」という点への着目からスタートした「無料経済」の本である。経済だけでなく、歴史的、心理的、哲学的な方向からもアプローチされている。 無料経済は「1円も動かない」のだから、経済指標には本来、絶対に現れない。 けれど、それがデジタル社会によって、無視できないほど巨大になっている。巨大な「無」がどんどん存在感を増しているのだ。
0投稿日: 2011.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ今だからこの本を読むべき。 世の中の「無料」と言われる仕組みがわかる。 なぜお金を払って新聞を読むのか。 なぜ送料が無料になるのか。 なぜ無料オンラインゲームは無料なのか。 いろいろ試したくなる事がたくさん載っている良本。
0投稿日: 2011.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ尊敬する上司が読んでいたので読んでみた。個人的にインターネットとかに詳しく、ビジネスのことなどを日ごろ考えているので、ほとんど知っていることばかりで参考にならなかった。 ●面白かった点 なし。 ●気になった点 すでに内容が古い(というか周知の事実)。また、例をだらだらと書いてあるだけで、ぜんぜん一般化できていない。
0投稿日: 2011.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ大体予想できた内容やった。 フリーでは、お金は後から回収するというビジネスモデル。 ただ日本では、特に稲盛さんは、まず資金がないと安全・安心なサービスが提供できないと主張する。 稲盛さんが言うことはわかるけど、浸透スピードを考えると、フリーの威力は半端ない。いくら値下げしたところで、0円と1円の差は大きいらしい。例えば1円でもお金が発生すると消費者はお金を使うという決断を迫られるみたい。 今後もビジネスモデルは刻々と変化していくんやろし、それに適応せなあかんのやろな。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ「フリー」についてビジネスモデルのヒントというよりは、フリーのカラクリについて学べる啓蒙書として読んだ感じ。 商品を1個買えばもう1つはタダになるなど、「フリー」という概念は昔から用いられてきたビジネスの形ではあるが、それがネットや携帯事業などの話になると、少々胡散臭く思えてくるのは仕方ないのだろうか? 5%の顧客の支払いで、残り95%の顧客分の費用をまかなう「フリーミアム」モデルなど(日本ではニコニコ動画が良い例)は正直好きではない。 また、無料で登録させて約15%のユーザからの課金で利益を得ているソーシャルゲーム等の企業も全くもって気に入らない。 毎年、ネットの通信帯域速度は速くなり、ストレージ容量は巨大になりながらもコストは下がり続けてほぼ0円に近い価格になっているのに、ソーシャルゲームなどを展開する企業は価格を下げずに莫大な利益を得ていることに気づいている人はかなり少ないだろう。 唯一、Googleだけがユーザに不快感を与えることなく、フリーの広告収入でで大きな利益を得ている稀有な企業といってよいかもしれない。 また一方で、フリーと従来の物売りのハイブリッドで、大きなビジネスモデルを築けるチャンスがあることは確かだ。 これから特にフリーが絡んだ企業間の競争が激化するのは間違いないが、倫理観だけは忘れてはならない。 著者が提唱する理論は賛成出来ない点も多々あるが、稀少と潤沢のトレードオフ、マズローの欲求段階説を絡めた企業とユーザの「フリー」へ関わる理論は非常に興味深かった。 一度は読んでおいて損はない良書には入ると思う。
0投稿日: 2011.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ2年前に読んでいたものを再読。訳の難しさからか、正直読むのに難儀したがフリーという概念はやはり興味深い。この概念はつい最近出て来たものではなく、昔からあるものであった事。単純に無料にすれば良いという訳ではなく、プラスアルファでビジネスに合った選択や自分のアイデアを盛り込む必要がある事。これから仕事を行っていく上でも頭に置いておくべき考え方である事を改めて学んだ。
0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ浸透し始めている<フリー>の市場。 フリーのビジネスモデルをわかりやすく説明してくれ、 実例も面白かった。 アトムからビットへ。 有料から無料へ。 ビジネスモデルは変革期に来ている、ということを実感した一冊。
0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログフリービジネスが世界を席巻する. 4~5年前に無料サービスが全面に押し出されてきた, インターネトサービスの潮流を解説しています. 内容はインターネットの普及によりデジタル化されたコンテンツは加速度的に0に近づき安くなる. 実態の商品・サービスも競争により0に近づき安くなるが, インターネットにかなわない. インターネットの無料ビジネスでも上位5%で収益が十分取れる. アメリカのアーティストなんかは無料でPVを公開していますが, 無料にした分,広告効果を得てライブ収入・楽曲収入なんかに結びつけています. この本では海賊版の音楽ビジネスが該当します. ざっと今のインターネットサービスの歴史を振り返るには良い本です.
0投稿日: 2011.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
多くのSaaS型のサービスや有益な情報を提供するサイトではユーザーに対して無料である。これは筆者がビットの経済と呼ぶネット上でのビジネスが、現実の物を扱う商売(アトムの経済と呼ぶ)とは大きく異なる特徴を備えている事に起因する。本著ではそのようなフリーを扱うビジネスのトレンドについて記している。 ①フリーのビジネスモデルの区分 フリーのビジネスモデルはおおかた以下の四分類に分けられる。 (ⅰ)直接的内部相互補助 複数の商品のうち一つを無料で提供することで他の商品に客がお金をかけることを想定している場合である。古典的な「一つ買えば一つタダ」や携帯電話の本体価格をほぼゼロにして利用料金で補完するというかたちである。 (ⅱ)三者間市場 ユーザーではなく別の主体から広告料という形でお金をとる形態である。マスメディアなどは当然これにあてはまる。ネット上のサービスにおいてもこれにいきつく場合が多い。ビットの経済では「ワンクリックあたり~円」のように明確に結果が現れる形でも広告料金を取れる。これは企業にとって大きなインセンティブとなるので一つの大きなアドバンテージである。 (ⅲ)フリーミアム 基本的には無料でサービスを提供し、より高次のサービスを求める一部のユーザーには課金する制度のことである。オンラインゲームやスカイプなどが当てはまる。これはほとんどがビットの経済にみられるものである。ネット上のサービスは開発などに初期費用はかかるものの複製して何人に提供しようがコストはあまり変わらない。このように限界費用がゼロに近い事が10%程度の限られたユーザーからしか徴金するだけでもビジネスを成立させたのである。 (ⅳ)非貨幣市場 企業や個人がサービスを提供するかわりに評判や名声を得ることで成り立っている市場である。ウィキペディアなどが含まれる。当然ながらこの評判という利益やそれを求める社会的欲求は定量化が困難である ②「希少」な市場と「潤沢」な市場 テレビなどは放送枠という希少な資源をうることによって利益をあげていた。一方でネットにより情報が溢れかえり潤沢になった現在では潤沢なものとしての情報は「フリーになりたがる」。潤沢であるということと玉石混合であるということは表裏一体でもある。筆者はYouTubeこそ潤沢な市場におけるサービスをよく体現していると指摘する。潤沢な市場のサービスではしばしば「ムダを受け入れる」ことが肝要となり、TouTubeでも技術的にも内容的にも低いものが多いもののユーザーは自分との関連性でコンテンツを選択するので一向に構わない。テレビの枠であれば希少な資源なためそうはいかない。 ③フリーとの競合 筆者は情報がフリーになりたがることを良い事とも悪い事とも言っていない。ただ法律も越えて情報がフリーになりたがるというのは経済現象としては当然の成り行きであるとみているのである。既存の企業は必然的にフリーとの競合を迫られる。しかし情報の希少性で利益を得ていた既存の企業に未来がないと断罪しているわけでもない。中国の音楽レーベルがレコードによる収入から、マネジメントにフォーカスしライブ収入などにシフトして成功した例などが挙げられている。この例では音楽自体をネットで無料配布した結果400万人にダウンロードされムーブメントとなったことから、フリーのシステムを上手く利用しフリーによって得た評判を別の希少性に生かしたといえる。基本的にフリーと競合する既存の企業は①新聞のように質で差別化を図りマネタイズする②既存のコンテンツをフリーにして別の希少性を創造するという手段しかないと筆者は主張している。 350ページにおよび少し骨が折れますが、その分マクロ的な視点から実際的な戦術までここに纏めきれない多くの視点を備えています。おすすめです。
0投稿日: 2011.10.17
