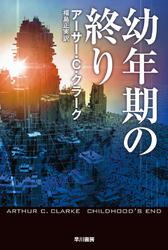
総合評価
(179件)| 68 | ||
| 56 | ||
| 30 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ神本である。 ところどころ、なかなか読み進まないところもある。しかし、想像力がとにかくすごい。解説にもあるように、確固たる理論に支えられているためだろうが、絶妙にあり得そうな雰囲気。
0投稿日: 2026.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログフルダイブVR的な話しが書かれていたり、1979年発行の小説とはおえない内容。 前半はオーバーロードの気長な時間軸で人間が管理され、彼らの目的を徐々に暴く展開であったが、最終的には予想以上に壮大なことになった。 オーバーマインドはカルダシェフスケールの上位の存在なのは間違いない。
9投稿日: 2025.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生の時から読んでる。面白いから、と人にあげたりして3冊購入している。今は息子が読んでる。 何度読み返したかわからないくらい読んでいるが、年齢によって登場人物への感情がかわる。若い頃は自分も密航する!と思った。親になってからは、子どもを失う両親の気持ちに胸が張り裂けそうなった。
0投稿日: 2025.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なかなか物語の世界に入ることができなかった。 「どんなユートピアも絶えず、すべての人間を満足させておくことはできない」 カレルレンが目先だけでなく、長い目で見た時の地球について考えており、おぞましかった。
0投稿日: 2025.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ★3.5かなぁ。 ストーリーとしても面白いし、ちょっとした詩的感もある。また、ある種の諦念が全体に漂っているところもストーリーの組み立て、キャラ設定に役立っているかと。 ただずっと静かな感じが続くのでエンタメ的には少々物足りない気もする。この点で最近読んだ「星を継ぐもの」の方が上かなぁ、個人的には。 まぁ好みのレベルかと思われ、一読をば、という小説でした。
0投稿日: 2025.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんか悲しい。 数々の種族と星の終焉を見てきたカレルレン含むオーバーロードは病んでそうだな。残されるものが辛い。
0投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログそれは突然やって来た。世界の大都市の上空に無数の飛行物体が現れた。 それは人類にとって敵なのか、それとも味方なのか。何を目的としているのか。どんな姿形をしているのか。謎は深まっていくばかり。 1952年に書かれた本作は、古典的SFの名著だと思います。
13投稿日: 2025.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
もしも突然、人類より上位の存在が地球に到来したら。。。 オーバーロードは敵なのか、味方なのかとヤキモキしながら読んでいたが、結局はそのどちらとも言い難い存在だった。 超科学的な結末で全く予想できなかった。 SFの古典を読めてよかった。 いろんな作品に影響を与えてそうだなと思った。
1投稿日: 2025.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
SFらしいとてつもなく面白い設定と、エンタメらしい次々に状況や場面が変わる面白さ さすが名作と語り継がれるだけある 人類が思っていたオーバーロードと実際のオーバーロードにはギャップがあったが、カレルレンは人類を裏切らなかった、と私は思う ジャンが宇宙船に乗り込んだときどんな世界が見えるのかワクワクしていたが、その後地球に起こった変化が激しすぎて銀河系の外とかどうでもよくなってジャンが帰ってきた地球がどうなってるのかが気になって気になってページを捲る手が止まらなかった
1投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・あらすじ 人類が宇宙への第一歩を踏み出そうとしたその日、空に無数の巨大な飛行物体が現れた。 上位存在であるオーバーロードたちの管理下のもと人類史上で初めて苦しみや争いのない平和な社会が実現する。 オーバーロードたちの目的、そして管理された人類の行く末はどうなるのか? ・感想 超超超有名古典SFをやっと読めた。 夏への扉や渚にての描写が合わなくて、この作品に対しても少し構えてたところがあるんだけど杞憂だった! 面白かったなーー。 読後はカレルレン…カレルレン…がんばれ!ってなった。 終盤まではゆっくりペースで読み進めてたので時間がかかったんだけど、ジャンが飛び立った辺りから続きが気になってあっという間に読み終わった。 (というかジャンやらジョンやら似たような名前が多くってちょっと混乱した) 「室内飼いの犬や猫のように自分の上位存在に全てを管理してもらって何でも手に入って快しかない環境で自分の好きなように生きられるの羨ましいわ」とたまーに思うけど、もしいま私が生きてる世界もすでに上位存在により管理された社会であるならもっと上手くやれよ!!って文句言いたくなるw いやでもこれも彼らの計算のうちなのかもしれない…とか想像したりするのも楽しかった。 でも個が無くなって全体に統一されるのは嫌だな。 三体もそうだけど上位存在が登場するSFというのは最後はやっぱり観念的というか哲学的な思想、精神的な描写に進んでいく傾向にある。 全てを想像するしかないしね、抽象的になっていくのも仕方ない。
3投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ古典SFと思えないリーダビリティ、展開も相応にあって途中まで頁を捲る手が止まらなかった。 ただ、ラストだけ良くわからず、んーといった感じで、惜しくも星4つになってしまった。 文体や雰囲気は、『星を継ぐもの』を彷彿とさせる感じで非常に好みだった。
0投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下の問を、人類よりも発展した種族≒宇宙人の出現というストーリーの中で描きたかった本である。と読んで思った。 ・人間というものは、何を希求して生きているのか? ・人類とはどんな世界を目指し、どんな道を選んできたのか? ・人類はどのような発展ないし進化、変化をとげていくのか? 目的意識、論理的発展、科学の発展という現代が希求していることの限界を感じた。 サイエンスフィクションでサイエンスの限界を描くというのはSF名著で共通して見られると思った。 「議論をやめて事実を集めるべきだ。それには行動が必要だ」 「これが人類のメタモルフォーゼの結果なのか。」 この言葉が心に残った
1投稿日: 2025.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ巨匠アーサー・C・クラークの代表作の一つであり、歴代のSF小説のなかでも屈指の作品と呼ばれている作品。 突如、地球にやってきた巨大宇宙船団。その宇宙船団の総督であるカレルレンが率いるオーバーロード。彼らが地球人に変わって地球を統治することになる。地球にはそれまでの国境による線引きされていた国家がなくなり、戦争から飢餓、疫病、差別はなくなる。 そしてカレルレンによる地球人の進化が長いスパンをかけて行われていく。 オーバーロードがなぜ地球にやってきて、地球人たちを統治して、進化をさせていくのか、その目的と理由が明かされていくというもの。 本書から影響を受けた他の小説、映画、ゲーム、アニメなど多く存在する。 それくらいに影響力が強い本作。1952年に刊行された本作は正直SF作品のなかでも古典に位置する作品だと思う。しかし、今読んでもまったく古臭さを感じない作品で驚いた。 何ならまだアーサー・C・クラークの想像した世界は遥か先で、現実は到底追いつけないように思えてしまう。 ゴールデンエイジ期のSF小説家は数作品くらいずつ触れてたりはするのだが、改めて読み直してみたくなった。 アーサー・C・クラークもかなり昔に読んで、それ以降は今更読まなくてもいいでしょくらいに思ってたので。 この想像力がどこまで広く世界を見ていたのか、触れてみたくなった。
2投稿日: 2025.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ある日突然、地球に飛来した超高度な文明をもつと思われる種族。オーバーロード。それを取り巻く人間の姿。人間の週末。 もし本当にそうなったら、確かに地球人には遠く及ばない文明水準なんだろうな。そして地球にわざわざ来るということは、何か目的があるということ。その目的は、オーバーロードのさらに上の存在、オーバーマインドの意志を遂行すること。地球人は、まさに未開の民族で、人間にとってのアメーバのような存在でしかない。 そして最後の地球人ジャン。彼がどう考えどう行動するか。物語としてうまくできている。 SFは昔から好きだけど、異世界の描写、そこに巻き込まれる人々の心理。考え尽くされているなと思った。 また、異世界の描写は、エヴァの人類補完計画と似ていた。この本が元になったんだろな。 偉大な作品。
0投稿日: 2025.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログSFの古典の名作ということで読み始めた。序盤からグイグイと本の世界に引き込まれていった。後半、難解で何度か読み返す場面に遭遇し、読み返しても??という場面に遭遇した。これをどう解釈するかで決着をつけた部分もあったりでこれが筆者の問いかけ、問題提議なのかとも解釈した。そして時間をおいてもう一度読み直してみたい。つまりそれほどこの本に引き込まれたということで星を一つ追加しました。 強大で圧倒的な力を持ったものから授かる自由と平和。争いと競争のない世界。戦いや争う本能を失うのに何年必要なのか。 今の日本を象徴しているようで恐ろしい。
0投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
三大SF作家による作品 かなり昔に読んだもののため内容はあまり覚えていないものの、面白かった、もう一度読みたいという記憶はある
0投稿日: 2025.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ”このままでいくと、近いうちに人間は、自分の人生を生きることをやめてしまうかもしれない。テレビのシリーズものに遅れないようについていくのが、一日がかりの仕事ということにもなりかねんのです!” なってるー!!!え、私たちってすでにオーバーロードの支配下にいるの? 誰にも支配されていないはずなのに、支配されているような生活を送っている現代人。オーバーロードに支配されている小説の中の世界より、現実の方がなんかホラーだなと思った。 人類は受動的なスポンジになってしまったのだろうか、私たちは一体誰の養分になるのだろう。
0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ(⌐■-■)宇宙人がサタンの容姿なのがちとキモイ。映像化するとチープになりそうだな。 ⊂|⊃ [ಠ_ಠ]まずまずおもしろくて読ませるけど、巻末あたりの情景描写の漢字が読めないな。
0投稿日: 2025.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
巨大宇宙船が地球に到来したことで、地球上の人々に変化が訪れる。本作は全部で三部構成となり、特に第三部の最後の世代については、人類はどのようにして終わるのかを想像したときに考えさせられる。地球規模を超えた壮大なストーリーが本作の特徴である。人類は現代に至るまでにさまざまな分野で高度化して、古代と比べると、より多くの人々が豊かさを享受できるようなった。以前なら苦労した出来事が現代なら、いとも簡単に得られるようになり、解決できるようになった。しかし本作のように地球を超越するような存在に接触して、平和という名目で地球そのものが管理されるようになると、人類は長期的に見てどうなるのか、とりわけ子供がいない世界になるとどんな末路を辿るのかは見物である。
0投稿日: 2024.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログSFに抱くアクション映画的なイメージとは裏腹に、哲学や宗教、政治について考えさせられる一冊です。 人が何に対して関心を抱き、何を恐れるのか。オーバーロードの統治を通じて人の本質を感じられました。
9投稿日: 2024.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
SFマガジンの「オールタイム・ベストSF」特集等で常に上位にランキングする不朽の名作。そして、積読10年という中々食指が伸びなかった作品でもある。結論から言えば、私にはこの面白さを十分理解出来なかった。 例えるなら、理路整然とした哲学書の読後感に似ている。作者は(きっと)すごい事書いているなぁと感心するも、再読したいなとは決して思わないような。 私にとっては、再読したいかどうかの目安が評価の肝となる。ハード・コアなSFファンからは評価が低すぎる、との怒りの声が聞こえて来そうだが、申し訳無いが仕方がない。 ちなみに、私のイチオシ本は、JPホーガンの三部作「ガニメデの優しい巨人」「星を継ぐもの」「巨人たちの星」です。これは今でも、老若男女が楽しめる最高のエンタメSFだと確信しています。
3投稿日: 2024.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ突如現れたエイリアンに管理されるようになった地球人たち、何故管理されるのかエイリアンたちは何の目的で動いているのか? エイリアンとの遭遇というよくあるところから、地球の終焉までを描く壮大な話だった 結末が近づくに連れて話の壮大さが見えてくるのは良かった
0投稿日: 2024.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログSF映画とか好きなので、本でも読んでみようかなーと思い、教養としてSF作品を紹介する雑誌を手に取ったところ、系譜の最初にこれがあったので(うろ覚え)読んでみました。 人名と関係性を覚えるのが苦手で途中期間が空いてしまいながらも、メモを書き書きなんとか1章読み終えて次行ったら序盤の人ら全然出てこなくなってズッコケました。だから貸してくれた同居人は「序盤そんなに真面目に覚えようとしなくていい」と言っていたのか…。 読んでいくうちに「あ、これは難しい政治の話ではなくて、未知の存在に対する人の好奇心を追いかけていけばいいのか」と思い、読むスピードは上がったのですが、能力目覚めた子どもの夢とか、ジャンがオーバーロードの星で見た内容とかは想像するのが難しくて(というか「この想像で合ってるかな?」と自信がなくて)時間がかかりました。壮大すぎて…。 80年後に帰ってきてジャンが見た地球の様子も気持ち悪くて面白かったです。 ディスりではなくて、この作品がなぜ名作と言われているのか、読んだだけではよくわかりませんでした。 あとがきのアーサー・C・クラークの生い立ちを読んだら、この人がガチ科学者でもあり、当時の科学的知見から書かれた何かしらの新しい発想がすごかったのかなと想像…無知ながら…。 これからもっと教養つけて、この作品のすごさを知ることができるといいなと思いました。
0投稿日: 2024.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログマイオールタイムベストSF 『オーバーロードのカレルレンの下、人類は管理され世界はより良く生まれ変わるのだが... はたして異星人の目的は?幼年期の人類はどこに向かうのか?』 「本当に人類は終わってしまった」と錯覚して読後3日間、虚脱状態を味わえましたw それぐらい尾を引く本でした。 SFが科学的なものだけでなく、霊的なものも範疇になると実感したのもこの本からでした。
33投稿日: 2024.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【2024年43冊目】 SF小説をよく読む友人に勧められて読みました。読了後に幾人かの感想を拝見しましたが「壮大すぎて理解できないのが良い」っておっしゃってる方がいて「わかる…」となりました。これは、時間を置いて再読かな。 あまりSFを読まないので、多分とんちんかんな感想ですが思ったことを。 オーバーロードという人類の更に上位の存在と共にあった物語が、更に上位のオーバーマインドという存在によって、更に在り方をコントロールされていたところ、もしかして、オーバーマインドの更に上位の存在もいます?その更に上位の更に…みたいな。現地球においては、人類が全ての種の頂点にいるような気がしてしまうけれど、あくまでそれは地球という括りの話だけ、かつ人類視点の発想なのかもしれない。 途中、不思議な力が目覚めていったところから、なんで?ってなってしまったんで、もう一回カレルレンの演説を読む必要がありそうだけど、それでもやっぱり理解するのは難しそう。→wikiで概略読みました。全てはオーバーマインドの掌の上だったのか…そうか…やっぱ壮大。 しかし、マジで壮大すぎて、壮大だった。「幼年期の終わり」というタイトルの秀逸さも。 咀嚼するのに時間かかってるんですけど、最初の方でストルムグレンを誘拐した人たちが、ポーカーやろうぜ!ってなってるの、余りにも人類の矮小さ(この物語の全体から見た時に)が現れてて一周まわって、最早可愛いと思いました。
0投稿日: 2024.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずとも知れたSFの古典小説。宇宙人が地球を暴力的に支配する作品はよく映画などで目にするが、これに登場するオーバーロードは、平和的かつ理性的に地球を統治する。しかし、実はオーバーロードにもさらに上位の種、オーバーマインドが存在しており、人類は彼らの一部になるために生まれ変わる運命にあったのだ。
0投稿日: 2024.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログSF好きを明言しながら未読なのもどうかと思い、意を決して読んでみましたが、これまで読んでいなかったことを大後悔…!ベストSFに上げる方が多いのも納得の大傑作でした。 オーバーロードという人類を超越する存在との接触を描く前半は、いわゆるファーストコンタクトものとして展開していきますが、後半、オーバーロードの目的が明かされてからは、物語の様相が一気に様変わりします。さらなる上位種の存在、個を消失し進化する人類、道を閉ざされながらも個としての未来を諦めないオーバーロード。これは悲劇なのか喜劇なのか。一言では言い表せない展開と結末に、読後、しばらく呆然としてしまいました。
8投稿日: 2023.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最高。読みたかったSF。人類とは広い宇宙のなかの地球に存在する一つの種族であるということ、時は過去から未来に流れて記憶を残していくということ、そういう常識が全く通用しない世界を見せられた。壮大すぎて理解できないのが良い。 ―種族的記憶――そうだ、そういったものがあるにちがいない。そしてその記憶は、なぜか時間とは無関係なのだ。そこでは、未来も過去も一つでしかない。だからこそ、すでに何千年、何万年かの昔、人類は畏怖と恐怖のもやを通してオーバーロードの歪んだイメージを見ていたのだ。
1投稿日: 2023.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスの作家「アーサー・C・クラーク」の長篇SF作品『幼年期の終り(原題:Childhood's End)』を読みました。 「アーサー・C・クラーク」の作品は2008年(平成20年)4月に読んだ『イルカの島』以来なので久しぶりですね、、、 ここのところSF作品が続いていますね。 -----story------------- 異星人の宇宙船が地球の主要都市上空に停滞してから五十年。 その間、異星人は人類にその姿を見せることなく、見事に地球管理を行なった。 だが、多くの謎があった。宇宙人の真の目的は? 人類の未来は?――巨匠が異星人とのファースト・コンタクトによって新たな道を歩みはじめる人類の姿を描きあげた傑作! ----------------------- 1952年(昭和27年)に発表された「アーサー・C・クラーク」の代表作で、SF史上の傑作として国際的に広く愛読されている作品、、、 いつかは読みたいと思っていたんですよねー ■プロローグ ■第一部 地球と上帝(オーバーロード)たちと ■第二部 黄金時代 ■第三部 最後の世代 ■解説 アーサー・C・クラーク――その人と作品―― 福島正実 宇宙進出を目前にした地球人類… だがある日、全世界の大都市上空に未知の大宇宙船団が降下してきた、、、 オーバーロードとばれる彼らは遠い星系から訪れた超知性体であり、人類とは比較にならない科学技術を備えた全能者だった… オーバーロードの総督「カレルレン」は国連事務総長「ストルムグレン」のみを交渉相手として人類を全面的に管理し、ついに地球に理想社会がもたらされたが……。 宇宙の大きな秩序のために百数十年間にわたって飼育され創造しない動物に成り下がってしまった人類の姿と変貌する地球の風景… そして、念動力のようなものが発現し、一切睡眠を取らなくなる子どもたちの出現、、、 進化した新たな知性の種により、地球人は変化し、旧来の地球人は自滅していく… 哲学的思索を交えて描いた作品でしたね。 SF市場の傑作として国際的に広く愛読されている作品ですが、壮大な人類進化の一大ヴィジョンがテーマとなっており、やや難しさを感じましたね… もう少し娯楽作品要素が強い方が好みかな。
0投稿日: 2023.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの方がマスターピースに挙げておられるのに頷けます。常套句ですが、不朽の名作と言えるでしょう。ソリッドな物語でした。とても良かった。私は好みから、ウェットな作品をどうしても楽しめないのですが、乾いていて、微温的な余地を排していて、とても主義に合いました。
1投稿日: 2023.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログいきなり地球外生命体と出会い、たちまち人類が精神的に支配されていく過程は、リアリティがありとても面白かった。 自分は「成長」という概念に疑問があるので、オーバーマインドなる人類よりも遥かに優れた存在が、成長を望んでいるのが、どこか信じられなかった。 個人の意識が溶け合って一つになるのは、どこか東洋思想っぽくて好きだった。 オーバーロードの住む惑星の描写がとても綺麗で、50年代に描かれたとは思えない。しかし、2020年代には高レベルのCGがあり、アバターのような映画も存在するので、感動が薄れてしまった。もっと前に読めたらよかった。
0投稿日: 2023.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類が娯楽にふけり、遊生夢死していたときが「黄金世代」と称されていたのを恐ろしく感じた。小人閑居して不善を為すとはまさにこのこと。 人類そのものの存在理由や運命を問いかける作品。作品としては文句なしだが、私の性には合っていなかった。「すばらしき新世界」を読んだ時は著者の物事についての思想が語られていて終始学びのある読書だったが、本書ではストーリー重視といった所だろうか。ただ、これは単に個人の好みであると感じている。 本書では地球の運命の一切をオーバーロードに委ねられている状態である。人自身の手で作られたユートピアと人以外によって作られたユートピアという点で他のSFとの違いを見出すことができる。人以外によって統治された地球はこのような悲惨、壮絶な最期を迎えるとなると、やはり人類の主人は人類でないといけないという結論になるのだろうか。
0投稿日: 2023.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読み終わってポカーンとしてしまった。空虚、おいてけぼり、消化不良、うまく言えないがそんな感じ。 圧倒的な科学力で人類を間接支配する「オーバーロード」は、人類にかつてない繁栄と平和をもたらしたが、あまりに圧倒的すぎる力の前に人類はハングリー精神を失う。オーバーロードの真の目的は後半まで明かされない。 真の目的が明かされたとき、「は?」と思った。圧倒的科学力を持つオーバーロードのさらに上位「オーバーマインド」がいて、科学力などではどうにもならない存在だという。 科学力が唯一の宗教となった人類というか我々にはまさに想像がつかない。科学だけでは進化の限界があり、オーバーロードは進化できない。オーバーロードはそれを知っている。だから人類のテレパシー的能力を観察する。 やがて今の人類と地球は消滅して、新たな「子ども」は目的なく個性なく地球上に漂う。 こんな展開というか設定があるのか。ハッピーエンドとかバッドエンドとかそういう話ではないな。前半のファーストコンタクトなエピソードはオマケに過ぎないな。 進化はの果てに何があるのか?進化は真の幸せをもたらすのか?目先のテクノロジー設定が巧みに隠されているおかげで古さを感じにくい普遍的物語になっていると思う。
0投稿日: 2023.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間の精神的な成長過程において所謂「大人になる」ということとはある種の自己中心の一側面、「自分は本当は特別(な人間)なのだ」という慢心からの脱却である…とするのであれば、本作はその普遍性を人類含む種族そのものにまで拡張し当て嵌め何重もの意味で「幼年期」としている(ようにみえる)のが非常に面白く思う。今でもそこに無視しきれないリアリティを感じるのはやはり著者の学びと洞察の賜物なのだろうか。
0投稿日: 2023.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ第65回アワヒニビブリオバトル「ミステリー」で紹介された本です。オンライン開催。 2020.06.07
0投稿日: 2022.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
オーバーロードと出会ったばかりの頃である第一部を読んでいる時が一番楽しかった。まだ幼年期であるこの世代の人々が最も私自身に近いからだと思う。共感しながら読めるのだ。 何が隠されているのだろうと恐れながら読んだが、科学を超えた力がその上に君臨しているなんて考えてもみなかった。たしかに努力ではどうにもならない世界だ。 地球人類の終わりもそうだが、オーバーロード達のこれまでとこれからのことを考えて絶望感に打ちひしがれた。本当に突然変異でもしない限り、流れを変えるのは難しいのだな。 結果的に、地球人類は自滅の期限を少し延ばしたというだけだった。宇宙規模で見れば。それがまた虚しくもある。 時代によって語り手が変わっていったが、最終的にはカレルレンの背中の哀愁が目に浮かぶようだった。最後の光を放つ星と、静かで深い宇宙のコントラストはきっと美しいだろう。
0投稿日: 2022.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ずっと前に読んだことがあるはずなんだけど、後半の展開はまったく覚えてなかった。そのおかげというかなんというか、衝撃の結末だった。人類の未来について書かれた作品は星の数ほどもあるけど、ユートピアとかディストピアとか、希望とか絶望とか、そんな物を超越した未来。種としては高次元の存在になったんだろうけど、それがいい事なのか私にはわからない。
0投稿日: 2022.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇宙人到来!「インディペンデンスデイ」ばりの衝撃!でも何もしない。宇宙船からじっっっ…と見てるだけ。という入りがまず不気味で一気に引き込まれる。「え…何しに来たん???」「どんな姿なん???」「つかどっから来たん???」という状態から何十年もかけて人類とコンタクトを取っていく。少しずつ少しずつオーバーロードの正体が分かっていったり、地球文明も宇宙人ことオーバーロードたちと関わっていくうちにいろんな発展を遂げていき、最後はとんでもない所まで話が進んでいくのでじわじわ面白くなっていくタイプの作品。言語化が難しいのだが、現在までSFだけに限らず色んな作品に影響を与えたらしく、発表当時はかなり画期的だったのではないかと思われる。正直、既視感がすごいけど「この作品だとこの展開に対するカウンターがあるな」とか「この作品はここをオマージュしたのかな」など他作品の考察もできてなかなか面白かった。では他作品と比べて元祖とも言える本作はというと、展開に対するド直球さが逆に全然わざとらしくなくてスッキリするし、文章がとっても詩的で美しい。一周回ってむしろ新鮮に思える。
0投稿日: 2022.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
クラークは20代の頃に何冊か読んだが、「幼年期の終わり」は今まで読まずじまいだった。人類の幼年期が終わる様子に結構な衝撃を受けた。でもきっとそうなんだろう。進化は福音であるのと同時に強烈な喪失感を伴うのだ。
0投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的存在である地球外知的生命体に支配された人類。その目的が分からないまま平和的な完全統治下に置かれて人類は無目的で安全な時代を迎える。そしてその時期を超えて更なる高次元の存在へと変態するために、まさに人類は幼年期の終わりを迎えていく。圧倒的なスケールと宇宙の情景、ハッピーエンドやバッドエンドを超越したラストシーンは圧巻だった。
0投稿日: 2022.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯読み終わって改めて考えると、いかにこの本が後世のSFやマンガなどに影響を与えたのかがよく分からる。当日書かれたということは革新的であり、今にしてみれば、まぁありそうな話し…と感じて、何が凄いのか分からないこと自体がすごいのかもしれない。 ◯現在のグローバル社会を維持するために必要なのが多様性の尊重だと思うが、その先ににあるものを飛躍させるとおそらくこの本に出てくる人類なのではないかと感じさせる。共感を発達させることによって、個人の境界が無くなり、溶け合っていくのかもしれない。
13投稿日: 2022.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
フロム・ソフトウェアのゲーム『Bloodborne』を友人に勧められたところ、どハマりしてしまい、同じく友人の紹介で、当ゲームの元ネタとなった本作を知った。 読み始めに想像していたよりも、ずっとファンタジックな展開となった。 科学を一種の宗教であると認めながらも、進んだ科学が全ての宗教を淘汰した世界を展開する前半に対して、後半では、霊的な方向性で人類が進化していく世界を展開していた。 後半の、あまりに超能力じみている展開をファンタジックと捉え、少々げんなりした気持ちになってしまった私は、すでに科学という名の宗教の虜になってしまっているのかもしれない。 オーバーロードと人類の違いの一つとして感情のあるなしが挙げられる。これは、感情が摩耗した種はオーバーロードのように進化が頭打ちになってしまうことを暗に示す筆者からの警句ではないかと思った。 話は変わるが、1974年に想定されていた進んだ技術や文化体系が、どういったものであったのかという視点で楽しむことができた。 昔の(特に半世紀ほど前の)SFで描かれた未来の様子と現在の様子がどれくらい乖離しているかを楽しむことができるのはSFの面白いところだと思う。 以下、Bloodborneとの関連で気づいたところ カレル文字のモデルはカレルレンではないだろうか。 赤子を失い、求めているという上位者たちは、進化の道を絶たれ、進化した人類の保護を目的としているオーバーロードたちを表現しているように思える。 オーバーロード≒上位者とすると、自然災害からジェフを救けたオーバーロードの構図は、赤子を守っていた(?)メルゴーの乳母の構図にそのまま当てはめることができる。 上位者に赤子を取られたトゥメルの女王ヤーナムは、オーバーロードにジェフを取られたジーンと同じ構図をしている。 ヤーナムの夜明けエンドで目を覚ました主人公は、地球に帰還してカレルレンから説明を受けたジャンが一人で地球上を生きる様子と似ている。 遺志を継ぐ者エンドでゲールマンに代わった主人公は、地球に残って星の終わりを見届けたジャンの様子と似ている。 幼年期のはじまりエンドで上位者となった主人公は、ジャンが地球を捨ててオーバーロードに着いていくことを選んだ可能性を示唆していると思う。 ↑の説が正しいとすれば『幼年期の”終り”』という作品に対して「幼年期の”はじまり”」というタイトルを付けることで、〖ジャン«Bloodborneの主人公»がこれから別の星«悪夢»で発生する種の進化«獣狩りの夜»をオーバーロード«上位者»として見届ける〗という構図を示唆しているのではないかと思う。 赤子を倒して入手する「3本目のへそのお」を使用して月の魔物(上位者)と戦闘することになるのは、ジェフをはじめとした子供を死なせてしまうとオーバーロードと対立することになっていたかもしれない可能性を示唆しているのではないかと思う。
3投稿日: 2022.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ息子に勧められ、初SF。 この作品とんでもない昔に書かれたはずなのに、、この発想、設定が凄すぎる。 私の世界観、価値観、少し変わったかも。 良い意味で。 読後感想書かずいた所、、MARVEL映画にハマりマイティ・ソーを見ていたら登場人物の女性が、アーサー・C・クラークが、、、て言うてた。 ので、改めて覚え書き程度の感想(˙꒳˙ก̀)
3投稿日: 2022.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初読(創元推理文庫版だった)は小学生(中学に上がった頃?)だった筈なので、約50年ぶりの再読。 当時は、作品中に提示されるビジュアル描写に圧倒されてばかりで、作中にちりばめられた諦念や悲哀までは理解できなかったように記憶する。 生物の進化とはすばらしいことだと今でも思ってはいるが、進化の過程から取り残された存在(それが地球人であれ宇宙人であれ)の観念がもの悲しい。 グレッグ・ベアの“ブラッド・ミュージック”と読み比べてみたい。
2投稿日: 2021.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログカレルレンが主人公って書いてあるあらすじもあったけど、個人的にはいくつかの視点で見つつも人類全体が主人公なのかなと。 人類の進化?を題材にするという読んだことないタイプのSFで、なるほどこういうのもあるのかあと思った。 ビジュアルを表現する文が多いけど、古めの訳語調なのが少し引っかかるところ。
0投稿日: 2021.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ初読み英SF作家アーサー.C.クラーク1952年S27刊行。 エイリアンの巨大船団が主要都市上空に現れて世界の支配を開始する。彼らの目的は?人類の未来は? 難解映画「2001年宇宙の旅」原作者だけあって、本作も理解するのになかなか難しい哲学的な作品でしたが、神がテーマなのかも。
0投稿日: 2021.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は伏線。後半一気に結末へ。現代の国家間の覇権争いが小事に感じます。SFらしいSFはほぼ初めてでしたが、世界が広がりました。
0投稿日: 2021.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
題名が秀逸。このタイトルじゃなければ意味が分からなかった。 人間の肉体(または肉体があるという錯覚)を捨てて、より高次のものへと進化する。 解脱する。 神と一体になる。 SFというよりは宗教なので、合わない人には合わないだろう。 人類は何処に向かうのか。 人類の終焉はどうなるのか。 現実には幼年期を卒業すれば、お迎えではなく、より良き未来が築けるのだろう。 けれども温暖化やら争乱やら差別やら、人類はいつまでたってもどうしようもない。 幼年期を脱するのはいつになるのか。。。
0投稿日: 2021.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的な色彩感と、神秘的で幸福と寂しさに包まれた世界観とに没頭して中々ページを捲れなかった。美術館で気付いたら2時間近く経ってた様な感覚。 古い作品ですが古くささは感じず読みやすい。SFの原典の一つ。
0投稿日: 2021.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログSF小説を初めて読んだのですが、とても考えさせられる作品だった。 進化は良いことだと思っていたが、本当に進化することが全て良いことなのか、私たちが今暮らしやすい世の中になるように進めている“進化”は私たちに楽園をもたらしてくれるのだろうか。
0投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題 CHILDHOOD’S END 幼年期、に違和感を感じる。 人類は、始まりから終わりまで、救いようがない。 知的生命体との接触は、管理されることでしかなく、終わりは更なる上位の存在による吸収。 オーバーロードの存在意義は面白いけど、オーバーマインドは次元が違い過ぎてうまく想像できない。まあ、アメーバが人類を想像するということなんだよね…。
0投稿日: 2020.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
いやー、凄かった。 中盤以降の怒涛の展開に、後半の章は、ほとんど一気読み。震えたー! これはSFなのかな?1979年刊行とのこと。 予言書のようでもあるな。 人類は科学が万能であり、 人類は無敵かもしれない、と勘違いをしているようで、宇宙人やUFOはバカげた都市伝説だと笑う人々は、いったい宇宙の何を知っているのだろうか? カレルレンの言葉が全てを表してる。 「星々は、人類のものではない」 ワンネスとは物理次元の自我にとっての恐怖なのか。なるほど!だから死が怖いのね。 自我の消滅と自我の抵抗。 アセンションと統合。 オーバーロードたちの行きつくさきは…どこなのかな…
0投稿日: 2020.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類より遥かに進んだテクノロジーを持った宇宙人オーバーロードが地球に訪れ、人類の進むべき未来を導いていく。 地球にユートピアを築き上げたオーバーロードだったが、ラストで明かされる真の目的と人類を待ち受ける運命は…。 進化が必ずしも喜ぶべきものではない、ということなのだろうか。
0投稿日: 2020.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ地球に圧倒的な知力技術力を持つ異星人が突然やってきた、しかし彼らは統治することはせずただ上から地球人を眺めて存在を誇示するだけ。圧倒的科学力の前に、宗教が無くなり戦争が無くなり、そして進歩する気持もなくなる。50年経ってようやく異星人は姿を地球人に見せた。さらに80年経って異星人の故郷と超高速移動したただ1人の地球人が戻ってきたときに地球は様変わりしていた。いったい何のために異星人は地球にやってきたのか?設定が非常に哲学的でSFの傑作であることは間違いないし、第1部だけでも映画化してほしい
0投稿日: 2020.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳が悪いのか? 手こずった本。訳が堅すぎるためかよくわからないまま終わった。文中の「それが」「彼らが」は何をさしているのかはっきりしないことが多い。
0投稿日: 2019.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログSFの二文字がサイエンス・フィクションの略語である、という当たり前の事実をあらためて、それも強烈に再認識させられた気がする。科学的な知見から描かれた物語の規模、テーマの壮大さがずば抜けていて、説得力に殴られている感覚が終始あった。「終わり」を書いた話って多分この世にごまんを越えてありふれているんだろうけれども、自分が知る限り最も納得のいく形で最期を迎えている作品だった。 ……なんて事を書いたあとにこんなこと言うのもなんだけど、やはりSFは決して自分の好みのジャンルではないのだなと……笑 なんだろう、内容自体への興味は決してないわけじゃないんだけど、翻訳として表現された日本語の雰囲気がそもそも肌に合わないのか、ただひたすらに淡々と綴られていく文体が苦手なのか……自分は人の感情が動いていくストーリーが好きなので、地球という星や人類、宇宙という万象にフォーカスされていると感情移入のしどころがなくて困ってしまうのかもしれない。仕事で疲れていたのもあるんだろうけど、寝る前に読み進めていて何度も寝落ちしてしまった。修行が足りない。知性も足りない。
0投稿日: 2019.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
突如人類の前に飛来した巨大なUFOにより、人類の歴史は一変した。上帝《オーバーロード》と呼ばれる彼らにより、地球上の戦争や飢餓は去り、人類は栄光と繁栄の道を歩みだしたかのように見えたが……。 古典名作のSFだが、今読んでも色褪せておらず、SF初心者が読んでも分かりやすい筋書きとなっている。苛烈な宇宙競争の果てに訪れた、突然のファーストコンタクトという開幕から、第一部は主に人類を管理するオーバーロードの正体とその目的に焦点を合わせているため、読者の気になる部分とストーリー進行上の謎が噛み合わさっているため、ぐいぐいと物語に引き込まれていく。人類が嫌悪感を覚えるような異形異様の姿だから隠している説や、実は人類と同じヒューマノイド型のエイリアンだからという説など、隠された謎に対する議論の数々はオーバーロードの正体に対するハードルを無尽蔵に上げていくが、第一部の最後で明らかになったオーバーロードの正体=悪魔というのには、あれだけハードルを上げていたのに想像に至らず、驚いてしまった。エイリアンの造形が神話や伝説上の姿であることから、はるか古代にも訪れていた可能性を出しつつ、一発でイメージ喚起させる上手い造形である。また正体という美味しいネタを最後まで隠さず、序盤の段階で切ってきたのは素晴らしい。第二部は黄金時代の名の通り、オーバーロードによって変革した人間社会、所謂ユートピアを描いているわけだが、こういう架空の革新的な出来事による未来社会の予想図はいつ読んでもワクワクする。そしてオーバーロードの目的に対する若干の懸念と、冒険を求めて密航とする若者という小さなエピソード、いずれ夫婦になる二人という市民の視点を挟みつつ、物語は終局へと移行する。オーバーロードの支配、それに対する抵抗というには、あまりにも文明力に差がありすぎるため、それは無いと思っていたが、明かされた真実、オーバーロードより上位のオーバーマインドという存在の判明は、一気に絶望と諦観をもたらせてしまう。それはもう人類に分かるレベルの支配とか搾取ではなく、摂理にも似た、圧倒的な矮小さの現れである。宇宙は人類のためにあるのではないという、ごく普遍的な真実はひどく残酷にも映るが、旧人類の繁栄と滅亡という、壮大なテーマの前には塵芥に等しい感情だろう。知的生命体が一段上の進化をするという、壮大なスケールの物語を一冊にまとめた驚異的かつ、アメイジングなSFである。
2投稿日: 2019.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳:福島正実、原書名:Childhood's End(Clarke,Arthur C.) プロローグ◆地球と上帝(オーバーロード)たち◆黄金時代◆最後の時代
0投稿日: 2019.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログどこかの書評で読んだけど、前半の俗っぽい感じと後半の突き抜けた感じの差が結構激しいかも? 前半は昭和28年に書かれたということを考慮するべきだろうけど、後半は今でも十分問題ないのはさすが。 1990年代に前半部を書き換えたバージョンもあるらしいけど、それでも後半は完全にそのまま使えてるはず。 オーバーロードの姿、というのはキリスト教世界を念頭に置いた一発ネタ、と思いきや、一応最後に説明してるのもさすが。
0投稿日: 2019.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人間が30兆個の細胞から一個体を構成していて、それぞれの細胞の生き死ににはこだわらない所が、人類の次のステージと重なった所が感慨深かった。人類の意識が集合して統合するのは一個人にとっては恐ろしい。一個体として意識を持ち、文明を発展させていくオーバーロード達の方が幸せだと感じる。
0投稿日: 2018.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・千夜千冊でチラ見して、そんなにすごかったっけ?再読してみたいと。 【期待したもの】 ・ 【要約】 ・ 【ノート】 ・ある意味、サイキックなエスパーオチかいという気がしないでもないが、壮大。クラークだから、もっと人類賛歌的な感動があるかと思ったが、そうではなく、ホモ・サピエンスの終焉が描かれている(でも人類の終焉ではない)。 ・幾世代にもわたる叙事詩であるため、壮大感はある。しかし、ゼノギアスのカレルレンって、本書が出典だったんやな。 ・富野監督がガンダムで2001年宇宙の旅を超えると豪語し、高千穂遙に、その前にSFちゃいますやんと論破されたのは有名な話だが、本書におけるホモ・サピエンスの覚醒はニュータイプというコンセプトに影響を与えているんじゃないかなあ。 ・正剛さん大絶賛だが、自分的には、壮大だけど、でもちょっと...というのが正直なところ。 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
情感溢れる文章と科学や機械に対する作者の造形の深さが伺える描写。読み終わってからも、私の行動がクラークの美しい文章であらわせるんじゃないかと思ってしまう。それほど世界に没入してしまった。 一読してこの本の全てを分かったとは思えない。伝えたい事、裏側を読み取れてはいない。まるでそれは人類がオーバーロードの真意を、オーバーロードがオーバーマインドの真意を読み解けていないように。 今作では宇宙人が来たらどうなるかということより、恵まれた争いのない豊かな世界で人々はどのような暮らしをするのかが面白かった。 オーバーロードは差別や貧困をなくした。アフリカでは人種差別が甚だしかったのだが、総督はアパルトヘイト政策をやめなさいと警告をし、従わなかった政府が何もしないでいると、太陽がケープタウンで子午線を通過する30分の間、太陽を消してしまった。これにより差別はなくなった。 闘牛をなくしたときは、闘牛師の槍が牛に刺さった時の痛みを、見ている人全てに一瞬だけ味あわせた。これだけで闘牛は地球から姿を消して、政府は新たな国技にクリケットでもしようかと提案した。 オーバーロードの艦艇はロケットを撃ってもかすり傷もつかない。そこしれぬ恐怖に国達は慄き、言いつけ通りに戦争はなくなった。 富は倍増して、犯罪も争いもなくなったが、文化は今まで人類が経て来たどの年代よりも上にはならなかった。人々は文化の火種を絶やさずに大きくするために、芸術家だけのコミュニティーのニューアテネを作り出した。 その後に、世界中の子供達に特殊な能力が出て、オーバーロードの目的が明かされる。オーバーロードはオーバーマインドの指図で動いていたこともわかる。オーバーロードは人間の超常現象を理解できずに、その力が進化すると宇宙に対して良くないことが起きることを知っていたので、地球にきて阻止した。人類は自らの力で破滅を阻止する方法を知る事は出来ない。 オーバーロードはもう成長はできない。地球人はその新しい能力で最後の成長を手にして、遊びで自分たちの故郷である地球を消す。 私はクラークの地球に対する扱いに対してまだ理解していない。ちっぽけな物として書いたのか、それとも重要だが代替可能な物か。化学、文化、人間、意識。この中でクラークが最後に残したのは、意識か。だがそれは認識できるものではない。そんなものはロボットと変わらない。 やはり分からない。でもいつか分かるようになる。この本はそう思わせた。
0投稿日: 2018.10.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「2001年」にもつながるテーマだが、こちらのほうが詩情的。「ノーライフキング」の元ネタになっているような気もする。さよなら人類。
0投稿日: 2018.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログSFの古典的傑作。ある時高度な知能を持った異星人が地球にやってくる。侵略や居住のためではなくそれはある目的をもっての人間社会の観察のためだった。 実際に惑星間を移動することのできるようなテクノロジーを持った異星人が現代の地球人を見れば非常に下等な種族であると認識するだろうし、それを支配したいとか侵略しようという意識は持たないだろう。たとえば、人間が蟻やミジンコを支配したり、奴隷にしようと思わないように。 最終的には人類と地球の終焉まで描かれているのだが、1970年代にここまで未来を描写できたアーサー・C・クラークのこの小説は今読んでも全く色あせることがない。驚異的な傑作。
0投稿日: 2018.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類よりも高度な存在である宇宙人が突然やってきて、いい感じに管理してくれる話。国連としては宇宙人に従う道を選んだが、一部の人たちは「人類のことは人類がなんとかするべきだ」と反発する。 快適な生活を提供してくれるのであれば、それが人類であることにこだわる必要は無いのでは。今も俺がGoogleやAmazonを使っているのはそれが人類が開発したものだからではなくて、単純に便利だからである。しかも俺の頑張りとは関係なく作られている。すでにオーバーロードの下で暮らしいているのではないだろうか。
0投稿日: 2018.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログずいぶん昔に読んだので覚えていない。オーバーロードさんがなんやら感やら。アニメのタイトルではないよ!
1投稿日: 2018.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログまぁ普通。 東洋でのパウチカムイ(アイヌの精霊 姦淫と文化の啓蒙を司る)とかは無視してもいいとして、観音様が分かるんならほかにゐるだらう と言ふのがある。 そのオーヴァーロードの人は、空を飛ぶ。うむうむ。 あと悪魔の属性で、「笑いを司る」と言ふのがあったが、オーヴァーロードの方はさう言ふのの、ちゃんと笑ふ所で笑ってるといふ描写がある他、・・・「漫画映画」に興味を持ってゐる。えー。 ラストは感動した。
0投稿日: 2018.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ初クラーク。これは凄いッ!!何とも言えない結末。ただでさえ無い生きる気力が更に失われていくよう、嗚呼…。人類の未来は本当にこうなるかも知れないと思わせるリアリティは“圧巻”の一言。
0投稿日: 2017.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ名作だと言われていたので手を出した作品。 オーバーロードの正体は驚いたものの、それを上回る驚きをもたらした圧巻のラストに胸打たれ、その壮大さに映像化作品を見てみたいと思ったものでした(ドラマ化されたようで見てみたいと思います)。
0投稿日: 2017.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に内容が濃い感じ。 夢中で読み進める章もあれば、なかなか頭に入ってこない章も。 あまり読書の時間をとれず、細切れに読んだせいかな? 時間をおいて、じっくりと再読したい。
0投稿日: 2016.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ1953年発表、アーサー・C・クラーク著。平和裏に地球人を管理する、宇宙人「オーバーロード」。彼らの目的が見えない中、人類に異変が起こり始め、ついに真の目的が明かされる。 名作と呼ばれているのは分かる気がした。 まず政治的、社会的な描写がかなり詳しく書いてあった。そういう基板をしっかり構築してこそ、後半の急展開が強調される気がする。人間の争いなど宇宙レベルでは些細なものだったと思い知る、というわけだ。 それにともなって少し気になったのは、前半の、理性によって人類が宗教を捨てて平和になる、暴力衝動を制御できる、といった科学楽観主義的な部分だ。昔のSFによく見られる傾向だから、これはしかたないのかもしれない。 文章としては、詩的表現が巧い。海の描写はきれいだし、自然に関しての哲学的な解釈も見られる。特にどんどんスケールアップしていくストーリーの後半部分、星レベルでの描写などはなかなかに圧巻される。 ストーリー的には、正直一度は誰でも考えるような話ではあるだろうし、特に今だったら似たような話はごまんとあるだろう。ただ、ラストのなんとも言えないバッドエンド(とも言い切れないが)は新鮮だった。こういう展開になったらもう少し明るいエンドを迎えるのかと思ったが、全く違った。こんな形での人類滅亡もありうるのかと思わせてくれる。 「Childhood's End」、「幼年期の終り」。読後、このすばらしい題名自体がとてもしんみりくる。 どこかのレヴューで旧約聖書のヨブ記がベースにあるのではないか、と書かれているのを見た。なるほど、確かに本小説はそういう懐の深さ(解けない謎)を持っている。
0投稿日: 2016.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類よりはるかに知性の優れた宇宙人と接することで、自分たちの驕り、プライドというものを認識していく。そういう意味で宇宙と人間の関わりがよく分かる本であった。そしてSF小説ならではのサイエンスも多く含まれている。相対性原理、脈動変光星、重力場、重力波。。。特に最後の方は優しい気持ちにさせてくれる本だ。ほかの惑星にどのような宇宙人がいるのか期待の持てる結末だった。
0投稿日: 2016.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ1952年に出版されたのだから、65年前の作品。流石に情景描写など古臭い。ひねりの効いた人類絶滅テーマの傑作。全き絶滅では無いのだが、人類史の終焉と言う意味では同じで、却って哀しい。
0投稿日: 2016.03.11種の終焉
地球に突如として現れた宇宙船。中の宇宙人は地球人に対して敵意はないが、姿を見せない。 圧倒的な科学力で人類に対し、世界統一を指示する。そして、様々な技術を与える。人類は生活に困らない状態で幸福な暮らしを送る。 しかし、宇宙人は姿を見せない。見せるのは50年後だと言うのである。果たして彼らの目的は何なのか? 星には必ず燃え尽き、終わるときが来る。そして、そこに暮らす生き物も、種として終焉を迎えるのだ。 それぞれの人がどのような状態で、そして精神状態でそれを迎えるのかを描いた一冊。
0投稿日: 2016.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間は神から生まれたのではなく、自然発生的に生まれ、その終焉において、神の管理により秩序を与えられるのでは無いだろうか。この小説を読んでいて、そのように感じた。確かに、民族紛争を解決できず、不満なく安全に共存するメカニズムの形成において、我々は未熟だ。野蛮人、未開人とすら言えるのかもしれない。しかし、同じ程度の力を持ち利害対立した個人や組織が、その解決に労力を使い、人類全体、いやもっと小規模な人間関係において、非生産的な行動を取る図式に陥るのは、種の存続においては仕方の無い事である。我々は常に、優秀さを競い、そしてそれを振るいより多くのカロリーを得なければならぬのだから。 そこで、この解決に必要なのが、別の上位種族による、導きなのである。物語における、上空に留まる宇宙船が象徴的だ。異次元の存在により、ようやく我々は争いをやめる事ができるのである。 文句無しに面白い。しかし、私はこの話の夢を見た。読み始めて、そのまま寝てしまったのだ。こんな事は初めてだった。そして、物語の象徴的なシーンを浮かべ、示唆的な恐怖に囚われてしまった。
1投稿日: 2016.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ初クラークSF。読み応えがあり、筋が良く練られていてそして予想もつかぬ展開と結末。さすが。 不気味な予感に続きが読みたくて仕方なくなります。そしてこんな結末だとは。 人類とは、知性とは、宇宙とは……
0投稿日: 2016.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログどんでん返しっぽいけど、アーサーCクラークってこのパターンがおおい。思考実験としての側面は面白いと思う
0投稿日: 2015.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「オーバーロード」と「オーバーマインド」 今の人類はどちらに向かっている? どちらもやってくるかも!? 約30年経った今でも新鮮な作品です
0投稿日: 2015.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ50年以上前に書かれた作品だけど、まさにSF史に残る傑作。さすがに訳文がいささか古臭く感じるけど、当時、この内容の作品が書かれたことに驚く。ありきたりなSFにありがちの表面だけ賑やかな小説とちがって、こちらは哲学的でさえある。明らかにこの小説に影響を受けた小説やハリウッド映画も見受けられるし、後世に残した足跡は大きいと思う。 ・プロローグ ・地球と上帝たち ・黄金時代 ・最後の世代 の四部からなる構成で、それぞれの章で少しずつ時代が進んでる。その時代の中で生きる人々の生活や思想なども上手く描かれていて、なるほどなぁ、と思う記述も多々あり、作者クラークの深い洞察力に驚かされた。 ラストはハッピーエンドと言えるのか、言えないのか・・・微妙なところだけど、宇宙の未来、宇宙を動かしている神?(のような存在)に想いを巡らせてしまうような余韻の残り方。まさに哲学的な内容。 ☆4個(訳文が良ければ5個) いわゆるハードSFに分類される小説だと思うけど、読書慣れ(SF慣れ)してない人がいきなり読むと、けっこう辛いかも・・・。自分も高校時代に友達に薦められて読み始めたけど、第一部・地球と上帝たちの章で投げ出してしまった。 今回、読了することが出来て満足。 背表紙~ 人類が宇宙に進出したその日、巨大宇宙船団が地球の空を覆った。やがて人々の頭の中に一つの言葉がこだまする-人類はもはや孤独ではない。それから50年、人類より遥かに高度の知能と技術を有するエイリアンは、その姿を現すことなく、平和裡に地球管理を行っていた。彼らの真の目的は?宇宙知性との遭遇によって新たな道を歩みだす人類の姿を、巨匠が詩情豊かに描きあげたSF史上屈指の名作。
0投稿日: 2015.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ1953年に初版と知ってビックリ。有名な古典SFの名作でもある。地球に宇宙人が来て全ての面において高度な文明進化させる話だが実は目的があり…派手なアクション系はなく、淡々と進む物語。そして刹那的な寂しいラスト。今読んでも古臭さは感じない。
0投稿日: 2015.08.30異星人とは仲良くなれないですよね?
2001年宇宙の旅より以前に書かれた本作は彼の代表作だと言われていますが、 今は亡きアーサー・C・クラークさんでさえ想像もできない程の 地球外生命体は存在しているわけだし、UFOが世界の大都市の 上空に現れて、姿を見せずに人類を支配するようになったという話は SFドラマのVみたいな設定ですよね。異星人にとって我々はどんな存在なのでしょうか? 人類の歴史の中では異星人は様々な形でコンタクトしてきました。 彼らの存在なくして現在の我々の文明も発展しなかったのかもしれません。 同じ地球人同士でさえ、仲が悪くて戦争しているのに、 別な星からの訪問を受けたとしても彼らと仲良くなれる段階にまで、 まだ人類は進化していないような気がします。この小説に書かれているような 事態はもう現実に起こっている可能性もあります。もうすでに我々の文明は 彼らに支配されてしまってるかもしれませんね。怖いです・・・・。
2投稿日: 2015.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類が国家の威信をかけ宇宙進出を競う話、、のような出だしから 突如圧倒的科学力の宇宙人がやってきて地球を管理し始める。 地球から争い事は減り、生活も豊かになって行くが彼らの目的が分からない… その謎が一つの大きなテーマです。 加えて、ユートピアで暮らす人々の思考や地球を飛び出そうとす青年のる冒険劇 要素もあります。 人類、というか生命の進化の方向性を描いていますが、今読んでも納得感がありさすがクラークという印象。
0投稿日: 2015.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ分けられた3章により,読者の視点は当事者,一歩引いた第三者,そして世界を俯瞰した神,と移りゆき,最後にカタストロフに導かれる.成熟した幼児性を,手を変え品を変え提示され,自らの足下を見,恥じ入るばかり.
0投稿日: 2015.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた巨匠の名作。50年代に書かれたものとは思えない斬新な着想と、圧倒的なスケール。ファンタジーではない本格SFは、いつまでも色褪せることがありません。
0投稿日: 2015.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最初はファーストコンタクトものかと思った。オーバーロードは地球の都市上空に宇宙船をとどまらせるだけだった。その後、いつ本性をあらわすのかと考えているうちに、オーバーロードは地球人をペットか家畜のように考えているのではと感じた。しかし、ようやく姿を表したオーバーロードは、地球人の想像する悪魔そのものの見た目だった。それでも彼らは地球人と友好関係を結び、世界から戦争や差別、飢えなどをなくしていった。 物語の結末はさらに意外なもので、オーバーロードをも支配するオーバーマインドの存在が明らかになり、人類の子供たちはすべて彼らの一部となった。地球から子供がいなくなり、人類は滅亡に向かう。宇宙船に忍び込んでオーバーロードの母星に向かったジャン・ロドリックスは、最後の人類として地球に帰ってきた。そこで彼は人類だけでなく、地球そのものの終末を見て、地球とともに消滅した。
0投稿日: 2015.06.16人とは何なのか?物質から精神へ!
アーサー・C・クラークの気になる1冊でした。タイトルに興味があったのですが、難しそうでなかなか読む気になれませんでした。そしてやはり難しい内容でした。人の未来は物質から精神に昇華して最終的には宇宙と一体化することを思わせる内容です。読後、まだ自分の中に入ってきていません。奥深い内容なので何回か読むと小説の中に入っていけるように思えました。
1投稿日: 2015.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログさすが!の一言。巻頭の圧巻のシーンにはひさびさに背筋をぞくぞくさせられた。ラストも壮大かつ広大。やっぱりクラークが大好きだ!
0投稿日: 2015.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルが有名。SFのなかでも特に想像力豊かで壮大な話。「幼年期の終わり」が意味することが予想外。人類は次の段階に進んだということなのか、それとも終わったということなのか。捉え方によって異なるが、ハッピーエンドでないことは確か。オーバーロードの存在が段々明らかになり、最初と最後で印象が逆転するのがうまくできている。
0投稿日: 2015.02.191953年発表の名作。これをいまだ幼年期の我々はどう読むか?
私は今回初めて読んだのですが、あまりにも有名な作品でこれまで様々な人達が論評してきていますので、今更何も言うことはありません。ただ、このReader Storeの書籍説明では内容がよくわからないかもしれませんので、少々その説明をします。 ストーリーは、大きく3つに分かれています。まず、第一部、宇宙開発競争華やかなりし時代、今まさに人類が宇宙へ飛び出そうというタイミングで、地球に宇宙人がやって来ます。彼らの目的は不明なのですが、強大な科学力を持っており、地球を支配することになります。その結果、国家機能は意味をなさない物になりますが、その支配の方法は、統治すれども干渉せずといったものであり、窓口は国連の事務総長のみ。そして、その事務総長にさえ姿を見せませんが、50年後には姿を現すと断言します。一方、国が解体したことにより、地球上から戦争という物がなくなります。ある意味、人類の夢が叶ったわけです。 第2部では、その統治が第2段階になったのか、宇宙人は約束通り姿を見せます。地球人はそれを戸惑いながらも受け入れて平和に暮らすわけですが、当然、それに反発する人や、かの宇宙人の真の意図を知りたいと思う人も出てきます。で、ついにある人が、その宇宙人の母星への密航を企てます。 第3部では、地球人らしさを復活させよう、という人達がコミュニティーを作ったりするのですが、密航した人も80年後の地球に戻ってきます。そして、いよいよ事の真相が暴かれていく、というストーリーです。 なんせ宇宙人が地球上空に現れてから、物語の終焉まで100年以上の時の流れを描いた作品ですので、長編であることもさることながら、登場人物の数も多い。しかも当然名前はカタカナですので、読むのは骨が折れます。でも、そんなことは別として、色々考えさせる名作であり、傑作であります。 アーサー・C・クラークは、なぜこのようなストーリーを、米ソ冷戦時代の1950年代に書こうとしたのでしょうか?またその時は、人知を超える強大な科学力を持つ宇宙人が物語のように現れたら、地球上から戦争がなくなると考えていたのでしょうか?多分に欧米的発想だなと今なら思います。 昨今の世界情勢を見ると、別の意味で国は解体し、また、別の意味での戦争が起こっています。世界には飢えた子供達がひしめき、この瞬間にもその命を落とし、格差は広がるばかり。今、アーサー・C・クラークが生きていたら、どんなSF小説を書いて世に問うのでしょうか。
7投稿日: 2015.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログクラークのファースト・コンタクトもの 表紙 7点中西 信行 展開 7点1953年著作 文章 7点 内容 700点 合計 721点
0投稿日: 2015.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ全てのSFのはじまり、元になっていると言われている本。 発行ねんから考えると凄い。 今読んでも色あせない。 音楽も映画も本も本物は沸る。
0投稿日: 2015.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログSFの古典的名作。 卓越した技術を持った宇宙人が半ば地球を植民地のようにすることで、地球人同士の殺し合いを止め、宇宙連合みたいなの一員として参加出来るように技術的・精神的に育てていく話かと想像しながら読んでいたら、上の上くらいをいかれた印象。 作内でめっちゃ時間経過するので、人類側の主要人物はめまぐるしく入れ替わっていく一方で、オーバーロード側は総督が変わらずに存在するというのも種族の対比で面白い。
0投稿日: 2014.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログやっぱり古典と呼ばれるものはそれなりのすごさがある。最近似たテーマのにあたることがしばしばあったけど、それぞれ面白くてよい
0投稿日: 2014.09.24追加で一票
良いレビューが既にたくさん書かれているいるので書き足すことはありませんが、強くお勧めということで星5つ。
0投稿日: 2014.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログある日突然世界中の主要な都市の上空に現れた巨大な飛行物体。そして宇宙人の代表であるカレルランは、人類が全く及ばない科学力と知略を持っており、人類を瞬く間に管理下に置き…… SF史上屈指の名作と呼ばれる作品ですが、作品からあふれ出る想像力や、全人類のその後を描くスケールの大きさというものはまさにそれを感じさせるものでした。人類は何のために生まれてきたのか? そしてどこに向かっていくのか? そんな壮大な問いを投げかけてくる作品です。 前半から中盤にかけてはカレルランの目的が全く見えず話全体がまどろっこしい雰囲気だったのですが、三章からの流れは圧巻! 中でも印象的だったのがラストシーンです。その描写の美しさとカレカランの目的が分かってからの複雑な気分も相まって、読後感は絶望と希望とがいっしょくたになった、表現するのが難しい感情を持ちました。 この未来予想は希望なのかそれとも絶望なのか、それは人間としてこの本を読むのか、人類としてこの本を読むのかで変わってくるのだろうな、と思いました。
1投稿日: 2014.07.041これは
これは、最高ね! 読みなよ最高な本だね、はまる事間違いないわよ、ベストね
0投稿日: 2014.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
SFが、まだ解明されていない最後の未知の領域に踏み込むと、霊的な事象だとか神に触れずにはいられないのだろうと思った。 頂点に1つの大いなる存在が君臨=やはり一神教?
0投稿日: 2014.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
僕の想像した最強の世界征服がここに存在したと言う衝撃作。 まあ、と言うか、そう言う話は誰でも思いつくのであったかと言う話だったわけですけど。 当然、想像だけでぐるぐる回る世界ではないのでちゃんと結末も来るわけですけど、後半の話は正直それほど好きではないんだけど、中盤までが僕好み過ぎてうっとり。 名作と呼ばれるものに触れるのも良いなあと今更思ったり。
0投稿日: 2014.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇宙人の来訪と彼らによる世界統治を主とする序盤はイマイチぱっとせず牽引力を感じなかったのだが、終盤の流れは圧巻。 SFはどちらかというと人類にとって希望的な描写が多いと思うのだが、この作品で描かれたのが果たしてどちらだったのか。 人類の進化の果てについて面白い見解を示していると思う。
0投稿日: 2014.02.04SFファンならマストアイテム
SFと言えば当時ハミルトンやスミスのスペースオペラやハイラインやアシモフのエンターテイメントものが主流でクラークは少し敷居が高かった(私見)。ですがリバイバル上演していた「2001年宇宙の旅」を観て書店でクラークを一冊読んでみるかと手に取ったのが本書。読み終わって最初に思ったのがすごいものを読んでしまったという興奮と作品内容自体を消化し切れていないという焦燥感。SFを読んでいたのにいつの間にか哲学的なものを読んでしまったというモヤモヤ感。それは再読しても思ったのですが「人間はどこへいくのか?」という普遍的なテーマと物語の後半の観念的展開と相まってそうおもったのだと思う。今まで読んできたSFの未来像の類型とは離れた結末にショックを受けたのと同時にSFの懐の深さを改めて実感させてもらった傑作SF。 人類進化やオーバーロードなどの設定は今や当たり前の様に世の中には溢れ返っていますが、この作品から始まったのだと考えると感慨深い。どことなく哀惜のある終わり方も好きでオーバーロードのカレルレンが選ばれなかった悔しさと観察者として矜持を思う最後のシーンがすばらしい。SFファンならマストアイテムでしょう。 ※「幼年期の終り」と聞くと事務総長ストルムグレンの墓の前に佇むカレルレンの姿が思い浮かぶ。小説にはないシーンですがね。
27投稿日: 2013.11.24
