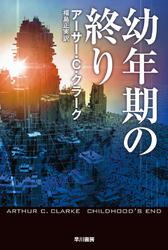
総合評価
(175件)| 65 | ||
| 56 | ||
| 30 | ||
| 5 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類が次の何かに進化する、そんな印象をまず読む前にもってた。読みながら、やっぱりそんな感じか!と思ったもののラストにはなんか違うものを感じた。 だってさ〜・・・人類がさ〜・・・・
0投稿日: 2013.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ1950年代に書かれた米国産SFの古典。 種としての限界に達し、終焉を迎える人類を描いた作品。 前半のグダグダ感から一転して終盤の芸術的な描写がすごい。 何とも言えない寂寥感が残る小説。
1投稿日: 2013.10.30啓蒙主義者の創造話
イギリス人(アングロサクソン?)の作家らしい物事を頭で理解して言葉にしてしまう薄っぺらい思想です。ですが頭は物凄く使い込んでるので、東洋の無我思想とか、唯識思想をさすがに長年交易を重ねてきて物事をより多く知っている知識人らしく、うまい具合にミックスして一つの物語にしています。 話の構成は名の売れている外国人作家にはいつもながら圧倒されます。
6投稿日: 2013.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり久しぶりの再読。後半は全然覚えていなかった。 突然巨大な宇宙船で地球にやってきた異星人”オーバーロード”の圧倒的な力により、人類は戦争も飢餓もない平和な時代を迎える。姿を見せない彼らの狙いは何か… 前半のサスペンスから後半は一転して、種の進化というせつなくも哲学的な内容に。クラークの作品はいつも科学と人間に対する愛に溢れていると思っていたが、これはもう人類を超えた宇宙規模の愛。今読んでも古さを感じない、古典SFの傑作。
0投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ高度な知性を持った地球外生命体に管理された人類が辿る顛末。 予想してたSFとは違い、どこか哲学的な物語でした。 読後、今の生活も悪くないなぁとしみじみ。
0投稿日: 2013.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログストーリーに意外性はあるけれど、他には何もない。面白い想像だとは思う。設定を楽しむためのSFという感じがした。 ジャンの好奇心の強さを細かく描いたり、オーバーロードの葛藤を掘り下げてほしいと思ってしまうけれど…そういう楽しみ方は期待されていないのだろう。
0投稿日: 2013.09.30人類進化ものの古典。おもしろいですよ
「あたりが真っ白になった。そうか、これが進化の次のステップか!」みたいな作品は多いです。たぶん、これが草分けなんだろと思います。パイオニアであるがゆえに、ストーリーはド直球です。 もし現代の小説家が書いたら、ありきたりという理由で没にされるのではないでしょうか。ありふれているが故にエバンゲリオンみたいなひねり方をしないと商品にならない けど、内容はおもしろいし、読みやすいし、古典をしるという意味でマストな一冊だろうと思います
2投稿日: 2013.09.26SF史上最高傑作
これを読まずしてSFを語るなかれという名作。
1投稿日: 2013.09.26これまでの人生で読んだ中で一番好きな小説
謎の提示から始まり、背後にあるシステムが暴れ、人類のポジティブな未来が描かれる。 私がSFで素晴らしいと思うすべての要素が入っている。暗い未来や、破滅へのストーリーを描いて注意を惹くのはある意味たやすいと思うけれど、ポジティブなストーリーを描いて、ここまで感銘させられる作品には出会ったことがない。本作が最高。 ACクラーク、初期の短編「太陽系最後の日」にも通じるものがあるけど、「太陽系最後の日」どこかから発売されないでしょうか……?
9投稿日: 2013.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類が宇宙を目指した時、地球の科学を遥かに超越したオーバーロードと呼ばれる地球外生命体が訪れる。オーバーロードは真の目的を隠しながら、長い年月をかけてそれまでにあった色々な問題を平和的に解決していく。 オーバーロードの真の目的が何なのか色々想像しながら読み進めたが、まさかあんなこととは・・・ 予想を遥かに越えた内容に驚き、人類とオーバーロード、それぞれに悲哀を感じた。
0投稿日: 2013.09.25幼年期の終り
SF界の巨匠、アーサーCクラークの代表作であり、 その後、多くの作品に影響を与えた。 人類とは何か、人類はどう進化していくのか、という壮大で、究極のテーマに 挑んだ作品。 その中で異星人との遭遇という場面も鮮やかに描いている。
1投稿日: 2013.09.24数多くの作品に影響を与えた不朽の名作
SF史上最高の傑作とも言われる作品。オーバーロードと言われている宇宙人との出会い、そして「人類の進化」という究極のテーマ。この作品の影響は、文学のみならず、現代の映画、漫画なども多く感じる事が出来る。(スタッフT)
1投稿日: 2013.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類より遥かに高度な文明を持つ異星人オーバーロードの飛来により、地上から争いは消え、人々はより発達した文明のもと、労働から解放された平和な時代を得た。 しかしオーバーロードは多くの謎を持ち、それが人類の疑問と不安とを募らせた。 すなわち「オーバーロードは味方なのか敵なのか?」 人類はオーバーロードの保護者の様な施しを享受しながらも、子供の様な好奇心を持って彼らにささやかな反発をするが… ◆さすがSF界の名作、読みごたえが半端じゃないです。 オーバーロードの目的は何なのか?とオーバーロードに注目させておきなが、本質はオーバーロードをも凌ぐもっと大きな存在の物語です。 ミスリード…とはちょっと違うかもしれませんが、これまでの疑問よりも驚愕の事実の出現に根底が覆されるという展開でここまで成功している話は見た事がありません。 オーバーロードは高度な文明や肉体・知識を所持しながらも自分たちの種の行き詰まりを感じていました。 一方人類はいまだ幼稚な文明でありながらも、オーバーロードには持ち得ない種の可能性を持っていました。 両者は互いに憧れを抱きながらも、どちらにもなれず、結局はオーバーマインドの掌の上で人類は幼年期を終え、オーバーロードは進化を焦がれ待ち続ける… 宇宙に限りがないように、途方もなく果てしない物語です。 よくこんな大きい物語を作り、そして描ききることが出来たなぁと作者の想像力と表現力に感心するばかりです。 子供は希望の象徴と言いますが、まさにその象徴が手から離れていく最後の描写は絶望的です。 人類は進化を遂げますが、それは人類が人類ではなくなったということを意味します。 人類の滅亡よりもエグく、哀しさを覚えるラストが印象的でした。
1投稿日: 2013.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ宇宙人オーバーロードとそれに幸せに支配される地球人。 クラークは科学者としても一流だったらしいが、ジェフの見る惑星の夢や、オーバーマインドの描写が美しい。 でも、正統派SFはあまり好きではないと自覚した。
0投稿日: 2013.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代に住む私たちの「幼年期」もまた、クラークのこの作品の様に終わりを迎える日が来るのだろうか…。読み終えてすぐこんな考えが脳裏を過ぎりました。 地球人類は幼年期を終え、オーバーマインドの一部へと吸収され言わば宇宙を支配する概念と同一化しましたが、果たしてそれは喜ぶべきことだったのでしょうか。オーバーロードは、精神的進化の限界を迎えた種として、人類を羨望の対象として見ていましたが、オーバーロード(の役目)になるかオーバーマインドになるかは賛否が分かれる問題のように思われます。プラトンのイデアが好きではないというのもありますが、「個人という最後の垣が取りはらわれてしまえば、孤独は個性の消滅とともに消えていくだろう。無数の雨滴が大海に呑みこまれるように。」この文にゾッとした私はむしろ孤独でありたいと強く思いました。 余談ですが、アニメ「機動戦士ガンダムOO」が、この作品に大きく影響を受けていることを読んでいる最中に知って感動しました。
2投稿日: 2013.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人類が特異点を超え別次元へ。 まず設定の着眼点が途方もなく、人間には感知できない知性の集合体の存在を打ち出したのは驚きだ。 あとはオーバーロードが悪魔の風体をしているだとか、長い時間を掛けてゆっくり進化を促すさまを描くだとか、そのあたりの進め方が上手いと思った。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の「えらい人」は日経新聞を捨ててSF小説を読んでください - デマこいてんじゃねえ! http://d.hatena.ne.jp/Rootport/20120905/1346856312?utm_source=API&utm_medium=twitter
0投稿日: 2013.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログSFにおける古典的傑作のひとつ。おおざっぱなストーリーは(誠に残念ながら)以前から知っていたのだけど、実際に全編を読むのは初めて。 読み終わった印象はと言えば、「さすがに傑作と言われるだけのことはある」って感じである。物語そのものに謎が仕組まれているし、時々起きるサプライズ的な展開も、(誠に残念ながら)あらかじめ知った上で読んだのだけど、それでもうーんとうならされた。 なにより、物語の持っている切なさというか、やりきれなさのようなものが後半になるにつれてじわじわと広がってきて、しかもそれでは終わらないあたりがすばらしく、前半のやや散文的な部分の印象をかき消してくれる。 この切なさ、やりきれなさが、同じく未来史を書いているアシモフやハインラインとの一番大きな違いのような気がする。あえて言えば、日本人好みの美学が感じられると言ったら、言い過ぎだろうか。 なんだかじっくりと大人の読書をしたなあという気分であった。
2投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ一時代の終焉の描写が緻密に描かれてる。 読み終わった後にわびしさを感じるが、それがなんだか心地よい。
2投稿日: 2013.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログーーー人類が宇宙に進出したその日、巨大宇宙船団が地球の空を覆った。 やがて人々の頭の中に一つの言葉がこだまするーーー人類はもはや孤独ではない。 宇宙知性との遭遇によって新たな道を歩みだす人類の姿を、巨匠が詩情豊かに描きあげたSF史上屈指の名作 さすがに名作と言われるだけのことはある。 すばらしく素敵なスケール感。想像力を掻き立てられる。 異星文明とのファーストコンタクト 栄華を極める"理想郷" 新たな旅立ち の三部に分けられた、人類進化の黙示録 Scienceを突き詰めたものも、Scienceの枠を超越したものも扱われているけれど紛れもなくSF 段々とオーバーロード達に「人間味」が出てくるのが印象的だった。 今こそ彼は悟った。ーーかつて彼を星々へ誘った夢が、その究極の分析においていかに空しいものであったかを。
0投稿日: 2012.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者の想像力がすごすぎて、私の妄想が追い付かず読み進めるのに苦労した。 この想像力の行き着く結末はどうなるのかと期待と不安が入り雑じり、読み終わると寂しさでいっぱいになった。 これほど壮大なストーリーを紡げるなんて、さすがSF界の巨匠だと感嘆せずにはいられない。
0投稿日: 2012.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がどこか漠然と抱いていたユートピアのイメージが第二章:黄金時代できっちり描かれていたので楽しすぎて笑ってしまった。ジャンの密航までは非常にわくわくした。そのわくわくは第三章:最後の世代で裏切られることになるのだが、その物悲しさは小説の出来を損ねるものではなかった。
0投稿日: 2012.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わって、ひどく寂しい気持ちになった……。人類滅亡もののSFは数多いけれど、読み終えてここまで寂しい気持ちになることは、そうはないように思う。
1投稿日: 2012.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。 何がすごいって、地球でない星々の描写がすごい。 彼の眼には何が見えていたのだろう。その星たちの上にどんな空が広がり、どんな大気がたちこめ、どんな海が、山が、大地がひろがっているのか、まるで彼自身の目でつぶさに眺めてきたかのようだ。 もちろんストーリーも面白かったよーていうか光文社古典新約文庫で出てるなんて知らなかったよー 「古典」って言いすぎじゃないかwww確かに不朽の名作だとは思うけど。
3投稿日: 2012.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ"これが人類の終末なのか ――――いかなる予言者も予見し得なかった終末、楽観主義と悲観主義とをともにしりぞける終末"
0投稿日: 2012.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ地球人類の行く末を扱った壮大な物語。オーバーロードの目的は何か。50年もの長きにわたり、目の前にいながら姿を現さなかったのは何故か?その姿を見たとき、そして新たな進化のビジョンが現れたとき、震えにちかい感動があった。SFにして哲学的な問題に取り組んでいる。私たちは何処へ向かっているのか?そして今の原子力問題をオーバーロードが見たらなんと言うのか?きっと、地球人は進歩を故意にやめていのか?と嘆くのではないのか。そして本来なら好まない強制介入に踏み込むのではないだろか?SFの古典ではなく、小説界の古典的名作。
3投稿日: 2012.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
これだけはいくつ星をつけても足りない。 この話は序盤からずっと容赦なく暴力的で救いがなく寒々しい。その残酷さは意図されたもので、こちらにその意図を感じとらせるような書き方がなされている。しかも多面的で、いろんな種類の人間の痛いところを的確についてくる。矛盾を示唆し、無力さを浮き彫りにし、媚をせせら笑う。読みながら無傷でいられる人は少ないと思う。でも最後にはそれすらどうでもよくなるぐらい話のスケールが大きくなる。何もかもが圧倒的に変化し、根こそぎ去っていく。それは成長であり喪失で、今のような人類は名誉はあるが残りカスである。 オーバーロードたちの容姿についての謎が終盤まで引っ張られるが、地球上のいろいろな文明が「悪魔」として指定した姿がなぜかどれも似通っているその理由が、未来でのオーバーロード達の到来が幼年期の終わりを意味することを、幼年期の人類は種の記憶として知っていたから、というのが衝撃的だった。
0投稿日: 2012.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルしか知らなかった本。 引き込まれて一気によんだ。 古い本なのに、すごくどきどきした。章ごとにどきどきする気持ちの種類が違う感じ? うまく表現出来ないけど、なんだかいろいろ考えながら読んだ。 SFっていろいろなことに感心を持てるし未来や技術、宇宙、生物について想像が膨らんですごくどきどきする。大好き。
0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログまだ高校生だった兄が勧めてくれた本を当時の父親の年齢になって読むことになるとは!青年期に出遭った忘れ得ぬ題名。ガガーリンの「地球は青かった」が'61年、アームストロングの「この一歩は小さな一歩だが…」は'69年。本書の初出'53年。時は米ソによる宇宙開発前夜。人類は宇宙への第一歩を踏み出そうとした瞬間その夢を奪われ、暫しの物質的繁栄期の後、地球と共にその幼年期を終える。精神的メタモルフォーゼの進化論的意味には留保を置くも、宇宙の深遠を唯一経験した男が地球の最後を看取りながら一人語りする場面は儚くも美しい。
0投稿日: 2012.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2001年の宇宙の旅を映画で観ただけで、初のクラーク作品を読んだ。(SF自体初かもしれない) とにかく序盤からオーバーロードについての謎への好奇心がずっと続いていて、その気持のまま終盤になっていくので、最後はページを捲る手が止まらなかった。宇宙や地球外生命体に関しては今でもわからない事だらけで、フィクションなんだけど、「もしかしたらあり得るかも」っていう気持ちがあるのでロマン溢れる作品だった。 途中までは当然人間側の視点で読んでいて、圧倒的な力を持つオーバーロードへの好奇心と畏怖が混じり合っているんだけど、中盤くらいから人間がオーバーロードに近親感を持ち始めるようになった。ルーパートやジョンの企みや、オーバーロード同士の会話などである。そして、終盤から当初神であるようなオーバーロードに人間が近付けたのではないかと思い始めると、実は更に上位の存在であるオーバーマインドというものが登場し、その考えは打ちのめされる。 これは、実はオーバーロードが人間でオーバーマインドが神である、という風な解釈をしてみました。どんなに人間が発展しようと、更に偉大なもの(=神)が存在するという話なのかなと。 少しキリスト教的な考え過ぎるかもしれないけどね。 でも、自然への畏怖というものは東洋的な考えでもあるか。 まぁ他にも潜在能力の無いオーバーロードと有る人間の対比で、人間の方が救いのあるというような解釈もあったり。 なんにせよ、面白い展開でかつ壮大な物語でした。個人的にはもう少し具体的なラストも見てみたかったです。
0投稿日: 2012.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
学生の視点で見ると、モラトリアムに守られた主体性なき安泰、およびその崩壊と否応のないステップアップを示唆しているようにも感じた。 もっともオーバーロードとオーバーマインドのどちらになれるか、どちらが良いのかまでは分からない。トータルブレイクスルーの結果を、肉体的文化的特徴を放棄した原点回帰と考えると種としては不幸でしかないのではないだろうか。 そう考えるとクラークが以下の2点を取り扱ったのが皮肉にも思えてくる。 1.人類で一番最初にトータルブレイクスルーの兆候を見せたのが、人類が築き上げてきた芸術的文化の維持発展を目的とした島で育った少年であった。 2.物質的な進化を極めたオーバーロードが、トータルブレイクスルーの可能性を持つ地球人類のことを羨んだ。 もっとも1は因果律が場合によっては時間の前後に影響されなかった点を考慮すると違ってくるのだが
0投稿日: 2012.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ話の展開は良くも悪くも あぁ、そっちにいっちゃうのか、と言う感はありましたが 随所の具体的な描写にリアリティがありながら壮大、 という好きなタイプのSFです。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類と異星人の出会いは衝撃ではあるが、実際重要になるのは宇宙人の地球への訪問目的である。侵略ならばひたすら攻撃し、親睦ならば利益を追求するのだろう。人間とはかくや果てない欲求を持ち、いかに壊れているかを著した作品なのである。
0投稿日: 2011.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初クラークでしたが、もう感動しました。構造で言うと『伝説巨神イデオン』『新世紀エヴァンゲリオン』が近いかな。オーバーロード=独立した主体性のある常識人、人類=依存した主体性のない(あくまで自分の論理ではなく模倣された)常識人、という見方もできなくもない。『彼』はきっと、生命が感じることの出来ない、感覚も論理も挟むことの出来ない透明で平板な、つまり『不感の領域』ではないか。
0投稿日: 2011.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
突如地球上にあらわれた異星人オーバーロード。地球人との接触は国連の事務総長ストルムグレンのみ。姿をあらわさないカレルレン。オーバーロードの統治になれ黄金期を迎えた地球。ついに姿を現したオーバーロードたちの容姿。オーバーロードの補給船に密航し彼らの星に渡ったジャン。ある世代の子供たちにあらわれた変化。オーバーロード達の真の目的とは? 2011年11月1日読了
0投稿日: 2011.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ競争こそが進化を生むものだと思っていた。 古来よりひとは競争に打ち勝つために、進化を外に求めた。それが道具であったと思う。それ以来ひとは内なる進化を止めた。ユートピアは、道具の進化すらを抑制し、実はひとを堕落させるものだと思っていた。 進化は必然?抑圧された進化のはけ口がひとを幼年期の終りへ導いた? なんてことを想像してしまった。 「2001年宇宙の旅」を読み進めている時にも感じたが、この作者のイマジネーションの洪大さは、時に読者の頭を繁雑にさせる。 それは、この物語を読み解こうと頭を回転させるだけでなく、その溢れるイマジネーションに誘発されるように、物語に由来した、或いはそれと異なる想像の種を芽ざそうとするからかもしれない。 実際、読んでいる最中、作者の特異な発想に着眼点を得て、全然別のことに思いを馳せてしまっていた。 「これこそ、歴史が息をひそめる一瞬であり、現在が過去から断ち切られる瞬間なのだった。」 異星人とのファーストコンタクトを表現する言葉にはいくつも出会ってきたが、上述の言い回しは、シンプルでありながらも、この先待ち受ける物語の行く末に許多の期待と興奮を抱かざるを得ない描写であった。 以上に限らず、詩的な描写の数々は、この作品の魅力の一部であることに間違いない。 こんな風に、この本を読んでいると自分の言葉の稚拙さや、想像力の矮小さに嫌というほど気付かされる。 そんな繊細でありながらも巨大な小説を読めて良かった。まじで。
0投稿日: 2011.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類はどこへ行くのか・・・、「2001年宇宙の旅」の巨匠、アーサー・C・クラーク作品の中でも一番面白かった。と言うか、考えさせられた。
1投稿日: 2011.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
終戦からおよそ30年。宇宙への進出を始めた人類の前に宇宙船団が現れた。 人類より遥かに優れた技術力を有する宇宙人との遭遇とそこから始まる人類の進化を描いた作品。
0投稿日: 2011.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類の”進化”を描く古典的名作SF。その壮大なスケールや、美しくも哀しいイメージの奔流に圧倒される。オーバーロードの意外な正体もだけど、何よりも「われわれ自身は、石女なのだ」という言葉に込められた悲哀、諦念が印象的。いや〜、面白かった♪
0投稿日: 2011.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ高一ぐらいに読んで、それから20年ぶりに再読。 その後いろいろなSFを読んだり映画見たりしたが オマージュとか引用みたいなの、リスペクトとかさ 後に作られた作品に見られるのに今更気がついた。 オーバーロードの緩やかな支配下に置かれた地球での話。 彼らの目的がなかなか出てこないが、なかなかに壮大な話だよね。 生きるものの可能性について考える。
0投稿日: 2011.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ高度な宇宙人のもとに実現された理想的社会と、その末にある滅びゆく種族の姿。人間がよく描かれ、まあ良。
0投稿日: 2011.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログいままで読んだSFにまったく引けをとらないスケール・ギミック・ストーリーなのに、最初のページを開いてみると、「1953」!本当に半世紀前に書かれた作品なのか…!?なんて疑ってしまうほど、科学への考察やアイディアには褪せた色が見えない。途中からはここまで話進んだのにまだこんなにページ残ってるの?なんて思ってしまった。名作です。必読。
0投稿日: 2011.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログドラッカーの「ネクストソサエティ」に惹かれるか?それともクラークのこれか?どういうタイプの大人になるのかはそれでわかる。
0投稿日: 2011.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類を遥かに凌ぐ高度な知識と技術を持ったオーバーロードとの邂逅、そして地球管理する彼らの真の目的とは…?。 エイリアンとの遭遇物ですが、やっと姿を表した時のオーバーロードの容姿に対する驚きや、彼らの超科学の前に意気消沈し静かに停滞していく地球文明など描写がリアルで今読んでも衝撃があります。 また物語の後半では、物質世界を知り尽くしたオーバーロードでさえ進化の袋小路に入ってしまった事が明らかになります。これに対してもう一方の道を辿った種族の存在が明らかになりますが、この究極の対比が進化とは何かという問いに対する一つの答えなのだと思わされました。 全く古臭さは無く、新鮮に読む事が出来ます。必読推薦。
0投稿日: 2011.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ少しでもSF映画とかマンガとが好きならばこれは読むべし。 絶対に読むべし。 なんというか、もうSFの持つ魅力すべてを この物語は内包しているように思う。
0投稿日: 2011.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログあああ、ごめんなさい。 こんなにSFの巨匠と言われる方の作品なのに、 まったく、ページをめくる手がすすまない。 なんど読み返しても、書いてある内容が あたまにはいらない。 わたし、だめだなあ。
0投稿日: 2010.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログChildhood's End(1953年、米)。 見送る者の虚脱と悲哀。見守る者の憐憫と羨望。この悲劇性にもかかわらず、これほどの喪失感にもかかわらず、これは挫折ではなく成就なのだ――。読む前にはSFらしくないと感じたタイトルが、読み終えた後にはこれ以外にないと思えてくる。この悲しみと諦めと達観のないまざった、複雑な情感を表現するためには。 異星人との遭遇、そして人類の行く末が、壮大なスケールで描かれている。それでいて、個々の謎はジグソーパズルのピースのように、きっちりとおさまるべき所におさまっていく。理知的なスタンスを崩すことなく、同時に圧倒的な抒情性も兼ね備えているという、稀有な作品である。完成度の高い、金字塔の名に相応しい傑作だと思う。 部分的には、ジェフが見る夢の描写がとても印象的だった。超重力の惑星や、6つの恒星をもつ惑星など、想像すると少し背筋が寒くなるのだが、畏怖に近い感覚で非常に心惹かれる。作者のイマジネーションの豊かさに脱帽。
5投稿日: 2010.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ米ソが熾烈な宇宙開発競争を繰り広げる20世紀後半のある日、巨大な円盤状の宇宙船多数が世界各国の首都上空に出現する。 オーバーロードと呼ばれる異星人たちは国連事務総長を通じ、人類共通の国家を建設し、地球上に未だはびこる差別や戦争の根絶を促すべくその船の中から間接支配を始める。 そして50年の月日が流れた。 人類にその姿を見せることなく地球の管理を行なってきた異星人が、人々の前に姿を現す。 やがて人類…子供たちに次々と現れる変異。 彼等は両親たちとさえ断絶し、変わって行く。 宇宙人の真の目的は何か? 人類の未来は? 進化とは? ――SFの巨匠が異星人とのファースト・コンタクトによって新たな道を歩みはじめる人類の姿を描きあげた傑作。
0投稿日: 2010.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログSFを感じさせるのはその発想の部分が一番大きく、内容に関しては、ある特殊な状況におかれた人間がどう発想してどう行動して行くのか、という心理的な部分への興味と、この先どうなっていくのだろう?という興味を惹きつけて、最後まで一気に読ませる迫力があった。 ただ、個人的には最後はちょっとリアリティに欠けるのが残念だった。 物語の展開が秀逸だっただけに、それに少し負けてしまった感じを受けた。
0投稿日: 2010.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ前評判を聞きすぎたのかも。ラストは背中が薄ら寒くなった… 宇宙に満ちる意識と同化…って、「2001年宇宙の旅」でモノリスをもたらしたものと通じる? リンクしてると考えるのが間違いか。
0投稿日: 2010.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ悲しさだけが伝わって来る翻訳で人類と地球に何が起きているのかいまひとつ解らなかったのでありますが、今はそのままで良かったと思うのです。空が蒼くなるまで沈んで行く夕陽を見届けた気持ちになる話でした。
0投稿日: 2010.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ホラーじゃないのに怖い。ラストあたりでタイトルはそういう意味だったのね!と納得できると同時に背筋が寒くなる。
0投稿日: 2010.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ史上初のロケット発射、人類が宇宙への第一歩を踏み出そうとしたとき、彼らはやってきた。主要都市の上空を巨大な円盤で占拠し、電波を通して、地球統治宣言が出される。「オーバーロード(上帝)」と呼ばれた彼らは、その圧倒的な技術力によって、地球上のあらゆる政治・環境問題を解決、そして国際連盟のもとに全地球を統合する……。だが彼らの目的はいったい何なのか。侵略か? それとも植民地政策のごとき地球からの搾取なのか? あるいは彼らの言う通り、「人類の育成」が目的なのか? しかし、「育成」とはどういう意味なのか……?
0投稿日: 2010.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログジェフの見る夢の描写が凄く好きです。未知の星々とそこに住む(人間にとっては)不可思議な生命体の数々…。 この部分は何度読んでもワクワクしてたまらなくなります。ああ、宇宙っていいなあ! こういう「異世界の風景」みたいなのが大好きだ。 「2001年宇宙の旅」シリーズのどれかにも、木星だかの描写があったような?あれもよかったなあ。
0投稿日: 2010.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ古いSFだけに、ちょっとなぁという所も。国境が無くなって平和だとか、一回警告しただけで紛争が無くなるとか。戦争じゃなくて自爆テロが日常的に起きる今読むと、人間の情念ってそんなもんじゃないだろと思う。ぎゅうぎゅう働かなくても経済が回って行くという話も、スター・トレックで最初に聞いた時は「そりゃすごい!」と思ったけど、共産主義が自滅(このことは、人間の欲望だけが経済を牽引できることの証明なのかも知れない)したり、経済工学でバブルが起きたり、経済的価値っていったい何なのさ?と思う今では、それこそ安っぽい宗教みたいで、およそ実現可能なアイディアとは思えない。そんな理由で「黄金時代」として書かれている理想的な社会が実際どのように実現されるのか、さっぱり実感がわかなかった。人間はそんなに理性的に、感情に影響されずに、生きて行くことができるもんだろうか?経済的、技術的問題ではなくて、むしろ、種としてそこが克服できないからこそ、今の人間の世界があるんじゃないの? 個体の限界を超えて統合された知性という考えは、キリスト教かなにかに元があるのか知らん。エヴァンゲリオンとか、最近ならハルヒとかエウレカにも出てきたけど、そういうのを望むセンスがあるんだろうか?でも、エヴァの映画版では否定されてたよな。よく分からん。 というわけで、何がおもしろいのかさっぱりでした。
0投稿日: 2010.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大分放置してしまってたけど・・・ エヴァンゲリオン、最近YouTubeに上げられたガンバスター、庵野さんはこっから色々影響を受けてるのかな?ネットで引いてみたら伝説巨人イデオンとかいうやつも元ネタとして有力のようだけど。 ここから来てるSFは現代でウケる。マトリックスとか、あとナウシカとかもそうだな、いろいろある。 更に元をたどれば仏教思想に行きつく、それをアングロサクソンチックにアレンジできるのは彼の想像力の高さのたまもの。エヴァンゲリオンは逆輸入とでも言うべきか。 ネットで引いたときにGooの教えて!で「エヴァは~のパクり」論争をやってた。そこでパクリ容認派のユーザーが庵野の言葉を引用していて、それが印象的だったので載せておく 「僕の持っている人生観や考え方以外に確実なオリジナルは存在しない。それを突っ込んでしまえばただのコピーでしかないと言えるんですよ、胸を張ってね。そこの部分なんですよね。コピーをする時に自分の魂をこめる。まあ、それは人の魂が入っている、ただのコピーではない。いままでのマンガや特撮もの、アニメをコピーした「エヴァンゲリオン」はそこのメタファーみたいなところはありますけれど、いちおう、基本的には置き換えで作ってますんでね。」 まぁ今となっては対して新鮮な意見でもないんだけど、「オリジナリティー」というものに関わる議論はこれからの時代活発になってくることだろうから考えておく必要がある。 僕は庵野さんみたいな考え方に寄ってる。僕世代では中学の時に「オレンジレンジをどう考えるか?」という事が一種の流行と化していて、その時は「乗りがいいだけのパクリバント!アレンジレンジ!」って考えていた。でも大学行って実際に曲をつくってみようということになった時、どう考えたって完全に独立したオリジナルなんてものは作れないんだということに気がついた。 実際、作るときの感覚として「オリジナルだから、自分の感覚から湧き出るものを表現する」という時には、なんかどっかで聞いたような、しかも何曲作ってもおんなじようなテイストの曲ができてつまらない。それよりも「この曲から、これを持っていこう!」と考えた時の方が、かえってオリジナルなものができたりする。 最近じゃ、オレンジレンジのあのあからさまなパクリ方そのものが、J-POPの流れの中では「新しい」「オリジナリティー」だと言えるんではないかと思うようにもなった。庵野も言ってるように重要なのはそれを「誰が」やるのかということではないか。 矢沢栄吉好きだけど、矢沢の曲はひとつも印象に残らない。でも、彼が歌ってる姿は強烈に記憶に刻まれる。じゃぁ、曲なんか作っても意味ないじゃん、ということにもならないと思う。それは不可分なもので、そういう理屈の通らんことがロックという・・・・・・・・・・・っておぃ 例えば、この小説に即して「人類は何を源に文明を築いてきたのか?」と想像力を巡らせることが、「創造」そのものについて考えを巡らせる一歩じゃないかと思う。
0投稿日: 2010.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ地球と文明の進んだ謎の異星人とのファーストコンタクトから始まる壮大な物語。アーサー・C・クラーク らしいSFマインド溢れる傑作。最近では新訳版も他社から出ているようなので、そちらのほうが読みやすいかも。
0投稿日: 2010.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログあ、幼年期ってそういうことなのね。と最後のほうになって気づく。 地球人を見守っている間のオーバーロードの胸中を思うと切なくなってしまうが、最後の人間の成長と覚悟に関しては自分ならここまでにはなれないなぁとただただ関心するのみでした。 一度は読むべき話かもしれません。
0投稿日: 2009.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ近未来の人類の、超文明との接触とその行く末。 淡々とロマンティックにとっても壮大。派手に動き回るお話でもないのにぞくぞくです。
0投稿日: 2009.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔は面白さが先に立ったけど、今(子供ができてから)読んだら哀しいこと夥しかった。 そして、カレルレンではなく、「人間」に感情移入する自分に驚いた。 個別性は高度の成長には本当に要らないものなのか、それとも広域の中でアーシアン(とでも言っておくか?)という個別性を手に入れたのか。
1投稿日: 2009.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ超有名SF小説。 読むと背筋がぞわっとします。 特に子供たちが、私の『人間』という概念から外れた別の生物として変異する辺りが。 人はやはり異質さを恐れるのだ。 その未知なる異質さ故に。 そして自らの方が異質なものであると気づいた時の絶望は如何に。
0投稿日: 2009.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ古典SFの金字塔 【書評じゃないよ】 松屋のカレーの話である。 たまに福神漬けがカレールーに浸されて出てくることがあるのだが、私はこれを許せない。許せないのは個人の嗜好だからいいとして、そもそもルーに浸して客に出すのはバカだとも思う。 もちろん中には「ルーに浸した福神漬け」が好きな人もいるかもしれない。だけど、そういう人は出されてから浸せばいいのだ。米の上の福神漬けをルーに浸すことはできても、既にルーに浸った福神漬けからルーを取り除くことは不可能なのだから。客にとって、どちらが自由度が高いかはちょっと考えればバカでもわかる。 というわけで死刑制度廃止には反対なのですヨ。
0投稿日: 2009.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのSF小説が映画化されないのはやはり宗教的な問題が あるからだろうけど、映画ファンにとっては残念なことだ。
0投稿日: 2009.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「2001年宇宙の旅」の原作者、アーサー・C・クラークによる近未来小説。 その広大なスケールを持つシナリオ、物語のリアルさを支える設定もさることながら 詩的な、読むものの心にその場面を想起させる表現が素晴らしい。 一気に読み終えました。 ある意味わけのわからないようなラストだけどなんとなく納得できる感覚。 この筆者ならではだと思います。
0投稿日: 2009.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の辺りは泣きながら読みましたね。 カレルレンは地球を見守り続けて、そして最後になにを思ったのでしょうか。 ヒトならざる彼の目に映った人類の「幼年期の終わり」は一体どんなものだったのか。私のような凡人には想像もつかないところではありますが。
0投稿日: 2009.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログかなしくもうつくしい終焉への道しるべ。 ほんっとに感動しました。ラストの美しさが秀逸! さすがSF屈指の名作と言われるだけあります。 この感動を分かち合える人が欲しい これ星あと五つぐらいつけられないかな。
0投稿日: 2008.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類はオーバーロードと出会って本当に良かったのか。これを考えると本当に難しい。 とはいうものの、オーバーロードと出会わない未来は存在し得なかったろうし、出会ってしまえばもはや結末へ通じる道しか残っていなかった。人類には、始めから選択権などなかったのだ。もちろん、拒否権もあるはずがない。確かに人類は次のレベルへ移行したかもしれないが、それが「幸せ」かどうかは分からない。 楽しく読ませてもらった。
0投稿日: 2008.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れたSFの古典的名作ですが、 今読んでもちっとも古く感じないところがすごい! 地球にやってきた「オーヴァーロード」の正体とは? 地球の未来とは??? 予想もしない結末とは??? その後のSFに 多大な影響を与えた秀作。 SFファンでなくても必見! お勧めの一冊です。
0投稿日: 2008.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこんなに胸が躍る小説を読んだのは、いつぶりだろうか。 ふだん小説を読むのにたいして時間を必要としないわたしが、この本を読むのには三日以上かかった。それはこの本が何よりも思考を必要とする本だからである。 二行、三行の文章にすら想像力が問われ、その世界が自分の想像したこともないものであり、一から新しいものを想像することを求められるからである。 人類が宇宙に進出しようとしたまさにそのとき、人類は自分たちが出遅れたことを知った――。 人類よりも遥かに高度な文化を有する異星人が地球に降り立ってきた。彼らは長い時間をかけ、地球をその管理下におき、地球の文明は飛躍的に発展する。 しかし彼ら<オーバーロード>の目的は明らかにされない。 オーバーロード側の最高責任者であるカレルレン総督と、彼にかかわる人類の未来の物語がつむぎだされる。 はじめは仕事上のパートナー、ストルムグレンが彼の容貌を知りたいと願い、 次には自分の子供たちがなぜかオーバーロードに庇護されていることを知ったジョージが戸惑い、 そして若い青年ジェフがオーバーロードの母星をつきとめ密航し、地球に帰ってくるところまでの長いスパンで。 八十年の時を経て帰って来たジェフが見る地球の姿とは? そもそもこの本を手に取ったのは、名作だという話題のほかに、ゼノギアスにも登場する「カレルレン」という人物に惹かれたから。 オーバーマインド、オーバーロードのあたりは何も知らなければもっと楽しく驚けたのかも。 個人的にはほんとにゼノギアスと同じだなあ・・としか思えなかったので。いや、あのカレルレンは人類なんだけどね。 宇宙の広大さ、無意識下の神秘を感じるにはうってつけの本。自分の体さえ不思議に思えてきます。 たしかにわたしたちは、人体の謎についてもほとんど知らずにそれを動かしているわけで、それを可能性と呼んだ小説。 面白かったのは、オーバーロードが初めて姿を現したときのことが悪魔として描かれている、とか。 人類はあらゆるものを科学で説明しようとして、魔法とよばれる超自然のたぐいのものをまったく無視してしまった、とか。鋭い。 これが書かれた年代を考慮に入れてみると、この鋭い予知警告にぞっとするほど。 オーバーロードとオーバーマインドの関係についてはやっぱり謎が多いけど、そのへんを知りたいなあ。 いや、たぶんカレルレン総督たちもどう頑張ってもその運命から抜け出すことはできない、んだろうけれどもね。
0投稿日: 2008.10.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこれぞSFだなー、と思いつつ読む。 随分昔に書かれたものらしいけど、あんまり古い気がしないですね。
0投稿日: 2008.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログまさに衝撃の未来。 人類の行く先がこんなにも切なく、鮮やかで、寂しい物だとは。 ていうか、これが書かれたのが50年も前だということにも吃驚。 人間の想像力には、心底感心させられます。
0投稿日: 2008.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2001年宇宙の旅よりも印象深い作品。著者はスリランカにいて、宇宙を体感していた。まだ読みたかったのに、惜しいです。今の日本は幼年期のような気がする。読んでいない人は一読して下さい。
0投稿日: 2008.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ考えれば、この作品のおかげで現在のSFの定番とも言える、異性人による地球人観察モノができたんですよね。 このアイディアを出すことができたことだけでも、星5つですが、内容と翻訳もすばらしい。
0投稿日: 2007.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「われわれは”科学”に慣れています。あなたがたの世界には、もちろんわれわれの理解できないことがたくさんあるでしょう。しかし、だからといって、われわれはそれを魔法とは思いませんよ。」 「あなたは本当にそういいきれるか?電子時代と蒸気時代とのあいだには、わずか百年のへだたりがあるだけだった。だが、ヴィクトリア朝時代の技術者は、テレビや電子計算機をどう考えるだろう?(p.231)」
0投稿日: 2005.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、この作品のオーヴァーロード達のありようが、某作品群で描かれるエルフ族に似ているのではとようやく気づきました。
0投稿日: 2004.10.03
