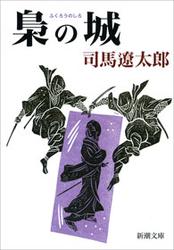
梟の城(新潮文庫)
司馬遼太郎
新潮文庫
名作
娯楽系といっては文豪 司馬遼太郎に失礼かと思うが、超人的な忍者の技には、多少そのような趣を感じる。ただし、だからと言って本作の面白さは変わらない。つまり、忍者の世界の非情さや、駆け引きを通じて司馬が言いたかったことを汲み取ることに、本書の魅力を見出せるだろう。 本書を推すのは、私ばかりではない。読書家として名高い漫画家 吉野朔美氏のご尊父も本書を推薦している(「お父さんは時代小説(チャンバラ)が好き」)。
1投稿日: 2015.06.05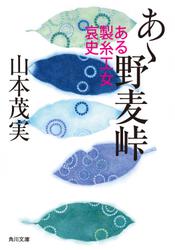
あゝ野麦峠 ある製糸工女哀史
山本茂実
角川文庫
働くって何だろう?
言わずと知れた、昭和のノンフィクションの金字塔。岩波の「女工哀史」が未だ電子化されていないので、本書が電子版で読めるのが本当に嬉しい。が、電車の中で読むと、うっかりして、つい落涙してしまうかも知れないので、注意が必要。 本書を勧める対象は簡単だ。つまり、全ての日本人に勧めるから。日本人なら是非1回は読んでほしい。 特に若者の多くが、本書や大竹しのぶ主演の映画を知らないらしく、残念で仕方ない。 本書は3通りの読み方ができる。1つ目はプロレタリア文学の延長として、2つ目は日本近代史の文献としてである。そのどちらの読み方をしても、最高評価を得ること疑いない。 数年前、デフレ景気の影響で小林多喜二の「蟹工船」といったプロレタリア文学が人気を呼んだとか。多喜二の「セメント樽の中の手紙」にしても、吉村昭の「高熱隧道」にしても本書にしても、今日の日本が尊い犠牲のうえにあることを忘れてはならないことを思い出させてくれる。そして、本書を読むと、日本人自身の犠牲の存在は、もっと日頃から強調されるべきと思えてくる。そうすれば、よそから何か言われても「強制労働だけでなく我々の祖先だって・・・」と主張できる(ただし、私自身はどこの国の人間であったにしろ等しく扱いたいが、いずれにしろ、国力が劣るのは絶対悪に違いない)。 世界遺産を巡る無邪気な喜びと議論を、チョッと斜に構えて眺めてみる。 3番目の読み方は、趣味によるけどマルクス経済の傍証としての読み方。 ロバート・オウエンのような希少な例はあるが、資本主義は抑制されなければ暴走するし、搾取するものなのだ。改めて、ため息とともにジッと手を見る。ただし、製糸業を”生死業”という観点から考察を加えているのは本書の凄みでもある。黎明期の起業家が高いリスクを負っていたとはいえ、そのシワ寄せ先を考えるのではなく、知恵でリスクをなくす仕組みが講じられなかったのか・・・いやあの当時では誰もが精一杯だった、と言うことだろうか。 それにしても、元女工のばあ様達の、肯定的な思い出語りが何とも言えず考えさせられる。 産業革命当時の児童炭鉱労働者からはじまり、現在も世界中に多い児童労働者は?苦しいとは思わないのだろうか?もし、そうならば、それは、選択肢を持たないが故なのだろうか?
1投稿日: 2015.06.05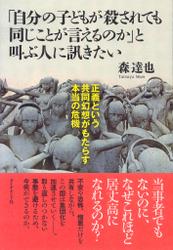
「自分の子どもが殺されても同じことが言えるのか」と叫ぶ人に訊きたい
森達也
ダイヤモンド社
評価はパス
一番目に強調する。森達也は注目しているドキュメンタリー作家である。下山事件、放送禁止歌は非常に興味深く読んだ。未だ心の準備が出来ないが、代表作であるAシリーズも是非読みたいとは思っている。 二番目に強調する。社会は、いかなる意見も封殺してはならないと信じている。それは、社会にとって批判意見は全体として見れば有益と思うからである。ヘーゲル的弁証論に即して言えば、ジンテーゼに至るにはアンチテーゼの存在が不可欠だからとか、全員賛成の多数決は全員が誤っている危険を検知できないからでもあるが、そんな理屈を言うまでもなく、そもそも意見は全く以て自由である。 三番目に強調する。私のように匿名でなければ言いたいことも言えない人間と違い公然と意見を表明している人々は、真に尊敬に価すると思う。 そのうえで、敢えて言う。本書は勧めない(興味深いテーマもあるにはあるが・・・)。大手出版社刊行なので、興味のある人は立ち読みしてから購入することをお勧めする(電子書籍は古本屋に売れないので)。 勧めない理由を一言で言えば、主張に納得性の乏しいことが多かったからである。例を2点示そう。 【死刑制度について論じた部分】 ・そもそも社会の多くは死刑に賛成しているのではなく容認していると思う。無くて済むなら結構だと思う。しかし、一命を以て始末をつけるという武士道を精神的規範としたわが国では、死刑を最高刑の位置に置くのは納得性が高いし、廃止するまでに社会は成熟していないと思う。 ・諸外国との制度比較については、参考にするとしても廃止の論拠には不適切だと思う。憲法の議論は最終的には、我々がどのような憲法を持つ国に住みたいと考えるか?が最重要である。同じく、死刑制度も我々の問題であって、外国がどのような制度であるかは決定的な意味を持たないと思う。そもそも死刑制度を廃止している国と比較自体が難しい。例えば、多くの死刑制度を廃止した先進国では、テロ事件等の凶悪事件が発生した場合、実行犯の逮捕より鎮圧が優先されるようだ。つまり、取り調べは勿論、裁判にすらかけないで刑を執行していると私には見える。 ・廃止後の犯罪率の予想も語られているが、統計調査の経験も多少ある私としては、他人の調査を信じない。誰がどんなパネルで、そんな質問票で、どんな分析をしたか分からないが、調査依頼主の望む結論に応じて如何ようにでもする。それが腕のいい統計屋というものだ。私も過去、某行政施策は大成功!というグラフを・・・(泣笑)。 ・冤罪については被害者に本心から同情する。また、そのような事を行った人々に底知れない恐怖を覚える。その点は作者と同じだが、作者は制度と制度の運用を同列に論じようとしている。それは別に議論すべき事だと思う。また、執行方法の不確実性、残酷性を指摘しているが、昔、逆説的に生を鼓舞する趣旨で書かれた「完全自殺マニュアル」によれば、現行方式が医学的には推奨されるようだ。 ・執行現場を見た検察官の意見は個人の感想に過ぎないと思う。命は終わるまで続くもので、途中で止めるからこそ、それがどのような生き物であれ苦しいだろう。私も恐らく某検察官同様、確実に正視に堪えられない。それは屠畜でも同じで、社会としてその困難を専門職の方にお願いするしかないのだ。誠に心苦しい限りである。つまり、執行官のように末端で一番苦しい人を思うと、エリート法曹家の感傷は私の心には響かないのである。 【イルカ漁について論じた部分】 マスメディアが取り上げない社会の片隅、あるいは、少数派、反対側に光を当てるのが作者の特徴だと思う。そして、イルカ漁を妨害した外国人活動家の態度が堂々として見えたというのも個人の感想として自由だ。でも、この場合、弱者はどう見ても漁師さん達だと思う。 あくまで想像だが、イルカ漁の漁師達はガソリンが値上がりする中、ボロ船を一生懸命手入れしながら、採算ギリギリを覚悟で船を出すのだろう。細々とした水揚げにため息を漏らし、古びた木造の家に帰り、ビールか酎ハイを飲みながらプロ野球をTVで観るのが何より楽しみ・・・。そして、多くは海外旅行だって一生に数回、何かの記念に一大イベントのように出かける程度、そんな人たちを想像する。 そんな漁師たちからすれば、イルカのために、わざわざ日本まで海外旅行し、船をチャーターし、自分たちの前に立ち塞がるなどということは、まるでエイリアンの所業に見えたのではないだろうか?どんなお貴族様だ?と。 海獣類は北洋で海産物に対する脅威として捕獲されているそうだ。NDLの調査部の資料で知った。僭越な私見で恐縮の限りだが、イルカ漁は魔女狩りにあっているいるのではないだろうか? このコメントを書くか半年悩んだ。筆の過ぎた点は伏してご寛恕賜りたい。
7投稿日: 2015.05.30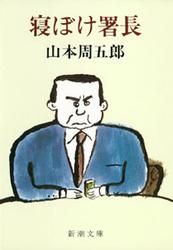
寝ぼけ署長
山本周五郎
新潮社
時代劇ばかりじゃない!
毎年、上司にしたい人物のランキングが発表される。 大体が芸能人、スポーツ選手等、まずは名前が知られている人物が上位を占める。毎年繰り返しランキングされる人もいれば、大体は1回だけの人で構成されるように見受ける。まぁ、一種のお遊びの人気投票なので、そういうモノなのだろう。 ところで、本書はやはり若者に勧めたい。 何年か前に、新潮社のキャンペーンで上司にしたい人物と書かれた帯が巻かれていたことがあった。 けだし、名言、名コピーであった。 最近はメンターとやら言う単語もあるようだが、身近にいて成長の目標の具体像としたい人物、それが理想の上司かも知れない。ねぼけ署長の凄さは、風林火山を体現している点にある。最後の交渉も下手と思ってはいけない。公権力側の外堀を事前に全て埋めてあることを確信してから、実際の交渉に臨んでいる。つまり、勝敗は戦う前に決まっていたのだ。これは戦略は戦術に優先するという用兵の基本とおりだ。警視庁特車2課第2小隊の隊長より、理想像としては現実的と言えるだろう。
1投稿日: 2015.05.30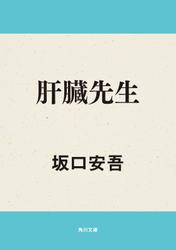
肝臓先生
坂口安吾
角川文庫
評価はパス
文体のせいか、感受性の乏しさのためか、書籍説明のように感動することはないが安吾の代表作なので、一読の価値はあると思う。敢えて勧めるということではないが、良かったらどうぞと言う感じです。 もし、感動を味わいたいなら映画「カンゾー先生」の方が良いでしょう。 ところで、名湯、伊東温泉にある「ホテル ラ・フォーレ」は東郷元帥の別荘であり、その湯を健身湯と名付け愛したところである。後には、海軍の将校用の保養施設として井上成美が籠り終戦の施策を練ったところでもある。 その宿の斜向かいが肝臓先生の診療所である。現在は存じないが、昔は見学が可能だった。古色蒼然とも味わいのあるとも言える外観の佇まいであった。本作を読み、モデルとなった人物に興味を覚えたら訪ねてみると良いでしょう。
0投稿日: 2015.05.30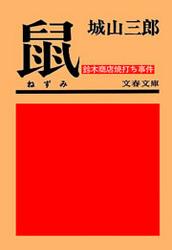
鼠 鈴木商店焼打ち事件
城山三郎
文春文庫
業を営む者の鑑
今日、YAHOOニュースに鈴木商会を偲ぶ会合が催されたとあった。 若い人は「お家さん」で鈴木商会を知った人も多いだろう。 本作は鈴木商会の大番頭、金子直吉に焦点を当てた名作です。特に若手の男性ビジネスマンに勧めたい。 実業家、企業家、起業家、経営者・・・どう称しても良いが、人を雇用し事業を営む者の、ある種の 理想像を私は金子直吉、鼠に見出す。「働きたい者に仕事を与えるそれが企業家の責務である」、この 言葉を口にした人物を、私は寡聞にして他に2人しか知らない。湯婆婆(鈴木敏夫)と池田勇人である。 アメリカ流の経営学に疎いが、わが国における企業の存在意義はこれが第一であろうと愚考する。 それと、ビジネスとはやはり個人のセンスだと思う。ビックデータやら、戦略分析フレームワークやら 結構だが、そこからは「BUY ANY STEEL,ANY QUANTITY,AT ANY PRICE.」は出てくるのだろうか? 男子たるもの生涯に一度は、このような業務指示を出す、または受けたいものだ・・・と思う人も多いの ではないだろうか?そういう意味で若手の男性ビジネスマンに勧めたい。 城山三郎、吉村昭、新田次郎の3氏には原則、レビューを書くのは畏れ多く憚られるが、つい拙を枉げてしまった。城山三郎で言えば、本作を気に入った人は、石田禮助の「粗にして野だが卑ではない」もお勧めです。
0投稿日: 2015.05.27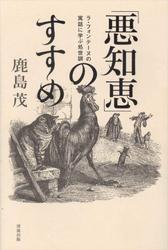
「悪知恵」のすすめ ラ・フォンテーヌの寓話に学ぶ処世訓
鹿島茂
清流出版
悪知恵ではなく・・・
作品中でも説明がありますが、所謂、悪知恵ではなく生きて行くための知恵の書です。 ただし、そこにはフランス人と日本人の違いが出てきます。ですので、異文化理解の読み物としても読め ますし、あるいは国際関係論の教訓集としても読めます。基本的に軽い語り口の”読み物”ですので大袈裟 かもしれませんが(笑)。でも割と本気で、今日でも変わらない国際関係論の基本の結晶知だと思い ます。 いずれにしても、ラ・フォンテーヌを肴に鹿島茂が茶々を入れるというのが基本構成なので、大人の あなたは時々ニヤッとしながら読むには、お勧めの一冊です。紙の本の岩波のラ・フォンテーヌも入手 困難なことですしね。 時々、著者の茶々が現代日本にも飛び火します。たとえ、その内容が頷けないとしても「著者の意見は 余計だ」など言わずに味として楽しみたいものです。私は酒を嗜めないので、酒場の親父の小言・人生訓 の替りのように楽しみました。親父の小言と茄の花は千に一つも無駄がないと言うじゃないですか!? 余談ですが、鹿島茂は「かの悪名高き」が電子化されることを楽しみにしているで、早くして下さい。 三角形ののど飴の販売権を掌握し、オペラ座のオーナーとして君臨した、稀代のグルマンにして医学博士 万人からの怖れと嫌悪を一身に受けた、かの悪名高き蛸(たこ)博士! その名もドクトル・ヴェロン!あぁ、思い出しただけでもワクワクします!是非、電子版で!
1投稿日: 2015.05.12
走れメロス
太宰治
角川文庫
誰かこの謎を解いて下さい(評価はパス。コメントのみです)
私にとっては分かったつもりでも、未だ作者の真意がはかりかねる作品です。 つまり、教科書で読んだ当時は道徳的教訓に富んだ美談として読みました。恐らく、この話が好きな人も 嫌いな人も、多くの場合そう読むでしょうね。 私が分からないのは、作者は何故、主人公の名前をメロスにしたのか、ということです。 太宰治ならではの皮肉か、それとも何かの寓意を込めたのか・・・。永い間、察しかねています。 勿論、本作の着想が壇との熱海事件に起因するのは間違いないでしょうから考えすぎかも知れませんが。 急いで解決したい疑問でもないのですが、どなたか分かる方は教えて下さい(笑)。 あ、ご存知ない方も居るかもしれませんので、ご紹介しておきますと、メロスというのはギリシャ時代 の都市国家の名前です。専門ではないので非常にザックリした言い方で勘弁して欲しいのですが、アテネ とスパルタのペロポネソス戦争のとき出てきます。自由を掲げるアテネと、軍事国家スパルタ、その間 に位置していたメロスは中立の姿勢を堅持します。そのメロスをアテネ(注1)が攻撃し全滅させてしま いました。アテネの戦後処理は苛烈を極めたようです(注2)。まぁ、アテナという女神がそもそも戦いの神様 でもあるのですが、一般的なイメージとしてはアテネが正義、スパルタが悪という図式のようなので何か 太宰には言いたいことが有ったのではないかと考えてしまうわけです。うーん。 注1:スパルタの書き間違えではないです。もともとスパルタの植民地が独立した経緯があるので、 それも影響しているのかも知れませんが。 注2:寛容な戦後処理など歴史上少数でしょうから強調する必要はなかったかも知れませんね。
0投稿日: 2015.04.29
17年と13年だけ大発生?素数ゼミの秘密に迫る!
吉村仁
サイエンス・アイ新書
【内容ではなく媒体の問題として】
ゼータ関数を本当に表層的に調べている中で、ついで程度のつもりで本書を買いました。 内容は、十分面白いですよ。でも、ね・・・。 うっかり表示を見落としましたが、専用機でしか読めないんです。 しかも、字が小さいんです。 さらに、文字サイズの変更が出来ないんです。 そのうえ、フォントの濃度が薄いんです(薄墨みたい)。 つまり、超絶見難い紙面なんです。 一緒に購入した「素数に憑かれた人々」も文字サイズの変更はできませんが、PC上のブラウザで読めるのでまだ逃げ道があります。が、こちらは逃げ道なし、何としてでも専用機で読むしかない。 紙面の印字領域だけを拡大して凌いでいましたが、本当に泣きたくなりましたorz フォントの濃度が薄く見えるのは、原本の印刷の影響だと思いますが、どうなんでしょうか? また、写真、図表も多いのですが、写真や図表のある頁はロード時間が凄く重いです。それもイラッとくるレベル。 私は専門書こそ電子書籍化が望ましいという自論を持っているのですが、課題が多そうですね。 それと、セミの接写写真が多いので、虫がキライな人は避けた方が良いかも。 昔なっかしいジャポニカ学習帳は、昆虫写真の表紙を、虫が苦手という教師や保護者、生徒・児童の苦情で止めるのだとか・・・。
0投稿日: 2015.03.28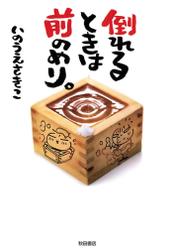
倒れるときは前のめり。
いのうえさきこ
ヤングチャンピオン
国語センスが秀逸な作家です
一番のお勧めは、電子化されていませんが「理由は聞くな。大人なら。」とか「大まかに生まれた女。」、「もっと大まかに生まれた女。」ですが、本書も面白いですよ。 二宮知子の酔っ払い研究所と、まぁ同じような話が多いですが、お酒ネタ以外の笑いもはさみつつ、連綿と”いのうえワールド”が続きます。その世界は(関東人の私には判断できませんし、作者本人は関西人の笑いと主張していますが)ダジャレとトホホ系のオチです。 個人的には、その笑いの中で使われる国語のセンスが面白いです。きっと、関西風の言葉遊びの文化背景が生きているのだと思います。例えば、本書の題名も面白いと思います。 更新が長期間途絶えることも多かったブログ「ことのはマッスル」も最近は順調のようで目出度いことです。 安定して面白い作家なのに何故売れないのでしょうね?好き嫌いが分かれるのでしょうか? 是非、一度、読んでみてください。
1投稿日: 2015.03.16
竃猫さんのレビュー
いいね!された数64
