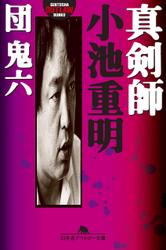
真剣師 小池重明
団鬼六
幻冬舎アウトロー文庫
果報な人だ・・・
西村賢太の作品を地で行くような人生を垣間見る。 多くの人が、きっと迷惑を蒙っただろう。また、少なくない人に嫌悪されただろう。私自身、現実世界では、絶対に係り合いになりたくないと思う。 本人も自分の人生に満足して、この世を去った訳でもないことは明白だ。 でも、果報な人だと思う。 だって、迷惑な奴だ、困った奴だと言いながら、こんなにも長い長い弔辞を書いてくれる人がいるなんて、そうある事じゃない。そう、これは一遍の弔辞なのだろうね。
1投稿日: 2017.02.27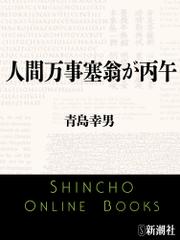
人間万事塞翁が丙午(新潮文庫)
青島幸男
新潮文庫
人生いろいろ
才人、青島幸男の御母堂を主人公とした物語。桃井かおりが演じてTVドラマ化もされたもの。まさに、諺のとおり起きた出来事が結局、良いのか悪いのか分からないという、市井の生活者なりにジェットコースターのような人生が展開されます。こういう先達の苦労は勉強になるなぁ。個人的には、ご尊父の商売人としての時代の読み方は、ヘぇと思って読みました。 登場する脇役達も、味のある人物ばかりの役者揃いです。もし、現実も作中と同じような生活だったとしたら、さぞ賑やかな日常だっただろうと羨ましいです。それは、江戸の残り香のする昔懐かしい風景なのかも。作中では御母堂とご尊父の馴れ初めから嫁入りするまでの著者の語り口に江戸っ子らしさ感じられる気がしますので、是非、味わって一読をお勧めします。 どうも、渡世の苦労に今昔で大差があるや無いや知れませんが、今の世の中、なにかにつけ”ギスギス”し過ぎた感じがありはしないでしょうか。同じ苦労をするにしても、塞翁が馬と受け流せれば、心に少しは空気も入るのでしょうか・・・。
0投稿日: 2017.02.17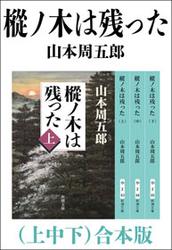
樅ノ木は残った(上中下) 合本版
山本周五郎
新潮文庫
シリアス版『男はつらいよ』か、いや、漢の鑑か・・・
命を懸けても守りたいもの、守らなければならないものがあった、そして守り切って微笑しながら死んでいった、しかも汚名を残すことを承知の上で・・・、そんな漢の生き様を根性なし腑抜けの私が読みました。 現在に続く大河ドラマのご当地ブームのきっかけになった原作です。 ひたすら救いのない、読んでいて、苦しくなる物語。全てを放擲して出家でも脱藩でもしたらどうかと、逃げるは恥だが・・・(苦笑、オッホン(咳払い))、少なくとも命は落とさないのにと、何度も思って読みました。山本周五郎にしては主人公の社会的地位が高いものの、周囲との”しがらみ”や自分に課せられた責任・使命を全うしようとして悩み苦しむ姿に貴賤の差はないようです。本日は山本周五郎の命日にあたり、読売新聞のコラムでもエピソードが紹介されていました。それによれば、あらゆる受賞を辞退したそうですが、その姿は主人公と重なって見えはしないでしょうか・・・。 主人公が守ったものは教科書的には、伊達藩の存続、ということになるのですが、「何を守ったか?」に対する読み手の解釈が本作に対する評価に深みを与えてくれると思います。あなたは、どう思いますか?私の解釈は・・・恥ずかしいので書けませんm(_ _)m。 山本周五郎、次に読むのは宮本常一と名を連ねている『日本残酷物語』の予定です。
0投稿日: 2017.02.14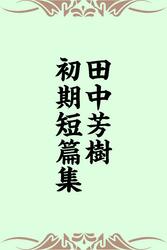
田中芳樹初期短篇集
田中芳樹
らいとすたっふ文庫
喜んで”人柱”になりました。
収録作品が明記されていなかったので購入を躊躇しましたが、どうせ何が入っていても損はないと思い直した次第です。1978年から1980年にかけての以下の作品が収録されています。ご参考にして下さい。 「緑の草原に・・・・・・」 「いつの日か、ふたたび」 「流星航路」 「懸賞金稼ぎ」 「黄昏都市」 「白い断頭台」 「品種改良」 「深紅の寒流」 「黄色の夜」 「白い顔」 「長い夜の見張り」 「炎の記憶」 「夜への旅立ち」 「夢買い人」 「ブルー・スカイ・ドリーム」 「銀環計画」 「訪問者」 「戦場の夜想曲」 「闇に踊る手」 「死海のリンゴ」 個人的には、アルスラーン戦記もいいですが、”中国もの”の電子化を期待して首を長くして待っています。 特に「天竺熱風録」は知らない人はビックリするだろうなぁ。苦行の種類が違うから、三蔵法師より凄いとは言わないけど、確実に”彼”は同じ水準の偉人であることは確か。あと、『黒竜潭異聞』中の各短編も魅力的ですよね。「宛城の少女」なんて痛快だと思うのですが、早く電子化しませんか?
1投稿日: 2016.08.20
もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『イノベーションと企業家精神』を読んだら
岩崎夏海
ダイヤモンド社
もし夏休みの読書感想文の宿題やレポートにするなら
延々とあらすじを書いてページ数を稼ぐのも、ある程度は仕方ないかと思いますが、せめて本書の中で紹介されている「マネジメント理論を、こう適用した」という内の一つくらいは、特に取り上げて自分なりの意見を書くべきではないかと思います。なかでも「ノーバント・ノーボール」作戦を考え出したくだりは、外したくないポイントでしょうね。欲を言えば、開成高校野球部の「弱くても勝てます」との比較に言及があると、評価が高くなるのではないかと。
1投稿日: 2016.08.15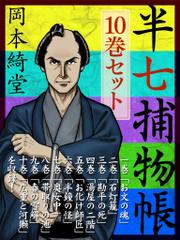
半七捕物帳 10巻セット 『お文の魂』『石灯籠』『勘平の死』等どこから読んでも楽しい岡本綺堂の人気シリーズ「半七捕物帳」セット
岡本綺堂
ゴマブックス
注!伝七に非ず、半七なり。
私自身は間違えて買った訳ではないのですが、NHK-BSのドラマに合わせて伝七の原作を買おうとしている若者は、ご注意を。 シャーロック・ホームズに触発されて、わが国で初めて創作された推理小説が、この半七シリーズ。と、まぁ言われているものです。本製品には抜粋ではないものが全作品が収録されており、お値打ちものと思います。もっとも、10作品とも、中短編といった分量ですので。 余計なお世話かと思いますが、鑑賞のアドバイスとしては、トリックの謎解きや推理を楽しもうというのではなく、壮年期の半七の粋(いき)と、老人となった半七の語り口、佇まい渋さを、じんわり味わうのが宜しかろうと思います。 江戸から明治へと激変した世の中を映した作品中の空気感が、杉浦日向子の「東のエデン」と通じるものがあるように感じられます。そういう読み方も、面白いかと思います。
0投稿日: 2016.08.15
疵 花形敬とその時代 本田靖春全作品集
本田靖春
講談社
濃厚な昭和の残り香を味わいつつ戦後を考える
「敗戦を終戦などと馬鹿を謂い」とは内田百閒の至言だが、敗戦後より終戦後という表現が馴染んでしまったので、ここでも終戦後と呼ぶとして、終戦後の闇市がバラック建てのマーケットに移り、もはや戦後ではないと言われるまでの復興に至った時代背景を舞台に、花形敬を中心とするアウトロー達の群像劇を見るが如き作品である。 敗戦とは単に戦争に負けるということだけでは勿論なく、その結果として伝統的な価値観、文化や技能の伝承、市井の暮らしぶりや、親から子へ受け継がれてきた生活習慣その他諸々を一挙に喪失することになる、その事を思い出すために、再確認するために花形らの足跡を辿るのは実に有効だと思われる。本書の意義は、花形の人物評価を云々するのではなく、その点に求めたい。 きっと、押井守の『立喰師列伝』を愛読する奇特な人なら、本書を気に入る筈である。何故なら、「あの決定的な敗戦により・・・」を頻出させる押井の問題意識と本書のそれは一致しているうえ、語り口まで似ているからである。 余談だが、高倉健の『唐獅子牡丹』も同じ時代であるものの、根差す精神は伝統的任侠道であり、花形らとは一線を画す、お互いに似て非なる存在であろう。 戦後、我が亡父は糊口を凌ぐため道玄坂で金物屋を営んだそうだ。その隣では元教員が食用にならない米で煎餅をつくり菓子屋を開いており、高等教育を受けた少数ということでお互い商店街組合の役員をしていたという。その菓子店は現在、有名企業となっているが亡父は一介のサラリーマンで終わった。本書で本田は自身と花形を比較し、彼我を隔てた差はほとんど何もなかったと言っているが、あの時代とはそういう人生が行き交う時空間であったのだろう。
0投稿日: 2016.08.07
レナードの朝〔新版〕
オリヴァー・サックス,春日井晶子
ハヤカワ文庫NF
ただし、映画の方が感動的ではある
同名映画の原作。映画の方は、もう、「騙されたと思って取り敢えず観とけ!」、と強要しても良いくらいのレベルに傑作。だが、本作はレナード以外の患者も含めた、ノンフィクション作品。映画はレナードを取り上げ、ノンフィクション化しているので、より感動的になっているので、その点は注意されたい。率直に言えば、難しく、硬い。ただし、映画と同じく、人生に対し疲れちゃった気分になったとき、ヤケな気分になったときに、パラパラめくると襟を正された感じになる。完読しなくても、本棚に置いておく”御守り”としてお勧め。
0投稿日: 2016.06.22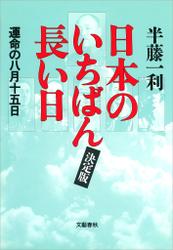
日本のいちばん長い日(決定版) 運命の八月十五日
半藤一利
文藝春秋
意思決定論の問題として読んでも圧巻の一冊
大事を決めるときの意思決定プロセスとは、どうあるべきか? 勿論、サイモンら米国流の組織的意思決定論はあるにはあるが、一国の命運を決するような場合はどうなのか・・・。 非常に興味深いが、極めて事例が少なく、かつ、データが収集し難いテーマだ。 3.11やリーマン・ショック以降、レアイベントに係るリスクが関心を集めているが、そのリスクが顕在化したあとのディザスタリカバリフェーズでの意思決定論に、個人的には特に関心がある。 しかも、その意思決定がわが国の国民性に馴染むものであるべきと考えると、本書に見られる合意形成プロセスは実に含蓄に富んだものと思えてくる。 『失敗の本質』と並んで、ビジネスマンにも是非お勧めしたい。
0投稿日: 2016.06.19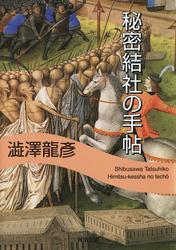
秘密結社の手帖
澁澤龍彦
河出文庫
かの人の語る如く語る人を知らず
昔から、『カソリック教会の転覆を諮る秘密結社の首領を、謀略が成就する一歩手前で追い詰めたら、地方の平凡な修道院の”うだつ”の上がらない万年修道士だった』、といったモチーフの物語が読みたいと思っていた。残念ながら本書は実在の秘密結社を紹介した真面目なものである。知識欲が旺盛な人には興味深く読めると思う。 翻訳物を巡る係争および世評に関しては、一旦、置くとして、それを煽るかのような本人の言動や露悪的な態度は、もしかしたら演出または屈折した心理の発露でもあったのだろうか、と思える。本作などは噂に違わぬ博覧強記ぶりを遺憾なく発揮しているほか、行間に垣間見える著者の判断能力は健全な良識人のものである。澁澤龍彦という個性についての更に深い今後の研究が待たれよう。 ”営業妨害”になるやも知れないので、”あちら”にはコメントを付さないが、桐生操の秘密結社に関する著作の主要部分は本書からの引用でもある。より硬派ではあるが、オリジナルを味わうのも一興と思う。
0投稿日: 2016.06.13
竃猫さんのレビュー
いいね!された数64
