
身体を売ったらサヨウナラ 夜のオネエサンの愛と幸福論
鈴木涼美
幻冬舎文庫
「飽き」こそ我が救世主
日経記者がAVに出演していたと話題になった鈴木涼美さんの記事を最初に見たのはBLOGOSの記事だったか、週刊文春で火がついたようなのだが在職中に「AV女優」の社会学と言う東大大学院時代の論文を加筆修正して出版しており、この記事以前にAV女優としての経験を語っているというのでどうも隠していたのがバレたということではないらしい。BLOGOSのリンク先に本人の緊急投稿が載せてありそこで書いていることがなかなか興味深いので覚えていた。著書の中で「AV業界をうろうろしながら」と意図的に自身のAV出演経験を隠していたことについて、「AV出演の経験を持っていることは、AV業界の魅力や問題点を知るのに、圧倒的に有利だったのではないだろうか。その自分の優位性を1行目で告白しないことは、研究者倫理に照らし合わせててどうなのか、少なくとも書き手の姿勢としてどうなのか。読者への敬意にかけるのではないだろうか。」「日経記者がAV女優であることよりも鈴木涼美がAV女優であることのほうが余程大きな問題をはらんでいる、と私は思う。」 ここだけ取り上げるとすごく論理的なのだが本書の中ではもっとくだけている。高校時代はブルセラショップに通う渋谷のギャルが1年間勉強して慶応のSFCに入学。しかし在学中はキャバ嬢として働きついでにAVにも出演した。モラトリアム期間が欲しくて東大大学院に入りその時の研究テーマが「夜のオネエサン」、卒業後は地味な日経記者になり今では文筆業というような経歴だ。この本では主にキャバ嬢時代から日経記者時代(仕事の話はないが)の自分と周囲の夜の世界の話が中心になっていてとりとめはないが文章は読みやすい。 ネタバレにならない程度に少し紹介するとこんな感じ。 「どんなに偉いオヤジが、「魂に悪い」と言っても私たちはキズつかないけど、好きな人がゲロまみれになっている光景には、それなりにひるむ。 問題は、そこで得られるオカネや快楽が、魂を汚すに値すると思えるかどうかであって、いいか悪いかではない。好きな人にゲロ吐かせてまで手に入れたいものだって、私たちにはあると思う。言い換えれば、少なくともそれに値すると思えないんであれば、そんなはした金、受け取らない方がいい。」 「私たち、結構ごみみたいな生活が嫌いじゃなくて、むしろ積極的に汚れることが、どうしても必要な時期ってあるのよね。オトコは、クソであればクソであるほど、たまに私たちのごみ生活を飾る、最高のごみになる。」 「私は極度にハマりやすい性格である反面、極度に飽きっぽいらしい。そしてハマりやすい性格によるあらゆる人生の罠から、飽きっぽい性格によって救われてきたのである。「飽き」こそ我が救世主。スカウトマンとの破滅的な同棲生活からも、夜のオネエサンとしてのくだらない生活からも、ホストとの実らぬ生活からも年収1億円の投資銀行家との勘違いセレブ生活からも、ドラマみたいでちょこっと楽しいってこと以外は何も生まない社内恋愛からも、大学院生としての国会図書館に引きこもった生活からも、いつもぎりぎりのところでアイツがやってきて、私を救い出してくれたのだ。」 こうして見ると感覚的な文章にはほど遠いな。 母親との会話が時々出てくるのだがこの母親がなかなかかっこいい。調べればわかるがある世界では有名な人らしい。週刊誌的には父親の方が話題なのだが。 「あなたって割と安っぽいよね。私は確かに自分にとって魅力的ではないオトコからの評価も欲しかったけどそれに応えて与えちゃったらダメなのよ。彼をショボいというなら、そんなどうでもいい小さなメリットのために彼と付き合ってるあなたこそショボい。」 「でもママも、どうしようもないショボい勘違い男とか、馬鹿な男とか、鼻をへし折って、ヒールの先っちょで自尊心をぐりぐり踏みにじりたい、とか思うこともあるでしょ?」 「それは生き様で見せればいい。そもそもそんな男が寄り付けないくらいにすごくなれば?あなたはさ、そういうバカな男を相手にしながら、中途半端にぐりぐり虐めて、それで買わなくていい反感を買って、結局自分がいちばん割を食ってるイメージ」 著者紹介は自分で書いてる様だ。 1983年、東京都生まれ、蟹座。 慶応義塾大学環境情報学部卒業。2009年、東京大学大学院学際情報学府修士課程修了。専攻は社会学。大学院修了後、会社員時代に出版した著書「AV女優の社会学」は小熊英二サン&北田暁大さん強力推薦、「紀伊国屋じんぶん大賞2013 読者と選ぶ人文書ベスト30」にもランクインし話題に。夜のオネエサンから転じて昼のオネエサンになるも、いまいちうまくいってはおらず、2014年秋、5年半勤めた新聞社を退社。
0投稿日: 2019.12.12
神は数学者か?──数学の不可思議な歴史
マリオ リヴィオ,千葉 敏生
ハヤカワ文庫NF
数学は発明なのか発見なのか
「数学はなぜこれほど上手く物事を説明できるのか?」それを言い換えたのがこのタイトルの「神は数学者か?」日本人にとってはキャッチーな上手いタイトルだがキリスト教圏などではもう少し刺激的な意味があるのだろう。 ピタゴラスやプラトンなどの哲学者の時代の影響は長く、中世の大学のカリキュラムは三学すなわち弁証、文法、修辞と四科すなわち幾何学、算術、天文学、音楽からなっていた。なぜにここに音楽がと思わないでもないが、音は振動だし、惑星が奏でたという「天界の音階(ハルモニア)」という話もある。ヨハネス・ケプラーは惑星ごとの作曲までしている。ホルストの交響曲「惑星」はさらに3世紀後のもので平原綾香の「ジュピター」に続く。 アリストテレス、アルキメデス、ケプラーにガリレオと続く数学はデカルトの座標によってユークリッド幾何学と代数学が結びつく。高校の数学でいうとX2+Y2=a2が円の座標を表すというやつだ。そしてニュートンのプリンピキア(自然哲学の数学的諸原理)でとうとう惑星の動きが万有引力を元にした数学的な計算に非常に良く一致するという最初の頂点に到達する。 最初の質問に答えるために数学のたどった歴史を現代までおいかけ、非ユークリッド幾何学、統計学、トポロジーや不完全性定理、そしてアインシュタインの重力理論まで続く。これはこれで良い読み物だ。 アインシュタインが良い例だが理論物理学者は数式で物理学の理論を表し、もしその理論が正しければこういう減少が現れるはずだといくつもの予言をしそれは次々に確認されてきた。大きな重力により光が曲がることは日食のときの星の位置で確認され、速い速度で動く物体は時間の流れが違うことも確認されGPSでは当たり前のように補正がされている。そこで最初の質問に帰ると「なぜ数学はこんなに有効なのか?」という答えのない疑問にぶつかる。数学は発明なのか発見なのか? この宇宙で物理法則が破綻なく守られ、その法則が数式で表されるとすると物理法則は数学で表されることになるが、だいたいこういうことは証明できない。例えば超弦理論の場合9次元だか13次元だかは忘れたがそこまで考えると理論がよく一致するという。数学が有効ならば9次元は存在するのか?わかるとは思えない。そう言えば超弦理論の大栗先生もちょろっと登場している。宇宙論には多元宇宙論などもあるがもし神が数学者なら多元宇宙はこの宇宙と同じようにできているのか?? 例えばもし重力の定数がもっと小さければ星間物質は集まらず星は生まれなかった。逆に大きすぎればビッグバンの後重力が勝って宇宙は収縮してしまう。最近の研究では宇宙のはては加速している証拠が得られたという説があり、これは引力ではなく斥力が働いていることになるのだがその原因物質といわれるダークマター<暗黒物質>が何者かも良くわかっていない。数学はこれらも説明することになるのか。ひょっとすると神がいるとしてもやったことはいくつかの素粒子と定数を決めることだけなのかも。 翻訳の千葉氏は似た様な感想をミジンコを例にだしている。ミジンコそのものが一つの宇宙だとしたら、ミジンコ宇宙の中にはミジンコ素粒子があり・・・・それはさすがにないだろう。 最後にクイズをひとつ。連続する数字n,m,l,o,pにたいしてn2+m2+l2=o2+p2=?となる数字がある。この答えを見ると数字にはなにかあると思ってしまうかも。
0投稿日: 2019.12.12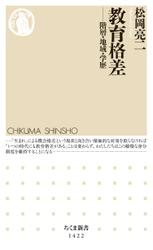
教育格差 ──階層・地域・学歴
松岡亮二
ちくま新書
ふつうの話は同じではない
ふつうに育ってくれれば良いと親は言う、しかしそのふつうは例えば住むところによっても大きく違う。例えば通勤時間、家賃、教育環境などで住む所を選ぶと階層が似た人たちが集まって来てそこには町の文化が立ち上がる。例えばこの街では中2から塾に通うのがふつうと言ったように。それぞれの家庭や地域や学校での教育格差はどうやら小学校に入る前には現れ、ずっと持続しているのが日本の社会だ。日本が特殊と言うことでもなくOECDの報告書からは、どこの国も「生まれ」によって学歴達成格差のある緩やかな身分社会であり、学歴によって社会経済的便益が異なる学歴社会なのだ。少なくとも国際比較が可能なデータでは、日本の15歳の能力は高い。しかし格差という見方をすると平均的だ。教育界で礼賛されることが多いフィンランドを含めどのような社会であっても格差を埋めることは難しい。教育業背だけではなく、税の再配分を含めてどれだけ平等主義的にしても、SESによって15歳時点の学力格差が明確に存在するのだ。 日本では親の学歴と世帯収入は大きく重なり、本書では親の学歴を大卒0、1、2人の3階層に分けて格差の実態をこれでもかと並べている。この元になるのがSES、社会経済的地位という考え方だ。世帯収入だけでなく、経済的、文化的、社会的要素を統合した地位を意味する。似通ったSESの階層では親の子供に対する働きかけ方が似てくる。そして格差は小学校入学前にすでにあらわれ、そのまま維持され、高校では偏差値によって固定化されている。 SES階層の違いによって様々な行動で違いが見られる。親子の大学進学希望率、私立校への進学、1日あたりの学習時間、メディア消費時間、蔵書数、学校活動への参加、親から子への関与の度合い、習いごとの数や塾に通う時期などなど、明確な相関関係が見られるのだ。全国共通の教育指導要領と義務教育は格差を縮める方向に働くが例えば夏休みにはその差が開く。継続して学習する環境があるかどうかと言って良いのかもしれないがどちらも普通の生活を送っている。 私たちにとってはごく当たり前の高校ランキング制度は世界的にかなり特殊だ。義務教育段階で「生まれ」による学力格差を埋めないままの「能力」選別は、SESによる分離(隔離)を制度として行なっていることになるのだ。高校受験に失敗しても大学受験で敗者復活する者もいるが、その生まれは高階層出身者に大きく偏っていた。そして低ランクの高校教師は達成感の無さのためか生徒に期待していない。生徒は諦められている。 これまでの様々な改革と言われるものはこういった現実を見ないものだった。例えばよく言われる大学無償化をしたところでSESごとの元々の格差は埋まらない。経済力だけが大学進学の格差の理由ではないからだ。学校群制度は高校による能力選別の解消を目指したものだったが高学力、高SESの生徒は私学に流れた。結果として同じ学内にロールモデルがあれば高ランクの大学を目指していたかも知れない生徒から機会を奪うことになってしまう。 基本的には「平等」に軸を置いて「公平」をめざす介入か、個人の「自由」による「優秀さ・効率」の追求かという価値の相克に話が戻る。1つの価値軸を重視することは誰かの血が流れることを意味し、同じ扱いでは結果が出ず、選抜という現実があり、データによる現状把握をすると「自己責任」の名の下に格差が拡大する姿があらわになる。 ではどうするか、まずは現状をデータで把握すること、そして教職課程に教育格差のカリキュラムを入れること。少しでもましな対策を取るためには改革の効果を測定しないとできない。
0投稿日: 2019.11.18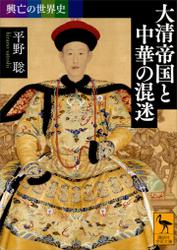
興亡の世界史 大清帝国と中華の混迷
平野聡
講談社学術文庫
モンゴル、チベットはいつから中国に組み込まれたのか
中国の歴史上中華の統一を果たしたのは秦の始皇帝だがその範囲は北は万里の頂上、南は長江流域、西は四川盆地といったところで主に中原を中心とした範囲だ。漢の武帝の時代に張騫が西域を平定し、朝鮮、ベトナムまで支配下に置いたのが漢人帝国の最大領土になる。中国の領土が最大になるのはむしろ騎馬民族の隋唐帝国、モンゴルの大元ウルスそして本書の満州人の清の時代で、現代の中国はかなりの部分清の枠組みを引き継いでいる。 東北三省、内モンゴル自治区とモンゴル人民共和国、新疆ウイグル自治区、青海省、そしてチベット自治区は歴史的には漢人支配ではなかった時期が長い。中華世界では対等な外国との通商は基本的には無かった、そこに西洋が入ってきて幕末から明治の日本と同様に清末の中華は西洋の国際的な枠組みに適応していった結果が今の姿につながっていく。 女真族を統一し後金を建国し東北部を勢力下に置いたヌルハチに続き、モンゴルを破り皇帝であると同時にハーンの称号を継いだホンタイジは盛京(瀋陽)で清を建国した。満州という名前はヌルハチのマンジュ部から来ており文珠菩薩に因んだものと言われる。地名が先ではなく女真族が満州人となったのが先だ。 15世紀にツォンカパが発足したチベット仏教のゲルク派はダライ・ラマ3世とモンゴルのアルタン・ハーンの会合を契機にモンゴル部族の中に拡がっていった。モンゴルは今日のチベット自治区一帯を征服しダライ・ラマ5世に寄進しここからポタラ宮の造営が始まる。ダライ・ラマはモンゴル語で大海の如き上人と言う意味である。ホンタイジがモンゴルのハーンとなったことで中華を取り囲む清、モンゴル、チベットという巨大な連合体が生まれた。北京に遷都した清の第3代順治帝はダライ・ラマ5世を相互対等の立場で招聘しその後いろいろあったが、続く雍正帝がチベット仏教を庇護する文珠菩薩皇帝としての名声を高めることになる。モンゴル、チベット、東トルキスタンは同君連合として清の間接統治下の藩部となった。 満州人のアイデンティティを重視した清は中華に染まるのを嫌い今でもモンゴル語、ウイグル語、チベット語には中華の概念は翻訳されていない。雍正帝は自らを夷狄とした上で中華の優位を謳う華夷思想を批判した。雍正帝の使った中外一体とは中華も夷狄も上下の差はなく真の皇帝の元で臣民として平等だという思想であるが結局これが現代中国の版図の正当性を訴える元になっていく。続く乾隆帝の時代に最大の栄華を誇った清は19世紀にはアロー号事件、アヘン戦争を経て思わぬ転落を続けていくことになる。 西洋の国際関係では冊封国は独立国となる。琉球は清と日本に対する二重冊封国だったが国際法の枠組みに先に適応した日本が取り込み既成事実を重ねていった。台湾についても清が化外の地=無主の地と捨て置いたのが日本が占領した根拠となった。そして朝鮮は朝貢国のままで清に事えようとして失敗した。伊藤博文は李鴻章との日清修好条約改正交渉の中で八重山、宮古を清に割譲すると提案し、大戦後も国民党の蒋介石が要求を取り下げなければ沖縄は日本に戻って来なかった可能性が高い。「固有の領土」というのは歴史上のある時点を切り取りそこに近代の国際法を当てはめたものだが辺境はその時々の国際関係に翻弄されている。 夷狄=辺境の国家であった清が中華と一体したことがチベットやウイグルが中国の固有の領土という正当性の元になったのだが、実態としては自治区と言う名で辺境としての管理になっている。清があれほど強大ではなかったり、太平天国がもう少しまともで中華が清から分離独立していたりしたら満州やウイグルやチベットは今頃独立国だったかもしれない。
0投稿日: 2019.11.13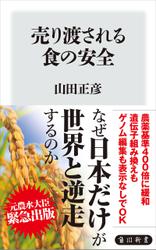
売り渡される食の安全
山田正彦
角川新書
国の関与による安全保障と民間への開放のバランスなのでは
モンサントがかなりえげつない企業だというのはこの本にも映画が紹介されている、マリー=モニク・ロバンの書いた「モンサント」に詳しい。EPAやFDAを手玉に取り、モンサントの種子が意図せず紛れ込んでしまった農家相手に訴訟を起こし、古くはダイオキシンの安全性データを捏造した。それでも農家は善で企業は悪だと言うように描くのは一方的に感じた。 企業は常に悪者なのか?ファクトフルネスでは犯人捜し本能で人は自分の思い込みに合う悪者を探そうとすると指摘してあったが典型的な悪者は「悪どいビジネスマン、嘘つきジャーナリストそしてガイジン」だ。山田氏は国内農業保護の立場にあり、対するはいかにも悪者のモンサント。構図としてはわかりやすい。では企業は悪者なのか。 日本モンサントのF1品種を育てる契約をした農家は禁止事項や損害賠償について書かれたA41枚の英文?の契約者を「いや、ほとんど読まずにサインした」と山田氏に答えている。また、住化アグロがセブンイレブン向けにJAに米の生産を委託した契約ではJAから栽培を委託された農家について「両者(相手がJAか住化アグロか読み取れない)の間には契約書はなどは存在していないが、農家もまた住化アグロとJAとの間で交わされた契約書内に記された義務や責任を負うことになっていた。」とある。農家が不利な契約を押しつけられたように見えるがこの文章からは判断できない。ついで検査は住化アグロが行い、不合格品は生産者側の負担とすると言う工業製品であればまあ当然の内容について一方的と批判するが企業側の感覚では普通の契約だろう。米の買取価格については収穫終了時に「収穫量、品質、米相場に鑑み、別途協議の上決定する」とあるのだがこれはそもそもJAがもう少しましな契約を結ぶべきなのでは?同じ内容をそのまま農家に押し付けてるのであればJAなどいらないと言う話だ。 GMOについては十分に安全性を確認したのかと言う指摘はその通りだろう。一般的な品種改良は時間がかかることが安全性の確認にもなっている。消費者が選択できるような表示義務をというのも妥当な意見だと思う。ただほかのリスクについてはどうか。例えばグリホサートについて人に対しておそらく発がん性があるグループ2Aに指定されたことが書かれている。いかにも危ないものと読めるがより危険なグループ1に含まれるものにはタバコ以外に日光やアルコール、加工肉などもある。赤肉は同じく2Aだ。量を無視して発がん性のあるなしを議論しても役には立たない。 1代限りのF1種子の価格が数倍になったことを問題視しグラフを載せているのだが単位はドル/エーカーで米やトウモロコシであれば過去20年で20ドルが100ドルになっている。1エーカーは約40千平米種子代の上昇より得られるメリットが明らかに大きいとしか読めない。また昭和30年代に1粒2円だったイチゴの種子が今では40ー50円のF1種子になってしまったともあるがこれの何が問題なのだろうか、全く理解できないのだ。 グリホサートに代わる新たな除草剤として天然の非毒性成分が用いられたファームセイフを輸入したいと書いてあるので調べてみたがその有効成分は酢酸1ー5%と塩酸1%未満、そして水を含む無害な成分80ー95%だった。この除草剤は雑草のクチクラ層を分解し枯れさせると言う事なのだが、効果があるとすれば栽培植物も枯らすのでは。まあ安全性の試験をした上で効果があれば切り替えれば良いだけの話だろうがこんな組成が有効なのだろうか? 一般の農家は手間もコストもかかる自家採種には積極的ではなく米の場合自家採種は約1割にとどまる。企業がF1品種の自家採種を禁止するのはそれを認めると事業として成立させるのが難しくなるからだろう。モンサントのように意図せず育ってしまったものまで訴えるのはやりすぎだが。コシヒカリの種子は税金が投入され原原種、原種を専門の採種農家が育てた結果500円/kg程度で売られている。1粒の米は収穫後3〜400倍になるのでここでも原材料費としてはたいしたことはない、税金の補助がkgあたりいくらか知りたいところだ。民間の進出を種子法は妨げていないと主張しながら米の品種改良に費やされる膨大な時間と労力、そして予算を税金でまかなっていると誇る、それこそが企業から見た場合の参入障壁なのだ。種子の多様性を守り、安定した量の供給を保障するために税金を使うことは意味のあることだが本来はどの程度が適当かという話になるべきだ。全般に意図したかどうかはともかく印象操作をしているように感じた。
0投稿日: 2019.10.02
戦前日本のポピュリズム 日米戦争への道
筒井清忠
中公新書
戦前日本が特殊なわけではない
文在寅の韓国の行動は国際関係から見ると理解し難いが、ポピュリズムが基底にあり国民感情を優先していることは間違いない。これを韓国の国民性と言ってしまえないのは戦前の日本もポピュリズムの強力な圧力に屈していたことからだ。 日露戦争開戦当初、国民の戦争支持は熱心ではなかった。しかし新聞社が戦勝を報道し、戦勝会を主催する中で盛り上がっていった。その行列の解散場所が日比谷公園だ。まだ戦中の1904年5月8日には死者が21名出るほどの熱狂を見せている。新聞社、政党人などを中核に暴力的大衆との結びつきがポーツマス講和条約反対運動、護憲運動、普選運動などを盛り上げたのだが、群衆は警官とは戦っても軍隊とは戦おうとしなかった。その後ろにある天皇の威光と戦うことはないからだ。幕末の武力倒幕から日比谷焼き討ちを経て2・26事件まで構造的には「君側の奸」を打つという思想的な共通性が見られ、天皇をシンボルにした政治利用とポピュリズム化についてはこの後も繰り返しあらわれる。後の5・15事件報道も似たような構造で新聞は元老、財閥、特権階級への批判を正当化し、「小説的・物語的面白さ」はたえず追求されていく。裁判の中でも赤穂浪士になぞらえられ、徳富蘇峰は渋沢栄一だ関東大震災を「天譴」と称したのを持ち出し、5・15事件「人譴」になぞらえ首相暗殺犯の「所信を社会に実行せし」と唱えた。別の新聞は「各被告の同期に至っては、憂国の純情そのものであって、日本国民にして何人か、かりにもこれを憎むものがあろうか。従って動機のみより言えば、却ってこれを表彰こそすべきで、罰するはずはないのである。」とまで書いている。 大正期のポピュリズム的な運動はナショナリズムと平等主義に方向付けられたが、このナショナリズムは排日移民法を受け反アメリカに向けられ、親中国的なアジア主義の高揚が見られた。平等主義については普通選挙の実施という非暴力的な運動の成果が生まれた。ポピュリズムそのものには方向性はなく世論は時には大きく方向を変えていく。 ワシントン海軍軍縮会議では対米7割の支持は2割程度で、対米6割で早期妥結支持が6割あった。海軍は対米7割を達成できなかった理由を世論形成の失敗と捉えロンドン会議では新聞社に協力を要請する。海軍の意向に新聞が踊った結果、世論は対米7割を絶対視するようになったが、最終的には財政上の影響と国民負担の軽減を持ち出し新聞は妥結を支持する。国際協調主義の財部財相、若槻全権の帰国を大歓迎で迎えた国民はわずか3年後にはリットン調査団報告書受諾拒否共同宣言を全国132紙が一斉に出したことも影響s、国際連盟脱退の松岡全権を大喝采で迎えることになる。 1931年の陸軍軍縮期には軍人は厄介者扱いをされていた。軍縮を支持していた朝日新聞は満州事変勃発後不買運動の拡がりに大きく部数を落とし、満州事変支持に転向する。これに対し当初より満州事変を支持していた毎日は部数を伸ばしていっていた。戦争と、その大々的報道という「劇場型政治」が展開され、世論は急速にその支持に傾いていった。対外危機は大衆デモクラシー状況におけるポピュリストの最大の武器である。 「最低でも県外」と訴えた鳩山由紀夫はポピュリズムの失敗例だろう。民主党への期待は裏返り政権を取ることだけが求心力だった民主党は解体した。民主主義である以上ポピュリズム的な要素は常にあり、合理的な判断が優勢な間は大きな問題にはならないだろう。ただ小選挙区制では支持率の差以上に議席数に差がつくのでポピュリズム的な手法はやはり魅力的なのだ。国際的な関係の中で現実的な最適解がポピュリズムの求める方向と一致しない場合には気をつけたほうが良い。
0投稿日: 2019.08.31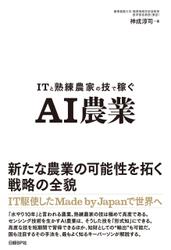
ITと熟練農家の技で稼ぐ AI農業
神成淳司
日経BP
60過ぎたら農業なのか?
国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では2065年に総人口は8200〜9500万人になる。直近の出生率からすると中位推計を達成するかどうかも疑問だがこの場合で8800万人と現在の約7割になる、14歳未満が10%、生産年齢人口が4529万人と現在の6割で52%、65歳以上は現在とほぼ変わらず3381万人で38%を占める。出生率が一定の場合はこの後は年齢別の構成比はほぼ変わらない。思い切った少子化対策をするか外国人を受け入れるのか、あるいは人口減を受け入れて社会の構造を全て変えるか、いずれにせよ20年後には大きく変わっているはずで、そうすると経過措置も含めた準備期間は10年〜15年ほどだろう。 会社で言えば今の新入社員が現役のうちに働き手が6割になり、国内需要も同じように減りかねないという話。目先の問題は色々山積みだとしても日本全体で言えばこれがあらゆることに影響する最大の問題のはずなのだ。 本書のテーマの農業に限れば、農業従事者人口と平均年齢は2005年/335万人/63歳、2010年/260万人/66歳、2015年/209万人/66歳だ。2015年65歳以上が133万人、50歳未満は25万人となる。実はこれは将来真っ暗ということではない。現状でも65歳以上が農業をやってるのだ。40年後も65歳以上の人口は変わらないので単純な働き手であればなんとかなる。ただし今の農業だと水やり10年と言われるほど技能の習得に時間がかかる。 問題は熟練者の技術の伝承で、そこでAIの話になるのだが人工知能ではなく、人工知能を含む農業情報科学=AIだった。書名は意図的なひっかけだろう。人工知能=AIについては適用範囲が限定されると考えているようで中心的な話題にはなっていない。ついでに植物工場はコストが高く生産性は高くないと否定的な評価だ。 本書で紹介している事例は簡単に言うと、熟練者の本人も気づいていない暗黙知をモデル化しITを初心者〜中級者の教育に生かすことで、一人前になる期間を10年から3年程度に短縮することを目指している。アイカメラを使い何をどう見ているかを見える化し、外部環境変化はセンサーで測定する。加えて主観的な気づきデータを入力するのが熟練者の暗黙知を見える化するためのポイントだろう。同じような取り組みは工場でもできるし、一部ははじまっている。色や形や匂いに音、そして触覚や味、人工知能でもなかなか勝てない熟練者の技術は確かにあるが、センサーに置き換えやすいものも多い。 それで日本の農業が何を目指すかというと、比較されるのがイスラエルとオランダでいずれも農業の先進国だ。イスラエルは食料自給率が高い農産物の輸出国であり、水不足は点滴栽培で補う。熟練農家は富裕層に属し、キブツの伝統で指導者となる熟練農家を育てる仕組みが特徴だという。広大なビニールハウス、毎日指示をする熟練者と海外からの労働者二人という組み合わせが儲かる仕組みのようだ。 オランダは少人数で、大規模な農場にITを取り入れていることで知られている。施設面積は日本の1/5、生産者数は1/60、単位面積あたりの平均収量は4〜5倍、平均単価は1/3ながら総生産額は日本とほぼ同じ低コスト大量生産が特徴だ。ただし筆者の意見ではオランダは目指すべきではない。規模では周辺国とのコスト勝負になるので熟練者の知恵を生かし、他社には真似できない高付加価値品をめざすべきだという。 ここは新たな就農者をどう設定するかにもよるのではないか。60過ぎて就農する人を考えればコストは勝負できるだろう、2ー3年でものになる作物の栽培が入り口にあっていいはずで、上級者になれば違う農場に移ればいいのだ。いずれにせよ本書のような取り組みは農業以外にも広まっていくはずだ。そうしないと回らなくなるのだから。
0投稿日: 2019.08.27
ビッグデータベースボール
トラヴィス・ソーチック,桑田健
角川新書
リサイン、ラス!
メジャーリーグを変えたマネーボールが出版された2003年以降野球は加速度的に増加する大量のデータとともに、まったく新しい時代に突入していた、チームがデータ分析での競争で遅れを取れば、追いつくことも加速度的に難しくなる。 ポストシーズンを20年以上逃し続けアメリカのスポーツ史上最悪の記録を作ったピッツバーグ・パイレーツの監督を引き受けることはクリント・ハードルにとってはメジャーの監督を続けるには最後のチャンスだった。クリント率いるパイレーツは過去2シーズン続けて後半失速しピッツバーグ市民から見放されていた。「ピッツバーグ:この街にはチャンピオンたちがいる・・・あと、パイレーツも」NFLのスティーラーズ、NHLのペンギンズという強豪チームと違い観客も入らず、予算も充分ではない。GMのハンティントンとハードルは残された僅かな時間で若くもないチームにあまり金をかけずに15勝分の上積みをはからねばならなかった。ハンティントンのデータ処理軍団が提唱したのはこれまで誰も注目してこなかった守備の領域だ。マネーボール以降出塁率の重要性は認識されていたが、これまで記録も分析もされてこなかった新たな領域には2007年以降大量の新しいデータが積み上げられていた。しかし、フロント主導の新しい守備戦術を取り入れるにはピッチングスタイルを変え、守備位置を変えなければならない。野球は素人の分析官のいうことを聞いて打たれたり、これまでであれば平凡な内野ゴロがヒットになったら誰が責任を取るのか。何より極端なシフトはピッチャーにとっては落ち着かないものだ。 2012年シーズンのパイレーツにはメジャーで通用するキャッチャーがいなかった。FAの予算は1500万$しかなくこれで先発投手と野手を取るとFA選手の平均年棒は出せない。パイレーツが選んだのはワールドシリーズを逃したヤンキースのラッセル・マーティンだ。自己最低の打率に終わったマーティンにヤンキースは金を出し渋った。ハードルはマーティンにチーム内にはベテランが必要だと伝えた。肩の強さも魅力だと。しかしパイレーツはマーティンに本人にも隠された価値を話していなかった。それがピッチフレーミング、簡単に言うと捕球のうまさで際どいボールをストライクと思わせる技術だ。審判は無意識にミットの位置に判断を影響される。マーティンはストライクのミットの位置で外れたボールを捕ることができた。カウントが2ー1か1ー2かで打率は2割も変わる。2007年からの5年間でマーティンが防いだ失点はランキング2位の70点、パイレーツのドゥーミットはワーストのー65点で10点を1勝分の価値とカウントするとキャッチングだけで120試合あたり4勝の上積みが期待できる。結果は正しかったが当初ファンはなぜ打てないキャッチャーを取るのかと失望した。 パイレーツも守備シフトを取り入れた。もしバッターがシフトの穴を狙って流し打ちに来れば?やらせておけば良い、ホームランバッターがその特徴を消してくれるのならば。2013年パイレーツは極端な守備シフトを5倍に増やし着実に成果を上げていった。2014年シーズンにはほとんどのチームが追随しメジャーリーグ全体の打率は下がって行く。この先に現れたのがフライボール革命だ。 ピッチフレーミングの技術はマーティンがプロ入り後に身につけたものだ。「ブルペンで捕手を務めている時は、ただボールを捕っているだけではない。常にボールを捕る技術を磨こうとしている」「今ではそのことをいちいち考える必要もない。自然とそうやっている。全員がそうあるべきだと思う」マーティンは主審とも良好な関係を築こうとイニングの合間に話しかける。野球でホームチームが有利なのは微妙なコースの判定だということが統計に現れている。観客の声援に審判が無意識に影響を受けるのだ。 2014年再びポストシーズンに進出する時にはマーティンはパイレーツ史上最高のFA選手となっていた。守備シフトに対応した流し打ちをチームの先頭に立って実行したマーティンの打撃成績はキャリアハイで、出塁率はメジャー4位、ピッツバーグ市民はマーティンが投手に声をかけたり、クラブハウスの規律を保ったりと言う目に見えない価値を学んだ。ファンは野球にかけるマーティンの情熱や競争心の高さを愛するようになった。ワイルドカードの9回裏、バムガーナーの前に沈黙するパイレーツ打線とファンだったがマーティンのパイレーツでの最後の打席でスタンドの雰囲気は一変した。「リサイン、ラス」再契約しろと言う歓声が球場全体を包み込んだ。ビッグデータはパイレーツとそのファン、そしてこの後ブルージェイズと5年総額8200万$の契約を結びマーティンに大きな価値をみつけだしたのだ。
0投稿日: 2019.07.18
Die革命~医療完成時代の生き方
奥真也
大和書房
お前はすでに死んでいる。いやまだだ
ユヴァル・ノア・ハラリは新たな人類の課題は不死と幸福と神聖の獲得であり、ホモ・デウス(神)を目指すのだと予言する。2016年の世界の平均寿命は72歳、40年間で10歳伸びた。100年前には30代前半だったがスペイン風邪の大流行のため20代に落ち込んだこともある。現在の世界人口は76億、2100年には110億になると予想されているが子供の数は今と変わらない。現在女性1人あたりの子供の数は2.5人。すでに子供の数の増加は横ばいになっている。 15歳ごとに区切ると30歳までの人口が40億、75歳までに15歳ごとに各10億というのが現在の姿だ。2060年、今の30歳はほとんど死なずに75歳になる。この時の人口が約100億だ。世界人口は120億で安定すると言われている。つまり平均寿命は90歳にはなるというのがごく一般的な見方だ。日本の平均寿命は84歳なので乳幼児死亡率の高い国の経済が発展し社会インフラが整えば現在の技術レベルでも90歳というのは普通に達成できるレベルということになる。 Die革命はさらにその先の世界だろう。平均寿命が105歳になれば人口は140億に120歳になれば160億になる。「すべての病気を克服してしまうのが、『医療の完成』だとするならば、現在は9合目まで来ている」。エイズはすでに治療可能な病気になっている。がん治療では分子標的薬や光免疫療法などがんを克服する治療法が着実に成果をあげている。 最後の1合には最も困難な3種類の病気が残る。 1 発見・アプローチが難しい病気 2 症例が圧倒的に少ない病気 3 急死 https://www.japan-who.or.jp/act/factsheet/310.pdf ファクトフルネスのレビューに同じことを書いたのだが2016年の世界の死者数5670万人のうち300万人が亡くなった感染症のトップは下気道感染症(気管支炎や肺炎)、次いで140万人が亡くなった下痢性疾患、130万人が亡くなった結核が死因のトップ10に入る。また道路交通障害140万人が最大の傷害となっている。自然災害は恐ろしいものだが死因の0.1%に過ぎない。高齢者が恐るべきは誤嚥性肺炎ということになる。年寄りは歯を磨こう。 Die革命の最初の課題は最大の死因である虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)、脳卒中などの急死を防ぐことだろうか。「近くに人がいない孤立した環境は容易に『急死』を呼び込んでしまう」日本では奥さんの書いているように医療を支える財政の方が問題だろう。ITの発展で急死の原因を自動で通報できるようになったとしても物理的な移動手段が維持できるかと言った問題は残る。またAIによる診断が実際には生身の医者を超えていたとしても誤診を許せるかは社会が受け入れられるかだ。自動運転が当たり前になれば急死にも効果的に思えるがこれも同様だ。 この本でも紹介されていた遺伝子を編集する「神のハサミ」クリスパーcas9を発見したジェニファー・ダウドナは自書で「科学者よ、研究室を出て話をしよう」と結んでいる。遺伝子編集という画期的な技術を社会全体が受け入れられるのかはまだわからない。そして人生150年となったとして長寿を積極的に受け入れるには個人と社会の財政的な裏付けが必要だ。それでも最初の一歩はそれがすでに起こった未来だと知ることからだろう。本書もその一つ。
0投稿日: 2019.05.26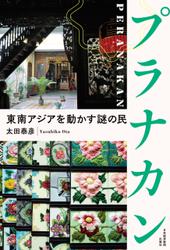
プラナカン 東南アジアを動かす謎の民
太田泰彦
日本経済新聞出版
血筋ではなく文化だ
プラナカン(peranakan)、地元マレーの言葉で「その土地で生まれた子」という意味である。プラナカンの男性をババ(Baba)、女性をニョニャ(Nyonya)と呼ぶ。 とあるのだがマレーーインドネシア語でanakは子供、基本中の基本の単語だ。perーanと言う共接辞をつけると動作やプロセスを表す名詞となり、良くあるberと言う接頭語に対応するらしい。beranakは子供を持つと言う動詞、peranakanは検索では子宮が出てくる。BABAはbapak(Mr.)の転用だろうか、ニョニャはそのままだが。 プラナカンはただの華人ではなく祖先がマレー人などと結婚している。ちなみに華僑は中国共産党の定義では中国国籍を持つものの呼び名で、国籍がないのは華人。また客家は華人の約1/3を占め中国の中原から南へと移住した集団で独自の文化を持ち客家語を話す漢民族の集団だ。wikiではシンガポールの初代首相リー・クアンユーは自叙伝に基づき客家系華人の4世と書かれているがこの本ではプラナカンとしての出自を隠していたと紹介されている。 1965年のシンガポール国会で同じくプラナカンの女性議員シュー・ペクレンの質問に対し、リー・クアンユーは「私のことを、その名前で読んで欲しくない」と公式に答えた。シューの質問の意図は「異なる民族、文化、宗教が融合したプラナカン」と言うアイデンティティがシンガポールと言うハイブリッド国家を象徴すると肯定的に捉えたのに対し、リーはプラナカンと言う言葉に含まれる「この地で生まれた外国人」と言うニュアンスを否定的に捉えた。プラナカンは宗主国であるイギリスの支配層に取り入ったエリート集団でもある。リーは自分のことを「マラヤの民」と呼んだ。 この辺りはインドネシア語の感覚ではよくわからない。ババ・マレー語と言うプラナカンの言葉があるので意味が違ってくるのだろうか。著者の太田氏は2015年から3年間シンガポールに駐在した日経記者で取材対象のプラナカンとはおそらく英語での会話は苦労しない。だからかマレーーインドネシア語との違和感は感じていないように見える。 マラッカのババ・ニョニャ・ヘリテージ博物館でとなった家で生まれたヘンリー・チャンは後に大陸から労働者として大量にやってきた新客とプラナカンを区別するのは血筋ではなく、文化だと言う。「文化とは教育であり、品位や礼儀でもあり、経済力でもある」、紹介されているプラナカンの文化は刺繍だったり装飾だったりが女性的と形容されているが、良く言えば貴族趣味、悪く言えば成金趣味な感じがある。客家自体が王朝の血筋のものが多く、独自の文化を守ったとある。現地の支配層と結びつきながらも独自の文化を守り続けたプラナカンは労働者階級ではなかったようだ。シンガポールプラナカン協会の定義ではマレー系の血筋が1/16以上、ババ・マレー語を話す、4世代以上遡って現地化しているなど厳格だ。 東南アジアのプラナカンの街といえばシンガポール、マラッカそしてペナンと言う海峡植民地だ。そしてもう一つ人口の70%がプラナカンなのがタイのプーケットだ。しかしプーケットではタイ人と結婚した華人の子孫は全てプラナカンでありそこに独自の文化を守ると言う意識はない。さらにインドネシアに行くと定義もはっきりしない、あえて言えば地に落ちた(土着化した)華人だ。 プラナカンの政治家でタイの外務大臣タナット・コーマンが生み出したものがある。ASEANがそれだ。東南アジアに生まれたよそから来たこどもがばらばらだった国を結びつけたのだ。
0投稿日: 2019.05.09
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
