
スポーツ遺伝子は勝者を決めるか? アスリートの科学
デイヴィッド エプスタイン,福 典之,川又 政治
ハヤカワ文庫NF
ハッピートレーニング
スポーツでの成功を決めるのは遺伝子か、それとも1万時間の練習か。 人口300万人のジャマイカなかでもトレローニー教区はウサイン・ボルトをはじめとするスプリンターを生み出してきた。「身体が丈夫な人間がアフリカから船に乗せられ、そのなかから、過酷な船旅に耐えられた者だけが生きてジャマイカにたどり着き、さらにそのなかから、最も屈強な者だけがジャマイカの辺境の地でマルーンの戦士の仲間入りをした。そして今日のオリンピック・スプリンターは、この戦士の遺伝子が継承されている地域の出身者である。」よくできたストーリーだが遺伝子的にはマルーンも他のジャマイカ人も西アフリカ人も非常に多様な先祖を持つ。 鎌状赤血球遺伝子はマラリアの危険地帯で出現確率が上がる。この遺伝子を一つ持つとマラリアに感染すると赤血球が鎌状に変形しマラリアごと取り除かれる。持久系のスポーツに不利なこの形質はスプリンターには多く現れる。ヘモグロビン値が下がると速筋繊維が増えることはラットでは確認されたが人間ではまだだ。 過去にマラソンで2時間10分を切ったアメリカのランナーは17人、一方でケニアのカレンジン族は2011年10月だけで32人が達成した。アメリカの高校生で1マイル4分を切ったのは5人、同様にカレンジン族がトレーニングを積む場所の高校では同時期に4人が達成した。カレンジン族とデンマークのランナーには最大酸素摂取量にも遅筋比率にも差はなかった。違いがあったのは脚の太さでカレンジン族ランナーの脚は500g軽かった。1km走るのに8%のエネルギーが節約されることになる。細長い身体と狭い腰幅に細長い手足はマラソンに向いた体型だ。またケニアの高地には蚊が少なくマラリアも鎌状赤血球遺伝子もほとんど存在しない。 低緯度の低地出身者は人種に限らず手脚が長くなる傾向にある。同じ身長で重心が高くなると走るのには有利で、低いほうが泳ぐのには有利だ。現在、短距離走と長距離走のいずれでも、最速の人間は黒人である。では遺伝子が成功を決めるのかというとやはりそれだけではない。「チャンプス」の名で知られるジャマイカの高校陸上競技大会は、1910年から継続して開催されている。ジャマイカでは、ほとんどすべての子供が何らかの形でスプリントレースに参加する。そして陸上競技大会に熱心な大人が足の速い子に着目し、陸上競技に力を入れている高校に入るように働きかける。クリケットのスター選手になりたいと思っていたボルトは14歳の時にダントツの1位となり練習嫌いで有名だったが、ジャマイカにいたから陸上の世界に入ったと言える。 ケニアのランナーは子供の頃走って通学するしかなかった。ケニアには、趣味でジョギングをする者はいない。いるのは、移動手段として走る者、トレーニングのために必死で走る者、そして、全く走らない者がいる。世界2位の長距離走大国エチオピア人とケニア人のDNAを調べた結果系譜は必ずしも近くはない。エチオピア人のミトコンドリアDNAはむしろヨーロッパ人に近いのだ。そもそもアフリカ大陸の遺伝的多様性は非常に大きく、500万年前に生まれた人類のごく一部がアフリカから出たのが2万年前、つまりおそらく世界で一番遅い人間もアフリカにいる。 1万時間の法則にもかなりのばらつきがあり人により必要な時間は変わってくる。1万時間を目標にトレーニングをするのではなく、一人一人に向いた競技とトレーニング法が有るというのがこの本の結論に近い。特定の競技を除けば専門を固定するのは必ずしも速い方が有利ではない。高校卒業時に175cmしかなく、妹の方が大きかった男はその後2年のバイト暮しの間に203cmになり再びバスケを始めた。そしてその頃には以前ほど不器用ではなくなっていた。21歳まで組織だったチームでまともにプレーできなかった男は奨学金を得て大学に入り最後はNBAの殿堂入りを果たした。デニス・ロッドマンだ。 「すべての人間が異なる遺伝子型を保有している。よって、それぞれが最適の成長を遂げるためには、それぞれが異なる環境に身を置かねばならない」 ハッピートレーニング!
0投稿日: 2017.04.16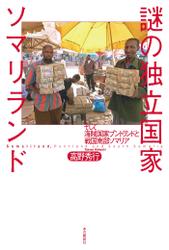
謎の独立国家ソマリランド
高野秀行
本の雑誌社
命の価値はラクダ何頭?
ソマリアと言えばアフリカの角と海賊、一般常識としてはこれで十分だろう。映画「ブラックホーク・ダウン」を見てればもう少し詳しくなってとんでもない無政府地帯だと知っていたり、ケニアのデパート襲撃事件の犯行組織がソマリア南部に本拠地を置くイスラム過激派アル・シャバーブでアルカイダとなんかつながりがあるらしいとかこれで十分ソマリア通・・・のはずだ。 1992年以来20年ほど中央政府が存在せず内戦状態だったソマリアで昨年連邦議会が発足し、大統領が選挙で選ばれ久々に国としての体裁が整ったのだがその国名はソマリア連邦共和国。ソマリ人が85%を占めるほぼ単一民族国家が連邦制をとった理由はこの本を読めばよくわかる。ソマリア国内には謎の民主国家ソマリランドや海賊国家プントランド、ガルカイヨと言う都市の半分が勝手に名乗ったガルムドゥッグそしてリアル北斗の拳の世界南部ソマリアと中央政府は無くても地方政府?は乱立しているのだ。それぞれ氏族によって支配されているので戦国時代と考えれば分かりやすいだろう。高野は勝手にイサック奥州藤原氏のソマリランドとかハウィエ源氏の義経系ハバル・ギディルと頼朝系アブガルなど氏族名に日本名を割り当て分かりやすく整理してくれている。分かりやすいか??? ソマリ人は一般のアフリカ人とは一戦を画している。とにかく行動が早い。何せインターネット回線が3日で引けるらしい。ホテルのフロントもテキパキしている。そしてウルサい。好きな事を話しては興味が無くなると次へいく。自己主張が強く交渉にも強い。なぜかそんな彼らが内戦を自分たちの氏族代表の話し合いで解決し、武力解除し民主的な選挙によって作り上げたのがソマリランドだ。ソマリ人のイスラムの掟では人が殺された時には男の場合ラクダ100頭分、女だと50頭分の金が支払われ解決する。金で解決すると言うとひどい話の様だが、これは復讐の連鎖を防ぐための仕組みらしい。しかし、大規模な内戦ではどちらが何人とか数える事も出来ず新たな解決方法が考えだされた。対立する氏族間で20名ほどの若い女が嫁入りするのだ。最初はいじめられていても孫が生まれればその内関係が強くなってくる。とは言え離婚も多いらしいのでほんまに機能するんかいと突っ込みたくなるところだが。 プントランドの海賊も元はと言えば氏族間での構想で捕虜をとり金で解決するという伝統があったらしい。そして氏族社会である以上海賊たちもどこかにつながっていてソマリアの一大産業になってしまっている。高野が試しに海賊を計画した所話は簡単に進むのだがその相談相手はプントランドの議員に立候補を考えるジャーナリストとその友達であっという間にホテルの隣の部屋にいる海賊を連れてくる。初心者用一般コースだとボート1台に海賊7人、月に3回アタックするとして計1万8千ドル。バズーカ砲のレンタルが月2〜3千ドル、マシンガンなら1台5千ドル。身代金交渉の通訳代(8%なぜかここだけ歩合制)に食費や酒(ムスリムなのに船酔い対策で飲む)等々で4千ドル。ドキュメンタリーも撮るとして初期費用が5万ドルほど。身代金の平均は100万ドルほどで(人質には価値が無く積み荷が石油のタンカーなどが狙い目、なにせラクダ100頭だから)成功すると大量に両替が行われるので何となく分かるらしい。成功しても地元の有力者に40〜45%を召し上げられてしまう。と言う事で海賊はイスラム過激派とは何の関係もない事がわかってしまった。ものすごい取材力である。 しかしプントランドの旅では警護、車、取材に協力してくれるジャーナリストなどから次々と金を巻き上げられるはめにあう。もはやぼったくりバーで夜間はホテルに缶詰と取材をしているのだか軟禁されているのだかあまり大差はない。とにかく協力者はよってくる、金を払いさえすれば。 リアル北斗の拳の世界モガディシュは意外な事に一番上品なソマリ人たちの街だった。街にはネットカフェや家電店にレンタルビデオ屋もあり洋服店のスタイルも日本と変わらない。民主的なソマリランドのソマリ人がウルサく、荒っぽく、人の話を聞かないのに対し、内戦下のモガディシュで迎えてくれたのは人当たりもよく、人の話もちゃんと聞いてくれる。モガディシュのテレビ局の支局長は20そこそこの若い女性ハムディで高野が町を離れる際に地図を用意してくれ、しかも自分からは請求もしない。そしてホテルに来て料理までしてくれたりする。おもてなしの心はソマリアにもあったのだが、一方で街を歩く外国人ジャーナリストはいつ誘拐されてもおかしくない状況でもあり、高野は別の取材で実際に襲撃され乗っていた装甲車に銃弾を受けている。 この本から得られるのはアメリカの視点では決して見えない独自のルールに基づいて生きている人たちだった。
0投稿日: 2017.04.14
宇宙創成(下)(新潮文庫)
サイモン・シン,青木薫
新潮文庫
神はサイコロを転がすのか
後半はビッグバンモデルと定常宇宙モデルの争い。科学者同士の争いは時に醜く同じ観測結果を見ても別の理論の信奉者は別の結論を導きだす。しかし上巻でビッグバンを否定したアインシュタインは下巻冒頭ではハッブルの赤方偏移のデーターを元にルメートルが正しかったとビッグバンモデルに転向した。「この項を持ち込んでからというもの、ずっとやましい気持ちでした。・・・私には、あんな醜いものが自然界に実現しているとは考えられません。」 ビッグバン仮説に対する定常宇宙論がどうやって赤方偏移、つまり遠くの宇宙は膨張し遠ざかる光を説明するのか?膨張すると空間にある物質は当然薄くなるが、もにょもにょっと新たな物質が生まれて薄まった分を埋めるので全体としては変わらないというのがそのモデルだ。エネルギー保存則は無視してしまうのね・・・E=MC^2なら物質が穴埋めした分エネルギーが減り冷えていくはずなんだが。 ビッグバンモデルへの攻撃はルメートルがカトリックの聖職者だったことにもある。ルメートル自身は科学と信仰は切り離していたが反宗教派はビッグバン仮説を創世記と結びつけて攻撃した。またこのころハッブルの観測から計算された宇宙の年齢は20億年と地球上の岩石の放射線測定から計算された34億年に満たないなどの矛盾もあった。 天文学で測定された宇宙にある部室の推定では存在比は水素1万に対し、ヘリウムが1千、酸素が2で炭素が1、その他は全て合わせて1未満である。ルメートルは原初の重い原子が次々と軽い分子に分解していくモデルを考えていたのだがそれではこの比率は説明できない。ロシアから亡命したガモフは逆に水素が核融合して重い原子を作るビッグバンモデルを考えこれで水素とヘリウムの比率は計算結果にあった。しかし炭素が作られるルートが見つからない。数学が不得手だったガモフは初期宇宙出の元素合成の問題に若いラルフ・アルファーを引き込む。ビッグバン初期のモデルを発表する際にガモフは仲の良かったハンス・ベーテを引き込むのだがこれはアルファー・ベーテ・ガモフとαβγをかけたシャレだった。このため若いアルファーは目だたなくなり後々悶着の種になる。ガモフのたちの悪いジョークはいろいろと騒動を引き起こしたがなかなかお茶目でもある。ののしり合いよりはよっぽどましだろう。この計算結果は大ニュースとなり1948年ワシントン・ポストは世界は5分で始まったと取り上げた。初期宇宙の元素合成は300秒でヘリウムを生み出した。 原初の宇宙は陽子や中性子、電子が好き勝手に飛び回っている。宇宙の温度が1兆度から百万度の間の頃陽子と中性子から重水素の原子核ができヘリウムの原子核ができた。とは言え電子はあいかわらず激しく飛び回り分子としては存在していない。いわゆるプラズマと言うもので詳しくは大槻教授に説明してもらいたいがもう少し温度が下がると電子と結びつき水素とヘリウムになる。原初の宇宙は光の海でもあったらしい。やはり「光あれ」か。光は電子と相互作用するため明るいが不透明な世界が30万年ほど続く。そして温度が3千度に冷えた頃、水素とヘリウムはプラズマから分子へと状態を変える。これが分子が誕生した瞬間だった。同時に光は分子とは干渉せず宇宙を真直ぐ進み始める。この時の光はあらゆる方向に進み、つまり地球からみればあらゆる方向からやって来ている。空間の膨張とともに今では波長1mmのマイクロ波があらゆる方角からやって来ておりこれが観測されるのは1960年代まで待つことになる。 宇宙に残されたもう一つの謎炭素原子以上の重い原子が出来ることを証明し、ビッグバンに残された最後の課題はビッグバンの宇宙は均一で重力の偏りがないため星が生まれそうにないことだった。膨張する宇宙に少しでもゆらぎがあれば重力差が生まれ星が生まれる。最後の観測はあらゆる方向からやってくる放射線にゆらぎがないかを見つけることだった。当初1989年に衛星を使って観測を行う予定であったがチャレンジャー号の打ち上げ失敗のため計画は暗礁に乗り上げた。何とかスターウォーズ計画の標的に使われるはずだったロケットを確保したが今度は衛星を軽くしないと打ち上げ出来ない。そして1989年1月18日ついに打ち上げは成功した。そして3年に及ぶ観測の結果わずか10万分の1のゆらぎが発見された。 1本の棒の影から始まった宇宙観測の歴史はこうして宇宙がどうやって出来たかを解き明かす所まで来ている。サイモン・シンはエピローグを一つの挿話で締めくくっている。 神は天地創造以前に何をしていたのか? 神は天地創造以前に、そう言う質問をするあなたのような人間のために、 地獄を作っておられたのだ。
0投稿日: 2017.04.14
宇宙創成(上)(新潮文庫)
サイモン・シン,青木薫
新潮文庫
宇宙は膨張するのか?
「光あれ」と神が言ったかどうかは知らないが、150億年ほど前にビッグバンと呼ばれる宇宙=空間の大膨張が起こったことは証拠が出そろって来ており、カトリック教会も実は喜んでいるのかもしれないが公式には自然界を説明する仕事は科学に任せている。1992年ようやくヴァチカンはガリレオを罰したことは間違いだったと認めた。 天地創造は古代から各地で様々な物語によって語られて来た。やがて観測と理論が様々な事実を明らかにして来ている。大きなターニグポイントと言うか天文学上のヒーローは二人が有名だが、実際には数多くの人たちがビッグバンの証拠探しに貢献している。中にはビッグバン仮説を攻撃しながら計らずも証拠固めに手を貸してしまったものもいる。 地球の大きさを初めてはかることが出来たのは紀元前276年生まれのエラストテネス。北回帰線上の街シエネで夏至の日に井戸の底を太陽が照らすことから、アレクサンドリアの同じ日の影の長さと2点間の距離から地球の外形を計算した。地球の大きさが分かれば月食の時間から月の直径は地球の凡そ1/4であることが分かり、簡単な三角測量(月をちょうど隠す大きさのものを目からどれだけ離すか)で月までの距離がわかる。そして半月の時の太陽と月の角度から太陽までの距離が分かる。古代ギリシャでは地球が太陽を回るモデルが既に出来ていた。 しかし、地球が動くと言う説はあらゆるものは宇宙の中心、すなわち地球の中心に向かうという重力モデルでは説明がつかない。地動説の復活は1543年春、コペルニクスが刊行した「天球の回転について」がきっかけになるのだが、コペルニクスは脳出血で倒れこの本の完成はようやく一目見ただけであった。そして、原稿には無く、出版時に後から書き足された序文にこの本は地動説を覆すものではなく、計算に便利だとされたため不動の大地の足下は揺るがないままであった。1609年ケプラーは惑星が楕円軌道だと発見しガリレオが作った望遠鏡の話を聞くことになる。 天文学上の最初のヒーローはガリレオ・ガリレイ。理論、観察、実験と発明の全てが高いレベルにあるまさに科学者の父だ。望遠鏡の発明はガリレオではなく、彼の功績は望遠鏡の精度を天体観測レベルに引き上げ、そして木星の衛星の観測からコペルニクス・ケプラーモデルが正しいことを証明したことだ。地球の動きを感知できないことについても相対性で説明がつく(この場合は電車の中でのキャッチボールのような)ことを理解していたが1633年の裁判で天文対話は禁書とされ37年には視力を失い、42年に亡くなった。カトリック教会は敬虔な信者だったガリレオを教徒として葬ることを拒み、それがようやく撤回されたのが冒頭に書いた1992年だった。このとき同時にようやく地動説も認めている。1642年生まれのアイザック・ニュートンがケプラーやガリレオの法則をまとめ、万有引力によって楕円軌道の惑星の運動を説明できるとまとめたのが1687年、しかしこの本ではなぜかニュートンは脇役としても登場していない。コペルニクス的転回というと一気にひっくり返ったイメージだが実際にはカトリック教会の影響力に反比例して科学者は地動説を取り入れていったようである。 次なるヒーローはアインシュタイン、ガリレオの相対性原理を思考実験で使ったアインシュタインは当時信じられていた光はエーテル中を進むと言う常識を疑うことになる。当時16才だった。やがて得られたアイデアは光は観測者に対して同じ速度で進むと言うもので、これが発展して特殊相対性理論が生まれる。そしてこの理論から生まれる結論は時間や空間が一定ではないと言うことだ。重力により時間や空間(アインシュタインによると時空としてひとくくりで扱われるもの)がゆがむ。ニュートンとアインシュタインのどちらの理論が正しいかを示したのは皆既日食の際の星の観測結果だった。太陽ぐらいの質量の星があれば重力により空間がゆがみ光は曲がって進むと言うのがアインシュタインの予測で1919年の観測で実証された。 アインシュタインの重力理論にも困ったことが起こる。と言うのは宇宙は星などの質量により縮まなくてはおかしいのだ。困ったアインシュタインは収縮する宇宙を嫌い重力方程式に宇宙定数と言う項を滑り込ませる。この項は斥力として働き宇宙が縮むのを防ぎ、値を調整すれば宇宙は伸び縮みせず永遠でいられる。後にアインシュタインは後悔することになるのだが、スーパースターにも失敗はある。ちなみにニュートンモデルでも宇宙は縮んでいく。アインシュタインモデルを元に修正したのはロシアのフリードマンで宇宙が膨張すれば宇宙定数を無くせると考えたがアインシュタインはこの考えを否定する。
0投稿日: 2017.04.14
代替医療解剖(新潮文庫)
サイモン・シン,エツァート・エルンスト,青木薫
新潮文庫
サイモン・シン英国カイロプラクティック協会に勝訴
2000年以上前にヒポクラテスはこう述べた。 「科学と意見という、二つのものがある。前者は知識を生み、後者は無知を生む。」 この本では「〇〇を試した所、元気になりました・・・」という体験談は全て意見として扱っている。ある人が何かを試して効果があったとしてもそれは科学ではなく意見だと。では、科学として取り扱われるのは何か?簡単に言うと証拠に基づいている事である。例えば統計的なデータに基づき効果が有ると言えるか。対象者はランダム化されているか。ブラインドテストをくぐり抜けたかなどで、特にランダム化とブラインドテストを経た者は理論がどうであれ医療効果が有るとされる。現代最高の科学ジャーナリストのサイモン・シンが代替医療(ホメオパス)における世界初の大学教授エツァート・エルンストと組んでいろいろな代替医療を検証している。 鍼の真実 ーいくつかのタイプの痛みや吐き気に対して効果が有るという信頼性の高い臨床試験結果は有る。しかし、同様に効果を否定する信頼性の高い結果も出ている。ー 経絡、経穴は存在しない。秘孔もなければケンシロウもいない。少し残念ではあるのだが。 鍼が効いたという体験談ならいくらでもあるし、その体験が間違いだと言うのではない。 治験者に知らせず、経穴の一定の深さに打つ鍼と偽物の鍼(皮膚表面をさすが押すと引っ込むので経穴には届かない)を使ったブラインドテストの結果それぞれの効果に差は出なかった。プラセボ効果(効くと思えば症状が緩和する)以上の効果はほとんど見られなかった。 ホメオパシーの真実 ー忘れましょうー インドではアユールヴェーダと並んであらゆる階層で用いられているホメオパシーだが別に神秘性はない。18世紀末のドイツの医師ザムエル・ハーネマンがマラリアの特効薬キナの木(キニーネの原料)を健康な人が飲むとマラリアにた症状が出ると言う事から思いついたのだ。健康な人に症状を起こす者は病気を治すと。そしてよくわからないのだが薄めれば薄めるほど効果は強くなるという。たとえばホメオパシーで百倍希釈をCで表し30Cと言うのはごく普通なのだがそこまで希釈するともとの分子はまず含まれていない。普通はここまでで証明終了だ。 それでもいくつもの研究成果をちゃんと検証している。おつかれさんですな。 フランス産の1羽のカモの肝臓と心臓から取られるホメオパシーのインフルエンザ・レメディ(治療薬と思ってください)は2千万ドル以上の売り上げが見込まれているのだが、その容器には薬剤1g中、蔗糖0.85gと乳糖0.15gと明記されている。 カイロプラクティックの真実 ー腰痛に効果があるケースはある。より安い通常医療で効果がなければ試してみてもいい。ただし首は絶対に施術させない事ー 残念な事に腰痛に必ず効く治療法は無い様だ。カイロプラクティックでは無理に外的な力を込めて動かす技術を使う。1997年に治療を受けたカナダの女性は頸椎にマニュピレーションを施した結果、椎骨動脈を損傷し、できた血栓が脳につまり死亡した。骨がばきばきなると効いた気になるがあれは指の骨と同じで気体の泡がはじける音だ。ストレッチの際に言うように無理な力をかけない、反動を使わないやり方のほうが明らかにリスクが少ない。 ハーブ療法の真実 ー効果があるものとないものいずれも有る。近代薬のもとになった。ー 普通の薬は天然物の中から薬効成分を抽出し、化学組成を少し変えてできるだけ効果に対し副作用が少なくなるように膨大な時間と金をかけた臨床試験を行っている。天然物が安全で、人工物が危険だという思い込みには何ら根拠が無い。それでも薬害は起こりえるのだが。また例えば漢方薬の重金属汚染などもニュースになったように薬効とそのものの安全性は少し異なる。 ラベンダー「不眠には効かない」、朝鮮人参「基本的に効果なし」、ニンニク「高コレステロール血症に効果は有るが、血糖値を下げる可能性がある」等々。効果の例の割りに副作用の項目はたくさん並んでいるのではあるが化学屋からすると「毒は薬」効果は有っておかしくない。普通の薬との相互作用も注意すべきである。 科学的な手法を用いて大きな成果を上げた有名人は誰か?候補はいろいろ挙がるが知らなかったのがナイチンゲールだった。戦場病院で一生懸命手当てした人と言うイメージだったのだが実際には統計に基づき病院の衛生管理をする事で死亡率を大きく下げた科学者でもあった。一方で伝統的なやり方が明らかに間違っていた例もある。瀉血といって病人を傷つけ悪い血を抜くという治療法は今では考えられないが19世紀までは通常の医療だったため、結果としては治療をしない方が長生きできた例は多い。 原題はTrick or Treatment ?
1投稿日: 2017.04.14
暗号解読(上)(新潮文庫)
サイモン・シン,青木薫
新潮文庫
ofcbanniと175828273
暗号の発達と解読の歴史からロゼッタストーンなど失われた言語の解読、最後は量子暗号まで。とても全部理解できないが分かりやすく噛み砕いてる著者はすごいな〜と思ったらケンブリッジの素粒子物理学のDr.でした。 割りと基本的な暗号の作り方はまずキーワードを決める、例えばfacebook。重複するoを除きアルファベットの順番の一番始めにfacebokと並べ後は使った文字を飛ばして順に並べるこの場合kの後はdghijlmn... で元のアルファベットに対応する位置に置き換える。fはo、aはf、cは偶々そのままc(普通は必ず変わるようにするらしいが)と続き例えばfacebookはofcbanniとなる、当初はキーワードさえ分からなければ通用していたが、英語ではeが最も多く使われる12.7%から始まる頻度分析、スペースの空いた文だと1文字の単語はaかIの何れか、何度も使われるtheやqの後は必ずuなどキーワード無しでも解読出来るようになっていった。 暗号は複雑化し世界大戦中は暗号機エニグマと日替わりのランダムの鍵でドイツの暗号がリード。一方解読機も発達し機械式から真空管を使った電気式計算機のアイデアが生まれた。コンピューターの原型だが暗号解読が出来たことを秘密にしたいイギリスは終戦後装置を破棄した。 インターネットの暗号化は二進法の数字の列をある関数を使って変換するのだがいつまで立ってもキーワードをどうやって安全に受け渡すかという問題が最後に残った。これを解決するアイデアは暗号化の鍵を公開し、解読の鍵を持っておくというもので具体的には下のような数字を使う。 17159x10247=175828273 左の二つの数字は素数でこれ以上は割り切れない。右の数字が公開鍵で桁が小さければ力づくの計算で左の数字は出せるが桁が大きいと事実上因数分解に時間がかかりすぎて解けない。この鍵を自動的に作るpgpと言うソフトは個人使用についてはフリーソフトだそうだ、しかし中国などは無許可で使うと法律違反になる。 最後に量子コンピューターと量子暗号。同じ言葉を使うが原理は違う。量子コンピューターは解説不能。完全に私の理解力を超えている。例えば1から128までの掛算の結果が鍵だとしたら今のコンピューターは順番に計算するのに対し量子コンピューターは重なった状態で同時に計算する。よく分かりません。 量子暗号の方は実験的には完成していて光の性質を利用する。偏光板はある向きの波は通し、45度傾くとランダムに半分の波が通り向きがそろう、90度傾くと通らない。この光の向きが暗号の鍵で数字を表す。受け取る側は真っ直ぐなのと45度傾いたフィルターをランダムに使って計測する。暗号の波の向きとフィルターがあっていれば正しい情報だが傾いたフィルターを使うと受け取った情報は確立半々で間違っている。後で正しい測定器がどれかを教えて間違ったフィルターの情報は捨てる。誰かがスパイして同じことをしていたとしても偶々受け取る側と同じフィルターを使っていない限り意味がない。測定自体が結果に影響を与える=斜めの光がランダムに半分通り向きがそろうやり直し出来ないのがポイントのようだ。同じ理由でスパイしていたらその痕跡が残る。 暗号の話は難しいところも有るがそれにまつわるエピソードが豊富で単純に読み物として飽きさせない。
0投稿日: 2017.04.14
フェルマーの最終定理(新潮文庫)
サイモン・シン,青木薫
新潮文庫
サイモン・シン&青木薫に外れなし
X^n+Y^n=Z^n(^nはn乗のかわり)はnが2より大きい場合には整数解をもたないと言うのがフェルマーの最終予想。 n=2のピュタゴラスの定理に始まり、孤独なアマチュア数学者だったフェルマーが書き残したこの数式の発見からこれを証明しようとした人たちの物語。アマゾンの科学本上半期第3位でした。(2012年当時) 証明の話自体はまったくわかりません。説明不能。 作者のサイモン・シンはBBCで「ホライズンーフェルマーの最終定理」をドラマ化しその後この本をきっかけに作家に転身、暗号解読も一部この本と話が絡み合っています。 この本にでてくるいくつかの数式とクイズ π=4(1/1−1/3+1/5−1/7+1/9ー1/11+・・・・) へーっ 天秤を用いて1〜40Kgまで1Kg単位ではかるのに最低何個の分銅が必要か。 途中まで考え断念、惜しかった。 オイラーの予想X^4+Y^4+Z^4=W^4には自然数解が無い。実はあった。 X=2682440、Y=15365639、Z=18796760、W=20615673 200年かけて発見パチパチ。 そして謎の証明 a=b 両辺にaをかけると a^2=ab 両辺にa^2-2abを足す a^2+a^2-2ab=ab+a^2-2ab 簡単にまとめると 2(a^2-ab)=a^2-ab 両辺をa^2-abで割ると 2=1 はて? 最終的にフェルマーの最終定理を証明したのはアンドリュー・ワイルズでしたが、手法としては谷山=志村予想を証明できれば結果としてフェルマーの最終定理が証明できる。そのために岩澤理論を用いるなどと日本の数学者が非常に大きな働きをしており、谷山=志村予想は数学の発展に大きく貢献したそうだ。
0投稿日: 2017.04.14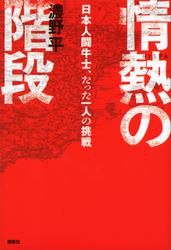
情熱の階段 日本人闘牛士、たった一人の挑戦
濃野平
講談社
そうだ闘牛士になろう
「かつて古き良き時代には、闘牛士になるのは将来も何もない餓えた若者たちであることが多かったのだが、現代において闘牛士となるのは有名な闘牛士の息子や牧場主のそれなど、経済的にも人脈的にも恵まれたものたちがその圧倒的な主流となっている。一般にノビジェロ・シン・ピカドール(満2才牛の仕留め士)から始め、ノビジェロ・コン・ピカドール(満3才牛の仕留め士)を経て、最高位であるマタドール・デ・トロスへ(満4才牛の仕留め士)と到達するまでに、少なくとも日本円で三千万円以上の資金が必要とされるからだ。」 高校を出て10年間フリーターだった男がわずかな時間テレビで見たのをきっかけに闘牛士になりたいと聞くとどう思うだろうか。多くの人がなれるわけがないと思うだろう。濃野平は1997年に28でスペインに飛んだ。当時はまだ何でもググれる時代ではなく、どうやれば闘牛士になれるかどころか日本にいてどこで闘牛が開催されているかすらはわからない。少なくともスペインに行かなければ闘牛士になれないことは確かだ。 濃野がたどり着いたのは大西洋に面したスペインの西の港町ウエルバこの町の近くで闘牛があったからだ。スペイン語は全くしゃべれず、辞書と会話集を頼りに闘牛学校が有るか聞く濃野、セビリアに有ると聞き街を離れようとする濃野を「セビリアに行くなここに残れ」と止める若い男がいた。10才年下で闘牛士を目指すビクトルは濃野の親友となり目標ともなった。このころのビクトルはノビジェロ・シン・ピカドールの資格は持っていたがまだプロ闘牛士としてのデビューは果たしてなかった。 闘牛の練習を始めて4日目濃野はいきなり生きた牝牛相手に練習することになる。闘牛士が使う道具は両手で持つ大きなマントのようなカポテと右手で剣を持つ際に左手で持つムレタと言う布。闘牛は人間と牛との戦いではなくカポテやムレタで牛をコントロールし一体となって様式美を完成させる芸術のようなものだ、そして最後に牛の肩甲骨の間に剣を突き刺し牛を殺すことで芸術は完成する。しかし一度この布になれた牛はその後は人間を狙ってくる。牛が闘牛に使えるのは一度きりだ。殺された牡牛は肉になる。(食用と育てられたわけではないが)ごく並外れた働きを見せた牛だけは余生を種牛として暮らすことが出来る。 では練習はどうするかと言うと運が良ければ4日目の濃野のように牧場の雌牛を相手に出来る。練習で良い反応を見せた牝牛は繁殖用に残されそれ以外はやはり肉となる。初めての練習で2才未満とは言え100KGを超える牛に濃野は吹っ飛ばされるが逃げることはなく踏ん張った。 ビクトルと練習できる牧場を探す間にヒッチハイクのために濃野は道路脇で死んだ振りをする。この時からビクトルが濃野の見る目が変わった「お前って凄いぜ、人の出来ない馬鹿なことをやれるってのは才能だし、とてつもなく勇気が有るってことなんだよ」 濃野の草闘牛のデビューもビクトルと一緒だった。基本技を身につけていない濃野はポルタ・ガジョーラと言う大技一発にかける。門の前でカポテを大きく広げ両膝をついて牛を待ち、一瞬の判断でカポテを振って牛をやり過ごす技だ。あくまで優雅にゆったりとした動きで。最初にやるはずだったビクトルは躊躇する草闘牛でそこまでのリスクは取れないと。一方の濃野はそれでもやり成功させた。闘牛修行わずか4ヶ月目であった。 その後なんとか闘牛士免許を手に入れた濃野はデビュー戦を前に練習用の牡牛相手に負傷を負う。それでも出番が来た濃野はまた扉の前に向かう。ポルタ・ガジョーラだ。濃野は負傷した右手でやってのけた。技術的には褒められたものではなかったかもしれないがこの日一番観客を湧かしたと自負できるものであり、メディアからの賞賛も受けた。しかし、その後3年間濃野が試合に出ることはなかった。 闘牛士の世界は基本足の引っ張りあいだ。稼げる闘牛士はごく一部でほとんどのものは試合に出るために手配師に金を払う。見込みのないものは食い物にされ使い捨てにされる。資金繰りに行き詰まった濃野は一発にかけた。飛び入りだ。 今では日本人として初めてノビジェロ・コン・ピカドールの資格を持つ濃野だが闘牛士としての成功はまだまだ先だ。濃野の物語は闘志や度胸と言うよりこの本で何度も使われているドス・コホネス(ど根性)が似合う。夢は叶うと信じていると言うのでもない。くじけそうになり、あきらめかけそれでも何とか前進を続ける理性を超えた濃野の突き抜けっぷりがすごい。
0投稿日: 2017.03.12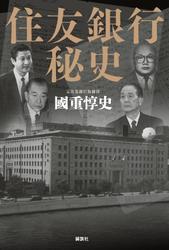
住友銀行秘史
國重惇史
講談社
孤軍奮闘と自意識過剰のブレンドに酔うかも
「ただ、何かが起きている、このバブルを謳歌している日常の裏で、恐ろしい出来事が起きているという直感はあった。 行動を始めなければならない。何かしなければならない。 私にはできる。いや、私にしかできない。」 その決意の表れとして1990/3/20から約2年間國重氏がつけたメモがこの本の元になっている。この本そのままであれば当に孤軍奮闘。保身に汲々とする上司を時には煽り、匿名の告発文を駆使して週刊誌や新聞を動かし、ついに住銀の天皇と呼ばれた磯田一郎を追い詰めた。 主要登場人物が70人ほどで、うち半分ほどが住銀社員。肩書きだけでなく入行年次出身大学が書かれているのがおかしい。銀行というところはそんなもんなんだ。磯田会長、辰巳頭取を筆頭に副頭取が2人、専務が4人、西川善文氏など常務が8人恐らく実際にはもっと役員がいるのだろう。そんな人数で頭取になるのを争ってたら行内がぐだぐだになるのも不思議ではない。 それにしてもだ、MOF担もやり、一選抜中の一選抜だった國重氏も当時の肩書きは業務渉外部の部付部長でしかない。ここまで行内政治の情報に通じているのかというのも驚きだが、これが本当なら同じような情報はそこら中に溢れていたのではと言う疑問はある。メモにも数多く行内で情報収集とある。國重氏のリークを知っていて利用してた人がいるのではないか。 イトマンの伊藤須永光ー許永中が住銀を食い物にしたのは間違いないとして、この本では川崎定徳の佐藤茂は住銀を救う側として描かれているがどうなんだろうか。いずれもグレーゾーンの人々に見えるのだが。 國重氏自身も面白い人でリークのlettterを投函した時にはハワイで休暇を取っている。「私は、こういう休みはきちんと取る。日本人のサラリーマンにありがちなのが、土日も構わず休みも取らず、一心不乱に働き続けるというタイプだ。それは私の流儀ではない。」と書いているがその後の佐高信氏のインタビューでは「女と行ってたんですよ」とあっけらかんと話をしている。その後楽天の副会長を辞任したのも68歳にしてダブル不倫の末の暴力沙汰と言うスキャンダルがあったりとあまり典型的な銀行員らしくはなさそうな人物だ。それくらい突き抜けてないと当時の銀行システムをひっくり返そうとしなかったのかも知れないのだが。國重氏の言い分だけを全部信じるのは難しいが大きな役割を果たしたのだろう。とにかく生々しくて興味深い告発だ。 http://honz.jp/articles/-/43433 普段書いてるパターンのレビューはもっと上手くここにまとめられていた。
0投稿日: 2017.01.11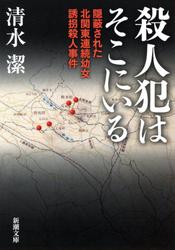
殺人犯はそこにいる―隠蔽された北関東連続幼女誘拐殺人事件―(新潮文庫)
清水潔
新潮文庫
ごめんなさいが言えなくてどうするの
1979年から96年にかけて栃木県足利市から群馬県太田市の半径20km圏内という狭い範囲で5件の幼女誘拐・殺害事件が起きていた。その中で唯一記憶に残っていたのはいわゆる足利事件、菅家利和さんが冤罪で逮捕され2009年に17年半ぶりに釈放されたところだけだ。菅家さんは90年5月に起こった松田真美ちゃん殺害事件の犯人として91年12月に逮捕され、自白を強要させられた。また当時導入されたばかりのDNA型判定ー後に清水氏の取材で証拠能力が無かったことが判明したーを証拠として1993年に宇都宮地裁は菅家さんに無期懲役を言い渡した。しかし、1996年7月に横山ゆかりちゃん誘拐事件が発生したが警察は事件の関連性に気がつかなかった。警察にとっては足利事件は解決済みでそれ以前の事件も起訴はできなかったが菅家さんが犯人だというストーリーが出来上がっていたからだ。 日テレの事件記者清水氏がこの横山ゆかりちゃん事件に注目したのはテレビ番組で未解決事件を取り上げることになるのがきっかけだった。事件の事前リサーチを始めるとすぐに5件の類似の事件が浮かび上がった。しかも足利事件は解決済みだ。警察も認めていない、マスコミも全く取り上げていない幼女連続誘拐・殺害事件。本当にそんなことがあるのか?菅家さんは冤罪を訴えているが、自白がありDNA型判定は1000人に1.2人の割合で一致すると報道されていた。リサーチ結果は菅家さんが犯人だと示している。しかし、どうしても違和感が残る。『やはりおかしい。おかしいんだよ。何かが』 もし、真犯人が他にいたら?もし6人目の被害者が出てしまったら?疑念を持ちつつ調べていくとある男の影が浮かび上がって来た。解決済みの事件を追ってどうするのだ?しかし。『記者が現場に行かず、取材もせず、もたもた考えていて何になる。飛び込むのだ。現場へ。』 清水氏は桶川ストーカー事件では取材の結果真犯人を警察より早く突き止め警察に情報を提供していた。桶川事件では警察はストーカーの相談を受け、告訴状を受け取ったのにも関わらず、捜査をせず猪野詩織さんは殺害されてしまった。警察は「市民を見殺しにした」という自分たちのミスを隠すため意図的な情報操作を行い、裏でマスコミにリークをし普通の女子大生の猪野さんをあたかも「性風俗店の店長と付き合って殺されたブランド好きの風俗嬢女子大生」と見せかけ被害者に落ち度があるように誘導した。そして遺族に告訴状を取り下げさせようとさせ、失敗すると告訴状を被害届に改ざんした。清水氏の情報提供にも関わらず警察は実行犯は逮捕したがストーカー男小松を事件から排除し、小松の兄を真犯人とするストーリーをでっち上げた。全ては自分たちのミスを隠蔽するため。 足利事件でも同じ構図が現れる。菅家さんは無職で、市内の隠れ家からロリコンビデオが多数見つかったという情報をリークしたが、隠れ家は仕事の都合で時々寝泊まりするのに借りたものだし、菅家さんが借りたビデオは巨乳ものだった。女の子を連れた河原におりていく男を見たという目撃者の証言は重要でないと片付けられー清水氏はここから真犯人にたどり着き、その情報は既に警察に提供されているー状況証拠はトリミングされていた。菅家さんが自供させられてしまったのはDNA型判定という動かぬ証拠があると言うことからだったが、この判定の不確かさが次々に現れていく。それでも警察は再鑑定を拒み、一方で遺族からの証拠品(真美ちゃんのシャツ)の返還請求も拒み続ける。これは菅家さんの無実が確定したあともそうなのだ。 真犯人は警察もおそらくわかっている。それでも警察がDNA型判定に誤りは無かったというストーリーに固執し続ける。なぜか?ここにはもう一つの事件が隠されていた。足利事件を判例としてDNA型判定の証拠能力を根拠とした飯塚事件は2006年に最高裁で死刑が確定し2008年に執行されていた。もしこれが冤罪だったとしたら? 清水氏の怒りは何よりも犯人に向けられており、読んでると怒りが伝わってくる。 「おまえがどこのどいつかは残念だが今は書けない。だが、お前の存在だけはここに書き残しておくから。いいか、逃げ切れるなどと思うなよ。」 警察や検察、裁判所、そして警察発表を鵜呑みにするマスコミにもその怒りは向けられる。これはレビューでは伝えきれないところだ。 菅家さんとそして恐らく警察や検察を含む多くの関係者を救ったのは真美ちゃんの母親だっただろう。「菅家さん。あえて『さん』をつけさせて頂きますが、菅家さんが無罪なら、早く軌道修正をして欲しい。捜査が間違っていたんであれば、ちゃんと謝るべきです。誰が考えたっておかしいでしょう」「ごめんなさいが言えなくてどうするの」
2投稿日: 2016.12.23
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
