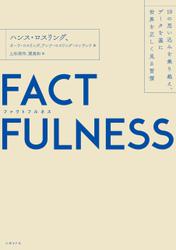
FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣
ハンス・ロスリング,オーラ・ロスリング,アンナ・ロスリング・ロンランド,上杉 周作,関 美和
日経BP
ファクトフルネスを学ぼう。いつやるか?いまでしょ!
ギャップマインダーテストは2017年に始動した。質問は13問で全て3択。www.gapminder.org/test/2017に質問がwww.gapminder.org/test/2017/resultsに回答がある。 全問正解した人にとって本書に目新しいことは書いてないかもしれない。 2017年に14カ国、1万2千人に行った調査では最初の12問に対し全問正解者なし、11問正解が1人、チンパンジーがランダムに答えても正答率が33%になるところがチンパンジーに勝ったのはわずか10%だった。やってみたところ9問正解でいずれも知っていたか予想できた。2問はパッとみて間違えたがちゃんと回答を読めば知っていた問題。2人目になりそこねたようだ。 事実を見ず間違った判断に導く10の本能 分断、1965年の世界では先進国と発展途上国では明らかな差があった。しかし今ではほとんどの人がこの中間にいる。 ネガティヴ、昔は良かった?そんなことはない。例えばアメリカの犯罪件数は1990年の1450万件に対し2016年は950万件だ。 直線、過去の延長に直線を引いても未来はわからない。グラフは直線も対数もS字もある。 「貧しい子供を助けると、人口はひたすら増え続ける」いや、「貧しい子供を助けないと、人口はひたすら増え続ける」が正解だ。 恐怖、テロや自然災害に飛行機事故というものを必要以上に恐れる必要はない。2016年の世界の死者数5670万人のうち300万人が亡くなった感染症のトップは下気道感染症(気管支炎や肺炎)、次いで140万人が亡くなった下痢性疾患、130万人が亡くなった結核が死因のトップ10に入る。また道路交通障害140万人が最大の傷害となっている。自然災害は恐ろしいものだが死因の0.1%に過ぎない。高齢者が恐るべきは誤嚥性肺炎ということになる。年寄りは歯を磨こう。 過大視、2016年420万人の赤ちゃんが亡くなった。大変な数字だが死亡率は3%で1950年の15%から大きく改善し続けている。大きな数字は単独で見ずに比較をしよう。 パターン化、宿命、単純化、犯人捜しそして焦りが残りの5つ。事実を正しく見るためのテクニックが各章ごとに紹介されている。 導かれた答えはいろいろ。女性に教育の機会を与えることは、人類史上最もすばらしいアイデアのひとつだ。世界中で、子供の生存率が伸びている原因を調べてみると、「母親が読み書きできる」と言う要因が、上昇率の約半分に貢献している。50年もすればアフリカの人たちは難民ではなく観光客としてヨーロッパに歓迎される存在になる。世の中で一番悪者扱いされるのは悪どいビジネスマン、嘘つきジャーナリスト、そしてガイジンだ。 ファクトフルネスを学ぼう。いつやるか?いまでしょ! 最終章のヒントは今やらなければならないことはそんなにないと知ることだ。
1投稿日: 2019.05.06
戦後史の解放II 自主独立とは何か 前編―敗戦から日本国憲法制定まで―(新潮選書)
細谷雄一
新潮選書
ナショナリストと愛国者
我々はイデオロギー、時間、空間などに無意識のうちに束縛されている。戦後史の始まりには日本国憲法の起草があった。どのようにしてこの憲法が定められたかについても束縛された視点からは一面の真実しか見えてこない。この束縛から逃れ視点を解放しようと言うのが本書の目指すところだろう。細谷氏は「今の日本には、希望が足りない」と言う。戦後の日本人が感じてきた希望を追体験しようとするのが本書のもう一つの試みだ。 ジョージ・オーウェルは「否定的な感情」を元にしたイデオロギーを「ナショナリズム」と定義して攻撃した。「いかなるナショナリストも、可能なかぎり、事故の勢力単位の優越性以外のことは、考えたり、話したり、書いたりしない」、今の世界はナショナリストにあふれている。オーウェルは攻撃的なナショナリストに対し「自分では世界中で一番いいものだと思うが他人には押し付けようとは思わない、特定の地域と特定の生活様式に対する献身」を「愛国心」と定義した。戦後の日本を形作る上で国際協調を基本とするリベラルな国際国家の路線に舵取りをした、幣原、吉田、芦田をオーウェル的な愛国者と位置づけ再評価しようとしている。 歴史的事実として8月15日に終わった戦争は存在しない。東アジアでの戦後各地域形成の原点であり、10年がかりの一連の複数のプロセスだ。終戦時、外地には日本の総人口の1割に当たる688万人が居留しており、うち321万人が民間人だった。ポツダム宣言を受諾した大東亜省が送った方針は「居留民はできうる限り定着の方針を執る」である。日本政府は外地居留民を保護する意思と能力を欠いていた。その結果もっとも大きな困難に直面したのがソ連軍と対面することになった満州などに暮らす200万人だった。居留民にとっては日本に帰国してからが戦後の始まりだった。 日本軍が居なくなった後の力の真空では中国の国共内戦、朝鮮戦争など一連のプロセスが続く。「われわれが慣れ親しんでいる戦後史とは、そのような大日本帝国崩壊に伴う混乱と戦争を忘却することによって、あるいは無意識のうちに戦前と戦中の日本軍の活動との関連性を切断することによって成り立っている。」 対日占領ではアメリカのマッカーサーが圧倒的な存在感を示しており、またGHQがアメリカ政府の意向に沿って対日占領政策を進めていることに、ソ連政府は意義を唱えようとしていた。ソ連の狙いは日本への要求の引き換えにウラン鉱山のあるブルガニアとルーマニアをソ連の勢力下に置くこと。アメリカとソ連のそれぞれの思惑があったにせよ、戦後日本の再出発は東欧の犠牲の上に成り立っているとも言える。 戦後日本が後継首相を選ぶにあたって、何よりも重要なのは、対日占領を実質的に仕切っているアメリカ政府の協力が得られる人物かどうかとなった。その中で選ばれたのが、幣原、吉田、芦田と言った元外交官であった。主権を回復し吉田が退任した後には外交官出身の首相は一人もいない。幣原と吉田に共通していたのは戦後日本が再出発し、新国家を建設する上で、国際社会=英米からの信頼を回復することを何よりも重視していたことである。その幣原の目標は天皇制の維持であり、当初は憲法についても改正は必要なしと言う意見だった。 日本の占領を円滑に進めるためには天皇制の維持が得策と判断したマッカーサーだが民主化はそのためには絶対的な条件となる。一方、幣原が招集した憲法問題調査会は国際情勢の潮流を理解せず、明治憲法をそのまま維持することを優先したためその憲法改正案はGHQに拒否され、GHQ案に基づいた憲法が起草されることになっていく。 戦争放棄はマッカーサーの三原則が元には有ったが、マッカーサーは幣原が提案したと述べている。実際には幣原はマッカーサーに対し戦争放棄のアイデアについて話をしたが憲法に含めることまでは考えていなかったようだ。「戦争放棄を宣言することで、天皇制に批判的な国際社会を懐柔せねばならない」だった。GHQに押し付けられた憲法案に不満を持ちつつ幣原がこれを受け入れたのは国際条約交渉においては限られた条件の中で大局的に判断をするしかないと言う国際感覚が働いたからだ。 幣原と対照的に描かれるのが近衛元首相だ。「近衛の自害は、大日本帝国の抱えていた宿痾とも言える無責任と弱さを象徴するかのようであった。はたして誰に戦争責任があるのか。なぜ、戦争を開始する必要があったのか。それを十分に自覚せず、その責任を十分に感じていない近衛の認識は、当時の多くの国民によっても共有されるものであったのだろう。日本は独裁と専横のもとで戦争に向かったのではない。むしろ近衛が示すような無自覚と無責任、そして絶望的な弱さから戦争に向かったのである。」
0投稿日: 2019.04.28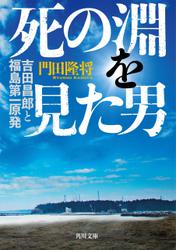
死の淵を見た男 吉田昌郎と福島第一原発
門田隆将
角川文庫
逃げる?誰に対して言ってるんだ。
吉田昌郎さんへの感謝を込めて。 主人公は吉田氏だけではなくいわゆるFUKUSHIMA50と言われる人たち。東電本社はともかく現場の人たちは限られた条件の中で出来ることはした。よくあの状況の中で自発的に必要な判断を出来たと思う。 一例に挙げると福一を最悪の事故から救ったのは津波と全電源喪失直後に1号炉に冷却ラインを作り消防車の応援を呼んでいたことだった。事故直後の報道ではわからなかったが吉田所長の最悪の想定はチェルノブイリの10倍の規模の放射能漏れであり、班目氏はさらに福島第二と東海原発への連鎖まで想定していた。彼らは専門家でありその想定は重い。しかし、全電源喪失については防げる事故でもあったのが残念だ。 一号、三号が爆発した3月15日の明け方席に戻った吉田所長はゆらりと立ち上がり、机と椅子の間に胡座をかき目を閉じて座り込んだ。その時周囲の人間はプラントの「最期の時」を感じたのだが、吉田は腹を決めている。「私はあの時、自分と一緒に”死んでくれる”人間の顔を思い浮かべていたんです」「やっぱり、一緒に若い時からやってきた自分と同じような年嵩の連中の顔が、次々と浮かんで来てね。頭の中では、死なしたらかわいそうだ、と一方では思っているんですが、だけど、どうしようねぇよなと。ここまできたら、水を入れ続けるしかねぇんだから。最期はもう、(生きることを)諦めてもらうしかねぇのかなと、そんなことをずっと頭の中で考えていました」 その吉田にテレビ会議で管が言う。「事故の被害は甚大だ。このままでは日本国は滅亡だ。撤退などあり得ない! 命がけでやれ」「撤退したら、東電は百パーセントつぶれる。逃げてみたって逃げ切れないぞ!」 逃げる?誰に対して言ってるんだ。いったい誰が逃げると言うのか。(なに言ってんだ、こいつ) 厳しい批判を受けた中では班目氏はどうやら限られた情報の中で想定される事態を把握していたようだ。少なくとも官邸に対しての助言は間違ってはいない。しかし、どうしようもなく当事者意識が無く官邸が自分の言うことを理解しなければどうなるか薄々わかっていながら怒れる管に何も言えないでいた。伝わらなければ正しいことを言っても意味が無い。 最終段階では出来ることはないとわかっていても残ろうとした若者もいた。残ってくれると信じていたが退避したものもいた(彼らを責めるのは筋違いだが)。そして新潟から応援に来てそのまま残った協力業者もいた。一旦退避してから戻って来たものも多い。「ヤクザと原発」によれば協力業者の中には必ずしも使命感だけで残ったのではなく、その場のノリで残ったものもいる。それもこれも含めて彼らに救われたんだろうと思う。
0投稿日: 2019.03.31
争うは本意ならねど 日本サッカーを救った我那覇和樹と彼を支えた人々の美らゴール
木村元彦
集英社文庫
いやあ、マスコミが騒いじゃったからさ〜
「先生、厳重注意処分でいいのではと書いてあるじゃないですか。どうしてドーピング違反にしたんですか?」 「いやあ、マスコミが騒いじゃったからさ〜」 2007年4月川崎Fは浦和レッズを我那覇和樹の先制点から2対1で下した。しかし、我那覇の体調は最悪で試合後は水も飲めないほどであった。2日後の練習も何とかこなすがチームドクターの後藤は生理食塩水を点滴した。治療は30分ほどで終了。そして駐車場へ向かう我那覇を報道陣が取り囲んだ。それが・・・ 「我那覇に秘密兵器 にんにく注射でパワー全開」この記者に我那覇は話をしておらず内容はでたらめ、この記事通りならドーピング禁止規定に抵触するものだった。 WADA(世界アンチ・ドーピング機構)の定義では疲労回復のためのにんにく注射は正当な治療とは言えず禁止方法に当たる。2007年1月の会議でJリーグのDC(ドーピングコントロール)委員長の青木治人は禁止規定の改定点の説明をしており、その際今後は全ての点滴で使用許可申請(TUE)が必要であるが、緊急時には事後でいいと説明していた。WADAの規定には「静脈内注入は、正当な医療行為を除いて禁止される」とある。我那覇のケースは正当な治療でありTEU提出の必要も無いのだが、青木はドーピングであると考えていた。 最終的に処分を決めるのはJリーグアンチ・ドーピング特別委員会だが医学メンバーはDC委員会と兼務しており検察がそのまま裁判官になっていた。WADA規定では対象者には抗弁の機会があるのだが川崎Fはこの機会を行使しないとし、我那覇には知らされないままだった。我那覇には6試合の出場停止、川崎Fには1000万円の罰金が科せられる事が決定した。 青木はさらにJリーグに適切な医療かどうかは現場の医師ではなくDC委員会が判断する。点滴は原則禁止であり、TUEは提出したからと言って必ず認められるとは限らないと伝えた。この前日ドイツ遠征で骨折し緊急帰国したのだがJリーグは「そちらが正当と判断したら先に手術してあとでTUEを出してください。その後で審議します。」と回答する。結局後藤はTUE認められる真夜中まで手術を送らせることになった。日本代表合宿でも風邪をこじらせた選手が点滴を受けられず肺炎をおこしている。 チームドクターたちが一致団結して立ち上がり質問状をだすがJリーグはとりあげない。ついにチームドクターは連絡協議会で青木と対決するが青木はFIFAからドーピングだとの回答が有ったと答えた。実はこれは青木が旧知の医事委員にガーリック注射はドーピングに当たるかとメールで質問したものであり、その回答は軽微な違反であり、厳重注意でいいのではと書いてあった。冒頭の一文はこのメールを見せられた浦和レッズのチームドクター仁賀が連絡協議会の後青木に見せられたときのやりとりだ。 後藤は日本スポーツ仲裁機構(JSAA)への申し立てを希望したがこの時反対したのは川崎Fだった。後藤に対して申し立てをするなら辞任をしろと迫る。そして浦和の仁賀が我那覇に送った手紙が我那覇を動かした。これまでの経緯とともに「この間違った前例が残ると全てのスポーツ選手が適切な点滴治療を受ける際に常にドーピング違反に後で問われるかもしれないという恐怖にさらされます」。これは、自分だけの問題ではないのだ。他のサッカー選手にも被害が及ぶ。こんな嫌な思いを他の選手にさせてはいけない。チームドクターたちが選手のために頑張っているのならば、そのために自分も声を出すべきではないのか。そして我那覇が立ち上がった。 Jリーグは我那覇の訴えをスイスのスポーツ仲裁裁判所(CAS)で英語でやるなら応じるとした。JSAAならば5万円で申し立てできるところが我那覇の負担額は最終的には3441万円(選手会やサポーター達の寄付でかなりの部分がまかなわれた)になっておりJリーグ側がプレッシャーをかけようとしていた事が見て取れる。結果は我那覇の完勝で、仲裁費用はJリーグの負担、さらに我那覇の負担した費用のうち2万ドルを支払うように命じている。懲罰的な判決だ。 それでもJリーグは反省の色は見せない。鬼武チェアマンに譴責処分が科されただけで、青木は処分を受けていない。鬼武は「CASはドーピング違反の認定が否定されたわけではない」と言って川崎Fへの罰金の返還を拒んだ。また、川淵会長もインタビューに答え「我那覇の名誉が回復された事はよかったと思う。ただ、その行為が違法だったのかどうか、何がどう悪かったのかは触れられていない。納得しづらい無いようになってしまったと思う」とコメントした。いずれも何が問題だったか全く理解しておらず、医学的な事は青木に任せており、選手やドクターの話には聞く耳を持たなかったのにだ。
0投稿日: 2019.03.31
SHOE DOG(シュードッグ)―靴にすべてを。
フィル・ナイト,大田黒奉之
東洋経済新報社
世界は繋がっている
始まりは神戸1962、徒手空拳、アイデアだけのフィル(バック)・ナイトはタイガーを売らせて欲しいとオニツカ(現アシックス)に飛び込んだ。アディダスが独占する北米のランニングシューズ市場に、安くて品質の良い日本製を持ち込めばいけるんじゃないか!カメラがうまくいったのだから靴だって。とはいえバックは世界一周旅行の途中でもあり、目的の日本の前にはハワイで3カ月近くサーフィンを楽しんだりもしている。 とにかくオニツカはバックを代理人と認定し前金50ドルでサンプルを送ると約束した。金は振り込まれ12足のシューズが届いたのは1年後だった。1963年のバックは地味に重要なキャリアを積んでいる。会計士の資格を取り収入基盤を手に入れた。のちに妻となるペネロペ・パークスと出会ったのは輸入業のかたわら収入を得るために助手として働いた大学でだ。倍々ゲームで成長を続けるブルーリボン社の弱点はキャッシュフロー、売れて喜ぶのはオニツカでバックたちの商売は回り続けるが危なっかしい。「会計士としての私にはリスクが、起業家としての私には可能性が見えていた。そこで私はその中間をとって、とりあえず進む事にした。」 バックの重要な資産となったのがオレゴン大コーチでのちにアメリカオリンピックチームのコーチになったビル・バウワーマンだ。タイガーのサンプルを気に入ったバウワーマンは共同経営者に名乗り出た。靴を良くするための多くのアイデアはバウワーマンが出したものだし、彼の弁護士ジャクアはオニツカとの対決では交渉役を務め、ジャクアの義理の兄チャック・ロビンソンは日商岩井との提携、中国進出そして上場と重要な場面でバックにアドバイスをした。 バックには徐々に仲間が集まってくる。手紙魔のランナーで安月給でも働き続けるナイキの名付け親ジェフ・ジョンソン、トラブルシューターで最後に頼りになる車椅子のボブ・ウッデル、PWcの先輩でのちにナイキで働くヘイズとオニツカの裁判からナイキの仲間になった弁護士ストラッサーなど。そしてのちに対決するオニツカではフジモトがバックの情報源となった。 1971年ブルーリボンの売り上げは1300万ドルに達したが、銀行は新たな融資を拒否しオニツカは買収を提案してきた。呑まなければ別の代理店に切り替えると。当面はオニツカを繋ぎながら自前のブランドの準備が始まった。ナイキの誕生だ。 新生ナイキには日商岩井が大きな支援をしている。資金を出しオニツカに変わる日本の靴メーカーを紹介したのが始まりだ。ポートランドオフィスでは世界中の工場をよく知るトム・スメラギがバックを支援し続けた。ニッショーファースト、まず日商岩井に払えその裏でスメラギは金回りに苦しむナイキのためにわざとインボイスの発行を遅らせ実質的なサイトを伸ばしていた。ナイキが不渡りを出した際に融資責任者のアイスマン・イトーに問い詰められるとスメラギは彼らが好きだから助けたと告白する「ナイキは私にとって我が子のようなものです」 銀行を始めとする債権者達を前にイトーが宣言する。「日商がブルーリボンの借金を返済します。全額」イトーに礼を言うバックへの返事はこうだ。「何とも愚かなことです」「私は愚かなことは好みません、みんな数字ばかりに気をとられすぎです」バックではなく銀行のことだ。二人のサムライがバックを支えていた。 ナイキのアイコンといえばジョーダン、コービーそしてオニツカではないタイガーが思い浮かぶ。そのタイガーが使ったことで花開いたトップブランドの開発初期を隣の研究室で見ていた。ひょっとしたら自分が担当していた可能性もなくはない。ゴルフシャフトのディアマナだ。当時の社長は皇芳之さんでその弟がトム・スメラギこと孝之氏。世界は繋がっているのだな。
0投稿日: 2019.03.01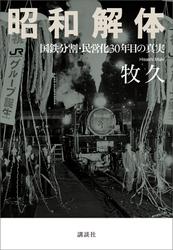
昭和解体 国鉄分割・民営化30年目の真実
牧久
講談社
昔は良かったわけではない
国鉄は明治39年以来国家の事業として日本経済の基盤を支えてきた。しかし昭和39年の新幹線開業と同時に赤字となると最終的には鉄建公団や年金を含めると37兆円の累積赤字に至った。田中角栄は47年度末に8千億の累積赤字となった国鉄を日本列島改造論でこう書いている。赤字線の撤去によって地域の産業が衰え人口が年に流出すれば鉄道の赤字額を超える国家の損失を招く怖れがあると。 昭和42年国鉄の職員数は47万人、翌年のダイヤ改正では増発などで3万人が必要で、石炭時代の名残の機関助士を中心に5万人の合理化を計画していた。2014年の東洋経済の記事では世界最大のウォルマートが220万人、2位のマクドナルドが44万人だ。国鉄の巨大さがよくわかる。ちなみに現在では6社+貨物の本体で12万人ほどだ。国鉄の分割・民営化は巨大赤字企業の再建を図るとともに、国鉄労働組合(国労)ー総評ー社会党の解体を目的とした戦後最大の政治経済事件でもあった。労使共にいずれは国がなんとかしてくれると親方日の丸意識に安住し、労使の対立、派閥抗争、組合同士の争いに明け暮れ政治家に利用された。井手正敬、松田昌士、葛西敬之の「三人組」を中心とした若手キャリアの改革派が立ち上がり、中曽根内閣の土光臨調では行財政改革の目玉として国鉄解体と民営化による再建を手がけた。現在単体の営業利益は北海道と四国を除けば黒字化し合計では1兆円を超える。 国鉄迷走の原因となったのが昭和43年に国労、機関士・運転士が中心の動労が勝ち取った現場協議制度だった。石炭をくべるため2人乗車だったのを1人乗車にして合理化をはかる当局に対し、反対した組合が代償として現場での団交権を手に入れたのだ。裏で絵を描いたのは国労中央執行委員の細井宗一、スト権の無い国鉄では違法ストを実施すると処罰が待っている。そこで「定められた運行手順を、ゆっくりと時間をかけて完全に実施する」順法闘争というサボタージュ戦術を編み出した国労きっての理論家だ。細井は国鉄は多少の赤字がいい、10万人きっても年間4千億、1兆円の赤字の有効打にはならないと語っている。同じようなことを言った田中角栄は同郷で満州へ赴任した騎兵連隊では士官候補生の細井が新兵の田中をかわいがると言う関係だった。 国鉄は国家独占資本主義の機構で、労働者を搾取し国民から収奪している。その利益の源泉が現場だ。現場が止まるのが一番怖い当局に対し、現場が団結することで組合は力を持つ。この細井の理論は結果的には現場協議を駅長や助役を吊るし上げる場に変え、職場は荒廃した。例えば昭和57年に朝日がスクープしたブルートレインのカラ出張は組合員ののタレコミによるのだが、その内容は外から見れば非常識そのものだ。毎日故障は発生しないと合理化のため降ろされた設備要員に既得権として手当の継続があったが「手当を支給しておいて、さらに合理化を強行するというのはどういうことか」とタレ込んだのだ。 国鉄当局の方も問題が多い。職場の管理権を取り戻そうと始めた生産性向上運動、略してマル生は労使協調して成果は配分されると言うものだ。しかしこの本では生産性向上の具体的な中身はない。マル生運動の実態は当局に賛同する組合員を取り込み組合を弱体化させるのが目的だったからだ。実際に国労からは1年半で5万人の組合員が脱退している。マル生に対するマスコミの風当たりも強く、昭和46年10月に不当労働行為の証拠テープが流れた。「いま騒がれているのは組合切り崩しの不当労働行為だ。しかし、やむにやまれずこれはやらなきゃいかん。知恵を絞った不当労働行為をやっていくというのだということがあるわけです。」 昭和47年沖縄返還協定発効後に佐藤首相が6月に退陣を発表、その3日後に田中角栄の日本列島改造論が発刊された。目玉は全国新幹線網の整備であり国鉄の赤字は拡大する。マル生に勝利した組合は増長し、順法闘争がきっかけとなる乗客の暴動が同時多発的に発生した。昭和50年組合はスト権の奪回を目指しゼネストに突入するがトラック輸送が普及した結果国鉄離れが進んでいた。国鉄の運行はマヒしたが国民生活はマヒしなかった。そしてスト権問題を協議していた専門委員会はスト権を認めないのみならず国鉄分割・民営化にまで言及していた。 この後政府、政治家、労使ともに権力闘争と一体となった国鉄対策が続く。成果は出た、今や日本の新幹線といえば定時運行、事故の少なさともに世界最高水準だろう。そこに向けた努力の積み重ねは評価すべきだが、国鉄を含め解体された昭和の世の中が今より良かったとはとても思えない。
0投稿日: 2019.02.04
フォッサマグナ 日本列島を分断する巨大地溝の正体
藤岡換太郎
ブルーバックス
日本海は拡がり、千葉沖は沈み込む、そして
世界に唯一の地形フォッサマグナ、そしてこれまた世界にひとつしかない海溝三重点。日本海の生成からフォッサマグナが生まれるまで何があったのか、謎は全ては解けてはいない。 フォッサマグナといえば日本海から太平洋にかけて本州を横断する大地溝帯のことだが有名なのは糸魚川ー静岡構造線だろう。長野の大町から諏訪を経て甲府まで左に日本アルプス、右には八ヶ岳などの山塊に挟まれた地形は確かに地溝としてはわかりやすい。実際に糸魚川ジオパークでは糸静線が目に見える。しかし糸静線はあくまでフォッサマグナの西端であり東端は明確にはなっていない。秩父などを含む関東山地は日本アルプスや東北地方と同じ古い地層だが関東平野がフォッサマグナに含まれるかどうかがはっきりしない。フォッサマグナの底は少なくとも地下6000mで日本アルプスとの落差は1万mほどになる。大昔は日本海と太平洋は繋がっていたかもしれないというまさに大地溝帯なのだ。 1900万年前日本は大陸にへばりついていた。その後日本海が拡大し1500万年前には日本列島は今の位置に落ち着いたと考えられている。ここからは仮設だ。プレートが沈み込むと冷えて重くなりマントルの底に沈み込む。一方高温のマントルからは地殻破って上昇するスーパーホットプルームが生まれマグマの供給源となる。このスーパーホットプルームが到達したことにより地殻は押し出されるように引き裂かれ拡大する。オラーコジンという説ではこの中心点から三方に裂け目が広がりTの字の上部は直線上に伸びる広い裂け目となり日本海を作った。下の細い裂け目がフォッサマグナとなったのだ。拡大する日本海に対しフィリピン海プレートが北上し、太平洋プレートが西進する。西日本は時計回りに、東日本は反時計回りに回転し今の日本列島の原型ができた。 同時期、フィリピン海プレート北端の伊豆半島が本州にぶつかり一体化した。沈みきれず剥離した地殻は乗り上げ丹沢山地となる。フォッサマグナの南側の堆積は海からもたらされたわけだ。中央構造線は九州から豊橋までほぼ一直線に伸びその後諏訪に向けて北上する。そしてフォッサマグナでは一旦姿を消すが関東山地の北側から霞ヶ浦に向かってまた現れる。伊豆半島に押し上げられた形だ。 北海道からフォッサマグナまでがのる北米プレートは東から太平洋プレートに南からはフィリピン海プレートに押され、西では西日本がのるユーラシアプレートで日本海が拡大した。房総沖海溝三重点から相模トラフ、糸静線からスーパーホットプルームの上昇点あたりまでが北米プレートの南端となる。プレートの境界に裂け目が広がり三重点を軸に北日本がねじれ、フォッサマグナが拡がったというのが本書から得たイメージだ。 プルームから生み出された三方の亀裂と海溝三重点の対比で締めくくられるのだがひとつ疑問が残った。3つのプレートのもうひとつの三重点は本書ではあまり触れられていない。甲府盆地辺りでユーラシアプレートと北米プレートとの境界線(糸静線)とフィリピン海プレートの北端が1点で交わる。つまりフィリピン海プレートの北端にあるのが富士山だ。これは偶々なのか?地下では何が起きて起きているのだろう。
0投稿日: 2019.01.13
経済学者たちの日米開戦―秋丸機関「幻の報告書」の謎を解く―(新潮選書)
牧野邦昭
新潮選書
秘密文書か秘策か
昭和19年(1939年)陸軍省軍務局の岩畔は関東軍から秋丸次郎を呼び寄せ石井細菌部隊に匹敵する経済謀略期間の創設を命じた。日本、アメリカ、イギリス、ドイツなどの戦争継続能力を分析し、それぞれの経済的な弱点を見極め対策を立てるのが目的だ。現在では「経済学者が対米戦の無謀さを指摘したにもかかわらず、陸軍はそれを無視して開戦に踏み切ってしまった」というのが通説となっている。あるいは経済学者たちは実際には高度な経済分析に基づく「秘策」を提示し、それを信頼した陸軍が開戦に踏み切ったという異説もある。著者は新たな証拠に基づき別の答えを導き出した。 ・アメリカとイギリスの経済力を合わせれば第三国に対しても供給余力はある。しかし、海上輸送には弱点が有りドイツがイギリスの船舶を月平均50万t沈めればイギリスを屈服させられる可能性がある。 ・アメリカも商船隊が老朽化しており現時点では輸送力が不足しがちである。 ・ドイツの抗戦力は現在がピークであり、対ソ戦を短期に終わらせウクライナの農産物とソ連の労働力を手に入れる必要がある。対ソ戦が長期化すると対英米戦長期遂行は全く不可能になる。 ・日本はドイツを助けドイツに対し強い立場に立つため、また英米ソの包囲を突破するためには北進ではなく南進して資源を確保すべきというのが「ドイツ編」の結論となっている。ただ、ドイツ編を書いた武村自身は慶応大教授として参加した座談会でドイツの思い通りにはいかないだろうと否定している。 ドイツが短期間でソ連に勝ち、抗戦力をつけてイギリス商船を沈める。日本は南進してイギリス領を支配しドイツと連携して中東の石油をイギリスに入れさせないようにする。できればアメリカにはドイツと戦わさせれば有利な状態で講和できるかもしれない。こういった内容は武村もいろいろなところで発表しており「秘密研究」ではなかった。またどうやってというのが無ければなんとでも書けるので秘策とも言えない。それではこの報告書がどう受け止められなぜ対米開戦に踏み切ったのだろうか。 日本が長期戦を戦うことが難しいというのは調査するまでもない常識であり、一般の人々にも英米との差は数字で公表されていた。では「非合理的な意思決定」「精神主義」が原因かというと著者は別の回答を示している。その一つが行動経済学でいうプロスペクト理論だ。 経済封鎖を受けた日本は3年後には確実にアメリカに屈服させられる。しかしドイツ編の結論にあるように極めて低い確率であっても開戦すればよりマシな講和の可能性がある。期待値では開戦しないほうが合理的な選択なのだが損失回避性が嗜好されリスクを取ると言うのがその説明だ。またリスクを取らなかったフランコ独裁のスペインとは違い日本には強力な意思決定者がいない「集団意思決定」の状態では極端な意見が採用されるリスキーシフトが起こったという社会心理学からの説明も試みられておりいずれも精神主義よりはもっともな意見に思える。世論も好戦的な対米強硬論が拡がっていた。 日米開戦を避けるために経済学者はどうすべきだったのか。同じくプロスペクト理論で言えばジリ貧にならずに3年後にアメリカに抗戦できるポジティブなプランがあれば開戦は先延ばしにされた可能性はある。例えば満州で発見された油田が有望であり日本は力を蓄えることができるであるとか。岩瀬昇氏の著書によれば、アメリカの経済封鎖を受ける前であれば関東軍が自前主義を捨てアメリカの探鉱会社を起用すれば大慶油田を発見できていた可能性は充分にあった。 牧野氏にしてから武藤章軍務局長の考えを否定しない。屈服する民族は永久に屈服する、避けられない敗戦でも再び伸びることを期待して戦うことを選んだ。「日本が太平洋戦争によって多くの経験をし、反省し、教訓を学んだことが戦後の日本の発展につながった」と。であれば経済学者はやはり開戦を止められない。 この本では対中戦についてはほとんど語られていない。そもそも中国は主要な研究対象にもなってないようなのだ。3年後にジリ貧になるのは中国や満州の権益を捨てられないからで、今から見れば損切りをしてアメリカからの経済封鎖を解くというのも合理的な対案となる。それができない理由がいくらあったにせよ検討すべき方策だったはずだ。後知恵ではあるのだがそれが歴史から学ぶということだろう。
0投稿日: 2018.12.07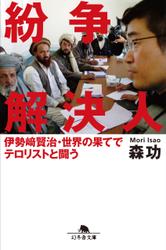
紛争解決人 伊勢崎賢治・世界の果てでテロリストと闘う
森功
幻冬舎文庫
現場の国際貢献という意味で言えば憲法9条はまだまだ使える
建築家志望の伊勢崎賢治が紛争屋になったきっかけはたまたまインド政府の国費留学に申し込んだことからだった。伊勢崎は世界最大のスラム、ダラビでわずか10人のNGOで40万人の住民の組織化を目指した。後に紛争地帯の住民を味方につけ地域を安定化させる手法の元がこの時に培われていた。リーダーになり得る人物をスカウトし教育するのが伊勢崎のソーシャルワーカーとしての仕事だ。宗教対立や民族対立で殺しあってきたスラムを組織化するには、水がないトイレがないと言った具体的な必要性に基づきそれらの共通目標を獲得するために協力させる。このまま紛争を続けると生活できなくなるとの生存に直結した必要性が団結を生むと言うのが紛争地帯の安定化の出発点だ。 次に伊勢崎は国際NGO職員としてシエラレオネに赴任した。伊勢崎は大統領の指名で事務所のあるマケニの市会議員となり国内屈指の実力政治家として名を馳せる。議員としての立場がないと開発事業も動かないのだ。隣国リベリアの軍事クーデターが波及しシエラレオネ政府は崩壊した。伊勢崎は1992年4月に内戦状態のシエラレオネを後にした。ハードシップも有るが業者との癒着を防ぐと言う国際NGOの方針により任期が来たためだ。 1999年独立を目指す東チモールのPKOに参加しインドネシア軍との最前線の県知事として国連平和維持軍を率い、対面するインドネシア軍、独立派の東チモール民族解放軍、ゲリラ活動を続ける併合派民兵とのパワーバランスの中で地域の安定化を目指した。3年以内に東チモールは国連の手を離れ自ら治安を維持しなければならないが伊勢崎は軍の創設には反対だった。紛争地帯の軍のだらしなさを実感しており、クーデターの原因にもなるからだ。 「日本が憲法9条をなくし、国防軍を持つという事態は、有事の際に国民がみな銃を持って戦うということを意味します。日本国内では甘く考えるきらいがあるが、それこそ平和ボケというものでしょう」理念より現場を優先する伊勢崎の言葉だ。 伊勢崎は武装解除を進めたが国軍は創設され、同程度の兵力の警察との主導権争いも起こる。そしてクーデターが起こった。 東チモールを離れた伊勢崎は再び戻ったシエラレオネのPKO、そしてアフガニスタンでは日本政府の特別顧問として武装解除を指揮していくがアフガンの老兵から武器を奪ったことで力の空白が生まれタリバンが復活した。アメリカが急ごしらえで作った警察組織は腐敗し、タリバン政権ではなかった史上最悪の麻薬国家が生まれた。政治的な前進は軍事的な後退につながったのだ。武装解除は時期尚早という伊勢崎たち現場の意見は受け入れられなかった。 結局タリバンと妥協しながらも、穏健派を見つけて対話し、地元の社会には開発という利益誘導で地域を安定化させテロの温床となる不満を取り除いていくしかない。タリバンを支援してきたパキスタンの諜報期間ISIの新長官がシエラレオネPKOで伊勢崎に協力してくれた将軍だったこともあり国境開発はうまくいくように見えたが、就任したてのオバマがアフガン撤兵対策の為にアフガン総選挙を強行したことから雲行きが怪しくなった。そこでアメリカが考えたことが国防軍の倍増だ。軍に武器を持たせアメリカの代わりにタリバンと戦わせる。しかし増強された軍は機能せず、カルザイ政権は求心力を失い、民兵ゲリラやテロリストが跋扈し、国内の腐敗が急速に進んだ。 「ゲリラは民衆の海を泳ぐ魚である」だから民衆を味方につけゲリラの住みにくい海を作る。それはアメリカもわかっているが当事者に問題が有るからできないし、民衆もアメリカを信用しない。そこで伊勢崎は日本が貢献できるという。「テロの温床となっている地域において日本ほど評判がいい国はありません。それは日本の憲法があるから。日本は第二次大戦後、戦争をしたことがない。永世中立国以外でいえば、先進国で唯一の立ち位置なのです。」 自衛隊には軍法が無い。憲法を変えない限り今後も持てない異常な状態で海外派遣されている部隊だ。では国際貢献のために憲法を変えるべきなのか。「現実と理想の乖離があり、矛盾もあるのは間違いありませんが現場の国際貢献という意味で言えば憲法9条はまだまだ使える。というか、今ここで踏ん張らないと、最大の国際的課題であるテロとの闘いに光が見えなくなるように思えるのです。この先、憲法は変えなければならなくなる時期が来るでしょう。しかし、いまはその時期ではない。世界のために今なくすのは惜しい。もう少し使い古してから変えた方がいいと思うのです」非武装の停戦監視団の派遣など現状でも日本が必要とされる役割は大きいという。国際貢献に部隊を派遣するには国民の理解と覚悟が不可欠になる。憲法をどう変えていくかはその先にあるのだろう。
0投稿日: 2018.11.27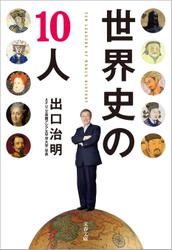
世界史の10人
出口治明
文春文庫
ナポレオンやカエサルや始皇帝だけじゃない
なにを成し遂げたか、後世にどの様な影響を与えたかで、真のリーダーかどうかが決まる。そして歴史的にはある集団が長く生命力を保つためには軍隊と役人、つまり軍事組織と官僚制がしっかりしている必要がある。フェアな官僚制というシステムは、民主主義と同じ様に、これを超えるものを人間はまだ考え出していない。 この本で選ばれたのはユーラシアの大平原に帝国を築いたバイバルス、クビライ、バーブル。いわゆるゲルマン民族の大移動の時代にできた遊牧民帝国の武則天、宋の王安石。ヨーロッパの祖母アリエノール、ローマ教皇を無視したフェデリーコ2世、海賊の胴元テューダー朝のエリザベス1世、ロシアの女帝エカチェリーナ2世そしてナポレオン3世。あえてロールモデルとして女性を4名入れている。素直にナポレオンやカエサル、始皇帝などが入ってこない。 ユーラシアの歴史を動かして来たのは強力な北方の遊牧民族の南下で、中華では遊牧民を取り込み漢民族に同化していき、ヨーロッパでは遊牧民を追い払ったリーダーが強固な王権を手に入れた。 中世温暖期まで西方世界の中心は東ローマからイスラム世界であり、ヨーロッパは辺境の地だった。温暖化すると北方騎馬民族はユーラシアの草原地帯から南下する必要がない。ヨーロッパでは人口が増え食糧も行き渡る。そこで相続対策でもあったのが十字軍だった。イスラムからすると野蛮なフランクの侵略と映る。十字軍を押し返しアイユーブ朝と言うクルドの王朝を建国したのがイスラムの英雄サラディン、そしてアイユーブ朝を支えた軍事組織が奴隷出身のトルコ人でバフリー・マムルークだった。その実態は奴隷というより私兵に近い西方に流れた遊牧民族の末裔だ。 第6回十字軍の遠征ではスルタンのサーリフが病死し皇太子も不在、この危機を救ったのがこれまたトルコ系奴隷出身の後妻シャジャルでエジプト軍副将のバイバルスがフランス軍に圧勝し、バイバルスの謀反を恐れた皇太子がバイバルスの返り討ちにあい、アイユーブ朝が滅び、シャジャルがマムルーク朝の初代スルタンについた。シャジャルは再婚し夫、息子が後を継ぐとバイバルスは追放され辛酸を舐め、マムルーク朝ではシャジャル一家での内紛が続く。事態が変わったのがモンゴルの襲来で、クビライの弟フレグがエジプトに迫ってきた。 モンゴル側もクビライとフレグの跡目争いが起こりかけたのだがクビライが先んじ、フレグはアゼルバイジャンにフレグ・ウルスを建国した。バイバルスはフレグ不在のダマスカスのモンゴル軍に戦いを仕掛け不敗のモンゴルを始めて破った。バイバルスの生涯の戦績はモンゴルに9回、十字軍とは21回戦い連戦連勝だった。勝ったバイバルスは第5代のスルタンにつきイスラム世界に権威を確立した。その後マムルーク朝はオスマン・トルコに滅ぼされるまで270年の治世を続けた。 日本では全然知られていないバイバルスだが対外的には戦争に勝ち、内部では一度追放されたものの裏切りと内紛では最終的に勝ち抜いている。 他にも官僚制を確立した王安石、ヨーロッパ最初の合理的な近代人としてカエサルやナポレオン1世と並ぶ影響を後世に残したフェデリーコ2世なども知らなかったが世界史の10人と呼ばれるにふさわしい。ロシアの崩壊後に遊牧民世界の歴史研究が進み評価が大きく変わったと言うのも面白い。権力者が伝えた歴史観にはバイアスがかかっているのだ。
0投稿日: 2018.09.23
okadataさんのレビュー
いいね!された数197
