
ハーモニー
伊藤計劃
早川書房
テーマはおもしろいのだけれど
うーん、やっぱりそこまで良いとは思えず。。。おもしろいはおもしろいのだが、評判がよくて期待しすぎてしまったか。ヒトの「意識」をテーマにするのはよいけれど、虚構をホントらしく見せるのになんかもう一押し足りない気がする。 しかし病気で死を意識しながらこういうのを書いたっていうのはなんだかドッシリくる。健康云々ってところじゃなくて、ヒトの「意識」を問題にしているところが。
2投稿日: 2014.01.06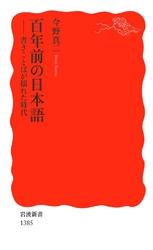
百年前の日本語 書きことばが揺れた時代
今野真二
岩波新書
明治期日本語の"虫"瞰図
サブタイトルに「書きことばが揺れた時代」とあります。これを見ると、百年前≒明治期に、それまで安定していた日本語の書きことばが「揺れた」という本なのかと思います。しかし読んでみると話は少し違っていて、それまで揺れ続けていた日本語表記が標準化に向かったのが明治期だったということです。 明治より前の日本語では、漢語は外来語であると(今よりかは)強く意識されていました。それがますます和語に溶け込んでいくのが明治期以降の流れで、ほかにも印刷物の普及や、学校教育による標準化で、現在の書きことばが出来上がっていく様子が描かれています。むかしは崩し字の活字まであったとか、トリビア的な要素も多くて楽しめます。 本書で少し気になるのは、とにかく事例が多く取り上げられているのですが、それらを総括して大きな流れを考察したりするところが少ない点。著者もあとがきで、自らの研究スタイルを「虫瞰」と称しています。ワタクシ個人としても、やたら声高だったり大風呂敷を広げるスタイルより、事実に語らせる「虫瞰」スタイルが好みですが、一般向けの新書であるので、さすがにもう少し説いて聞かせるようなアプローチでもよい気はします。
2投稿日: 2014.01.06
虐殺器官
伊藤計劃
早川書房
筆の勢いがすごい
言語による認識、自由意志、進化論などをテーマに、近未来(ポスト9.11って感じ)の米軍暗殺部隊を描いているSFです。 たいへんに評判となった作品ですが、個人的には肌にあわないところがありました。ところどころ説明的で薄っぺらくおもえたり、”虐殺の器官”もちょっと拍子抜けの感が。。。それでも、筆の勢いというか一気呵成に書き上げた熱は読んでいて伝わってきました。欠点もその勢いとのトレードオフなのかもしれませんね。
2投稿日: 2013.12.13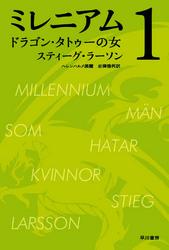
ミレニアム1 ドラゴン・タトゥーの女(上・下合本版)
スティーグ・ラーソン,ヘレンハルメ美穂,岩澤雅利
早川書房
主人公のキャラ設定にひとひねりあり
全世界でベストセラーだそうですが、主人公コンビのキャラクターがやっぱり魅力的だからでしょうか。あとは奇をてらったところのないオーソドックスなミステリだと思います。この手のシリーズものは長くつきあうことによる楽しみや味わいがあるものですが、作者急逝で3巻までになってしまったのは残念。 スウェーデン人の登場人物名をおぼえるのに少し苦労しましたが、そういうときに電子書籍の検索機能がけっこう役に立ちました。「あれ、この人だれだったっけ?」がすぐに検索で分かります。
1投稿日: 2013.12.13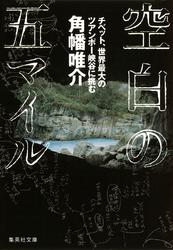
空白の五マイル チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む
角幡唯介
集英社文庫
遅れてきた探検家
舞台となるのはツアンポー渓谷。チベット高原を横断しインドへ流れ込むツアンポー川(現地語でヤル・ツアンポー、実はツアンポーの方が「川」って意味なのですが)がヒマラヤ山脈東端でおれまがる屈曲部の渓谷です。19世紀までは、そもそもツアンポー川の下流がどこにつながっているかすらも諸説あり、ほとんど人跡未踏の地でした。「空白の5マイル」とは、1924年にツアンポー渓谷を踏破したフランク・キングドン=ウォードが探検できなった最後の秘境をさします。 著者は早大探検部OBです。空白の5マイルとはいうものの、1990年代にはあらかた探検されてしまっています。それでもわずかに残された秘境に挑む、いわば遅れてきた探険家であるがゆえに「何でそこまでするの?」という問いが否応なく浮かびあがります。装備が不十分だったり、中国政府の許可がなかったり、結構ムチャな単独行。そのムチャに、臨場感というか読み応えがあります。
3投稿日: 2013.12.08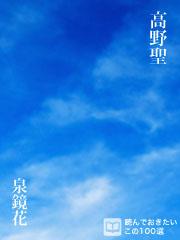
高野聖
泉鏡花
青空文庫
ル、ルビが。。。
怪談ですね。旅僧がむかしの体験を作者に語ってきかせるという趣向。 内容はともかく、おびただしく振られたルビを括弧書きにくくりだしているのは読みにくいです。他にやりようがないのでしょうか。短い話なので読みきるのに困難はありませんが、なんというかリズムが大切な文章なのにちょっと残念です。
0投稿日: 2013.12.01
渚にて 人類最後の日
ネヴィル・シュート,佐藤龍雄
創元SF文庫
静かな静かな
オリジナルは1957年刊行。原題"On the beach"は、巻頭に掲げられたT.S.エリオットの詩からとられていますが、巻末解説によれば「陸上勤務となって」という慣用句でもあるそうです。 核戦争後の世界を描くというのはSFとしてはステレオタイプでもありますが、1957年という年代を考えると、本作はそのはしりだったのでしょうか。牧歌的ですらある取り残されたオーストラリアの光景にはじまり、物語は淡々と進みます。こんな枯れた味わいのSFというのも珍しい気がしますが、ある状況を設定してみて、そうした状況のなかで人々がどう行動するかを描く、というのはSFの王道でもありますね。 メアリの言動がなんだかうちのカミさんを思わせてラストがますます切ないです。
4投稿日: 2013.12.01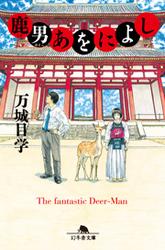
鹿男あをによし
万城目学
幻冬舎文庫
『坊ちゃん』+しゃべる鹿
奇をてらったようでいながら物語のつくりがカッチリとしていて悪くないです。キャラといい伏線といいストーリーといいベタといえばベタなんですが、基本を外さない感じでとにかく気分良く読めます。設定の大ボラぶりも好きです。 この感じ、特に中高生くらいにオススメでしょうか。もちろん大人が読んでもOKです。
2投稿日: 2013.11.19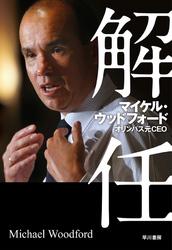
解任
マイケル・ウッドフォード
早川書房
衝撃の告白!っていう訳ではないですが
事件発覚から2年ほど過ぎて早くも古びた感じはありますが、オリンパス元社長の事件にかかわる手記です。 やはり支援してくれた人への配慮から記述を省いているところもあるようですし、なにか驚きの新事実が具体的にあるというわけではありません。しかし、当事者としての心の動きや、菊川氏らの様子を間近から見た記述は、ワタクシも一組織人として興味深く読みました。やっぱり集団思考って怖いです。 これを読んでも、なぜウッドフォード氏を社長にしたかなど、この事件に関する疑問点はいくつか残りますね。
0投稿日: 2013.11.12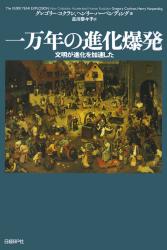
一万年の進化爆発 文明が進化を加速した
グレゴリー・コクラン,ヘンリー・ハーペンディング,古川奈々子
日経BP
意欲作にして問題作
人類の進化は今まさに進んでいて知能が自然選択で伸びたりしているという、ともするとポリティカリー・インコレクトな主張をしています。 たしかに、見た目の違い、オリンピックの100m走、乳糖耐性、鎌状赤血球などを見れば、民族間で遺伝子レベルに由来する表現型の差異があるのは明らかに思えます。それが知能に話が及ぶと、急にムズカシイ問題になってしまいます。 著者らの論証は説得力のある部分もありますが、肝心な所で細かい説明を省いていたり(2Sやユダヤ人の遺伝的ユニークさ)して、個人的には懐疑的です。しかし、そのデリケートさゆえに真正面から論じられにくい分野であるので、こういう議論自体は非常に興味深いものです。
2投稿日: 2013.11.12
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
