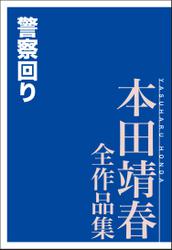
警察回り 本田靖春全作品集
本田靖春
講談社
昭和の新聞記者
元読売社会部の記者による自伝的ノンフィクション。昭和30年代を中心に、キーとなる登場人物の「バアさん」が亡くなる昭和60年までが本書の時代背景です。著者は昭和60年ごろの視点から、かつての警察回りを懐古しますが、読んでいるこちらはその後さらに時代が移り変わっていることに思いを馳せました。 この本、意地悪く見れば鼻持ちならぬやさぐれエリートの懐古譚でしかないのですが、それがなかなか胸に迫ります。著者の熱い思いによるものなのか、それとも、昨今の世相が窮屈なため自分が生まれてもいなかった昭和30年代を懐かしんでいるのでしょうか。
1投稿日: 2014.05.01
誘拐 本田靖春全作品集
本田靖春
講談社
昭和38年のの誘拐事件
「吉展ちゃん事件」について読売の元記者がかいたノンフィクション。犯人である小原保の生い立ちや行動にスポットライトをあてています。 東京で自分のだらしなさ故に借金を作ってしまった小原。決してベラボウな金額ではないが首が回らなくなります。金策のため郷里へ帰るものの、会わせる顔もなくてこそこそと野宿して過ごします。故郷には頼れる人もないことが改めて身に沁みたことでしょう。そして本来は交わるはずのない小原の人生と、村越家の人生とが、不幸な形で交わることになります。 なお同テーマを扱った本で、元東京新聞記者により後から出版された『誘拐捜査』があります。捜査陣の内幕については、当時の担当記者が書いた『誘拐捜査』がより詳しいです。
0投稿日: 2014.05.01
国をつくるという仕事
西水美恵子
英治出版
個人的には語り口が苦手
世界銀行で副総裁(*)をしていた著者がその仕事を振り返る内容です。途上国に健全なガバナンスをもたらそうという熱意にあふれていますが、熱意があふれすぎて語り口が説教くさく感じられ閉口しました。個人的な好みの問題に過ぎませんが。ちなみに同じような理由で塩野七生も苦手です。 ムシャラフ高評価&ブット低評価、グラミン銀行嫌い、ブータン大好きなど、現場で接した方ならではの個別評価は興味深いです。 *)世銀には副総裁がたくさんいるのでナンバー2という感じではありません。外資系の Vice president ってやつですね。
1投稿日: 2014.04.06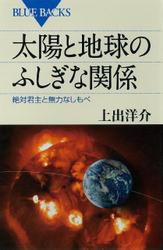
太陽と地球のふしぎな関係 絶対君主と無力なしもべ
上出洋介
ブルーバックス
太陽にお世話になっていない人はいないことですし
サブタイトルによると「絶対君主=太陽」と「無力なしもべ=地球」です。単に暖かい日光を燦燦と浴びせるだけではない、もっとダイナミックな太陽圏に地球もすっぽり包まれているわけです。人工衛星時代になりやっと知見が集まりだしたばかりの分野とのこと。 フレア爆発などによりプラズマや高エネルギー粒子が降り注ぐのを、地球は自身の磁気圏でなんとか防いでいます。太陽活動が活発化すると、オーロラが出現するにとどまらず、通信がかく乱されたり伝書鳩が迷子になってみたりと人間社会に直接的な影響すら及びます。また、太陽活動の変動は気候変動にも影響しています。 ひとつ気になるのが、そんな大事な地球磁力の減少傾向。ガウスが200年前にはじめて測定して以来、年0.05%のペースで減りつつあるらしいです。メカニズムは不明。このペースのままだと1200年ごろにはゼロになる計算。日本でもオーロラが見れる!と喜んでいる場合ではなく、地球磁力がなくなると放射線がビシビシ降り注ぐし、大気を太陽風に持っていかれるしで大変なことになります。N極・S極が入れ替わる現象さえ地質学的年代スケールではたまに起こっているので、このまま一直線に減ることはなさそうですが、たかが200年間とはいえ足元で急速な変化が生じているのは何となく穏やかでないです。 この本について敢えて注文をつけるとすると、語句の解説などをもっと丁寧にできたのではないかという気がします。また、思いのままに語っているような書きぶりで、繰り返しが多くて少し散漫に感じるところも。編集次第で改善の余地ありでしょう。 また、画像での電子書籍化というのはチトいただけませんね。多くの点数を早く電子化するひとつの手ではあるのでしょうが。。。(ちなみにワタクシは以前に紙で読みました)
1投稿日: 2014.04.06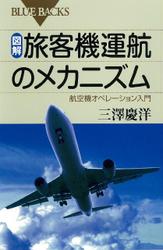
図解 旅客機運航のメカニズム 航空機オペレーション入門
三澤慶洋
ブルーバックス
飛行機に乗る人なら楽しめそう
旅客機「運航」がテーマなので、出発準備から、飛行計画、離陸、航行中、着陸までを通して、ふだんは見ることのできない裏側を解説してくれます。そんなにハードな話ばかりではないので、豆知識好きな方なら「ふーん、こうなっているのか」と楽しめるのでは。 個人的には、飛行機のトイレがすごい勢いで吸い込むメカニズムに膝を打ちました。 しかし、画像での電子書籍化というのはチトいただけませんね。多くの点数を早く電子化するひとつの手ではあるのでしょうが。。。(ちなみにワタクシは以前に紙で読みました)
0投稿日: 2014.04.06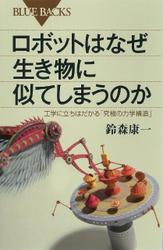
ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか 工学に立ちはだかる「究極の力学構造」
鈴森康一
ブルーバックス
比べてみてこそ気づくことも
著者はロボットの専門家です。ひとつにはロボットと生き物とがはからずも似てしまう例を、もうひとつにはそれでも違うロボットと生き物の特徴を挙げていきます。 ロボットと生き物との相違点の一例として、やわらかさ=コンプライアンスの違いがあります。人間はやわらかい筋肉と、拮抗筋や二関節筋の採用により、周囲の環境からのフィードバックに絶妙に対応する能力を手にしています(逆にロボットみたいに中腰のまま立っていると疲れてしまう)。しかし、その機能を解き明かすことで、もっと「やわらかい」ロボットを作ることも可能になってきているそうです。 また、敢えてロボットと比べることによって、当たり前として見過ごしてしまいそうな生き物の特徴が見えてきます。ふつうは人間の腕関節を「自由度」という観点から考えたりはしないでしょう。進化のようなランダムな試行錯誤でできたデザインと、人間がアタマを使って設計するデザインとの比較として読んでも面白いです。 しかし、画像での電子書籍化というのはチトいただけませんね。多くの点数を早く電子化するひとつの手ではあるのでしょうが。。。(ちなみにワタクシは以前に紙で読みました)
1投稿日: 2014.04.06
絶対音感
最相葉月
新潮社
ワタクシ自身は相対音感すら怪しいのですが
前から評判は知っていたのですが、テーマへの興味がイマイチで読んでいませんでいた。このたび著者の新刊を読むにあたって予習的な気持ちで手にとったものです。 読みはじめは「このテーマでなにを書くのかな?」と思ってしまいましたが、日本の音楽教育史、認知科学、現代のクラシック音楽の一断面まで、絶対音感をキーワードに話は広がっていきます。 著者がわりとオモテに出ててくる文章ですが、要所要所は抑制が効いて読みやすいです。「素人の視点からがんばって取材をして書いた」感じがプラスに出ている気がします。
0投稿日: 2014.03.16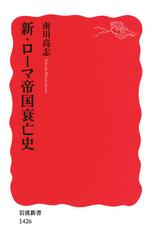
新・ローマ帝国衰亡史
南川高志
岩波新書
衰亡の原因は結局よく分からず
本家本元のギボン『ローマ帝国衰亡史』にたいして21世紀の衰亡史を書こうとのねらいだそうです。本家は文庫本で全10巻。こちらが断然、手に取りやすいのは確かです。 カエサルの時代(前1世紀)、ローマ最盛期の五賢帝時代(2世紀)、軍人皇帝時代(3世紀)からまず概観して、コンスタンティヌス大帝、ウァレンティニアヌス朝、東西ローマ帝国分裂(4世紀)、西ローマ皇帝廃位(5世紀)までを扱っています。ローマの歴史に詳しくないので、ざっと掴むのにはありがたい記述の分量でした。 著者の主張は、ローマ人アイデンティティの崩壊=偏狭な排外主義がローマ帝国衰亡につながったと読めます(実はあまり因果関係を明示的に主張してはいないのですが)。しかし、帝国の勢力衰退が排外主義台頭につながったと、因果を逆に考えるほうが素直に思えました。
6投稿日: 2014.03.09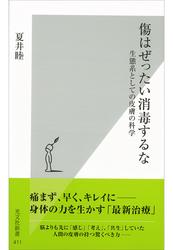
傷はぜったい消毒するな~生態系としての皮膚の科学~
夏井睦
光文社新書
けっこう論理的
少々くどくて独善的な語り口のせいかホントかいなと思うところもありますが、湿潤療法なんてなぜだかウチの会社の休憩コーナーにも張り紙がされていたし、常在菌の話など人体のトータルなバランスを重視する考え方は時代の流れかもしれません。 なんで大腸吻合部を消毒しないでOKか(できるわけないのだけれど)なんて疑問を持った、著者の論理思考は分かりやすいです。創傷治癒機能が転用されて脳神経系ができたという仮説も面白く読みました。
0投稿日: 2014.02.09
3日もあれば海外旅行
吉田友和
光文社新書
うーん、海外に遊びにいきたい
いさぎよくノウハウに徹した実用書。なんとなく旅に出たい気分にはなります。 賞味期限は短そうな本ですし、これくらいの内容ならググってなんとかしなさいという見方もありえますが、こうやって旅という軸で一冊にまとまっている価値はあると思います。航空券の仕組みとかよく知らないので改めて解説してもらうと意外とありがたかったり。なかなか旅慣れしない身としては旅支度の話なんかも期待していたのですが、「語り始めたらキリがないほど奥深い」とのことで、そこはごくサラリとだけ。
0投稿日: 2014.01.06
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
