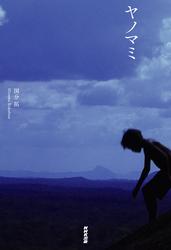
ヤノマミ
国分拓
NHK出版
ヤノマミとは彼らの言葉で「人間」という意味です
ブラジルの先住民族と同居してノンフィクションを撮ったNHKディレクターによる本です。番組は既にTVで見ていて、生まれた子供を精霊として森に還す様が非常に印象に残っていました。 言葉も文化も異なる人々の中に入り込んでいく苦労から始まり、彼らの行事・祭りの様子、家族関係や個々の人物像、シャーマンとその思想、そして女たちの出産へと村の描写がされていきます。終盤は一転して、長老シャボリ・バタがこの村ワトリキに至るまでの流転へ。淡々と語られる歴史ですが、病気による大量死などが語られ圧巻です。今の彼らの姿だけでは平板なものになりかねないところを、歴史と重ね合わせることで移ろい行く儚さが見えてきます。最後のとどめは文明に触れて変わり行くヤノマミたち。起承転結のはっきりした展開で読ませます。さすがTVマンですね。 ヤノマミと照らし合わせることで、われわれが当たり前だとか絶対と思っている価値観の相対性が沁みるように分かります。われわれもヤノマミ同様、大きな世界の中のちっぽけな存在です。
1投稿日: 2013.10.13
顔のない裸体たち
平野啓一郎
新潮社
期待して読んだのですが、、、
一見したところテーマが刺激的なようでいて、紋切り型にはまっているというか新鮮味を感じませんでした。こういうテーマで書くのって意外と難しいものなんでしょうね。
0投稿日: 2013.10.13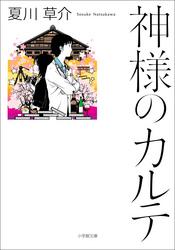
神様のカルテ
夏川草介
小学館文庫
品が良いお話
ともすると「さあ泣きなさい」と言わんばかりのお話なのですが、不思議といやらしさを感じず素直に読めました。主人公の語り口なんて奇妙な設定ですが、その辺のひねりがうまく働いて品の良さを出しているのでしょうか?松本の風景や、下宿の様子なんかもイイ雰囲気を出しています。 あと、書いているのがホンモノのお医者さんだそうで、やっぱり病院の描写は元手のかかり方が違うだけあってリアルだと思いました。
3投稿日: 2013.10.13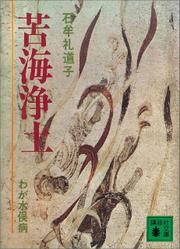
苦海浄土 わが水俣病
石牟礼道子
講談社文庫
容易ならざる「小説」
水俣病告発の書、という側面も勿論ありますが、ただそれだけにとどまらぬものがある作品です。巻末の渡辺京二による解説(Reader Storeで売っているのと違う版で読んだので、こちらにも付いているのか分かりませんが)で明らかにされていますが、この本をノンフィクション・ドキュメンタリーに分類するのは的を射ていないかもしれません。
1投稿日: 2013.10.13
ミッドウェー海戦―第一部 知略と驕慢―(新潮選書)
森史朗
新潮選書
太平洋戦争のターニング・ポイント
ミッドウェー海戦といえば太平洋戦争の流れを変えた戦い。まだ日米の戦力はほぼ互角でしたが米側の圧勝に終わったため、なにが明暗を分けたかを解き明かそうと多くの言説があります。本書は2012年刊と比較的あたらしい本ですが、両軍の公式記録だけでなく著者が長年にわたって行ってきた関係者へのインタビューを元にしており、海戦の推移を大局的な観点、および当事者の思いの両面からつづっています。 本書は、わりと有名な「運命の5分間」を参謀らによる責任逃れの作話として退けており、南雲司令部の慢心(真珠湾攻撃前の悲壮感とはだいぶ違ったらしい)や優柔不断さを主な敗因としています。けれど個人的には、ひとつひとつの経緯を追っていくと、むしろ錯綜した「戦場の霧」の中でのちょっとした運が勝敗を分けたのだと感じました。取材した情報を積み上げてある本なので、そうした多面的な読みもできるのだと思います。 やや記述が錯綜していて分かりにくいところもあるのが残念ですが、臨場感をもってミッドウェー海戦の様子を伝えてくれる本です。
0投稿日: 2013.09.29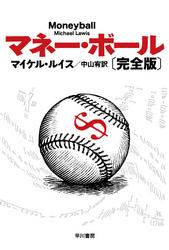
マネー・ボール〔完全版〕
マイケル・ルイス,中山宥
ハヤカワ文庫NF
マイケル・ルイスの魅力
マイケル・ルイスはシニカルな筆致が特徴ですけれど、その裏側に取材対象への優しさとかあたたかい眼差しがほのかに感じられるのが好きですね。 この本について言えば題材の面白さもバッチリだと思います(セイバーメトリクスもよく知られるようになったので以前ほどの新鮮味はないかもしれませんが)。野球か統計かのどちらかが好きならば楽しめるでしょう。
2投稿日: 2013.09.28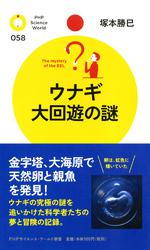
ウナギ 大回遊の謎
塚本勝巳
PHPサイエンス・ワールド新書
ウナギ研究の40年
ウナギたちが、太平洋は遥か南方のマリアナ海溝あたりで産卵しているのが明らかになったことは聞き及びの方も多いと思います。あの黒いニョロニョロが大海原を何千kmも泳ぐ姿を想像すると、「何故わざわざそんな遠くで?」という疑問が湧き上がってきますよね。 この本は、魚の回遊行動を研究してきた先生が書いています。ウナギの豆知識解説書であると同時に、産卵場所探しに取り組んできた研究者の半生記であり、仮説を元にフィールドで実証に至る科学のプロセスを解説した本でもあります。著者40年の研究生活を贅沢に素材にして、薄い新書にギュッと詰め込んだような一冊です。 著者の塚本先生がはじめて調査船に乗り組んだのが1973年の「第1回白鳳丸ウナギ産卵場調査」。それから天然ウナギ卵を発見するまでのあいだ、何回にもわたって航海が繰り返されました。この間、もちろん闇雲に海を探していたわけではありません。手持ちのデータを元に産卵場所の仮説を立てて、それに基づいて網を引いてまわってウナギの稚魚を採集します。広い海をグリッドに区切って、稚魚が採れる海域/採れない海域、採れたならばサイズや海流をマッピングしていくのです。成果があがる航海ばかりでなく、望む小ささの稚魚がぜんぜん採れないこともあります。徐々に網を狭めるように産卵場所を突き止めていくプロセスは、丁寧な解説や詳しい図表のおかげで、研究者の思考を追体験できるようです。 Readerでこの本を読むにあたっての注意点は、カラーの図版がふんだんに使われていることです。長い本ではないので、もしお持ちならばタブレットで読むのがオススメです。もちろん紙の本、という手もありますが。。。
3投稿日: 2013.09.27
日露戦争、資金調達の戦い―高橋是清と欧米バンカーたち―(新潮選書)
板谷敏彦
新潮選書
単なる美談としてではなく
もし高橋是清の外債公募ツアー回顧だけならば、ちょっと面白い歴史物に過ぎないでしょう。また、日露戦争当時の世界経済・ファイナンス概論だけならば勉強にはなっても無味乾燥でしょう。両者をうまく組み合わせることで、面白く読める上に、知的興奮のある読み物になっています。 舞台となる20世紀初頭は、産業革命が世界にひととおり浸透して経済・金融がグローバル化した時期です。ヴィクトリア朝は終わっていますがまだ英国が世界のリーダー的地位にあり、太平洋に達した新興勢力米国の勢いはすさまじく、極東の島国日本がようやく世界に向かって本格的に開かれ、ロシアでは革命の予兆が漂っています。 当時のロシアの人口は日本の3倍、GDP(購買力平価ベース)も同じく3倍。 あれ?一人当たりGDPは日露で同等だったんですね。ロシアはヨーロッパの後進国とは言え、この事実は個人的には意外でした。 こういったデータの積み重ねで、当時の日本が置かれていた状況、さらには、高橋らがどんな判断でどう行動したかが伝わるようになっています。また、ロンドン公債市場や東京株式取引所の相場が、戦況の報道を受けて上下する様も丁寧に追われており興味深いです。
3投稿日: 2013.09.27
新しい市場の作り方―明日のための「余談の多い」経営学
三宅秀道
東洋経済新報社
組織人(サラリーマン)には耳の痛い話
はじめのほうは「それなりのことは書いてあるが新味がないし、もったいぶった書き方でタルい本だな」と駆け足気味に読んでました。顧客思考が大事だとか、マーケティングができてないと技術があっても云々なんて話は、それこそ耳タコものです。 しかし読み進めるうち、大きな組織の病弊について話が至ったあたりから、サラリーマンの心のやわらかいところに急にグサリと突き刺ささってきたのです。相変わらず、そんなに新味のある話ではありません。けれど、いま自分が会社で抱えている閉塞感のあまりにもど真ん中に命中するのです。 印象に残ったところから1つだけ引用します。 <<大きい立派な組織に属していて、しかも、近年新しい価値を産み出せていないと嘆く人と話していると、製品開発についても諸分野にいろいろと詳しい方だなと思いますが、どれだけ話しても、まだこの「言葉が追いつかない」ような感覚が私に感じられにくいのです。「言葉にしにくいが新しい」存在に話題が至らないことが多いのです。この方は「まだ何と呼んでよいかわからないくらいの新しいネタ」を扱われた経験は乏しいのではないかと思わされることが、たびたびです。>> p.707 分かっているつもりのことですが身に沁みます。 本書で訴えられていることは、商品開発だとかをやっている人にばかり当てはまることではなくて、会社という組織の一員としてタコツボ化しがちな多くの人々に思い当たる節があるのではないでしょうか。スマートな本ではないですが一読の価値があります。
0投稿日: 2013.09.27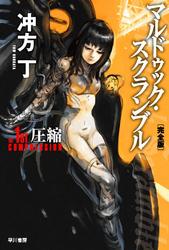
マルドゥック・スクランブル The 1st Compression─圧縮 〔完全版〕
冲方丁
早川書房
職人芸の一品
グイグイ引き込むように読ませるところがあります。隠れ家での畜産業者との対決や、ブラックジャックのシーン。電車で読んでいて降りる駅を乗り過ごしてしまったほどです。 Readerではじめて読んだ本だったのですが、こういう軽いけれど「巻を措く能わず」タイプの本は、電子書籍との相性が良いように思います。 ところでウフコックって、一体どんな仕組みなのか気になるな。SF好きなら気になるはず。
5投稿日: 2013.09.27
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
