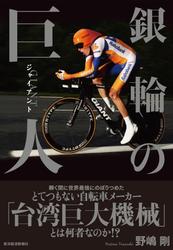
銀輪の巨人
野嶋剛
東洋経済新報社
自転車産業の日台比較
台湾の自転車メーカー「ジャイアント」。漢字で書くと「台湾巨大機械」と何だかものものしい。 1970年代にいかにも華人らしい家族工業的な小さい会社としてスタートし、米国メーカーのOEMを手がけて急成長した後、自社ブランドを確立して世界的な自転車メーカーとなった会社です。大陸勢のような低価格帯の自転車ではなく、技術にこだわって中・高価格帯の自転車を手がけているそうです。この本は、その「ジャイアント」を新聞記者が取材してまとめた本で、ジャイアントに代表される台湾自転車業界に対比して、斜陽というか、完全に日が沈みきってしまった日本の自転車業界についても描かれています。 著者は日本の自転車産業の復活を期待するような書きぶりですが、シマノは別として完成車メーカーはもう手遅れに見えます。部品メーカーの集積もすっかり中国、台湾になっているようですし。生き残る産業、他国に任せる産業、それぞれあって仕方がないと思います。個人的には、自転車道などが整備されて、台湾製でも良いからもっと自転車の乗りやすい環境さえ出来ればうれしいですね。
0投稿日: 2013.10.14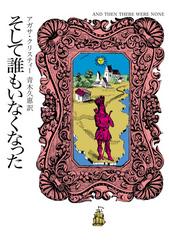
そして誰もいなくなった
アガサ・クリスティー,青木久惠
クリスティー文庫
なつかしく読みました
子供のころはジュニア版のミステリを図書館で片っ端から借りていたのですが、最近はこの手の小説もトンとご無沙汰でした。そういうのを、ふと手にとってみる気にさせるのも電子書籍の功徳でしょう。 さすが古典と呼ばれる作品だけあって、香り高いサスペンスを楽しめました。少々無理筋なところもあるストーリーですが、それも技術でサクッと読ませてくれます。
0投稿日: 2013.10.14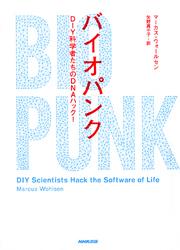
バイオパンク ―DIY科学者たちのDNAハック!
マーカス・ウォールセン,矢野真千子
NHK出版
やっぱりアメリカ人はDIYがお好き
ジャーナリストらしく、バランスがとれた視点からガレージで起こっているバイオ研究のムーヴメントを描いている。やはり大学、企業等の研究機関がメジャーである現実は変わらないようだが、著者の見立てでは「パンク」として既成の権威に反発するDIYの精神が大事とされる。このDIY精神はやっぱりアメリカ人ならではだろう。この精神の祖先として『森の生活 ウォールデン』のソローが挙げられている。これは森に入って文明の恩恵を受けずに独りで暮らす試みを書いた本で、アメリカでは有名な古典だそうだ。森の独り暮らしとバイオ研究との間には脈々とつながるDIY精神があるのだ。
1投稿日: 2013.10.14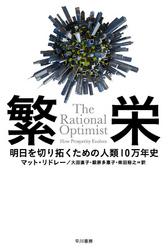
繁栄 明日を切り拓くための人類10万年史
マット・リドレー,大田直子,鍛原多惠子,柴田裕之
ハヤカワ文庫NF
通俗悲観論の解毒剤として
本書の主張をまとめるとこんな感じでしょうか。 「分業による専門化が人類の発展をドライブしてきた。現在の人類は、過去のどの時代とも比べ物にならないくらいの繁栄を手にしている。だから未来への過度の悲観論は慎もう。」 当たり前と言えば当たり前のことでありワタクシも大筋で同意するのですが、たとえて言えば社会科の教科書を読んでいる気分で、当たり前なだけにいまひとつ面白みに欠けます。ちょっと難癖気味の感想ですが、刺激的な終末論のほうが流行るのが分かる気がしました。 また、古今東西にわたってさまざまな例を引いて見事な博引傍証ぶりではありますが、事実を元に考証すると言うよりか主張をサポートするために事実を並べている印象を少し受けました。重箱の隅をつつくようで恐縮ですが、日本に関する記述で「あなた一体ナニを調べて書いたの?」と言いたくなる箇所もあって、全体的な信頼性に疑問符がついてしまいます。大部分まっとうなことが書いてあるに違いないとは思いますけれどね。
4投稿日: 2013.10.14
「社会的うつ病」の治し方―人間関係をどう見直すか―(新潮選書)
斎藤環
新潮選書
最近のうつ病に関する傾向と対策
著者はいろんな所にモノを書いているのでご存知の方も多いと思いますが、引きこもり専門の臨床医としてフルタイムで病院勤務もしているとのこと。うつ病は専門領域とは違うということですが、引きこもりの治療方針は最近のうつ病にも適用できることに気づき、「うつ病に関して2冊目に読む本」として書いたそうです。 解説編と対応編からなっており、臨床医らしい現場的な内容だけでなく、なぜこんなにうつ病が増えたのか(1999年→2008年で患者数が2倍以上)の社会的な考察もしています。必ずしもクリアな答えが提示されるわけではありませんが、なかなか説得力があります。
1投稿日: 2013.10.14
ストーリーとしての競争戦略 優れた戦略の条件
楠木建
東洋経済新報社
経営談義のネタ本
こなれた語り口の戦略論。部分部分はうなずける話がいっぱいでスイスイ読みましたが、全体を振り返ると、結局のところ本書自体がどんな「ストーリー」であったのだか一般化しきれずに戸惑います。経営論や戦略論ってものがあまり自分の性に合わないせいでしょうか? ただ個別のストーリーは結構面白かったので、読み物としてはイケていると思います。サウスウエスト、ガリバー、アマゾン、マブチあたりが印象に残りました。
1投稿日: 2013.10.14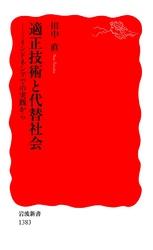
適正技術と代替社会 インドネシアでの実践から
田中直
岩波新書
「MAKERS」副読本?
クリス・アンダーソンの「MAKERS」と前後して読みました。だいぶノリは違いますが、「ブラックボックス化したモノ作りを我々の手に取り戻そう」というマインドは同じです。インドネシアで排水処理をしたり、バイオマス・ボイラーを作ろうとしたりといった体験をもとにして、途上国で自前で賄えて、さらに環境にやさしい技術について語っています。この著者は自らがエンジニアなのですが、専門外の知識については大学や企業に協力を請うていて、一種のオープン・イノベーションをやっている訳でもあります。 資本主義経済への反省みたいな方向に行ってしまっているので印象こそ異なる本ですが、アンチ権威的な気風は、WEB系(クリス・アンダーソン)と左派系(こちら)とで結構共通していることに気づきました。
3投稿日: 2013.10.13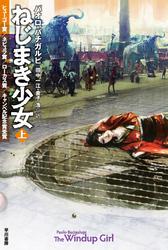
ねじまき少女(上)
パオロ・バチガルピ,田中一江,金子浩
ハヤカワ文庫SF
バンコクの蒸し暑さを感じるSF
初長編で大きな賞を獲ったということで「『ニューロマンサー』以来の衝撃」が売り文句になっていますが、さらに言うと雰囲気・手法もギブスンを意識しているみたいで、テクノロジーの世界観への組み込み方とか変な日本人とかセリフ使いとか多視点とか、もろに似ています。 普通は人造人間(ねじまき)の自意識が人間と同じホンモノなのかがテーマになりそうですが、そこはねじまき本人が語り手になっていることもあって「当然ホンモノですよ」という感じでスルー。遺伝子をいじっているとは言え立派な生物だからでしょうか。可愛そうにまだ社会的にはモノ扱いではありますが、電気羊なんかと比べると、世界観的には人造人間の人権確立が進んでいる気がします。 惜しむらくは、終盤にかけて筋の運びがぞんざいでアラッと思うところが少々あります。トントンとテンポがよろしいという評価もあるかもしれませんが。 また、バイオを道具仕立てにしていますが、世界観への組み込みはうまくても発想自体にはさほど新しさは感じません。そういうタイプのSF小説ではないと思います。
1投稿日: 2013.10.13
みなさん、さようなら
久保寺健彦
幻冬舎文庫
団地なつかしいな
元団地住人として楽しませていただきました。不条理小説(ふつうは主人公を取り巻く環境が不条理なのだが、この場合は主人公こそが不条理)と思わせつつ、ちゃんとベタなクライマックスを作るあたりは好きです。
0投稿日: 2013.10.13
〈意識〉とは何だろうか 脳の来歴、知覚の錯誤
下條信輔
講談社現代新書
少し古い本ですがこれをラインアップしてあるのはエラい
まず、人間が認知の過程で犯してしまう「錯誤」からその意識の仕組みを解明しようというアプローチがとても面白いです。 「脳」科学と呼ばれるように意識の座としての脳がスポットライトを浴びがちなわけですが、意識というものは脳に閉じているのではなく周りの環境と交じり合うものだという視点から、「来歴」という考えが提唱されています。
3投稿日: 2013.10.13
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
