
メルトダウン ドキュメント福島第一原発事故
大鹿靖明
講談社文庫
当時の官邸での雰囲気は伝わってくる
朝日新聞記者によるドキュメント。前半が事故当時の官邸を中心とした状況で、後半がそれに続く東電救済、原子力政策を巡る駆け引きを描いています。全般に抜きがたい朝日臭のようなものがたちこめて、いちいち仄めかされる価値判断に個人的には辟易してしまうのですが、直接の関係者に多く聞き取りをしていて当時の雰囲気(特に官邸の)が何がしか伝わってくるところは良かったです。 それら証言のなかで最も「おおっ」と思ったのは、少し本筋から離れますが、管首相(当時)のある人物評です。 「菅さんは何でも自分でやりたがる人に見られるのですが、実は以外に他人にゆだねる人です。それで、菅さんから見て良い判断を、その人が主体的にしてくれることと期待する。だからギリギリまで任せきりで。ところが自分のまったく想定外のものを、任された人が持ってくると、菅さんは『違うだろう』とひっくり返してしまう。それで相手を怒らせてしまう。怒って離れていく人は、だいたいこのパターンなんです。」 なるほどって感じで、こういう生の発言が面白い本です。
0投稿日: 2013.11.12
「いき」の構造 他二篇
九鬼周造
岩波文庫
「いき」をとことん分析
江戸の「いき」。関西では粋(すい)とも呼び、似ているが微妙に異なるそうです。その「いき」について、パリに留学したりした哲学者がなんだか可笑しくなるくらい分析的に説いています。最初の発表は昭和5年です。 手短に要約してしまえば、垢抜して張のある色っぽさが「いき」となります。反対語は野暮。ヨーロッパ仕込の哲学者である著者にとっては、日本独自の美的概念である「いき」を、哲学の手法でもって分析的に叙述するのが主眼であるそうです。「何故そんなことをしなきゃならないの?」と(野暮ながら)思ってしまわなくもないですが、1920年代にヨーロッパで研究に打ち込んだ日本人の気概があったのではないかと。 この本は、21世紀を生きる日本人(わたし)にとってもリーダブルです。普段の生活で「いき」なんてことを考えたり口にしたりする事は滅多にないですが、「ふんふん、それは確かにいきだね」なんて納得しながら読めます。民族的伝統の残滓がちゃんとわたしの中に息づいてるのか、はたまた概念的分析で提示された「いき」には意外と普遍的なところがあるのか。また、文章がとても明晰かつ美しいです。外国語を習得した人独特の明晰さであるように感じます。それも、この本の読みやすさの一因でしょう。 他に、もっと後期の著作である「風流に関する一考察」、「情緒の系図」を収録。そこでも哲学者の分析魔ぶりがいかんなく発揮されています。
1投稿日: 2013.11.08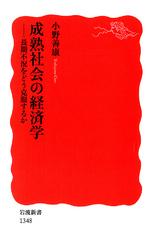
成熟社会の経済学 ――長期不況をどう克服するか
小野善康
岩波新書
別にイロモノではないと思う
管政権の経済政策ブレーンをつとめ、「増税で景気回復!」みたいな主張が切り出して取り上げられて話題になったりもしましたが、もう少し奥があるようなので読んでみたものです。 財政支出重視だからケインズ派なのかな?と思っていましたが、そういう訳ではないようです。ケインズ派の想定する不況は「短期」の現象ですが、こちらは「長期」の不況を想定しているとのこと。さらに乗数効果への批判のところで分かりましたが、財政支出も増減税もぜーんぶクラウディングアウトしてしまいますよ、という所はゴリゴリの新古典派。けっきょく財政によって創り出されるところの所得移転以外の効用そのものが問題であり、そこから経済成長・雇用確保ができると主張しています。発想の根っこは新古典派に近いですが、供給力は足りているとの認識で需要サイドを問題にしているところと、貨幣への偏愛を問題にしているところとがケインズ風味でしょうか。 お金を保有したくなってしまう欲求にはキリがないというのがとにかく大事なポイントのようで、しかもこの場合の「お金」は通常の意味での貨幣に限りません。本書ではあまりそこは直接に解説されていませんが、ところどころの記述から推測するに、株だって土地だって価値を表象していて取引がされるのであれば「お金」的要素があると考えてよいみたいです。そうなると、お金への欲望が土地や株に向かえばバブルが起こり、お金そのものに向かえばデフレと不況が起こる、と。両者はコインの裏表でしかなく、背後にあるのはモノ・サービスに対する供給力過剰と需要欠如という訳です。これは肌感覚的に説得力がありますし、スマートな理論ですね。 かと言って、、、じゃあ需要不足を解消するために、政府が高齢者へ現物支給するだとか言われると、「ホントにそこまでのことなのか?」と思ってしまいます。いや、議論の方向性は分かります。社会保障にしろ震災復興にしろ環境にしろ、ある程度やった方が良さそうで、政府がやることでよさそうで、今現在十分にできていないことはたくさんあるでしょう。でも、この本の議論はあんまりに極端で引いてしまうところもあります。そこまでしないと需要を見出すことができないのでしょうか? なお、金融緩和の効果に対しては否定的ですが、金融政策について記述されている分量自体が少ないし、議論もなんだかフワッとしてここでは力が入っていない感じです。アベノミクスへの評価もちょっと聞いてみたい気がします。
0投稿日: 2013.11.08
ぼく東綺譚
永井荷風
岩波文庫
震災前の東京
舞台は昭和11年、玉の井(今の東向島、墨田あたり)。60手前の主人公≒作者による、震災前の東京への懐古が色濃いです。荷風は素直な人じゃないなあ、と思いますが、その素直じゃなさが魅力でしょうか。また、簡潔な描写で以って匂いや体温まで伝わってくる気がします。
2投稿日: 2013.11.08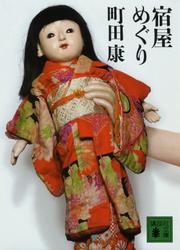
宿屋めぐり
町田康
講談社文庫
めくるめくマチダ節
同じ作者の『パンク侍、斬られて候』や『告白』がお好きだったら心配ありません。ある意味マンネリズムというか、良くも悪くも作風は同じです。ただ展開の目まぐるしさはこれまで以上に際立っており、ページをめくらせる力はめっぽう強いです。 しかし、この人はよくもまあ、こんなにハチャメチャな文章・ストーリーをどんどこ書けるものだと感心してしまいます。
1投稿日: 2013.11.07
日本辺境論(新潮新書)
内田樹
新潮新書
いつもの内田節ではありますが
中井久夫が『関与と観察』所収の書評で日本文化の辺境性について語っているのを読んで「ふーん」と思っていたら、そこにポンと出会ったのがこの本。 ふだんより著者のブログで学びの構造や、武道の「機」について読んでいたので新鮮味こそなかったものの、「面白いなー」とサクサク読めました。 足利義満が中国に対して「日本王」を名乗ったことを論評したくだりには思わず吹き出してしまいました。
1投稿日: 2013.11.06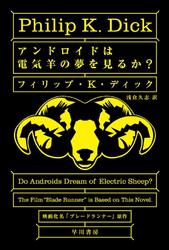
アンドロイドは電気羊の夢を見るか?
フィリップ・K・ディック,浅倉久志
早川書房
四半世紀ぶりの再読
断片的には覚えていましたが、これは中坊(高校生だったかも)には少し難しかったかも。 やや古びた感は否めませんが、それでも世界観はバッチリきまっていますし、ディックらしい虚と実のあわいを味わえます。
0投稿日: 2013.11.06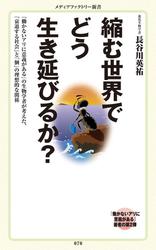
縮む世界でどう生き延びるか?
長谷川英祐,いずもり・よう
メディアファクトリー新書
何が縮んでいるかが問題では
前作『働かないアリに意義がある』は素晴らしいできでした。一方こちらは、二匹目のドジョウを狙ったもののつい生煮えの本を出してしまった印象です。 生物の増殖は環境により制限されますね、ってことは当たり前。でも、それを人間に敷衍しようとしながらも、われわれを取り巻く環境の何がどう「縮んで」いるのかを曖昧にしたまま(資源か環境問題にでもフォーカスするのかと思いきや、途中からリーマン・ショック経由「資本主義の限界」方面へ飛んでいってしまう)なので、いまいち議論が宙をさまよってしまった感があります。残念。
2投稿日: 2013.11.06
わたしたちが孤児だったころ
カズオ・イシグロ,入江真佐子
早川書房
不思議な小説
なんとも不思議な小説です。主人公と周りの世界とのズレを匂わせながら展開していって、いよいよ上海にて主人公はまるで異世界に入り込んだかのようになります。でも結局なんというかオチがないって感じなんですよね。じぶんの読解力不足かもしれんのですが。 以前に読んだ「日の名残り」も一人称独白振り返り式でしたが、そちらがエンディングできれいにオチるのとは一味違います。
1投稿日: 2013.11.06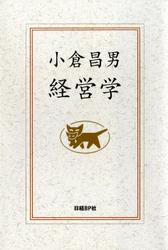
小倉昌男 経営学
小倉昌男
日経BP
孤高の経営者
まず、官に従うのが当たり前だった時代なのに規制緩和に挑んだ信念には敬服します。 宅急便のサクセスストーリーで印象的なのは、経営資源を一点集中させたリスクテイクの姿勢。その裏にあった計算と、さらに最後のトップによる決断とが、本人の筆で伝わってきます。他にも、「絶対的なサービスが需要を掘り起こす、利益は後でよい」といった、言えそうで言えない台詞がたくさんです。 「全員経営」という日本企業的スローガンも掲げているものの、どちらかといえば小倉氏は情より知の方というふうに見受けられます。本書でも宅急便にまつわる数字は細かくあげられている一方で、固有名詞の人名はほとんど出てきません。特定の人だけ取り上げることに対する配慮などあったのかもしれませんが、苦楽をともにした社員とかの名前が少しは出てきても良さそうな気はします。孤独な経営者という影も感じられますね。 (もっとも、たいがいのトップは孤独だという話もありますが)
0投稿日: 2013.11.06
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
