
ディアスポラ
グレッグ・イーガン,山岸真
ハヤカワ文庫SF
あまりの壮大なスケール
あまりの壮大なスケール。はっきり言って難しすぎてついていけない所があるが見事な大法螺イーガン節である。すばらしい。 これまで読んだ作品と比べるとユッタリとしたストーリーで、解説の大森望氏が指摘するようなビークル号的古典的冒険譚の香りもある。もう少し異世界の細部をギリギリ書いて冒険譚風味を出して、という気はするが、それじゃテーマとそれるし冗長か。
3投稿日: 2016.10.10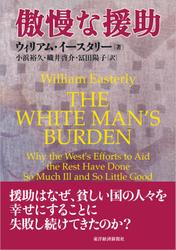
傲慢な援助
ウィリアム・イースタリー,小浜裕久,織井啓介,冨田陽子
東洋経済新報社
経済学者による途上国援助批判
「プランナー」による「全ての貧困を終わらせる!」みたいなユートピア的アプローチの援助を批判し、もっと現場主義の「サーチャー」による援助をすべきだという主張。著者の考え方は市場メカニズム(インセンティヴ、可視性&説明責任、自律性など)を重視したもので、第三世界の現状もあわせ考えると非常に説得力がある。 ただし学者の議論としては、あまりにも現場主義、ケースbyケースを強調すると「じゃあ、何も言っていないのと一緒じゃん」となる難しさはある。ある程度の一般化をする努力もいるのかなと思う。もちろん著者にしてみれば、援助機関の現状を踏まえると、とにかく無責任なユートピア的発想に一言物申したいのだろう。
2投稿日: 2016.10.10
贈与の歴史学 儀礼と経済のあいだ
桜井英治
中公新書
室町時代の今とはすこし違う「贈与」観念
15世紀前後の室町時代での貴族・武家社会での贈与のありかたを題材にしている。当時は贈与経済が市場経済と並んで幕府財政をも支える柱にさえなっていた。 室町幕府は京都に所在したため都市的性格が強い。土地や農業からの収入よりも、商業・流通・金融・貿易からの収入に重きを置いていた(江戸時代と違う!)。年貢を現物でなく銭で収める代銭納制が1270年ごろから急速に普及していった。これは南宋の滅亡により銅銭が大量に国外に流出したためと言われている(東アジア全域で中国銭使用がこの時期に拡大)。米などの作物を現地で換金するため商品経済、信用経済が発達した(なお江戸時代に改めて米納に回帰する)。 有徳思想、けち(欠けるってこと)、「例」、「相当」などの概念は現代人でも充分に理解できる。しかし室町人は、それらにメチャクチャこだわっていた。それが現代から見ると特異な贈与経済をうむ。将軍も皇族も、財政基盤が弱かったこともあって、自転車操業で贈り物のやり取りをしてる。贈り物はそのモノ自体に価値がある場合もあるが、ほとんどは非人格的なあつかい。贈物の贈物への転用も当たり前。さらに極めつけは銭の贈与。やはりモノより薄礼という意識はあったみたいだが。さらに現金がなくても「折紙」により贈物が手形化する。中世は権利の譲渡については現代よりよほどドライでもある。 はっきりとした主張ないし結論的なものがある本ではないのだが、今と似ていて少し違う時代の経済・儀礼感覚をリアルに描き出して面白い。市場経済とは贈与経済の単純化・非人格化を推し進めたひとつの形であると言えるかもしれない。 室町時代では皇室と幕府が近所づきあいをしていたのも、贈与儀礼が妙に発達した原因かもしれない。
1投稿日: 2016.10.10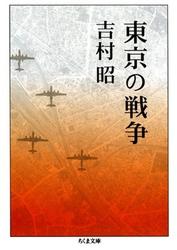
東京の戦争
吉村昭
ちくま文庫
クールな観察眼による戦争の記録
戦争や終戦直後の混乱を体験した14歳から19歳までの記憶が書き綴られている。空襲、物資不足、戦時下の人間模様、人の死。60年ほどの時間を経たうえで書かれているせいもあるだろうが、若かった著者の観察眼はとても冷静だ。単に冷静なだけでなく、一種の虚無感さえある。著者はそれなりに裕福な家の生まれのようだが、この期間に両親を病気で亡くし、兄弟からも戦死者が出ている。著者自身も結核で苦しんでいた。死が身近な故の諦念だろうか。戦争に負けてそれまでの秩序・価値観が崩れたアノミーによるところもあるかも。 この少し怖いようなクールさからは、色川武大の『怪しい来客簿』を思い出した。あの短編集も戦中や終戦直後に時代をとった作品が多かったはずだ。作風はぜんぜん違うが、1970年代生まれの人間からすると同じ時代の空気がするように思える。また、著者が山梨へ列車旅行するくだりからは『楡家の人びと』のラストシーンを思い出した。
2投稿日: 2016.10.10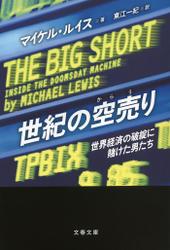
世紀の空売り 世界経済の破綻に賭けた男たち
マイケル・ルイス,東江一紀
文春文庫
金融市場に興味のある人は必読
住宅バブルからリーマン・ショックへ至る顛末は、興味のある向きには大筋だけなら周知のことと思うが、そのとき実際に現場で動いていた群像劇は圧巻。ドラマがある。世間では「バブルは予見できるか?」なんて、ややアカデミックな議論などあるが、そんな理屈が吹き飛ぶような迫力だ。これはウォール街を占拠したくなる気持ちも分かる。 本書の主人公たちはサブプライム債(を材料に合成されたCDO)をショートしていた面々。いずれもウォール街の主流からはだいぶ外れたアウトサイダー。こういう独立独歩の人が利益を求めて行動した結果、首尾よく価格発見に至ればまさに効率的市場仮説どおりだが、簡単にそうならぬのが現実の難しさ。本書でも再三指摘されているが、債券市場の不透明性(+その不透明性を最大限に利用した強欲)がひとつの原因だろう。 また主人公たちの「敵方」として、第9章で取り上げられるモルスタの特殊部隊の話がきわめて興味深い。サブプライム債がクズであることを十分承知していながら、トリプルBのCDOショート、トリプルAのCDOロングで見事に飛んでしまう。後知恵で何とでも言えるのだが笑うしかない。投資銀行、CDOマネジャー、機関投資家といった「敵方」の様子は本書でもハッキリとは分からないのだが、こうしたカオスが多々あったのだろう。 金融市場についての箴言あり、主人公たちの人間ドラマありで、マイケル・ルイスの皮肉な筆致も絶好調。ただ、ある程度は金融市場に興味・知識のある人でないと十分には楽しめないかもしれない。
4投稿日: 2016.10.10
贈与論
マルセル・モース,吉田禎吾,江川純一
ちくま学芸文庫
ポトラッチは人のためならず
マルセル・モース、有名な社会学者である。これはその代表作。たまには重たい内容の本を読むかと手にとってみたのだが、じつは文庫本で300ページ程度、しかも半分くらいが註だったりするので、本文はたいへんコンパクトだった。 まず、太平洋や北米の「伝統社会」における贈与の慣習を検証して、そこに見られる共通の要素を抽出していく。ポトラッチという名前はご存知の方も多いだろう。気前の良さを見せつけるために法外な贈り物をしあったり、あげるだけでは飽き足らずに貴重な財産をぶっ壊したりする風習である。そこで重要なのは、贈与には必ず返礼の義務が伴うということである。たとえ明示的に義務付けられていなくても、貰いっぱなしでは大変に具合が悪い。その観念はどの民族にも共通している。だからこそ、無謀に見えるポトラッチでも利益に無関心な訳ではなく、あくまでも贈与の相手に対し精神的な優位に立つことにポイントがある。富とは何よりも他者を支配する手段なのだとモースは看破する。 モースは返す刀で、ポトラッチに代表される伝統社会の慣習が、古代の法にその名残をとどめていることを、ローマ法、ゲルマン法などで例証していく。伝統社会での贈与の慣習が、売買になじんだ近代社会の経済観念と地続きであることを示すためだ。最終章で、モースはこれらの知見が近代社会に対して示唆することを述べる。例えば、社会保険や労働組合といった制度の裏づけを、伝統社会から綿々と伝わる道徳意識に求めていくといった具合に。 ごくごく簡単にまとめればこんな内容なのだが、一読しただけでは消化不良。コンパクトだし、部分々々の議論も明快だが、全体像としては簡単に飲み込めて終わりという本ではない。モース自身も、本書の議論を未完成であり、問題提起だとしている。
1投稿日: 2016.10.10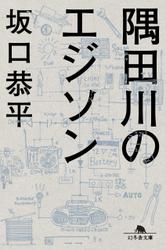
隅田川のエジソン
坂口恭平
幻冬舎文庫
狩猟採集民としてのホームレス
実在のホームレスをモデルに書かれた「小説」。主人公の硯木が著者に向かって語り聞かせているような文体でサクサク読める。 ホームレスと言っても一般的なイメージとはだいぶ違う。硯木は、己の腕で己の生活を切り開く、いわば都市の狩猟採集民とでもいうべき生き方をしている。廃材やブルーシートで快適な家を建て、電化製品まで動かす。食生活も案外と豊か。社会の経済情勢にあわせて、ある時まではテレカを拾い、それがダメになるとアルミ缶を拾いして、わずかながら現金収入も得る。行政や一般市民とも、交わるか交わらないかの微妙な距離感で付き合っていく。 こうした「都市型狩猟採集生活」については、著者がこの本より後に書いた『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』でより詳しく主張されている。しかし、『ゼロから・・・』よりむしろ小説形式のこちらの方がホームレスの辛い側面も率直に描かれる。結局は体力・気力・才覚、そして仲間がいないとやっていけないのである。誰にでも真似できるかと言えばそうではないだろう。もとより広くはないニッチに生きている人たちである。 しかし、誰もがこんな生活ができるか否かは別として(ボクはたぶん無理)、本書の不思議な魅力は、生きる実感とでも言うべきものがホームレス生活の様子から伝わってくるところにある。単に束縛がないだけではない、決まりきった日常に薄ボンヤリと乗っかって生きるのではない、能動的な生き方なのだ。主人公たちの創意工夫には、子供の頃に読んで興奮したヴェルヌの『神秘の島』を髣髴とさせるものがある。
3投稿日: 2016.10.09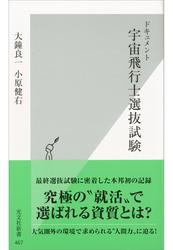
ドキュメント 宇宙飛行士選抜試験
大鐘良一,小原健右
光文社新書
「人間力」だなんてそんな
しばらく前のことになるが、勤務する会社の採用面接で面接官を仰せつかっていた時期がある。こんなことを言ってはいけないかもしれないが、やや気の重い仕事である。人を見る目には自信がない。けれど「気が進まないのでやりません」とも言えないので、むりやり気持ちを奮い立たせて学生諸君と相対してきた。実際お会いして真剣に話をすれば、有望そうな学生さんに出会えたり、ノンビリした人には昔の自分を見たりと、いろいろ思うことはある。すごく疲れるけれど。 そんな面接の後に、積読にしていた山から手に取ったのが本書。もともとマンガ『宇宙兄弟』を読んでみて興味を引かれて買った本だ。宇宙飛行士の試験も就職活動とちょっと共通するところがあるかしら、と思ってパラパラとページをめくってみれば、のっけから「宇宙飛行士選抜試験とは”人間力”を徹底的に調べあげる試験」であり、「”就活”の大学生にもヒントがあるはず」ときて、こうも真正面から言われると、半ば予想していたにもかかわらず、なんだか夢や希望も半減した気分になってしまう。 こういう風に、いとも簡単に”人間力”とかに引きつけてしまう語り口はいかにもNHK的であり興醒めするのだが、やはり試験の様子自体にはとても興味がある。たしかに、きびしいメディカルチェックがあったりするのを除けば、採用面接の超手の込んだハイレベル版と言えなくはない。閉鎖環境施設での1週間泊り込みの試験なんてカネと時間さえあれば(ないけれど)自社の採用でやってみたい会社もあるのでは。 『宇宙兄弟』でも一番おもしろかったのはJAXAの閉鎖環境施設の場面だった。実際の試験をしている様子もあそこに描かれていたのとかなり近い感じで、あれはしっかりした取材に基づいていたのだなと改めて感心。
1投稿日: 2016.10.09
第六ポンプ
パオロ・バチガルピ,中原尚哉,金子浩
ハヤカワ文庫SF
職人芸的SF
バチガルピは短編の方がうまいのではないか。職人的な手つきでディストピアな世界をさっと呈示してみせる。くどくなく、分かりやすく、強くイメージを呼び起こす。 暗い世界観だが、希望の要素が必ず入っているのもよろしい。たとえSF的な発想に目新しさはなくても、技術で読ませる手堅い作家だと思う。 収録作は甲乙付けがたいものが並んでいる。敢えていくつか好みを言えば、デビュー作にして作風が確立されている「ポケットのなかの法」、異世界の民俗・風習を簡潔に描きだしてみせた上にドラマを重ねた「パショ」、ねじまき少女と同じ世界を描いた「カロリーマン」、なんともエグいのだがあるかないかのほのかな希望を描く「ポップ隊」あたり。
4投稿日: 2016.10.09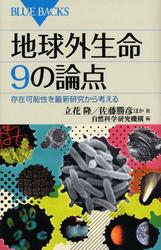
地球外生命 9の論点 存在可能性を最新研究から考える
立花隆,佐藤勝彦,長沼毅,皆川純,菅裕明,山岸明彦,重信秀治,小林憲正,大石雅寿,佐々木晶,田村元秀,自然科学研究機構
ブルーバックス
2012年の本ですが
生物学者や天文学者が集まったシンポジウムを土台にしたアンソロジー。「9の論点」とあるが、論点がはっきり9つあるんじゃなくて9人集まったから「9の論点」にしたみたい。 火星運河論争に決着がついて以来、地球外生命はSFの定番ネタでこそあれ科学の対象にはなりにくい時期が続いた。ドレイクらによるSETIの活動などはあったわけだけれど、夢物語か酔狂の類と一般には看做されていた。ところが最近では地球外生命の存在はにわかにリアリティを持って語られだした。背景には、以下のような事実が明らかになってきていることがある。 ・彗星や隕石には生物の素材になりうるような有機物が多く含まれている ・系外惑星が次々と見つかっている。特に地球型のあまり大きくない惑星も技術進歩で見つけられるようになった ・地下深くや熱水噴出孔近くなど、極端な環境で生きる生物の様子がだんだん分かってきた ・太陽系内で、液体の水や火山活動など生命が存在しうる環境が見つかってきた この本では、生物学や天文学などさまざまな分野の研究者が地球外生命関連のトピックスを論じている。こんな本に参加するくらいだから、もちろん地球外生命の可能性について肯定的な人ばかりだが、一般的にはどちらかといえば物理学者に地球外生命肯定派が多くて、生物学者に否定派が多いらしい。しかし系外惑星が次々と発見されたり、太陽系内でも生命が存在しうる環境が見つかったりする中で、徐々に肯定的な見方が増えてきて、学問として成立するようになった。でも、まだ知的生命の存在までは簡単には考えられないが、微生物くらいなら本当に太陽系内にもいそうな気がしてくる。 この手の話題に興味を持ってニュースを追いかけたりしている人だと目新しい話題は多く含まれてないはず(2012年出版なのでむしろ少し古い)。逆に、ここ15年くらいの地球外生命や宇宙関連の話題に明るくない人ならば、読めばちょっとした驚きを覚えるんじゃないか。学校で習ったようなこととは随分違ってきているはずだ。この宇宙のなかで生命と言うものが、地球だけの特別な孤立した存在なのか、それとも本当は平凡などこにでもある存在なのか。自分の生きている内には何らかの見通しが立ちそうで楽しみ。
1投稿日: 2016.10.09
bookkeeperさんのレビュー
いいね!された数185
