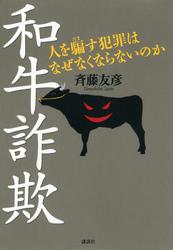
和牛詐欺 人を騙す犯罪はなぜなくならないのか
斉藤友彦
講談社
新聞記者による取材雑記のようなレベル
「安愚楽を詐欺だと判断したと同じように」のような文章の稚拙さにはじまり、林原のことを「トレハロースで有名な東原」とそのまま誤記したり、事件の構図を解説する大学教授が誰かも明かさないなど目に余る。そもそも、巻末には参考文献もないので、ノンフィクションを読んだというよりは個人的な印象論を読まされた気分。 関係資料を徹底的に読み込んでというのではなく、「この時点から詐欺だと認識していたな」と早合点した体当たり取材で、記者の直感も大事だが、スタンドプレー報道の危うさを感じた。 安愚楽の30年が畜産業界に与えた影響をもっとよみたかった。 特に、預託農家が「安愚楽に救われた」と言わしめるほどの関係の背景にどのようなことがあるのか、あるいは「安愚楽バブル」と言われる業界に与えたインパクト、相場の乱高下、それと2010年の口蹄疫騒動に裏でどのように関わってきたのかなど。 優れた書き手の登場を待ちたい。
0投稿日: 2013.12.12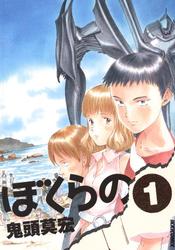
ぼくらの(1)
鬼頭莫宏
月刊IKKI
限られた時間でどう身の回りの人たちと折り合いをつけて旅立つか
「地球を守る」であるとか、ロボット、パラレルワールドなどいろいろな要素を思いきって取り払ってみると、理不尽な形で死期を決められた子供たちが、残された数日でどのように身の回りの人たちと折り合いをつけていくかを連作で綴った作品だとわかる。 だから、ロボット同士の戦闘シーンは時に淡泊で、あっけなく勝敗は決する(むしろ残り人数を考えたら、どうせ勝つんだろうと高を括ってしまう)。 その一方で、それぞれのパイロットの死なせ方には工夫をこらしている(コモは演奏後に父親の腕に抱かれて死ぬ設定でいこう、など)。 それぞれをあまりに巧みに描き分け過ぎたせいで白々しいし、後半になればなるほど多弁で自分の感情を言葉に出させ過ぎていて萎える。 唯一面白いと思ったのは、登場人物の死ぬ順番で、男女比もそうだが、キャラクター的に主役クラスから殺していってるのが新鮮といえば新鮮。
2投稿日: 2013.12.12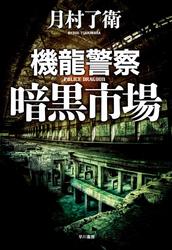
機龍警察 暗黒市場
月村了衛
ハヤカワ・ミステリワールド
渇きをいやすことはできても、決して酔えない安酒のような作品
前作含め未読だが、この巻だけでも愉しめる。 が、渇きをいやすことはできても、決して酔えない安酒のような作品。文体は短文を多用して読みやすく、脚本を読まされているよう。言葉の微妙な綾もなく、読者が登場人物の心情を忖度できるような余白もない。 最後の「班長はやっぱり班長だったんですね」とユーリが叫んだところで、思わず本を落としそうになった。本を閉じ、カバー裏に「世界水準を宣言」と書いてあるのを見つけ鼻白む。これだったら、『チャイルド44』のロシア3部作の方が数段愉しめるだろう。 読む前は期待していたのに残念だ。
0投稿日: 2013.12.12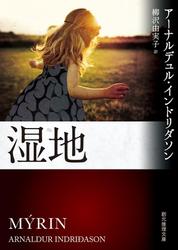
湿地
アーナルデュル・インドリダソン,柳沢由実子
東京創元社
ほんとは国民の幸福度の高い国が舞台
読んでて一番ゾッとしたのは、事件の真相もさることながら、捜査の過程で数十年ぶりに墓から引き上げられた少女の解剖結果だった。検死官からその事実を告げられた主人公が「いまなんと?」と聞き返すほどの衝撃度。そこで謎がより重層的になった。 その一方で、犯人が死体になぜメッセージを置いていったのか、釈然としない理由だったのは残念。また、花嫁の失踪劇の顛末を見ると、わざわざ同時並行で語るテーマだったのかも疑問が残る。こちらはああいう真相ではなく、もっと別の家族の再生を示す話であれば良かったのだが。 この本よりも前に、エリック・ワイナーの『世界しあわせ紀行』を読んでなかったら、なんてアイスランドっいう国は、性的倒錯者が多いことかと偏見を持ってしまったに違いない。実際は国民の幸福度の高い国なのに。 そういえば同書にも、出会ったばかりの男と一夜を共にした女性が、翌日に親戚のパーティーで出くわし、「わたしまた、いとこと寝ちゃった」と悲嘆に暮れるエピソードが紹介されていて、アイスランドの近親性の高さを伺わせていた。
1投稿日: 2013.12.12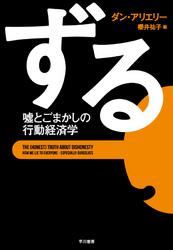
ずる 嘘とごまかしの行動経済学
ダン・アリエリー,櫻井祐子
単行本
自らの嘘やごまかしを見つめ直すきっかけ
この本を読んでると、知らず知らずに行なってるちょっとした嘘やごまかしを見つめ直すよいきっかけになった。 ただ、前作で紹介されたようなアイデアあふれる実験が、講演で多忙なためか、今回は少ない気がする。不正の判定に使われる実験がいつも同じもの(数字探し実験)なので、新鮮味に乏しい。しかもこの実験では、シュレッダーでテスト用紙を実験者が自分で破棄するのだが、事前に答えた別のテストの正当数と比較して、「4問ほど水増しして申告した」、いわゆるズルをしたと認定されるのだが、何か釈然としない違和感を感じて仕方なかった。 不正を防止する、より効果的で実際的な方法をもっと紹介して欲しかったが、最後のメイドの盗み癖に対抗して冷蔵庫に鍵をかけるという例のように、不正をへらすための秘策が、結局は単に複雑で不便な一手間を加えることに過ぎないとなれば、少し拍子抜けしてしまうな。 歯医者と患者の例も面白かった。普通、つきあいが長くなればなるほど、医者は患者の身になって次の治療方針を立ててくれそうに思えるが、実際はその逆で、患者がどんどん信頼を寄せるのをいいことに、医者は自分の利益となる治療を押し付けてくるというのは、何か思い当たることが多すぎて考えさせられた。 それと、不正の典型例である浮気を取り上げたコラムでは、読んでいて「浮気は文化だ」という迷言を吐いた某氏の顔が浮かんでしょうがなかった。
0投稿日: 2013.12.12
モサド・ファイル イスラエル最強スパイ列伝
マイケル バー=ゾウハー,ニシム ミシャル,上野 元美
単行本
2013年度のインテリジェンス関係の必読本
読み終えるのが惜しかったし、今後も折りに触れて再読するだろうなと思わせる本。 一人始末するのに、30人近くが現地入りしたりする。国籍も多彩で、旅行者の格好で現れ、捕まりそうになると各大使館に駆け込む。現地では、弁舌巧みに説得したり、賄賂を贈るかと思えば、誘惑し、静かに引き金を引く。 決して忘れないのは、受けた仕打ちだけでなく、不運にも捕まってしまった仲間に対しても。決して捨て駒にはしない。 工作員もそれぞれ頭の回転が速く、機転が利き、とにかく献身的なのだ。 ただ注意深く読めば、その歴史においてモサドの活動が変質していることがわかるし、いまインテリジェンスの世界で占める地位も不変ではないことがわかる。 勝ち逃げを決して許さず、一度でもお尋ね者のリストに加えられれば、モサドの手から逃れることはできないとテロリストに思わせることで、敵を動揺させ、危機を未然に防ぐ狙いもあってか、最強神話を自ら作り上げている。
5投稿日: 2013.12.12
六人目の少女
ドナート・カッリージ,清水由貴子
ハヤカワ・ミステリ
ひたすら残忍で、沈黙させるほど不条理な物語
はじめから著者は、リアリティなぞ目指してなどいない。 特定の地名はいっさい出てこないし、捜査陣は犯罪学者をリーダーに瞑想室でミーティング。 他者に共感できない主人公は、悲しみを分かち合うため自傷を繰り返し、瀕死の犯罪者からは霊能力者の手助けを借りて自供を得る。 その犯行が可能かどうか、犯罪の動機が理解可能かどうかではなく、悪の根源、もしくは我々の身近に存在している黒い穴が作品のテーマだろう。 平凡な人間であっても断ち切りがたい闇への誘惑。 ひたすら残忍で、沈黙させるほど不条理な物語だが、読み終えても考えさせられる。
1投稿日: 2013.12.12
皮膚感覚と人間のこころ(新潮選書)
傳田光洋
新潮選書
「ここにも目や耳がつまっている」
かつて百科全書派の集うサロンでデュ・デファン夫人は、啓蒙思想家のフォントゥネルの心臓の上に指を置いて「ここにも脳味噌がつまっている」と言ったらしいが、本書を読めば皮膚には脳だけでなく目や耳までつまっていることがわかる。 おまけに、自他を区別する自意識も脳ではなく皮膚感覚が作っているという指摘は私たちを強く揺さぶるものだ。 ただ、著者自身が事あるごとに「たましいなぞ認めない」「念力や安っぽい神なんか信じない」という表明を読むにつけ、科学者としての逞しさに共鳴すると共に、デファン夫人のつぶやきもよみがえってくる。
1投稿日: 2013.12.12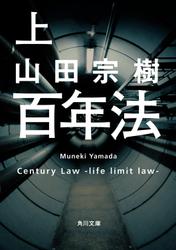
百年法 上
山田宗樹
角川文庫
大著だが、一気読み必至のエンタメ本
寿命を制限する法律をめぐって社会や人びとがどうなっていくかが描かれる。 奇抜な設定も最初のアイデア倒れに終わらず、その後の展開もしっかりと練り込まれていて、あぁなるほどと納得させられることもしばしば。 小説の中で流れる時間も長丁場だが、折々の時代の細かな変化を説明調にならず、流れの中で自然と語っているのうまいと思った。 ただ、映像系に近しい文体で、「目を瞑る。サイレン。真下で鳴り止んだ。目をあける。背筋を伸ばす。夜空を見上げる」など読むと、およそ文学書を読んだ気にはなれない。
3投稿日: 2013.12.11
ファスト&スロー (上)
ダニエル・カーネマン,村井章子
ハヤカワ・ノンフィクション
自信を揺らがせ、深い自省の念を抱かせる好著
脳は、因果関係が大好きだが統計的な推論にはとんと弱く、偶然の罠にもたやすく陥る。後講釈も大好きで、一貫したストーリーを作りたがるが、予想外の出来事が起こるとたちどころに記憶を消去し修正する。 平均への回帰なんて説明では満足できず、そのため直感は、不可避的にバイアスがかかる。だけどその修正は、ホームランを打つチャンスを減じてしまう。 「主観的な自信は感覚であって判断ではない」が印象的。 これからはある予測や行為に自信を感じたら、それは正しいことだからではなく、脳がつじつまが合ってると喜んでいるに過ぎないと思おう。 著者は、直感を信じるなと言ってるのではない。過信するなと言ってる。過去や歴史を十分に理解し教訓が得れるなんていうのは幻想だし、将来や未来を知り得るとというのも思い込みにすぎない。倫理的にも社会規範的にも支持される行為であっても、われわれが本来備えている見方と合致しなければ、その望ましい結果にまで目を瞑ることになる。 社会も、標準業務から逸脱したがらない役所の連中や慣例通りの治療に満足する医師のように、リスク回避に走る生き方が一般的になりつつある一方で、一発逆転の無謀な賭けに出るギャンブラーが時に無批判で賞賛されている。 ニスベットとボージダの「人助け実験」の結果は考えさせられる。統計的な数字に納得しても、いざ感じの良い被験者を見ると、そんなことはすっかり忘れてしまうのは、総論賛成各論反対のいまの政界や、財政再建のために増税が必要だと分かっていもいざ報道で低所得層にどれだけ負担が増すかを知ると先延ばしする心性に通じている。 本書の端々で「自分がこの分野の第一人者である」ことを読者に分からせる書き方。 最後に著者近影を見て、鼻の穴の大きなドナルドダッグみたいな顔だと思った。 読み通すのに時間がかかるのは仕方がない。頭では分かったつもりなのにそう見えてしまう有名な錯視の2本の線を終始見続けてるよう。自信は打ち砕かれ、何をよりどころとすれば良いのか(統計か?)途方に暮れるのだから。 本書を読んで、深い自省の念を抱くか、自覚的に利用してやろうというよこしまな気持ちが芽生えるかは読者次第。
3投稿日: 2013.12.11
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
