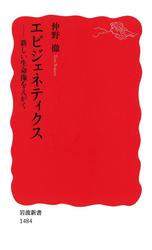
エピジェネティクス-新しい生命像をえがく
仲野徹
岩波新書
短命なのは、おじいちゃんの飽食のせい?
専門でもないので正しく理解してやろうなどとは思わず、面白いところをつまみ食いする感じで、誤読を恐れず読んでいくと結構たのしめた。 記憶や恋愛、がん、生活習慣病、寿命、ストレスなどの能力や症状、社会活動に対して、不変で決定的なゲノムDNAに上書きされる形で、エピジェネティクスという付箋や伏せ字が影響を与えているなんて知らなかった。 特に爺さんの栄養過多が孫息子の余命にまで影響を及ぼすなんて、何という因果関係か。 それにしても「DNAのメチル化」とか「ヒストンのアセチル化」とか意味がわからないのだが何かカッコいい。
2投稿日: 2014.09.02
人間の建設
岡潔,小林秀雄
新潮社
数学のような知の最先端の現場で出てきた感情の問題とは?
小林は岡の『春宵十話』という随筆集に感銘を受け、対談に臨んでいるので、合わせて読みたい。 事実、岡の話には考えさせられる点が多かった。 神風に見られる日本人の自我の話は『永遠の0』に感動している我々に浴びせられた冷や水のようだし、数学者の考える「1」という観念、何であるかわからないしあるのかないのかもわからないが、この中に全体がある、なんて深遠な禅問答みたい。 他にも、赤ちゃんの話では、自他の別もないのに、親子の情が先に育つということや、人間というものは感情が納得しなければ、本当に納得することの難しい存在など、われわれのどこに根本があるのかがよくわかる話。 「矛盾がないことを説得するためには、知性が説得しても無力なんです。心が納得するためには、情が承知しなければなりません」
7投稿日: 2014.08.14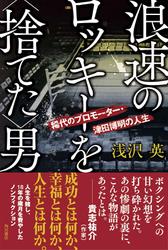
浪速のロッキーを<捨てた>男 稀代のプロモーター・津田博明の人生
浅沢英
角川書店単行本
風呂屋のポスターを見てこの世界に入り、赤井と出会い別れるまでの物語
何とも異色のプロモーターである。 経歴は元プロボクサーではなく、タクシー運転手の業務の傍らジムにかけつけ、時には理髪師の腕を活かして練習生の頭をカットする。 指導は手取り足取り懇切丁寧で、自宅や公園でもつきっきりで教え、練習後には生徒の体を拭いてやるほど献身的だ。 弱小のジムの会長らしく、時には新幹線の車内放送を利用して、ジムの宣伝にも余念がない。 従来のミットを構えつつ同時に算盤もはじく、狡知に長けた傲岸不遜のプロモーターのイメージとは異なり、津田にはどこまでも不器用で純粋な印象がある。 ただ正直言えば、津田が赤井という傑出したボクサーの世界への挑戦に寄り添いながら、なぜ去っていった竹ノ内に未練を残し、赤井より魅力も戦績も劣る杉本に執着したのか最後までわからなかった。 赤井にしてみると、教えてくれと何度も頭を下げ、ジムの立ち上げの際には自ら練習生をリクルートし、最大の後援者の心までとらえたのに、津田に自分の成功の可能性を最後まで信じてもらうことは出来なかった。 「津田が自分に交互に向けてくる甘い蜜と冷たい棘の記憶は、消化されない心の澱となって残り続けるしかなかった」という赤井の複雑な感情は読者の胸を打って止まない。 カバー絵がタクシーの制帽をかぶったまま練習生のパンチを受ける津田の写真であればもっと良かったのに残念。 というより本書の中で写真が一切使われていないのは、関係者の同意を得れなかったためか、何とも解せない。
0投稿日: 2014.08.04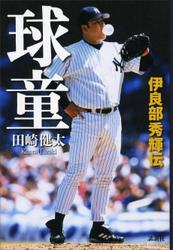
球童 伊良部秀輝伝
田崎健太
講談社
野球を続けることで社会と会話していた男の評伝
「球童」というより「悪童」、もしくは躯は大人だが、精神は子どもという意味の「マンチャイルド」で、自分には甘く、他人に厳しい。 自分を認めてくれる人間としか付き合わないという性質は高校時代の甘やかしに端を発し、プロ入り時には注意事項として怒り方までアドバイスされ球団を唖然とさせる。 たまたまヤンキース時代に錚々たる面々と共にしたため投球術の知識は吸収したが、練習も自主的にはせず、マウントでは容易く冷静さを失い、飲酒で体を傷つける。 伝記も芯のないまま上滑りしたまま終わり、妻の証言や投資の実態などは書かれていない。
1投稿日: 2014.07.26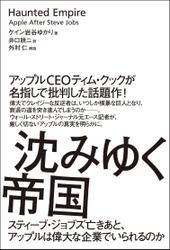
沈みゆく帝国 スティーブ・ジョブズ亡きあと、アップルは偉大な企業でいられるのか
ケイン岩谷ゆかり,井口耕二,外村仁
日経BP
『スティーブ・ジョブズ』の次に読むべき本はこの一冊
これまで何冊かアップルを取り上げたノンフィクションを読んでいるが、アイザックソンの『スティーブ・ジョブズ』の次に読むべき本はこの一冊かもしれない。 CEOの健康状態をどこまで発表すべきかのせめぎ合いや、徐々にゴジラ化していくアップルに焦点を当てた前半は、闘病中のジョブズの様子も描かれるが重複は少なく、彼が結婚20周年の記念日に送るものを古い友人であるデザイナーと相談しながら決めていく様は実に感動的。 後半では、アップルもソニーのように偉大な企業から単なるよい企業となってしまうのかという疑問を掘り下げていく。 特別だったジョブズがいなくなってアップルも変わったが、何より社外からの見る目が大きく変わった。 フォックスコンにおける労働条件やサプライヤーに対するアップルの厳しい姿勢、米国に対する何十億ドルもの納税を逃れるための複雑な仕組みなどが次々と明らかになり、「世界をよりよい場所にするのが会社のミッションだ」と言って自分たちを倫理的に一段高いところにいると取り繕うことが難しくなっている。 アップルは、「ほかの業界の破壊者であるとともにみずからの破壊者である」とも言われているが、この姿勢を貫くのは生半可なことではない。 データや分析に頼るのではなく、大胆な発想から製品開発を進めることができるのは、リスクを取り自分の行動が正しいと証明できる創業者だけで、盛田やジョブズの後の、雇われ経営者にはそもそも荷が重い話のような気がする。 そもそもクックはリスクをとって業界自体を変えてしまうような新製品を出す本当に革新的な会社を目指していないのかもしれない。 彼はこれからも確実に利益の出る、すばらしい普通の会社を目指し、彼を選んだジョブズも、後任には自分と同じワイルドカードではなく、きちんとふるいにかけられた人物を選んでいる。 ジョブズとクックのスタイルの違いも面白い。 ・ジョブズは休暇中の幹部を呼び戻すことが多かったが、クックは部下の私生活を尊重するため、以前より休みを多く取るようになった。 ・ジョブズは興味を持つとなんにでも首を突っ込んできたが、クックは信じて任せるタイプであるため、結果が出るまではジョブズのようにNoと言わない。 ・ジョブズは摩擦上等だったが、クックは協力関係とチームワークを大切にする。 ・ジョブズは利益をあまり気にしていなかったが、クックのような経営者は利益を重視し過ぎることが多い。 ・クックはわずかな金額を値切って利益を出すタイプで、ジョブズはそのお金を使って人々を幸せにするタイプだ。 アップルは、これまで、市場に新たな可能性を拓くこと、新たな消費者の欲求を生み出すことを一番の目標とし、利益は二の次にするのが特徴だったのに。 クックの人事における眼力やコントロールも当てにならない。 企業文化がそもそも大きく異なる家電量販店出身のブロウェットにアップルストアをまかせるべきではなかったし、何よりフォーストールをクビにしたのは一番の間違いだった。 著者は、フォーストールがいなくなり、アイブが製品のデザインとユーザーインターフェイスの両方を統括するようになったが、うまくバランスをとれず、見た目はいいがまともに使えない製品が生まれるおそれがあると指摘する。 「アップルの現幹部が認めようが認めまいが、彼らはいまも天才という罠に捕らわれたままだ。この罠が彼らを縛り、悩ませ、あらゆる決定にまとわりついている。ビジョナリーリーダーが世界的な偶像となり、さらに死によってその影響力が昇華されたいま、残された人々は、創意工夫と意思の力をかき集め、炎をふたたび燃え上がらせることができるのだろうか。それとも、あちこちで言われているように、アップルは単なる企業になりつつあるのだろうか。その場合でも、世界的にも有数の成功を収める企業にはまちがいなくなるはずだが、その卓越した力が世界を変えることに発揮されるのではなく、利益をあげることに発揮される企業、そういう企業になりつつあるのかもしれない」
4投稿日: 2014.07.22
機械との競争
エリック・ブリニョルフソン,アンドリュー・マカフィー,村井章子
日経BP
この競争はお釈迦様の手のひらを飛び回る孫悟空の運命に似ている
現代版ラッダイト運動の思想的根拠を示す本かと思っていたので、いまから予測不能なほど指数関数的に進むテクノロジーの進歩に対し、片方では憂慮を表明しながらも、そのデジタルフロンティアが約束する未来に希望を寄せるという著者の矛盾する立場に少しガッカリさせられた。 デジタル技術の進展が「驚天動地の結果をもたらす」ほど甚大かつハイペースなものであるなら、著者が提言する教育や法規制の改革などやる前から手遅れで実効性がどこまであるのか疑問だろう。 それでもテクノロジーが雇用に与えるインパクトの大きさは再認識できたので読んで良かった。
0投稿日: 2014.07.13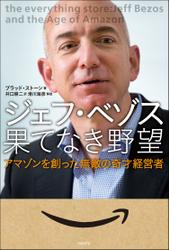
ジェフ・ベゾス 果てなき野望 アマゾンを創った無敵の奇才経営者
ブラッド・ストーン,井口耕二,滑川海彦
日経BP
やまない反発と魅力の理由がわかる良書
ジョブズ本と同じ訳者なのでついつい両者を比較してしまう。 どちらもまぬけの増殖を警戒し、ワークライフバランスなんてどこ吹く風で社員を馬車馬のごとく働かせる。 部下には高い要求をぶつけ、気に入らないと辺りかまわずどなり散らすが、ジョブズとは違い後を引かず、しばらくするとばか笑いをして体をよじらせる。 どちらも先見の明にすぐれ未来を見通す力を持つが、優れた人材を確保することにかけてはベゾスの方がより積極的。 ジョブズが極限までそぎ落としたシンプルさを志向するのに対し、ベゾスは過剰とも思えるほどの無限の品揃えを志向する。 二人とも傲岸不遜で、ジョブズはAppleの理念と合わなければ使わなくて結構という考えだが、ベゾスはすべてのユーザーはAmazonを利用するべきだと考えている。 アップルとの一番の違いは、革命的な製品を発売して儲けるのではなく、「買い物についてお客が判断する時、その判断を助けることで儲け」ていること。 読者によるレビューやリコメンド機能、アフェリエイトなどのプログラムが早い段階で実装された結果、ライバルに優位な立場を築くことに成功している。 会社の命運を左右するピークは、アップルが新製品の発表だとするとアマゾンはホリデーシーズンで、毎回が混乱とともに切り抜けその度に一回り大きくなる。 転機となったのは、ドットコム・バルブの崩壊で、アマゾンも一転して窮地に追い込まれるが、それまでの「早くでかくなる」という成長一辺倒から、利益や効率を求め無駄を排除する経営方針の変更に成功する。 アマゾンが、本業のオンラインショップ事業とはかけ離れた、CIAにクラウドシステムを提供するようなウェブサービスをどのように始めたのかがわかって興味深い。 オライリーからアマゾンを利用するサードパーティや開発者に向けて販売データを提供できるようにすべきだと助言を受けたのもそうだが、もともとは自社の硬直化したサーバーシステムの改革の一環として、外から使いやすいように自由にアクセスできるようにするべきだという発想が出発点となっている。 彼のパーソナリティ形成過程も面白い。 顧客重視の名のもとに一切の治外法権を要求するコチコチのリバタニアン。 秘密主義者で永遠の宇宙少年。 エネルギッシュで外向的だが、冷酷で共感能力に欠ける典型的なサイコパス。 先の先まで読むチェスプレイヤー。 「無限拡大」がモットーであるベゾスは、普段は楽しく話せるのだが、ひとたびナッターにスイッチが入ると「オレの人生を無駄遣いするとはどういう了見だ?」と叱るので、いつもビクビクと隠れて過ごす社員もいるらしい。 摩擦が多くぶつかり合う文化に慣れることができず、退職する社員も多い。 アマゾンの成功の秘密やベゾスの経営手腕の一端を知ろうと本書をとった読者には、後半からますますこの会社は偉大なのか単なるブラックなのか判然としなくなってくる。 何もベゾスが変質したわけではなく、当初からの経営理念から驚くほど変わっていない。 会社が大きくなれば身の丈に合った振る舞いを期待されるがそうしないし、初期には交渉相手の業界出身の社員がいたので他社とも敬意をもった連携ができていたが、次第にジェフボットと呼ばれるクローン的な社員が増殖したために、社内外でありとあらゆる混乱を引き起こす。
6投稿日: 2014.05.05
カルニヴィア1 禁忌
ジョナサン・ホルト,奥村章子
ハヤカワ・ミステリ
処女作にして、成功が運命づけられた三部作の第一作。
『チャイルド44』でデビューしたトム・ロブ・スミスもオックス・ブリッジの英文科卒だが、こちらも処女作とは思えない出来。 魅力的な人物造形、複雑で秘められた歴史的背景を巧みに配したプロット、クライマックスに向けてさらに勢いがつくストーリーテリング。 「この国で統制が取れているのは犯罪組織だけ」など、イタリア人にとっては恥部とも思われる暗部も包み隠さず描かれるが、この国への熱い思いは揺るがない。 ヴェネツィアっ子の主人公は、検死の時も食事の時も足を濡らしながら平然としていられるし、ゴンドラの上でも決して転ばない。 舞台となったヴェネツッアに関連した、気に入った文章をいくつか。 「頽廃の上に築かれた美しいこの街にはイタリア文明の栄光と殺人集団が同居していて、都合の悪いことは、香水を振りかけて覆い隠しているのだ」 「あの水も引いて、ヴェネツィアはまたきれいな街に戻るはずだ。潮が秘密を洗い流してくれて」 解説では、『ダ・ヴィンチ・コード』や『ミレニアム』を彷彿とさせると書かれているが、後半の逃亡劇では、TVドラマの『24』のバウアーとクレアの関係を彷彿とさせるほどスリリング。 とにかくダニエーレのキャラクターが凄すぎる。 誘拐によって鼻と耳をそがれ、極度の人間不信から古い館に引きこもる。 数学をこよなく愛し、ヴェネツィアの街を正確に再現した電脳空間を作り匿名で集える交流サイトを立ち上げる天才プログラマー。
0投稿日: 2014.04.29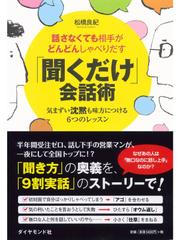
話さなくても相手がどんどんしゃべりだす 「聞くだけ」会話術
松橋良紀
ダイヤモンド社
まずは「アゴを合わす」ところから
最近の自己啓発本は芸が細かい。ダメ営業マンが、NLPを基にした会話の技術を身につけて、どんどん売り上げを伸ばしていくというストーリーは月並みだが、彼を導くメンターが一人ではなく、不定期営業のバーテンや多忙なキャバ嬢に、おどおどしたガイコツ君という多彩さ。主人公が教わったスキルを手にして次々と高額品を売りさばいていく姿に、手に取る想定読者も気持ちを高揚させつつ、その先にちょっとした挫折を用意し、より大事な何かを気づかせるという巧みな設定。ありきたり?その通り。ただ誰もが実践できてないからこの世界は廃れない。
0投稿日: 2014.02.28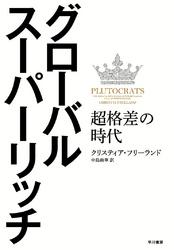
グローバル・スーパーリッチ 超格差の時代
クリスティア・フリーランド,中島由華
単行本
スーパーリッチと単なる金持ちとの間にも格差がある
なぜグローバル・スーパーリッチが誕生し、彼らとそれ以外の人々との差が開いたのか? それは、テクノロジー革命とグローバル化の影響から世界経済が再構築され、その結果としての経済的転換が起こったため。また、なぜミドルクラスは空洞化しつつあり、彼ら向けの製品やサービスが廃れつつあるのか? それは、ヘンリー・フォードの時代には購買力のあるミドルクラスを必要としていたが、いまや新興国に増え始めているミドルクラスを顧客にできるので、国内の彼らへの依存度を減らせるからで、グローバル化により人材よりも雇用が流出している。 プルトクラシーに決まった国籍はないが、決まった学歴はあり、どの名門校に通ったか、MBAをどこで取得したかが重要。また、自分探しに時間をかけすぎる者に対し、勝者総取り経済は容赦がない。所得上位1%に入りたければ、35歳までに年収が10万ドルに達していなければならない。スタート直後に全力疾走しなかった者や、誤った方向に走った者には、セカンドチャンスはほぼなくなっている。 革命的変化に対応するためには、地域の公立学校から名門校に進んだ学生のような主流のパラダイムを客観視できる人物が理想で、適切な時に適切な場所にいたかどうかなどの運も必要。生き残るために大胆な行動をとる必要はないが、成功のためには大胆になる必要があり、変わらないことは最大のリスクとなる。「昔は大きな魚が小さな魚を食うと言われていた。いまや速い魚が遅い魚を食う時代」なのだ。著者もこの後ジャーナリストを辞め、政界進出を果たしている。 所得上位1パーセントと残りの99パーセントとが対峙している現状は深刻で、「ウォール街を選挙せよ」運動だけでなく、アラブの春やオレンジ革命でさえ、民主化運動ではなくビリオネアに対するミリオネアの反乱であるとする。スーパーリッチにとって、世界を分かつのは国境線ではなく、金持ちと貧乏との境界線である。 最上層の富が大きく増加した場合、所得分布の下部の停滞が見えづらくなるため、景気回復の実感は感じにくくなる。もはや景気回復を主導するのは、圧倒的多数のミドルクラスではなく、桁外れの専門技術を持つひとにぎりの知識層である。
0投稿日: 2014.02.27
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
