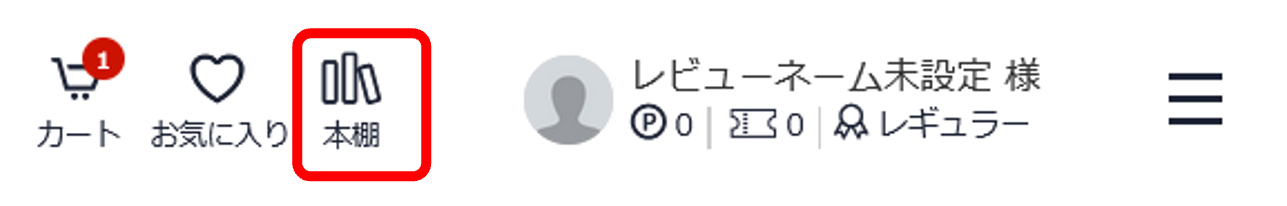![]()
ABAKAHEMPさんのレビュー
参考にされた数
248
このユーザーのレビュー
-
繊細な真実
ジョン・ル・カレ, 加賀山卓朗 / 早川書房
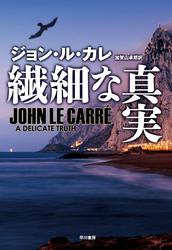
両手の指先を合わせ、おもむろに語られる機知に富む会話が魅力
9
82歳の老作家が書いた本書を読んで、何の恥ずかしさも感じない作家はいないだろう。
とりわけ登場人物がどこで買い何を食べたかを事細かに書くことが人物描写だと思っている日本の小説家にとっては、ほんの一、二…行ですべてを描写すると評されるほどのル・カレの筆力など顎がはずれて戻るまい。
壮大に練り上げられたプロットも、派手なドンパチも、甘美なベッドシーンもないが、両手の指先を合わせおもむろに語られる会話が本書の魅力。
特に外交官同士の会話は、丁寧で洗練された物言いの中で静かに弾を込め合ってるような迫力があってスリリング。
ル・カレの作品が近年も相次いで映画化され、あれだけの名優がこぞって出演するところを見ると、この魅力はあながち間違いではないのだろう。
ここに登場する政府による不都合な秘密の隠蔽や古き良きイギリス的妥協を読んでいると、とても彼の国だけの問題とは思えない。
不穏で唐突なラストからも、読者に少しでも事の切迫さを感じてもらいたい著者の思いが透けて見える。
授けられた勲章や年金の返上を辞さない母娘の真実の希求や、決して荒野に泣き言をこぼすような未熟さも思い上がりもない矜持と誇りには感心させられた。
世界中の外交官のあるべき姿も示される。
「相手をおだてて少しずつ攻略し、議論し、説得し、丸めこむ。だが期待はしない。万事において神聖なる基本外交政策にしたがい、あらゆる国の凶悪犯罪にそれを適用する、自国も含めてだ。会議室に入るときには、自分の感情は入口に置いてきて、特段の指示がないかぎり決して怒って退出することはない。何もかも中途半端で終わらせることを、むしろ誇りに思っている。ときには偉大な主人に注意深く進言することもある。けれども、決してウェストミンスター宮殿の国会を一日で再建しようなどとは思わない。思い上がったことをする危険も冒さない」 続きを読む投稿日:2015.01.13
-
フードトラップ 食品に仕掛けられた至福の罠
マイケル・モス, 本間徳子 / 日経BP

自分や家族の食習慣をオーバーホールするためのヒント
9
読む前は、「食べてはいけない」のような単なる企業告発物を予想していたが、アメリカ食品メーカーの企業史や新製品開発秘話など、かなり読ませて面白い。
業界ではこれまで、糖分や塩分や脂肪分の配合量がある値に…ぴたりと一致していると消費者が大喜びするという「至福ポイント」を見つけ出すのにやっきになってきた。
ゆえにメーカーにとっては、塩・砂糖・脂肪は、栄養素というより兵器に近いのだが、あまりにもこれら三つの成分が便利でなくてはならい存在になったため、その罠にも容赦なく引きずり込まれることになったと著者は指摘する。
加工食品の原材料とその配合は、熟練の科学者や技術者たちが緻密な計算のもとで設計し、過食をそそのかすように計算し尽くされている。
われわれの脳は、糖分、脂肪分、塩分に目がない。
なら、これらが入った製品を作ればいい。
利幅を稼ぐために低コストの原料も使おう。
次に、『スーパーサイズ化』して販売量をさらに増やす。
そして『へビーユーザー』に照準を合わせて、広告とプロモーションを展開する。
加工食品業界には鉄則や基本ルールがいくつかあり、「迷ったときは糖を足せ」や奇抜な商品を戒める「80%の親しみ」などもその一つ。
また、体に良いとされるーつの成分を前面に出し、消費者が他の事実を見過ごしてくれるよう期待するなんていう姑息な方法も用いられる。
幹部が「われわれは、需要を作り出すのではありません。発掘するのです。試掘して、見つかるまで掘るのです」と語るほど、マーケティングは徹底している。
それによって、チップス類のように、いままでおやつとして間食で食べていたものを、朝昼晩の食事の常連アイテムに変えたり、贅沢品から成分になったチーズのように、いままで単品で食べられていたものを、原料化して消費を増やすことに成功している。
「糖分」
・ドーナツはより大きく膨らみ、パンは日持ちが良くなる。
・“かさ”を増し、色合いを良くする。
・泣いてる子も泣き止むほどの「鎮痛薬」。
・脳の興奮作用を持つ恐るべき存在。
・素早く強力な作用を持つ覚醒剤のメタンフェクミンに似ている。
「脂肪」
・目立たず、さりげなく作用するアヘンに似ている。
・食品の口溶けや口当たりを良くし、食感を高める。
・至福ポイントがない。
・脂肪分は糖分と一緒になると、脳は脂肪分の存在をほとんど検知できなくなり、過食を防ぐブレーキがオフになる。
・甘さは、好まれる限度があるが、脂肪分は多ければ多いほど好まれる。
・多くても少なくても気づきにくく見えにくい。
「塩分」
・「加工食品の偉大なフィクサー」
・最初のひと口で味蕾に生じる刺激感を増大させる。
・糖分の甘味を強めてくれる。
・クラッカーやワッフルをさくさくに仕上げてくれる。
・パンの膨らむスピードをゆっくりして、工場で大量生産できる。
・腐敗を防いで賞味期限を伸ばしてくれる。
・多くの加工食品につきまとう苦味や渋味といった不快な味を覆い隠してくれる。
・肉の再加熱臭を手軽に解消できる。
「われわれは安い食品という鎖につながれている。安価なエネルギーに縛られているのと同じだ。ほんとうの問題は、われわれが値段に反応しやすいこと、そして、残念だが持つ者と持たざる者との格差が広がっていることにある。新鮮で健康的な食品を食べるほうがお金がかかる。肥満問題には大きな経済問題が関わっているのだ。そのしわ寄せは、社会的資源に最も乏しい人々、そしておそらく知識や理解が最も少ない人々にのしかかってくる」
本書は、自分や家族の食習慣をオーバーホールするための大きなヒントを与えてくれるが、問題は2つある。
1つは、「便利さの対価」をどう考えるか。
われわれは調理という「単調な繰り返し作業」を回避するために、便利さにお金を払ってもいいと考えている。
塩分への渇望は後天的であり、塩分摂取を減らそうとするなら早くから始めることが重要だとわかっていても、忙しい働き盛りの若い夫婦は、子供のために今日も塩分たっぷりの加工食品を買ってくるだろう。
もう1つは、当たり前のことだが「安全な食品を食べたければ金がかかる」ということ。
例えば、スープの滅塩に適した方法は、カーギルの提案する塩化カリウムではなく、新鮮なハーブやスパイスを使うことだが、コストは安価なナトリウムやそれより割高なカリウムよりもさらに上がる。
また食肉は、脂肪分が少ないほど価格が高くなる。影響を受けるのは、無知な人々だけでなく、貧しい地域の人々やその子どもたちなのだ。 続きを読む投稿日:2014.10.15
-
無私の日本人
磯田道史 / 文春文庫
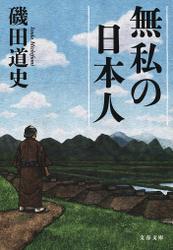
一途な志は喋らなくても誰かが分かってくれる
8
いつもは年貢などむしり取られるだけの民草が、お上から金を取ろうという大それた考えも面白いが、出資者である仲間を募っていく過程もいい。
調子のいい男には理屈ではなく、酒席で情に訴えたりなどなかなかにし…たたかだし、銭湯好きが一転して、水垢離をとり始めたことが思わぬ効果を生むところなどは、一途な志は喋らなくても誰かが分かってくれているんだなと感動する。
計画に一銭も出さずタダ乗りしようなんて欲得ずくの人間は、江戸時代には庶民に至るまで見られないし、たとえ思い通りならなくても恨み言を言わず、相手を気遣う質朴さは頭が下がる。
悪く言えば、仙台藩のイメージが変わった。
東北人特有のお上に対する従順さをいいことに、米を専売して利益をことごとく手中にするさまは醜悪この上ない。
震災復興の過程で宮城県政がこうした過去と重ね合わされることのないように望む。 続きを読む投稿日:2016.05.12
-
6度目の大絶滅
エリザベス・コルバート, 鍛原多惠子 / NHK出版
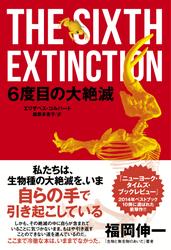
人がこの地上に出現した時「生存の条件」が変わった
7
「地球上の誰かがふと思った。『生命の未来を守らねば・・』」
漫画『寄生獣』の有名な冒頭シーンだが、本書でも「人類は最も成功をおさめた外来種」であり、人がこの地上に出現した時、地球上の全生命体の「生存の…条件が変わった」のだと説く。
大海原を躊躇なく漕ぎ出す狂気の遺伝子を持つ現生人類は、はるかに大きく頑強な大型生物やネアンデルタール人などを絶滅させ、人間の移動がなければ維持された種の地理的分離を元に戻し、あげく海の酸性化や地上での大変動に影響を及ぼす。
いま、これまでとは質的に異なる、何か特別なことが進行している。
しかし事はそう単純でもなさそうだ。
理論と現実が食い違うことはままあるし、予測が観測と一致しないこともよくある。
人間のやること、観測の限界は避けられない。
いまも「何千何万という新種が人知れず成育していて、正式な分類を待っている」のだ。
しかも、絶滅には時間のかかるものもあるし、破壊で失われた生息地の再生も考慮に入れる必要がある。
そう、自然はしぶといのだ。
「現実はいつももっと複雑」という一文は思い上がりをくじき、謙虚にさせてくれる印象的なフレーズだ。
それにしても本書は生命を新しい視点から見るきっかけを与えてくれる。
18世紀の終わりまでは、絶滅というカテゴリーは存在せず、まったく自明の概念ではなかったというのも、あらためて考えると驚きだ。
その転換となったのがマンモスなどの奇妙な骨の発見なら、現代ならさしずめ1隻のスーパータンカーやジェット機の出現が引き起こす転換も凄まじい。
グローバル化が数百万年かけて進行した地理的分離の巻き戻し、「新パンゲア大陸」の形成過程にあるという指摘は強烈だった。 続きを読む投稿日:2015.06.14
-
紙の動物園
ケン・リュウ, 古沢嘉通 / 新☆ハヤカワ・SF・シリーズ
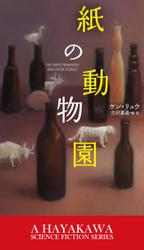
形容しがたい複雑な味わいと魅力を持った15篇の短編集
7
三種の異なる糸が撚り合わされてるよう。
通底に流れるのはノスタルジックで寓話的な愛の物語で、例えば「人々はいっしょに年を取らなくなった - いっしょに成長しようとしなくなった。結婚している夫婦はおたが…いの誓いを変えた。もはやふたりをわかつのは死ではなく、退屈だった」と永遠に続く人生を送る夫婦を描写してみせる。
時に展開されるハードSFの片鱗、例えば哲学者サールの"AIは幻想で、思考も幻想だ"とする謎の問いかけに煙に巻かれ、どこか懐かしみを覚える東洋の文化的背景に支えられ、読者は過去と未来を往還する。 続きを読む投稿日:2015.11.21
-
火星の人
アンディ・ウィアー, 小野田和子 / ハヤカワ文庫SF

策を考え、しぶとく生き残る術を教えられる思い
7
「自分の本領をあますところなく発揮するためには、まず自分自身から叩き出される必要があり、そのためには運命は不幸以外の鞭を知らない」と語ったのはツヴァイクだが、本書の主人公もジョークの好きな典型的なアメ…リカンで、地球と交信できれば「天才集団がきめてくれたとおりにやってる」方がいいと思っている、どちらかといえば怠惰な人物。
だが、ひとり火星に取り残されるという絶体絶命の状況に陥ってはじめて、時間に追われながら生き残るためにひたすら脳味噌を絞り、最後には「火星でのサバイバルのエキスパート」と評されるまで成長する。
しかも、その悪戦苦闘の連続の中でも、持ち前のユーモアと楽天性が決して失われない。
ヒューストンやリーダーの命令に従うのではなく、自らの命は頭の中の計算に預け、あとは仲間が残した70年代のテレビドラマを見まくるという図々しさ。
正統派の「ハードSF」らしいが、SF愛好者向けに限定していたらもったいない。
万人向けの、むしろ一部の人にはクスリにも作用する良書で、「いまの厳しい状況に諦め、自らを哀れんでばかりで、事態を打開するために本当に考え抜いたか?」と読んでて自問自答させられることがしばしば。 続きを読む投稿日:2015.03.18