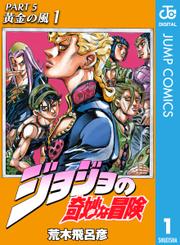
ジョジョの奇妙な冒険 第5部 黄金の風 1
荒木飛呂彦
週刊少年ジャンプ
スタンド版『ゴッドファーザー』
作者は、スタンドで『ゴッドファーザー』がやりたかったんだろうな。 前半で出てくる、「僕には夢がある」というジョルノの意味深な叫びも、結局は「ボスに近づいて、取って代わりたい」ということだったのか? 承太郎の調査や康一くんのイタリア訪問も宙ぶらりんのまま終わっていて、通して読んでると異和感ありまくり。 シリーズの中では、承太郎と同じく、特別な訓練などを経ずに、戦闘中に確変しちゃったジョルノだが、どちらかというとプチャラティの戦いぶりの方が印象に残る感じ。
0投稿日: 2013.12.12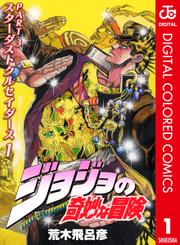
ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダストクルセイダース カラー版 1
荒木飛呂彦
週刊少年ジャンプ
トーナメント方式を断って、双六方式のバトルに
編集部から今度はトーナメント方式のバトルをという要請を断って、双六方式のバトルにした本編。登場する敵の中には、ディオに心酔して加わっているものもいるが、ほとんどが金で雇われた傭兵(あと恐怖も)なので、最後に形勢が不利になるとすぐに逃げたり恭順を示したりするのがほほ笑ましい。双六なので、敵の背景を説明する必要もないし、倒せば次に進める。とてもわかりやすい。 あと、第4部以降に登場するヒーリング能力者が出てこないので、やられたら終わりだし、ダメージを受けたら入院もする。
2投稿日: 2013.12.12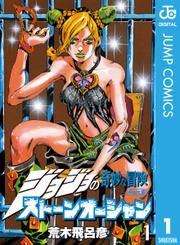
ジョジョの奇妙な冒険 第6部 ストーンオーシャン 1
荒木飛呂彦
週刊少年ジャンプ
承太郎の姫化は必然か?
第6部になって女性が主人公になったことが、読みどころの一つだろうが、あまりそれで新たな味わいが加わった気がしない。 承太郎が姫化してるって言われるけど、徐倫を一人前のスタンド使いにするためには必要不可欠だろう(あのお父さんがいたら、一人で何でも解決しちゃうから眠らせとかないと...)。 むしろ最初の設定では、お父さんが意外にも娘を溺愛してて、娘も父親離れしないとダメだったというスタートだったら良かったんだが...。
1投稿日: 2013.12.12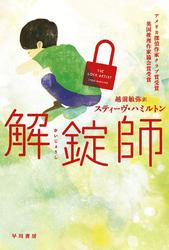
解錠師
スティーヴ・ハミルトン,越前敏弥
早川書房
何もかも完璧すぎて少しあざとい
前にもMWAとCWAをダブル受賞した作品って読んだことあって、その時はガッカリしたけど、こちらは楽しめた。というより著者も設定を考えた時点で、いけそうだという直感が働いたんじゃないかと思うほど、何もかも完璧で、悪く言えばちょっとあざといくらいかな。 ジュリアンのチームとの仕事の話を読んでいる時は、ジョジョの第5部が思い出されて、映画化というよりマンガ化を望みたい。 最後に、師であるゴーストは、マーシュ家で出会う錠前師がそれだと思ったけど、違ってガッカリ。登場シーンとしてはこちらの方が数段いいと思うんだけど。
1投稿日: 2013.12.12
未完のファシズム―「持たざる国」日本の運命―(新潮選書)
片山杜秀
新潮選書
原発存続・反対にもつながる「持たざる国」であることの自覚
とても平易な語り口で、中高生でも読めそうだが、間違いなく大人向けの本。目からうろこが落ちると思う。 戦前の軍人は単細胞でまっしぐらに無謀な戦争に猛進したのかと思ったら、結構複眼的で裏でしっかり算盤を弾いてたのがわかって面白い。「持たざる国」であるという冷静な自覚が、狂気の「玉砕」思想へと至る道はそれほど大きな飛躍を必要としていないんだな。 それと、結局この国で優れたリーダーが現われて国を導くなんてことはありえないんだということと、国難を前にしてもなかなか一つにまとまらない国民であることが身にしみてわかった。 原発存続派は、「持たざる国」であるという自覚を持っている、現代の「皇道派」。 原発反対派は、「持てる国」に変えられると信じる、現代の「統制派」。
2投稿日: 2013.12.12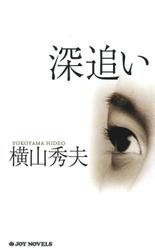
深追い
横山秀夫
JIPPIノベルス
三ツ鐘署のそれぞれの課の警察官を主人公にした短編集
いわゆる「警察物」ではあるが血なまぐさい話はほとんどなく、事故といってもいいような案件ばかり。また、人情話でホロリとさせるという展開ではなく、その課に所属している警官をよく熟知した話ばかりなので、語りが安定している。 やや解決へ至る天啓が唐突に現われる回(「仕返し」)もあるが、「又聞き」のような鑑識に入ったからこそ感じる違和感を出発点した作品や、「締め出し」のようなこれぞ短編といった"体言止め"的な終わり方をした作品など、どれも魅力が多い。 中でも一番良かったのは、「訳あり」。意想外の展開や伏線の見事さも美点だが、やはり警察官になりたくてなれなかった大里富士男の存在感が凄すぎて、読後この人物しか印象に残らないほど。
2投稿日: 2013.12.12
「日本経済ダメ論」のウソ
三橋貴明,上念司
知的発見!BOOKS
合いの手の応酬が続く歓談本
二人の本は本書がはじめてなのだが、論旨の明確な差異はないため、後半になっても主張と発言者が結びつかなかった。 対論と言いつつ「そうそう」と相手の主張に合いの手を入れるぐらいしか議論が発展しないので、門外漢には何を前提に話し合っているのかよくわからないところが多々あった。 こういうときには司会者みたいな人が入って、場合によっては背景を詳しく説明させたりという形式の方が良かった気がする。
0投稿日: 2013.12.12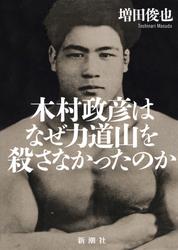
木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか
増田俊也
新潮社
格闘技に興味なくてもはまる、寝不足必至の面白さ
すこぶる面白い。700ページでしかも二段組の大著だが、数日の間一度も読書が遠のくことはなく、文字通り貪るように読んだ。 だが、読後感はすっきりしない。 これは戦後以降からの章で感じていたことだが、読めば読むほど木村という人物がわからなくなる。人より3倍も練習し試合前には瞑想もするほど精神が研ぎ澄まされていたはずなのに、思想・信条が心のうちに芽生えてこないというのにも納得いかないが、負ければ切腹する覚悟をもって勝負に臨むと言う一方で、練習も程々でしたたかに酩酊して現地入りするのだ。鬼と呼ばれるが性質は柔和。 力道山には卑怯なだまし討ちで負けただけで真剣勝負なら勝っていたはずという作者の思いは、太田の「後になって悔やむならリングに上がるな」という一言で一気にしぼむ。面白いのはこれを作者は隠さず、手の内をさらしていることだ。 読後この一戦を見たが、どうひいき目に見ても木村が負けるべくして負けたという印象しか残らない。本を手に取る前に見なくて良かった。ただ天覧試合はあるなら見てみたい気がする。
1投稿日: 2013.12.12
コストを試算!日米同盟解体
防衛大学校安全保障学研究会,武田康裕,武藤功
毎日新聞出版
だから日米同盟ってやめれないでしょ?的な本
日米同盟の重要性は踏まえた上で、もしも同盟が解消された場合に、日本は限られた資源や多くの制約の中でどのように自国の防衛を構築していくかという試算ではなく、安保反対派や自主防衛・核武装派に向けた、だから日米同盟ってやめれないでしょ?的な本。 日米同盟解体のコストを22兆円以上と試算するが、日本の財政が厳しい中で、米軍が行なっていたことの代替や勢力均衡にもとづくあれもこれもと経費を追加していった結果の数字。 すでに同盟による"巻き込まれ"を心配する現況ではなく、なんとか袖にされないようにというのが共通認識なのか?
1投稿日: 2013.12.12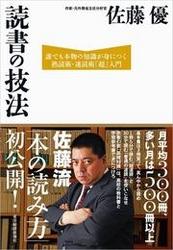
読書の技法―誰でも本物の知識が身につく熟読術・速読術「超」入門
佐藤優
東洋経済新報社
「知の巨人」による読書遍歴と「受験の神様」ばりの受験書指南
むかし立花隆、いま佐藤優。「知の巨人」による読書遍歴を公開と思いきや、途中から「受験の神様」和田秀樹の御株を奪うほどの受験書指南が始まる。 いわゆる「国際的なビジネスパーソン」に向けて書かれた本で、すでに12万部を突破という帯を見て、そんなにこの層は多いのかと疑問に思った。 私は一冊を読むのにも四苦八苦している現状を打破したいと手に取ったが、キリスト神学の本を読んでる時が息抜きで、仮眠は15分程度で切り上げ、日付の変わる0時から自分のための読書に打ち込む著者の姿に、ただただ畏敬の念を感じてしまった。 スマホやネットなどの誘惑をどうやって退けるかなんて悩みを共有してくれるのは、デヴィッド・L. ユーリンの『それでも、読書をやめない理由』の方だったな。ただペンを持ち本に直接書き込むって言う結論は同じだけど。
4投稿日: 2013.12.12
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
