
エブリシング・バブル 終わりと始まり――地政学とマネーの未来2024-2025
エミン・ユルマズ
プレジデント社
コモディティのデフレと消費者物価のインフレ
著者は、日経平均株価が2050年に30万円になり、これから黄金期を迎えると主張する。 執筆時の株価4万円から最高値5万円を目指していくだろうと書いてあるが、現在の2025年1月末の株価はその4万円をも下回っている。 先は長そうだ。 強気の未来予測の拠り所となっているのが、地政学的な風向きがこれから日本の追い風となるとの読みがある。 米中新冷戦により、最前線となる日本を強くするためさまざまな支援がなされるはず。 しかも日本の少子化や人口減少が更なる追い風をもたらす。 自動化やAI化の急速な進展で、長期的に見れば、人口の多い国の方が大変になるからだ。 地政学的リスクが高まれば、次に起こるのはインフレの昂進で、資産を何も持っていない奴は泣きを見る。 だから投資しろ、と。 現在のインフレが一時的なものではなく長期的なトレンドになるというのはその通りだろう。 著者は、毎年3~5%のマイルドなインフレを予想しているが、天井が抜けたような強烈なインフレもありうる。 中国経済の成長とほぼ軌を一にして推移していたコモディティ価格は、これから中国バブルの崩壊と共に下落していくだろう。 しかしコモディティのデフレは消費者物価には連動せず、逆にインフレとなり上昇していく。 なぜなら、中国が西側諸国のサプライチェーンから外されるため、これまで通り安い製品を供給できなくなり、製品の製造コストが上昇するためだ。 「中国とのデカップリングが実現した場合、西側資本主義諸国にもマイナスの影響が生じてくる。それがインフレだ。中国という世界の工場、デフレ輸出マシーンから離れれば、今までのように安い労働コストで製品をつくることができなくなる。西側資本主義諸国は構造的なインフレ要因を抱えることになるだろう」 さらに追い打ちをかけているのが、西側諸国がコロナ禍で採った政策だ。 政府がお金を刷りまくり積み上がった借金により、インフレは不可避となった。 インフレは作り出すのは簡単でも、制御は極めて難しい。 日本の借金はもはや返済不可能な水準に達しており、更なる高インフレが襲ったとしても、あえて政府はインフレ抑制の政策を講じないのではないか。 著者はその根拠を、これまでの借金踏み倒しの歴史から類推しているが、「黄金期」という独自予測がいかに薄氷の上に成り立ったものかよくわかるだろう。
0投稿日: 2025.01.30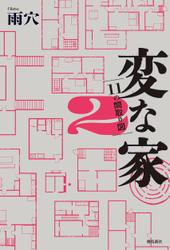
変な家2 ~11の間取り図~
雨穴
飛鳥新社
説明のつかない間取りの謎
前作よりさらにパワーアップした印象。 冒頭から順に11の家にまつわるミステリーが綴られる。 依頼調査だったり、特殊清掃人の聞き取りだったり、古い紀行本や月刊誌の記事、はては虐待死した児童の日記だったりと多種多様。 脈絡なく相互のつながりも見えず、相談への回答もない。 ただ11の歪な欠落部分のあるブロックが積み上がったと思ったら、設計士の栗原が登場し次々と推理を展開する。 それはすべての穴を埋める棒を刺し貫き、ブロックを消していくような爽快感が味わえる。 11の謎を整理・腑分けし、着目すべきポイントを指摘し、論理的な解釈を与えていく。 子供の日記の断片からからおじさんの家の間取り図を描いていく様などその最たるものだろう。 普通の小説ならこういう謎の呈示の仕方はしないし、解明パートで合いの手のように適宜ノートや証言の引用が付されることもないだろう。 欠点とも思えるが、広く読者を集めているところを見ると、こうした体裁に心地よさを感じるのかも。 袋小路の廊下や、扉のない隠し部屋など、説明のつかない間取りの謎の答えとして、本書は大別すると2種類の答えを用意している。 ひとつは窓のない部屋を監禁部屋と、謎の部屋を殺人を行なうための通路と解釈するような合理的な説明と、因習やシキタリ、宗教・祭祀的な意味合いの説明だ。 これらでもまぁ面白いのだけれど、少し殺伐とし過ぎている。 それより深謀遠慮に基づく、深い慈愛や願望からの間取りであるという説明も読んでみたい気がする。 本書はクライマックスで何回転か推理の反転が行なわれるのだが、どれも余計に思えた。 全体の構図をひっくり返すのは最近の定番だが、何度くるくる回っても、着地も決まらず余韻を損ねてしまった。
0投稿日: 2025.01.28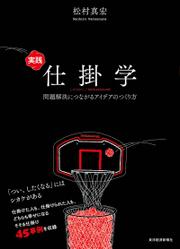
実践仕掛学―問題解決につながるアイデアのつくり方
松村真宏
東洋経済新報社
ついしたくなる選択肢の追加
数々の実践例が紹介されているが、いいなと思ったのは「大阪環状線総選挙」の事例。 混雑緩和と事故防止を目的として、殺到するエスカレーター利用客を横の階段に促す仕掛けとして、「アフター5に行くならどっち? 天満派、福島派」と問いかけるポスターを貼り、階段の右側を「天満派」、左側を「福島派」に分け、贔屓を選ばせる仕組み。 別に投票結果が知りたいのではなく、利用客が面白いと思って意図を汲み取り階段を使ってもらうことにあるため、いくらでも投票の中身を変えられる。 ポスター制作や色分けなどのコストはかかるが、ご当地ならではの出題ができるので、仲間連れで別れて通っても話のタネになる。 もう一ついいのは、エスカレーターを止めているわけではないこと。 足の不自由な人などこれまで通り利用できる。 このように従来の選択肢は残したまま、その他の選択肢の魅力を高める手法を著者らは仕掛けと説明している。 強制するのではなく、誘引すること。 面白いと思ったり、意図に共鳴した人だけが、エスカレーターから階段に変えてくれればそれでいい。 ただ、その他の実例はどれも興醒めするような事例ばかり。 真実の口を模した手指消毒機も、じきに飽きられて利用されなくなりそう。 特に興醒めなのは、何度も紹介されるマジックハンドでポケットティッシュを配る方法。 コロナ禍という特定の状況下とはいえ、あまりにおぞましく、とても誘引性があると思えない。 第一こんなの受け取り損ねて、ティッシュを地面に落とす人が続出しそうだ。 より非衛生になり考えられない。 あと、効果の検証がほんと微妙。 真実の口だと、次第に飽きられて利用率が減ったけど、併設している従来のスプレーの利用率は増えてるから効果があったと評価する。 達成率自体も微妙な結果が多く、じきに飽きられ景観にそぐわぬモニュメントと化しそうなのも多い。 想定した目的を超えた副次的な効果も評価の対象になっているが、きちんとデータの裏付けができているのか怪しい。 ほとんどがゼミ生と行なった実証実験なので、研究の材料としては有効だし、なかなか楽しそうなゼミになりそうだが、その割に驚くほどアイデアが貧弱なのも気になった。
0投稿日: 2025.01.27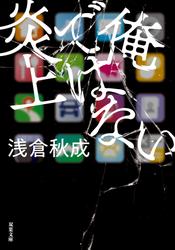
俺ではない炎上
浅倉秋成
双葉文庫
「自分は悪くない」という思考の危うさ
フォロワー数たった11人のアカウントによるツイートがあれよあれよと拡散され、そのうちどこからともなく有志の特定班がしゃしゃり出て、警察顔負けの分析力で過去ツイから本人を特定。 上を下への大騒ぎとなり見事、炎上に至る過程は確かに臨場感がある。 ただ著者はネットやSNSの持つ恐ろしさを描きたかったのではなく、世代を超えて蔓延している「自分は悪くない」という思考の危うさを描きたかったようだ。 あいつがこいつが、もしくは社会全体が、とにかく自分以外の誰かがこの世界の足を引っ張っているんだ、と。 本書で逃げ回る羽目になる山縣泰介は、その典型だろう。まったく身に覚えがないし、何も知らないし、やってない。 自分こそ被害者で、俺はこれっぽっちも悪くない。他人の失敗に厳しく当たるのも本人のためを思えばこそ。 なのにこの窮地、そして四面楚歌。 きっと俺のことを恨んでいる奴がいるんだろうが、俺にはとてもじゃないが候補すら思いつかん。 かつての部下に教えてくれと頼みに行って呆れられる。 「あなたは、もともと恨みを買いやすい人ですよ」と。 少しずつ自分の暗部や恥部を見つめ直し、やがて考え方にも変化が訪れ、ついには断罪されるべきは、本当に反省すべきは、自分なのではないかと悟る。 仕舞いに「こんなにも罪深い俺に親切にしてくれるなんて」と涙まで流し…。 前作の『六人の嘘つきな大学生』が面白かったので期待して読んだが、同じ作者かと信じられぬ思いでまったく支持できない。 叙述トリックのミステリで一番大事なのは文章だと思う。 別に名文である必要もなく、ただ的確な言葉で物語を紡いでいき、読者は些細なワードや言葉遣いに謎解きのヒントを探るもの。 しかし本書の文章は、その前提以下の水準というか、読んでいて胸騒ぎがするような表現の連発だ。 「胸の中にある怒りのコンロにぽっと炎がともる」とか、「フリーズドライされていた心に水が垂らされたように」なんて、大昔に書いた習作を読み直した時の気恥ずかしさに似た感慨を覚える。 「慰めが生傷の上にそっと巻かれた包帯のように、優しく泰介の心を包み込む」、「勇ましいまでの決意は、栄養を絶たれた真冬の向日葵の如く、いつしか完全に萎れていた」などちょっと平静ではいられないだろう。 形容の仕方がとにかく漫画的で、「全身の毛穴から粘り気のある汗がどろりと滲み出す」というのも、読んでて話の筋を忘れそうになるほど現実感が薄い。 本書も登場人物の言葉の使い方から嫌疑を晴らすという展開になるため、日本語には相当に注意が払われているはずなのに、トリック云々以外のところで気になる文章が多かった。 また前作のようなインタビュー形式の独白という会話文のスタイルに戻れば、違和感が薄まるのかもしれないが。
0投稿日: 2025.01.25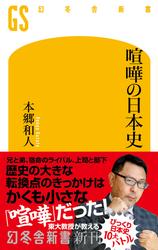
喧嘩の日本史
本郷和人
幻冬舎新書
日本史上最大の兄弟喧嘩の影響
日本史上の喧嘩の達人たちによる巧みな戦略の数々。 1)小さな火種を大騒動にまで発展させる。 源頼朝は、朝敵となった義経の捜索・探査を理由に、朝廷から全国に守護、荘園に地頭を置く許可を取りつけることに成功する。 義経追討を理由に心の底から欲しかったものを手に入れるという頼朝の見事な戦略で、これにより鎌倉幕府を成立させている。 2)権力簒奪の第一歩は合議制の提案から。 北条時政は、将軍家の権力を無力化させる目的から合議体制への移行を目論む。 一見、専横を生まない民主的な体制のようにも思えるが、すでに権力を手にしている者からすれば、合議制など必要ない。 源氏将軍家の権力を奪うため、自らが権力を振るおうとした北条氏だからこそ合議制を必要とした。 3)すぐに派閥間対立に突入するのではなく、最初は敵対勢力間の仲間割れを誘う。 13人の合議制のメンバーのうち、北条時政の最初の標的となったのは、頼朝の一番の家臣だった梶原景時。 いってみれば秀吉亡き後の石田三成状態で、嫌われ者。 不満を一身に集め、反北条派からすれば仲間なのに、弾劾されてしまう。 敵対勢力は、わざわざ自分らにとって都合のよいはずの勢力を削ぐことに協力させられているのがわからない。 図に乗った時政が嫌われ者の次に標的としたのが、一番の人気者だった。 武士の鑑と評され、御家人たちからも人気の高い畠山重忠を亡きものしようと、陰謀を巡らす。 これが失敗だった。 「彼が謀反などするはずがない。軽率に誅殺すればきっと後悔する」という息子・義時の諌言も聞かず突っ走った結果、逆に鎌倉から追放される憂き目に遭ってしまう。 4)権力差がついてきたら、火種を煽って敵を倒す。 挑発を繰り返し暴発させたり、堂々と喧嘩をふっかけライバルを蹴落としていったのは、北条だけでなく家康もそうだった。 単なる個人間の喧嘩を軸に日本史上で起こった重要な対立を読み解いていくなど無理があるだろうと思わなくもないが、足利尊氏・直義の兄弟喧嘩のように、日本史上に絶大な影響を残した対立もあった。 尊氏と直義の兄弟喧嘩に端を発する路線対立は、その後の室町幕府の歴史を通じてずっと続いていき、ひいては江戸時代にまで影響を及ぼしている。 「西国の京都を中心に政権を構想する足利尊氏派と、東国の鎌倉で政権を構想する足利直義派の対立は、室町幕府の歴史を通じて、射程の長い対立の原理となってきました」 最初は、「京都へ行くか、鎌倉へ戻るか」の行軍の進路の問題だったのが、国家観や理念の違いとなって先鋭化する。 直義の思想は、頼朝以来の「朝幕分離」路線。 「武士の政権は東国に、貴族の朝廷は京都に」という棲み分けである。 それは徳川家康の江戸幕府へと受け継がれていく。 この理念の根底には、「京都のことなんてどうでもいい、関東は関東で好きにやればいい、関東のことだけを考えよう」という東国武士に共通する思想がある。 ようは直義は鎌倉幕府の続きをやろうとしたのだ。 武家は武家で、公家は公家であり、幕府と朝廷は違うものと考えた。 朝廷の争いに武士が関わるとろくなことにならない。 その反対に、武士の政治には朝廷に口を挟ませない。 そのためには、朝廷には近づかずに、鎌倉に戻り、政権を固めるべきだという立場だった。 しかし尊氏の考えは違った。 京都に拠点を置く路線をとり、朝廷と関わり合うことを恐れず、あくまでも武士の政権にイニシアティブがある状態を目指そうとした。 これは常に朝廷の承諾を前提にしながら、自分たちの政権の権益を確立していった頼朝にも通じる思想だが、鎌倉時代とは異なる時代の要請もあった。 つまり、京都とは距離を取ろうという勢力と、貨幣経済の観点から財政基盤を無視して東国に政権を置くわけにはいかないという立場の対立だったのだ。 京都を押さえるということは、商品流通を押さえることであり、経済の中枢を押さえることでもあった。 このように尊氏と直義の対立には、根本的な国家観・政権観の違いがあった。 面白いのはここから。 尊氏と直義といったトップ同士には明確な思想・路線の違いがあっても、家来レベルではそこまで明瞭な違いはなく、単純に「あいつが気に食わねえ」「許せん」といった気持ちだけで対立が継承されていったと言う点。 時代が経るごとに思想や理念は失われ、応仁の乱の頃にはただ代々引き継がれてきた「憎き細川」「憎き山名」という恨みのみで、両陣営分かれて戦さとなっていたということ。 そんなものだろうと思う。
0投稿日: 2025.01.25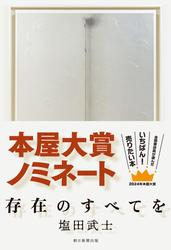
存在のすべてを
塩田 武士
朝日新聞出版
タイトルの意味と作品との齟齬
前の『罪の声』が良かったので期待して読んだが、イマイチだった。 ホキ美術館の展覧会に行って間がなかったので、本書のモチーフとなってる超細密な写実絵画への関心が高かっただけに残念。 著者が本書で描こうとしたテーマは明白だ。 写実画家が創作を通じて対象に向ける眼差しを、自身の前職であるジャーナリストの仕事に結びつけて解釈し直すこと。 それには写実画における"存在"の捉え方を問わなければならない。 貴彦の求めに応じ亮少年がみかんを描いてみせるシーンが印象的だ。 大抵の人はみかんのみに集中してそれを描いて終わり。 しかし亮君はみかんを載せたコタツの天板の木目まで描き、貴彦を驚かせる。 目の前に存在する「ありのまま」を写し取っていると。 背景が薄っぺらい絵には緊張感がない。 対象物だけを見ていたのではダメで、キャンバスの中のものはみんな等価値、同じくらい大切なもの。 髪の毛もそうだし、水面の揺らぎもそう。 本物に迫るとは、実際に目にしているものを丁寧に拾っていくことなのだ。 タイトルの「存在のすべてを」にはそういう意味が込められている。 大事なのは「存在」で、「写実画を描くということは"存在"を考えること」にあると貴彦は語っている。 ちなみに巻末の「取材協力」にも名前があるが、曽根茂の棚田の油彩画などは、本書に登場する風景画をイメージするのに最適な作品だろう。 昨今の超写実ブームの背景にも、世界がどんどんネットでつながれバーチャル化していく中、実体の存在感が失われていく現状に抗いたい気持ちが人びとにあるからではないかとも記されている。 著者はさらに、新聞販売の低調や望ましい報道とは何かを巡って、記者の存在意義も揺らいでいると語る。 いろいろな価値観が揺らぎ、すべての事柄が曖昧に消費されている中、記者が果たすべき役割とは何かと問いかける。 このことを象徴する表現として著者は、門田に「質感なき時代」と語らせている。 しかしこのワードは本書でもう一度だけ別の人物が口にしている、亮だ。 「父は写実画を描くことで『質感なき時代に実を見つめる』大切さを教えてくれました」 ここに猛烈な違和感を覚える。 何と都合よく示し合わせて、と。 そもそもなぜ貴彦の視点のパートを描くのだろう。 そこは新聞記者の挟持として、「空白の3年間」も自らの手で構築させるべきなのではないか。 大方の読書は、亮を中心とした疑似家族間の様子が伝わる視点の転換を好意的に捉えるだろう。 だけど「存在」をテーマとした小説としてはずいぶん肩すかしな帰結に終わったような気がしてならない。 さらに、行方を追う記者パートとその対象の画家パートとを分割するなら、結末における突如の再出奔の意図も語らせるべきではなかったか。 それと本書で感じたもう一つの違和感は、亮の真の母である瞳の存在の描き方。 著者は記者らしくネグレクトや児童虐待に対する把握が不十分だった30年前の社会体制の欠陥として、育児放棄していた母親の存在感を物語から放逐してしまっているが、それでいいのだろうか。 線引きも曖昧なまま、地域や親族間で包摂し物事をまるく治めていた時代はすでに去り、外部の警察や児童相談所の介入が当然視され、医者にも注意欠陥障害だ発達障害だとの過剰診断を求めてレッテル貼りに安堵する。 自堕落なダメ親とされた瞳は、一人息子が寄越した絵葉書のみを大事に抱える孤独な存在として扱われ、物語後半からは綺麗に消し去られている。 この場合の「存在のすべて」とは「見たいものすべて」ではないかと鼻白んだ。
0投稿日: 2025.01.19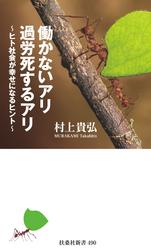
働かないアリ 過労死するアリ~ヒト社会が幸せになるヒント~
村上貴弘
扶桑社BOOKS新書
喋るハキリアリの活用に向けて
いつもの「人間がアリから学ぶことも多いよ」系の話だと高をくくっていた。 不可思議なアリの生態の紹介から、過労死するほど働くアリがいる一方でまったく働かないアリも一定の割合で存在する巣内の状態まで、人間の社会組織に準えて何らかの示唆を与えてくれる本だと。 しかも著者がメインに調べているのは、あのハキリアリだというから、より確信を強めた。 ハキリアリはアリ界の中ではかなり有名で、いくつもの本で取り上げられている。 生態に注目しているのは昆虫学者は言うに及ばず、社会学者や経済学者から果ては物理学者まで多岐にわたる。 農業を行なうアリとして知られるハキリアリの農耕の歴史は古く、人類など比べ物にならない、1500年もの悠久の歴史を持つ。 ヒトを除けば、この地球上で最大の複雑な社会を形成すると評される、ハキリアリのコロニーは800万以上の個体からなり、地下の巣は直径が30メートルを超える。 大きな脳をもつ脊椎動物がふつうは2、30の個体からなる社会を営むので精一杯であるのに、神経線維の入ったちっぽけな頭しかないアリが、これほどとてつもない規模で運営できているのはなぜなのか? その社会は高度な職能に分かれた厳格な分業制が敷かれている。 ノコギリのような大きな顎をもった葉切り職人に、 切り落とされた葉を巣までリレー式に運ぶ運搬職人。 ちなみにハキリアリは体重の30倍もの重さのものを運ぶことができ、例えるなら背中に自動車を背負って運ぶようなもの。 それほどの力持ち。 さらに持ち込まれた葉をキノコに与えて育てる園芸家に、病原菌がいないか絶えずキノコの状態をチェックしている検査技師までいる。 ちなみにハキリアリの社会の衛生状態は極めて高く、GDPの多くの割合をその分野に投資してもいる。 そして卵や幼虫の世話をする家政婦から、外敵から巣を守る屈強な軍事工作員まで揃っている。 ハキリアリに大切に育てられる菌類は巣以外では見つからず、アリなしには生きていけない。 そしてアリもまた、この菌が紡いでくれる栄養分の塊がなければ飢え死にしてしまう。 持ちつ持たれつだし、ハキリアリが菌を養っているのか、菌類がアリを養っているのかよくわからない。 そんなハキリアリがしゃべっていたなんて初めて知った。 従来のフェロモンを介した情報伝達ではなく、音声コミュニケーションを用いることで、複雑な社会を維持しているのだと。 嘘だぁ、アリが喋っているなんて、これまで読んだ本に書いてなかったぞ。 いや、多くの研究者はアリが音を出していることには気づいていたんだと。 それがあまりに小さい音で、聞こえるのは個体サイズの大きな個体だけだった。 だから巣内でも割合が多く、もっとも働いている中型サイズ以下の個体の音は、人間の耳で感知できなかったのだとか。 それを著者らは独自に高性能な録音装置を開発し、音声を集めることに成功したのだ。 それを実験室で再現したコロニー内のキノコ畑やゴミ捨て場、葉を刈る場所などに設置して、音を聞いているのだと。 するとアリたちは「ドゥルドゥルドゥルドゥル」などと、胸部と腹部の間にある節をこすりつけて「会話」をしていることがわかったのだ。 ちなみにこの「ハキリアリの音声コミュニケーションに関する論文」は審査待ちの状態で、学界から認められた新説ではない。 単に手続き上の問題なのか、何か研究に致命的な問題があるのかははっきりしない。 葉っぱを切る時、幼虫の世話をする時、警戒音を出す時で異なる音が使い分けられているのが確かなら間違いなさそうだが、統計上の有意差が明確でないのか、シチュエーションとの関連づけの問題なのか、審査に時間がかかっているのは事実。 あと気になるのは、「ドゥルドゥル」とか「ギュンギュン」という音を論文上でどう表現しているのだろうか。 カタカナのある日本語でこうした特異な音を文字で表現することはわけないが、論文は英語だろうから、外国語でどのように変換するのか気になった。 著者がアリの音声コミュニケーション研究で考えているのは、音を活用して防除などに貢献できないかということ。 警戒時に発せられる音はわかっているので、「こっちに来ないでね」とのメッセージとして利用したり、「こっちの雑草も刈ってちょうだい」など労働力として活用したりと、夢は長大だ。
0投稿日: 2025.01.15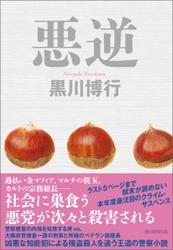
悪逆
黒川 博行
朝日新聞出版
盗まれたものがわからないのは厄介
傑作というわけではないが満足感が高く長いけど一気読み。 なんでも『週刊朝日』連載時とは結末が180度違うらしいので、そちらも読んでみたい。 著者は前々から完全犯罪を描きたいとの思いがあったようで、インタビューで本作を「警察小説と完全犯罪の組み合わせ」と語っている。 犯人側パートと警察パートが交互に平行して描かれるため、読者は捜査の進捗具合が手にとるようにわかる。 このへんは微妙なバランスを要するところで、下手をすると興を削ぎかねないが、完全犯罪を描きたかったという目的からすれば必然だったのだろう。 ちょっと読んでると著者が「俺ならこう犯行計画を組み立てる」と宣言してるような趣もあってちょっと恐ろしくなるほどディテールが精緻。 犯行前は体毛を丁寧に剃り上げ、現場で使用した道具はその日のうちに残らず処分。 強盗の格好の標的は、まんまとマルチで会社を計画破綻させ莫大な金を詐取した詐欺師に限る。 おおぴっらに銀行や貸金庫に金を預けることのできない。 売買記録も必要ない無刻印の金塊は資産隠しにうってつけ。 違法だが、闇ルートでは頻繁に売り買いされていて、需要も高い。 公的な記録がないから警察も何が盗まれたのかわからない。 これからはニュースで、強盗にあったが端金だったり何も盗まれなかったとかいう事件を耳にしても、裏では実はと勘ぐってしまいそう。 他にもATM機で一日におろせる限度額は50万円までと思っていたが、いまは生体認証取引のATMだと限度額は1千万円だというのは知らなかった。 Nシステムの裏をかく方法も凄まじい。 赤外線避けのカバーをプレートに貼る手法は知っていたが、システムに数字の相似を認識する機能はないことを逆手に取って、数字を部分的に細工する手法はおもわず膝を打った。 著者は、画家も小説家も新人とベテランの差は省略だと語る。 不安からついつい書き込んでしまいたくなるが、読者は行間を読んでくれると信頼し、徹底的に余分を削いでいく。 著者お得意の軽妙な掛け合いのしゃべくりも、念頭にあるのは漫才ではなく落語。 例えば、玉川と舘野の2人が情報屋に合いに行くシーン。 「彫甚。和彫りや」 「気難しいですか」 「よう喋る。鶏ガラみたいな男や」 「痩せてるんですか」 「痩せてはないな。肥えとる」 「鶏ガラいうのは」 「喋ったことから出汁がとれる」 「それはいいですね」
0投稿日: 2025.01.10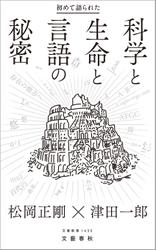
初めて語られた科学と生命と言語の秘密
松岡正剛,津田一郎
文春新書
ノイズや破れ目、場所と順序、そして数学
対談者の一人はすでにこの世にない。 昨年亡くなった松岡正剛は、肺癌治療と平行して三年もの歳月を本書に捧げ、「世界の発生と解釈」をめぐっての生命やら意識、情報について縦横無尽に語り尽くした上でも、本書のあとがきに"いまだにわからないことがこれだけある"とつらつら列記している。 この口惜しさが伝わる文章を読むにつけ、奇才と評されるほどの博覧強記の碩学の知見をこれ以上新しく知ることはできないのだなと思いとともに、年始早々何か物悲しい気持ちになってきた。 本書で両者とも、深く思考することの重要性を説いている。 むしろこの快楽を知らずに終わることのもったいなさを訴える。 本書の内容も相当に手強く難しい。 一度読んだだけで、すべてを理解できたとは到底思えない。 だけど、いまの自分の実力より負荷をかけたものを読まないと、筋力と同じで神経も鍛えられない。 「深く思考することは、最初は大変なんだけど、それによって得られる快感は大きい。わからなかったことがわかるようになるとか、人がわからなかったことを突き詰めたとか、とにかく一歩深められたという実感は、なにものにも代えがたい。それを一つ二つ経験するから、研究者ってやめられなくなっちゃう。快感を一回味わうと、きっとまたあの快感がくるんじゃないかと思って、研究に没頭するんです」 XやTwitterなどが与える環境では、思考の泳ぐ深さが浅すぎて、思考力が動かない。 安易に流され続ければ、神経もどんどん劣化していく。 それに抗するには「世界の堂々たるわかりにくさ」にひるまず立ち向かい、感じ続ける必要がある。 本を「読む」という行為はなるほど「目が文字を追う行為」に過ぎないが、同時にそれを通して「意味が出入りする行為」でもあり、認識が立体的になる行為でもある。 AIだ、ChatGPTだと喧しいが、ディープラーニングの効果が出るにはビッグデータがないと駄目である。 学習機会をどんどんふやしていけば、ある程度はいい特徴抽出になるんだけども、問題はデータが少数のときどうするか。 つまりスモールデータをどうやって学習するのか、それをどう意味づけるのか。 パターン学習も特徴抽出も、同定や差異化も働かない。 たまにしか起きないまれな現象の予測には使えないはずだ。 その点、われわれの意識は「まれな現象」を感知できる。 オカルト現象や神秘体験もそうした「まれ現象」にしか現れない。 ビッグデータ云々でなくとも、繰り返しの検証可能性を旨とする科学的方法論とはソリが合わない。 かつて小林秀雄が問題にした科学者の神秘現象に対する冷笑的な態度の話にも通ずる。 しかしよく肝に銘ずべきなのは、「万物の原理は数である」と説いたピタゴラスも、数と同時に神秘学も同時に解明しようとしていて、「魂は調和する」ということを数と平行して思索していたということ。 数理科学者の津田一郎は、数学が健全なのは不完全定理があるからだと説く。 「不完全があるということはきわめて健全です。完全性定理だけだときれいに閉じる。不健全だけど、不完全性定理が出たことによって数学は健全なものになった。それと同じ」ことだと。 科学が真に発展するためには"破れ目"をつけておくや”ノイズ"をかけることが肝要で、これは情報を作っていくためにも意味を生成するためにも必要だ。 それら無しには、研究の多くが閉じた世界になってしまうからだ。 ノイズの役割は意外に大きく、宇宙の始まりにもランダムなノイズがなければ何もおこらなかったはずだ。 津田はその重要性を自ら携わるカオスにノイズをかけると秩序化するノイズインデュースド・オーダー仮説を通じて知り抜いている。 無秩序に思われるカオスに、これまた無秩序なノイズをかけ合わせると不思議なことに秩序が生まれる。 これは生命誕生のメカニズムとも関連していて、無機物の世界では、状態を放っておいたらエントロピー増大になってしまって、どんどん無秩序になってしまうけれど、生物だけはエントロピーを減少させる方へ、秩序を作る方へ向かっている。 無秩序を拒否して秩序を形成し、自己組織化に向かうというのは生命の仕組みそのものである。 もう一つ情報の生成において重要なのは”拘束条件”を設けること。 フリーにしておくと何も起きないのに、何か条件を与えたり、拘束をかけてやると生み出されるものがあり、それこそが情報であり生命なのである。 ただ「自由にしていい」と放任されると何もできなくて、ある程度は拘束をかけると頑張れるというのは我々も同じ。 何らかの拘束がかかって、そこから生命が分化していったのが、進化に必須だったのではないか。
0投稿日: 2025.01.08
地雷グリコ
青崎有吾
角川書店単行本
バトルではなくハンティングに近い
著者はインタビューで、ミステリーファンに向けて自身が好んで読んでいるギャンブル漫画のロジックを推理小説に持ち込んだらどうなるかを期待して描いたと語っている。 おそらく漫画『カイジ』のことではないかと思われるが、比較してみるとずいぶん味わいが異なる。 両者とも、登場人物が独自のルール設定のゲームで頭脳バトルを繰り広げるのは一緒だが、カイジの方で著者が特に描きたいのは、逆境に立たされた時の主人公の心模様。自分の弱さやダメな部分を痛感し、汗や涙をだらだらと流しながら、絶望感に暮れても必死に這い上がろうとする逞しさ。 人生訓めいた言葉がコマを埋める中、大逆転の秘策を思いつく、そういう展開である。 対する本書では、勝敗は戦う前から決している。 「真兎は最後に勝敗をひっくり返す。あとは全部、仕込みに使う••••そういう戦い方をする」というように、負けが込み、不利な状態に立たされ、意気消沈する姿を見せても、基本的にはポーズであり、どう相手に勝ったと思わせ、そのまま勝負し続けるよう仕向けるかにある。 対等なバトルといようり、ハンティングやフィッシングに近い。 しかもその手法は、ルールの穴をつき、かつ審判にクレームを出させないイカサマを用いたもので、それはすでにゲーム開始前に仕込まれている。 本書は、2024年上半期の直木賞候補作である。 本命不在の選考だったが、支持を集めることは出来なかった。 「図版に頼るのが小説と言えるか」(林真理子)、「何でもありの出し抜き合戦はワンパターン」(高村薫)、「どう面白いのか説明できない」(宮部みゆき)などとの選評が続く中、興味深かったのは選考委員の京極夏彦と桐野夏生の二人が、"視点の切替により小説の安定感を悪くしている"と指摘している点。 確かに、最初は主に介添人である鉱田さんの視点から物語が語られているのが、最後には真兎や絵空など多視点となっている。 推理小説のフィールドからすれば、こうした視点の途中からの変更は、"ゆらぎ"として感じられるのかもしれない。 作家・石田衣良は、この選考レースを予想する自身のYiutubeの番組でこう語っている。 「選考前ですでに推理作家協会賞と山本周五郎賞など三冠していて、これをそのまま直木賞も受賞させていいのかという問題がある。読むと確かに面白い。だけどその面白さはどこかで百回は見たなという面白さ。イカゲーム、カイジ、嘘喰い、カケグルイ…。"いや小説でこのタイプは新しいのでは"という指摘もあるが、それは単に小説というジャンルがドラマや漫画など他のメディアに比べ遅れをとっているだけでは。内容も、プレーヤー同士がどうやって相手の裏をかくかという話というより、毎回イカサマでいかに勝つかという話で、それは正直言ってウーン…。これが直木賞も受賞して四冠になるとしたらたら、いよいよ日本の小説もヤバいと思う。読む前は愉しみにしていたけど、受賞すると四冠かと考えると萎えた。それに『テスカトリポカ』のような衝撃はない」 感想として面白かったのは、脳科学者・茂木健一郎の感想。 「きわめてクレバーな作品。一番感心したのは、独自のルール作りやその最適化ではなく、そこからの逸脱を描いている点。多くの読者の支持を集めているのは、こういう小説を読みたいという願望の裏返しでもあるし、日本の現在の特徴も示しているように思う。小説の表現方法も非常にゲーム実況的だし、若い人たちは限定された時間や空間で、プレーヤーが騙し合い、バトルし合う作品を好んで見ている。自分も人生は広い意味でゲームだと思っているが、そこではルールが明確化されていない。人生というゲームにおいてルールは、プレーヤーには絶対明かされない不可知のもの。かつゲームには始まりも終わりもない。これまでの文学も、人生をそういうものとして描いていて、そうした不可知さを引き受ける形で昇華させている。だから、起きている出来事やルールの確定的な記述ができるのだという思想や、人生をそういうものだと捉える思想には疑問を覚える。そういうフィルターを通して人生を語るという本書のような小説が、世間にこれだけ幅広く受けいれられる現状にも違和感がある。そういう意味では、著者が書く普通の意味での文学を読んでみたい気もする」
0投稿日: 2024.12.31
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
