
認知症医療革命 新規アルツハイマー病治療薬の実力
伊東大介
扶桑社BOOKS新書
アルツハイマー病の治療薬作りの難しさ
まぁなんと、知らなんだ知らなんだ。 てっきり通常のMRIでもこの病気は発見できるんだと思ってた。 確かに脳の萎縮なんかは捉えられるだろうけど、アルツハイマー病の元凶とされる2つのゴミのいずれかをチェックするには独自のPET検査が必須らしい(これ以外の方法もあるにはあるが)。 数が少ない上に非常に高額(30万円)。 このゴミがまた厄介で、実はまだ正体がよくわかっていない。 ゴミとされてるが、健常な人でも作り出されているので、何らかの役割を持っていることは確か。 ただ、明らかになってきたアルツハイマー病発症のメカニズムからすると、まず脳の中で、アミロイドβがゴミとして溜まってくる。 それが一定以上に蓄積してくるとスイッチが入ってしまい、今度は神経細胞内でタウという別のゴミの蓄積が始まってしまう。 それが線維化することで細胞を傷つけ、症状を進行させるんだとか。 だから、1つ目のゴミであるアミロイドβは、症状の重篤度に直接関与しているわけではなく、単なる引き金に過ぎない。 やっかいなのは、たくさん蓄積してても認知症を発症しない人がいること。 そしてこの蓄積が、具体的な症状が出始めるはるか前から、それこそ15年も20年も前の4,50歳頃から始まっているということ。 で、ここからが驚きなんだけど、夢の新薬レカネマブ、まさに革命を起こす画期的な薬で救えるのは、軽度の認知症の患者のみだということ。 重症患者はおろか、中等度の症状の人も対象外。 さらにその効果はと言えば、進行を数ヶ月もしくは数年遅らせる程度らしい。 具体的には、診断に用いられる指標の数値を27%改善するというもの。 投与期間が終了すれば、またゴミの蓄積が始まってくる。 そりゃそうで、身体はそのゴミの産生を促しているわけだから、止めようがない。 それでこの新薬がいくらかというと、1年に300万円だと。 もちろん保険が適用されるから自己負担はもっと軽くなるけど、それでもこれにより、約0.9年は健康な生活が送れるらしい。 これまでの認知症の治療薬の開発は山あり谷ありで、困難を極め、出てきた薬はどれも風邪薬程度の対症療法に過ぎなかったことから比べると、確かに画期的ではあるのだけれど、それでもこんなものなのかというのが正直な感想。 レカネマブやその次に控えるドナネマブにしても、ゴミの除去はできるけど、産生そのものを阻止するわけではない。 だから、こんなことを言っている。 症状が進んでからでは手遅れだし、具体的な症状が始まってから投薬を開始するのも遅い、と。 ゴミの蓄積が始まる前に早期発見して、早期治療をしていけば、脳に大きなダメージを負わなくても済むのではないか。 それには簡易な血液検査でゴミの蓄積を予測できなるのではないか。 それこそ定期的な健康診断で、偽陽性みたいな形で血液から異常を炙り出せれば、その後の精密検査で、アルツハイマー病を予防することが可能になると。 言ってみれば、コレストロール値と同様に、無症状の時から治療を開始すればいいのだと。 ただ、繰り返しになるが、それにはアミロイドβが本当にゴミなのかわかってからにしてほしいな。 何らかの有用な役割を担っていることが、後からわかっても後の祭りだから。 それと、どれほど溜まってもへっちゃらな人と、そうでない人との見極めをどうするか。 これは遺伝の問題とも関わってくる。 アルツハイマー病が発症しやすくなる遺伝子は、日本の全人口の15%もの人が持っているらしいから、彼らだけに限定すべきなのかどうか。 もっと厄介な問題は、そんな高額の先進医療を、国民誰もが安価に受けられる体制を実現できるほど国の財政は強靭か。 安価な血液検査により裾野は広がっても、その後の治療となれば、安価では済まなくなる。 さらには仮に高齢者がアルツハイマー病の発症を回避できたとしても、次には超高齢者特有の新たな認知症が待ち受けているという。 まったく別の種類の脳のゴミが蓄積していき、今度はそれを回避するために更なる高額医療が、という風に無限にループしていく。 長生きし過ぎたため生ずる避けられない運命とも見做せないわけではないが、それこそ老化自体を止めてしまわぬ限り、果たしてこれは病気なのか単なる老化に伴う現象の一部なのか判然としなくなってくる。
0投稿日: 2025.03.31
Q
呉勝浩
小学館
あるのは不自由の選択
細胞は叩き起こされ、神経を焦がし、思考が煮える。 こんなワードがポンポン飛び出す本書は、ボリュームも含め、著者のかける力の入れようを雄弁に物語る。 もし「誰かを自分たちの手で世界的なスターにする」なんて話ではなく、血のつながりのない戸籍上だけの奇妙な擬似家族を中心に描いていたら、おそらく直木賞の候補作に選ばれていたのではないか。 もちろん主要登場人物たちを接着しているのは、絆や思い出なんかではなく、Qに対する「鬱陶しいまでの執着」ではあるのだけれど。 世の中には、追いつく距離や速さ、時間を超え、すべてをイコールで結びつける存在があり、それは人生を賭けるに値するほどの価値があると信じる、というのが本書のもう一つのモチーフになっている。 だからこそのキュウなんだろうけど、その描写があまりにも月並みで平凡。 しかも普段からシニカルで諦念しきった言葉を並べ、自分自身に何ら期待せず、他への関心も極端に低いロクやハチに、キュウがどれほど眩い存在かを語らせるものだから白々しく感じちゃう。 それよりは「なかったことにしない?」の一言だけで一切の説明を省き、その返答も「何を?」でも「なぜ?」でもなく「どうやって?」と返すだけのつながりを丹念に描いた方が、読んでいてよっぽど面白いのに。 「当然の顔で無茶を語り、必然のように命じてくる」ロク。 人は簡単に壊れ、人生もあっという間に姿を変えることを痛いほど知り、「できるだけ、息をひそめているしかない」と決意するハチ。 そんな二人が手に染める犯罪は、完全な自由を求めたものではなく、単にどちらの不自由を選ぶかだけの選択に過ぎなかった。 過去の謎のさりげない明かし方といい、独特のテンポある文章もとてもいいのに、本当に残念。 「太陽が嫉妬するくらい輝け」って何だよ。 それを期待すること自体が自己矛盾だろうに。
0投稿日: 2025.03.26
なぜ重力は存在するのか 世界の「解像度」を上げる物理学超入門(マガジンハウス新書)
野村泰紀
マガジンハウス
なぜ重力の解明は難しいのか
「重力」、その理解は物理学の中心テーマであり、かつ最初に定式化された力の一つでありながら、いまだに完全に解明されていない現象。 何が解明の障害になっているのか、それはとりもなおさず、量子力学との折り合いの悪さにあり、将来的には「量子重力理論」が「相対性理論」などと並んで完成を見るはずなのだが、いまだミステリアスなままなのである。 意外に感じられるが、自身の体から天体の運行まで、あらゆる物体に働く重力が重要と見なされるのは、マクロの世界のみで、ミクロの世界では無視できるほど小さな力しか及ぼしていない。 電磁気力など重力以外の力がそれほど大きいのなら、なぜ我々は重力ほど強いと感じられないのかと言ったら、マクロな物体においては、プラスとマイナスが相殺しあっているユニークな力であるためだ。 それに対して、物質に働く重力には引力しかないため、相殺されて打ち消し合わず、足し上げられてしまうため、重要な力と感じられる。 最初に見つかり定式化されたのもこのためだ。 ニュートンが発見した万有引力の法則により、リンゴが木から地面に落ちるのも、月が地球の周囲を回るのも同じ現象であることが解明された。 アインシュタインは相対性理論により、重力を時間と空間の歪みとして説明し、加速度や重力によって時間の進み方が変化することを明らかにした。 標高の高いところほど重力は弱まるため、時間の進み方は遅くなる。 ゆえに地上と人工衛星では時間の進み方が異なるため、GPSは一般相対性理論に基づき時刻のずれを補正している。 ここからミクロな世界の法則を解明する量子力学と融合させ、統一された量子重力理論が速やかに確立されると思われたが、さきほども述べた通り、思わぬ障害のため極めて難航している。 その要因として一つ目に、重力という力の非常に弱い性質が挙げられる。 重力の効果は実験結果の非常に小さな桁にしか現れないため、現在の実験精度では捉えきれないのだ。 もう一つには、理論の適用範囲の違いと、量子効果と重力効果が同時に重要になる場面の少なさが挙げられる。 マクロな状態では、量子力学の効果が平均化されて事実上消えてしまう状況なのに対して、重力の効果は先ほども述べた通り足し合わされて、明確になる。 そのため、量子力学と重力がともに重要になってくる場面に出会うことはほとんどなかった。 しかし今後は、ブラックホールの中心や宇宙の始まりの解明に向けて、ミクロな量子力学の世界とマクロな重力の世界が統一された理論の完成が求められている。 本書は、古典物理学から現代物理学までの歴史を素早く概観できる、手頃な解説書でもある。 なぜ大正時代の人が、英語の「quantum」に「量子」という語を当てたか定かではないが、著者を含め物理学者は、この言葉に「とびとび」というイメージを抱いていること、ゆえに「量子論」とは「とびとび力学」となること。 そしてその量子論は「溶鉱炉の中の温度を正確に知りたい」という1900年らしい、当時の社会的要望を背景して生まれた研究であることが説明される。 「プランク定数」という、従来の物理学では連続的に変化する物理量を扱ってきた学問から、「不連続に変化する、つまりとびとびの値しか取ることができない」現象を扱う、全く異なる新しい物理学の誕生だった。 温度という概念も、実際には個々の原子や分子の動きの統計的な結果にすぎず、全体の平均的な活動量を表しているだけなのである。 もしすべての原子や分子の動きを追えるのであれば、温度という概念などもはや不要となる。 しかし、膨大な数の粒子の挙動を全て計算するのはどんな高性能のコンピュータでも困難であるため、それを大まかにでも理解する必要にせまられ統計力学が生まれた。 統計力学的な考え方からは、いろいろ面白い示唆を与えてくれる。 例えば、私たちが通常「時間が進んでいる」と呼んでいるものは、マクロな世界に統計的な表れにすぎず、エントロピーが増大する方向への進行を「時間が進んでいる」と感じているだけなのではないか、つまるところ錯覚ではないか、「時間の一方向性」なんてそもそも存在していないのではないかなど、触りだけの紹介に留まるがとても面白いと感じた。
0投稿日: 2025.03.18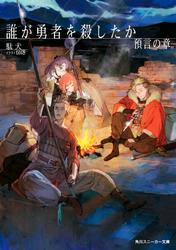
誰が勇者を殺したか 預言の章【電子特別版】
駄犬,toi8
角川スニーカー文庫
前作の面白さが消し飛ぶ、フツーの後日譚
街の噂で評判も悪く、軽薄で金のためなら何でもやるレナード。 そんな冒険者を演じる意図は何か。 彼の目的に賛同し、集う面々も三十路を過ぎた、いわば遅咲きパーティ。 戦場に背を向けたことと自分だけ生き残ることの是非に揺れ、弱さと強さの境界線でもがく勇者未満の存在。 だが、勇者は魔王を倒すだけでいいのか、現実に人々を救うため戦っているのは、勇者未満の自分たちではないのか。 また今回は、預言者の罪にも話が及び、影に隠れて自分では何もせず、ただ次の勇者を示し導くだけの存在を、我々は本当に必要としているのかにも焦点が当たる。 ただ全体的にはしょうもなく、全く面白くなかった。 普段ラノベを読まない人間も夢中にさせた前作の面白さは、人間の側から見ると絶対的で、不可知で不可侵な御宣託をなす預言者が、実は失敗に次ぐ失敗の、やり直しの末の勇者選びを宿命として背負っているという、お馴染みの構図の換骨堕胎にあったのであり、それに勇者の入れ替わりミステリーを絡めて、インタビュー形式で話が展開したところに面白さがあったのであって、今回の後日談は何ら見るべきところのない普通の話に終始する。 勇者の器ではないとはっきりしているのに、レナードに付き纏い、あっちに行くなとか指図し纏わりつく預言者。 わざとやってるのか、後から効いて来るのかと気を揉ませるが、レナード自身から「俺に構ってないで、真の勇者を探しに行けよ」とウザがられてしまう。
0投稿日: 2025.03.13
「怠惰」なんて存在しない 終わりなき生産性競争から抜け出すための幸福論
デヴォンプライス,佐々木寛子
ディスカヴァー・トゥエンティワン
怠惰や先延ばしに共感すべき理由
これは片野秀樹の『休養学』に通ずるところだが、著者は人が怠惰になったり、やる気が起きないのは、自分を守るためのサインだと考えている。 身体や脳が切実に休息を必要としているために発せられたシグナルだとすれば、これ以上いくら頑張ってみても、集中力が続かないし生産性も落ちる一方だろう。 じゃあ、とすぐに休めるはずもない。 では、どうするかと言うと、自分の中で生産性への期待値を、しばらくの間、ぐっと下げてみてはどうかと著者は提案する。 いきなりブレーキを踏むのではなく、アクセルを弱め減速してみる。 いたずらにプレッシャーやストレスを溜め込むのではなく、のんびりゆったりと思考と感情のエネルギーの充電を図っていく。 自分もそうなのだが、先延ばし癖のある人は、側から見ると怠け者と映る。 しかしそうした人は決してやる気がないわけではなく、むしろ、やらなくちゃと人一倍思い詰めている。 完璧主義で、非現実的なほど高いハードルを自らに課してしまったがために、よりナーバスになり失敗を怖がっている。 その不安を宥めようと、目先を変え、気を紛らわせようと他のことを始め、ずるずると先送りしてしまうのだ。 先延ばしで動けなくなる人はたいていこのサイクルに陥っている。 この悪循環を断ち切る方法も、まずは内なるハードルを思いっきり下げてみることだ。 「大きなタスクを小さな作業に分割し、短期の締切を設定するサポートと励ましが得られればうまくいく。『10ページのレポートを書き上げる』という課題には足がすくむが、『1日2段落を書く』ならやれないこともないだろう。不安にならないよう自身をケアしつつ、このように進めれば、先延ばし癖のある人でも、自己実現と信頼性を高められ、自分の能力に自信がつくはずだ」 無気力、やる気のなさが知らせるサインには、社会的評価に対する反発の意味合いもある。 有色人種や貧困層の投票率の低さや、職場環境の劣悪な中での従業員の能率の低さも、自分たちの期待や意見が反映されないとわかれば、頑張る意味も見出せず、自分の出力レベルを下げるのは、きわめて合理的な行動だと言える。 これは怠惰のウソにまつわるパラドックスでもあるのだが、誰よりも長時間働き、皆の要求に応え続けてきた人たちほど、自分はやる気が足りないのではないかと不安に駆られている。 本当はダメ人間だと思い込んでしまっているが故に、身体の声を無視し、休息も取らず頑張らなければ、利己的でやる気のない本性を克服できないと信じ込んでいる。 華やかなショービジネス界においても、裏では限られたチャンスとSNSでの注目を巡って、熾烈な多忙さの競い合いが行われている。 「SNSで他人の活動や業績を常に知らされるので、自分は落ちこぼれたダメ人間だと感じてしまう。奇妙なパラドックスだが、自分にとってちょうどいい以上のことをやろうとすると、かえって何もできていない気になるものだ。”やることリスト”に自分ができる以上のタスクを並べていれば、いつになっても達成感は得られない」 もっと自分を追い込め、限界など認めるな、怠惰は悪だと考える慣習からは想像つかないかもしれないが、怠惰は創造性を高める。 「クリエイティビティや発想力は、頑張れば出てくるものではない。何も考えない時間が必要なのだ。往々にして、良いアイデアは考えていないときにやってくる。シャワー中や散歩中などに、どこからともなくアイデアが降ってきたように感じるが、実は休んでいる間に、私たちの脳は無意識下にアイデアを練っているのだ」 私たちは情報過多の時代に生きている。 しかし情報過多は、時に絶望を生む。 恐ろしい情報や悲観的なニュースは、自分たちで何とかやれるという感覚を失わせるために、諦念や無関心を生む。 いま人びとは極端な二元的思考を強いられている。状況にかかわらずひたすら頑張るか、そうでなければ絶望的に怠惰かの二択だ。 これを解決するには、より多くを知ろうとするより、むしろ一歩下がって、今より少ない情報量をより意味のある方法で摂取する必要がある。 その他に著者は、トランスジェンダーとしての自らの体験から、社会から求められたことに失敗すること、期待に背くことが、すべてを変えるのだと訴える。 失敗することで私たちは、他者のために価値を生み出すというプレッシャーに抵抗し、自分自身が本当に望む目標や優先事項を選べるようになるためだ。
0投稿日: 2025.03.12
正体
染井為人
光文社文庫
どうストーリーを語るかが重要なのだと悟らせる一冊
誰かの冤罪を確信し、釈放を求める運動の支援に回るというのが、いかに容易ならざることかよくわかった気がする。 鏑木慶一の無罪を求めて動いた野々村和也や渡辺淳二、近野節枝、安藤沙耶香、酒井舞、四方田保も、元は赤の他人同士。 逃亡中にたまたま鏑木とそれぞれ接点を持ったことではじめて芽生える疑念、そして脱獄した凶悪犯というイメージの齟齬。 それまでは世間の人と同じように憎み、一刻も早い再逮捕を望んでいたのに。 ただ鏑木本人から直接、事件の詳細を語られ、自身が無罪であると訴えられたのは酒井舞のみ。 その酒井舞も、事件当時者である井尾由子から潔白だと知らされるまでは、態度を保留していた。 鏑木と接し、彼が他人に対して見せる細やかな心使いや世話の数々を見てきて、実際に恋心を募らせていても、判断がつかなかった。 おそらく自分もそうだろうなと思う。 人となりに触れたから、優しく抱きしめられたから、励ましの言葉をかけられたからなどで、冤罪を確信できるだろうか。 地方旅館の住み込みバイトとして働いていた渡辺以外のスタッフが見せる態度の豹変ぶりを見てもそうなのだが、自分たちも騙されていた、ある種の被害者だという感情に陥るのではなかろうか。 そしてこうも思う、同じ潔白でも、鏑木慶一と正反対の人物が脱獄して、同じ行動を起こしていたらどうだろう、と。 鏑木慶一のように要領も良くなく、愛想は悪く、容姿も優れず、立ち寄り先でドジばかり踏んで、周りに迷惑をかけ倒して、でも自身の無罪を求めて同じ行動を取っていたら…。 あるいは逃亡中に本当に人を傷つけたりした場合は? だけど子供を含む一家惨殺という容疑は全くの濡れ衣だとしたら? 物語も結末もまるで違ったものになっただろう。 文庫版の巻末は文芸評論家による解説が通り相場だが、本書はわざわざ著者本人のあとがきが付す。 そこで語られている結末に対する反響や著者の思いについて読むにつけ、何か危ういものを感じた。
0投稿日: 2025.03.11
消された王権 尾張氏の正体
関裕二
PHP新書
草薙剣を祀る尾張氏とは何者か
名古屋市の熱田神宮と言ったらお馴染みのパワースポット。 今でこそ東海地方を代表する大神社だが、かつての熱田社の社格は想像以上に低かったらしい。 しかしここには何といっても草薙剣がある。 曰く、ヤマトタケルが尾張氏のもとに置いていき、遺品として祀られたものだと伝わっている。 ただ実は七世紀に、草薙剣は一度宮中に戻されている。 ところが時の天皇に病をもたらし、あまりの霊力に一緒に暮らせないと、再度熱田社に戻されてしまったのだ。 王の正統性を裏付けるはずの神宝が、なぜ宮中で大切に祀られず、あまつさえ天皇を祟り苦しめたのか。 そしてなぜ天皇家は、熱田神宮に預けたままにしているのか。 なぜ尾張氏は、恐れられ、遠ざけられた神器を、熱田神宮の御神体として守ってきたのだろうか。 あちこちの古文書の記述の微妙な齟齬や引っ掛かりから、思考を細かくして焦点を絞った先に見えてくるもの。 点と点で存在していた謎めいた豪族の影が、推理後には古代史の構図の大胆な見直しにつながっていく。 これもある種の歴史ミステリー作品として割り切って愉しめればいいが、中には腹を立てる人もいるかも。 十中八九、学会内に著者の主張のすべてを真に受ける人はいないだろう。 「ここは嘘でデタラメ」とした資料の別の箇所から論拠の裏付けとして活用されたり、点と点とを都合よく結びつけ、あまりにも融通無碍に論が展開される。 著者に言わせれば、我々が聖地として崇めている「伊勢内宮は、持統天皇と藤原不比等が創作した”張りぼてのアマテラス”を祀っている」となるし、武内宿禰は住吉大神であると同時にスサノヲで、彼が応神天皇の父親となり、蘇我氏の系譜につながる人物ということになる。 政敵・蘇我氏を大悪人に仕立て上げるために、『日本書紀』編纂の際、藤原不比等によって徹底的に尾張氏の痕跡を消し去られた。 しかし尾張氏は、後から中央進出を果たした新参者の弱小豪族ではなく、そもそもの最初からヤマトに乗り込んでいた東海勢力の一部であり、ヤマト建国にも深く関わった大豪族だった。 黎明期に活躍した王家の「忠臣」、いやそれだけでなく「裏の王家」とも言える存在だったのだ。 時の権力者が正史を自分の思うままに手を加えるというのはよくある話だし、異論はなかろう。 ただ『古事記』が、勝者の立場から書かれた『日本書紀』に対抗する形で、後から敗者の敵対勢力が編纂したものだというのはどうだろう。 前半は考古学的知見と絡めて説得力があった。 東海系の文化が発展し各地に伝播していった時期は、巨大地震や寒冷化を伴う気候変動によって、地域の再編が起こり、新たなリーダーが誕生する時期と重なっていたこと。 前方後円墳とは違う、前も後ろも四角形の前方後方墳が、この地域を中心に作られれていたこと、などだ。 そして、出雲と対抗していた但馬・丹後の日本海地域も台頭し、近江や東海地域の勢力が手を組むことで、ヤマトの主導権を確立していったのだということなら、消し去られたのは「大丹後」も同様ではないか。 熱田神宮への記述は中盤以降からは全く触れられず、ひたすら氏の私見の大披露ということに。 それはそれで一粒で二度美味しいとなって、近著の作品の要約がまとめて詰め込まれているため、全体像が一望のもとに見渡せる。 それでもさすがに詰め込みすぎな気がしないでもないが。 尾張氏の正体を探るなら、ヤマト政体の正体も合わせて解明されねばならないというのもわからなくはないが、最初の謎の答え合わせが不十分に終わった気がしてならない。 尾張氏側が草薙剣をどう位置つげて、守り祀ってきたのかくらいは記すべきだったのではないか。
0投稿日: 2025.03.10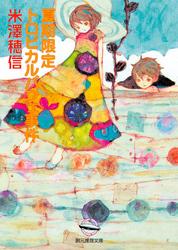
夏期限定トロピカルパフェ事件
米澤穂信
創元推理文庫
狐と狼の知恵比べ
前作でかぶっていた小市民の皮は捨て去られ、露わになったキツネとオオカミによる知恵比べ。 結局、小市民を目指してますという宣言は何だったのか? 嘘、偽善、どうせ小市民になりきるなんて器的に無理というある種の傲慢さ? 前作で語られた取り決めの中では、お互いの本性の発露を防ぐ防波堤として緩い依存関係が成立していた。 本作で片側から宣言される目的は、ひたすら功利でお互いを便利に使い合うための、外面上のカモフラージュにすぎなかったと。 前作より面白いと思ったが、同時にこの小説自体が内に相当な狼を隠しているなとも感じた。 ほのぼのとした日常系の予定調和の物語と思わせてのこれだもの。 学生生活はある種の小世界で、校外では全くの別の顔を持つ、断絶した世界。 その小世界の中に新たな内と外を作り、「小佐内スイーツセレクション・夏」という外装に包ませる。 読んでいて心地よく感じる箇所はいくつかあって、堂島健吾が小鳩くんを自身の泣き言を聞かせるために激辛タンメン屋に連れ出すシーン。 なぜわざわざ自分を聞き役に指名したのかとの小鳩の問いに、周りの友はいい奴すぎて励まされて終わりなるところを、お前なら同情もせず淡々と聞き流してくれるだろうと思ったからと平然と口にする健吾。「あんまりな言い草だ」と心でつぶやきつつ、怒りもわかず、妙に納得してしまう脱力さ加減が何ともおかしい。 と同時に、こんな文章も。 「健吾は正義漢なので余計なことに手を出すけれど、迷うより先に手が出る単純な積極性は見ていてそれなりに面白いのだ。そんな健吾が偽善なんてタームを持ち出して自分を縛っちゃいけない。その言葉は、もっと冷笑的なタイプの人間が口にしてこそ面白いのに。どうやら健吾の泣き言は終わったらしい。 そしてタンメン激辛大盛もできあがった。 白い丼が二つ、ぼくたちの前に置かれる。 『はいよ、タンメン激辛大盛お待ち!』」
0投稿日: 2025.03.07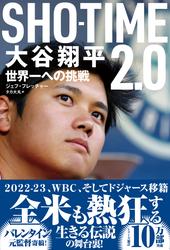
SHOーTIME2.0 大谷翔平 世界一への挑戦
ジェフ・フレッチャー,タカ大丸
徳間書店
あの最も忘れがたい一日の顛末をめぐる物語
例のトロント行きフライトをめぐる協奏曲は、誤情報やデマがSNSによっていかに拡散され、メディアをも巻き込む情報錯綜を引き起こし、それがファンの心理状態にいかに多大な影響を与えたかという、情報社会論や集団心理学の研究テーマになってもおかしくないほどの忘れがたいトピックだった。 そもそもの発端は、コロナウイルスに感染して眠れなくなったカナダ人政治記者による深夜のツイートから始まった。 フライトトラッキングが趣味で、たまたまアナハイムに近い空港から1機のプライベートジェットがトロントに向かって飛んでいることを知る。 ブルージェイズファンの彼がSNSにのせたフライト情報は一気に広まり、数時間のうちに100万人以上の人に拡散される。 同時並行で、トロントのスポーツラジオ局に寄せられた、菊池雄星がトロントにある寿司店を借り切ったとい噂も一人歩きする。 司会者はラジオの中でこの噂を根拠薄弱と指摘していたのだが、それをたまたま聞いていたカナダ人オペラ歌手がSNSに投稿し一気に広まることに。 そしてトドメをさしたのが、MLBネットワークのモロシ記者による「オオタニがいまトロントに向かっている」とのツイートだが、すべてが合わさって裏付けのない誤情報が、相互に確証を高め合う効果をもたらし信憑性を高めるにいたる。 こうしてID番号N616RHの3時間43分にわたるフライトトラッカーを、全世界の野球ファンが固唾を飲んで見守ることになったのだ。 あの日を「1日で怒り狂い、夢中になり、奇妙な展開になり、爆笑もので、かつ悲しさと感動を一気に味わった特別な日」と評したのは、FOXスポーツのジェイク・ミンツ記者だった。 この狂乱劇には噂を育む下地があった。 「大谷がブルージェイズ関係者と接触しているらしいぞ」と「最終決断が近いらしいぞ」というインサイド情報が、これらは事実であったのだが、ファンの間に点と点を結びつける状況証拠として作用していた。 もう一つの要因としては、大谷というミステリアスな存在も騒動に拍車をかける推進剤として作用した。 いっさいの交渉過程を秘密厳守とし、必要なこと以外は何も語らない頑なな姿勢。 単独の取材には応じず、すべて共同会見で、型通りのコメントしか発しない大谷。 こうした沈黙を貫くスタイルは、2023年シーズン終了前のケガの責任の所在をめぐる論争も引き起こす。 ファンは、大谷が痙攣や疲労に襲われていた段階で、何らかの対処をすべきだっのではないかとエンゼルスを批判した。 GMは、本人が試合に出たいと言い、痛みも報告してこなかったと反論する。 ファンはそれでも、何らかの疑わしい症状が出てるんだから、MRIを早めに受けさせていたら怪我は回避できたのではないかと食い下がる。 しかし専門家に言わせれば、仮にMRIを受けさせても、メジャーリーグの投手の90%の肘には問題があり、正常な靱帯から程遠く、しかも違和感を訴えていない段階で登板をやめさせることなんてできないと語っている。 こうしたことがあり、例のロッカー空っぽの騒動があったときも、大谷はひょっとしたらエンゼルスに怒りを溜め込んでいたのではないか、チームを見捨てたのではないかなど、いろいろな憶測を呼ぶことにつながった。 著者のように長年取材してきた番記者でさえ、空っぽのロッカーを見つめ狼狽え、記者団で一致して報道を自粛しようという紳士協定なんか結んでいる。 それくらい大谷の本心を掴めずにいた著者だが、エンゼルス残留の可能性は結構高いのではないかと考えていた。 なぜなら、エンゼルスがいかに大谷を特別扱いし、試合の起用法からインタビューの頻度に至るまで、自由と権限を与えているかを知っていたからだ。 このような干渉されない放任に近い環境を大谷も快適だと感じているはずだと信じていた。
0投稿日: 2025.03.06
死んだ山田と教室
金子玲介
講談社
声を出すのを忘れ、音を拾いなぞる日々
声だけ生き返り、スピーカーになって復活した山田。 二年E組の教室は、クラスの人気者の突如の帰還に盛り上がる。 山田は挨拶がわりに最強の席替えの腹案を披露し、更なる羨望を集める。 相性や関係性だけでなく、視力や聴覚など細かな観察力に裏打ちされた分析だったためだ。 先生のモノマネが上手い人もクラスの人気者になれたけど、教室内のことを熟知した眼を持つことも必須の条件だった。 しかしやがて、クラスメイトとの間に微妙な齟齬が生じ始める。 いじめられっ子から人気者になった経緯や、実は高校デビューだったことなどの秘密も明らかに。 山田は山田で、2Bの仲間とずっとバカやっていたいという思いの一方で、消えてしまいたいと願う気持ちを募らせる。 周りも、思い出の中のアイツで留めておきたいと考える者や、「いつまでも構っているから成仏できないんだ」とか、「アイツは完全に消えるタイミングを失った」と腐す者まで現れ始める。 「だって山田くんの時間、ずっと止まってるんだもん。こっちはもう大人になってるのに、どんな言葉掛けたらいいかわかんないよ」 卒業し、社会人になっていく仲間たちとは裏腹に、一人だけ大人になれない焦燥と孤独を抱える山田。 「自分の人生は空っぽだ」 教室のスピーカーに憑依して声を取り戻し、バカ話を言い合っていた時は過ぎ去り、誰もいない教室で、周囲の微かな音に耳をそば立て、天気や四季を感じ取るだけの「音を拾う屍としての日々」が続くことに。 小説全体のノリはお笑いのシチュエーションコントを想起させるし、「カッピカピでパッサパサでカッサカサ」といったジャルジャルのネタを彷彿させるワードもある。 クライマックスなんかまんま、M-1の最終審査で披露されるラストの掛け合いにも似ていて、妙に感慨深いものを感じた。
0投稿日: 2025.03.02
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
