
人間はどこまで家畜か 現代人の精神構造
熊代亨
ハヤカワ新書
家畜になれない者たちの今後
昭和、平成、令和と学校における生徒の問題行動は質的に変化している。 学校環境の変化を如実に表わす2つの矛盾する統計結果からそれがわかる。 一つは文科省が出した小学生の暴力件数・いじめの発生件数の調査結果で、平成25年以降の急増が示されている。 もう一つは警察庁の犯罪白書で示される校内暴力で検挙・補導された人数の統計データで、昭和から平成、令和と減少を続けている事がグラブでわかる。 この大きく異なる調査から著者は、教室がかつてなく穏やかに変わってきている一方で、暴力や逸脱に対してより敏感になっていることを指摘する。 かつては教師に食ってかかり、激しく物品を損壊するなど激しい荒れだったものが、注意力が散漫になって授業中に勝手に動き回り、SNSで友だちの悪口が交わされる静かな荒れへ、学級崩壊の質が変化している。 おとなしく従順な子が増えたと見える一方で、表面上では良い子を演じられる生徒の割合が増えたとも言え、結果として落ち着きのない、昔ながらの問題児はより目立ちやすく、異質化しやすくなる。 いじめの定義も、国の方針により、より広く定義されるようになった一面もあるが、より許しがたいものという認識が共有化される一方で、それだけ隠蔽されやすく陰湿化しやすいものに変わった。 著者が強調しているのは、過去と現代で子供に求められている必須の能力が異なってきていて、「より素早く、より厳格に“文化的な自己家畜化〟に沿った行動」を身に付けなければならなくなったと語る。 それができない子どもは排除され、支援や治療の対象となっている。 発達障害を示すADHDも、最初は重度の男の子の患者に限定して治療の対象になっていたのが、治療薬の誕生によって対象範囲は拡大され、それまでグレーだった子供たちも積極的に診断されるようになっている。 注意欠如や多動性障害の子供の増加が話題に上っていた時、こうした医療や製薬会社の思惑や、圧倒的なマジョリティーとなりつつある真・家畜人だらけの教室を想像したことがあっただろうか。 文化や環境から求められる社会適応に直面しているのは子供たちばかりではない。 大人も社会人として、負の感情がマネジメントされコンプライアンスが遵守されたホワイトな職場環境を創出せねばならない。 アンガーマネジメントは言うに及ばず、感情は常に安定していなければならいし、自己抑制も強く働かせた、穏やかで物わかりのよい人間でなければいけない。 勇敢で猛々しく、時に衝動的な感情表出や行動は、かつては美徳とされた時代もあったがいまはそうではない。 侮辱に耐え、冷静沈着、合理的・効率的な行動や抑制した情感の持ち主は、かつては臆病者や卑怯者、落伍者と見なされ、それこそ中世であれば修道院行きであったがいまはそうではない。 すべては逆転した。 HPA系に由来した衝動性は矯正の対象となり、セロトニン分泌量の多い人間は、協力したり教えたりできる必須の人材として持ち上げられる。 ようは「家畜」になれない者たちに待っているのは、肩身の狭い現実なのである。 他人を不快にさせず、安全であることを証明しなければならない世の中は、そうしたくてもできない精神疾患を持つ人々にとっては堪らない時代である。 IoT化が進み生活の隅々までオンライン化した未来には、発達障害と同じ足切り対象の拡大が待っている。 ゲームやネットに没頭できない者、バーチャル空間に馴染めない者、スマートグラスやVR端末に酔う者、監視カメラだらけに違和感を覚える者など、発達障害と似た形で隔離され、治療や支援の対象となるかもしれない。
0投稿日: 2024.12.30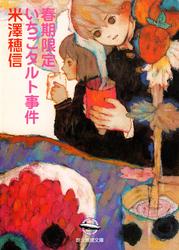
春期限定いちごタルト事件
米澤穂信
創元推理文庫
謎解きではなく雰囲気を愉しむためのもの
泣き寝入り上等、理不尽は受け流し、顔でも心でも愛想笑いを浮かべる"小市民の星"を目指すことを誓い合った高校生二人の物語。 無芸で結構、現状維持最優先、心の中で育んでいるのは"諦念と儀礼的無関心"。 健全なのかよと思いつつ、殺伐とした世の中だからこそ求められるものなのかも。 "小市民たれ"以外にも彼ら二人の取り決めがあって、どちらかが逃げるときは、もう一方が楯になったり、お互いを言い訳に使うなどだ。 こうした互恵関係の約束は微笑ましいほどゆるくピースフル。 逃げ道は用意するが、攻めには用いない。 防御優先でただひたすら、お互いにとっての穏やかな時間創出を願ってのもの。 もともと性向としてお互い、小市民的性質があったというわけでもないようだ。 気づいたら背後に立ち、忍者張りに隠れるのが得意な小佐内さんは、恐ろしいほど執念深く、復讐心も人一倍強い。 一方の小鳩君は、とにかく解きたがりな性格で、小賢しさ満点で犯した過去の失敗に懲りて、もう探偵役をやらないと誓っている。 そんな二人が織りなす推理小説なので、かなり風変わりな展開を見せる。 小佐内さんは私怨から心の底から犯人を知りたいけど禁を破ることになるので言い出せない。 そんな小佐内さんの思いを汲んで小鳩君は、事件を解き明かしせっかく真相を突きとめても、約束違反になるから言い出せない。 なんとももどかしい話だが、ただ二人にできるのは、小佐内さんはひたすらケーキをやけ食いし、小鳩君はそんな彼女の愚痴に付き合ってやることだけなのである。 面白いか、これ? うーむ、たしかに堂島健吾の斜め上をいくココアの作り方にはのけぞったが、そもそも小市民シリーズに関心ないなら、米澤ファンでもスルーでいいかもしれないな。
0投稿日: 2024.12.26
多元宇宙(マルチバース)論集中講義
野村泰紀
扶桑社BOOKS新書
奇跡を説明するにはそれしかない
宇宙の話でここまでわかりやすい本を読んだのは初めてかも。 前にもくだけた語り口の類書は読んだことがあったけど、「しょうがないから」とか、「ってことにしとくか」っていうフレーズを目にすると、いくら何でもと思いつつも、敷居が思いっきり下がるので取っつきやすい。 それに記述の仕方にも工夫が凝らされていて、あえて宇宙のスケール感を出すために、数字の0がやたらと並ぶ。 確かに「秒」や「m」なんていう単位は、人間のスケールを基準としたもので、宇宙の単位は人間なんかのものより、かけ離れていて当然なのだ。 だけど10の30乗とかだといまいちスマートすぎる。 0.000000000000000000001なんて方が、どれだけ「かけ離れた」世界なのかがより実感できる。 そもそも量子力学自体が感覚的に理解しづらい分野だともおっしゃってくださってる。 普通の人にとってはまず理解不能だとも。 実際、ほとんどの物理学者だって「感覚的に」理解しているかと言えば、全然そんなことないんだって。 単に数式などから導いた予測が、驚異的な精度で観測結果と一致する様子をみて、「理解した」と言っているに過ぎないのだと。 研究者でもない普通の人からすればそういう機会もないんだから、「電子は確率的に同時にいろんなところにいられる」なんて記述に出会っても、諦めてそういうものかと割り切るしかないということなのね。 それでも今回のマルチバース論は、成り立ちがよくわかる。 要するに、誕生の奇跡を説明するにはそれしかないってことなんだね。 我々が住んでいる宇宙しか存在しないなんて仮定したら、ダーツの矢を一発で、的のど真ん中に刺せたことになってしまう。 そんなことできるのは神しかいない。 だけど科学者なら神ではなく別の説明ができる。 1本しかないと思われた矢が実は無数にあったのです、と。 ただこれだと多元宇宙論は科学者の苦し紛れにひねり出された根拠の薄い説みたいにみえるが、ぜんぜん違う。 むしろ次々と謎を解いていった先に、トンデモ説と思われていたマルチバース論が「なくはないか」と支持する学者が増えてきたといったのが実情に近い。 観測結果から「宇宙は加速膨張している」とわかったのがそもそもの出発点。 だけどその理由がわからない。 それまで宇宙の真空エネルギーはゼロだと思われていた。 というよりそうしたかった。 その方が既存の説とも帳尻が合うから。 だけどそれだと加速膨張している事実と整合しない。 宇宙には物質以外にも何かあるのでは?、真空エネルギーによって空間を膨らませてるんじゃ?、だけど我々は吹き飛ばされも潰されもせず宇宙に構造が残っているのはなぜ?、ならいろんな種類の宇宙があることにすれば、その中でたまたま真空のエネルギーがものすごく小さいのがあってもおかしくないから、それで『われわれの宇宙』ができたのでは、と。 真空のエネルギーが小さいこと自体に、必然性もカラクリもない。 小さい値の真空だけしか観測されないのは、そもそもそこにしか人間がいないから。 大きなのは人間もろとも吹っ飛ばされますもん。 この論理展開でいくと、確かに神を持ち出す必要はない。 “宇宙が我々にとって、あまりにもよくできすぎているのは、なぜ?”、”地球が、知的生命体に都合のいいように太陽からの距離とかサイズとかチューニングされているのは、なぜ?”。 「なぜ」そうなったのかを考えたって答えなんか出ない。 たまたまそうなったところに我々がいるというだけで、そうなったこと自体にメカニズムも理由もないんだよ、と。 「『我々の宇宙』がすべて」という前提に立っているとこの発想は起きない。 「我々が宇宙だと思っていたものが、宇宙のすべてではなかった」、「我々の知っている宇宙以外にもいろいろな種類の宇宙が存在するのでは」とつながっていったんだね。 無数と言ったけど、「我々の宇宙」以外にどれくらいの数の宇宙が想定されているかというと、10の500乗ものバリエーションがあるのだそう。 ただその多くは真空エネルギー密度の違いから、宇宙らしい構造を留める前に潰れてなくなっているだろうから、勘定に入れようがないのだけど。 そういう意味で種類なのであって、理論上はあり得ると言うにとどまってる。 だけどこんだけあればきっと知的生命が住む宇宙もきっとあるはず。
0投稿日: 2024.12.25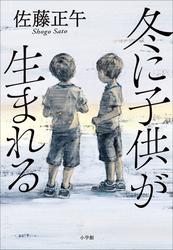
冬に子供が生まれる
佐藤正午
小学館
記憶と身体の齟齬がテーマ
読者に相応の読解力が求められる本。 あと、忍耐力も。 例えば、高校の同窓生との会話。 彼は共通の友人の渾名を間違って記憶しているが、どうせ無駄だと訂正もせず会話が進行する。 読者はこの会話中の誤解を脳内で変換しながら咀嚼しなければならない。 さらに語り手の問題。 この小説中に唯一「私」と出てくるし、語り手は湊先生なのだろうと見当つけて読んでみるがどうもしっくり来ない。 例えば、自身が脳梗塞に襲われる場面では、自分のことを「先生」と呼び、奥さんは「妻」とする。 マルユウが実家に戻る場面では、「丸田君」と「父」という具合に。 一人称とも三人称とも読める曖昧な視点は意図したものなのだろうが、果たしてどのような計算に基づくものなのか。 湊先生が脳梗塞の前兆現象を感じる場面の文章が素晴らしい。 そのあと、マルセイが駆けつけ不思議な力で先生を癒し、思念の伝達のみで会話を続ける場面も。 周りでは微かにパクチーの匂いのする霧が漂い、手のひらの温もりが瞼から喉、肩へと移っていく。 意識は混濁状態にも関わらず、徐々に不安が減じ、外の雨音まで聞こえるようになる。 痺れから声にもならない状態で、思念のみの会話をどう成立させ、文章にするのか。 相変わらず凄いなと感心したし、この場面だけでも小説の元をとったような気持ちになる。 この場面では、本書のキーとなる重要な事実も明かされる。 考えてみるとずいぶんと風変わりな物語だ。 読者は何となく過去の天神山の出来事の謎を解くのは、東京から来た雑誌記者なのだろうと思う。 だけど実際には二人の先生である。 それに謎も最終的に明らかにはならない。 天神山での事故の際、三人は何を経験したのか? マルユウに痣の転移は起こったのか? マルユウと佐渡君にも特殊能力があるのか? マルセイはなぜあんな死に方をしたのか? N先生はなぜ行方不明になったのか? 杉森のお腹にいる赤ちゃんの父親は誰なのか? これらはすべては曖昧なまま終わらせているので、あとは読者の想像に委ねることに。 ただ本書の主題は、入れ替わり体験が中心ではないことは確か。 本人も認めている通り、その入れ替わりは部分的であり、全般的なものではない。 「自分がしたはずのことに自分で実感が持てないとか、自分がした覚えのないことの記憶が残っているとか」や、「全部が全部じゃなくても、記憶の半分くらいが混ざり合ってしまった」とあるように、ある人の記憶の中に、自分じゃない人間のしたことや望みが混じってしまった時、人はどのようになるのかがテーマである。 これは、記憶の一貫性や、記憶と身体の齟齬の問題に関わり、別に宇宙船に出会わなくても起こりうる普遍的なテーマでもある。 おばあさんが孫に囲まれ、それぞれに愛情を感じつつ、自分の親族だという実感を伴わない時、あるいは自分の記憶の中に誰か他人の思い出が混じっているように感じられる時、もっと平易に言い換えれば、自分が自身の人生を生きている実感を感じられない時の様々な情景を映し出した作品なのではないか。 各章の冒頭は著者らしい独特のリズムがある。 「その年の七月、七月の雨の夜、」、 「八月、八月初旬、八月初旬の炎天下の午後、」、 「九月、九月に入ったある月曜の朝、」というふうに。 最後の杉森先生がマルユウに諭す"夫婦の心得"もいいな。 大事な話をすることが"夫婦の大事"ではない。 「いちばん大事なのは、小さくて平凡な話をすること。何年も何十年も、倦まずに小さな話を続けること。だから覚悟しなさい。きみが仮にジェダイのフォースパワーの使い手だとしても、そんなものは夫婦の間では何の頼りにもならない」
0投稿日: 2024.12.18
暗殺
柴田哲孝
幻冬舎単行本
赤報隊事件との類似性
司法解剖結果の2つの不可解な謎は、実際の銃撃事件発生時から一部で話題になっていた。 一つは貫通した跡がないのに見つからない"消えた弾丸"の行方と、もう一つは下から上ではなく上から下、つまり首から心臓に向かって撃たれた"射出角度"の問題である。 本書はこの2つの状況証拠から、単独犯行ではなく第二の狙撃手の存在を導き、暗殺事件の背後の巨大な謀略を描き出す。 関係者の氏名など名前は全て変え、完全なフィクションの体裁になっているが、「そんなバカな」という飛躍した展開を辿ることから、荒唐無稽と鼻で笑ってしまいそうになる。 ただ、数十年後には大真面目に、今度はノンフィクションの態で「これが真相」と謳った本が出てきそうな気がするのも事実。 "(体内で)消えた弾丸"については、警察発表の説明でも特に矛盾は感じないが、発射された数十の散弾の行き先の方が気にかかる。 周囲のスタッフや聴衆に一発も当たらなかったことも不可解なら、どこに行ったかわからないというのももっと不可解。 本書で関連性が指摘されている赤報隊事件でも、撃たれた記者の体内から数百の散弾が見つかっている。 いちばん奇妙なのは、首から心臓に向かった弾道の"射角"問題。 175cmの身長の元首相が40cmの台に上がって演説している際の銃撃である。 はるかに低い位置から手製の銃を腰だめに構えて近づく犯人。 元首相までの角度には壁となるように5人の選挙スタッフが並んでいる。 確かにあり得ない弾道でないと、間に立つ人々を避けて、頸部から銃弾は入っていかないだろう。 と、ここまでは何とかつきあえるのだが、ここから著者はぶっ飛びの珍説を展開する。 本書の参考文献にもなっている樋田毅の『記者襲撃 赤報隊事件30年目の真実』でも指摘されているように未解決であることが社会に与えた不安は大きかった。 「われわれにとって、捕まらないまま逃げおおせた赤報隊はまさに好都合だ。記事や言動次第では、赤報隊が再び動き出すぞ、という無言の圧力をかけ、今後も社会の重しの役割を果たしていくのだ」 これは取材先の右翼が語った言葉だが、本書もこういった陰謀論を流布する事で、見えない「社会の重し」につながっていないか、よくよく注意した方がいいと思う。
0投稿日: 2024.12.10
宇宙になぜ我々が存在するのか
村山斉
ブルーバックス
すべてはニュートリノのおかげ
この宇宙は発生直後に消滅しているはずだった、途方もないほどの膨大なエネルギー放出を伴って。 物質は生成すると同時に同じ数だけ反物質も生まれ、それらがベアとなって対消滅を起こすからだ。 なのになぜか我々は生き残っている。 なぜか? その鍵はペアの内実にあった。 完全な対称であれば粒子同士で消滅するはず。 トランプの神経衰弱のように場から退場となる。 しかし三世代のクォークがあることで、ペアに違いを作り出すことになり、対称性に乱れが生じ、この宇宙に物質が残ったのである。 えっ、でもそれだと、対称でない反物質も物質と同数ないとおかしくない? だけど今の宇宙に反物質はほとんど見当たらない。 なんで? すべては"いたずらっ子"のニュートリノの仕業で、反物質を物質に変える特殊能力を持っていたから。 言ってみればニュートリノのおかげで宇宙は空っぽを免れたのだ。 だけど反物質を物質に変えるって並大抵のことではない。 マイナスの電荷をプラスに変えるのだから、男を女に変えるレベル以上の至難の業である。 さらに謎なのは、逆向きの、物質を反物質に変えることはできないのかということ。 どうもそれはできないらしいのだが、それがなぜなのかよく分かっていない。 謎を探ろうとスーパーカミオカンデとかの研究施設で日夜実験を繰り返しているが、見えず触れず、あらゆる物体や地面を平気ですり抜けるニュートリノは、"いたずらっ子"であると同時に"恥ずかしがり屋"でもある。 「ニュートリノを捕まえました」と言っても、その実、反応や痕跡から間接的にその存在を確認したに過ぎない。 ニュートリノに限らず素粒子の世界は兄弟や仲間だらけで、読んでてしはしば遠い目になってくる。 それとこの不自然なアンバランスさ。 とてつもなく小さなものを観測するために、目を見張るほどの巨大な装置が必要であること。 しかも粒子探しは、メタルスライムとの遭遇など比較にならないほどの困難さで、ゴミの山から針を見つけ出すほど。 素粒子物理学の世界では、大きな発見は半世紀に一度程度。 ヒッグス粒子の発見が2012年なので、うまくすればあともう一回、生きているうちに世紀の大発見に立ち会えるかどうか。 ただ200年後になっても、「これで新しい時代の幕開けだ」と、今と同じことを言っていても何ら不思議ではない。 それほど息の長い話。 まぁ宇宙誕生の謎を解明しようと言うのだから、すぐに何もかもわかるなんて虫が良すぎるか。
0投稿日: 2024.12.06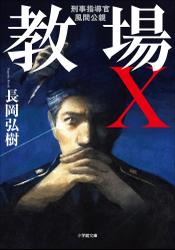
教場X 刑事指導官・風間公親
長岡弘樹
小学館文庫
置物としての単なる見届け人役
テンポ良く、読者にリーダビリティの高さを感じさせる仕掛けがある。 風間指導官と新米刑事の間のやりとりは、無駄なおしゃべりを省き、一気に事件の核心に触れる。 学校での教官だったときは「言ってみろ」と教則や条文を諳んじさせた。 今回は殺人現場で、まず何に着目すべきかのポイントを挙げさせている。 いきなりの無茶ぶりに戸惑いつつも、苦心しながら所感を語る新米刑事に読者は心を寄せ、「やるじゃないか」とは決して言わないが、風間の目の表情だけで、回答の出来不出来を判断する瞬間の連続が、小気味の良さと満足感を感じさせるのだろう。 ただ残念に思うのは、今回の風間の立ち位置。 現場に臨場した瞬間に事件を解決してしまう伝説の存在という設定で、後進の育成を目的とした道場の指導教官という立場から、答えは教えず、謎めいたヒントのみを示し、新米刑事が自力で犯人を追いつめさせるという展開なのだが、波乱もなくすんなりと行き過ぎている。 途中からチャチャを入れたり、最後の最後に犯人側からの手痛い反論を喰らいシドロモドロになる所をさっと救うという場面もない。 警察学校のときはかなり瀬戸際の悪どい手口も用いていたので、ずいぶんと今回の風間は物わかりがよい印象。 単に置物としてノコノコと同伴するだけの、見届け人としての役割しかないのが一番の不満な点。 さらに事件も、最後の盲目の教授が登場するケース以外は単純で、謎とされる部分もほとんど見当がついてしまった。 ちょっと設定や状況がありえないほど無理繰りな点は、短編の制約上、仕方がないにしても、優れた倒叙ものに見られる、聞き取りでの些細な矛盾点を突破口とする解決法が一つもないのも物足りなさを感じた。
0投稿日: 2024.12.05
トッド人類史入門 西洋の没落
エマニュエル・トッド,片山杜秀,佐藤優
文春新書
歴史の反転モデル
思い込みだったとは恐ろしい。 世界の家族形態は、歴史的に新しくなればなるほど、女性の地位が上昇していったと思っちゃうし、共同体家族なんかより核家族社会の方が新しいと思っちゃう。 すべては逆なのだ。 家族の歴史は、女性の地位が低下し続ける方向で進んできたし、なんなら女性の地位が低下した社会は、先進的で革新的ですらあった。 核家族社会なんて周縁部だからこそ生き残れた、最も古い未開の家族形態にすぎなかった。 歴史にはこのように奇妙な逆転・反転現象が存在する。 女性の地位が低く近親婚が推奨された中東の家族形態が、実はもっとも先進的で複合的だったりする一方で、ある時点で社会の発展が停滞し、狩猟採集民たちとさほど変わらない未開の西洋人が、科学技術を発展させていくという皮肉。 この逆転の重要なファクターとなったのもやっぱり「女性の地位」だった。 かつては"文明化の指標"だった「女性の地位の低下」が、ある時点から"社会の発展の阻害要因"となった理由は、女性だけでなく実は男性も、個人としての自由が制限されていて、自立性を失った〝子供〟のような存在になってしまったからだった。 ユーラシアの中心部で発明された文字や国家、技術は周縁部にも伝わったが、「女性の地位の低下」までは受容されなかった。 おそらくキリスト教の影響が作用していたのだろうが、何はともあれそのおかげで、近代のイノベーションが勃興していくのだから何が幸いするかわからない。 今日の英米を中心とした、集団を否定し個人の自立を極端に称揚する、行き過ぎた個人至上主義も、歴史の揺り戻し・逆転現象が働きつつあり、社会的な連帯や専制的国家への見直しが始まっている。 日本でも進歩的な左翼知識人が「日本の近代化の阻害要因」「遅れた日本の象徴」と糞味噌に貶した日本の家族制度が、実は急速な近代化や民主化の促進に貢献していたというのも、ある種の歴史の逆説である。 左翼の高学歴エリートを巡っては、日本だけに限らず世界的に、社会の大多数の労働者や大衆からの遊離現象が起こっていて、それは彼らの依って立つ「高等教育」が、格差是認や平等の否定、体制順応主義への迎合が背景にあると説明している。 核家族と民主制の連関というか親和性も、面白い指摘である。 結婚した一組のカップルとその子供だけで形成される人類学的形態であればこそ、自由への理想は開花する。
0投稿日: 2024.12.03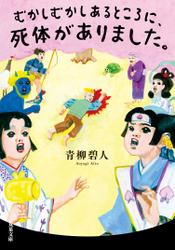
むかしむかしあるところに、死体がありました。
青柳碧人
双葉文庫
日本昔ばなしのパスティッシュ
"打ち出の小槌を使って完全犯罪できないかな"...小説の着想は案外こんなところだったのかも。 ただ味わいは、本格ミステリというよりパスティッシュ文学に近い。 『鶴の恩返し』で機織りの部屋を覗くなという「見るなのタブー」を逆に主人から娘に対し、奥の部屋は覗くなとタブーをかけるというのも面白いし、『桃太郎』のお話も、退治される鬼側の視点に立つと、刀を手にして鉢巻き締めた侍がいきなり島に乗り込んで、猛獣を使って殺戮を繰り広げるという恐怖譚に変わる。 そのまま我が者顔で居着いた桃太郎をキジが説得して帰郷するのも愉快だ。
0投稿日: 2024.12.01
なぜネギ1本が1万円で売れるのか?
清水寅
講談社+α新書
何か一抹のむなしさも...
これまでは生産者の本を読んだらたいてい作ってるものを食べたくなるのだが、今回はまったくならなかった。 ネギが嫌いなわけではない。 他より数倍高い価格で20度超えの糖度のネギを欲しくはないというのがまず一つ。 普通のネギで十分。 「ネギはそういう野菜じゃない。庶民的な値段でないと無理なんだ」というスーパー担当者の感覚に近いかな。 それと売り方が何か嫌。 著者は、消費者金融時代に培った営業スキルを駆使して大都市圏に積極的に売り込みをかける。 「恋するカボチャ」とか「キスよりあまいほうれん草」などキャッチーなネーミングを考え出すのだが、ずぶの素人でも自信満々の大言壮語。 何万個を出荷したらどれくらいの儲けになるとゴールを設定したら、あとは見切り発車でGO。 適正分量もわからず原液のまま消毒薬をドハドバかけて、虫が付いてるとクレームがあると、回収して高圧洗浄機で吹っ飛ばし塩水に漬けてまた売り場へ。 そりゃ腐るって。 あまりにも事業計画が無謀すぎて、山形を飛び出て日本中を車で駆け回ることに。 気づいたら運転席で脱糞していたことも。 ゆっくり慎重に歩くのではなく、とにかく全速力で走り続ける。 失敗を何回繰り返そうが、助走があればあるほどその分飛躍も大きいという考え方。 農業ビジネスに参入してやると鼻息荒く野心満々な人には拍手喝采かもしれないが、自分はどちらかというと彼らに敗れ去った者たちにシンパシーを感じる。 ネギと苗だけで3億円を売り上げ、従業員もパートを含め数十人を雇用し、地元経済への貢献は大きいが、ネギ全体の消費量が爆発的に増えたわけでもないのなら、その分だけ割りを食った農家もそれなりにあるはず。 勝者の裏には敗者あり。 2Lなど高価格帯のボリュームゾーンを独占されているなら、MやLなどのそれ以下のサイズはますます薄利多売となるはず。 どんどんと廃業が進めば、ゆくゆくは安くて普通のネギを買い求める消費者にも皺寄せが来るかも。 それでも知らなかった、面白い話はいくつかあった。 雨の日に畑に入られるのを農家の人は特に嫌うというのもそう。 濡れた土を踏むことで、土中の酸素が抜けてしまう。 おまけに乾いた時にそのまま固まってしまうため、根の呼吸もしにくくなる。 湿った畑には入るべからず。 土は常にフカフカをキープしたい。 畑をフカフカに保てば、内部が乾燥しやすく、雑草の発芽も抑えられる。 だが、赤ちゃんネギの時は別。 フワフワだとヒョロヒョロの弱い丈しかできない。 ギュウギュウの土にして、上に重い土まで載せることで、太くて丈夫な丈にすることができる。 赤ちゃん苗は過保護に育てたいが、早い段階で風雨に当てた方が強く太いネギが育つのも経験してわかったこと。 「いかに育ちすぎを防ぐか」というのも農家にとっては重要な指針で、東北のような雪国の苛酷な環境も、丈夫な苗作りとってはアドバンテージになりうるのだ。 経験上わかったことは、雑草とは無理に戦わないこと。 どうせ勝てっこないのだから、撲滅を目指すのではなく、はなから雑草が好む土地には作付けしないこと。 いまはどんな畑でも借りやすくより取りみどりなのだから、土の質を見て、雑草の出やすい畑は借りないこと。 目の敵の雑草だが、実は中に病気や虫に効果のある雑草もあって、そういう雑草はあえて畑に蒔いて、休眠中の畑のリカバリーに貢献させている。 ネギなどのお馴染みの野菜は、大量に出荷できるところが有利で、価格も高く買ってもらえる。 普通ならバイヤーが大量に買い付ければその分リベートで安くなるはずだが、農産物の世界では逆になる。 スーパーやレストランなどの大口顧客が最も恐れているのは欠品で、それを避けるためなら、多少高い値段を支払うことも躊躇しない。 他にも、ホウレンソウは大きく育てた方が甘くなるというも知らなかった。 事実、大きくすればするほど、エグみの原因となるシュウ酸や硝酸が減少するのだとか。
0投稿日: 2024.11.27
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
