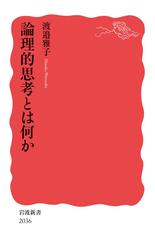
論理的思考とは何か
渡邉雅子
岩波新書
作文の型は思考の型を形成する
日本の大学入試の国語で特徴的なのは、小説の登場人物の心情を問う問題がやたら多いこと。 状況描写から心情を読み解くこの問題は、場の空気を読んで反応できる共感力を試している。 一見非論理的と思われがちな日本の感想文も、実はこの能力を育んでいる。 我々は、読み手の期待する順番にすべての要素が並んでいると、論理的だと感じる。 日本の感想文は、必ずしも結論が明確に示されるわけではないけれど、体験に基づく感情の推移や変化を重視する。 これは、共感に基づく社会性や協調性を重んじる日本の文化を反映した、独自の論理と言えるだろう。 アメリカのエッセイのように、結論を最初に提示し、根拠を論理的に積み上げていくスタイルとは大きく異なる。 しかし、だからと言って日本の感想文が非論理的かというと、そうではない。 感情の描写を通して、書き手と読み手の間に共感の橋を架ける。 暗黙の了解や行間を読むことを重視する日本のコミュニケーションにおいては、この「共感」こそが重要な論理なのだ。 日米の4コマ漫画への感想の違いも興味深い。 アメリカの子どもは、結果に直結する原因を重視するのに対し、日本の子どもは、出来事の順序を丁寧に説明する。 これは、日本人が物事を多角的に捉え、様々な要因が複雑に絡み合って結果に至ると考える傾向を示している。 一つの原因に絞り込まず、全体像を把握しようとする姿勢は、複雑な社会状況を読み解く上で大きな強みとなる。 また、古いものを捨てずに、新しいものと融合させていく日本の文化も、この思考法と関連している。 伝統と革新を両立させるバランス感覚は、世界的に見ても稀有な才能と言えるだろう。 一見遠回りに見える共感重視のコミュニケーションや、多角的な視点も、実は日本独自の論理に基づいた、高度な思考法なのだ。 相手を非論理的だと感じてしまうのは、多くの場合、自分と相手の「論理の型」が異なっているため。 自分が当然だと思っている思考の進め方、情報の整理の仕方、結論の導き方が、相手とは全く違う場合、私たちはそれを「論理的ではない」「筋が通らない」と認識してしまう。 これは、文化的な背景の違いによるものが大きい。 例えば、アメリカ文化で重視される明快な結論提示と根拠に基づく論理展開は、結論を曖昧にすることを良しとする文化圏の人々には、回りくどい、あるいは冷たいとさえ感じられるかもしれない。 逆に、間接的な表現や文脈を重視する文化圏の人々のコミュニケーションは、直接的な表現に慣れた人々には、何を言いたいのかわからない、非論理的だと受け取られる可能性がある。 さらに、コミュニケーションの目的の違いも影響してくる。 相手を説得することが目的なら、明確な論理展開が求められるが、共感を得ることが目的なら、感情に訴える表現が有効だ。 目的が異なれば、最適な論理の型も変わるため、互いの論理を非論理的だと誤解してしまう可能性があるのだ。 つまり、相手を非論理的だと感じるのは、必ずしも相手が本当に論理的に考えていないからではなく、自分と異なる論理の型を使っているからなのだ。 多様な論理の型が存在することを認識し、相手の論理を理解しようと努めることで、より円滑なコミュニケーションが可能になる。 学校作文は、単なる文章作成の練習ではなく、その社会が「論理的」と考える思考の型を学ぶための、重要な訓練場でもある。 たった一つの、永久不変な論理的思考なんて存在しない。 作文の構造、結論に至る道筋、そして結論そのものの形は、社会の価値観や文化によって変化する。 目的が違えば、論理的思考も変わる。 論理的思考はひとつではなく多様。 これは、社会的な合意によって形成された「論理的」の規範が、それぞれの社会に存在することを意味する。
0投稿日: 2025.02.28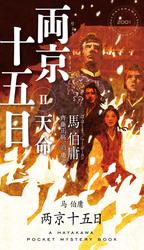
両京十五日2 天命
馬伯庸,齊藤正高,泊功
ハヤカワ・ミステリ
凶炎と熾熱が人を窒息させる
下巻に入り一気に情勢は錯綜し複雑化する。 かつての敵は友となり、かつての追っ手が助力の相手に切り替わる。 両京を結ぶ運河での十五日は彼らの考え方を変え、人生の目的を悟らせる。 道理は明々白々、頭ではわかっても感情がすぐに追いつくことはない。 和解も妥協もできない路を行く者たちに身の栄達など眼中にない。 「痛快に死ぬか、さもなくば、ぜんぶ終いにするかだ」 本書を読みながらたびたび漢詩の魅力にページを繰る手を止めた。 「進むに必ずしも媚びず 居るに利を求めず 芳るに人の為ならず」 瓦松賦の一節もそうだが、つい声に出し朗唱してみたくなる美しい賦。 漢王の権力簒奪の陰謀の筋書きも実に奥が深い。 単に帝を暗殺するのではなく、死ぬことも生きることもできない状態に追いやることで、自身を平時では叶わぬ跡目争いに加わえることができた。 この手があったかと思わずにいられないが、その策謀のさらに上を行くのがまたも蘇荊渓だ。 言葉でいかに人を動かすか。 蘇荊渓の人心掌握術の要諦は、相手にしてもらいたいことを直接言葉にするのではなく、悟らせ、裏を読ませ、自らが主体的に信じ、判断したと錯覚させること。 例えば、一行が徳州手前の十二連城で追手に捕捉された際、折よく張泉と于謙が救援に駆けつけることができた場面。 昨葉何が事前に鳩を飛ばして臨清の白蓮教の分壇に次のような指示を与える。 「太子が臨清にまもなく到着する、信徒はみんな城から出て、迎え撃て」と。 これを于謙にも伝わるように流すことで、白蓮教からの襲撃に先んじて、臨清から出て救う方策を自ら講じさせることに成功する。 これは于謙という男が極めつきの忠義者であることを利用した策でもあるが、かつての敵の白蓮教を間に挟むことで、表の話を裏読みさせることで、真の目的を成就させる。 済南府衙へ行き山東都司が白蓮教と結託し謀反を起こそうとしている訴え出て、官府の軍を動かした策は、いかに荒唐無稽、天衣無縫の通報であろうとも、立ち上る黒煙や爆発などバラバラの細部を相手が自ら勝手に組み立て貼り合わせさせることで、こちらの意図通りに行動させるよう仕向けている。 極め付けは、漢王が用いた続命奇方という奇跡的延命の処方と、蘇荊渓らが作った四逆回陽湯という劇薬を同一と誤認させた場面だろう。 まったくの別物を同じものだと確信したのは太子本人だが、関連があるように仄めかしたのは彼女だ。 「人の心というものはまず定見があると、往々にしてそれに合う事実だけを信ずるものです。陛下の心にまず定見を植えつけ、重要なところをねじ曲げて伝えれば陛下が自然に残りの物語を組み立ててくれます。難しいことではありません」 本書はこれでもかというくらい荒唐無稽な因果が満ちている。 病仏敵という異名をもつ梁興甫の戦いの目的もそう。敬愛する鉄鉉の旧臣であるはずの男が、比類なき忠誠心に導かれて、鉄鉉の息子である呉定縁を殺そうと追い回す。 あるいは朱瞻基は、自らを仇と思っている呉定縁や蘇荊渓に命を救われ、京城まで送ってもらっていたというのもそうだ。 これなど例えて言えば『西遊記』で知られる三蔵法師が、苦楽を共にし、道中に散々命を救ってくれた孫悟空や猪八戒から、天竺に着いた途端に「お前は絶対に許さぬ仇だ」と罵倒されるようなもの。 天の定めとはいえ、宿縁の因果とは恐ろしい。 「まるで闇の中で不可視の巨手が数十年をかけてゆっくりと動き、次々に衝突が連鎖して今日の皮肉にして荒唐な場面を作りだしたようだ。まことに業には必ず因があり、必ず果をまねくものだ」
0投稿日: 2025.02.22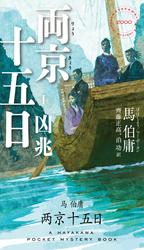
両京十五日1 凶兆
馬伯庸,齊藤正高,泊功
ハヤカワ・ミステリ
とにかく、行け!買え!!読め!!!
内藤陳風に言えば「とにかく、行け!買え!!読め!!!」本。 華文冒険ミステリだとか、”深夜プラス1+隠し砦の三悪人+山田風太郎”など様々に形容されているが、それよりは真っ当な歴史小説を読めたという印象の方が強い。 作者の方も実は、これだけ「晦渋な用語、辺鄙な地名、マイナーな典故が氾濫」する作品が日本人に受け入れられないと思っていた。 しかし蓋を開けてみれば、年末の主要なランキング1位を総ナメに。 訳者の貢献も大きい。 ”十五日”ならぬ “十五ヶ月”に及んでしまったと自嘲気味に振り返るほど、訳出は難渋を極めたと思う。 しかし、ともすれば注釈だらけになりそうなところを、絶妙な引き算で訳文を仕上げ、活劇の面白さを救っている。 文章のリズムもいい。 「果たして船頭の言葉通り、進鮮船が淮河に入った途端、天が暗くなった。雲がたちまち墨のように凝り、大粒の雨が甲板を叩き、水の輪が滲む。すぐに雨粒が連なって平らなかけらとなり、雨のかけらが集まって幕となる。無数の幕が天穹から垂れると、船に乗っている人々を、はるかにかすむ波うつ水沢に閉じこめた」 「息つく暇もなく」なんてのは安易に使われる賛辞だが、これほど字義通りの意味で実践された本もないだろう。 大明国の皇太子が「これで水に落ちるのは何回目だよ」と独りごちる程、試練に次ぐ試練の連続。 読者が心配すべきは、「いつ面白くなるか」という現在の不満ではなく、「いつ読書をやめられるか」という明日の不安の方だ。 登場人物もまた素晴らしい。 てんかん持ちで金にうるさく、やる気なし。 呑んべいな上に品性も下劣で口が悪いが、実務となれば鬼平並みの能力を発揮する呉定縁。 いつも「これ以上面倒事には関わらぬ」と宣言しているのに、あれよあれよと騒動の渦の中心へ流される。 于謙は小臣にも関わらず、デカい声で太子を罵り叱咤もする熱血な直言居士の人。 仲間の中で一番自分は貢献できていないと悲観的だが、実は有能な能吏らしく文書の謎はすべて看破する。 ただ一番推理のキレが凄まじいのが、蘇荊渓という名の女医だろう。 刺繍の図柄から失踪の事件性の度合いを測るなんてのから、何気ない会話の端々から相手の心理の裏読みまでやってのける。 毒薬を繊細に調合し、宿年の恨みを晴らす必殺仕掛人でもある。 太子・朱瞻基は本書で一番評価が一変する人物。 蟋蟀遊びにうつつを抜かす典型的な暗愚かと思いきや、決死行の途中から、先の帝から続く遷都の問題を真剣に捉え、いかに政をすべきかに頭を悩ませる聡明さも見せつける。 都が北にある事で叶えられる辺境への備えと運河の活用も、国都が南に遷れば漕運は止まる。 安寧や苦役は減り、経済的なメリットは大きいはずだが、国境だけでなく国の根本も危うくする。 遷すべきか残すべきかの間で右往左往逡巡する様はハムレットだが、国を統べる者も避けて通れぬ仕事でもある。
0投稿日: 2025.02.17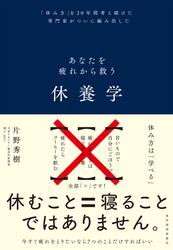
休養学―あなたを疲れから救う
片野秀樹
東洋経済新報社
疲れを取るためにあえて自分に負荷をかける
日本では休まないことが美徳とされるが、70%とか50%のパフォーマンスしか出せないのに出社してきちゃっている罪悪感をもっと抱いた方がいい。 会社はたぶん100%のパフォーマンスを前提に契約してるはずだから。 職場で同僚に声を掛け合う「お疲れさま」も、考えてみれば異常だろう。 あたかもハードワークすることが前提となっているからだ。 外国なら「調子はどう?」という挨拶も、日本だと先にお疲れさまと労われるのだから、何かズレている。 “粉骨砕身して働くのが当然だ”と意識に染まった日本だが、意外にも昔のような「働きすぎ」には陥っていない。 どちらかと言えば、お隣の韓国の方がもっと働いているし、睡眠時間も短いワーカーホリックだ。 ちゃんと休んでいるんだけど、統計を取るとなぜか8割の人が疲れていると回答する、不思議な国ニッポン。 休養の取り方がダメなせいだというのが著者の主張。 疲労は、痛みや熱と並んで、最も重要な生体アラートなのに、軽視されがちだ。 「熱が39度ある」「痛みがひかない」と訴えれば「病院に行きなさい」となるが、「疲れているので休ませて」と言ったらドヤされるだろう。 疲労のシグナルはたいてい、自律神経の変調から始まる。 ゆえに自律神経を整えることは、疲労回復の第一歩となる。 注意すべきなのは、交感神経と副交感神経両方のバランスで、どちらかが優位でも良くない。 自動車と同じで、エンジンのふかしすぎもダメなら、ブレーキのきかせすぎも弊害がある。 同じくらいのパワーになるよう均衡させることがもっとも重要。 著者が語る休養学で面白いのは、運動を休養の一部とみなしている点だろう。 疲れを取るのに寝ているだけではかえって血流を滞らせるだけ。 疲れを取るために体を動かす。運動は休養の一種なのだ。 考えるべきは、疲れにくい体づくりをしたり、活力を得るにはどうすべきかということ。 活力を高める上で大事なのは、疲れた時にあえて自分に負荷をかけてみること。 負荷をかけることで、回復時の体力は10から11、12と上がっていく。 これは筋トレと同じ考え方で、あえて一度筋繊維を壊し、その上で休養しトレーニングに励むことで、筋繊維を肥大化させるのと一緒。 活力を高めないまま疲労と休養のサイクルを繰り返しても、ジリ貧は目に見えている。 スマホの充電で例えれば、日本人は休養しても50%程度にしか充電できていないのだから。 なおかつ自律神経のトータルパワーのピークは、10代後半がピーク。 あとは年を重ねるほどに目減りして、40歳で50%、60歳で25%と落ちてしまう。 総量を増やすことを考えないと、疲れは常態化する一方だ。 バランスの良い食事は休養学の基本だが、同時に「食べないこと」「食事の量を減らす」ことも重視している。 腹八分を心がけ、むしゃくしゃするからスイーツなどやけ食いするなどもってのほか。 甘いもの摂取することで、かえって興奮状態になり、自律神経のバランスも乱し、逆効果となるのだ。 電車で居眠りする横の人に寄りかかられた経験は誰でもあるだろう。 不思議と大抵の人は、眠ったままでも姿勢を維持していて、倒れかかってくることなんてまずない。 これは深い睡眠に入るまでにある程度時間がかかるためだが、もしレム睡眠に入っちゃったら、いっさいの体の力が抜けてしまって、全体重がこちらにかかってくる。 ひょっとしたら、その場で転倒しちゃうかもしれない。 でもたまーに、電池が抜けたようにストンと倒れこんでる人も見たことがあるような...。
0投稿日: 2025.02.13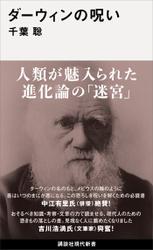
ダーウィンの呪い
千葉聡
講談社現代新書
「ときとしてまっすぐな善は凶器になる」
ダーウィンの呪いが生み出した優生思想。 ダーウィンの正統なる後継者とも言うべき主要な進化学者の多くが、優生学者と同一だった。 なぜ彼らは誤ったのか? ダーウィンの思想を曲解したから? そうとも言い切れない面が本書で指摘される。 ダーウィンのオリジナルな思想は確かに優生学の出発点となった側面がある。 もちろん彼は、人種の存在もその優劣も否定していた。 しかしダーウィンは進化と人間社会を分けて考えなかったし、彼の自然選択説そのものが、人間の進化を念頭において打ち立てられたものだった。 本書の白眉は、英国の議会で戦わされた2人の人物による優生学法案をめぐる激論だった。 心神耗弱者の不妊手術法案を起草したのは優生学会の会長であるダーウィンの息子であり、その法案に断固反対を唱えたのもダーウィンの進化論の恩人にして親戚のジョサイア・ウェッジウッド4世だった。 「優生学者は、過去に自然選択で人間集団から”除去”されていた”不適”な遺伝子が、医学の発展や文化の変容のため、集団から除かれなくなったのを懸念し、人為選択で対処しようとした」 優生学運動を推進していたのは、リベラルで進歩的で道徳意識の強い人々だった。 「なぜ自由を求め、自由を主張する人々が優生学の統制を実現させるのか。なぜ反差別主義者が差別主義の優生学運動を推進するのか。なぜ道徳的であろうとして、反道徳的な優生政策を求めるのか」 そこにあるのは、「生まれてきたせいで苦しい思いをする人々を減らしたい」というやさしさからか、民族のあるべき姿を追い求めて、完璧な人間を進化させるのが可能だと信じた錯誤や傲慢さからか、ある種のわかりやすい科学的な説明を信じきったためなのか。 日本でも旧優生保護法のもと不妊手術で被害になった方々への謝罪はようやく始まったばかりだ。 時として強い道徳意識は、反道徳的な結果をもたらしうる。 あまりにも思いが強すぎるがゆえに、道徳的な欠陥や誤りを見過ごせなくなる。 道徳的完全性を阻むものは、徹底的に排除、抑制される。 優生学で起きた顛末もこうした道徳のパラドクスゆえであり、決して優生学が最後ではない。 「最高の知性と道徳性と善の持ち主だと自他ともに認める人々が悪と不道徳をこの世から無くし、社会を浄化しようと目指した結末が、最も邪悪で非人道的な地獄であった」 多様性の尊重は現在もっとも尊重されている規範の一つだが、これも完璧であろうとすればするほど、ディストピアに近づく。 字義通りに多様性を尊ぶなら、望ましいもの、美しいもの、快適になものばかりではなく、望まぬもの、醜いもの、不快なものも同様に尊重せねばならない。 したがって「多様性を善と考えた途端に、また利益を得ようと多様性を目指した途端に、多様性は失われる宿命にある」。 出発点となる理想は高らかで崇高なのに、ある価値判断、何が正しく善であるかの基準ができた瞬間に、それ以外は不道徳で悪となり打ち捨てられる。 無数の形で善は存在するはずで、そのすべてが道徳的であろうはずがない。 著者が「ダーウィンの呪い」としているのも、こうした選択と排除の価値判断に起因する。 「ダーウィンがこう言っている」というさも自明でわかりやすく、「そうあるべき」という規範の正当化に用いられる、科学を装った単純な説明。 科学的な客観性の権威を無条件に与えてしまうマジックワード。 科学的な衣を纏った呪文が力を与えた。 ダーウィンの自然淘汰の理論も、「生物進化では競争で弱者が淘汰される」というのが科学的事実であったとしても、そこから「競争で弱者は淘汰されるべき」という規範や価値判断を導くことはできないはずだ。 同様に「人間はそうした性質を進化的に獲得した」という進化学の事実から、「人間は競争し、努力すべきだ」という規範も導けないはずだ。 科学的知見や「何が事実か」という前提から、直接「どうすべきか」という価値判断や道徳律など規範的命題は導けないし、導くべきではない。 この「である」から「すべき」という、本来かけ離れた間隙を、一足飛びに跳躍してしまったのが、優生学の思想だった。 この飛躍はいまも、平等や反差別を訴える主張に見え隠れしている。 個人の自由と平等の追求者が、容易に個人の犠牲と差別を強いるようになる。 「この科学的事実から価値判断や規範への論理的飛躍こそ、『ダーウィンの呪い』の中枢である。神の摂理なら規範を導けるが、科学的事実は違うのだ」
0投稿日: 2025.02.12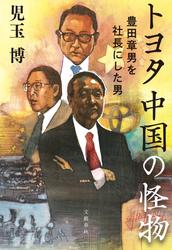
トヨタ 中国の怪物 豊田章男を社長にした男
児玉博
文春e-book
中国共産党というシワ
経済雑誌の内幕レポートとしては面白いが、評伝ノンフィクションとしては物足りなさが残る。 インタビュー中に何度も繰り返される、「児玉さん」との呼びかけ。 穿った見方をすると本書は、服部が社内で陰口を叩かれ、トヨタ公式記録からも消されつつある自身の功績に、光を当てさせるために書かせた自伝本のようにも見えてくる。 人物像へのアプローチは不完全で、中国での辛苦を極めた生活の実態はくわしいが、日本での私生活はベールに包まれたまま。 相手が語りたいこと、気持ち良く喋ってくれることだけを聞きとって、穿れば血が流れ出すような箇所は慎重に避けている。 それに「低迷していたトヨタの中国市場を大転換させた立役者」とか、「豊田家の御曹司、豊田章男を社長にした男」という評価も、両手を挙げては首肯し難い点もある。 確かに起死回生の買収・合併劇の絵図を描いて実現させた戦略はたいしたものだと思えるが、中国のWTO加盟による自動車産業の危機という追い風がなければ、あり得ない功績でもあった。 どんなにネイティブの会話ができ、中国流の商談が巧みでも、この風が吹かなければ、袋小路の状況の打開もできなかったはずだ。 それより興味深いのは、トヨタが中国市場で出遅れた理由の方だろう。 改革開放政策前からあれだけコミットしていたのに、ドイツなど他社の外国企業に遅れをとってしまった。 市場に残っていたのは部品供給会社としての役割だけで、手を組んだ会社も2000億円の不良債権を抱える破綻企業。 80年代から90年代は、米国市場対策でリソースを割かれたためだとの言い訳も出てくるが、それだけではきっとないだろう。 「中国人には買えないだろ」というより、「トヨタ生産方式を中国に根付かせるのは無理だ」との諦めがあったのではないか。 中国人は綺麗に死ぬよりも、惨めに生きたほうがマシと考える。 日本人とは真逆。 心の底では共産主義を嫌っていても、生き残るためにはどんな酷い帝王でも従う。 這いつくばってでも生きようとするのが中国人だと語る服部。 毛沢東が大号令をかけ始まった大躍進運動とその後の文化大革命を当事者として生きた日本人。 人類史に残るほどの餓死者を出した狂気と茶番の時代を、「日本鬼子」と差別され続け、中国時代は思い出したくもないと唾棄するほど嫌い抜いているのに、自分が知らず知らず彼らのように行動してしまっていることに気づき愕然とする。 「洗脳教育は、脳みそに中国共産党というシワを刻み込むようなものだった」と語るほど、自分の行動様式に染み付いてしまっていた。 他と交わらず、自分のみを恃みとし、夜な夜な政府高官や幹部を接待するだけでなく、他メーカーとも平気で情報高官を交わした。 陰口を叩かれる服部のやり口は、起死回生の秘策を成就する力ともなったが、習近平による汚職撲滅政策により、終の住処としようとした中国からも追い出される遠因ともなった。
0投稿日: 2025.02.06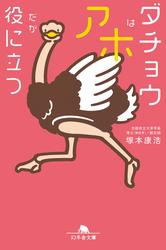
ダチョウはアホだが役に立つ
塚本康浩
幻冬舎文庫
アホでガサツで万能抗体の生みの親
どれくらいアホかというと、自分の旦那や嫁さんの顔も覚えられず、他人の子供との区別もつかないのだとか。 それでいて10羽くらいの群れで生活しているから、何羽か減っても気づかない。 当然、数も数えられない。 何千羽のヒナの中から我が子を見つけ出せるペンギンと比べても、月とスッポン。 「自分の家族の顔さえ覚えられへんくらいやから、当然、人間の顔も覚えません。毎日お世話しても、毎回『誰やコイツ?』みたいな表情をしています。ツンデレやなく、ツンツンです」 脳もシワがほとんどなくツルツルで、サイズも小さい。 脳より目の方が大きいのだとか。 アホなだけでなく、やることがとにかくガサツ。 餌はガガガッと頬張るだけ頬張り、かなり口からこぼしまくる。 ある程度口に溜まると、上を向いて、重力の力で一気に食道へ。 雑やわぁ。 飛べない鳥の代表格とも言えるダチョウも、かつては飛んでいたのだとか。 ただ、羽繕いなど羽根のメンテナンスを怠けすぎて、ついには飛べなくなったのだとか。 まぁでも、速く走れるし、飛翔という莫大なエネルギー消費を回避したために驚くほど長生きなのである。 怠け者なりの独特の進化を遂げたとも言える。 痛みにも鈍感で、血がダラダラ流れても平気。 カラスが患部をついばみ始めても、平然と餌を食べ続ける。 驚くのはここからで、どんなにひどい重傷を負っても、数日で傷が塞がり、回復するのだとか。 底抜けの生命力だ。 さらには、並外れた免疫力を持つということは、それだけ抗体を作る能力も高いということ。 著者はダチョウの卵から抗体を大量に安く作る技術を開発し、ベンチャー事業をスタートさせ、次々と商品開発に勤しむ。 抗体入りマスクからスプレー、キャンディー、果てはコンドームまで。 効能は幅広く、コロナウイルスから花粉症、アトピー性皮膚炎、薄毛、ガンとまさに無限である。 ほんまかいなと疑いたくなるが、本当ならノーベル賞ものだろう。 極め付けが、牛のゲップを減らす抗体を作って、世界規模でメタンガス排出を抑制し、地球温暖化をダチョウパワーで改善できる目処が立ったのだとか。 すでに特許申請済み。 ダチョウパワー恐るべし。 ちょっとツッコミを入れさせてもらえば、そんな驚異的な生命力・免疫力を利用するなら、卵から抗体を抽出するというまどろっこしい方法ではなく、その生体メカニズムそのものを移植できれば、人間の寿命は大幅に伸びそうな気がするが。 そうなると多少アホになるかもしれないな。 ただこのアホというか、進化を順調に重ねていくのではなく、置いてけぼりであることのメリットについては深く考えさせられた。 ダチョウの抗体が他のものとどう違うか。 速くて安いだけではない。 抗体を作り出す免疫グロブリンと呼ばれるタンパク質のY字の形状に違いがある。 進化した哺乳類は、Y字の先がある程度固定されていて、特定のウイルスには適しているが、それ以外や未知の異物には対応できない。 対して、恐竜から鳥への進化のドロップアウト組であるダチョウのそれは、Y字の先端が長すぎるし、揺らぎがある。 そのため、いろんなものに引っついて、ものすごい種類の抗体を大量に作り出すことができるのだ。 設計通りに細かくピンポイントで狙い撃ちするのと、ファジーというか成り行きで遊びを残しておくという生存戦略の違い。 戦略でもないか。 スボラにしてたら、身についたというべきか。
0投稿日: 2025.02.05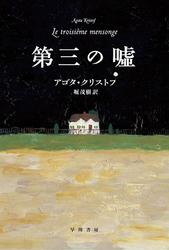
第三の嘘
アゴタ・クリストフ,堀茂樹
ハヤカワepi文庫
人生とはまさにこうしたものかも
「小説とはこういうものだ。読み終わって、そんな気がする」と評したのは養老孟司だった。 「子供がつづるような単純な文章が、きわめて切り詰められた客観的な表現を生む。それが、語られる内容の重さを、読み手に逆に強く意識させる」 「面白い小説がないか。そういう質問を受けたら、私はこの三部作を推薦する。安易な読み物ではない。しかし、引きつけられる。人生とはまさにこうしたものではないか、と」 1992年に刊行された30年以上も前の本だが、いっこう古びることのない魅力が詰まっている。 いまも山のように新刊書籍が出版されているが、本書のように堀茂樹という訳者が、クリストフという無名の作家を発見し、出版社に掛け合い共感に満ちた翻訳・解説を行なった作品に出会う機会はほとんどない。 あとがきで、三部作の最後である本作品で真相が語られているわけではなく、タイトル通りの嘘かもしれないと記されているが、どうだろう。 確かに第一、第二は嘘で、大きな帳面や日記を元にした物語は、事実を元にしたものではなく、リュカの純然たる創作物だったわけだが、第三の嘘は何だろう。 3つの嘘と読みかえれば、リュカが国境を超えた先で提出する書類の嘘のことだろう。 曰く、名前はクラウスではないし、国境越えに同行していたのは父親ではなかったし、年齢も18歳ではなく15歳だった。 とりわけこの年齢が最後に効いていて、クラウスが3歳も年長の男が自分の双子の片割れであるはずがないとリュカとの再会を拒む理由づけに使われている。 もちろんクラウスは、本物のリュカであるとわかっている。 いまさら母親に会わせても手遅れで、平穏な生活を乱したくないからつく抗弁ではあるのだが、嘘はこの部分を指しているのではないか。 それにしても『悪童日記』で、まさに一心同体と化した双子のあの鍛錬の日々、忍者の修行のようにお互いがお互いを鍛えあった日々の描写が、リュカの生き別れたクラウスへの思慕というか、現実ではなし得なかった願望の裏返であったというのは何とも切ない。 身の上話を誠実に書こうとすればするほど、深い部分で自分自身を傷つけてしまうため、こうあって欲しかったという願いに基づき美化しているのだ。 実際には起こってないけど、事実であり得たものとして変更を加えていく作業は、まったき作り話であり、嘘なのだ。 クラウスの視点から振り返ると、これがまた切ない。 父親が突然家を出て行き、逆上した母親がその父を撃ち殺す。 跳弾がリュカに当たってしまい生き別れ、その後何十年と再会できずじまい。 母親はその悔恨で精神を病み、傷つけたリュカを絶対視し、クラウスを陰に陽に傷つける。 さらに父の不倫の原因を作った愛人の元で育てられ、そこで出会った娘と許されぬ恋心を募らせるが成就しない。 一方では、リュカの行方を必死に探しながら、リュカといまの精神状態の母親を合わせてしまうと大変なことになると恐れてもいる。 自殺したリュカの葬儀を終え、また四人が一緒になれる日も近いなと夢想するクラウスの最後の言葉、「列車。いい考えだな」も印象的だ。 映画『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』の最後に、ロバート・デ・ニーロ演じるヌードルスが浮かべる微笑みを想起させる。 現世では決して叶わぬ、永遠に失われた関係性が、夢の中、あるいは来世で、そして創作においてなら実現できるのではないかという儚い思い。 人生もまさにこんなものなのかもしれないが。
0投稿日: 2025.02.03
法廷占拠 爆弾2
呉勝浩
講談社
犯罪と罰は、等価じゃない
「いつも先手は犯人が握り、(警察は)後手を引かされる宿命なのだ」 事件が起きなければ動けないし、周到な準備の面でも遅れをとる。 さらに十中八九ブラフだとわかっていても犯行予告には駆けつけねばならないし、どうせ爆発しないとわかっても三脚にくっついたスマホを前に、じっと爆発物処理班と一緒に待機し続けねばならない。 人手はいくらあっても足りはしない。 爆弾なんて一つ告知通りどこかの野原で爆発させれば十分で、あとは国会や東京タワー、銀座などで爆破予告を流してしまえば、警察は威信をかけて予告の場所へ大量の捜査員を送り込む。 あとは犯人の思いのままで、スカスカとなった方面に逃走を企ててもいいし、人手不足から鑑識がおざなりとなるのを見越し、自殺に見せかけた殺人を行なってもいい。 勝ち目のない勝負なのだが、幸運なことに現実の犯人は、狡猾でもなければ豪胆さも持ち合わせていないし、おまけに必ずと言っていいほどドジを踏む。 しかし著者が生み出した犯人は極めて周到だ。 たった二人で法廷を占拠できるか? 100人近い人質をどう制圧・管理するのか? まず手にしている拳銃や持ち込んだ爆弾が本物であると、その信憑性をどのように人質や警察に周知させるか? 今回はその問題を、大量のスマホなどのネット端末を持ち込み、法廷内を生配信することで解決している。 何十万という視聴者を監視役にすることで、イニシアチブがいともたやすく握られる。 人質にカメラの前で名を名乗らせることでプレッシャーを与え、自由を制限する。 逃げたら罰を受けるのは残った者たちだという恫喝により、人をつけなくても良くなる。 ただスマホを持たせ自分の顔を映しながら配信し続けることで、全国に顔と名前を晒しながら、身勝手な行動を封じる。 なんたる狡猾さ。 法廷内で遺族が犯人への復讐心から犯罪を働くという事件は過去にもあったが、本書はこの復讐心という犯行動機に別の2つの異なる目的を重ねることで、事件の様相を多層的にしている。 もう一つの焦点は、柴咲に代表される社会に対する逆恨みから、独自のルールを持ち出し、自らの不合理性を棚にあげる言説にどう反論するかということ。 これは実は、割とメディアでコメンテーターが、いかにも正論然としてなされる物言いとも親和性がある。 柴咲は「人は真実性とは無関係に、差し出した犠牲によって物事の真偽を測る生き物」なのだと語り、犠牲を差し出さない言動ほど空虚なものはないと嘯く。 そこで犯罪に対しては裁きによって、それに見合った量刑が下され罰せられるのであるから、先に罰を受け入れてしまえば復習しても許されるはずだと主張する。 強行犯係の立花班長が、湯村に語りかける言葉が印象的だ。 「良くも悪くも我々は、縁でつながった他人とともに生きていくしかないんです。愛情も憎しみも、嫌っていうほど絡まってくるんです。法律は、それを調停する知恵ですが、誰かを幸せにしたり不幸にするのはどこまでいっても人間なんです。犯罪と罰は、等価じゃない。それはまったく、等価じゃないんです」 前作も良かったが本作も期待に違わぬ出来だった。 惜しむらくは、スズキタゴサクのお喋りが中断してしまうことくらい。 それくらい彼の言葉は、造形も含め、読者を引きつけて離さない強烈さがある。
0投稿日: 2025.02.02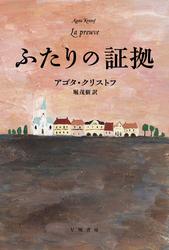
ふたりの証拠
アゴタ・クリストフ,堀茂樹
ハヤカワepi文庫
戦争より自由より存在の不確かさ
読む前はこういう展開になるとは思わなかった。 祖母の家に残った方のリュカの物語とはいえ、二人で一人。 結局は双子の話なのだから、やがては片割れと交差していくのだろうと。 あるいは国を出たクラウスの物語と並行して描かれて、自由の有無という視点から対比された物語になるか。 まさかこういう形で二人の人生を交差させるとは思わなかった。 さらに自由なんていう価値観に全然重きが置かれていないことも驚きだった。 訳者あとがきで本作と前作『悪童日記』の解説を読んで、衝撃を新たにした。 ラストの別離のシーン。かたくなに「ぼくら」と単体のとして綴られた物語が、突如として複数に、別々の行動をとる驚き。 読者はあたかも「単一細胞の分裂」を目撃するかのようだった。 そして本書の中心となる「大きな帳面」を元にした物語と最後の付記まで含めた公式記録を通して読むと、本当に複数形に分裂したのか判然としなくなってくる。 こうした存在の不確かさを念頭に置いて、著者が物語を描き、意識的に語り手の人称や文体を含め注意を払っているのだとしたら、とてつもない力量だと感心させられる。 『悪童日記』は何十年ぶりかの再読となったが、いまだその鮮烈さはいささかも褪せていないし、未読だった続編もなぜその当時に手にとらなかったのかと惜しまれる。 なぜリュカはマティアスに固執したのか。 もしブロンドの髪を持つ美しい子供、アニェスの弟サミュエルと先に出会っていたらどうなっていただろうと想像する。 リュカはその少年に別れた双子の片割れクラウスの面影を見出し、心吸い寄せられている。 それでもマティアスを、醜く不具の身体障害者で近親相姦の子供を自らの子供として手放さなかったのには理由がある。 双子との別離の後、リュカは危機的な状態にあった。 一心同体だったクラウスとの別れにより、想像した以上のダメージを負い、健忘症のような、無気力状態に陥っている。 そんな時に出会ったマティアスは、自分を警戒し全然なついてくれないのだが、彼のハンディキャップを目にすることで自分の存在意義を見出したのではないか。 この子は他所でこの先、嘲られ見くびられるかもしれないが、知識だけは遅れを取らないようにできるのではないか。 絵画や読書など、この子の知育教育に母親以上に貢献できるのは自分なのでないか。 リュカとマティアスにとって悲劇的なのは、そうした審美眼を鍛え、冴えた目を持つことが必ずしも人を幸福にしないこと。 見えすぎた目は、千倍万倍の愛の言葉より、内なる一つの疑心によって、絶望に転じてしまう。 先の先まで見通し、深いところで足を取られる。 「母親といっしょに行かせてやるべきだった。ぼくは致命的な誤りを犯しましたよ、ペテール。是が非でも子供を手放すまいとしたんです」 リュカの悔恨に対しペテールが言った一言が強く心に残る。 「われわれは皆、それぞれの人生のなかでひとつの致命的な誤りを犯すのさ。そして、そのことに気づくのは、取り返しのつかないことがすでに起こってしまってからなんだ」
0投稿日: 2025.01.30
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
