
遺伝子‐親密なる人類史‐ 上
シッダールタ ムカジー,仲野 徹,田中 文
ハヤカワ文庫NF
遺伝子とは何かを卒業し、遺伝子を使って考える段階へ
いやぁ面白いわ。 目から鱗が落ちまくりだし、腑にも落ちまくった。 遺伝子の歴史は、生命の謎を解き明かすための問いと、その問いに対する答え、そしてその答えがまた新たな問いを生むというプロセスの連続だった。 まさに著者の言う「新たな発見は新たな疑問を生む。古い疑問は新しい疑問に取って代わられる」という言葉通りの展開。 まず、最も根源的な謎として存在したのは、「遺伝とは何か」という問いだった。 親から子へ形質がどのように伝わるのか、なぜ子は親に似るのか、そしてなぜ違いも生まれるのか。 古代ギリシャの時代からピタゴラスやアリストテレスもこの謎に取り組んだ。 特にダーウィンの進化論が登場し、自然選択による生物の多様化と適応のメカニズムが提唱されると、その理論が機能するためには、形質が受け継がれるメカニズム、すなわち遺伝のメカニズムそのものが不可欠な要素となる。 ダーウィン自身も遺伝のメカニズムに悩み、自身のジェミュール説を提唱したが、当時の「融合遺伝」という考え方では、有利な変異体が世代を経るごとに薄まって消えてしまうという問題を説明できなかった。 この「融合遺伝」の謎を解決し、遺伝理論に決定的な洞察をもたらしたのが、ご存知メンデルの実験だった。 メンデルはエンドウマメを用いた緻密な交配実験によって、形質が混ざり合うのではなく、独立した分割不可能な「粒子」によって遺伝することを数学的なパターンとして見出した。 これにより、ダーウィンが求めていた遺伝の基本法則が明らかになる。 遺伝は連続的なものではなく、不連続な「単位」(遺伝子)によるものであり、これが多様性を生み出す基盤となったのだ。 次の大きな謎は、この「粒子」や「単位」の物質的な正体は何なのかという疑問。 細胞の核に含まれるクロマチンがタンパク質と核酸でできていることは知られていたが、生物学者はその多様性と機能の豊富さから、遺伝情報を運ぶのはタンパク質である可能性が高いと考えていた。 DNAは単純すぎて「情報の運び手には向いていない」と考えられていたというのだから意外。 しかし、グリフィスの形質転換実験によって、遺伝情報が化学物質として細菌から細菌へ移動できることが示され、マラーはX線を使って遺伝子に変異を起こせることを発見し、遺伝子が物理的な実体であり、操作可能であることが示される。 これらの発見により、遺伝子が物質的なものであり、化学物質の性質を持つことがわかった。 そして最終的に、遺伝情報を運ぶ本体がDNAであることが明らかになり、さらにワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造の解明は、遺伝情報がどのように保存され、複製されるかというメカニズムに物理的な根拠を与えることになる。 DNAの構造が明らかになったことで、遺伝子がどのような「設計図」なのかが分かり始めた一方で、新たな謎も生まれることに。 「遺伝子は何をしているのか」という機能に関する問いだ。 ビードルとテータムの「一遺伝子一酵素説」は、遺伝子がタンパク質をコードしていることを示し、遺伝子と生化学的な機能を結びつける。 タンパク質は細胞内の多様な化学反応を制御する「スイッチ」のようなものであり、生物の機能の中心を担っていたのだ。 さらに、すべての細胞が同じDNAを持っているにもかかわらず、なぜ異なる機能を持つ細胞(例えば赤血球と肝細胞)が存在するのか、なぜイモムシがチョウに変態できるのか、といった遺伝子の「調節」に関する謎が登場する。 ジャコブとモノーはオペロン説を提唱し、遺伝子にはいつ、どこで、どのようにつくられるかという情報(調節配列)も含まれており、特定の遺伝子群が協調的にオン・オフされるメカニズムを発見した。 これにより、遺伝子は単なるタンパク質の設計図だけでなく、プログラムとして実行されるための「文脈」を持っていることが明らかになる。 遺伝子調節の理解は、発生生物学における長年の謎、すなわち「単一の受精卵がどのようにして複雑な多細胞生物へと発達するのか」という問いに光を当てることに。 遺伝子のオン・オフの連鎖が、胚の基本的なボディープランや各器官の形成を指示していることが明らかになる。 発生は、マスター遺伝子や体節遺伝子などが、他の遺伝子を順次制御していく過程として理解されるようになった。
0投稿日: 2025.05.01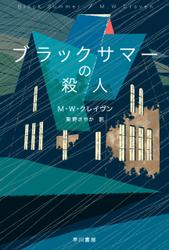
ブラックサマーの殺人
M・W・クレイヴン,東野さやか
ハヤカワ・ミステリ文庫
生きていると同時に死んでもいる
文句なく面白い。 ラストの胸のすくような一発逆転劇を思うと、前作よりも上かも。 物語の始まりが特にいい。 時勢柄、警察署が売却された田舎の図書館に、週に一度巡回で訪れる苦情処理担当の警察官。 彼の前に突如現れた放心状態の娘。 詳しいことは何も知らされず「大変なことになった。とにかくこっちに来い」と呼び出されるポー。 ほんと読ませる。 中盤はちょっと退屈に感じさせる。 前作と変わらぬ構成になっていて、ティリーはポーの繰り出すウィットやジョークを字義通りに打ち返すだけだし、ポーの動きを制限しようとする警察内部の暗躍もそう。 ただ魅力的な謎で引っ張るのでそんなのはどうでもよくなるのだが。 「エリザベス・キートンは生きていると同時に死んでもいる」 二つの相反する意見を持ちながら、その両方を信奉するという、オーウェルの「二重思考」というタームを出しながら語られる不可解な謎。 合理的な説明としては、誰かが他人の血液を、自分の体内に隠し持っていたとしか考えられないが、そんなことは果たして可能なのか。 明かされた答えは、まぁそういうことか、と若干熱を冷まさせるものであったけど、それでもこの証拠保全のプロセスの話はとても興味深かった。 いかにして証拠の連続性を維持するか。 改ざんやすり替えを排し、採血から保全過程まで逐一録画などで記録される。 本当に血液サンプルの取り扱いは適正だったのかどうか。 このあたりが丁寧に描かれている。 拠点となる警察署は次々と売却され、週に1回しか警察官が巡回しない地方の事件であっても、このあたりは手を抜かない。 それと、イギリスのコモン・ローにおいて長らく確立されていた一事不再理の原則が変更されていたというのも、本書で初めて知り驚いた。 もちろん例外扱いではあるが、これにより同じ犯罪で二度裁くことが可能となっている。 それと本書は、素敵な料理ミステリーでもある。 冒頭から、生きたままブランデーで溺れさせた鳥の料理も出てくるし、何よりタイトルのブラックサマーからして、最高級のトリュフなのだ、見た目はウンチにしか見えないが。 ポーが食べるテイティーポットの描写はもうヨダレが垂れてくる。 「てらてらとした子羊肉、濃厚な味のブラッドソーセージ、金色に輝くジャガイモのスライスをスプーンに取り、口に運んだ。目を閉じて、ため息を漏らす。舌がとろけそうだ」 さっそく検索して写真を見たが、無性にイギリス料理が食べたくなってきた。
0投稿日: 2025.04.22
鉄道路線に翻弄される地域社会 - 「あの計画」はどうなったのか? -
鐵坊主
ワニブックスPLUS新書
自治体が抱えるジレンマが、整備計画に飛びつくキッカケに
タイトルが示す通り、本書は日本の鉄道網、特に新幹線計画や地方ローカル線の存廃問題が、沿線自治体にいかに大きな影響を与え、翻弄しているのかを多角的に描いている。 自治体は、発展への期待と財政難、人口減少への危機感、そして災害からの復旧という複数のジレンマに常に直面しており、その中で鉄道というインフラに翻弄されながらも、地域社会の維持と活性化を目指す苦悩が本書全体を通して強く伝わってくる。 自治体が新幹線プロジェクトに大きな期待を寄せる背景には、地域経済の活性化と人口減少への抵抗という強い動機があることがわかる。 函館市が新函館北斗駅から函館駅への新幹線乗り入れを検討しているのは、札幌延伸後の特急廃止による乗り換え問題を解決し、経済効果を見込んでいるから。 新座市が大江戸線延伸に期待を寄せるのも人口を減少させないためにも、町の魅力度を向上させるツールとして大江戸線の沿線が必要不可欠と考えているため。 都心と直結することで新たな住民の転入を促し、人口減少の流れを変えたいという強い願いが背景にある。 川口市が巨額投資をして上野東京ラインのホーム建設を決定したのも、町の競争力・魅力度を底上げする重要な都市計画と捉えているからだ。 これらの事例から、自治体は新幹線や地下鉄といった新たな鉄道路線を、地域へのアクセス向上、経済効果の創出、そして人口減少に抗うための魅力的なツールとして捉え、積極的に誘致・推進しようとしていることがわかる。 しかし、多くの自治体は厳しい財政状況に置かれている。 本書では、北海道のローカル線維持におけるJR北海道の苦境や、第三セクター鉄道への財政支援の難しさが繰り返し語られている。 特に、肥薩おれんじ鉄道のように複数の県にまたがる第三セクター鉄道では、公的資金の分担率を巡る問題が常に存在し、鹿児島県のように支援金の拠出に苦慮するケースも見られる。 鹿児島県では人口減少による税収減少から、基金からの拠出に対する反対意見も根強く、財政的な限界が示唆されてる。 それでも、自治体が赤字路線であっても容易に廃線を認められないのには、複数の理由がある。 一つは、地域住民の生活の足としての役割だ。 米坂線の復旧問題では、沿線全体で通学の足を考える必要性が議論されており、日田彦山線のBRT化においても、東峰村のように村内に鉄道路線を失うことへの強い危機感が示されている。 二つ目は、忘れられることへの危機感だ。 鉄道の廃線は「JRのネットワークから外れてしまい、路線図からも消える」ことを意味し、沿線自治体の知名度低下や魅力の喪失に繋がりかねない。 人口減少社会において、自治体は「魅力度を高め、住んでもらえる場所になるべく、しのぎを削っている」ため、鉄道の存在は極めて重要な要素なのだ。 三つ目は、貨物輸送の役割である。 函館本線の渡島ブロックのように、旅客鉄道としては赤字でも、貨物列車が多数運行されているために廃止できない路線も存在する。 国土交通省が鉄道貨物のシェア倍増を目標としている現状を考えると、貨物輸送の重要性は今後ますます高まる可能性があり、安易な廃線は認められないという国の意向も背景にあるのだろう。 本書は、多くの自治体が厳しい人口減少予測に直面している現状も指摘している。 新座市の将来人口推計のように、一時的な増加が見込まれても、その後は緩やかな減少が予測されている地域は少なくない。 このような状況下で、自治体は交通インフラ整備に活路を見出そうとしているが、それが必ずしも人口減少を食い止める有効な手段となると断言できるだろうか。 川口市が上野東京ラインのホームを建設しても、「自治体間の格差、大都市への人口集中といった問題がさらに大きくなることが懸念される」と指摘されるように、一部の自治体の魅力向上策が、他の地域の人口流出を加速させる可能性も否定できない。 自治体の努力が、焼け石に水になるかもしれないという不安は常に付きまとう。
0投稿日: 2025.04.20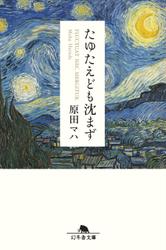
たゆたえども沈まず
原田マハ
幻冬舎文庫
たゆたいこそすれ、決して沈まない
いいのはタイトルぐらい。 文体は眠気を催すほど単調で、人物造形も薄っぺら。 小学生向け学習漫画の偉人伝を読んでる感覚に近い。 そのタイトルの意味もくどいほど解説がなされるので味も素っ気もないのだが。 一方で扱われた題材は興味深い。 ゴッホ兄弟に寄り添う形で交流を続けた日本人がいたというのはもちろん架空の設定なのだろうが、有名なタンギー親父の肖像画の背景にあれほどいくつもの浮世絵が配されている理由の一つとなっていて興味深い。 ゴッホがアルルの地を日本と同一視していたのは史実通りだが、それに林忠正と折鶴が関わっていたというのもフィクションとして面白い。 最近では他殺説も出ているゴッホの死の真相も、最大の謎であるピストルをどこから入手したのかの説明も試みられていて興味深い。 動機についても、テオを苦しみから解放することばかりを考え続け、自分がいなくなれば、弟の負担が軽くなると思い詰めた末の結末とされる。 自分も自殺性は揺るがないだろうし、弟テオの関与も、従来考えられていたより濃厚だろうと考えていたので、テオの所有物という線に異論はないが、貸したバックにたまたま入ってましたはさすがにないよなと思える。 それと自殺説の泣き所である、なぜ銃弾が貫通せず体内に残っていたのかについては全く触れられてない。 それ以外に本書で興味深かったのは、パリで日本美術の流行に寄与したのが、実は何の見識も造詣もない、語学だけが堪能な留学生たちだったという点。 何かが爆発的に異国でヒットする際、必ずしもそれに精通した専門家の関与など必要ないのだ。 現地に行って輸入・販売を通じて仕入れた、付け焼き刃の知識だけで結構何とでもなり、堂々とふんぞりかえって講釈を垂れるだけで何とでもなったということだ。 まさにブームとはそういうもので、仕入れる先から売れていく。 日本で浮世絵は古新聞と同程度の価値しかなく、まるで見向きもされない紙切れ同然の代物を、廃品回収の如く安価に大量に買い取っていけば、ヨーロッパでは信じられないほどの高値で売れたのだから。 パリで当時人気の雑誌に日本特集として林忠正が執筆・監修に加わり、その表紙にどの浮世絵を載せるかで、《雲龍打掛の花魁》という作品が突如として高騰する様子が描かれているが、これなども色々と考えさせられる。 新奇性や希少性から驚くような値をつけるだけで、その美術的価値とは無関係なのかもしれないが、何がそこまで惹きつけたのか。 明治に入ったばかりの当時の日本で、渓斎英泉の浮世絵の日本美術における評価も固まりきらぬうちに、何を優先して海外に紹介し、その魅力を思う存分語っていたのは、単に語学ができるだけのズブの素人だったというのは本当にアイロニカルで面白い。
0投稿日: 2025.04.18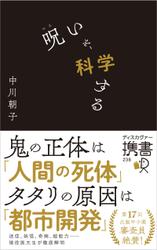
呪いを、科学する
中川朝子
ディスカヴァー携書
現役女子大生が紹介する呪いのアレコレ
オカルトはすべて既存の事実で説明できるし、超常現象も捏造であるなど、そのトリックはすでに明らかになっている。 呪いとしか思えなかった怪異現象も、科学的な解釈や治療可能な対象として見なされるようになった。 いまや呪いは科学技術に屈したと言ってよい。 未来においては、AIなどさらに高度に発達した科学により、別種の呪いが復活するかもしれないが、呪いがもたらしていた誤解や偏見は打ち砕かれるべきだと、出版時に現役大学生だった著者は考える。 私も含め多くの読者は、本書を読んで幾分か肩透かしに似た思いを味わうのではないか。 テレパシー研究など超心理現象を大真面目に研究している超心理学の分野があるが、その研究成果なんかをわかりやすく解説されるのだろうと思っていた。 あるいは呪いと感じてしまう脳神経分野からのアプローチであるとか。 ずいぶん前に倉知淳が小説『過ぎ行く風はみどり色』の中で、人が怨念を感じたり幽霊を見てしまうカラクリを”残存思念”というワードを用いて説明していた。 脳内を駆け巡る思考や感情を乗せた電気信号は、時に外へと漏れ出して、ラジオのノイズのように周囲に障害を与える。 例えば「恨めしい」という感情が、パルス信号として空中に放射され、特定の場所に残存する。 そうした残存思念に接した際、ある人は「何となくゾッとした」と感じ、また別の人は「何か恐ろしいものを見た」となる。 幽霊がよく出るとされる場所も、そうした残存思念の再構成なのではないかというもの。 誤りでもこのくらいの思い切った説明が読めるのかと期待したが、有名な呪いとか関連する病気などの単なる紹介に終始してしまった感じでもったいなかった。 つい最近読んだ本の中では、東北地方に古くから伝わる座敷わらしの正体は、だいたい科学的な説明が可能なことがわかってきたと書いてあった。 それは、レビー小体型認知症患者特有の幻視だという。最大の特徴は、日や時間帯によって認知機能が上下動するところ。 多くの場合、夕方などの薄暗い時間帯に出現し、「5歳くらいの子どもが家に入ってきた」など証言もリアリティを伴う。 つまり有名な怪異も、実はパーキンソン病に似た脳の認知機能の障害によるものだったのだ。
0投稿日: 2025.04.15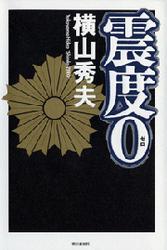
震度0
横山秀夫
朝日新聞出版
「今回は、勉強させてもらった」
「警察小説はここまで進化した」とは、本書の帯に付された宣伝文句。 進化したかどうかはわからないが、通常の警察小説とは趣を異にするのは確か。 扱う事件はとても地味だし小粒と言っていい。 何より聞き取りや鑑識など現場での捜査の様子は省かれ、指揮・命令する幹部たちを中心に物語が展開している。 どちらかというと解決までの推理ではなく、男たちの腹の探り合いでページを捲らせる小説。 仲間であるはずのキャリア組である県警のナンバー1と2が反目し、地元の生え抜き幹部ともいがみ合う。 主要な場面が県警本部長室内で起こる密室劇なのもいい。 こういう組織内の権力闘争が的確な人物評や描写によって描かれると、こうも読ませるものかとほとほと感心させられる。 失踪した不破の官舎の引き出しにある手帳をどちらが先に手にするかを巡って、刑事部長と警務部長と本部長が熾烈な駆け引きを繰り広げる様はとても痛快だった。 唯一の疑念は、同時発生する阪神大震災がどう事件に関わってくるのかということだった。 単なる背景描写として混乱を倍加させるだけの添え物なのか。 そんなことを思いながら読んでいたのでクライマックスで驚いた。 「震度0」 - タイトルに込めていたのはそういう意味だったのか。 宣告とも、固い決意とも読み取れる実に巧いタイトルだ。 「弱気につけ込まれるな。強気に浮かれるな」 - 将来の警察庁長官候補と目される警務部長の冬木はいわば「負けられない人間」で、組織内で一度でも敗北を喫することが許されない立場。 本部長の椎野は、確かに県警トップで本庁の先輩にあたる人物だが、これからの出世の見込みもない男。 おまけに私大出身だから政界との縁も薄く、国政選挙に打って出るような心配もないから安心して盾をつける。 地元生え抜きでトップの藤巻刑事部長と事を構えたくはなかったが、自身の目論見を妨害するなら容赦はしない。 天下り先などの人事の切り札を使って、地元の三部長の切り崩しを図る。 要するに、警務部長失踪という失態を取り繕い、汚点を挽回もしくは隠蔽することで、三者の思いは共通していても、その主導権をどちらが握るかで熾烈な探り合いが行われる。 目的も単なる権勢欲やプライド、強烈な出世欲とも割り切れない。 藤巻がいい例だが、もともといまの地位は僥倖のようなもので、やみくもに刑事として死に物狂いに働いて勝ち取ったものにすぎない。 だからその先の天下りポストなども、もとから期待などしていなかった。 なのに固執してしまうのは、「一度は掌中に握ったと確信したものを、今になってないものと考えるのは難しい」という未練にも似たサンクコストの感覚。 腹の探り合いや駆け引きは官舎内における幹部の妻たちの間でも行われる。 その中でのたわいもない会話、あるいは妻からの一言によって事態は大きく揺れ動く。 こうした中でとりわけ重要なのは確かな観察眼だが、実は最もそれに長けているのは桑江という男だった。 威勢のいい言葉なぞ吐かずとも、弱みを握り、人を意のままに操る。
0投稿日: 2025.04.14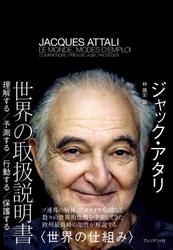
世界の取扱説明書――理解する/予測する/行動する/保護する
ジャック・アタリ,林昌宏
プレジデント社
人工物の奴隷から人類の消滅に
著者は、現代を「ポスト工業化社会」ではなく、サービスを新たな工業製品に変えることを目的とする「サービスの工業化社会」であると捉え、その最終的なフロンティアとして「自分自身の人工化」という新たな段階に移行しつつあることに懸念を示している。 これまで歴史の転換点ごとに新たな人工物が開発されてきた。自然や動物に植物、そしてついには人間自身が人工化される段階にまで辿り着いてしまった。 自己監視ツールによる常時監視と健康管理の人工化、遺伝子操作から脳の人工化、芸術やライブ興行なども人工化される。 人間関係も人工化され、ヴァーチャルな分身がさまざまな場面で登場し、ロボットが人間を雇うようになるだろう。 自己監視ツールは砂糖の摂取許容量だけでなく、能力低下、違法行為、排出可能な二酸化炭素量まで予測可能とし、管理や制御の対象となる。 世界の人工化の進行に伴い、著しい不正義が生まれ、公共サービスは消滅する。 教育や医療、治安などの公共サービスが儲けの対象となるからだ。 これらのサービスは次第に民営化され、世界的な営利サービスが提供されるようになる。 そしてこれらのサービスを代替する人工物が生産される。 「自己監視」と呼ぶこれらの人工物により、誰もが自分の健康状態、精神状態、教育レベル、環境のパラメータを常時把握できるようになる。 医療、教育、メディアなどの職業は、人工知能によって刷新される。 市場がグローバル化する一方で、政治はローカル化する。 国境の閉鎖、外国人の追放、執拗なポピュリズムが増殖する。 あらゆる形態の人種差別と過激主義が横行するだろう。 2050年の段階は、「《心臓》なき《形態》」の時代か、10番目の「心臓」の時代か、明確な結論は出されていない。
0投稿日: 2025.04.12
ストーンサークルの殺人
M・W・クレイヴン,東野さやか
ハヤカワ・ミステリ文庫
なぜストーンサークルなのか?
「ゴールド・ダガー賞受賞作」という言葉には期待よりも警戒感しかないのは、これまで散々騙されてきたから。 英国人が面白いと思う現代ミステリは日本人とは違うのだろうか。 だけど本書は、米ドラマ『FBI: 特別捜査班』や『CSI:科学捜査班』シリーズの英国版とも言えるような国家犯罪対策庁の重大犯罪分析課の活躍を描いていて、面白さは万国共通。 おまけに数学の天才まで登場し、統計分析やデータ解析を駆使して犯人を追い詰めるなど、とてもキャッチー。 テンポもハリウッド並みに小気味よく進むため、本の厚みを感じさせない。 残り100ページを余して犯人がわかってしまうのも驚きの一つ。 それでも魅力的な謎により最後までページをくらせる。 まずはなぜストーンサークルで次々と人を焼き殺されるのか。 そもそもストーンサークルがそんなにいくつもあると思わなかった。 舞台となるカンブリア州だけでも60以上もあるなんて...。 そしてなぜ、主人公であるポーの名が遺体に刻まれていたのか。 わざわざ警官を事件に引き込む犯人の意図とは? 挑発? それとも…。 他にも、なぜ犯人が今になって事件を起こしたのかも、不可解な謎として捜査陣を悩ませる。 つながりの見えなかった被害者を結びつける過去のチャーター便での出来事。 それでも数十年の前の出来事。 なぜ今になってなのか? 本書が単なる謎解き以上の魅力を備えているのは、それぞれの登場人物の出生をめぐる秘密にもあるのだろう。 好きだからこそ別れねはならず、別れる力を得るがために、あえて愛とは対極の行いに走らせる。 事件の真相に過去の卑劣な児童虐待が明らかになる小説は多いが、ポーの名付けの秘密は、これまで読んだこともない斜め上をいくものだった。 名前はこの世で一番短い”呪”と言ったのは、陰陽師の安倍晴明だったか、西洋でも名付けによって人の考えや行動を縛るという考えに似たものがあるんだなと変に感心した。 主人公のポーの強みは何だろう。 一度咥え込んだら離さない執念深さ。 組織の序列を屁とも思わない反骨心。 だけど一番は、その類稀な直感力なのだろう。 ブラッドショーの数理モデルがどれほど頭抜けていても、事件の解決に至る最後の跳躍を後押しするのは、ポーの察知する能力だったと言える。 本事件では、解決前と後に決定的な2つの直観を得ている。 読者はそれら2つにどんな感想を持つかわからないが、得てしてこんなもんだよなというのが自分の偽らざる感想。 途中経過なんてすっ飛ばして天啓のように舞い降りる違和感。 仕事でも何でもそうだけど、課題解決において決定的な差を生むのは、実はこんな「何か怪しいな」というひらめきだったりするんだよな。
0投稿日: 2025.04.08
AIにはできない 人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性
栗原聡
角川新書
私たちが気づかないうちに進化するAI
本書の中で語られるChatGPTと日本酒の醸造のたとえ話は、非常に分かりやすく、AIの学習プロセスを理解する上で重要な示唆を与えてくれる。 日本酒を造るには、米という原料と、それを発酵させる醸造システムが必要だ。 同様に、学習するタイプのAIにおいては、データが原料となり、AIシステムがそのデータを基に大規模言語モデルを生成する。 私たちがChatGPTを利用する際、それはChatGPTというシステムそのものではなく、膨大なデータから構築された言語モデルからの出力、つまり多くの人々の知識や意見を取りまとめたものを受け取っているのである。 このたとえ話は、AIの背後にあるデータと学習というプロセスが、まるで微生物の働きによって風味豊かな日本酒が生まれるような深遠さへの気づきを与えると同時に、これまでの設計された製品自体を使用するというテクノロジー利用とは根本的な差異を教えられる。 著者の理想とする未来をどう判断するかは読者によって賛否わかれるかもしれない。 ただ第7章は本書の読みどころの一つであることは間違いない。 学習データ量や計算リソースを指数関数的に増加させることで、質的な変化が生まれるというスケーリング則は、まるで微細な細胞が集まって複雑な臓器を構成し、個々のアリの行動が予測不可能なアリの行列という集合知を生み出すように、AIにおいても同様の創発的な現象が起こり得ることを示唆している。 著者は、細胞のスケールが臓器のスケールを生み出す一方で、それぞれのスケールには固有の世界があり、異なるスケール同士が同じ世界に登場することはないと述べる。 同様に、個々のアリの行動を理解しても、アリの行列全体の機能を完全に予測することは困難だ。 このアナロジーは、私たちが個々のAIの能力を理解していたとしても、それらがスケール化し、連携することで生み出されるより高次の知能や機能は、私たちの理解を超えたものになる可能性を示唆している。 それは、AIが高度にスケール化することで、私たちはその個々の動作や判断を意識することなく、より抽象的なレベルでその恩恵や影響を受けるようになるのかもしれない。 著者はさらに、小粒AIを束ねてスケール化することで、単体の巨大AIを超える性能を持つAIを構築する戦略や、そのようなスケール化の先に人工超知能(ASI)が見えてくる可能性にも言及している。 もし、私たちが構築するAIが群れることで、上位のスケールのAI、すなわちASIを創発するならば、それはアリの群れが創発する行列の機能を個々のアリからは認識できないように、ASIはそれを創発させたAIを越える能力を持ち、私たち人間、そしてASIを創発したAIでさえ、ASIの知能を完全に理解できないかもしれない。 この考察は、AIの進化が、私たちの予測や理解の範疇を超えて、気づかないうちに全く新しい段階へと進んでいく可能性を示唆しており、深い畏怖の念を抱かせる。
0投稿日: 2025.04.08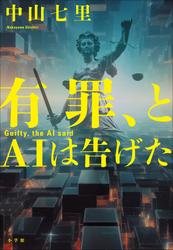
有罪、とAIは告げた
中山七里
小学館
もしAIが人間を裁くとしたら...
著者の力量不足なのか、AIの本質を突く物語を生み出せていない。 AIに対するイメージも古く、その批判も通り一辺倒なものに終始している。 曰く、過去のデータに依拠してるだけなので新しい概念が生み出せない。 分析や再構築はできても創造ができない云々。 事務処理程度で使うならまだしも、人を裁く現場に導入されるのはもってのほか。 人間が手間や時間をかけてこそ、下される司法判断にも情実が感じられるのであって、性急な効率化は百害あって一利なしと。 おそらく著者の中でAIは、単なるスーパーコンピューターや巨大な演算機の域を出てないのだろう。 本書に登場する法神というAIも、拡張性は皆無で、どこともつながらず、中国がレンタルしているブラックボックスの戦略物資の一環として紹介されている。 確かに物語の導入部は期待を抱かせるものだった。 過去のデータや裁判記録、証拠物件、証言などを入力してやれば、実際に下された判決文の通りに結果が出力される。 おまけに裁判官の構文の特徴や判決文の構成まで再現されるというから、懐疑派まで積極導入に宗旨替えさせるほど。 単なる判決文の作成代行ではなく、裁判官のクローン、判断の再現を実現するAI。 法神に個々の裁判官の倫理観や経験をコピーさせれば、もう一人の自分を作れるわけだ。 どうしてこのようなことが可能なのか。 細かく指標ごとに数値化しデータ化させただけなのに、裁判官の個性まで写し取ってしまえるのはなぜなのか? どこを重点的に吟味し、何をどのような基準から評価するかは裁判官個々に違いがあるはず。 にもかかわらず、結果的に本人が下したものと同じ結論に達するのは、どのようなカラクリがあるのか。 AIが人間を裁くことに恐れや躊躇を感じるかもしれないが、実際の判事のコピーが生成されるのであれば、それが裁いていると考えたらこちらの受け取り方も変わってくるのではないか。 単に過去の判決との照合という答えあわせのレベルから、現在進行中の事案の読み込ませによる出力結果の先取りまで進むことで、裁判官本人の判断が微妙に狂っていくなど、ここまではまぁ読ませるのだけれど。 アルゴリズムとして活用するには、あらゆるものを数値化してデータに落とし込む必要があり、その結果生み出されたものが、どうして裁判官個々の個性として再現可能なのか。 ここに魅力的な謎がある。 ミステリなのだから、てっきりこの謎の解明が主題になるのだと思っていただけに肩透かしもいいところ。 なぜか中国による儒教文化の洗脳政策の一環というくだらないオチに至り、思わず「しょうもな」と声に出てしまう。 せっかく法曹界にAIを持ち込むのなら、死刑判決の是非に絡めても面白かったろうに。 驚嘆すべき精度で判決が模倣されるのに、どういうわけか死刑だけは回避して出力されるとか。 あるいは人間の手による判決がそこまで大事なら、そこには数値やデータに還元されない言葉の持つ奥深さがあるのだろうから、そこにAIはどこまで迫れるのかなどを小説にすればもう少し知的興奮が感じられたかも。 裁判官個々の道徳観や判断基準も、温情判決か厳罰判決か、教育刑か応報刑か、更生主義か懲罰主義かの間に限定されていて、日本の司法システムが抱える問題点もそこに集約してしまっているのも、底が浅いなと感じられた。
0投稿日: 2025.04.02
ABAKAHEMPさんのレビュー
いいね!された数249
