
2052 今後40年のグローバル予測
ヨルゲン・ランダース,野中香方子,竹中平蔵
日経BP
子供と孫の世代
読み応えのある本です。 40年後の世界はどうやら、世界平和を実現しているバラ色の未来ではなさそうです。 各分野の専門家が利害関係を気にせずに40年後の未来を語っています。それらを総合してまとめると、このままでは地球温暖化が進み永久凍土が溶け温暖化への制御が効かなくなる・・・。そして、自然が破壊され標高の低い地域が水没、自然災害の激増、人が住める場所が減り、食料や土地をめぐる争いが増える。 すでにこの流れを止めることはできないかもしれない。この本を読んで自分の子供や将来生まれるかもしれない孫に本当に申し訳なく思い、陰鬱な気持ちになってしまいました。一方で本書の後半では、この温暖化制御不能状態はもしかしたら回避できるかもしれない、あるいはそうなってしまうことを少しでも遅らせるための提案、私たちがこれからどのように振る舞うべきかについても書かれています。 私にとっては、これからのこれからの生き方に影響を与えるほどインパクトのある本でした。 一方、少しだけ気になった点として、 本書では太陽光発電により化石燃料を代替することが可能であるといった趣旨の記述、そして近い将来の中国についてとても肯定的な記述がありました。 どうか、これらの記述が正しいことを祈るばかりです。 この2点を鑑みても、少しでも多くの人に読んでいただきたい本であると思いました。
6投稿日: 2017.01.13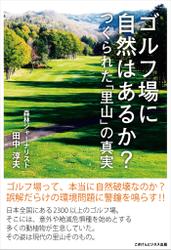
ゴルフ場に自然はあるか?
田中淳夫
ごきげんビジネス出版
ゴルフをしない著者が書いたゴルフ場の本
いつまでたってもスコアが良くならない中、ゴルフに関わる知識を得てそのうんちくを語ることもゴルフの楽しみの一つとしてよい、と聞いたこともあり本書を手に取りました。 環境汚染を引き起こすとのゴルフ場に対する批判を軸に日本におけるゴルフおよびゴルフ場の歴史やゴルフ場の管理に関わる記述が多くあり勉強になりました。このような知識を得ることで、グリーンキーパーをはじめとするゴルフ場(ゴルフコース)の維持に携わる方々や自然そのものに対する感謝の気持ちをもてるようになるのではと思いました。もしかしたらコースに出てボールを打つたびに「(ゴルフができて)ありがとう」と言っているとゴルフがより楽しく、結果としてスコアもよくなったりするのではと思ったりもしました。 本書では今後のゴルフ業界の行方についても触れており、この点についても考えさせられました。 これからゴルフがより身近なものとなり、最低限のマナーなどは守られつつ、多くの人に親しまれるものとなっていくにはどうしたものか、本書を読みながら考えました。
5投稿日: 2016.11.20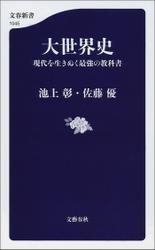
大世界史 現代を生きぬく最強の教科書
池上 彰,佐藤優
文春新書
テレビでも
本書は池上氏と佐藤氏が対談形式で"大世界史"を勉強することの必要性を語っているものです。本書の中で世界史に"大"が付くことの意味が説明されています。 現在世界的な問題になっている事案毎に両氏の知識に基づく考え方が紹介され、そこからこれからの世界を生きていくため、あるいは生き残るための知識として、大世界史を勉強することの必要性につなげられています。両氏の知識の豊富さに深い感銘を受けると共に本書の中で強調されていた点「細部を暗記することではなく、歴史上大きな出来事毎に俯瞰的に知る」ことについて強く共感しました。個々の事案毎の議論は両氏の知識をもってすればそれだけで本になると思われるが、あえて少々物足りないと感じさせる量の文章で記述させている印象を持ちました。物足りなさを感じた人は是非自身で大世界史の勉強を始めてほしいとのメッセージであると理解しました。 書中にある池上氏の発言の中には驚くようなこともありました。同じことを出演されているテレビ番組で説明して頂ければテレビがとても面白くなるのではとも思いましたが、まあそうもいかない事情がきっとあるのでしょう。
6投稿日: 2016.10.19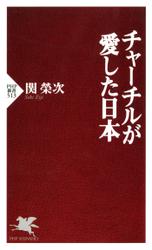
チャーチルが愛した日本
関榮次
PHP新書
福沢諭吉のような
自身の経験と本書からイギリスにおけるウィンストンチャーチルの存在は、日本における福沢諭吉に重なるものがあるのではと感じました。 理由: 1. イギリスで放送される歴史番組の中で紹介されるウィンストンチャーチルに対する評価からそのように感じたこと。 2. 本章の中で紹介されたウィンストンチャーチルの言動や思考パターンが、現在のイギリスにおいてリーダとして立っている人たちの思考パターンと類似性を持つように感じられること。 つまりその位ウィンストンチャーチルは今も多くの人々から尊敬され、リーダーとなる人の手本として意識的無意識的に関わらず影響を与えていると感じられたこと。 そのウィンストンチャーチルが日本に対して好意的な考えを持っていたことは本書を通じて知りました。 にも関わらず日英同盟が破棄されてしまいました。その背景には、特に日本側の極少数の人たちの個人的信条や信念に基づく決断が影響していたことが分かりました。ここから、大変多くの人に影響を与える一国の進むべき道を決める決断がごく少数の人たちの考えで決められることがあるということに感慨を覚えました。 当たり前ですが、リーダーの大切さとリーダーを選ぶことの大切さを改めて思い知らされました。
5投稿日: 2016.10.12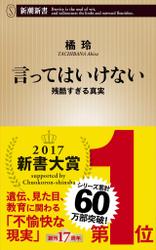
言ってはいけない―残酷すぎる真実―(新潮新書)
橘玲
新潮新書
なぜこんな本を書いたのか?それは、世の中に必要だから。
誰も口には出さないが、多くの人がきっと人間でこうなんだろう?実は世の中ってこうなんだろう? ということが、遺伝学的あるいは様々な調査結果をもとに書かれています。すくなくとも私にはそう感じました。 きっと、世の中を動かしている人たちはこのことを経験的に学んでいて、あるいは経験的に学んだ人たちから非公式にそのようなことを伝授され、それを基にいろいろな仕組みを作っているのだろうと思いました。そのような意味では、私にとってはあと30年早く読んでおきたかった本です。 世の中の倫理観に合わないこと、世の中で一般的にこうあるべきということと対立すること、でも現実ってこうだよな、ということが書いてあります。 ここで中身を書いただけで非難にさらされそうなので書きません。この本を読んだ人は本の内容を周囲の人に話さない方が良いです、周囲からのあなたへの評価が下がるかもしれないからです。あなたがこの本から得た知識は、あなたの心にとどめておき、あなた自身が何かの決断をする必要があるときの参考にされるのが良いです。 私が住んでいたことのあるイギリスでは、いろいろな社会の仕組みが、建前でなく、この本に書いてある現実的な内容により基づいて作られているように感じました。ひょっとするとその方がみんなが幸せになるのではとも思いました。 以下は本書から得た私の感想です。 遺伝や生まれた環境で、持っているものは違うかもしれないけど、 人生にとって大切なことは自身が幸せと感じるかどうか。そして幸せと感じるかどうかと、あなた持っている能力、資産とは必ずしも比例しないはず。 人生を価値あるものにするには、どんな分野でも良いので幸せになるように努力すること。 などと思ったり(自分に言い聞かせたり)しました。
12投稿日: 2016.08.14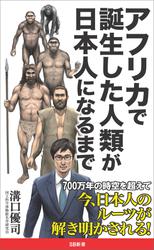
アフリカで誕生した人類が日本人になるまで
溝口優司
SBクリエイティブ
日本人はどこからきたのか?
タイトルの通り、日本人はどころから来たのかについて丁寧に記述された本です。 一方、日本人だけにフォーカスせず、人類が始まって以来の歴史に関する説明や、化石の調査解析手法など人類学の基本的な事柄にもふれられており勉強になりました。 最近、この分野の本に興味がありつい手に取っております。 なぜそうなのかというと、人という種がこの世界に現れてから現在までの多くの期間、人はどうしてきたのかを知ることで、人は本来どう生きるべきなのかという答えが見つかるような気がしているためです。つまり、現代の世界は人の歴史からすればとても変わった状態であると敢えて考え、現代になる以前の人の生活様式の中に、本来、人が取った方が良い生活の仕方へのヒントがあるのではないかということです。 まあ、私が勝手に思っていることですので、皆さまは気になさらないでくださいね。もちろん、原始時代の生活に戻りたいと思っているわけでもありませんし・・。(エアコンの効いた部屋でこのコメントを書いています。)
4投稿日: 2016.08.10
ヨーロッパから民主主義が消える
川口マーン惠美
PHP新書
ヨーロッパについて
仕事その他でヨーロッパと関わりが多いこともあり本書を手にしました。 EUの歴史から始まりその仕組みについて丁寧で分かりやすい説明がありとても勉強になりました。 その後、最近よくニュースなど紹介されている経済問題と難民問題、テロについて現状、背景等々解説されています。 感想:状況を知れば知るほど難しく解決が困難であることが身に染みてきました。 それゆえに、それぞれの問題について解が見えず、この先いったいどうなることか、なんとも言えない気持になります。 本書が出版された時点ではイギリスのEU離脱は決まっていませんでしたから、今現在の状況は本書にさらに輪をかけて複雑化していることが想像できます。 かの地の様子を知り、日本はどうするべきか、そして私達一人一人はどうするべきかを考えるための参考になる良い本だと思います。
4投稿日: 2016.07.24
フードトラップ 食品に仕掛けられた至福の罠
マイケル・モス,本間徳子
日経BP
この世に残すべき本
本書はアメリカの加工食品業界の状況について大変詳しく書かれています。 目標の性能を出すために最適に設計された機械を開発するのと同じように、加工食品は、いかにたくさん食べてもらえるかに焦点を絞り各種の変数を最適化しながら設計されていることが分かりました。そこには、製品を食べた人が健康でいられるかについては考慮されていないことが書かれています。 本書をこれから読まれる方は、アメリカと日本とでは状況がいくらか異なる可能性があること、本書が出版されやや時間が経過しているため本書に書かれている状況と比べ現在ではいくらか状況が改善している可能性を考慮されてはと思います。 本書はボリュームがあり、気晴らしに読むには少々努力のいる本ですが、私たちが知っておくべき情報を集約した書物として価値があるものだと思います。 とかく健康に悪い製品を製造販売する企業に批判が行きがちですが、私たちが何を食べるかを最終的に決めるのは私たちであることを考えさせられました。
6投稿日: 2016.06.11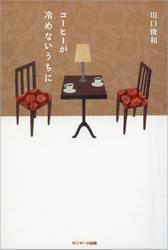
コーヒーが冷めないうちに
川口俊和
サンマーク出版
電車の中では・・・読めません
通勤電車内のドア近傍に掲載されていた本書の広告を見て、満員電車でもまれる中、その場で購入・ダウンロードしました。なんと便利な世の中でしょう。 本書のポイントは制約の多いタイムトラベル。この制約そのものが物語に意外性そして切なさを持たせ、面白くしています。 年を取るにつれ涙もろくなったこともあり、触れ込みの通り、4回以上泣きました。 いいおっさんが電車の中で泣くわけにもいかず、電車の中で買った本でしたが、電車の中では読めませんでした。
18投稿日: 2016.06.04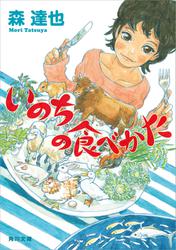
いのちの食べかた
森達也
角川文庫
良い意味で、
以前読んだ本のコメントに、本のタイトルと中身が違うことに少々苦言を呈したことがありました。 本書でも、タイトルから受けた印象と内容に差異を感じましたが、このことが本書では私にとって良い印象につながりました。 どうか、本書のタイトルと表紙を見て受けた印象のままこの本を手に取ってみてください。 すると皆さんが、これまで気にしていなかったけど大切なこと、悪気がなくても目をそらせてしまっていたことに心を傾ける良い機会になります。 本書は子供向けの本のように分かりやすく書かれています。ですが、ぜひ大人の皆さんも読んでみてください。
5投稿日: 2016.05.12
たかじ56さんのレビュー
いいね!された数262
