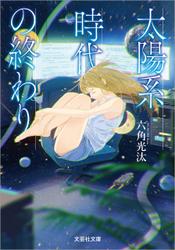
太陽系時代の終わり
六角光汰
文芸社文庫
これは読者の想像力?イメージ構築力が試されるかな
物語の内容は、作品情報に書かれていたり、他の人のレビューに書かれていたとおりのですが、作者の頭の中に描かれているであろうイメージが、果たして読者である私の頭にの中に描いているイメージが同じものかどうか、それがちょっと心配になりました。三次元のものが二次元に見えると言われても、私の拙い想像力では、う~んと唸ってしまいます。 物語自体は大変興味深いもので、ページをめくる手が止まることはありませんでした。ただちょっと尻切れとんぼかな?他の人が書いておられるように、この先が知りたいと切に思います。
0投稿日: 2024.04.08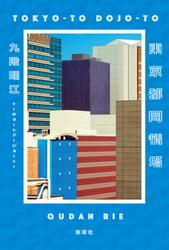
東京都同情塔
九段理江
新潮社
同情塔の効能?には疑問だが、言葉の深淵について考えさせられた
芥川賞受賞ということで、手に取ってみました。 言葉というモノは、本当に難しいものなんだなと実感した次第です。物語の最初の方で「東京タワー」という名称についてのエピソードがありました。確かに、もし「昭和塔」という名前だったならば、スカイツリーができた今、それでもなお東京のシンボルになっていたかは疑問です。AIで文章を綴るようになったとき、そのような未来予測ができるのでしょうか。また、東京同情塔ではなく、東京都同情塔という名称についての考察も、う~んと唸ってしまいました。確かに、たった一文字付け加わっただけで、印象は全く違ってきますね。 全体を通して様々な気づきがありましたが、個人的には「東京都同情塔」なるものに賛成はできないないなぁ。このような施設に入ることで、果たして人は幸せを、そして生きる満足感を感じるものでしょうか? それがどうも最初から引っかかって、物語そのものにはのめり込むことができませんでした。芥川賞選評の中では、平野啓一郎氏の選評がなかなか興味深いものでしたよ。
0投稿日: 2024.04.08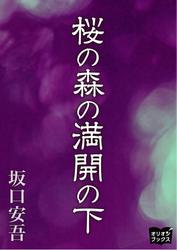
桜の森の満開の下
坂口安吾
オリオンブックス
桜が咲く季節に読むには、ちょっと怖いかな?
桜は、とくにソメイヨシノは全てがクローンなので一斉に咲きますよね。葉もなく、しかも並木のように植えられ一度に沢山の花を見ますので、誰もが不思議な高揚感に包まれてしまうものです。ある意味人を狂わせてしまうのかもしれません。そんなことがモチーフになっているのかどうかはわかりませんが、恐ろしい話ですよ。しかもこれに美しい女性が絡むとなると。。。男は両方に惑わされたのかもしれませんね。 短編ですが、サクラ散る木の下で読むと、なお一層雰囲気が出るかも。
0投稿日: 2024.04.08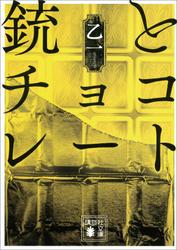
銃とチョコレート
乙一
講談社文庫
途中までは乱歩の少年探偵団風。それが次第に乙一テイストに……
皆さん指摘されているように、漢字が少なく平易な書きぶりで、大変読みやすい小説でした。しかも、前半部分は、江戸川乱歩の少年探偵団みたいな感じで、ちょっといつもの雰囲気と違うかなぁと思っていましたら、後半あたりから、乙一テイスト全開のミステリーサスペンスとなり、物語にどんどん引き込まれていきます。 さぁて乙一さん、どう結末をつける?と気になって気になってページをめくる手が早くなりました。文章は平易ではありますが、内容はハードです。もし映像化されるとしたらR指定は確実かもしれません。単なる謎解き小説では終わらないのが、乙一ワールドですね。
0投稿日: 2024.03.03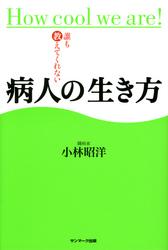
誰も教えてくれない病人の生き方
小林昭洋
サンマーク出版
いずれその時が来たら、私もプロの闘病家となるために。。。
私も何度か手術とは言えないような手術をしましたが、最長で2泊3日の入院生活した経験しかありません。でも人間の死亡率は100%ですから、事故か災害で命を落とさない限り、病気を抱えて長期かどうかはわかりませんが、闘病生活を送ることになるでしょう。その前にこの本に出会えたことは、一つの邂逅だったかもしれません。 闘病家という言葉を知るだけでも価値があるというモノです。自分がそのような状況になったら、もう一度目を通したくなるでしょう。また一方、辛いことから逃げようという「自殺」についての記述も興味深いモノがありました。不治の病にならなくとも、何か耐えきれないような辛いことから逃げようと死にたいと考えたとき、もし自殺したらどうなのだろうとイメージするというのは、一つの解決策かもしれません。 自殺じゃないような完全犯罪的自殺はない。プライドを保ったまま自殺することは出来ない。だから、諦めてください。生きましょう。自然死を待って、生きていきましょう。人は誰でも死にます。ずっと死ねないことはありません。死にたいなんていつまでも往生際が悪いことを言わずに、生きると覚悟しちゃってください。と著者は書いております。このフレーズは、結構突き刺さるフレーズじゃありませんか?
0投稿日: 2024.03.03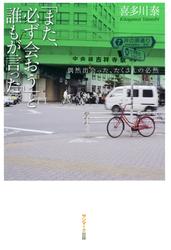
「また、必ず会おう」と誰もが言った。
喜多川泰
サンマーク出版
珠玉のフレーズで彩られた、最高のアオハルロードノベル
友達に対して、ちょっとカッコつけて嘘をついてしまう、結構若い頃はありますよね。そこから物語は始まり、親にまで嘘をついて、写真を撮るという目的だけのために、ディズニーランド向かうわけですね。これで問題解決、といかないところが小説です。ありがちなハプニングで家に帰れなくなってしまうわけです。 その大ピンチが発生したために、少年は様々な人々に出会い、お世話になりながら、一回りも二回りもデッカくなって家に帰って来るという、1人の少年の成長物語でした。 確かにフィクションで、世の中こんなにいい人ばかりじゃないし、こんなにうまくいくわけない、と思うのではありますが、そんなことを差し引いても、これはすばらしい青春小説であります。もし主人公と同年代の頃読んだら、ひょっとすると私の人生も変わっていたかも?なんていうのは言い過ぎかも。 人生は、出会いと別れ、一期一会の出会いで人生変わってしまうこともあるでしょう。中高生に是非読んで欲しい本ですが、私のような前期高齢者でも、ちょっと感動すること請け合います。調べてみると映画化もされているんですね。そっちも観てみたいですね。
0投稿日: 2024.02.05
ねえ神様、なぜわたしにネズミをくれたの?
上原愛加
サンマーク出版
あなたにとって幸せってどういう状況のこと?
「どうしたら幸せになれるんだろう」この疑問を主人公が呈するところから物語は始まります。でも問題は、彼女にとって、どういうことが幸せなのか、これが一番重要だと思うんだけどな。 被災地で、電気も水もなく、寒くて寒くて眠ることさえできない避難生活をしている人は、今1枚の毛布さえあれば、と思うでしょうしね。だから、どうしたら幸せになれるのか、という問いは、まさに今、幸せの実感がないことにほかなりませんが、自分にとって、どうなることが幸せなのかを、まず問わねばなりません。 そして著者の言う、「誰もが持つ、心の中の悲しみを抱きしめる。」というのは、結局、自分の幸せは他人の幸せを慮ることに繋がるのかもしれません。 NHKの番組「ドキュメント72時間」というものがあります。おそらく企画当初では、このような内容になるとは思わなかったのであろう奇跡のような番組だと思います。一カ所に三日間カメラを据えて、そこを訪れる人々にインタビューを行うという単純な内容ですが、人それぞれ皆、実に様々な悲しみを抱いて生活していることがわかります。その悲しみを共有することはできなくても、寄りそうことはできるのかもしれません。テーマ曲「川べりの家」の中で松崎ナオは、こう歌います。「幸せを守るのではなく、分けてあげる」こんな風に生きることができるならば。。。。
0投稿日: 2024.02.05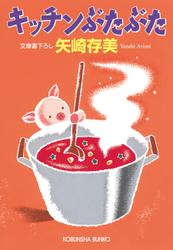
キッチンぶたぶた
矢崎存美
光文社文庫
時々、無性に読みたくなるシリーズです。今回選んだのはコレ。
何故か時折、この作品の雰囲気に浸りたくなる不思議な小説です。何作もシリーズがあり、どれから読んでも大丈夫というところもありがたいですね。パティントンか、テッドみたいな映画化はされないのでしょうかねぇ。絶対面白いモノが出来上がると思うのですが。 さて今回も、モフモフの中にほのぼのとしたモノを感じさせる珠玉の4編です。ホフホフのぬいぐるみがキッチンで料理しているのを想像するだけで、なぜか幸せな気分になりますし、一つ一つの話が、そうだようなぁと思わせてくれるのも嬉しい限り。 でもそのなかで、ちょっとだけ異色だったのが「鼻が臭い」という短編でした。コレについては作者の矢崎さん自身が「あとがき」の中で自身の鼻の不調がきっかけと書いておられました。 ま、兎に角、安心の一冊であります。
0投稿日: 2023.12.31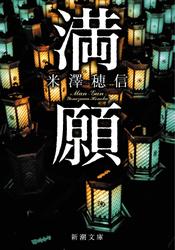
満願(新潮文庫)
米澤穂信
新潮文庫
私が一番好きな話は。。。。
6編の短篇集なのですが、流石ですね。一つ一つの話は短いながらも読みごたえがあり、充実した感じでした。 中でも私が一番好きなのは「関守」かな。語り手が殺されてしまう話はよくある手法かもしれませんし、途中から結末が見えてくる気もしますが、危ないぞ?大丈夫か?なんて感情移入してしまいました。人里離れた、滅多に人が来ないような峠の茶屋でおこる話は、如何にもありそうな感じで怖いですね。他の皆さんが絶賛している「万灯」もスゴイのですが、私には海外赴任の経験がありませんのでね。 人は誰もが心に闇を抱えているのでしょう。それは誰にも知られてはいけないことなのです。きっと。
0投稿日: 2023.12.03
都市と星(新訳版)
アーサー・C・クラーク,酒井昭伸
ハヤカワ文庫SF
タイトルからは想像できないくらい壮大な物語でありました
アーサー・C・クラークの小説を読むと、どれを読んでも現在のSFの元になっているように感じます。この作品は調べてみると1956年に発表されたそうで、その創造力・空想力たるや驚愕ものです。今でこそ、ストーリーに描かれている場面を読者である我々は、何となく今まで見てきた映画やドラマをもとに頭の中で描くことができますが、発表当時に読んだ人はどうだったのでしょうか。そんなことさえ感じます。 さてもし、この小説に世界に生きていたら、ダイアスパーとリスのどちらの都市に住みたいでしょうか?人間が不老不死を願ってきたのは紛れもない真実ですが、私はどうかなぁ。それはそれでしんどいような気がしますけどね。 というわけで、タイトルは「都市と星」というものですが、人間の幸せって何?ってところまで問題提起しているような気がしました。さすがはアーサー・C・クラーク。SFを遙かに超えております。
0投稿日: 2023.11.02
くっちゃね村のねむり姫さんのレビュー
いいね!された数863
