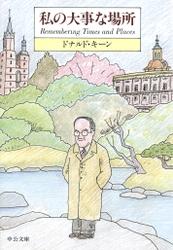
私の大事な場所
ドナルド・キーン
中公文庫
交友範囲の広さに驚嘆!
書籍の説明に、自伝的エッセイとありますが、中身はエッセイだけでなく、講演記録あり、講演の元原稿ありで、その語られている内容はまことにバラエティーに富んでいます。 とにかく文章がよみやすくわかりやすい。よく英語圏の人の話す英語より、そうでない人の方が、聞き取りやすいと言いますが、まさにそんな感じ。こんな日本語の文章を書ける文筆家はそういないのではないでしょうか。 そして、出てくるは出てくるは、私の知っている有名人は勿論、存じ上げない有名人?の数々…。多彩な著名人と交流されたことがよくわかります。おそらく氏の人徳のなせるところなのでしょう。 気軽に読めて、それでいてちょこっと教養がつきそうな一冊をお探しなら、これおすすめです。
4投稿日: 2014.01.14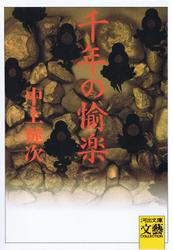
千年の愉楽
中上健次
河出文庫
じとっ!湿度の高い小説、いや物語
じめじめと言うより、じと~?これは、したたる汗のためか?あふれでる体液なのか? この本を読む前に、ドナルド・キーン氏の著作を読んだせいか、最初のページからものすごく読みにくい。一文が長いのだ!それが一種独特の雰囲気を醸しだし、わけのわからない世界観に我々を誘い込む。 オリュウノオバという巫女のような産婆さんを中心に話が展開するが、何が何だかよくわからない。とにかく抑圧された世界の中で、中本と呼ばれる一党が「路地」の中と外で蠢く世界。ここで表される「愉楽」とはいったい何か? 私の電子ブックでは、総ページ606ページであるが、500ページ以降、吉本隆明と江藤淳の解説?に費やされている。これを読んで、あーそういうことだったんだと納得した次第。この二人の解説は、必読ですよ。 解説を読んだ後、また読み返したくなる、後を引く、小説いや物語であります。
0投稿日: 2014.01.13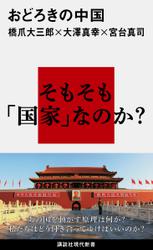
おどろきの中国
橋爪大三郎,大澤真幸,宮台真司
講談社現代新書
座談会ではなく、鼎談です。
あの「ふしぎなキリスト教」のお二人に加え、今回は宮台真司氏が加わった鼎談。 ポイントは、大澤氏、宮台氏が、それぞれ1958年、1959年生まれ。橋爪氏が1948年生まれという年齢構成と、橋爪氏の奥さんが中国人であること。そして、鼎談に先立ち、このメンバーで中国を旅行したという点。おそらく普通の観光客が行かない場所や行けない場所も訪ねたのでしょう。 ま、それはともかく、内容の構成上は、大澤氏と宮台氏が問題提起をして質問をまとめ、橋爪氏がそれに答えるといったパターンで進みますが、質問する二人も学者さんですから、当然、アホみたいな質問はしないわけで、結構読み進めるのに骨が折れます。難しい語句もバンバンでてきます。だいたい私は、「鼎談」だって思わず意味を調べましたもの。 そして、肝は、アマゾンのレビュー等でも問題となっている最後の「中国のいま・日本のこれから」という最後の項目についてです。 この本を批判する人は、あまりに中国寄りだと思うようですが、そう思うより中国の人は、そもそもこう思っている人が多いと考えた方が良いでしょう。 なぜ日本人の「常識」が彼らに通じないのか?という点については、きっとそうなんだろうなぁと思わせる点が多々述べられていて、私にはとても面白く感じました。 それよりひっかかかったのは、宮台氏の日本についての発言、日本は「まかせて文句をたれる作法」であって、「引き受けて考える作法」ではない。という点です。これは的を射ていると思います。昨今の諸々の情勢など、まさしくコレそのものではないですか?
3投稿日: 2013.12.19
テロリストのパラソル
藤原伊織
角川文庫
さすが圧巻のダブル受賞作
作者の藤原氏は、1948年の2月生まれ、私は、1959年の2月生まれ。 私自身は大学紛争を体験しているわけではありませんが、まだ学内にはその残り香みたいなモノはありました。教授陣達が体験者でしたからね。 さて、この物語はこの大学紛争が発端となっていますが、まず導入部分で、主人公の正体さえわからない。コイツはいったい何者なんだ?なんて考えている内に、ストーリーに引き込まれ、ページをめくる手ももどかしい状態になることうけあいです。 さすがに、乱歩賞と直木賞を同時に受賞しただけのことはあります。 ただ、凝った内容と引っ張った展開の割には、謎解き部分があっさりした感はあります。でも、単なるミステリーに終わらず、かの時代のある種の熱気と、そして何も変わっていない現代への一抹の寂しさに思いあぐまざるを得ない作品です。 この作者にはもう少し長生きして欲しかったな。
3投稿日: 2013.12.07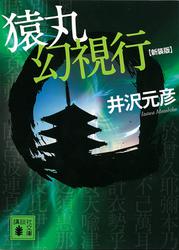
新装版 猿丸幻視行
井沢元彦
講談社文庫
知的好奇心をくすぐるミステリー
あの逆説の日本史、言霊の井沢元彦先生が記者時代に書かれて江戸川乱歩賞をとったという作品。文献主義の歴史観をこの頃から、チクッと批判されています。 さすがに面白いです。この作品以降、和歌等を読みとく話がいくつか出ましたけど、これこそ本家本元でしょう。 ただ、現実世界から薬によって意識を明治にタイムスリップさせるという設定は、どうなのかなぁ。必要があったのかなぁ。舞台は明治時代だけにして、折口信夫だけが主人公の方が、わかりやすい気がします。ま、そうするとタイトル名から考え直さねばなりませんが…。 また、「今だその機にあらず」と村人集めて語りかけるシーンは、どこかの藩の話として聞いたような気がするし、最後に南方熊楠まで登場するとなると、ちょいと凝りすぎといった感じかな。 とは言え、横溝正史ばり和の歴史ミステリーは、読み応えがありますよ。古代史、古典 文学に興味がある方も是非…。
0投稿日: 2013.11.21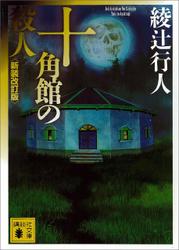
十角館の殺人〈新装改訂版〉
綾辻行人
講談社文庫
密室殺人の古典?
何かの折に、綾辻さんの名を知り、初めて読ませて頂きました。 面白いです。 たぶんミステリー好きには、なんとなく結末が見えてくるかもしれませんが、でも、一気読み確実ですよ。
0投稿日: 2013.11.16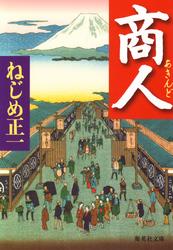
商人
ねじめ正一
集英社文庫
本来の商人とは…
サラリーマンの家庭に育ち、自分も典型的なサラリーマンであった私には、「あきんど」の心意気ってのは、正直わかりません。 というわけで、とても興味深く読ませて頂きました。 お客様の笑顔こそ商人の喜びというのは、拝金主義に凝り固まり、パソコンの前でマネーゲームに明け暮れる現代の金持ちとは一線を画します。 ただ、ものすごく苦労して店を建て直していく過程については、今ひとつ大変さがピントくるものがありませんでした。けっこう優雅じゃんと思ったりして…。世の中にはもっと極貧にあえいでいる人が大勢いますからね。 ちたみに、鰹節は我が家の味の必需品です。我が家の鰹節削り器は、大枚はたいて購入した日本橋「にんべん」製です。もっとも削るのはスーパーで売っている鰹節ですが、これで毎朝私が削った鰹節で、味噌汁を頂いております。
1投稿日: 2013.11.11
日本の選択 あなたはどちらを選びますか? ──先送りできない日本2
池上彰
角川oneテーマ21
いつ読むか?
池上彰さんの解説はとても明快で、明解です。でも、あまりに著作が多くて、どれを読んだら良いか迷いますよね。 オマケに、この手の本は、リアルタイムで読まないと、情報が古くなってしまいます。 この本は、「あなたは、どちらの考え方ですか?」という問題提起形式で、とくにわかりやすいと思います。とにかく、早く読んでおかないと、過去問になってしまいます。いつ読むかって?そりゃあなた、イマでしょ!
1投稿日: 2013.10.23
ドグラ・マグラ(上)
夢野久作
角川文庫
紛れもなく天下の奇書です
夢野久作という作者を初めて知ったのは、予備校の授業だったと思います。 「これを読む者は、1度は精神に異常をきたすと伝えられる」との宣伝文句に、刺激が強いんだろうなと、まず、瓶詰の地獄、少女地獄、押絵の奇蹟などの短編を経て、禁断の書に触れたのは大学の時。ところが、はやる気持ちを抑えきれず急いで読んだ1度目は何を言ってんだか、よくわかりませんでした。で、2回目は、じっくり。そして初めて内容がつかめたその晩……、ヘンな夢をみました!以来、時々読み返してみる私の愛読書であります。
0投稿日: 2013.10.04
庶民は知らないデフレの真実
森永卓郎
KADOKAWA
1番わかりやすいデフレ解説書かも
いよいよ消費税が上がるそうな。でもその前に、デフレっていったい何なのか学んでおきましょう。 デフレ大賛成だったのに…と、思っている人も実はいるらしい。森永卓郎先生が、例の調子でとてもわかりやすく、そして皮肉っぽく解説しています。あ~そうなんだぁと、思うこと請け合いです。
1投稿日: 2013.10.02
くっちゃね村のねむり姫さんのレビュー
いいね!された数863
