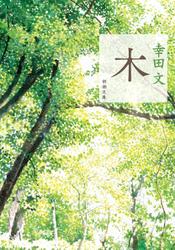
木(新潮文庫)
幸田文
新潮文庫
あの映画の中で、あの人が愛読していた本です
映画「PERFECT DAYS」を見た人ならば、おそらく興味を抱く一冊だと思います。幸田文の著作にこのような本があるとは知りませんでした。なんでもお亡くなりになってから出版されたようです。 単に自然礼賛というよりも、林業にも注目しているところがとても好感が持てます。実は私は、農学部林学科卒業です。もっとも専門は山地防災の方ですけれども。 あんな風に専門家と共に歩くことが出来たならば、充実した散策ができるのも当然かもしれませんね。ちょっとズルイかな? あの知る人ぞ知る西岡一族?とも親交があったようで、楢二郎さんの言葉、「大工という職業は(中略)みんな小さく減らしていく仕事」というものには、なるほどと目からウロコでありました。そんな風に考えたことはなかったですね。ただ、クスノキがうっとおしい木というのは、わからなくもないですが、防虫作用についても触れて欲しかったかなぁ。ちなみに我が家の木魚はクスノキ製でありますよ。 また随所に文学的表現もあり、「紅葉黄葉ほど美しい別れ、あるいは終わりはない、こんなきれいな老いの終わりが、ほかにあろうか、と毎年の黄葉をうっとりと見る、」というところなんぞは、今後紅葉を見る目が変わる気がします。それに、ポプラがマッチの軸木として価値が高かったなんて話は、全く知りませんでした。今でもマッチは売っているには売っていますよね。何の木の材質で作られているのでしょうか? この本は、樹木についての蘊蓄を知ろうとする人も、また自然を愛する人にもピッタリと思います。細かい章に分かれているし、文体は優しいので、とても読みやすいですよ。
0投稿日: 2025.06.24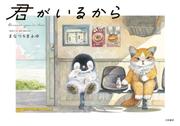
君がいるから
まなつ&まふゆ
大和書房
まさに大人向けに書かれた絵本。今後も時々ページを開くでしょう
分類としては児童書となるのでしょうが、中の文章は通常の小説のように漢字が使われていますし、それにフリガナはふってありません。まさに大人向けに書かれたイラストエッセイ?のような一冊でした。 なぜペンギンさんと猫さんなのかはわかりませんけれど、ベストチョイスですね。そして、誰にとっても一人ぐらいは、かけがいのない友人、知人、あるいは家族がいるものです。読み終わった後は、無性にその人に会いたくなりますよ。君がいるから、ここまでこれた、ありがとうと私も言いたくなりました。
0投稿日: 2025.05.30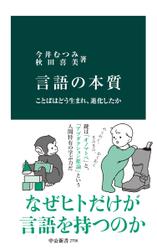
言語の本質 ことばはどう生まれ、進化したか
今井むつみ,秋田喜美
中公新書
実に興味深い、面白いエピソードが満載。言葉ってそもそも何?
我々日本人は、頭で考えるとき日本語で考えますよね。人間はそれぞれの言語を駆使して頭の中で様々な事を考えるわけです。もし、言語というものがなかったら、どうなるんだろう。そんなことを時々思います。 この一冊は、言語のとても興味深い問題を、まずオノマトペから考察を始めます。 日本語はとてもオノマトペが多い言語です。しかも、自由に作って独自の表現にも使用します。私事ですが、ワープロなるものが世に出て初めてそれを手にしたとき、オマケにブラインドタッチの教則本がついてました。 ワープロを使うには、まず入力に用いるのにローマ字入力か日本語入力かを選ばねばなりません。私が躊躇なく日本語入力を選んだのは、オノマトペを書くのにローマ字入力では入力しずらいだろうとの判断でした。この選択は間違いなかったとは思いますが、もしローマ字入力を選べば、英文タイプライターを使うのに苦労しなかったかもしれないのですけどね。 閑話休題。このオノマトペについて、外国人であっても、また、そのオノマトペを初めて耳にする日本人でも、想像で何となく理解できてしまうのはなぜか?ということについて、面白い言及がありました。 そして次第に話は、言語の深淵に向かっていきます。この手の問題に興味のある方は、必読の一冊だと思います。
0投稿日: 2025.04.29
ゲーテはすべてを言った
鈴木 結生
朝日新聞出版
「ゲーテ曰く」このフレーズを私も会話に使ってみようかな?
著者の教養の深さが垣間見える小説でありました。これは芥川賞の選者である島田雅彦さんや平野啓一郎さんが好きだろうなぁと思ったら、文藝春秋の選評にお二人とも「ペダントリー」という言葉を用いて評しておられました。私はこの「ペダントリー」という言葉を知りませんでして、調べてみましたら学問や知識をひけらかすこと、だそうです。まぁ、確かにそういうきらいはありますが、ここまで一つの物語にまとめ上げたのはスゴイと思います。とは言え、著者の教養の広さはホントに半端ではありません。初めてのステレオ映画だったあの「ファンタジア」も出てきますし、恥ずかしながら私は、「魔法使いの弟子」がゲーテ作とは存じませんでした。ちなみにファンタジアは、私をクラシック音楽に誘った映画でした。帰りにレコードを買ってもらったことを覚えていますよ。 閑話休題、ただ、登場人物の名前が独特すぎませんか?とても普通では読めませんよ。どこから発想したのでしょうか?
0投稿日: 2025.03.30
DTOPIA
安堂ホセ
河出書房新社
大変面白く読み進めましたが、途中から。。。少々盛り込み過ぎ?
かつて一世を風靡した恋愛バラエティーを思わせる、南の島での恋愛バラエティー。 美女一人対して 大勢の男が競い合う番組?ではあるけど、何台ものカメラで撮影されており、視聴する側は、自由に場面を切り替えられ、しかもサブスクで結論から見ることが出来る。う~ん斬新な設定ですね。この大勢の男に黒人がいないなぁ、ということは、結構最初の方で気がつきました。そして、「2024年の娯楽トレンドは、白人による白人のための懺悔ショー」という作者の言葉も、な~るほどと思わせるものがありました。 しかし、◇の次からは、少々込み入っていて理屈っぽく、私には読み進めていくのが面倒になってきました。 現在の様々なあらゆる問題に対して、著者は言いたいことが一杯ありすぎるのでしょう。文藝春秋にあった「受賞のことば」には、「小説は書くまでに時間がかかるし、(中略)今のことを書けば書くほど、どうしても古さが際立つこともあると思います。」とありました。今書かねばならない事柄は沢山ある。そのことは、わからなくもありませんし、それを一つの物語にしてしまう著者の力量たるやスゴイとは思いますが、もう少し絞った方が私にはありがたかったかな。
0投稿日: 2025.03.30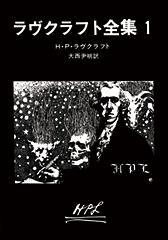
ラヴクラフト全集1
H・P・ラヴクラフト,大西尹明
東京創元社
ぞわぞわ、ジワジワと迫ってくる恐ろしさでありました。
初めてこの作者の小説を読みました。入門書としてはちょうどよいと、どなたかのレビューにあったものですから。 短篇集ではありますが、読みごたえがありました。怪奇小説というのは、単なるホラーともサスペンスともミステリーとも少々違う気がします。訳者のあとがきにあったとおり、恐怖という物は、当人の想像力の働きに由来する物で、読者の想像力がより一層試されるのでしょう。 私が一番好きなのは、いや好きというのも違う気がしますが、「壁のなかの鼠」かな。古典的怪奇小説をまだ読んだことない方は、1度手に取って見てはいかがでしょうか。
0投稿日: 2025.03.01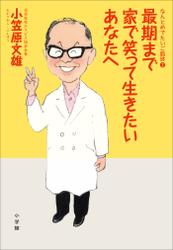
最期まで家で笑って生きたいあなたへ なんとめでたいご臨終2
小笠原文雄
小学館
緊急入院ならぬ「緊急退院」、病院は病をなおす場所、では家は?
なんとめでたいご臨終第1段を読んだのは4年ほど前です。続編?にあたるこの本は、より具体的に書かれていました。病院はあくまでも病気をなおすところであり、めでたくご臨終となることをよしとはしません。では、どう考えるか、これは個人個人の問題でしょう。「いのちの長さ」と「いのちの質」このどちらを選ぶことが幸せなのか、確かに人それぞれかもしれません。 在宅医療。この本を読んでから私も住んでいる街の「在宅医療」をネットで検索してみました。結構色々整備はされているようです。どの程度かはわかりませんけどね。 ただそれも、なにもわからないような認知症状になったら、どうしようもないかもしれません。人の死亡確率は100%、最後の最後に最期をどこで過ごすのか。私もそんなことを考える歳になりました。私はどこで臨終を迎えるのでしょうか?
0投稿日: 2025.01.30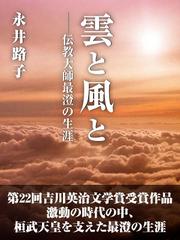
雲と風と ――伝教大師最澄の生涯
永井路子
ゴマブックス
小説というより、調査研究の成果をまとめた感じかな?
私自身は、共通一次試験(古いね)が実施される前の理系の受験生であり、世界史を選択したため日本史については教科書程度の知識もおぼつかないのが、正直なところです。でも、最澄や空海は勿論知っておりました。それでタイトルにひかれてこの本を手に取ったわけですが、ちょっと難しかったかなぁ。 中身は著者による詳細な勉強結果のようなスタイルでありました。 弘法大師は知っていても、伝教大師という称号は全く知りませんでしたし、延暦寺がこのような経緯をたどったというのも知りませんでした。ただ、純粋な小説のスタイルではありませんので、その意味では少々読み物としては、もどかしい気もしました。筆者が言いたかったのは、ラストの数ページに凝縮されていたよう思います。栄西も道元も法然も親鸞も日蓮も、叡山に学んで新しい宗教を立ち上げました。新しい宗派を立ち上げることがどのようなことなのか、私にはわかりません。そして彼らは叡山に敵対したわけではなく、それでいて今でも確固たる地位にある叡山は、やはり不思議な存在に思えます。
0投稿日: 2024.12.30
六人の嘘つきな大学生
浅倉秋成
角川文庫
仲良し集団が最悪の状態に。そして明かされるその真の目的とは?
楽しげな和気あいあいの仲間意識が一変して、疑心暗鬼の犯人捜し。その時点では、何故この会社への就職に固執するのかと思って読み進めていました。しかし目的はそれではなかったというのが、驚きと同時に確かにそうだよなぁと妙に納得いたしました。 実のところ、私自身は就職活動というものをしたことがありません。学科の専門性から、行政の技術職となるのが一般的なコースでした。だから、一般教養と専門科目の公務員試験を受けて就職しました。それでも面接はありましたよ。3人一緒と個人面接があったように記憶しています。ただ、おそらく誰もが就職してから、何でこんな人が合格したんだ?というような人が組織の中にはいるもんですよね。 さて、小説は、著者が後に語ったという「たぶん、嫌になるくらい理屈っぽいと思います」のとおり、確かに理屈っぽいです。そして物語の構成が少々普通ではなく、語り手が変わるし、伏線が多いし、展開はスピーディーだし、なかなか読み続けるのに骨が折れます。しかし、滅茶苦茶に面白く、ページをめくる手は止まりませんでした。 何でもこの小説を書くきっかけとなったのは、編集者からの「就職活動の話を書かないか」という提案だったそうな。人が人を評価するのはとんでもなく難しいし、大変なことでしょう。社内の業務評価なら、まだいざしらず、わずかな時間の中で誰がこの会社に相応しいかなんて、わかるわけがありません。小説の中でも指摘されていますが、会社は良いことしか見せないし、就活生だって、いかに自分を飾り立てるかということに腐心するのは当然です。会社によっては、エントリーシートと面接だけで決めるところもあるとか。 物語の会社は、この最終面接にいたるまでも数々の関門があったようですが、私ならば、最終面接をこんなカタチで実施するような会社は願い下げですね。もし物語で生じたようなアクシデントがなかったら、順当に票が入った末に、一番票を得た人物を選んだのかなぁ。また一方、犯人の企みがうまくいかず、犯人自身が選ばれた後、「私はこのような選考を行う会社に就職する気はありません。」と宣言するのも面白いかもねぇ。 映画化されるということで急いで読みましたが、この理屈っぽい込み入った構成の話をどう2時間足らずで描ききるか、とても楽しみであります。
0投稿日: 2024.11.30
テロリストの息子(TEDブックス)
ザック・エブラヒム,ジェフ・ジャイルズ,佐久間裕美子
朝日出版社
犯罪者しかもテロリストの息子となれば、憎悪の他、別の視線も
犯罪者の家族への偏見については、様々ところで取り沙汰されてはいます。しかし、その犯罪がテロとなると別の視線も集めることになります。 今も続く、宗教、イデオロギー、人種等の対立。その争いの根源は深い。息子である著者は、なぜ父がテロリストになっていったかの過程も、自ら分析しつつ記述していきます。 息子は、様々な困難を避けるため、父親の影から逃げ回ります。しかし次第に父親の行動に疑問を持ち始め、それが気づきとなり変わっていきます。反抗期?いやいやそんなものではないでしょう。すべてを乗り越えてのFBI本部でのスピーチは感動的です。 それにしても、何故人間はこんなにいがみ合うのでしょうか?ベルリンの壁が崩壊して時、これで徐々に世界から分断がなくなるんじゃないかと、誰もが思いましたよね。でも、今世界にはとんでもなく沢山の壁が存在し、一説には地球一週分あるとか。どうしたら分断がなくなるのか?その答えは風の中かもしれません。でも、この息子のような人もいるのです。諦めてはいけませんね。
0投稿日: 2024.11.02
くっちゃね村のねむり姫さんのレビュー
いいね!された数863
