
弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業
木山泰嗣
光文社新書
民法って、実は生活に密着した法律?
法律ってなんか小難しそう。どうせ実生活には役にたたないでしょ。 是非そんな方に読んでもらいたい本です。 私自身、何冊かこのジャンルを読みましたが、個人的には一番分かりやすかったです。 民法の基本的な考え方。 そして、具体的な事例の二部構成で、どちらから読んでも分かりやすいです。 そして法律関連の本を読むと、改めて人が集団で生活するって、こういうことなんだな~、感じます。みんなが無意識にやっていることを、なぜそうなのかを言葉にしてルール化する。その難しさと奥深さを感じた本でした。
0投稿日: 2017.05.15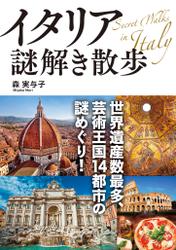
イタリア謎解き散歩
森実与子
中経の文庫
知ることで、イタリアの魅力が一気に増します!
紹介文にあるとおりといえばそうなのですが、観光名所を紹介したり、遊び方が載っている本とは、ちょっと違う、イタリアのおすすめ本です。 何が載っているかというと、観光名所は観光名所ですが、それぞれの歴史やエピソードが載っているため、知っている場所においては、知らなかった歴史があり、知らなかった場所においては、ここも見てみたいという発見があります。 ひとつひとつがそんなに量がないことと、たくさんの名所が載っていますが、それぞれのつながりや、歴史的な流れが記載されているわけではないので、断片的かもしれませんが、十二分にイタリアの魅力が増します! イタリアに限らず、身近なものも、もっとこういう知識があるだけで、すごく魅力的なものに変わるのにな~、と思います。
0投稿日: 2017.05.15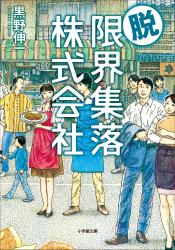
脱・限界集落株式会社
黒野伸一
小学館
事業は、誰のためにあるのか。
前作からのファンで、続編を読んでみました。 前作が、非常にきれいな終わり方をしていたので、あれ以上どんな展開になるんだろうと思っていたのですが、今回は前回の村の隣町が舞台。 ここからどう展開するんだろうと、まったく展開が読めないところからスタートでした。構図としては、「大手チェーン」VS「地方商店街」の構図へ。日本全国でよく起きていることではないでしょうか。 地権者にとってどっちがメリットがあるか、そこに住む人にとってどっちがメリットがあるか、行政にとって、開発業者にとって・・・いろいろな思惑が絡み合います。個人的に強く感じたのは、事業、サービスは誰のためのサービスなのか。ここがズレたものをどれだけ推し進めても、良い結果にはつながらない。 そして、「大手チェーン」と「商店街」は、ここがズレているからこそ、戦うことができ、共存ができる。 大手ナショナルチェーンは好きですし、よく利用しますが、大手ナショナルチェーンばかりが並んだ町にいくと、ちょっとがっかりする自分としては、商店街や、地元ならではのお店は残ってほしいなと思います。いち消費者として、そうしたお店を利用させていただくことで、その一助になればいいな~と思います。
0投稿日: 2017.05.13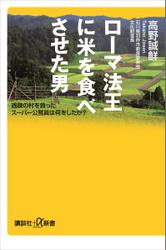
ローマ法王に米を食べさせた男 過疎の村を救ったスーパー公務員は何をしたか?
高野誠鮮
講談社+α新書
行動、行動、行動、行動。
圧倒的な行動力。本当にその一言です。 考えすぎて動けない、見えるまでは動かない。 自分自身を振り返っても、周りをみても、そんなことが多いように思います。でも、高野さんは違います。こんなことができるのではないか、やったほうがいいのではないか、そう思ったら、すぐに行動します。そしてあとは走りながら考える。 上司にめぐまれていた、ということも、大きな要素だとは思いますが、どんな組織であれ、高野さんのように、自分が実現したいことのために、必要だと思うのであれば、やればいいのだと思います。取返しのつかない失敗が出る場合を除いて、ですが、そもそも取返しのつかない失敗って、よっぽどの大金が吹っ飛んでしまうとか、命の危険とか、それくらいかではないかと思います。 仕事って、言われたことをやったり、やりたくない、と思いながらするもの、ではないですよね。本当はもっと、楽しくて、意義を感じながらやることだと改めて感じることができた本でした。
0投稿日: 2017.05.13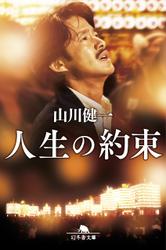
人生の約束
山川健一
幻冬舎文庫
人は常に誰かに生かされていると感じる本でした。
ちょっと仕事に疲れていたり、孤独を感じる方には、没頭することで、心のどこかが温かくなる、そんな本だと思います。 ある二人の男性を軸に、話は進んでいきます。もともとは二人で会社を立ち上げたものの、一人はあることを理由に、会社を去り、一人は会社に残り事業拡大を推し進めます。会社に残った人こそ、経済合理性を追いかける象徴のように描かれています。 そしてある時、その二人を再び結びつける出来事が。それは、ある町の伝統儀式でした。一緒に会社を創り、大きくしてきた友が、この伝統儀式に何を求め、何を見ていたのか。あとは小説を読んでみてください。 いきすぎた経済合理性は悪だ、と描かれているように感じますが、とはいえ、その原則にさからえない現実も描いています。 僕が読んで感じたのは、人は本質的には「誰かに支えられ、誰かに生かされている」ということ。どんなに経済合理性を追いかけ、一人でどんなに大きな富を持ったとしても、です。いやなことや辛いこともありますが、色々なことに感謝をして、生きていきたいですね。
0投稿日: 2017.05.13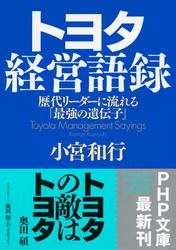
トヨタ経営語録
小宮和行
PHP文庫
トヨタ歴代経営者の言葉の重み
トヨタ自動車と聞いて思い浮かぶもの。今だと豊田社長を思い浮かべる方もおおいかもしれませんが、歴代の社長、と言われると、すぐに思い浮かぶ方が世の中にどれくらいいるのでしょうか。 正直私は、すぐには全員浮かばなかったです。 では、トヨタ自動車の歴代経営者が、高い業績を残していないかというと、決してそんなことはありません。 改めて、各経営者の言葉を読んで、トヨタの表には出てこない強さ、その裏にある経営者に、従業員に継承されてきた不変の姿勢を感じることができました。それを継承する為に、心血を注ぎ、時代に合わせてかじ取りをしてきたのがトヨタの経営者なのかなと思います。 本書は、豊田佐吉からのトヨタの経営者の言葉を、その時の時代背景、状況の説明と合わせて多く掲載している本です。トヨタ自動車の魂というか、トヨタ自動車のこと、社会のことを、日本のことを考え抜いた人たちから出る言葉の重みが感じられる本でした。
2投稿日: 2017.03.25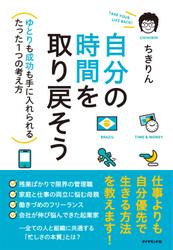
自分の時間を取り戻そう
ちきりん
ダイヤモンド社
生産性を何と定義しますか?
まさに、この生産性を何と定義するのか、これが非常に難しいものの、本質的な議論だと思います。 ちきりんさんのこの本は、4つのキャラクターを例に、それぞれが直面する生産性の問題で、何が問題になっていて、どう乗り越えるのがよいのかを例示してくれています。 それは、一人ひとりにとって、生産性として目指すべきところや、解が変わるということを示してくれていると思います。 まさにこの観点がないと、どの水準が適正なのか、何がどうなれば達成なのかが、決められないので、ここを考えられていないことが、生産性という話になったときに、いつもありきたりな答えになる要因なのかなと、思いながら読んでました。 一人ひとりがこの視点を持ち、生産性を改善することを意識しながら生活する世の中があったら、それは素晴らしい世の中だと思う。そんな気づきを得られた本でした。
7投稿日: 2017.03.23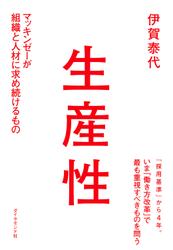
生産性
伊賀泰代
ダイヤモンド社
外資系にいた著者から見た、日本の企業の弱さ
もちろん、日本の企業には、強いところは良いところはたくさんあるのですが、外資系にいた著者から見ると、この「生産性」の観点においては、 日本の企業の多くは弱く見える様です。 本書で指摘されている内容は、納得できる内容が多く、いわゆる日本の企業で働く私には、耳が痛い内容も多かったです。 生産性は、インプットを減らすことに目が行きがちだが、アウトプットを上げることをしていかないとそもそも限界がある。 著者がこれまで携わってこられた採用領域を例に上げ、 生産性が上がらない障壁となっていることの一つとして、「経営者の見栄」を挙げているのは、興味深かったです。 そして、生産性を上げる方法を、インプットとアウトプットにおいて、それぞれ改善と革新という観点で整理をするやり方は、今後生産性を見るうえで、フレームとして使いやすい概念だと思います。ここで得られた知識をもとに、ちょっと実践をしてみようと思える本でした。そして、何%改善という積み重ねも大切ですが、〇倍にしよう、というレベルのものでないと、なかなか革新は生まれないですし、そういうことに挑戦をし続けること、考え続けることに、価値があるのかなと思った本でした。 生産性に関して、掘り下げられてはいますが、著者の専門である「人材」領域の話が多く、組織論や育成に興味のある方なら、より刺激を受けられる本だと思います。
5投稿日: 2017.03.23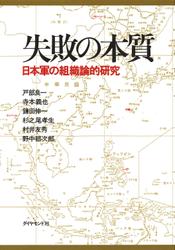
失敗の本質
戸部良一,寺本義也,鎌田伸一,杉之尾孝生,村井友秀,野中郁次郎
ダイヤモンド社
究極の合理性が求められるはずの、軍で起こった組織のもろさ
第二次世界大戦時で起こった、大きな戦場を分析し、日本軍がなぜ負けたのかを組織論の観点から考察している本です。 ポイントは、そもそも軍隊は、究極の合理性を追求した組織であるはず、ということ。 企業ももちろん、生死をかけて争っている部分もありますが、物理的な生命的な危機の近さという点では、軍隊のほうが圧倒的に近いことは、誰しもが否定しないのではないかと思います。 そういった組織であれば、当たり前に、非合理的な選択ではなく、自分の命を守るためにも合理的な選択をするはず。私もそう思っていました。 実際に日本軍がどんな失敗を犯したかに関しては、本書を読んで頂ければと思いますが、 ・ミッションが曖昧であり、組織としての相乗効果が発揮できなかった。 ・意思決定者と現場の距離の遠さ。 ・生死がかかっている判断にもかかわらず、特定の人間の体裁を重視。 ・過去の成功体験への依存。 ・上記に関連して、学習する仕組みが存在していないかった。軽視されていた。 など、今の組織でも起こりうることが多いのではないかと思います。 それが軍隊で起こっていた、というのは正直驚きでした。 特に、個人的には、体裁を重視した意思決定が存在していたことに、心底驚くと同時に、それが理由でなくなった多くの先人達の気持ちを思うとやるせない気持ちになりました。一方、判断した側にも、一定の理由があるので、責める気持ちがあるわけではありませんが。 軍ですら、陥る上記の組織の罠に、一般の組織はより落ちやすいのだと思います。だからこそ、自らを戒めながら、きちんと省みることが大切ですね。
11投稿日: 2017.03.21
なぜ人と組織は変われないのか ― ハーバード流 自己変革の理論と実践
ロバート・キーガン,リサ・ラスコウ・レイヒー,池村千秋
英治出版
必要があるとわかっていても変われない理由。それは自分を守ろうとする無意識の自分。
多くの方は変わらなければいけない、または変わりたい、と本気で思っていても、実際には変わることができるのは少数。必要だとわかっていても、85%の人が行動すら起こさない。 それはなぜなのか。 それを、事例をあげながら丁寧に説明すると同時に、それを克服するためのステップを提示してくれる本です。 マネジメントなど、組織・人を動かす立場にいる方や、そういった立場を目指す方にとってはもちろん、変わりたいと本気で思っている方には、すごく参考になる、新しい発見のある本田と思います。 この本で書かれているのは、その原因は、「自己免疫機能」という自分を守ろうする意識が働くから。 変わるためのアクセルを踏む(変わりたいと本気で思っている)と同時に、ブレーキも同時に踏む(別の理由で変わりたくないとも思っている)という状況が、無意識下で起こっている状況。 この無意識下というのが非常にやっかいで、自分が持っている固定観念や、こだわり、プライドが、表面化しているため、なかなか気づくことができない。 これを免疫マップというワークを通じて、自分で自分を認識し、徐々にそこから解放されていく過程を紹介。そして、これは組織においても同じです。 個人的には、これに本当に納得で、読みながら、自分の触れられたくない部分を、ぐりぐりいじられているような、辛い気持ちになりました。なかなか本を読んでこのような気持ちになる経験は少なく、それだけ真正面から人のずるさや、本能に向き合った本なのではないかと思っています。 もう少し早くこの本に出会いたかったと本気で思える本です。 実践までは、少し時間がかかりそうですが・・・。
5投稿日: 2017.03.21
あきばさんのレビュー
いいね!された数404
