
アインシュタインの宇宙 最新宇宙学と謎の「宇宙項」
佐藤勝彦
角川ソフィア文庫
アインシュタインの宇宙がよくわかる。
本書はアインシュタインの考えた宇宙について、19世紀末の謎から現在の宇宙論に至る過程を、順を追ってわかりやすく解説している。概念的に難しいこともうまくまとめられていて、専門家でない自分にも楽しんで読める内容だった。 自分は学生の時に物理を専攻したが、相対論や宇宙論は結局手が届かなかったので、本書を読んで改めて勉強し直したいと思っている。本書のような啓蒙書は、あるテーマを柱に書かれており、学生の頃に学んだ知識がどこに位置付けられるかがわかり、枝葉末節にばかり目が行っていた学生の頃になぜ気付かなかったのだろうと残念に思っている。 現在の宇宙論に至る過程では、エピソードも交えて説明されており、ついつい話題に引き込まれる。また、物理出身の身としては、概観だけ俯瞰する部分などはもう少し自分で調べてみたいと思わせる書き方で、とても面白かった。 本書はヒッグス粒子が発見される以前に書かれたものなので、7章の内容で「ヒッグス粒子探しはLHCで行われることになっている」という記述があり、時代が動いているのだと実感して、なぜか印象に残った。 全体的に楽しく読めて興味深い内容だった。
0投稿日: 2019.11.26
知ろうとすること。(新潮文庫)
早野龍五,糸井重里
新潮文庫
正しい知識とデータが必要
東大物理の早野先生と、コピーライターの糸井重里さんの対談集。福島第一原子力発電所の事故を機に、twitterに情報を投稿する早野先生。福島の事故は、放射能汚染などの恐怖で様々な憶測が飛び交ったが、その中で冷静さを失わない情報を投稿し続けた早野先生に信頼を寄せた糸井さんとの対話で、お二人が言っておきたかったことをまとめたものである。 4年前に読んだものだが、先日職場の方が福島第一原発に出張されたのを機に再読してみた。本書の内容は事故から8年たった今でも、非常に考えさせられる内容を含んでいる。いまだに福島の風評被害の話なども出てくることがあり、改めて冷静に正しく物事を見る目を養わなければならないと感じた。
0投稿日: 2019.11.23
地震は必ず予測できる!
村井俊治
集英社新書
現状では難しそう
3年ほど前に勧められて読んだものだが、また最近少し気になって再読した。地震予知はできないが、地震を予測することはできると著者は主張する。 著者は測量工学が専門であり、地震学については門外漢だが、地震の予測ができることを様々なデータを用いて広く知らせようとしている。地震の専門家からは、否定的な意見が多いが、防災面からも地震の予測研究は重要であると述べている。 ただ、地震に関しては、予測が確実でないとパニックを起こすことや、避難方法の難しさもあり、簡単に情報を発信することは必ずしも良いこととは言えない面もあると思う。 専門家が言うように、地震予知は不可能だろう。しかし、予測は本当に確実にできるのかと言うと、現段階では自分も疑問を持っている。また、情報発信して防災に役立てるためにはまだまだ確実なものとなっていないだろう。 著者らの理想が実現できたら素晴らしいことだと思うが、今後の発展に期待したい。
0投稿日: 2019.11.23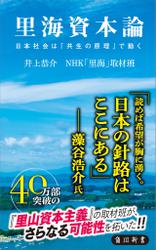
里海資本論 日本社会は「共生の原理」で動く
井上恭介,NHK「里海」取材班
角川新書
21世紀の豊かな人間社会へ
21世紀における、新しい自然との共存を目指す方法を、瀬戸内海を舞台に展開される。本書を読んで、これからの社会の理想を見せてくれたように思う。 20世紀の高度経済成長では、工業化によって海や山が壊されて行ったが、豊かになって行く過程で、自分たちの環境を住みにくく変えてしまったという弊害もあり、今後は違ったやり方で豊かな社会を築いていく必要があると感じた。 本書で述べられているのは、自然のバランスを見極め、人間も自然環境の一部であり、バランスを保った活動をすることで快適な暮らしを手に入れることができるというものだと思う。工場と森や小川、海が共存する、一見何か矛盾したような感じを受けるが、これからの社会のあり方はそういう新しいものにして行くことが求められている。本書で述べられた「海全体を生け簀にする」という発想などは、非常に印象に残っている。里海資本論というのは、豊かな人類の未来を築く重要なヒントになるだろう。
0投稿日: 2019.11.12
私たちは時空を超えられるか 最新理論が導く宇宙の果て、未来と過去への旅
松原隆彦
サイエンス・アイ新書
読みやすくて面白い
面白かった。 3部構成になっており、最初は時間、次に空間、最後に人間原理について述べられている。タイムマシンによる時間旅行や、想像上の宇宙船での宇宙旅行を通して現代物理学の先端を行く内容が、物語を読むように読める。わかりやすい文章でカラーのイラストなども交え、楽しい読み物となっている。 宇宙旅行にかかる時間で、数式を使った導出については巻末の付録に丁寧に解説されており、理屈に興味がある人にも満足感を与えてくれると思う。
0投稿日: 2019.11.04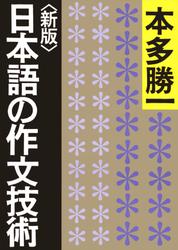
<新版>日本語の作文技術
本多 勝一
朝日文庫
こんな作文指導を受けていたら...。
わかりやすい日本語の文章を書くために重要なことがまとめられた本だと思う。こうした作文指導を、中学・高校時代から受けていれば、もっとまともな文章が書けたかもしれないなと感じた。 著者は元朝日新聞の記者であり、様々な意味で著名な人物だが、自分は残念ながら今までこの著書を知らなかった。新聞記事や小説、評論文など多岐にわたる例文を交えて文章を吟味し、文法的な正しさや表現の方法を解説している。仕事で報告書を作成する際にも、色々と参考になる内容だった。 特に、「日本語の論理や文法は、ヨーロッパ語の間尺で計測することはできない。」という意見は、今まで学んで来た日本語の文章の書き方への疑問や日本語の文章というものに対して認識を改めることになり、非常に印象的だった。 国語というものは普段から使っているため、何と無く文章も書けてしまうのではないかと思っていたが、わかったつもりになっていただけで、まともな文章になっていないこともあることに気づいた。本書を読んで、少しでも質の良い日本語の文章を書けるようになりたいと思う。
0投稿日: 2019.09.29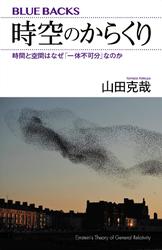
時空のからくり 時間と空間はなぜ「一体不可分」なのか
山田克哉
ブルーバックス
八つぁんと熊さんの掛け合いが面白い。
最近、一般相対論やブラックホールなど、重力関係の本を読んでおり、ちょうど電子書籍の割引で手頃だったので購入した。内容は、一般相対論を中心に重力とは何かをやさしく解説している。 一般相対論では、重力は時空の歪みであり、アインシュタイン方程式から導き出される測地線などは、ある程度までテンソルを用いて興味深く説明している。高校生に興味を持って読んでもらえる内容なのではないかと思った。 最後に、少し前に話題になった重力波の話が詳しく解説されており、読み応えのある内容だった。特に八つぁんと熊さんの掛け合いで書かれている部分(八つぁんと熊さんの掛け合い物理学)が面白かった。 これを読んで、もう少し突っ込んで一般相対論と重力波を勉強したくなった。知的好奇心をそそる一冊である。
1投稿日: 2019.09.16
日本語に主語はいらない 百年の誤謬を正す
金谷武洋
講談社選書メチエ
日本語の文法がすっきり理解出来る。
知り合いの英語の先生に薦められて読んだ。 明治時代以降、日本語の文法がいかに歪められて伝わってきたかが述べられている。この本を読んで、自分の長年の問題が氷解した。学校でも国語の時間に文法はあったが、どうにも理解できないことが多く、疑問に思うことが多かったが、学校で教えられる文法も、日本語を日本語としてそのまま捉えるのではなく、外国語の文法に当てはめて解釈されることが多かったからだと思う。 そもそも、日本語の「主語」というものが、「動作の主体」だとかさっぱりわからない説明ばかり聞いてきたのだが、英語やフランス語のような明確なものではなく、それらの外国語に無理やり当てはめて出来たものだということがよくわかった。 本書は、日本語の文法が外国語という異質の言語を通して構成されてきた現状を述べ、日本語そのままの形で理解出来る文法が本来のものであると、その誤りを指摘している。まさに「100年の誤謬を正す」という通りだと思う。 どの説明も非常にすっきりしていて、目から鱗が落ちたように感じた。改めて日本語の文章というものを考えさせられる一冊だった。
0投稿日: 2019.09.16
N.Yokoyamaさんのレビュー
いいね!された数5
