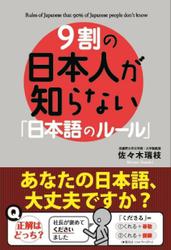
9割の日本人が知らない「日本語のルール」
佐々木瑞枝
中経出版
母国語を改めて見直したい。
普段意識しないで使っている日本語だが、改めて問われると答えられない言葉が多かった。本書は、会話や文書で何と無く使っている言葉を見直す機会を与えてくれたと思う。 一つ一つかなり具体的な例を出して解説されているので、非常にわかりやすかった。今後も意識して会話をしたり、文書を書いたりしたい。できれば、外国人に質問された時は出来るだけ色々なことに答えられる様になりたいと思う。
0投稿日: 2020.03.15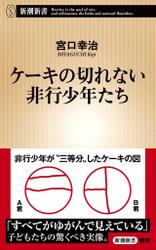
ケーキの切れない非行少年たち(新潮新書)
宮口幸治
新潮新書
衝撃的な内容
タイトルに興味をそそられて購入したが、衝撃的な内容だった。自分には簡単に出来ることが、出来ない人に対して「どうしてこんな簡単なことが...」と感じることは多いと思うが、この本の内容はそういうレベルではなく、多くの人にとっては信じがたいものではないだろうか。 本書に登場する非行少年の行為は、普通なら「わざとふざけているのではないか」と思えるようなレベルなのだが、実際にケーキを切ることが出来ないのが事実で、自分でもどうしようもない苛立ちが湧き上がるというのは、読んでいてなんとも言えない気持ちになった。 自分でも指摘されてわかっているのに、出来なくてもどかしい気持ちは何度も経験したことがあるが、非行少年たちはたえずそうした感情に苛まれているのかと考えると、当人たちにとってはまさに精神的な拷問としか受け取れないのも当然だろう。しかし、人間社会には歴然としたルールが存在し、本質的に守れない人間だからといってルールを無視した行為が許されるわけではない。 非行少年の問題は、非常に奥の深い問題だと提起している。しかも外からではわからないわけだから、早期の対処なども難しいことがわかる。こういうのは、周りの人間の理解と早期の専門的な訓練によるしかないような気がする。 本書を読んで、非行少年に対する認識が少し変わったが、自分の日常生活に影響が出てくるようなことになった時、何が出来るかはわからない。
1投稿日: 2020.03.15
大学入試問題で語る数論の世界 素数、完全数からゼータ関数まで
清水健一
ブルーバックス
数論と入試問題の魅力を実感した。
素数から始まって、完全数、ピタゴラス数、フィボナッチ数列など数論の様々な魅力が大学入試問題を解くことで語られる。最後はゼータ関数まで現れて、リーマン予想の話まで広がって行く。 この分野は、高校の時「数学I」という科目で学んだが、正直あまり面白いと思わなかった。一次変換や固有値を求めたり、微積分の計算が好きだったので整数の問題には魅力を感じなかったのかもしれない。概念としてはあまり難しくない感じだが、いざ問題を解くとなるとなかなか出来なくてイライラすることが原因だったかもしれない。当時は、数学を楽しむというよりとにかくテストで点を取りたいという気持ちが強く、本当の意味で数学を勉強していなかったと今になって思う。 改めて数論という分野の本を読んでみると、難しいと思っていた中にも証明方法に感動したり、じっくり考えてみると、あのつまらなかった入試問題が実は「こんなところに繋がっているのだ。」と意表をつかれることが度々あった。改めて整数の魅力を感じ、入試問題の面白さを味わえたよ
0投稿日: 2020.01.17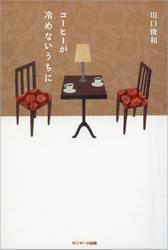
コーヒーが冷めないうちに
川口俊和
サンマーク出版
感動した。
感動する作品だった。 SFではタイムトラベルなどで過去へ行く話があるが、この物語はそれとは少し違う幻想的な内容だった。過去への介入は、しばしば因果律を問題にするが、これはその辺りもうまく調整されていてそんな工夫の仕方があるのかと驚いた。SFというジャンルではないので、心理描写に重点が置かれていて、自分にとっては非常に印象的だった。 登場人物が皆、個性的で非常に面白い。また、この物語はほとんどが喫茶店という限られた場所だけで繰り広げられる話なのが秀逸だった。今までこういう話は、多分読んだことがなかったので新鮮に感じられ、読んだ後まで余韻が残る。 人は誰でも、「あの時ああすれば良かった」などと後悔し、できれば「その時に戻ってやり直せたら...」という経験があるものだ。ただ、過去に戻っても現実が変えられないなら、意味があるとは思えないだろう。実際、自分もそう思っていた。しかしこの物語を読んで、過去に起こったことは決して変えられなくても、自分がその時にもう一度納得できる行動を選択することで、その後の自分の生き方が変わって来るのだと教えられた気がする。その時、その時で自分が納得できる行動を取っていきたい。
0投稿日: 2020.01.16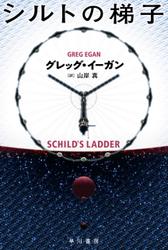
シルトの梯子
グレッグ イーガン,山岸 真
ハヤカワ文庫SF
読み応えのあるハードSF
久しぶりに読み応えのあるハードSFだった。 イーガンの作品は前から読みたいと思っていたものの、これが初めての作品となった。内容はなかなかハードである。量子力学に精通しているともう少し楽しめたかなと思うので、その点少し残念だった。ただ、前野先生があとがきで解説されているので、これを読んでから再読するとまた違った感動が得られるかもしれない。 訳者の山岸さんもあとがきで述べておられるが、SFというものにつきものな、現代の日常からかけ離れた環境などが出てきてもそれが詳しく説明されるわけでなくイメージが難しい。ただ、やはり読み進めて行くうちに結構何度もそうした描写に触れると、だんだん面白くなって行く。この辺りがSFの醍醐味でもあるような気がする。 第一部と第二部の構成からなり、その関係から最後の結末はなんとなく推測はできたが、結末の仕方がやはりプロの人は発想が違うと実感した。色々と難しい専門用語や馴染みのない言葉が散りばめられており、理解が追いつかない部分もあったが、物語自体は面白かった。 読み終わった感想は、ループ量子重力とスピンネットワーク理論が学びたくなる小説だというところか。
0投稿日: 2020.01.14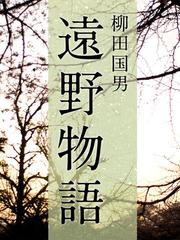
絶対読むべき日本の民話 遠野物語
柳田国男
ゴマブックス
古き良き日本
岩手県の遠野郷に伝わる話が収められた一冊。 民俗学者の柳田國男氏が遠野の住む佐々木鏡石という人から聞いた話をまとめたもの。遠野地方の様々な魅力的な話が語られ、ついつい先を読んでしまう。一つ一つは短いものなので、内容が完結していて読みやすかった。 山の神、里の神から座敷童子や妖怪など、ともすれば現代では忘れられがちな存在が心に訴えかけてくる。なんとなく子供の頃育った田舎を思い出して懐かしくも感じた。 文語文のため、読みにくいと感じられる方もいるだろうが、文章に特有のリズムがあり、慣れると口語文よりも味わい深い印象を受けると思う。どちらかというと音読したくなる文章だった。特に最後は歌謡となっているので声に出して読むと良いのではないか。 全体通して興味深い話であり、面白かった。
0投稿日: 2019.12.19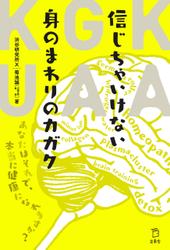
信じちゃいけない身のまわりのカガク あなたはそれで、本当に健康になれますか?
渋谷研究所X,菊池 誠
立東舎
ニセ科学に騙されないために
世の中には科学を装ってまことしやかに生活の中に入り込んでくるものが多々ある。 物理学者である著者が、渋谷研究所Xの亀さんと六さんと共に、巷で注目を集めているニセ科学の数々を紹介している。著者の菊池誠教授は、科学者の中でも疑似科学批判に力を入れている一人として有名だが、食品から薬品、健康グッヅなど間違った科学知識をもとに宣伝をしている商品や医療について警鐘を鳴らしている。中には中学校の理科の知識があれば、その真偽を判断できるものでも宣伝文句につられてついつい買ってしまったり、本気にしてしまうものもある。人が「こうありたい」と希望する力がそれだけ強いということなのだろう。 本書は亀さんと六さんの掛け合いの形で話が進み、中には少しマニアックな話題も交えながら楽しく読める。話題の最後には著者によるまとめがあり、何が問題なのか、どこが間違っているのかがわかりやすく解説されている。 「うまい話には裏がある。」とは良く言われる言葉だが、現代社会において、きちんとした科学の知識を持ち、物事を正しく判断する力を養うことが重要だということを改めて感じた。本書を読んで、実際に自分で考えることを実行したい。
0投稿日: 2019.12.18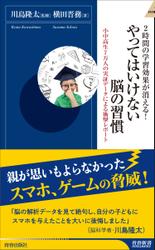
2時間の学習効果が消える! やってはいけない脳の習慣
川島隆太,横田晋務
青春新書インテリジェンス
子供は朝食を取るのがオススメ
こんなことをしていると脳がダメになる。本書は様々なデータを集めて、主に子供の能力を高めるために好ましいこと、好ましくないことを提案している。 スマートフォンやゲームは、世間的に子供の成長にとってあまり良いイメージを持っていない。本書では、やはりスマートフォンやゲームに長時間浸っていることに警鐘を鳴らす。ゲームのやりすぎは勉強したことを相殺してしまうようだ。ただ、スマートフォンの使いすぎと言っても、用途が良くわからないのでなんとも言えないが、前提としてゲームやSNSに興じる時間が長くなるということを言いたいのだろう。SNSというのがそれほど勉強に影響のあるものかは疑問だったが、絶えず相手からの返信が気になり、デバイスの通知音で集中力がなくなるということらしい。 データについては、分布がかなり広がっているように見えるので、弱い相関とはいうものの分布図に引かれた直線に意味があるのだろうかとは思ってしまった。ただ、成績の良い子はゲームやスマートフォンの時間を1時間以内に抑えている傾向があるとかいうのは、そういう自分を律することの出来る子だから成績も良いのではないかと感じた。能力を高める話で、外的要因と内的要因というものが出てきたが、これなども外的要因を内的要因に昇華させるのが重要だと思うが、そういうことが出来る子と出来ない子の差がデータに現れていると見ることも出来ないだろうか。 結論としては、本書が勧める生活習慣が良い結果をもたらすのは間違いないだろう。しかし現代社会はその理想とする習慣をかなり難しくしているのではないだろうか。 興味深かったのは、朝食を取るのが良いのか否かについて、子供はやはり朝から栄養を取るのがオススメだということかな。
0投稿日: 2019.12.12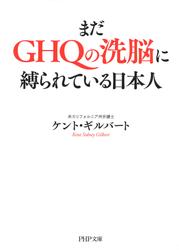
まだGHQの洗脳に縛られている日本人
ケント・ギルバート
PHP文庫
戦後の米国による占領政策が俯瞰できる。
戦後の日本で行われた、米国による“ウォー・ギルド・インフォメーション・プログラム”を通して、現在の日本人に親日米国人弁護士が活を入れる。戦後のGHQによる日本の占領政策は、色々なところで耳にはしていたが、本書はそれによる影響と、現在日本人が陥っている問題点を指摘しながら、内容を俯瞰できるようにまとまっている。 原爆投下については、心情として戦争を早く終わらせるための措置だと良く言われることだが、実際政治的には旧ソ連に口出しさせないためのものだったと、中学の社会でも授業で話を聞いた覚えがある。 ただ、ルーズベルトとスターリンが裏で繋がっていて、チャーチルを疎外するというのは結構印象的だった。本書の内容から、ルーズベルトが病気にならなかったらと考えると、日本は悲惨な道を歩んでいたかもしれない。日本人の力を奪うためには、皇室と神社を破壊すれば良いというのは良く聞いたことがある。もし旧ソ連との分割植民地化が実現していれば、当然皇室はなくなっただろうし、神社は取り壊されていたかもしれない。米国は、対共産圏の砦として日本の重要性を認識したことで、皇室を残したのだろう。 ぼくが小・中学生だった頃はあまりそうした政治的なことはわからなかったが、侵略戦争をした日本の罪の大きさは知っておかなければいけないという話は何度も聞かされたように思う。 本書で印象的だったのは、東條英機に対するイメージが全然違うことだった。自分も「東條英機」というと悪の権化というイメージがあり、欧米諸国の一般人と同じ印象を持っていたと思う。極東軍事裁判の不条理さは自分でも知識を得ていたが、「戦争犯罪人」ということだけで悪人と決めつけられた当時の人々に対して、本当に自分は何も知らなかったのだと認識した。 日本人として、自分の国をどう考えていくかを教えてくれる一冊だったと思う。
0投稿日: 2019.12.08
ブラックホール・膨張宇宙・重力波~一般相対性理論の100年と展開~
真貝寿明
光文社新書
重力波が印象的だった。
この本は、ちょうど「LIGOが重力波の観測に初めて成功した」というニュースを知り、重力波に興味があって購入したものだと思う。最近、また宇宙論関係の啓蒙書を読み始めて、改めて再読した。 内容は、題名通りブラックホール、膨張宇宙、重力波の3つのテーマをメインにそれぞれの100年を振り返る形で書かれている。最初にアインシュタインの時代と背景、相対性理論について述べられており、それぞれのテーマへのスムーズな導入部となっている。 特に印象に残ったのは最後の重力波の話題に関する内容で、著者の専門が重力波の数値計算に関する研究のためか、語りに熱が入っているような書き方で引き込まれた。本書ではLIGOを含めて、重力波がまだ見つかってない時のものだが、この後すぐLIGOで初めての観測結果が報道されたのも読んでいて印象的だった。啓蒙書も色々読んでみると、同じような分野でも著者によって語り口が違っていて面白いと思った。 また再読してみて、宇宙物理関係の最先端は本当に目まぐるしく進んでいるのだということも実感した。
0投稿日: 2019.12.06
N.Yokoyamaさんのレビュー
いいね!された数5
