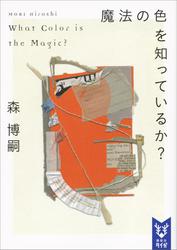
魔法の色を知っているか? What Color is the Magic?
森博嗣
講談社タイガ
ハギリ先生って何者?
森博嗣Wシリーズ第2作 主人公ハギリ博士の研究を巡って何やらキナ臭い展開が...。 今回はウグイに加えて博士の護衛に新たなアネバネという人物が登場。博士、自分の身が危険だということがわかっているのかなと思うような態度だが、まあ、一研究者としてはこういうものなのだろう。 しかし、今回もドンパチで博士の周辺の方々は命の危険にさらされることになったが、これも博士の「名推理」で危機を逃れたということなのか。もしかしてこれがミステリー要素なのか...。このシリーズは色が関係するのかな。 まあ、とにかくストーリーは興味深くて非常に面白かった。様々な謎が次々と現れ、博士たちは何かの意思によって動かされているようにも感じる。いずれ、この謎も明らかになって行くのだろう。今後の展開が楽しみだ。 それからマガタ博士...、こんな時代にまで影響力を持っているとは、やはり並みの天才ではなかったようだ。
0投稿日: 2020.07.25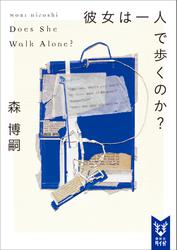
彼女は一人で歩くのか? Does She Walk Alone?
森博嗣
講談社タイガ
ようやくWシリーズにたどり着いた。
森博嗣Wシリーズ第1作 面白かった。ようやくWシリーズにたどり着いたという感じか。読んだ感じでは、このシリーズはミステリーだとは思えないので、SF小説ということにした。熊の魔法がミステリー要素なのかわからないが...、まあ、なんでも面白ければ良いと思う。 ウォーカロンと人間が共存する世界。舞台はどうもあのミステリーのシリーズの200年後くらいだと思うのだが、未来であることは確かだろう。年代的には100年シリーズの後になるような感じだが...。 新たな主人公、ハギリ・ソーイ博士が登場、やはり独特なキャラクターだと感じる。レギュラーになりそうなウグイも魅力的なキャラクターだ。このシリーズも面白くなりそうな感じ。 ウォーカロンにミチルなんて名前が出てくるし、マガタ博士だと...。今後の展開が楽しみである。 今回は電子書籍にしたのだが、だから解説がなかったのだろうか。少し寂しい気もする。
0投稿日: 2020.07.20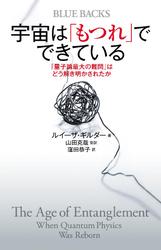
宇宙は「もつれ」でできている 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか
ルイーザ・ギルダー,山田克哉,窪田恭子
ブルーバックス
量子力学は面白い
量子論の謎であった「もつれ」について、その黎明期から現在まで、物理学者たちにどう語られてきたかが述べられている。有名なアインシュタインとボーアの論争や、EPR論文についての様々な物理学者の反応、さらには「実在とは」という問いに関して、エピソードを交えながら物語風になっていて面白かった。 最初、これは物理学の本だと思って購入したのだが、特に量子論に関する詳細な記述があるわけではなく、個人の書簡や会議での記録、取材をもとにした科学史みたいなものだと思った。ただ、それで期待はずれだったというわけではなく、著名な物理学者の様々な側面が見えて興味深かった。 エーレンフェストの晩年と死、ボームの終戦後の研究生活などは結構衝撃的で、読んでいて胸にくるものがあった。また、ボーアがなかなかコペンハーゲン研究所の独裁者という感じで、それまでの印象が変わってしまった。 21世紀に入り、実験技術も発達し、「もつれ」についての理解は前世紀に比べて大きく前進した。量子論は現代では情報理論だと言われている。波動関数は知識の束であり、物理学では局所的な実在というものは否定されている。 エピローグでのフックスの言葉は印象的だった。「量子論の構造は、物理学について何も語っていない。」、「量子論とは、我々が知っていることを記述する形式的なツールだ。」 量子力学から情報理論を切り離せば何が残るのかというフックスとルドルフの問いはこれからも議論されるのだろうか。
0投稿日: 2020.07.20
英語教育の危機
鳥飼玖美子
ちくま新書
今タイムリーな内容だと思った。
最近、大学入試の制度を見直すとかいうことが話題となり、特に英語に関して様々な意見が出ているので、興味が湧いて読んでみた。 英語に関しては、昔から学校英語は使い物にならないとか文法重視で訳読しかしないから会話ができないとか批判にさらされてきたの知っている。本書に書かれているように、英語教育というのは会話ができれば良いというものでもないと自分も思う。本質を見失っているため、英語教育がおかしな方向に向かっているのだろう。 今後はTOEICとか民間の英語の試験を大学入試に導入するという話が出ているが、そもそも目的の異なる試験で学力を測るというのも変な話なのかもしれない。今の入試などの議論は、グローバル人材の育成とかで企業というか経済界の意向が反映されるものになっていこうとしていると感じた。 小学校から英語の授業を作るとか、先生の方も大変なのではないか。本書では、教育の目的として文部科学省で目指している学力などが述べられていたが、そこまでしても一向にレベルが上がらない状況とその原因や問題点が述べられている。本書の問題提起に対して、今後の政府の対応が英語教育の未来を左右するだろう。
0投稿日: 2020.07.20
ロウソクの科学
ファラデー,竹内敬人
岩波文庫
ノーベル賞受賞者推薦の書
電気で有名な英国の科学者マイケル・ファラデーが、青少年のために行ったクリスマス講演会の講義録をもとに出版されたものである。 この本は、昨年ノーベル化学賞を受賞した吉野彰氏が、化学を志すきっかけとなったものとして有名になり、自分もその影響で購入した。 ファラデーの講義録は、さすがに青少年向けとあって非常にわかりやすく、当時の一般社会への科学啓蒙に対する情熱が伝わってくる。「ロウソクの科学」という訳で現代でも「ロウソクの化学史」といったようなところだが、内容はロウソクの話から広がって、気体の電気分解や酸化・還元といった化学の興味深い内容に詳しく触れている。 現代では中学の理科で習うような内容だと思うが、当時の青少年たちからしたら、これは科学の最先端の内容だろうと思う。本書にも、当時の子供達になったつもりでという記述があったが、当時この講義を聴いた子供たちは本当に衝撃的な印象を受けたに違いない。 本書は、ファラデーの生涯についても納められており、階級支配のあった当時の英国でしがない印刷工が、王立研究所の研究者になる話は非常に印象的だった。 幸運もあったろうが、ファラデーの科学に対する情熱が、様々な障害を乗り越える原動力になったのだろう。今からでもこんな情熱を燃やしたくなってしまった。確かにノーベル賞受賞者が推薦する本だとなぜか感心し、読んで損はないと思った一冊だった。
0投稿日: 2020.05.29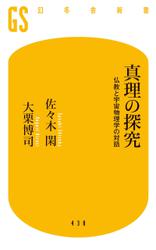
真理の探究 仏教と宇宙物理学の対話
佐々木閑,大栗博司
幻冬舎新書
大先生お二人の興味深い対談
理論物理学者の大栗先生と仏教学者の佐々木先生による、トークセッションの内容を本にして出版したもの。 最初に「宇宙の姿はどこまで分かったか」と題して佐々木先生を聞き手に、最近の宇宙論について述べられる。続いて「生きることはなぜ「苦」なのか」と題して、大栗先生が聞き手となり仏教の本質を説かれる。そして、「よく生きる」というテーマで対談が行われ、最後にそれぞれの特別講義が収録されている。 大栗先生のお話については、日頃から本など読んだり以前は朝日カルチャーセンターの講座にも参加したことがあるので割と馴染みのあるものだが、佐々木先生の仏教の話、特に学術的な面からのお話はほとんど聞いたことがなかったので、非常に興味深かった。本書の内容から、仏教とは宗教の中でも結構特殊な成り立ちや特色を持っていることが分かった。高校時代に社会の先生が、「仏教はどちらかというと宗教というよりは哲学だと思う」ということを言われたのを覚えているが、本書を読んで、本来の仏教は宗教というのとはちょっと違うようなものではないかと感じた。 本書では、やはり第三部の内容で、世界を正しく見るということが生きるためには非常に重要であること、科学的なものの見方はそれを教えてくれるということが一番印象に残っている。 佐々木先生は仏教学者であり僧侶ではあるけれども、仏教徒ではないというようなことを述べられている。この辺りは自由な発想をされていると感じたが、仏教が他の宗教と異なる自由さみたいなものもあるのではないか。そういえば、ダライ・ラマ猊下も科学に興味があり、その重要性を説いておられたと思う。 仏教が科学と親和性があるというのが興味深い。両者の関係をもっと知りたいと思うようになった一冊だった。
1投稿日: 2020.05.23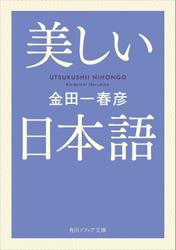
美しい日本語
金田一春彦
角川ソフィア文庫
日本語の良さを再認識
同じ著者による「ホンモノの日本語」の続編にあたるものらしい。日本語そのもののこと以外にも、文化的、歴史的な背景や民族的なことにまで記述が及び、「日本語」という言葉を通して様々なことを学べる一冊だった。 ただ、これはどちらかというと新作ではなく、今までの著者の作品の書き直しをベースにしてあるので、「ホンモノの日本語」を読んだ後に新鮮さが感じられなかった。 内容は全体的に興味深い。日本人が日本語を理解する上では重要なことが散りばめられていると思う。
0投稿日: 2020.05.23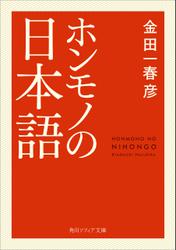
ホンモノの日本語
金田一春彦
角川ソフィア文庫
改めて日本語の素晴らしさを知った。
辞書の編纂も行なっている著者が、日本語の特徴や日本語を通してわかる日本人の性質などにも触れる。 普段何気なく使っている日本語だが、改めて「そういう意味だったのか」と気づかせられたり、深い意味を知らずに使っていたことも考えさせられた。個人差はあるだろうが、どんな言語を使っているかという観点から、日本語を使う日本人と欧米人の考え方の違いなども説明されていて、非常に興味深かった。 自分では意識していなかった日本語の素晴らしさを教えられた一冊だった。
0投稿日: 2020.05.17
時間は存在しない
カルロ・ロヴェッリ(著),冨永星(訳)
NHK出版
ループ量子重力理論に興味が湧いた。
題名が衝撃的だったが、読み進めて行くとこんな訳語の題名もなかなか面白いと感じた。原題をそのまま訳すと「時間の秩序」とかなんとからしいが、やはりあまりインパクトがないので、この題名の様な意訳にしたのだろう。 本書以外にも時間に関する本を読んだことはあるが、今まででは本書が一番印象の強い説明で、自分でもぼんやり考えていた時間像が、ある程度自分なりにまとまって腑に落ちた気がする。 物理学での時間を示す変数tの扱いには、過去や未来の区別は確かにないけれども、人の意識は時事刻々と一連の事象を経験し、過去の記憶はあっても未来の記憶というものは持っていない。不可逆現象を表す熱力学第二法則が、何かヒントを与えてくれるのではないかと考えていたが、本書の内容を読んで、全ては量子情報がキーポイントなのではないかと考える様になった。 数式もない一般向けの本だが、概念が結構難しいので、自分としては一読して理解できる内容ではなかった。なんとなくイメージはつかめたので、また読み返して理解を深めたい。 以前に読んだイーガンの小説がループ量子重力をネタにしていたので、学びたいと思っていたが、本書を読んでますますループ量子重力に興味が湧いてきた。時間変数のない理論というのも興味深い。
0投稿日: 2020.05.03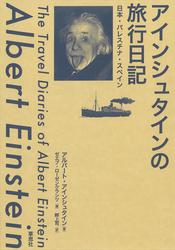
アインシュタインの旅行日記:日本・パレスチナ・スペイン
アルバート・アインシュタイン,ゼエブ・ローゼンクランツ,畔上司
草思社
日本の印象だけでも読む価値があった。
杖の師匠に紹介されて読んだ一冊。 物理学者のアインシュタインが、日本を旅行したときの日記が収録されている。パレスチナや香港なども収録されているが、日本について全体的に好ましいイメージを持っていたことが読んでいてわかり、嬉しく感じた。 この当時、ヨーロッパから見たら、日本は極東の小さな島で、よくわからないこともあり、神秘的な印象を持つ人は多かった様だ。アインシュタイン博士も例外でなく、東洋の小さな島国にもかなり関心があった様である。やはり日本人といえばその自然と礼儀正しいことが好ましい例として取り上げられるが、本書でも 「自然と人間が、ここ以外のどこにもないほど一体化しているように思えるのです。この国から生まれるものはすべて愛くるしくて陽気で、決して抽象的・形而上学的ではなく、常に自然を通じて生まれてくる現実と結びついています。」 「日本人のことをお父さんは、今まで知り合ったどの民族よりも気に入っています。物静かで、謙虚で、知的で芸術的センスがあって、思いやりがあって、外見にとらわれず、責任感があるのです。」 と述べている。 アインシュタイン博士が日本を訪れたのは大正時代だが、戦前の日本人のような、欧米人から見て素晴らしいと感じるような民族性が現代日本人にもあるのだろうか。戦後の日本の発展は目を見張るものがあるが、この日記に書かれているようなもので、失われてしまった伝統的良さも案外多いのではないだろうかとも感じた。
0投稿日: 2020.05.03
N.Yokoyamaさんのレビュー
いいね!された数5
