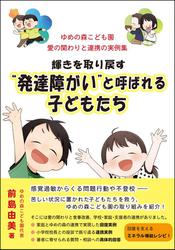
輝きを取り戻す“発達障がい”と呼ばれる子どもたち ゆめの森こども園 愛の関わりと連携の実例集
前島由美
どう出版
広く知られて欲しい。
杖の師匠から紹介された本である。 保育士としての経験を持つ著者が、発達障がいと診断される子どもたちについて、その食生活の見直しを柱とした療育により、様々な問題解決を実践した記録を残したもの。 最近では、発達障がいという言葉を聞くのも、あまり珍しいことではなくなったが、それでもそういった子どもたちへの対処は、なかなか難しい問題があるようだ。大体は、医師に相談して薬をもらうことで何とかしようとするが、向精神薬というのは、子どもに飲ませるには副作用が強く、害悪であるらしい。確かに薬で抑えるというのは一時的なもので、問題の解決にはならないと思う。本書は、現代の食品添加物などが弊害になっていると考え、食の見直しから療育を実践すればうまくいく可能性を示しており、今後、このような療育が主流になっていけば理想かなと感じた。 とはいえ、ここには成功例が並べてあるのだが、多分、良いことばかりでなくて、苦労も同じくらいあったのだろう。食は大事だろうが、その他のサポートもしっかりしていなくてはいけないだろう。ちょっと気になったのは、現代医療の否定や、根拠のない自然崇拝に陥ってしまうような書き方がしてあったところがあることか。 ぼくには子どもはいないし、妹の子も特に問題なく成人したので、こうした問題を身近に感じたことはなかったが、本書でこのような取り組みを知って、今後、世の中に広まって欲しいと感じた。
0投稿日: 2021.06.06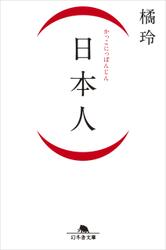
(日本人)
橘玲
幻冬舎文庫
イメージとは違ったが...
想像していた内容とはだいぶ異なるものだったが、読んでみて非常に面白かった。最初は日本人という題名なのに、なんかタイの話とか、グローバルスタンダードとか出てきて良く分からなかったのだが、読み進めていくうちに、自分が持っていた「日本人」というイメージが、実は外から吹き込まれたものではないかと思うようになった。 「本当の日本人の姿」というものは何だろうという疑問は残るが、実際の「日本人」というのは巷で言われているような伝統を重んじる民族というものではなく、著者が分析している姿の方がしっくりくると感じた。 そういえば、自分は確かに環境が変われば対人関係も変わり、基本的に以前の知り合いとは特に親しくすることはない。学校などの同窓会を好む人もいるだろうが、自分は全く興味がない、つまり過去の人間関係には全く興味がないことを、本書を読むことで改めて実感した。 こんなことを意識しながら、日常生活を送るのも面白いと思う。
0投稿日: 2021.06.06
孤独の価値
森博嗣
幻冬舎新書
孤独は好き
小説以外の著作も結構興味が出てきたので読んでみた。 自分も概ね著者に同意するし、著者のような生活は自分も夢見ていた。まあ、誰もがこんな風に生活できれば良いのになというのは、ぼくだけの考えだろうか。 やはり、今の社会は何となく情報過多で、多くの人々が様々な意図を持って発信される情報に翻弄されているような気がする。子供の頃は、情報源が少ないせいもあったが、今よりは単純な生活、目的のはっきりした日常が送れたと思う。一方的に価値を押し付けられているかもしれない状況でも、あまりそれに気づいていない。「孤独」という言葉のイメージも多分、様々なメディアから発信される情報によって作られたものだろう。 ぼくはどちらかというと、筆者のように一人で静かに落ち着いた状況が好きである。もちろん、他人との付き合いは拒むものではないが、「孤独」という言葉は嫌いではない。子供の頃は、結構友達に嫌われたり、仲間外れにされるのが怖いという気持ちがあったが、歳をとるにつれ、いつの間にか気にならなくなった。良く同窓会などで昔の友人に会いたいという話を聞くが、もう30年近く同窓会などというものには縁がないし、高校や中学時代の友人に積極的に会いたいとも思わない。確かにこんな考え方だと「寂しいやつ」と思われるかもしれない。 本書の内容は、自分には共感できることが多く、自分の日常や普段から考えていることを省みることができて良かったと思う。
0投稿日: 2021.06.06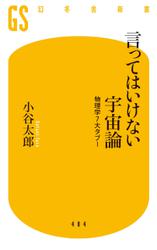
言ってはいけない宇宙論 物理学7大タブー
小谷太郎
幻冬舎新書
意外なことも書いてある。
物理学の7大タブーと言われるものを紹介している。 どれも面白い内容だったが、量子力学の解釈問題はまだ、波動関数の収束ということを問題にしているとは思わなかった。波動関数は物理的実在を示すものではなく、収束は観測者の持つ情報の変化であるという考え方だと認識しているが、ペンローズ博士などは、知識の変化ではなく物理現象だという見方をしているらしい。波動関数が示すいくつかの世界から、意識が時事刻々と一つの事象を選ぶメカニズムを物理的に説明することが出来ない限り、量子力学は完全ではないということなのだろうか。最近、ペンローズ博士が脳関係の著書を出していると聞いたが、そのことに関するものだろうか。 実験が技術的にできそうにないような理論も、いづれは何らかの方法で別の検証方法が提示され、本書に書かれている疑問が解かれていくのを期待している。 多分、当面は一般相対論と量子論が統合されるところが焦点となるのだろう。
1投稿日: 2021.06.06
ジャイロモノレール
森博嗣
幻冬舎新書
失われた技術
ジャイロモノレールは、20世紀初頭に未来技術として期待されたモノレールである。残念ながら、その後の世界大戦によりその構想は中断され、堅実で実用的な技術が追求される中で省みられなくなってしまった。 その後の鉄道は、コストや工事の方法などから2本レールが主流となり、ジャイロモノレールは失われた技術となってしまったということだ。 本書は、著者が実際にジャイロモノレールの技術文献を追い、その理論や実験を踏まえてモノレールの模型を試作していく過程がわかりやすく記されている。今日では特に何かメリットがある技術という訳ではないが、機械技術の面白さを追求した一冊に感じた。 自分は、今ではあまり模型作りに興味がなくなってしまったが、子供の頃はプラモデルなどにも興味があり、いくつか作っていた。しかし、不器用なためかあまり良い出来のものが作れず、学校の工作でも下手だったので、いつしか模型作りに興味がなくなってしまった。それでも、乗り物の技術は興味があり、その失われた技術の理論は非常に興味深かった。模型作りを趣味にしている方は、一層興味を持って読める内容だと思う。 ジャイロによって、レール1本でも自立して移動できる乗り物の原理が説明されていて、非常に面白かった。
0投稿日: 2021.06.06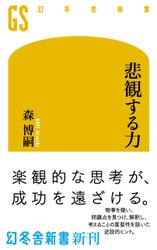
悲観する力
森博嗣
幻冬舎新書
タイトルに興味が湧いた。
タイトルに興味が湧いて、読んでみた。 著者はミステリー小説家だが、元は大学の工学部の助教授で、小説以外の著書も読んでみたいと思ったのもある。 内容は、だいたいフェイルセーフティーについて、人生に活かすようなものだと思う。本書を読んで、自分の日常生活で見直すべき部分、普段はあまり考えない部分について改めて考える機会を持った。 悲観という言葉の響きが良くないのかもしれないが、世間でいう言葉通りの意味ではないように感じる。日頃からの備えは多分、誰しも必要だと思っているが、なかなか実行に移せない人間は多いだろう。今一度、自分の生活を見直したい。
0投稿日: 2021.06.06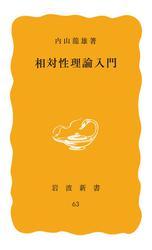
相対性理論入門
内山龍雄
岩波新書
興味深い相対論入門
日本で相対性理論の研究者といえば、知らない人はいないと思われる内山先生の著書。 色々と武勇伝のようなものがあると言われている著者が、一般向けに啓蒙書を出しているとは知らなかったので、興味があって読んでみた。やはり、啓蒙書ということで、なかなか書き方に苦労されているところはある。 多分、この時代に結構相対性理論が流行って、こうした第1級の研究者が依頼される機会が多かったのかなと思う。ただ、自分としては、今となっては数ある啓蒙書の一冊だという印象になってしまった。
0投稿日: 2021.06.06
時間はどこから来て、なぜ流れるのか? 最新物理学が解く時空・宇宙・意識の「謎」
吉田伸夫
ブルーバックス
時間は実在しない。
非常に面白かった。 時間については、これまでもわずかながら書籍を読んでいて、非常に興味を持っていた。少し前に、カルロ・ロヴェッリ氏の著書を読んで、何と無く自分なりの答えがつかめて来ていたが、本書を読んで、さらに自分なりの理解が深まったように感じる。 本書は2部に分かれていて、前半で時間とはどういうものかの本質に迫り、後半でその性質からくる様々な疑問に答える構成になっている。自分にとっては、とてもわかりやすく、興味深い説明が聞けたと思う。 時間とは、誰にも尋ねられなければ自明のものだが、誰かに説明しようとすると非常に難しいものだという。もう少し読み込んで、自分の言葉で説明できるようになりたい。
0投稿日: 2021.06.06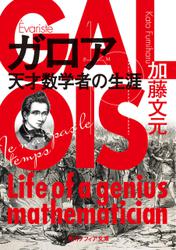
ガロア 天才数学者の生涯
加藤文元
角川ソフィア文庫
ガロアを知る上での良書
天才数学者ガロアの短い生涯が、当時のフランスの時代背景とともに詳細に描かれている。 ガロアについての逸話は、色々な書物に書かれているのだと思うが、この本を読んで結構間違って伝えられているのではないかと思うところが割とあった。著者は、本当にそういう話だったのかと、史料などから再検討している部分も多く、実際のガロア像を掴むのに非常に良い一冊だと思った。 コーシーのような大数学者が、ガロアの能力を正しく評価できなかったとか、よく聞く逸話ではあるが、これも実際はそうではなく、それがまたガロアの悲劇を一層深刻にしているような感じもした。 決闘についても、謎が多いようだが、数ある説について考察をしてはいるが、一応客観的事実を述べるにとどめている。 ガロアという天才数学者を知る上では、とても良い一冊だった。
0投稿日: 2021.06.06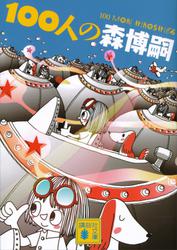
100人の森博嗣 100 MORI Hiroshies
森博嗣
講談社文庫
どうかな。
本書は、著者の作品のあとがきを集めたものや、著者による他作家の作品紹介と評論である。 あとがきだけ読むというのも、あまり面白いものではないかなと思った。作品を読んだ後に、読むのならまあちょっと意見交換みたいなことはできるが、正直、こういうのは実際の作品を読むのと比べると、あまり魅力的ではないと思った。 やっぱり作品そのものが読みたい。
0投稿日: 2021.06.06
N.Yokoyamaさんのレビュー
いいね!された数5
