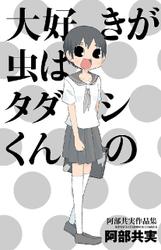
大好きが虫はタダシくんの 阿部共実作品集
阿部共実
週刊少年チャンピオン
このシュール感
以前から、ジャケットとタイトルが気になっていました。 今回読んで・・・すごいですね。 面白いとかそうでないとかを、突き抜けています。 アズマニア後期の壊れっぷりがわかる人にお勧めです。
0投稿日: 2017.09.26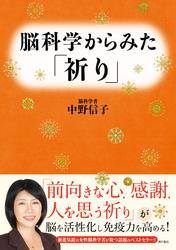
脳科学からみた「祈り」
中野信子
潮出版社
牽強付会かな
この著者の本は面白いのが多いけど、この本はちょっと疑問。 「祈り」をテーマに書かれているが、少々こじつけな所もある。述べたい意見に、これまでの脳科学分野の研究結果を拾ってきてくっつけている感じ。 一番変と感じたのは、「南無妙法蓮華経」のお題目の音韻分析をしているところ。お題目にはマ行、r,kが含まれていてそれぞれの長所を述べていて、響き自体に、深遠な意味合いや力強さを含んだイメージがあるとか。じゃあ、「みなころし」も同じなの? その上「法」は「母」に通じるって・・かなりトンデモな感じがします。 長くない本なのですが、途中で流し読みしてしまいました。
0投稿日: 2017.08.31
京都ぎらい
井上章一
朝日新書
よーわからん
京都の中でもヒエラルキーがあるとは、初めて知った。京都人は大阪、神戸を見下しているという意識があるのは有名(?)ですが。大阪で育った私としては、淀川と大和川を境として、北摂となにわと、大阪南部(河内とか和泉とか)の3つがあって、それぞれ「別もん」の意識があるとは思うが、上下があるかと言えば ??である。 しかし、著屋は何を言いたかったのだろう。京都市の辺縁からみた洛中、ひとくくりの京都人から見た東京、そこらへんを語っているが、定まったビジョンが感じられず、何を伝えたかったのが、まさに「よーわからん」なのでした。 ちなみに、「かみひちけん」は賛成です。本文読んでいて、ルビにわざわざ(ママ)がついていたのは、何で?と思っていたが、後書きを見て納得。
0投稿日: 2017.08.21
被差別のグルメ(新潮新書)
上原善広
新潮新書
食物の歴史書としても読める
「被差別の食卓」の続編とのことだが、こちらを先に読了した。「・・食卓」が世界の食事を題材にとっていることに対して、本書は日本での食事を重点的に記載しているとのこと。 見たことも聞いたこともない料理がほとんどで、個人的には想像を逞しくして読むことができた。 ただ冒頭に書かれていたような、提供した食事から妻の出自がばれて云々という話題は、私からはにわかに信じがたかった。確かに、アブラカスというものは、食品でなく肥料(植物性油脂を絞った残渣)の事しか知らなかったが・・・その一方、四国で肉屋で普通に売られていたイリカスという食品をみて、まさに著者の言うアブラカスと同じものと思い、ある種複雑な感銘を受けたことがある。 著者のスタンスは、特にこれらの食品や料理を淡々と述べていることにほぼ終始し、いわゆる偏見や差別意識はこの書籍からは生まれるはずはないと信じることができる。 イラブー料理は美味しいですよ
0投稿日: 2017.08.16
私家版 差別語辞典
上原善広
新潮選書
差別の歴史と現状は?
ひと昔前と比べて、部落解放運動は表面にはあまりでなくなってきたと思う。 しかし、「放送コード」「放送禁止用語(公式にはそのような用語はないとも聞いているが」は今も存在している。 現在も、あまりにこれらの言葉が多く存在していることに驚かされる。 ただ、被差別部落のことを著者は「路地」と表現している。他の著者の表現を使ったとのことではあるが、私は幼少時から単なる細い道を路地と呼称しており、なぜこの言葉を使用したのか、最後まで異和感を感じた。 また、差別される職種も色々記載されている。猿回しについては村崎太郎氏が自身も述べられていることもあり知っていたが、この書籍の中には木地師や陰陽師まで含まれているのはどうだろう。その意図がわかりにくかった。 民族としてアイヌに対する差別の歴史についても記載がある。しかし、それより北方の少数民族が強い差別を受けて、救済されなかったことにはもっとも驚きと悲しみを禁じ得なかった。
0投稿日: 2017.08.16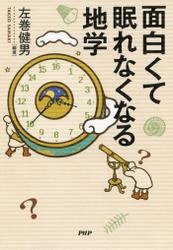
面白くて眠れなくなる地学
左巻健男
PHP研究所
やさしい解説本です。
地学関係のことを広く、わかりやすく解説しています。 ただ初心者向きで、残念ながら私は新たな知識を拾うことができませんでした。
1投稿日: 2017.08.16
カンブリアンモンスター図鑑 カンブリア爆発の不思議な生き物たち
千崎達也,左巻健男
秀和システム新社
生物の多様性
タイトルに惹かれて購入しました。 まず、イラストが素晴らしいです。そして、生物相の「爆発」がいかにすさまじいものであったか、その多様性に思いを馳せることができました。 このあたりの生物は、本に表現されているよりもかなり小さいはずなのですが、もし現代にもいたら、怖いででしょうね。我々のご先祖様かもしれないのに・・・
0投稿日: 2017.08.16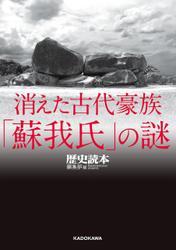
消えた古代豪族「蘇我氏」の謎
『歴史読本』編集部,古川順弘
中経の文庫
読みやすいです。
「蘇我氏とは何だったのだろう」と思い、読み始めました。なぜそこの思い至ったのかが想い出せないのですが(笑) 蘇我氏の全体的な興亡、一族の個人紹介、遺跡とあり、それぞれが非常に読みやすく、どんな人々がいたのかの理解が進みました。 第4章で梅原猛の解説が入ります。仏教の導入、藤原氏との確執などを含め、蘇我氏がいたことが日本にどのような影響を与えたのか、非常に面白い説明を見ることができます。 ところで、蘇我氏は滅亡していないんですよ。
0投稿日: 2017.08.16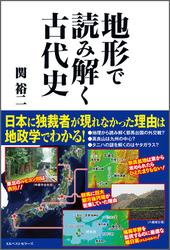
地形で読み解く 古代史
関裕二
ワニの本
是々非々です
地形の面から、古代の勢力争いを解こうとする本でした。この著者の作品は初めてです。 冒頭の、平城京と平安京との違いとして、西側が険峻な平城京、東側が険峻な平安京の特色を上げて、それから、どちらに敵勢力が存在していたのかを解析する方法は斬新と思われました。 しかし読み進めるにつれて、著者の歴史に対する見解にかなり独特なものを感じてきました。これが最新の一般的歴史認識? いやちがうのでは?思われる記載も目立ってきます。その論拠として地形のことを挙げているのですが、だんだん牽強付会じゃないか?と思われ、残念ながら読了できませんでした。
0投稿日: 2017.08.16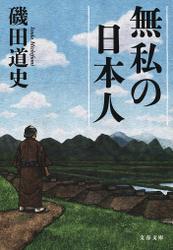
無私の日本人
磯田道史
文春文庫
無私とは・・
穀田屋十三郎、中根東里、大田垣蓮月という3人が題材に取り上げられています。この本を読むまでは皆さん知りませんでした。いずれも壮絶な人生を送った方々です。 さてここで「無私」ですが、私自身は滅私奉公のような、己を犠牲にして世の役に立つというイメージを持って読み始めました。穀田屋十三郎は、確かにその通りです。しかし、中根東里、大田垣蓮月はどうか。「私欲」から連想される、名誉欲や権力欲、金銭欲は本当になかった点で同じです。しかし、表だって広く世の役に立とうという行動も皆無です。すなわち、自分が本当の自分であることを貫く姿勢を見ていると、「私」が「無」いという無私とは対極なんですね。そういった意味では、中根東里、大田垣蓮月に対しては強烈な「私」を感じました。 素晴らしい本です。
0投稿日: 2017.08.16
arikaさんのレビュー
いいね!された数35
