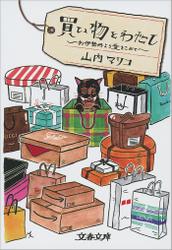
買い物とわたし お伊勢丹より愛をこめて
山内マリコ
文春文庫
自分の価値観を変える買物の仕方
『美味礼賛』の著者ブリア・サヴァランが、 「ふだん何を食べているのか言ってごらんなさい、そしてあなたがどんな人だか言ってみせましょう」 と言ったのと同じように、 「ふだんどんなものを買っているのか言ってごらんなさい、そしてあなたがどんな人だか言ってみせましょう」 という関係性もなりたつのではないだろうか。 買物はその人を映す。 お伊勢丹、つまり伊勢丹は山内にとって、 ”百貨店に対する畏敬と憧憬をいまもかき立ててくれる特別な場所” なのであり、そこで買うものを探すということは、一流を買うことでもある。 生きることは、買うことだと山内は冒頭で言うのだけれど、まさにその通り。 買物を続けていくうちに、買ったものが関係する社会や環境、自分とその周囲の人びとについて、 山内は考えるようになり、買う=消費という構図から離れた自分も社会もサステイナブルな ものの買い方をするようになる。 世の中のひとすべてが、考え、持続可能な買物ができたら、世界は大きく変わる。
0投稿日: 2016.05.08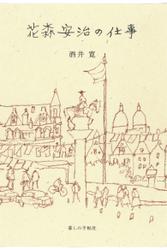
花森安治の仕事
酒井寛
暮しの手帖社
時代は変わっても変わらない課題と矜持
NHK朝の連続テレビ小説「とと姉ちゃん」のモデルは、 暮しの手帖社社長で、雑誌『暮しの手帖』の編集者であった大橋鎭子である。 その大橋とともに「暮しの手帖」を創刊し、編集長として辣腕をふるったのが花森安治だ。 花森は変わった人であるというのがもっぱらの評判であり、 いまにまで伝わる伝説のようなものである。 女装をすることがあり、相当に偏屈で神経質、 そしてこと雑誌づくりに関しては異常ともいえるほどのこだわりを見せた。 本書は、そうした花森の仕事ぶりを学生時代や大政翼賛会での戦争協力していた時期のことまで取材し、 丁寧にその生涯と仕事っぷりを明らかにしてくれている。 大橋からの女性のための雑誌を作りたいと誘いを受け、 「男たちの勝手な戦争が国をむちゃくちゃにした」のであり、 「自分も女性のために償いたい」と考え、衣裳研究所として『スタイル・ブック』を発行。 その後、48年、『美しい暮しの手帖』(後の「暮しの手帖」)を発行。 広告なしの雑誌で、最盛期には90万部を発行。 徹底して庶民のための雑誌づくりを行なった。 広告をとらないからこそできる商品テストは、使用中のストーブを倒して燃えないかを試し、 フライパンは本当に耐久性があるのか1ヶ月でも使い続け、 洗濯機ではどんな汚れがどのくらい落ちるのかを実験し、実証的に示してみせた。 これはいまの広告ありきの雑誌で絶対にできない。 それは誰のために雑誌をつくるのか、何のためにつくるのかが花森には明確だったのだ。 消費者に見えないように巧妙に企画されたステマやタイアップという名の広告が入り込み、 何を信じていいいのかわからないいまの状況にあって、 「暮しの手帖」が行なっていた精神をいまいちど消費者の目線から考えてみる必要がある。 お金を払う人間が賢くなること、共に賢い消費者になることを応援してくれるメディアを育てること。 この本に描かれる花森の哲学には、時代は変わっても変わらない課題と矜持が込められている
1投稿日: 2016.05.02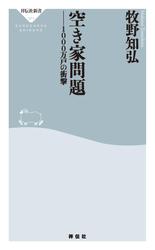
空き家問題
牧野知弘
祥伝社新書
日本大丈夫かな…
2020年の東京オリンピックまで、建築界の需要は右肩上がりになると思われる。 高層マンションや交通インフラなどを含めた大規模建築がラッシュになるなか、 日本全国で空き家が問題になっているのをご存知だろうか。 毎年20万件増加し、20年には1000万戸を越え、うち空き家率は15%に上るとされている。 高齢化が起こり、出生率も増えず、人口が減少。 核家族化や単身者住まい、晩婚化、夫婦のみの生活等、様々な要因が重なり、 今までの住宅ストックではライフスタイルが合わず、新しい住宅がつくられ、 過去の物件は残され、空き家となっていく。 建てなおす費用もなければ、住まない物件は潰して更地にすればいいと思っても、 解体費用もかかれば、建物が建っていない土地には高い固定資産税がかかってしまう。 相続によって土地が分割されてしまうこともある。 空き家を残しておくことで使わない水道などのインフラは老朽化し、 そこから悪くなることでその地域一帯への影響が出ることもある。 さて、ではこうした問題はいったいどう考え、何をしていけばよいのか。 社会状況、法的な制限、これからの景気や資産状況など現状の知り、 まだまだ見えない2020年以降の日本を考えてみる必要がありそうだ。
0投稿日: 2016.05.02
ランチのアッコちゃん
柚木麻子
双葉文庫
わたしを変えてくれることのよろこび
派遣社員として行った先にアッコさんがいたら、 さぞ楽しく充実した仕事ができそうだ。 派遣先の出版社で働く三智子は、彼氏にフラれ落ち込んでいた。 そんな時、派遣の三智子とは相手をしてもらうこともほとんどなかった部長の黒川敦子ことアッコさんが、 突如三智子のお弁当とアッコさんが毎日食べているランチを交換しようと申し出てきた。 手作りのお弁当というのはいつも丁寧な暮らしをしているようでいて、 結局ひとりでもくもくと食べることになってしまえば、 食が生み出す豊穣な関係性や場の空気の味わいをすっかり失ってしまう。 三智子が曜日ごと決めていたランチコースをめぐるうち三智子は、 あたらしい自分、気づいていたけれど表に出せなかった自分を見つけていく。 ちょっとぶっきらぼうだけど、やさしいアッコちゃんの言葉と行動、 自分から変われない三智子にとって変えてくれる存在の暖かさは何よりも心地よいのだった。
0投稿日: 2016.05.02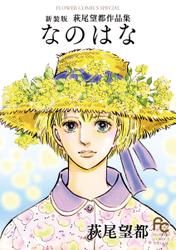
なのはな 新装版
萩尾望都
月刊flowers
自らが求めたもので滅びるということ
40年の時を経て『ポーの一族』の続編執筆が発表された萩尾望都。 萩尾が2012年、その前年の東日本大震災と福島原発事故に衝撃を受け執筆されたのが、 表題作の「なのはな」から始まる放射性物質三部作。 震災で行方不明となった祖母の帰りを信じる人間と信じたいけど諦めている人間。 地震と津波だけでなく、放射性物質によって帰ることすら困難になった自分たちの生まれた場所。 そこにいるはずの祖母、生きていたらみんなで楽しく暮らしていたはずの家族。 放射性物質を取り除く力があると当時言われた”なのはな”は、かつての自分たちの”家”を返してくれるだろうか。 そして プルートとウラノスという名で擬人化されたプルトニウムとウランの放射性物質。 人間が求め現れたはずの魔女は、人間を殺さずにはいられない存在だった。 人間は自らがつくりだしたもので滅びるという選択肢を選んでしまったのか。
0投稿日: 2016.05.02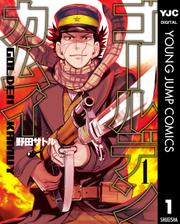
ゴールデンカムイ 1
野田サトル
週刊ヤングジャンプ
とにかくいろいろサバイブする方法
単一民族国家という幻想のようなものを信じてしまうと、 アイヌなどの存在を日本人はどうあつかってよいかわからなくなってしまう。 アイヌを語る、アイヌを作品のなかで扱うということは、 何を語ることになるのか。 日露戦争後の北海道、死んでも死なない”不死身の杉元”と呼ばれ、 多くの人間を殺してきた軍人である杉元佐一が主人公。 日本人から迫害を受けていたアイヌの人びとが軍資金とすべく貯めた金塊を奪った男がいた。捕まったその男は、金塊を隠した場所の秘密を網走刑務所の囚人たちにある方法で分散的に教えたのだった。 杉元はその秘密を知り、金塊の持ち主であった奪われ殺されたアイヌの娘、アシリパと囚人たちから情報を収集すべく、動き出す。 極寒の北海道で生きていく手段をアシリパから学ぶのだけれど、 狩猟や料理、自然や神との付き合い方など、とても丁寧にかつ、 実証的に書かれており、著者の文化や民族/民俗へのリスペクトが感じられる。 アイヌを描くことは、日本が失ってきたものを描くことであり、 日本が奪ってきたものを改めて見つめることでもある。 もちろんフィクションであることは十分ふまえて。 だって、その金塊に絡む大物があの◯◯組にいるっていうんだから。
0投稿日: 2016.05.01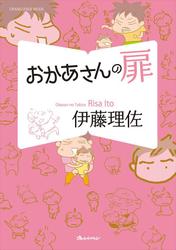
おかあさんの扉
伊藤理佐
オレンジページ
マンガのネタの宝庫としての育児
吉田戦車による育児マンガ『まんが親』の 妻版である『あかあさんの扉』 ページものだった『まんが親』と違い、こちらは4コママンガ。 子育てで経験したことや発見したこと、気づいたことを描くだけでなぜこんなにもおもしろくなるのか、本当に不思議。 夫婦だけで決めていたルールが、いつの間にかまわりの大人の影響でむやむやになってしまうことってある。 離乳食はアレルギーのことなどを考え、ゆっくりはじめて、徐々にあげていたのだが、子を抱っこしてくれいた女性がなんとタラモを食べさせてしまう。 ところが、その女性とはマンガの神、萩尾望都だった… 通常なら、なぜタラモなんてものを!と断固抗議するのだが、 あまりに大物過ぎて、下を向いて受け入れるしかなかったという… どうしようもなくおもしろさになってしまう子どもの行動を、 見逃さず、描きとめておけば、ネタは尽きないのかもしれない。
0投稿日: 2016.05.01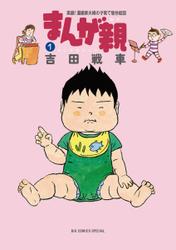
まんが親(1)
吉田戦車
ビッグスピリッツ
子どもの行動や成長に驚き、戸惑いながらも楽しむことの大切さ。
バツイチ同士のマンガ家夫妻。 夫の吉田戦車は45歳、妻の伊藤理佐は39歳。 高齢出産と呼ばれる時期をとうに過ぎたとき、 ようやく「桃が川の上流から流れて」きた。 実録マンガである本書は、マンガが進むと同時に子どもも歳を重ねていく。最新では5歳(今年6歳)になっている。 吉田戦車お得意の不条理節は炸裂しないのだが、 それはそもそも大人から見た赤ん坊が不条理のような存在だから。 その大人にとって不可解な存在が、成長とともに条理(言葉や習慣)を覚えていく過程が描かれていく。 吉田戦車はそのひとつひとつに驚き、迷い、喜び、悲しみながら、楽しんで子どもとの時間を過ごしている。在宅仕事のマンガ家は特にそのいつも見ている感がすごい。 仕事で出ている親にとって、一日中ずっとその姿や声を意識の隅に置きながら仕事をするマンガ家夫婦の観察力はさすが。 巻を重ねると娘さんの自我がよりハッキリして、「私をマンガのネタにしないで!」と抵抗し、吉田さんが執筆を断念する日もあるのかsもしれない… 奥さんの伊藤理佐さん側から描いた『おかあさんの扉』というエッセイマンガも、合わせて読むことをお勧めいたします。
0投稿日: 2016.05.01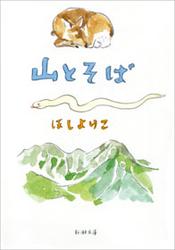
山とそば(新潮文庫)
ほしよりこ
新潮文庫
ほしよりこ本人が、旅に出た。
猫村さんでおなじみほしよりこ本人が、旅に出た。 旅は道連れ、ひとりときもふたりのときも楽しい旅は、 行く先々でいろいろ人に出会い、おいしいものを堪能する。 特に描くために始めたわけじゃないこの旅は、 途中でノートを買ったことで記録されることになる。 旅をした時間や場所、味、ことばを思い出しながら断片を繋いでいく。 長野の松本から始まり上高地へ、シロヘビを見るために福岡から岩国へ行き、 鹿児島では名物”白熊”を食べる。 何気ない旅のようで、心地いい場所、おいしいお店を見つけるうまさはすごい。 旅行ガイド的に使うには自分で調べなきゃいけないことが多いのだけれど、 何気ない旅の思い出を写真に撮って残すのではなく、 頭に残った思い出を絵に描き起こすという作業は、作者ともう一度旅を楽しむような感覚がある。
0投稿日: 2016.04.01
無敵の人(1)
甲斐谷忍
週刊少年マガジン
運は必要であるが、絶対ではない。
『ライアーゲーム』の甲斐谷忍が、描く新たな駆け引きと勝負の世界。 今回描かれる舞台は雀卓もしくは、モニター上の雀卓。 Mと呼ばれるネット上に突如現れた天才雀士。 あり得ないほどの強さでイカサマ以外でそんなことはあり得ないと、 その存在は伝説となり、正体とその手口をつきとめたものには、賞金がかけられた。 その強さの正体は、読んでいただくとして、 麻雀が持つゲーム性はたまらなくおもしろい。 多くは運だと言われるが、それはどこまで本当か。 運は必要であるが、絶対ではない。 では、何が強さを支えるのか。 その支えるものこそが個性であり、 牌を通じてぶつかる異能を刮目してみよう。
0投稿日: 2016.03.31
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
