
息の発見
五木寛之,玄侑宗久
角川文庫
仏教的観点から考える呼吸と人の生きる道。
五木寛之が、何事にも興味がわかなかったある時期、 自分の知らない世界のプロフェッショナルと対話するという企画が持ち上がる。 大ヒットした『大河の一滴』をはじめ仏教観に支えられた様々な作品を発表している五木が、対談相手に選んだのは作家で住職の玄侑宗久。 テーマは人間の生命活動の基本である呼吸。 実は、仏教の創始者であるブッダは息づかい=呼吸法について詳しく語っており、その教えが「アーナ・アパーナ・サティ・スートラ」という文書にまとまっている。 息絶える、長息(長生き)などい息は、まさに命そのものである。 玄侑によれば、下痢も風邪も呼吸で治るという(これは信じてない)。 自律神経が体をコントロールしているなか、唯一自分で調節できる呼吸。とはいえ普段の呼吸は無意識でしている。そうした”意識的な無意識のコントロール”をするための呼吸法としての瞑想や読経がある。 仏教的観点から考える呼吸と人の生きる道。
1投稿日: 2016.03.31![新編チョウはなぜ飛ぶか [フォトブック版]](https://ebookstore.sony.jp/photo/BT00002630/BT000026303700100101_LARGE.jpg)
新編チョウはなぜ飛ぶか [フォトブック版]
日高敏隆,海野和男
朝日出版社
「ものを探している」が答え
世界の動物行動学の第一人者、日高敏隆。 残念ながら2009年に他界してしまいましたが、 没後も著作が出版されつづけるほど、年齢性別を問わず広く愛された学者でした。 75年に出版された「チョウはなぜ飛ぶのか」に、 日高の教え子である昆虫写真家・海野和男の美しくも神秘的な写真を追加。 読むだけでなく、見てわかるという構成。 『チョウは「なぜ飛ぶか」といったら、「ものを探している」が答えだ。 探すものは三つあって、食べものであるミツをもつ花と、卵を産む場所と、それからメス』 チョウは、ふらふらとどこへ行くのかわからないような不安な飛び方をします。 ところが実際は、そこにチョウ道と呼ばれるすすむ道があるのだそう。 地形や光、温度、木の葉の種類などを1mしか見えない視力で見分け、 上に下によろよろと羽をはためかせているのだそうです。
0投稿日: 2016.03.31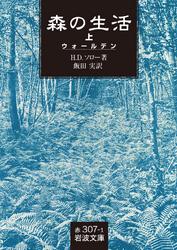
森の生活 (ウォールデン) 上
ソロー,飯田実
岩波文庫
むき出しの自然と気持ちよく上手に共生することの喜びと厳しさ
アメリカの作家であり詩人、博物学者、そして環境保護運動の先駆者でもあったヘンリ・デイヴィッド・ソロー。 人間と自然の関係を描いた作品を多く手がけ、ネイチャーライティングの代表的書き手としても知られています。 1845年9月7日、アメリカの独立記念日。ボストンの北西にあるウォールデン池で自給自足の生活を始めます。最も近い隣家まで1マイルあるような森での生活で、詩や古典、旅行記から科学書まで彼はひたすらに本を読み、何キロ、何時間も歩きつづけ思索にふけりました。 「私が森に行って暮らそうと心に決めたのは、暮らしを作るもとの事実と真正面から向き合いたいと心から望んだからでした。生きるのに大切な事実だけに目を向け、死ぬ時に、実は本当は生きていなかったと知ることのないように、暮らしが私にもたらすものからしっかり学び取りたかったのです。私は、暮らしとはいえない暮らしを生きたいとは思いません。私は、今を生きたいのです。」 むき出しの自然と気持ちよく上手に共生することの喜びと厳しさ、そして意義を感じる森の生活記。
0投稿日: 2016.03.31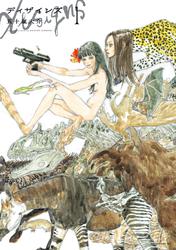
ディザインズ(1)
五十嵐大介
アフタヌーン
デザインされた生命はどこへいく
『リトル・フォレスト』や『海獣の子供』で知られる五十嵐大介は、 どの作品でも目の前の命と壮大な自然、地球という存在をリンクさせ、 生けるものの尊厳を描いてきた。 それは身近な農業という話題だったり、母なる海とのつながりであったり。 今回、描かれるのはたしかに生命の尊厳に関わることではなるのだが、 ハードSF的な世界のなかで生命/遺伝子の操作がテーマになっている。 HA(ヒューマナイズド・アニマル)と呼ばれる半人間は、 欲望にまみれた人間によって利用するためだけに”設計(デザイン)され””生産された” と言える。 人間の進化が行き着く果てにはいないかもしれないつくられた存在。 歴史の文脈に今後も出る予定がなかった特異点的がつくられていく。 神が想定も、望みもしていなかったかもしれないガンダムで言うニュータイプ的な存在は、大いなる自然の法則のなかでどんな生存競争のなかで生きていくのか。 軍事的利用、商業的利用、文化的利用…、理由はさまざまでも彼らはどこかで利用される存在なのかもしれない。 彼/彼女たちは2巻以降どんな動きを見せるのか。 戦いの構図はどうなるのか、人間という存在の醜悪さと希望を同時に感得してみたい。
0投稿日: 2016.03.29
スモーキン’パレヱド(1)
片岡人生,近藤一馬
角川コミックス・エース
人体を改造しても精神は変わらない…?
『デッドマン・ワンダーランド』(http://ebookstore.sony.jp/item/BT000014440500100101/)の著者二人による新作は、 突然進化した人体移植医療が生み出した災いの物語。 両足を失い移植手術を受けた妹を持つ角上陽光。 元の足があったかのような生活を送る兄妹に、 突如襲いかかる悪魔のような存在”スパイダー”。 そして陽光は、新たな人生を歩み始めるのだが、 その体はまったく新しい存在となっていた。 相変わらずのキレまくるキャラクターたちがじゃんじゃか登場し、 世界が終わりを告げる裂け目を時に広げ、時につなぎ、だいたい荒らしている。 それぞれのキャラクターの性格や武器の個性は1巻ではまだまだ。 これからますますおもしろくなっていくであろうことは間違いない。
0投稿日: 2016.03.29![絵本 [復刻普及版]](https://ebookstore.sony.jp/photo/BT00002212/BT000022125300100101_LARGE.jpg)
絵本 [復刻普及版]
谷川俊太郎,WilliamI.Elliott,川村和夫,山田兼士
澪標
300部限定の超レア写真詩集の復刊。
1956年、友人だった詩人北川幸比呂の的場書房から 300部限定で刊行された、「絵本」という名の写真詩集。 300部という限定数もあって、古書店でも伝説の1冊と言われてきた本が50年を経て復刊。 新装版では英訳も付され、より広い読者へ向けたものになっている。 収録されている17枚の写真は谷川自身によるもので、どれも手を写したもの。 言葉を届けるように、手を伸ばし手を取る。 自身の言葉との格闘を明快かつ軽やかな言葉で表現してきた谷川デビュー数年後の姿。
0投稿日: 2016.03.09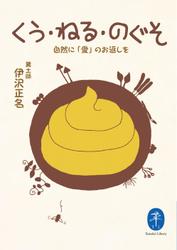
ヤマケイ文庫 くう・ねる・のぐそ
伊沢 正名
山と溪谷社
環境問題を考え、前向きに実践する糞土師の男の記録
野糞は、そもそもは環境問題へのアプローチの一環だった。 糞土師(まさかの予測変換に出てきた…)と名乗る、菌類写真家の伊沢正名。 人に見つからずどこででも野糞ができるわけではない都市化された現在にあって、 連続3000日の野糞達成という偉業を成し遂げている。 そもそも農業などでは、牛が耕作機牽いて歩かせ、 耕しては牛が糞をすることで土壌に栄養素を与えてきた。 土の中では分解と生成が繰り返され、自然の循環が行われている。 キノコなどの菌類写真家という職業は、ある種の必然だったのだろう。 人間が自然の恵みをいただき食べる→糞をする→キノコなど菌類が分解する→ 土の栄養となり、食物となるものが育つ→人間が食べる…という世界の順番が成り立っている。 伊沢はまさにその循環を生き様と職業の両方でもって一気に体験している。 おもしろいのは、堂々と野糞のことを話すようになろうが、こんな本を書くことになろうが、 いかに人に見られないようにするかを懸命に考えていること。 実際は軽犯罪法にひっかかる場合もある都会の野糞。 自分がよく通るあの道のあの木陰でまさか…という記述もあり、 景色を見る目が変わってしまいそうになっている。 紙を使わず葉を使い、手を使い、いかに自然と共存する野糞であることができるか。 実践してみてとは言わないし、自分もやらないけれど、 人も自然もまだ可能性があるんだなーと遠い目をしている。
1投稿日: 2016.03.09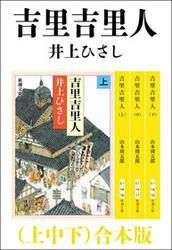
吉里吉里人(上中下) 合本版
井上ひさし
新潮文庫
地方ブーム、憲法問題、国際関係など、まさにいま読むべき傑作。
宮城県と岩手県の県境付近にある一寒村が、日本からの独立を宣言。 「吉里吉里国」と名乗りはじめた。 一体何が起こったのか、地方のひとつの村が独立国として成立なんてするはずがないと思いながら読んでいても、 エネルギーや食料の完全自給自足生活、高度な医療技術、金本位制やタックスヘイブンによる諸外国との連携など、 もしかすると本当に独立ができるのかもしれないと徐々に思い始めている。 全編にわたって、東北弁(いわゆるズーズー弁)で会話が構成され、 徹底的に中央集権、既存の国家権力への皮肉と批評が行われている。 地方ブーム、憲法問題、国際関係など、まさにいま読むべき作品。 ありえない現実を現実にあるかのように見せてくれる小説の力は、 いま我々が考えなくてはいけない目の前の現実に立ち向かう力もくれる。
1投稿日: 2016.03.08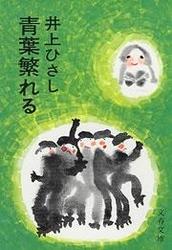
青葉繁れる
井上ひさし
文春文庫
第二の地元、仙台を舞台に繰り広げる青春のどたばた。
山形に生まれ、幼少期仙台へと移り住んだ井上ひさしが、 東北一の名門校と呼ばれた仙台一高時代を半自伝的に描いた小説。 でも描かれるのは、いつも女の子のことばかりを考えている名門校の落ちこぼれたち。 「じつに美(うづぐ)すい女(ひと)だった」 「父ちゃんも好きだったのすか?」 「余計なごというな」。 さすが言語学者並とも言われた日本語の知識を持っていた劇作家。 口語で喋れる方言も、書き言葉に適切に移し替えるのは、意外とむずかしいもの。 リズムも含め、さすが会話で物語をつくってきた劇作家。 会話の仙台弁は見事です。
1投稿日: 2016.03.08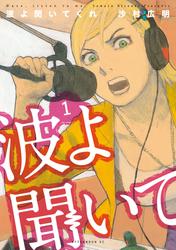
波よ聞いてくれ(1)
沙村広明
アフタヌーン
海に叫ぶのではなく、電”波”に乗せるのだ。
「無限の住人」や「シスタージェネレーター」など、 作画力において日本屈指の漫画家、沙村広明。 時代物でもなく戦闘シーンもない本作でも、 ストーリーやキャラクターの作り方においてその作画力は最大限に活かされている。 というか、全部うまい。 酒屋での愚痴を録音され、公共のラジオ電波に載せられたことから、 ラジオDJへの道にずるずると引きこまれていく主人公のミナレ。 どうしようもない男との経験を淀みないトークで一気に話しきる力を、 絵柄とストーリーの緩急を見事に使い分けて活かしている。 性的な意味ではなく、個性としてどうしようもなく誰かに魅力を感じたとき、 その魅力を最大限発揮させて、おもしろいことをやりたいと思う人間が世の中には存在している。 そのなかでそれをうまく活かせることができるのは、ごくわずか。 当然うまくいくんだろうと考えてしまうマンガにあって、 この稀ともいえる可能性がいかに展開されるのか、思わず読み込んでしまうのだ。
1投稿日: 2016.03.07
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
