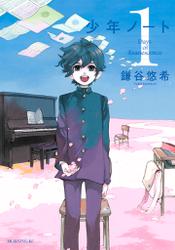
少年ノート(1)
鎌谷悠希
モーニング・ツー
豊かすぎる感受性が取りこぼしてしまう、人と歌と人のこと
個人的には、小中学校の頃の合唱は、最もいやな授業や行事のひとつだった。 もし自分の学生時代に主人公蒼井由多香(あおいゆたか)のような子が転校してきたら、自分の歌への想い、感受性はまったく別のものに変わっていたかもしれない(逆に恥ずかしさと嫉妬で余計に嫌になったかもしれないけれど…)。 由多香は、“天使の声”と言われるボーイソプラノの声を持ち、すべての音が音階として聞こえる絶対音感どころではない、世界のあらゆる音をイメージとして頭に浮かべてしまう、圧倒的な感受性を持った少年だ。転校してきた彼の歌を耳にした合唱部副部長の町屋は、「天使だ あんなに純粋に恥ずかしげもなく 音と遊ぶ人を見たことがあるか?」と心を震わせ、「音の中で息する男の子に私は出逢った」とその出会いに驚く。 しかし世界を音のイメージで捉えるほどの感受性は、彼を放ってはおかない。ひとりではなく皆で歌うことの楽しさと難しさ、何のために歌うのかの苦悩と挫折。鋭すぎる感覚はときに人を潰しもする。だけれど、それを乗り越えた天才の伸び代は、凡人では追い切れない射程にまで伸びていく。 “音”と“歌”を空間の絶妙な使い方で見せ/読ませ、“歌がうまい”ということが絵にできるんだ! という驚くことになる稀有なマンガ。
2投稿日: 2013.10.04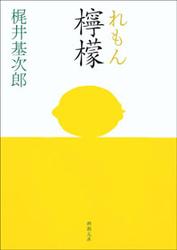
檸檬
梶井基次郎
新潮社
どうにもならない気持ちをやり過ごすということ
「イライラしてやった」、「カッとなってしまった…」というきっかけで起こる嫌な事件がニュースで報じられる日々だけど、「檸檬」の“私”は、そうしたどうにもならない気持ちをどうにかやりすごす方法を教えてくれる。 肺の病気や神経衰弱、そして借金に苦しむ“私”の愛する音楽や文学でも癒えない苦しみが、笑いながら本屋の爆破を想像することで心が解放されていく。実際には、空想上のことでしかなかったとしても。そのとき“私”は、自らの手で現実が変わる可能性を期待していただろうし、すべてを諦めてもいただろう。 作中で檸檬を置いた丸善京都店は、2005年に閉店している。閉店を惜しむお客さんたちが、作品にならい檸檬を『檸檬』の文庫の上に置いていったことが話題となった。閉店から8年。今年の6月、丸善京都店が2015年春にリオープンすることが発表されている。 2015年の春、また本屋で『檸檬』の上に檸檬が並ぶ風景を見ることができるかもしれない。 ちなみに、ちょっと恐い話しだけれど猫をめぐる「愛撫」もいい。(Y)
2投稿日: 2013.10.04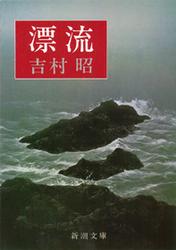
漂流
吉村昭
新潮社
自分に限界を感じたら、読んでみてください。
東日本大震災によって『関東大震災』や『三陸海岸大津波』が注目を集めた小説家吉村昭は、いま最も読み直されるべき作家な気がしている。 吉村は、残された記録や資料、証言、現場検証を丹念に調べあげて書く”記録文学”の代表的作家。「3・11」を彼が経験していたらどんな小説を残したか、そして現実に彼がいない今、その代わりとなる書き手はいるのだろうか。もしくはネットの上の無数の声がそれにあたるのだろうか。 本書は、震災のような多くの人間が共通に経験できるような事件ではない。土佐沖で難破し、伊豆諸島の無人島、鳥島へと流れ着いた船乗りの長平が、仲間たちが続々と死に絶える中、島唯一の食料であるアホウドリを食しながらサバイブし続けた12年間の記録。これは長平自身が残した日記などではない。救助後、漂流者を調べた政府(幕府)側の公的な記録から、つまり淡々とした事実からのみ気付きあげられた壮絶な物語なのだ。 極限を生きた者たちに命を与える、作家にしかできない大切な行為の結果がここにある。
4投稿日: 2013.09.20
理性の限界 不可能性・不確定性・不完全性
高橋昌一郎
講談社現代新書
頭でっかちでどうにもならないアタナへ。
人間が理性的、つまり論理的に考え、検証しても解決できない問題があると”されている”ことはご存知だろうか。 ”選択”におけるアローの不可能性定理、”科学”におけるハイゼンベルクの不確定性原理、”知識”におけるゲーデルの不完全性定理。この三つの”不”を中心に、数学や科学、哲学などにおける理性的思考の限界を、多彩な登場人物がシンポジウムで自由に議論を繰り広げるという形式で考察、検討したのが本書。 会社員を始め、数理経済学者・哲学史家・運動選手・科学社会学者・カント主義者、大学生などなど、総勢36名にも及ぶ人が登場し、時に読者と同じ目線で「分からない」とツッコミが入ることで議論が噛み砕かれている。 ともすると、人間は自らが理性的でありさえすれば完璧で最良の選択ができると思ってしまうけれど、実際は人間の理性も、それに基づいて設計された社会制度や科学も、(薄々感じてはいたけれど)やっぱり完璧ではないんだということに気づくはず。この後、”知性”、”感性”と続く、限界シリーズの第一作目。
1投稿日: 2013.09.20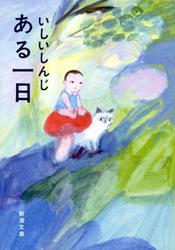
ある一日(新潮文庫)
いしいしんじ
新潮文庫
子どもが産まれるまでの1日は、驚くほど長く、濃密なものだった。
自身の子の出産立ち会いを経験し、「自分が生きてきて一番驚いたこと。余韻がこだましているうちに、書いておかないといけない」という思いから書かれた実話ベースの出産小説。 夕食後に産気づき、出産をし、初乳そして家族の風景へ。子どもが生まれる前日から、24時間にもならないであろう”ある一日”の出産の様子が、立ち会う夫の意識が世界中に飛びながら描かれる。 40代を過ぎて、母子ともに命や健康に危険性が高い自然分娩を望む園子(実在の妻と同名)。お腹の中に10ヶ月もの間ともに過ごした子どもという名の、自分であり他人を、外の世界に産み出す時、そこには分かち難さを乗り越えるだけの痛みが必要だったのかもしれない。するりと出たのでは、何かが終わらず、何かが始まらない。 命をかけた危険で贅沢な長ーい1日を、立ち会うように体験できる濃厚な物語。
2投稿日: 2013.09.20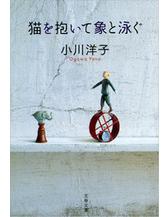
猫を抱いて象と泳ぐ
小川洋子
文春文庫
静かにただチェスをし続けるマシーンとなった、ひとりの男の子のこと。
本作に登場するチェスや将棋、碁のボードゲームは、その無限に広がる板状の可能性の世界をもって、宇宙に例えられることがある。 深く思考の海に潜り込み、考えうるあらゆるパターンの中から最良の選択肢を選び出す。それは相手の意志や戦略を自らの手の考慮に入れた、信じられないほどに高度なコミュニケーションでもある。 ロシアの伝説のチェスプレイヤー、アリョーヒンと同じようで違う、背中合わせの主人公”リトル・アリョーヒン”は、体が子どもの頃から大きくならず、年齢もはっきりしない男の子。自動チェス機の中に入り、自分という存在を消しながらチェスを指し続ける彼。唯一その人だけが生み出せる棋譜でのみ自分の存在が証明されること。 それは果たして悲しいことなのか。人が生きる以上に生き続ける自らの思考の軌跡。自然でいながら圧倒的な情報量を持つあまりに見事な言葉の選択と、静謐な世界を豊かに表現する物語の奥深さ。
2投稿日: 2013.09.20
わたしを離さないで Never Let Me Go
カズオ・イシグロ,土屋政雄
ハヤカワepi文庫
誰のために人生を生きている?
宗教的な意味でもなく、何の比喩でもない、文字通り”自分の人生が自分のものではなく、他人のためのもの”だったら自分はどうするだろうか。 子どもは親を選べないというが、この物語においては親どころかその後の人生すら自ら選ぶことができない。イギリスの海沿いの街、ヘールシャムという施設で生まれ育ったキャシーと親友だったルースとトミー。”提供者”と呼ばれる彼女たちは、いまいる”自分”を感じ合いながら、沸き上がる”自分”の感情で予め決められた運命に抗い始めます。 普通に日常を過ごす私たちにとって、異常で壮絶で恐怖ですらあるその事実が、カズオ・イシグロの静かで穏やかな言葉の運びによってゆっくりと語られる。どうでもいいような些細な事が彼女たちの心を揺さぶり、生きるとは何を意味するのかを底の底からすくい取って読者の前に差し出すのです。 長い、オチが読めると言った批判もあるようですが、丁寧にディテールを積み重ねることが、”ひとりの人間”を描くためには必要なのではないでしょうか。
10投稿日: 2013.09.20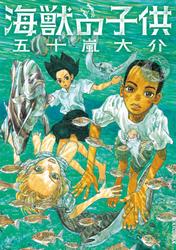
海獣の子供(1)
五十嵐大介
月刊IKKI
描かれた海の世界へ飛び込むように読む
このマンガは、ある女性(未来のあの子)がその女性をおばあちゃんと呼ぶ少年に、自分が生きて体験した”海の物語り”を語る、こんな言葉から始まる。 「海のはなしをしよう。まだ誰も知らない海の物語りを。深海に潜む巨大なサメの事。海を旅する幽霊たちの事。そして、海と宇宙を繋ぐ道の事」。 五十嵐大介の驚くべき自然の描写力にかかると、自然はまるで宇宙のようで、深い奥のほうから光が射す海や森に、思わず吸い込まれていってしまう。その自然=宇宙の物語は、自分をうまく表現できない少女と、ジュゴンと共に生きていた少年二人を通じて、海と人間をめぐる人類史にまで、その射程は伸びていく。 人はどこから来て、現在は未来へ向かうどの地点なのか。そうした大きなテーマも、結局は家族のことや男女のこと、かつての過ちのような、それぞれの人が抱えるパーソナルなことから始まる。 美大出身で、一時農家としても働いた異色のマンガ家の作品は、読むのと同時に体験するものでもある。その世界にダイブして、浸りながらゆっくり時間をかけて読んでみてほしい。
3投稿日: 2013.09.20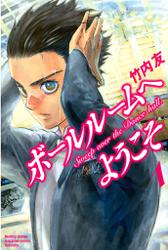
ボールルームへようこそ(1)
竹内友
月刊少年マガジン
これがデビュー作?! 恐るべき才能…。
このマンガを読んで、これが連載デビュー作のマンガ家とはにわかには信じがたい。 リズムやメロディに合わせた回転や上下動、体と表現を大きく見せる振り、男女ペアの複雑な関係性といった、ベテランでさえ描くのが難しい社交ダンスの世界を見事な作品に仕上げている。荒削りな部分がないわけではないけれど、ダンス初心者の主人公多々良が突然ボールルーム(舞踏室)に投げ込まれ、必死にやりぬこうとする勢いに筆が引っ張られ、おもしろい画の表現として目に飛び込む。 いじめられっ子が社交ダンスに出会い、得られるものは何か。もちろん何かをやり遂げることで自信は身につくだろう。このマンガで描かれるのは自らのエゴによる達成感だけではなく、社交ダンスが持つ競技として、スポーツとしての対人間の関係であり、愛の交歓であり、思いやりであり、個性とは何かという問いである。 悩んだら踏め、ステップを。
3投稿日: 2013.09.20
ぼくらのフンカ祭(1)
真造圭伍
ビッグスピリッツ
10代の苛立ちは、どうしようもないけど、どうにも楽しいもんだったりする。
何も変わらない毎日に何かを変えたいという苛立ち、そしてやっぱり誰かがいつの間にか変えてくれないかなという怠惰。10代の悩みの多くはこんなことだったりする。 いつもの日常に、ちょっと不思議な状況とギャグを加えて、楽しい一大事を描く真造圭伍。文化庁メディア芸術祭マンガ部門での新人賞受賞や、雑誌「フリースタイル」の「THE BEST MANGA 2013 このマンガを読め!」での1位など、話題の『僕らのフンカ祭』は、青春と噴火と地元を巡る作品。 過疎の町を突如襲った噴火は変えたのは、観光地化による賑わいと学校閉鎖に反対する文化祭だった。クールというより冷めた富山とノリノリでモテたがりの少々バカな桜島の高校生コンビは、変えたいと思うことは変えられず、不可抗力で変わる環境にどうにかアジャストして、自分の人生の楽しみ方を見つけていく。 どうしようもなく関わらなくてはいけない自分の人生も、なかなか捨てたもんじゃないと昔の自分に言いたくなる。
0投稿日: 2013.09.20
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
