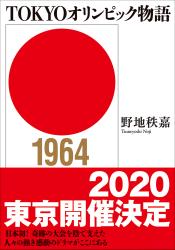
TOKYOオリンピック物語
野地秩嘉
小学館
【必要は発明の母】東京オリンピックが生んだもの
オリンピックの主役はもちろん出場する選手たちだけれど、大会を適切に開催、運営することができなければ、選手たちは戦うことさえできない。 オリンピックに初めてシンボルマークを導入したグラフィックデザイナー亀倉雄策と日本のデザイン界を作り上げデザイナーたち、世界で初めてリアルタイムで競技結果を速報した日本IBM、各国から選手村に訪れる1万人分の料理を取り仕切った帝国ホテル料理長の村上信夫、芸術か記録かという論争まで巻き起こしたオリンピック記録映画の監督市川崑、警備会社のさきがけとなった日本警備保障(現セコム)などなど、東京オリンピックを裏で支えた様々な人々の知られざるエピソードが語られる。 誰も経験したことのないオリンピック運営という大仕事。日本では、これをきっかけに新幹線、高速道路、ユニットバス、生野菜サラダなんてものまで誕生することとなった。本書内では負の遺産については言及がなく、まるでいいコトだらけだったように感じてしまうかもしれない。 今回のオリンピックに賛成か反対かはとりあえず伏せておくけれど、64年の東京オリンピックをきっかけに、今に繋がるたくさんのモノゴトが生まれたのはひとつの大きな事実なのだ。
1投稿日: 2013.11.22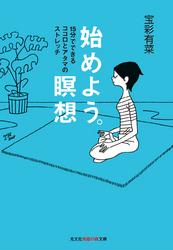
始めよう。瞑想~15分でできるココロとアタマのストレッチ~
宝彩有菜
知恵の森文庫
頭が空っぽになることの安心感と幸福感
瞑想は、禅やヨガなどとも関係の深い、古来から続く心を整える方法のひとつ。とはいえ、どうもスピリチュアルな匂いを感じ取って、苦手に思うひともいるかもしれない。極端な生き方をしている人や洗脳された人だけのものだと考える人もいるかもしれない。 著者の宝彩は、そうした批判を理解したうえで瞑想を科学として捉え、その方法論と効果を解説している。瞑想の一番のポイントは“何も考えないこと”。いわゆる“空”や“無”の状態になること。そのためにマントラというあまり意味のない言葉の連なりを頭の中で唱え、あえて雑念を呼び出して次々とそれを棚上げして次の雑念へと移行していく。そうして浮かんでくる雑念を棚上げしきった状態が“空”の状態。 瞑想がもたらしてくれるのは心の平穏ばかりではないようだ。羨ましいこと、不快なこと、嬉しいことに対して無意識に浮かぶ考えや感情を見過ごさず、つぶさに観察する“観照”という技術。あたかも、もうひとりの自分が自分を冷静に見つめるような視点を獲得するその技術は、行き詰まった頭に新しい考えをもたらしてくれるという。 瞑想は超越的な何かを信じるということではない。自分の思考の流れを意識し、空っぽにするとても真っ当な心を整える“技術”なのだ。
1投稿日: 2013.11.15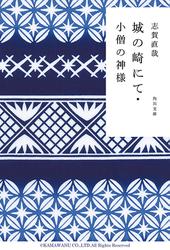
城の崎にて・小僧の神様
志賀直哉
角川文庫
100年読まれる作品
志賀直哉が山手線の電車に轢かれ、その療養のため城崎を訪れて今年(2013年)で100年になる。 自身をモデルに、電車に轢かれた怪我の療養のために訪れた城崎で、志賀はねずみ、蜂、いもりというちいさな生きものたちが命を落とす様を見つけ、自らの怪我とたまたま救われた命を思う。 作家自身、普段なら気にもとめなかったであろう自然と人間の間にある命の差異。自分の存在の際を見つめ、世界の輪郭を意識した小説家の目は、じつに繊細な視力とことばを得ている。 “小説の神様”とまで言われた志賀の中でも、文庫にしてわずか十数ページの「城の崎にて」は、傑作として読み継まれてきた。「城の崎にて」を含め、志賀直哉の作品がここから100年、改めて読み継がれていくといいなと思う。
5投稿日: 2013.11.12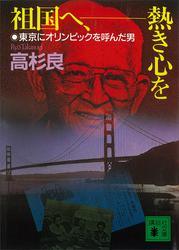
祖国へ、熱き心を 東京にオリンピックを呼んだ男
高杉良
講談社文庫
知られざる東京オリンピック(1964)開催の立役者
日系二世の実業家フレッド・イサム・ワダ(和田勇)。 和田は、出稼ぎ漁夫としてバンクーバーに渡った両親のもと、1907年にワシントンで生まれる。17歳で農作物の小売チェーン店に勤務し、二年後にオークランドで独立。日系人コミュニティの中心となって活動するも、太平洋戦争が勃発すると一部地域で日系人の強制収容が行われることになる。それに抗うようにユタ州へと移り、大規模農園を仲間と経営。 そして戦後、ロサンゼルスへ戻ると日本スポーツ界との交流が始まる。1949年、全米水泳選手権に出場する古橋廣之進ら日本代表チームの滞在先として自宅を無償で提供。食事や滞在中の一切の世話を行い、“フジヤマのトビウオ”古橋らが世界記録で優勝するなど、和田の支えのもと日本は戦後からのいち早い復興と存在を印象付けることとなった。 そこから和田は、日本からの様々な依頼に応える形で活動。58年、東京オリンピックを実現しようと動いていた東京都知事東龍太郎(60年からIOC委員)や日本水泳連盟の田畑政治らに頼まれ、日本への愛とオリンピックへの熱意、そして交渉力と日系人社会のコネクションを活かし、南米9ヶ国のIOC委員へ賛同依頼の行脚を行ったのだ。 結果として、その得票がポイントとなり、東京開催が決定。和田は知られざるヒーローとなる。 アメリカに生まれ、その土地に溶け込んで生きていきながら、一方で強烈に日本を愛し、私財を投げ打ってでも東京オリンピック実現しようと奔走した男。バカがつくほど正直でいい人である和田勇という人物を、日本人は忘れてはいけない。
1投稿日: 2013.11.05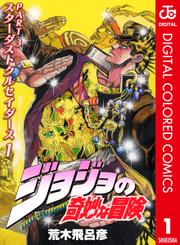
ジョジョの奇妙な冒険 第3部 スターダストクルセイダース カラー版 1
荒木飛呂彦
週刊少年ジャンプ
壮大な物語とトリッキーな登場人物たちを愛さずにはいられない
もはや何を言うまでもないのかもしれないが、やはりこのマンガは最高だ。 特にスタンドという能力が登場し始めた第三部から、俄然キャラクターの個性は際立ってくる。ドラゴンボールを筆頭に、週刊少年ジャンプマンガ特有の“戦闘力のインフレ”から解放された、ワンピースにみられる特殊能力バトルの原型はここにあるといえる。 能力として何が最強か。三部以降出てくる、ジョジョ愛好家たちにとって最高の話題であるこの問題。時間を止めるディオか、スタープラチナかマン・イン・ザ・ミラーかパープル・ヘイズか。 三部のタロットからのスタンド名ネーミング、四部、五部のミュージシャンからの引用、映画や絵画へのオマージュなど、ただストーリーを追うだけでも、絵を堪能するだけでもない、奥深き設定と歴史の厚みを堪能することのできる大きく長い物語。 ちなみに第3部で一番好きなキャラとスタンドは、イギーと「ザ・フール」。
4投稿日: 2013.11.05
藻谷浩介さん、経済成長がなければ僕たちは幸せになれないのでしょうか?
藻谷浩介,山崎亮
学芸出版社
もっとスピード落とした暮らししませんか?
コミュニティデザイナーとして、過疎や不況などの問題を抱える地方都市のコミュニティ創設、再生を手がける山崎亮と日本総合研究所調査部主席研究員で日本全国に自ら足を運ぶ地域エコノミストでもある藻谷浩介。 ふたりが鹿児島マルヤガーデンズや青ヶ島など地方の実例を取り上げながら、日本人が幸せになるために、経済成長は本当に必要かを問い直す対談本。 東日本大震災を経て、多くの日本人は人生において何が必要かを見直すきっかけになったと言われている。一瞬で生活のすべてが無に帰したとき、人が必要としたのは経済の成長ではなく、より根源的な生きている実感だった。 経済成長という平均化された数字で示されるものは、関係がないとはいえないが、個別の幸せを測ることはできない。改めて自分たちが自分たちで決める幸せについて、わたしたちの未来について考えてみたくなる。
3投稿日: 2013.11.04
宇宙は何でできているのか 素粒子物理学で解く宇宙の謎
村山斉
幻冬舎新書
何もないところから、何かが生まれるメカニズム
ビッグバンが起こり、宇宙が誕生。微生物が生まれ、恐竜の時代を経て、類人猿、そして人類へという進化の過程はいろいろなところで聞いてきた。けれど、そもそもビッグバンが起きて我々のもととなる“物質”ができるというのはどういうことなのか、についてはどうもよくわからなかった。 村山先生がこの本で教えてくれた素粒子物理学を読むと、どうやらその秘密は、素粒子=ニュートリノとヒッグス粒子にあるらしい。物質が生まれた時、同じ量の反物質が生まれたと考えられており、物質は反物質が出会うと1対1で消滅してしまう。同じ量のふたつがあるのだとしたら、宇宙の全ては無になっているはず。でも実際は物質が存在している。物質が存在するためにわずかにバランスを崩す役割を担っているのがニュートリノなのだそうだ。わずか数%のズレで生まれる物質は、宇宙に充満するヒッグス粒子によって原子になり、質量を持ち始めたという。 2013年、“欧州原子核研究機構(CERN)によって存在が確認された素粒子(ヒッグス粒子)に基づく、質量の起源を説明するメカニズムの理論的発見”によって、ヒッグス粒子の名前の元でもあるピーター・ヒッグスがノーベル物理学賞を受賞。 まだまだ宇宙のほとんどを占めるとされている暗黒物質はほぼ内も解明されていない状態ではあるけれど、真空状態で、無であるとされた宇宙に、我々が存在するきっかけは徐々にわかりつつある。
3投稿日: 2013.10.31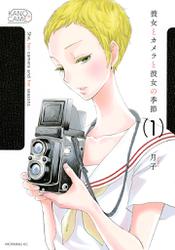
彼女とカメラと彼女の季節(1)
月子
モーニング・ツー
強いあの子に憧れて、わたしは女の子を好きになる。
進級し、新しい友だちたちともうまくつきあい、馴染んできたように見えながら、実際は個性を消して空気を合わせなければ、仲良く過ごせない。 それを友情と言うのかわからないけれど、すべてがハッピーな高校時代を送った人以外(故にたぶん多く人)は、少なからずこの主人公あかりのような気持ちを味わっているのではないでしょうか。 そんなあかりが、誰とも交わらない孤高の美少女ユキに憧れるのは当然のことでした。周囲に合わせて自分を消すのではなく、スッと背筋を伸ばしてひとり立っている。ときに写真は眼で見る以上に、真実を写してくれます。ユキがあかりをレンズ越しに見る時、あかりがユキをレンズで捉える時。そこには新しいそれぞれの女性がいます。 思春期の異性恋愛と女性同士の恋愛をモチーフに苦悩し、挑発し、直視する。これは恋か愛か友情か親愛か。
4投稿日: 2013.10.22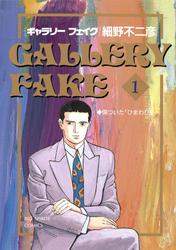
ギャラリーフェイク(1)
細野不二彦
ビッグスピリッツ
贋物だって、本物よりいいこともある、かもしれない。でも、本物がいい?
芸術/アートは、誰のためのものであり、何のためにあるのか。 描き手、創り手の思いがあり、そして鑑賞者、所有者の思いがある。それは美しく、理想的な関係性の時もあれば、製作者の意にそぐわない残念な場合もある。時にお金のためであり、時に生きることと同義であることもある。 ブラックマーケットに通じる、贋作専門のギャラリー「ギャラリーフェイク」のオーナーで、NYメトロポリタン美術館の元学芸員兼修復家でもあった藤田玲司。藤田は、アート作品とその所有者をめぐって巻き起こる様々な事件を、博覧強記の知識や技術、コネクション、時に強引な政治力や力技まで駆使して解決していく。どんな事件や問題に当たっても、その根本にあるのは藤田が芸術/アートを愛し、信じているということ。それは読んでいる私たちの安心感とも、共感と興奮とも繋がっていく。 そして著者の細野不二彦は『Gu-Guガンモ』の作者でもある。真面目で、硬くなってしまいがちなアートにまつわるストーリーに、笑いを織り込んで絶妙に力を抜く手腕は見事。 全32巻。もしかして後半はちょっと飽きてくるかもしれないけれど、自分の好きなアート作品が登場する回は俄然楽しい。
1投稿日: 2013.10.15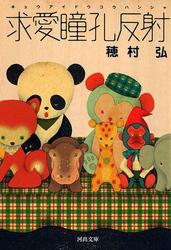
求愛瞳孔反射
穂村弘
河出文庫
ことばを組み合わせる楽しみはこの人に倣え
エッセイが人気の歌人、穂村弘による“詩集”。 人気のエッセイでもなければ、本業の短歌でもない。 詩である。これが最高の詩だった。 いつものように自意識は過剰だし、繊細だし、臆病だし、恋人たちはディスコミュニケーションだ。短歌のような定形表現の言葉ではなく、書こうと思えばいくらだって書けてしまう”可能性としての饒舌さ”を持ちつつ、実際は削ぎ落とされ、ゆったりと構える詩の言葉たち。よい詩、というか好きな詩は、そうした一見反対するようなことを矛盾と感じさせずにすんなりと腹の中に落ちてくる。 まず、ぜひ「シラタキ」を読んでみてほしい。言葉のリズムに乗せられて一気に読んでいると、何を言ってるんだ穂村弘はと思いながら、最後に噴き出している自分が待っている。
1投稿日: 2013.10.15
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
