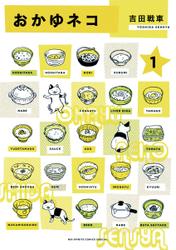
おかゆネコ(1)
吉田戦車
ビッグスピリッツ
吉田戦車が好きなものをくっつけたら…
菊川八郎は、両親が長期旅行に出て行ったがために飼猫“つぶ”を預かることになる。 つぶは、なんとしゃべり病にかかり人語を解するだけではなく、しゃべれる猫になっていた。 そして八郎宅にやってきたつぶは、朝食も食べずに会社に行く八郎を見かね、得意の料理おかゆを日々振る舞い始める。 動物がしゃべるのは、吉田戦車好きにはお馴染みのシチュエーションながら、 おもしろいのは途中からしゃべれるようになったということ。 相変わらずの不条理な設定と極端なキャラクターで最高なのだけれど、 猫が作るおかゆが実践的で、すこぶる美味しそうなのだ。 しかも、ところどころに差し込まれる猫に関する薀蓄やトリビアが、意外とタメになるという驚き。 作者が純粋に興味と愛情を持つ猫と食をくっつけた、食マンガというジャンルではくくれない不思議な空気感がある。 定番ジャンルの中の新ジャンルだけど、定番のおもしろさ。
4投稿日: 2014.04.28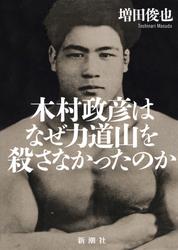
木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか
増田俊也
新潮社
腸が煮えくり返るほどの怒りのやり場はどこだったのか
“このミス”出身の小説家増田俊也が、ノンフィクション作品の書き手として素晴らしい仕事をしたのが、本書『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』。 日本の柔道史上最強と言われ、15年間不敗のまま柔道界を引退した怪物、木村政彦。練習中に膝を付かされることすら彼には耐え難く、深夜に包丁を持ち出して相手を刺しに行こうとしたという伝説が残るほどの怪傑だ。 その木村が、相撲出身の英雄力道山とのプロレス試合で、引き分けに終わる約束がだまし討ちにされ、敗北を期してしまう。それを契機に木村は表舞台から姿を消していったのだった。 最強とうたわれた男が、卑怯な手段で土を付けられた。「力道山に負けた男」と冠がついてしまった木村の心中はいかなるものだったのか。膨大な資料と取材で描き出した圧巻の1冊。
1投稿日: 2014.03.12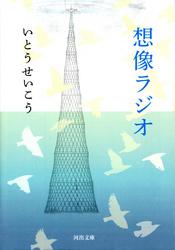
想像ラジオ
いとうせいこう
河出文庫
想像することは、人にやさしくなること
「ストーリー311」でも引用した、北野武の“この震災を「2万人が死んだ一つの事件」と考える”のではなく、“「1人が死んだ事件が2万件あった」ってこと”ということばは、この本にも当てはまる。 いとう自身が南三陸町を訪れ、聞いた「杉の木に引っかかって亡くなった人がいた」という話し。どうしようもなく頭に残ったそのイメージは、本書の主人公、海沿いの高い杉の木に引っかかったDJアークとして登場している。 アークは、亡くなった人々の声を憑代のように伝えていく。ただ自分だけが感じた紛れも無い事実、現実しか書いてはいけない、なんてことはないのだ。事実しか書けなければ、誰にも悼まれることなく忘れさられてしまう人も、こともある。 小説家というより、亡くなった人たちの声を集め、まとめた編集者のような気持ちでいるといとうは語ってもいる。先に引用した北野武も、大切なのは“想像力”だと言った。想像しなければ、誰かの悲しみも、喜びもわからない。想像力はやさしさでもあるのだ。
0投稿日: 2014.03.12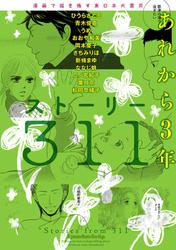
漫画で描き残す東日本大震災 ストーリー311 あれから3年
ひうらさとる,青木俊直,うめ,おおや和美,岡本慶子,さちみりほ,新條まゆ,ななじ眺,二ノ宮知子,葉月京,松田奈緒子
カドカワデジタルコミックス
震災の数は、人の数だけ存在します
甚大な被害とその後の生活を一変させた2011年3月11日の東日本大震災に対し、「漫画に出来ることは何なのか?」と考え、『ホタルノヒカリ』で知られるひうらさとるを中心に始められた「ストーリー311プロジェクト」。 1冊目は震災直後に出され、本書は3年後に出された続編。一度語って終わりではなく、関わった人々の経過もしっかりと共にすること、震災の記憶と被害と復興を風化させないこと。地に足のついた丁寧な活動に頭が下がる。 震災後、北野武が言ったように、“この震災を「2万人が死んだ一つの事件」と考える”のではなく、“「1人が死んだ事件が2万件あった」ってこと”だと考えてみること。 漫画家たちは、実際に現地に入り、現実の風景を凝視し、被災した人々の声を聞ききました。漠然と震災やその被害を語ることはしていません。取材したある個人とその周辺、そしてそれを取材した漫画家自身の声が登場し描かれるストーリーは、被災した人の数だけ無数にあるのです。 すべてはそれぞれの震災であり、日本全体が被災したひとつの震災でもあります。忘れないために、そしてあの日からの日々の変化と蓄積を見つめるためにも。
5投稿日: 2014.03.12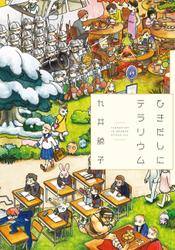
ひきだしにテラリウム
九井諒子
イースト・プレス
いったいどれだけの画風で描けるんだ、この人は。
基本的にSFであり、基本的に妄想であり、基本的にギャグ/ユーモアである。同じ人が描いているとは思えないほど、多彩な画風を使い分ける筆力には相変わらず舌を巻く。 多くは10ページにも満たないショートショートが33篇。星新一のような世界観にバカらしい日常を組み込む手法が、見事にハマっている。湿度低めな笑いの感覚は、とても今っぽいとも言えそうだ。
3投稿日: 2014.02.19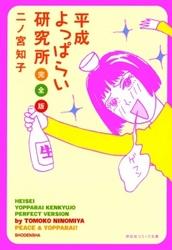
平成よっぱらい研究所 完全版
二ノ宮知子
FEEL YOUNG
お酒を飲むってこんなに楽しいことなんだ!(猛省も込めて)
『天才ファミリー・カンパニー』、『のだめカンタービレ』、そして最新連載『87CLOCKERS』と、ヒット作を出し続ける二ノ宮知子。 しかし彼女のもうひとつの顔である「よっぱらい研究所」所長の顔はまだまだ知られていない。もしかすると、イメージが壊したくないと言う人は読まなくてもよいかもしれない。それほどまでに二ノ宮知子の酔っ払いっぷりは見事。お酒にまつわる思い出がある人は、大笑いすること必至だろう。 よっぱらい研究所の所長である以上、仕事もそっちのけで彼女は飲み、騒ぎ、破壊し、酔いつぶれ、全員で倒れ、後悔し、また飲む。そんな生態観察のようなマンガ。 酒豪も下戸もこのマンガを読めば、酔っぱらいがいかに楽しくお酒を飲んでいるのかがわかるはず。これまで数々の天才を描いてきた二ノ宮知子自身も、酔っ払う才能は誰にも負けていない。
2投稿日: 2014.02.18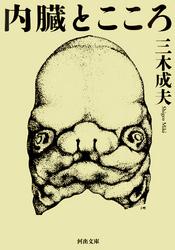
内臓とこころ
三木成夫
河出文庫
こころは内臓からやってくる
“こころ”は、どこにあるのでしょうか。よく人は心臓の上に手を当てながら、こころはここにあるという身振りをします。科学が好きな人は、脳の神経をつなぐ電気的な作用だと言うかも知れない。 解剖学者で発生学者、そして思想家でありタオイストでもあった三木成夫は、“「こころ」とは、内臓された宇宙のリズムである”と、保育園で保母さんやお母さんたちを相手にした講演で唱える。子どもの発育過程から、人間に「こころ」が形成されるまでを、ユーモアを交えた独特の語り口で熱く語る三木。 生命の数億年の歴史が、胎児の成長そのものに宿っている。人間は生まれるまでに人類に至るまでに経験してきた記憶を反復しているということか。三木は、解剖学的に人間の体は、感覚や運動に関わる動物系=体壁系器官と食と性を司る植物系=内蔵系器官のふたつに分けることができるという。そしてこころは内臓系器官から来ているというのだ。一方で頭は体壁系器官(神経と筋肉)に紐づくという。 自分では記憶できない胎児や赤ちゃんのときの世界を、知らない、わからないものとして退け、三木のような考えを疑似科学的、神秘主義的と見てしまっては、世界は小さなものとなってしまう。知らない世界のあり様を、可能性を三木はぐんと広げてくれている。
2投稿日: 2014.02.18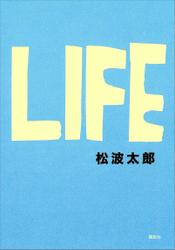
LIFE
松波太郎
講談社
“だらだら且ぶらぶら”な生活は、いつか終わってしまうのか。
まともに仕事もせず、日々“だらだら且ぶらぶら”過ごすことを日課としてきた主人公猫木。架空の王国を頭の中に作り上げ、自らが国王に就任し、長々とした演説のシーンからこの物語は始まる。 パートナーである宝田に妊娠を告げられ、子どもに王位を譲り、脱“だらだら且ぶらぶら”をしようと動き始めるのだが、現王様の猫木がそうそう急に変わられるわけもない。そして生まれてきた子どもには、ある先天的な障害があった。 子どもの障害を嘆き悲しむという小説ではない。むしろ全体を通してトーンはユーモアに貫かれている。生涯を持って生まれた子どもと向き合うために、猫木が取った作戦はユーモアを捨てずにいることだった。松波は、かわいそうという視点で生きることを語らない。ここから始まり、何十年と続くであろう命をしっかりと主人公の傍らに置いているのだ。
0投稿日: 2014.02.18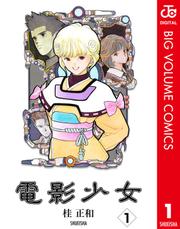
電影少女 1
桂正和
週刊少年ジャンプ
いまの30代の男子たちのハートをくすぐりまくった(人によっては)伝説のマンガ
このマンガ、そして桂正和に憧れの女性像を植え付けられた男性は、いったいどれだけいるのだろう。当時小中学生だった人にとって、それほどまでに桂正和の描く女性の体のラインは、まだ見ぬ果ての夢であり、読んでいるところを親に見つかってはいけないという背徳心の塊だった。 下の世代になれば、その後の『D・N・A²』や『I’S』で同じような感想を持つ人も多いかもしれない。恋に恋する世代の男たち、自分の思いを伝えられない不器用な男たちにとって、再生したビデオ(VHS)の中から出てきた女の子(ビデオガール)は、夢にまでみたものだった。後に『リング』の貞子出現までは、ビデオから飛び出す女性は、完璧な美少女だけなはずだったのだ。 そう簡単に恋が成就しないのは、当然なのだけれど、焦らし方ひとつとっても、内容よりもニヤニヤしながら読んでいたなという思い出の方が強く残る傑作マンガ。もう1度読みなおす、もしくは初めて読んでみる価値は十分にある。
1投稿日: 2014.01.31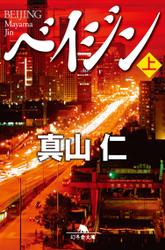
ベイジン(上)
真山仁
幻冬舎文庫
中国人の生理をこれほど的確に描いた小説はないかもしれない
本書のモチーフとなっているのは北京オリンピックと原発。なんといまの日本と似通った話題なのだろうか。この本は、たびたび話題となってきた。まずは発売当時、次は福島第一原発の事故、そして東京オリンピックの決定の時。そして2020年、原発問題にどんな進展が見えているのかわからないけれど、またこの本を肴に話しが再燃しているかもしれない。 北京オリンピックの開会式で中国が誇る技術と威信をかけた原発稼働を生中継するという、国威発揚や世界への先進国アピールの意味を含んだ、政治パフォーマンスは、かつてのヒトラー時代のドイツを思い起こさせる。 理解できないとよく言われる中国人の生理や考え方を、当の中国人が褒めるほどにしっかりと描いた小説は少ないのではないか。裏切りと信頼、偏見、粛清、そうしたネガティブな言葉の先にあるのは、著者が最後に残した希望だった。パンドラの箱に残された希望は、どんなかたちで示されるのだろうか。
5投稿日: 2014.01.31
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
