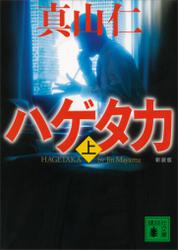
新装版 ハゲタカ(上)
真山仁
講談社文庫
お金を信じていますか? お金は何を叶えてくれますか?
2004年の発売後、ハゲタカファンドという言葉を一般化させ、企業買収の内幕を小説のかたちをもって暴露した作品。 “ハゲタカ”鷲津政彦は、ピアニストになるべく渡ったNYで凄腕ファンド・マネージャーへ転身。外資ホライズン・キャピタルの代表取締役として97年に日本へ帰国します。日本的な企業のあり方を理解した上で、鷲津はダメそうな第一印象を与える装いをし、虎視眈々とそして機を見て突如牙を向くのです。 バブル崩壊後、地に足がつかない日本の政治、金融、企業はどう動いたのか。実在の企業や銀行をモデルにし、企業買収という当事者以外に全貌がつかめないお金と経済の動きが、手に汗握る心理戦、信頼と裏切りの物語として展開されます。 ある出来事がきっかけで日本という国を憎み、日本をバイアウトすると豪語する鷲津のこころは、読む人の想像を超えて射程は伸びています。人の欲望と没落の恐怖、金が結ぶ同盟関係と壊れる人間関係。誰のためのお金、何のためのお金という人生の本質を見極める経済小説。
6投稿日: 2014.01.22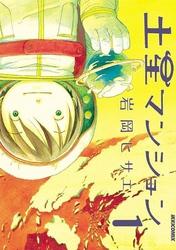
土星マンション(1)
岩岡ヒサエ
月刊IKKI
人間が人間らしく生きることの困難と宇宙
地球が自然保護区域となり、人が宇宙で暮らすようになった時代。35,000メートル上空に浮かぶコロニーのような巨大なリング状のマンションで暮らしています。地球の周囲をめぐる上層・中層・下層からなるその巨大なリングシステムは、暮らす階層がその人の富と地位を否が応でも決めてしまいます。 下層の住人である主人公・ミツは、中学卒業と同時に、仕事中の事故で亡くなった父と同じ職種「コロニーの窓拭き」を始めます。被曝に近い紫外線、気温−40℃、薄い大気と気圧という労働条件で働く窓ふきの仕事は、命の保障と防護作業服のメンテナンスのためにかなりの金額がかかってしまう。そのため結局自然光を目にできるのは、上層に住む高額所得者に限られてしまうのです。 所得も少なく、地位も低い下層の人々は、太陽を十分に浴びることさえもできません。命をかけて窓を拭くこと、仕事の仲間との交流、父親のことを話す周りの人々。ミツは知らなかったことをひとつひとつ知って、新しい世界と自分を見つけるのです。
0投稿日: 2014.01.22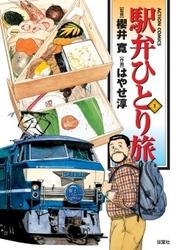
駅弁ひとり旅 1巻
櫻井寛,はやせ淳
漫画アクション
ひとりと言いつつ、ひとりじゃない
鉄道と駅弁が大好きで駅弁屋をやっている中原大介が、日本一周鉄道旅行へ。停まる駅停まる駅で駅弁を買い、乗り合わせた人に出会い、旅を共にし、鉄道の蘊蓄と駅弁の魅力を語ります。 九州から始まり、四国、中国、近畿、飛んで北海道、東北、北関東、北陸、東海、南関東の順に旅を続け、日本一周達成後には東日本大震災の被災地へ。 旅の途中で出会う若い女性や青年、外人さんと旅の景色を楽しみ、歴史を学び、食べる喜びを分かち合います。駅弁マンガという性質上当然ですが、とにかくよく駅弁を食べます。二巻の四国・中国編に出てくる、極上の金穴子を秘伝のタレで焼いた「あなごめし」や肉厚のかつおに舌鼓を打つ「かつおたたき弁当」。 食べる姿がたまらなくおいしそうで、よだれが出てしかたがありません。しかし、1万円以上の駅弁がいくつもあるなんて、まだまだ奥が深い…。
0投稿日: 2014.01.15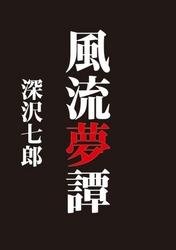
風流夢譚
深沢七郎
志木電子書籍
不敬とされ事件にまで発展した幻の作品が、50年を経てついに読めるようになる。
『楢山節考』などの土着的な村社会のあり様や周縁に生きる人々を描いた小説家深沢七郎。 深沢が、60年雑誌「中央公論」に発表した「風流夢譚」は、皇太子と皇太子妃がマサカリによって一般民衆に斬首されるという過激な描写が書かれていた。 夢譚、つまり夢の話として書かれた話しとはいえ、その描写は不敬であるとされ、抗議活動が勃発。発行元であった中央公論社社長、嶋中鵬二宅に右翼団体に所属していた少年が押しかけ、本人不在のなか夫人に重傷を負わせてしまう。 その後、深沢は危険を避けるため、放浪生活を余儀なくされる。以下、ウィキペディアで恐縮だが、事件後この作品はこんな展開となった。 “この事件の影響で身を隠していた深沢七郎は記者会見をし、「下品なコトバ」を小説に使い、「悪かったと思います」と述べ、護衛の刑事と供に姿を消した。深沢は1965年まで放浪生活を余儀なくされた。深沢自身は嶋中事件で犠牲者が出たことを悔やみ、様々な方面からの復刊依頼に対しても「未来永劫封印するつもりだ」として応じなかった。事件から26年後の1987年に深沢は死去したが、1997年刊行の『深沢七郎集』(全10巻)にも「風流夢譚」は収録されていない。” この電子書籍版「風流夢譚」は、50年を経て正式な形で出版された「風流夢譚」である。
0投稿日: 2014.01.10
居酒屋の世界史
下田淳
講談社現代新書
居酒屋でヨーロッパ文明史が学べるってどういうこと?
居酒屋の始まりは、ドイツ農民戦争や、フランス革命だそう。 古来ヨーロッパでは居酒屋は売春宿であり、銀行や裁判所でもあり、 貨幣経済の発展とともに、居酒屋は育ってきたといえる。 ビールは紀元前3000年頃にはすでにエジプトで国民的な飲み物で、 嗜好品ではなく健康を保つための栄養源だった。 居酒屋の誕生期には「ワインは薄めて飲むのがマナーだった」という話しや 「芸人と居酒屋」という目次が目を引く。 人が集まるところには、歴史の結節点が多く存在する。 馬鹿騒ぎするだけの場所ではない、ヨーロッパ文明を覗き見る窓としての居酒屋。
3投稿日: 2013.12.17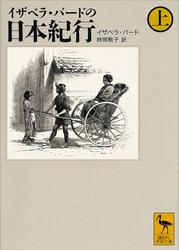
イザベラ・バードの日本紀行(上)
イザベラ・バード,時岡敬子
講談社学術文庫
いいことも悪いことも素直に、正直に
1878年に来日したイザベラ・バードは、当時男性ですらまだ少ない時代に、非常に珍しかった女性旅行家。 彼女は、欧米人未踏の内陸ルートによる東京‐函館間の旅を日本人のお供とふたりで敢行。外国人目線で見つめた日本の地方という、ともてユニークで貴重な地方史の資料になっている。 イザベラ・バードの感想は、いつも素直で正直。「日本人の黄色い皮膚、馬のような固い髪、弱弱しい瞼、細長い眼、尻下がりの眉毛、平べったい鼻、凹んだ胸、蒙古系の頬が出た顔形、ちっぽけな体格…」。一方で褒めるときは、山形県の置賜町地方を“エデンの園”とも形容する。 女性一人でも旅ができる、安全で安心の国は、そんな昔からあったんですね。
4投稿日: 2013.12.17
変身・断食芸人
カフカ,山下肇,山下萬里
岩波文庫
ありえない世界がありえる小説の世界が、好きになる。
初めて読んだ時の驚きが、今も消えていない。何の理由もなく、朝、目が覚めると虫になっているグレゴール・ザムザ。そんな異常事態に、周囲は驚きパニックになった家族は、ザムザを(物理的に)傷つけてしまう。 ザムザ自身、突然のことに驚きはするものの心配したのは、行かなければ行けない仕事の出張の事だったりするのだ。この物語では、ただひとりそうなったことに対して、原因を探ろうと誰かが躍起になることはない。その醜い見た目が、人々を不快にさせザムザを追い詰めていく。 人間が陥る孤独の状況を描いた“現代の寓話”と呼ばれるこの作品。圧倒的に不条理な設定にも関わらず、気づけば物語世界に読者を引きこまれている。それは純粋に驚きでもあり、読書の何よりの楽しみでもある。
0投稿日: 2013.12.10
永遠の詩02 茨木のり子
茨木のり子,高橋順子
小学館
「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」
2006年に79歳で亡くなった詩人茨木のり子。戦後詩を牽引した女性の頭から、手から、口から紡がれる言葉に、思わず背筋が伸びていく。 教科書にも収録され、最も知られている「わたしが一番きれいだったとき」や「倚りかからず」、「自分の感受性くらい」など、茨木のり子の代表作約40編を収録。 言葉遊びの言葉ではなく、自分が酔いしれるための言葉でもない。茨木は、自分を律し、自らの生き様を言葉でもって人に示してきた。 「自分の感受性くらい 自分で守れ ばかものよ」。なくしたものを恨んで終わらず、そこに自分はいたのかと問う茨木の鋭い視線。何気なく読んで、いつもハッとさせられる。
1投稿日: 2013.12.09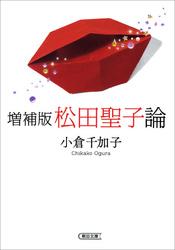
増補版 松田聖子論
小倉千加子
朝日文庫
欲望の対象としてのアイドルは、時代を読み解く鍵になる
88年の最初の著作『セックス神話解体新書』が話題のデビュー作となった心理学者でフェミニストの小倉千加子。 その小倉の二冊目の著作が、当時アイドルの象徴であった松田聖子について論じた本書。昭和最後の10年(バブル絶頂の10年)を、松田聖子という当時の女性像を牽引した女性をキーに読み解いたこの本は、あとがきで著者も言うように“フェミニズムの本なので”あり、“フェミニズムのパロディ本”でもある。 前半の半分で、“性器の備わった清純”として現れ、自立した女の様相を見せつつも結局は“日本の娘”に帰着した山口百恵を詳らかにし、そこからのカウンターとしての松田聖子を語り始める。キツネ顔の貴族的な山口百恵から、タヌキ顔で健康的な松田聖子へ。 土着的な日本の男女のあり方から、アイドルというシステムの中で役割を演じ、飛び立った松田聖子。娘を産み、離婚、結婚を繰り返してもなお彼女はアイドルであり続けている。 アイドルとは“実社会の無意識が投影されるスクリーンである芸能界という特殊な空間の中で、きわめて短い時間にモデルとしての人生を完成させる恍惚と不安を手に入れた女の子のこと”。 松田聖子の殆どの曲の作詞を手がけた松本隆論としても優れた批評になっている。
1投稿日: 2013.11.29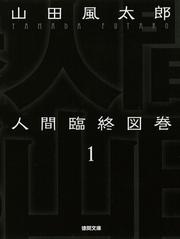
人間臨終図巻 1
山田風太郎
徳間文庫
1年に1回死ぬまで開き続ける本
忍法帖シリーズや奇想天外なアイディアを盛り込みまくった時代・歴史小説で、一般にはもちろんカルト的な人気も平行して得ていた山田風太郎(1922〜2001)。 小説内でも人を切りまくり、殺しまくった山田が、1巻の10代、20代を始め、30歳からは1歳刻みで4巻の100代まで、亡くなった人の年齢ごと、著名人(英雄、武将、政治家、作家、芸術家、芸能人など)、総勢923人の死に様を書き記した傑作。 赤穂浪士のひとり、大石内蔵助の息子大石主税が切腹したのは15歳。「主税、内蔵助に会いとうはないか」と聞かれた主税は、首をかしげて涼しくほほえんで、「お言葉で思い出しました」と答えたそう。それぞれの死の事情と、それぞれの死への思いや覚悟、そして恐れ。自分と同じ年齢で亡くなった人は、どんな死を迎えたのか。 長いか短いかではない、いかに生きるかの意味を考えてしまう。歳を重ねるごと、毎年読みたくなる。
3投稿日: 2013.11.29
BACH/バッハさんのレビュー
いいね!された数446
