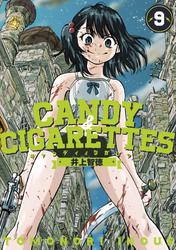
CANDY & CIGARETTES(9)
井上智徳
ヤングマガジン サード
ショーとしての戦争
今 戦われているロシアウクライナの戦争もそうだけれど、これだけインターネット SNS マスコミが発達した世界では、「ショーとしての戦争」という要素が多いにある。ストーリー展開にその要素を指摘した作者に感銘を受けた。
0投稿日: 2022.04.21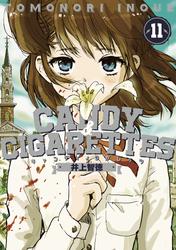
CANDY & CIGARETTES(11)
井上智徳
ヤングマガジン サード
JC美晴がいい。
ストーリーはアメリカ大統領選挙まで巻き込んだ大規模なものになって大団円を迎え得る。いくら漫画とは言え、この二人ちょっと強すぎるかな。最終カットのJC美晴が今後の安らかな日々を象徴しているようでとてもいい。
0投稿日: 2022.04.21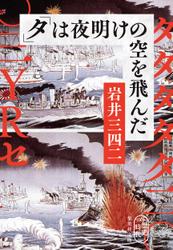
「タ」は夜明けの空を飛んだ
岩井三四二
集英社文庫
作者の新機軸
日露戦争に備えた無線機の開発話である。 岩井三四二の久しぶりの新作は従来の作風とは全く異なる作品であった。日露戦争を舞台とした作品で、語り口も従来作品とは異なってルポルタージュ 伝記風になっている。創作物ではない近代の実在の人物だけに人物描写がやや平板になっているのはやむを得ないかな。吉村昭の未発表の作品と言われたら信じてしまいそう。それよりも、いろいろなことを考えさせられた作品である。 「力こそ正義」と、日露戦争のときも、ロシアがウクライナに攻め込んでいる今も、国家 国民の運命を決める重要な要素の一つが「科学技術」であることは疑う余地がない。 日露戦争のときは、本書が描き出しているように新技術の開発 運用に成功したが、技術力の低下が言われている現代日本は、うまく切り抜けることができるのだろうか? 本書の中には、マルコーニは無線だから当然だが、ニコラ・テスラとかジーメンスや島津製作所などが出てきて嬉しくなった。 日露戦争はすでに現代戦の要素の萌芽を数多く持っていた。無線や火薬などの科学技術の面もそうだが、国外への報道.プロパガンダによる戦費調達、情報戦、諜報戦。そして何よりもそれらを使いこなす懸命の努力。
0投稿日: 2022.04.18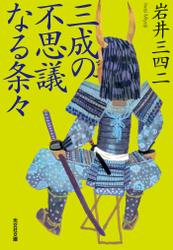
三成の不思議なる条々
岩井三四二
光文社文庫
多方面からの三成解析
石田三成のように評価が一定しない人物を、本人自身ではなく、多くの関係者の口を借りて活写してゆく という手法を取っている。手法そのものは珍しくはないが、縁の遠い東軍の将兵から、西軍、家中、身内と話者をどんどん身近にしてゆくなど、ずいぶん構成を工夫している。話しぶりも、お国言葉を存分に交え変化をつけているところが面白い。この作者 特有のユーモアや諧謔はそれほど感じられないが、話の組み立ての上手さは、この作者の作品の中でも第一番に挙げられるのではないかと思う。
0投稿日: 2022.04.17
飯野文彦劇場 山でやったとき
飯野文彦
e-NOVELS
凄まじく そして哀しいお話
凄まじく そして哀しいお話であった。最初は単なる誘拐モノ犯罪モノかと思っていたが、読み進めてゆくに連れてどんどん話が奇怪にグロテスクに変わっていった。幻想味というと言うよりは、ホラー味のほうが勝っている作品である。
0投稿日: 2022.04.13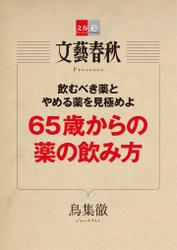
65歳からの薬の飲み方【文春e-Books】
鳥集 徹
文春e-Books
基本は食事と運動
高齢者がなりやすい生活習慣病に対して処方される薬について解説されている。人生のすべての判断に共通のことだが、効果とリスクの比較判断が重要 ということが強調されていて、納得させられる。残りの人生を楽しく快適に暮らすためには何が大事かを常に考えておかなくてはいけない。それにしても大事なのは食事と運動である。
0投稿日: 2022.03.31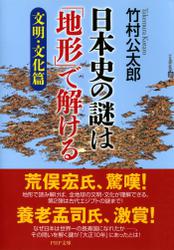
日本史の謎は「地形」で解ける【文明・文化篇】
竹村公太郎
PHP文庫
なるほど
前作「地形で読み解く日本史」の2冊め。読み始めは「前作よりは話が散漫かな」と思わせるような章もあったが、中盤以降どんどん面白くなってきた。特に東京の水道消毒への後藤新平の貢献の話には、感銘を受けた。日本史ではないが、最後のピラミッドの話も本当かどうかは別にしてとても面白い。
0投稿日: 2022.03.30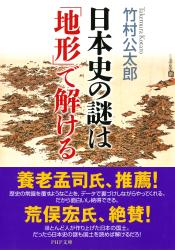
日本史の謎は「地形」で解ける
竹村公太郎
PHP文庫
下部構造から
マルクスの唯物史観から単語だけを借りてきたような「下部構造」が推論組み立ての柱になっている。下部構造=インフラ として「安全」「食糧」「エネルギー」そして「交流」を挙げ、それを根拠に話を進めている。どこまで本当かはわからないが、断定調にしかも思い入れたっぷりな語り口は、爽快感がある。とくに赤穂浪士の話は大変に面白い。とは言うものの、第12章の征夷大将軍の論説は牽強付会のきらいが強い。
0投稿日: 2022.03.27
かけおちる
青山文平
文春文庫
殖産興業
この作家の作品は3冊めであるが、どの作品も少し明るめの藤沢周平を思い起こさせるような読み心地の本である。主題は夫婦間の心情の機微とそのすれ違い なのだが、悲劇的な娘婿の話は全体の中でちょっと収まりが悪い。私はむしろ鮭の養殖や養蚕のような「殖産興業」の話の方に興味を惹かれた。江戸時代の殖産興業を取り上げた本を読んでみたい気にさせられた。
0投稿日: 2022.03.20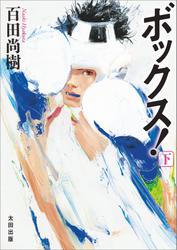
ボックス! 下
百田尚樹
太田出版
迫力いっぱい
ボクシングを題材とした小説には迫力あるものが多いが、この作品の迫力もなかなかのものである。特に高校ボクシングを題材としただけあって、アマチュアボクシング特有の規則の解説がとても興味深い。単なる学生スポーツと言えない怖さがよく分かる。ストーリーとしてはややお約束どおり という展開が多いが、逆にその分 引っかかりがなくどんどん読みすすめることができ、迫力が増してくる。
0投稿日: 2022.03.19
じゃがいもさんのレビュー
いいね!された数12
