
天使は結果オーライ
野尻抱介
ハヤカワ文庫JA
3人目が、これまた魅力的です
ロケットガールシリーズのリフレッシュ第2段^H弾、今回も宇宙なめんなのハラハラドキドキが楽しくって仕方なかった。つい先日3弾目も印刷書籍で出ているので、続きがめっちゃ楽しみです。
3投稿日: 2014.05.06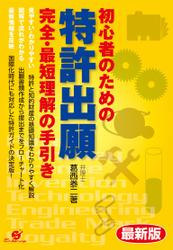
最新版 初心者のための 特許出願 完全・最短理解の手引き
葛西泰二
すばる舎
タブレット向きです
初心者や、実務者の全体的な復習に向いた本です。 字の細かい図版が多く、コミックと同様にタブレット向き。
2投稿日: 2014.04.30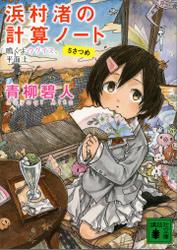
浜村渚の計算ノート 5さつめ 鳴くよウグイス、平面上
青柳碧人
講談社文庫
新ネタ連発で楽しかった
ちゃんと新しいネタを立て続けに振ってきて、かつ綺麗に消化してくれた感じでスッキリしました。 ただ、残念なことに解説が掲載されていないので減点1。今回は、あの結城浩さんなのに(泣)
1投稿日: 2014.04.22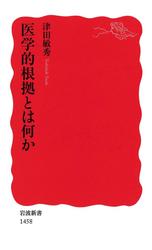
医学的根拠とは何か
津田敏秀
岩波新書
実にもどかしいガラパゴスな医学界
公害や薬害などに対し常に後手に回る日本の医学界や厚労省の体質は、明治期にロジカルなドイツ医学を直輸入して純粋培養した結果のようだ。 日本で分析的な基礎医学がどんどん深掘りされていった20世紀に、欧米では疫学が急速に発展し、いまやビッグデータ時代に入ってきた。それを無視し続けてきたことが、原発事故に伴う各種疾患への対応遅れや高血圧薬の治験問題にまで連なっている。 この構図はパッケージで輸入し後生大事にする後進国・周辺国の典型的陥穽に落ちているように思える一方で、科学的管理は日本の工学では手慣れた(既に過去になりつつある)手法なので、なんとかなりそうな気もする。 でも、大学の中でも医学部と工学部や経営学部とは距離があるか…
1投稿日: 2014.03.28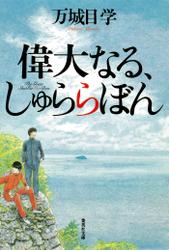
偉大なる、しゅららぼん
万城目学
集英社文庫
我が湖国のファンタジー
読後感がとっても爽やかなファンタジーでした。 琵琶湖検定のサブテキストみたいな「滋賀県あるある」の連発を少々引き気味に楽しんでいるうちに、お話に引き込まれていった感じ。中盤からの加速感が気持ちよかったです。 平和堂とイトーヨーカドーを取り違える人が多いかも知れないけど、その影響は軽微かな(^^;
1投稿日: 2014.03.20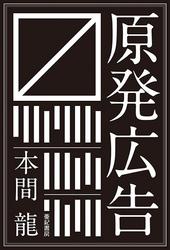
原発広告
本間龍
亜紀書房
無責任なポエム群、ここに極まれり
大手メディア関係者は異口同音に圧力など無かったと言うが、反対したことが無ければプレッシャーを受けたこともなく圧力を感じたことがある訳がない、と。そりゃそうだ。 数多くの広告の中でも東芝の「原子力の全てを担いたい」が印象的。これ、3.11の2週間前なのか… そして、これらの広告に多少のうさんくささを感じながらも受け入れてきた私たち自身が、実は3.11後も対象を変えただけになっているのではないか。反省しないと同じことがまた起こります。喜劇として…
1投稿日: 2014.03.08
著作権法がソーシャルメディアを殺す
城所岩生
PHP新書
クールジャパンって新しい話じゃ無い
欧米で著作権法がうまく機能しているところと日本のダメさとの対比が多く、著者が米国在住が長く弁護士でもあることからTTP絡みの警戒感も持ちつつ読み進んでいったところ、フェアユースの無い日本に非親告罪化を接ぎ木することの危険性が明確に示されて色々と納得した。 韓流ブームの背景に、10年以上前からのクールコリア戦略があったというのは全く知らなかった。その一定の成功を見ると、うさんくさいと思っていたクールジャパンも少しは応援しないといかんのかも。
1投稿日: 2014.02.28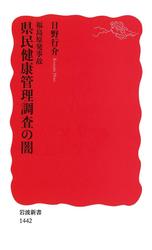
福島原発事故 県民健康管理調査の闇
日野行介
岩波新書
これぞ調査報道
KKK秘密会を知った当初は大した問題と感じなかったが、取材するうち一大事と気付き念を入れ慎重な調査をし始めるあたりの記述が興味深かった。 福島県(事務局)側は「リスクコミュニケーション」を、「リスクのあるコミュニケーションを避けてリスクが無いとアナウンスすること」だとでも思っていたようだ。 私自身、日野記者の秘密会第一報は「よくあること」と思ったのが正直なところ。続けて打ち続けられた記事から、その問題点を認識するようになったわけで、粘り強い調査報道に敬意を表したい。
1投稿日: 2014.02.07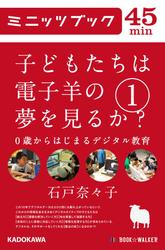
子どもたちは電子羊の夢を見るか?(1) 0歳からはじまるデジタル教育
石戸奈々子
カドカワ・ミニッツブック
リテラシーって、こういうこと
「デジタル教育」が「デジタルコンテンツ大量消費者養成教育」を脱するための仕掛けが様々に示されている。リテラシーを高めるという行為の具体的な事例が簡潔かつ分かりやすく書かれていて面白かった。
1投稿日: 2014.02.05
アメリカ・メディア・ウォーズ ジャーナリズムの現在地
大治朋子
講談社現代新書
本題はサブタイの「現在地」
マスコミがネット時代へ適応しようとするあり様や、NPO報道などの現状をアメリカからルポするのが狙いだったところ、日米そして中東のジャーナリズム立脚点の違いが浮き彫りになっていて面白かった。 米国では地方紙などで力を付けた記者が中央紙へとキャリアアップしていく中で、記者がジャーナリズムを極めていくという育ち方をしているようだ。対して日本は、中央紙が巨大で囲い込まれておりキャリアが単線的なのが根本問題に思える。 また、著者がヨルダン支局に異動されて直面したこととして後日談的に書かれている内容から、ネット時代にマスコミは要らないみたいな論調の危うさを示していて、良いデザートになっていた。
3投稿日: 2014.02.01
パドラッパさんのレビュー
いいね!された数200
