
盆の国
スケラッコ
トーチ
「THE BEST MANGA 2017 このマンガを読め!」1位!
夏のお盆になると帰ってくる「ご先祖さま=おしょらいさま」は、一部の限られた人にだけその姿が見える存在。主人口の女の子、秋もそのひとり。かつては秋のおばあちゃんも見えていたけれど、年をとって見えなくなってしまいました。間に挟まれたお母さんは元々見えません。 秋にとってお盆は、この時期にだけ会えるたくさんの幽霊? おばけ?との再開が楽しみなのです。夏休み真っ只中、友人関係にも悩んでいた秋は、このままずっとお盆だったらいいのにと思うのですが……。 その妄想のような願望が、なんと現実になってしまいます。何度でも繰り返す1日。終わらないお盆。浴衣姿の青年、夏夫と出会い、おしょらいさんが現れるこの季節の秘密を徐々に知っていくのです。人には歴史があり、霊はその歴史を体現した存在。終わらない=抜け出せない1日は、秋に大事な気づきときっかけを与えてくれたのかも。
1投稿日: 2017.04.21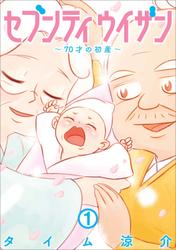
セブンティウイザン 1巻
タイム涼介
コミックバンチweb
高齢出産の増えた現代日本のパパママへの励ましになる漫画
日本では、35歳以上の女性が出産となると、高齢出産というふうに言われます。母子へのリスク/影響が高まることを意味しますが、日本での最高齢妊娠の記録は60歳。世界でも、2012年に66歳の女性が双子を産んだのが最高だそう。 そしてこの漫画。タイトルそのまま、70歳で初産を迎える老夫婦の物語です。絵はギャグ漫画のような造形であり、それは父となる65歳の男性が役割として担いますが、全体としてトーンは真剣。70歳の妻にとって、もうないと信じていた奇跡。しっかり丁寧に着地させてあげたいという作者と読者の気持ちが重なります。いつ何が起きてもおかしくないと、不安になりながら我々は読み続けます。 その不安は妻も夫も一緒です。妊娠を信じられず終始ボケ続ける夫の狼狽ぶり。妊娠の経過と共に、ふたりは来し方を見つめ直し、その絆を確認し合うのです。終始、穏やかでゆったりと進む中、妊娠は着実に進行していきます。 子どもを育てにくいと言われる昨今、新たな現実の可能性、夫婦や家族のあり方を考えるきっかけとしてもすばらしい良作です。
2投稿日: 2017.04.20
はたらく細胞(1)
清水茜
月刊少年シリウス
「このマンガがすごい! 2016 」オトコ編2位ランクイン!
マンガではこれまで様々な擬人化が行われ、キャラクターとして活躍をしてきました。ですが、本作で擬人化された細胞という例はこれまでなかったかもしれません。 およそ60兆あると言われる細胞を擬人化というだけでも気が遠くなりそうですが、赤血球と白血球のふたりを中心に、体内で日々外敵と戦い、人間の生命を維持し続けるおびただしい数の体内組織の活躍を描いていきます。 酸素などを運ぶ新米赤血球が、体内で目撃する様々な事件。このマンガで事件が起きるということは、すなわち人体に何か異物が侵入してくるということ。私たちが体験する病気や症状を見事に細胞とウィルスなどの戦いとして描き、細胞のすべての行動が、人間=読者が体験してきたことと繋がっていくのです。 ステロイドを使った後の風景や傷口をめぐる攻防は、まさに治る/治すとはどういうことか、を視覚的に表現していてすばらしい。学校で教科書的にも使えるかも?
1投稿日: 2017.04.20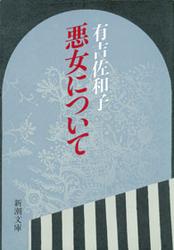
悪女について(新潮文庫)
有吉佐和子
新潮文庫
ドラマ化原作。沢尻エリカが15歳から40歳まで熱演!
富小路公子という女性が死にました。自殺か他殺かわからない、謎の死でした。若い美人女性実業家としてテレビにも多数出演し、世間にも知られた人物。順風満帆に見えていた彼女は、死んだ途端、虚飾の女王としてスキャンダラスな人生を暴かれていきます。 本書は、ある小説家が取材として、公子に関わった27人の男女にインタビューをしていく27章の証言集。彼女に騙されたと誹謗する人がいる一方で、あの人ほど素晴らしい人はいないと賞賛の声も聞こえてきます。これは、いったいどういうことなのでしょうか。 “人間も宝石も同じだと思うのよ。生命から輝くには、清く正しいことをしなきゃ”と言った公子。読者は、公子の本音がどこにあるのかをつかむことが難しい。なぜならすべての公子像が誰かによる伝聞であるから。近年では『桐島、部活やめるってよ』が同じような本人不在の物語でしたが、中心が空白で自分がない存在と考えてしまうのは、違うのかもしれない。 不在の人物が巻き起こした騒乱の人生は、いかに語られるのか。
1投稿日: 2017.04.20
「しきり」の文化論
柏木博
講談社現代新書
人と「しきり」の関係に迫る刺激的論考!
デザイン評論家、柏木博が注目したのは、“しきり”。自己と他者、ウチと外、聖と俗、日常と非日常、私と公など、AとB(とCと…)を分ける仕切りとは一体何なのか。空間を分けるという単純なことだと思われている仕切ることは、実は人間が人間であること、日本人が日本人であることと大きく関わっていたのです。 日本は、西欧式の空間のつくりかたとは違い、襖や障子といった可動式で音や光を透過する装飾可能なものを壁的なものとして使用してきました。完璧に空間を分けるのではなく、ゆるやかに仕切り、内と外が明確に区別されません。それは日本人のプライバシーや精神構造、社会構造などなど実に様々な文化の有り様と関係づけて語ることが可能なのです。 しきり、というとても日常的なモノ/コトを通じて考えられる射程は驚くほど広く、とても身近です。民族ごとの違いは、こうして現れてくるのでしょう。
2投稿日: 2017.04.20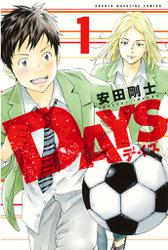
DAYS(1)
安田剛士
週刊少年マガジン
人を奮い立たせるものは何か。
元いじめられっ子で身長160センチもなく、サッカー経験もない柄本つくしは、高校サッカーの名門聖蹟高校でなんとサッカー部に入部します。バカがつくほど素直で、一生懸命であること、そして体力があること以外取り柄のない超サッカー初心者が、名門チームで一体何ができるのでしょう。 当然のようにドリブルで抜くことができるわけでも、華麗なスルーパスを出すわけでもありません。彼がチームに与えることができたのは、すでに持っていたその性格そのものと、その伝播感染力でした。見た目にわかりやすい技術や結果がなければ、一生懸命や素直という過程の領域は、なかなか評価されにくいもの。 つくしと過ごすDAYS=日々を共に過ごすチームメイトは何にも代えがたい何かを獲得していく。それはある意味でわかりやすい“結果”と呼べるものなのかもしれません。
1投稿日: 2017.04.20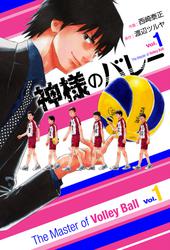
神様のバレー 1巻
渡辺ツルヤ,西崎泰正
週刊漫画TIMES
神様の指導と勝利哲学
スパイクの打点が高く、早いやサーブが強い、背が極端に高いなど、個々の能力が凄ければそのチームは強いのかと言われると、必ずしもそうではないのがスポーツのおもしろさ。なぜ強いのかと思うようなチームが、あれよあれよという間に勝利を手にすることほど、楽しみなこともないかもしれません。 実業団の凄腕アナリスト阿月総一は、自分たちの能力を適切に見定め、相手の弱点を見抜き、これでもかというほど相手チームの嫌がるプレイをしかける「嫌がらせの天才」。裏方としてチームを優勝に導いてきた阿月に、「万年1回戦負けのチームを全国優勝させれば、全日本男子の監督のイスを用意する」という声がかかる。 そして阿月は、気合と根性だけで練習を続ける弱小中学校バレー部のコーチとなります。彼がこのチームにもたらしたものはキツイ練習でも、難しい戦術でもありませんでした。しかし、試合はおもしろいほど阿月のペースで進み、勝ち進むのです。一体何が仕掛けなのかさえわからない、そんな読者も秘密を探しながら読む、そんな高度な戦術バレーマンガです。
1投稿日: 2017.04.19
体の知性を取り戻す
尹雄大
講談社現代新書
“ただ腕を上げる”という動作の困難さとは何か。
自分の体のことを、自分と体の関係をどれだけ“知っている”でしょうか。人は体を鍛え、筋力をつけることでより強力な力を発揮することができ、早く走ることができ、より強いパンチが打てるようになると思っています。 著者であるライターの尹雄大は、自身が柔道や空手、キックボクシングといった武道や格闘技を経験するうち、それらが持つ(筋)力の使い方や身体的な緊張について違和感を持ち始めます。鍛錬すればするほど鈍っていくかのような身体感覚。一度掴んだ“実感”というマジックワードを再現すべく、苦しい練習をひたすらしてしまうのです。 剣術家の甲野善紀と韓氏意拳に出会い、そうした疑問は徐々にはれていきます。「踏ん張らず、捻らず、タメをつくらずに動く」というおよそボクシングのパンチの打ち方の逆のような楽とさえ言えるような姿勢で相手と対峙し、圧倒してしまいます。 体の知性、とは何か。自然な体の使い方とは何か。“ただ腕を上げる”という動作の困難さとは何か。わたしたちの知らない自分たちの体がここにあります。
2投稿日: 2017.04.19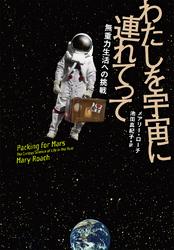
わたしを宇宙に連れてって―無重力生活への挑戦
メアリー・ローチ,池田真紀子
NHK出版
口の堅い宇宙開発機関への取材記録。
まだ見ぬフロンティアとして宇宙はまだ謎を含んだかっこいい憧れでもあります。そしてもちろん高度な知識や技術に厳しい訓練を経てなれる宇宙飛行士もそうです。でも、宇宙飛行が輝かしい!と思ったら、それは一部だけのことかもしれません。無重力での嘔吐に、拭えない体臭。排泄も…。人間の生理に関わることはまだまだ解決しなければいけないことも多そうです。 「宇宙」では、いったいどんな生活が待っているのでしょう。NASAが自ら明かすことのなかった宇宙開発の裏側。空気もシャワーもプライバシーもまだ整備されていないリアルな無呪力宇宙飛行の実態は、実は嘔吐の連続だそう…。 ユーモラスだけどちょっと下品に明かされる有人飛行にまつわる秘密を、未来の自分と重ねて読んでみてください。宇宙が近づきます(行きたくなるかはまた別です…)。
1投稿日: 2017.04.19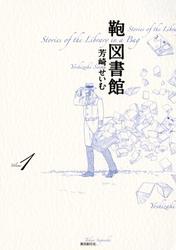
鞄図書館 1
芳崎せいむ
東京創元社
あなたが読みたいと思う本がこの世になくても、ここにある。
本は文字や絵が書かれたただの紙束の集まりなのではなく、モノとして存在することで具体的な人や記憶と結びつくのだということを、このマンガは伝えてくれます。 幻の“鞄図書館”と呼ばれるあらゆる書物が入っている鞄を持つ男。いつもゲーテの引用をしながら愚痴のような会話を続ける鞄と男。そう鞄は喋れるのです。その鞄と男は旅を続けながら、人々に本を貸し出し、返却を受けるために旅を続けます。 火事で失われるはずだった歴史的遺産の本や遺品として残された本、亡くした息子が読んでいた本など、鞄にはただ闇雲にタイトルが保管されているわけではないのです。たとえ同じタイトルの本があろうとも、ある1冊は特別な1冊として存在します。『金魚屋古書店』の芳崎せいむが描く、本をめぐる苦しくも、あたたかな物語。
1投稿日: 2017.04.19
Reader Store オフィシャルさんのレビュー
いいね!された数1437
