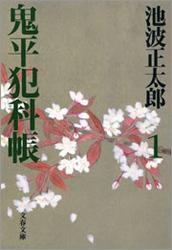
鬼平犯科帳(一)
池波正太郎
文春文庫
時代背景を知ると、小説の肌理が全くちがって見えてくる
ご存知、池波正太郎作品を代表する火付盗賊改方長官長谷川平蔵シリーズ。火付盗賊改方とは、江戸時代に重罪とされた火付け(放火)、盗賊(強盗)、賭博を取り締まった今で言う警察、裁判機関。ストーリーは、江戸で起こる犯罪行為を“鬼の平蔵”と呼ばれる彼が解決していくもので、時代物全般に言えることですが、特に時代背景を知っておくとおもしろい作品。平蔵が長官だったのは1787年から95年。重商主義で一部資本家を優遇し、収賄なども横行した田沼意次時代が終わり、反動から緊縮財政、思想統制を強く行った松平定信の“寛政の改革”期とほぼ一緒。そうした偏った思想や経済の停滞があった時期に起きた犯罪や人間関係と考えるだけで、平蔵の判断ひとつにも様々な意味が読み取れてきますよ!(スタッフI)
2投稿日: 2013.09.20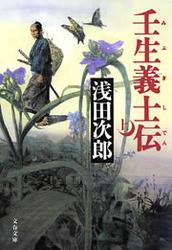
壬生義士伝(上)
浅田次郎
文春文庫
新選組には萌えないけれど、かっこいい男もいた
京都護衛のための最高治安機関京都守護職直轄の組織だった新選組は、その戦闘能力と権力によって、その本来の役目から逸脱した行為も多かったと言われています。ピーク時には200人にも及んだ隊員たちの中で、史実としてはほとんど語られていない人物吉村貫一郎を描いた本書。貧しい禄しか得られない藩を脱藩し、新選組に入った吉村は、家族への仕送りのためただひたすら戦い、金のために人を殺す守銭奴とまで言われながら、頑なに自らの信念を曲げませんでした。新選組の生き残りや関係者の回想という構成で、吉村が貫いた、愛する人のためにという行動力、生き様にどうしたって目頭が熱くなってしまいます。家族を持つお父さん、父親という存在を考えたい方にぜひ!
1投稿日: 2013.09.20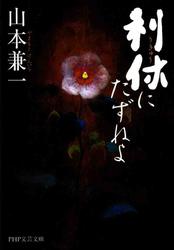
利休にたずねよ
山本兼一
PHP文芸文庫
美意識のおかげで生きて出世し、美意識のせいで死ななければならなかった人
侘茶の創始者としての千利休のイメージしかなければ、本書で描かれる彼は全く別人の顔を見せてくれるでしょう。秀吉が命じた切腹で命を絶つところから始まり、秀吉や妻、古田織部など、身近な人々が見ていた利休を語っていく構成。信長や秀吉の天下取りを後盾し、重宝されながらも、鋭すぎる利休の眼は次第に反発を呼びます。侘び寂びは、金の茶室を作るような派手好みな秀吉とは真逆の思想であり、器の価値をどう決めるかという問いに「それは、わたしが決めることです。わたしの選んだ品に、伝説が生まれます」と答える利休。絶対者としての利休に、秀吉はある種の恐怖を感じたのでしょう。その恐怖は冒頭の切腹へと導かれます。茶の湯が美的な話題だけで済まなかった、もしくは美こそが生き様の中心だった時代の、大胆かつ繊細な人間のこと。(スタッフI)
15投稿日: 2013.09.20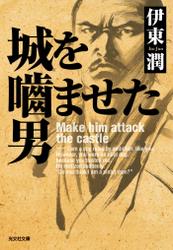
城を噛ませた男
伊東潤
光文社文庫
全方向土下座という手段
146回直木賞候補にもなった本書。戦国時代を舞台に、城や合戦を巡り、知略、奇略、謀略を駆使して戦った人々を描いています。“知略、奇略、謀略”と書いたように、ただの合戦とは一枚も二枚も違います。短編五編が収録されているのですが、「城を噛ませた男」「見えすぎた物見」「鯨のくる城」というタイトルを見ただけで、伊藤潤の他の本を読んだことのある人は、一体どんな戦いが繰り広げられるのかワクワクしてしまいます。知謀・真田昌幸の残酷極まる謀略を描いた表題作は、生き残るということに対する執着と快楽が見事に描かれています。(スタッフI)
0投稿日: 2013.09.20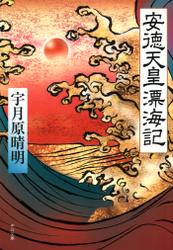
安徳天皇漂海記
宇月原晴明
中公文庫
こんなアクロバティックな歴史の語りが見たことない
わずか3歳で即位した安徳天皇は、8歳で迎たえた壇ノ浦の戦いで入水するも、神器の力で琥珀に封じられ、30年後、敵方であった将軍であり稀代の歌人源実朝と邂逅します。その後、魂を救済するために海を越えて運ばれて行くのですが、二部にはなんとクビライ・ハーンとマルコ・ポーロが登場、そして元寇にまで至るという壮大で奇想溢れる物語になっています。複雑に入り組んだこの物語。おもしろいのはその語りの構造。例えば、クビライ・ハーンに、中国の琵琶法師が平家物語を唄い、それを通訳がモンゴル語訳するというシーン。翻訳家・書評家の大森望さんが「翻訳というフィルタを通すことで、見慣れたものがまったく別のものとして立ち上がってくる」と言うように、幾重にも織り込まれた語りの構造は、奇想をただの思いつきにせず、小説内で見事な説得力を持たせています。綿密に資料にあたり、絶妙な飛躍をファンタジーとして成し遂げる宇月原の筆力をもっとも味わえる名作!(スタッフI)
4投稿日: 2013.09.20
耳袋秘帖 妖談うしろ猫
風野真知雄
文春文庫
長谷川平蔵と遠山の金さんを超える男
江戸南町の名奉行として名を馳せた根岸鎮衛は、本業の傍ら老人や同僚、ちまたの珍談奇談を集め続けた人物。『耳袋』と呼ばれるそれは、約1000編にも及ぶ膨大なコレクションとなり、当時を知る貴重な資料にもなっています。岩波文庫などで読めるこの『耳袋』が、まなかなりおもしろいのですが、それはまた別の機会に…。そして『耳袋』には誰にも見せない“祕帖”がありました。そこに描かれる江戸の不思議と怪異の物語が、根岸が関わる事件の中に織り込まれていきます。根岸は、遠山の金さんよろしく赤鬼の刺青を体に刻み、長谷川平蔵と出生争いをしながら、一刀流の名人で人情家の栗田と二刀流のおっとりした坂巻を両脇に、事件を解決していくわけです。イキイキした登場人物たちに、知っているキャラクターやニヤリとさせるような他の時代物へのオマージュ的な要素が絡む、時代物好きにはたまらないシリーズ。(スタッフI)
1投稿日: 2013.09.20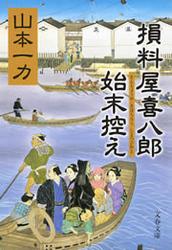
損料屋喜八郎始末控え
山本一力
文春文庫
江戸時代のディテールで描く、人情とお金と日々の暮らしのこと
10以上の職を転々として、80年代に2億円近い借金を背負い、その返済のために作家への道を歩み始めた山本一力氏。その経験は、本書で江戸時代の金貸し業者“札差”を描くことに役立っているようです。これは、幕府と侍たちの米の仲介業者であった札差が貸金業へと移行し、裏側での存在感を増していった時代の話し。貸金業者と庶民に生活用品を貸し出す”損料屋”に身をやつした主人公との対比構造は、江戸っ子の人情と生活を描く格好のモチーフとして、万全に配されています。江戸時代の経済状況、生活の水準、借金棒引きの“棄捐令”発令という政治との関係等々、江戸時代のデティールの知識と描写が、巧みに織り込まれたデビュー作とは思えない、充実の作品です。(スタッフI)
1投稿日: 2013.09.20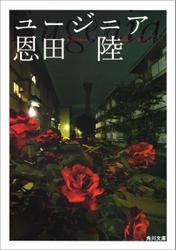
ユージニア
恩田陸,松本コウシ
角川文庫
読めば読むほど、"謎"が読者に絡み付く
乾杯の音頭の直後、家族や近所の住人を含めた17名がもがき苦しみ、死んでいく。そんな凄惨な事件を、数十年経った後に関係者の証言によって掘り起こしていきます。この小説、それぞれが自分の記憶を頼りに喋り、また嘘をつく者もいるので、当時の様子はぼんやりとした形でした表れません。それぞれの言い分が異なる、芥川龍之介の『藪の中』にも近い構成。『藪の中』の中と異なるのは、事件は確実に発生しており、また犯人も比較的早く判明すること。しかし、その動機が一向に掴めません。そう、物語が終わっても、この小説は読者にきちんとした結末を与えてくれないのです。「なぜ?」というモヤモヤが頭から離れない。読後もずっと心を奪われ続ける、魔力を持ったような推理小説です。(スタッフI)
2投稿日: 2013.09.20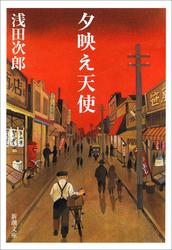
夕映え天使
浅田次郎
新潮社
余韻が響く人情話
人間臭く、じんわりと胸に染みるような短編が詰まった1冊。表題作「夕映え天使」では、中年の店主と年老いた父親が営む中華料理屋に、身寄りのない40歳の女性が住み込みで働き始めます。よく働く女性で、妻にしたいと思った矢先に突如姿を消してしまいます。その後店主は、同じように彼女が住み込みで働いていたという、うどん屋の店主と遭遇。彼女は何者だったのか? その謎は明かされないまま、ふたりは彼女との思い出を語り合います。他の短編も、語り過ぎずに巧みに物語を省略し、余韻を残した作りとなっています。(スタッフI)
0投稿日: 2013.09.20
MIX(1)
あだち充
ゲッサン
甲子園優勝から始まる物語
名作『タッチ』の世界を受け継いで新たに生まれたのが、この『MIX』です。舞台は同じく明青学園。上杉兄弟の活躍から26年後を描いています。直接的にはその繋がりが明示されないものの、時折『タッチ』の続編であることを感じさせるシーンが登場し、思わずニヤリ。例えば、5話に出てくる甲子園優勝皿には「上杉達也」の文字が!小物にもしっかりその歴史が描き込まれています。今回のヒロインは、幼なじみであり義妹の音美。あだち充さん持ち味のゆったりとしたラブコメも見所の1つです。(スタッフI)
7投稿日: 2013.09.20
Reader Store オフィシャルさんのレビュー
いいね!された数1438
