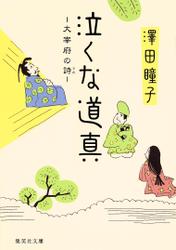
泣くな道真 大宰府の詩
澤田瞳子
集英社文庫
泣いてるなんて、らしくない!
一介の学者から大臣にまで登り詰めた菅原道真は、世渡り下手故に大宰府へと左遷されて失意のうちに亡くなり、一方で京の人々は道真の怒りを恐れて神へと奉り上げた…。 菅原道真に関して大体こんなイメージでいたのですが、当時最高の頭脳を持つ人物があっさりと失意のうちに死ぬっていうのにも違和感があった私には、この作品は「こんな道真像が見たかった!」と満足の一冊でした。 大宰府に着いた道真は始めは屋敷に引きこもり泣き暮らしているのですが、監視役の小役人・保積と大宰府庁幹部の姪・小野小町(恬子)が博多津の街に連れ出した後は大陸との交易地である当地を満喫する現金な暮らしぶり。 途中、度重なる不幸や他者からの批判に再び失意に陥るのですが、周囲から知恵を借りたいと求められてからは、これでこそ智者・菅原道真だという展開です。 道真の雷神伝説も、定説を知ってるとちょっとニヤリとしてしまいます。 物語の中では喜怒哀楽が激しく描かれていますが、人間くさい道真像も意外性があって魅力的でした。
12投稿日: 2015.01.26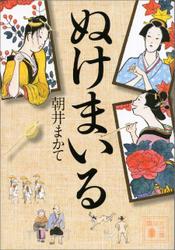
ぬけまいる
朝井まかて
講談社文庫
アラサー女子の旅、江戸時代Ver.
女三人集まれば、姦しいのは今も昔も同じ事。 娘時代に小町と呼ばれた幼なじみの猪鹿蝶の三人が、パッとしない気分を変える為、ノリと勢いで「そうだ、旅に出よう!」という物語。 江戸時代に流行った伊勢参りがテーマですが、人物造形はまるで現代のアラサー女子達を見ているかのよう。 家業の食堂を手伝いつつ作家志望のお以乃、親から継いだ店を繁盛させる女社長のようなお蝶、良いとこに嫁いだ若奥様のお志花。 それぞれ「自分はまだイケる」と思っているけど、本当はもう若くもないことにも気付いている彼女らの気持ちには共感してしまいます。 それに、ちょっとした冒険や大勝負もあり、クサクサしていた気分が上がるストーリーです。 気心の知れた幼なじみだから、安心することもあればムカッ腹立つこともある。けれど、こんな風に仲間と一緒に旅に出たらきっと楽しいだろうな。
7投稿日: 2015.01.26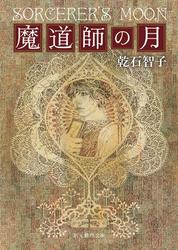
魔道師の月
乾石智子
東京創元社
直感と理論、大地と書物。二人の魔導師の物語。
『夜の写本師』の第2弾であり、前日譚です。 前作で主人公が用いた「ギデスディン魔法」の創始者キアルスと、大地の魔導師レイサンダーの物語。 富と繁栄をもたらすが、その後破滅を呼び込む邪悪な円筒〈暗樹〉を巡って、逃げたりあるいは封印の方法を求め旅する二人の視点で展開していきます。 黒髪に緑の瞳という外見が共通する他は真逆な性格で、何事にも執着心が薄く直感的なレイサンダーも理屈っぽいキアルスもそれぞれ魅力的に描写されていて、キャラクターに引っ張られつつ読み進んでいけます。キアルスが失い、復元しようとする「タージ(タゼン)の歌謡集」の展開も作中作と言える内容で、物語に厚みを持たせています。 二人が出会い、〈暗樹〉への対抗策を求めて別れ、再会して共闘する。邪悪な存在を打ち破るというファンタジーの王道なストーリーで今回も面白いのですが、復讐をテーマにした前作よりは軽い気分で読めるかと思います。前作と逆順でこちらを先に読んでも楽しめるかもしれません。
10投稿日: 2014.12.05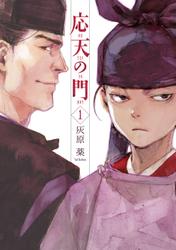
応天の門 1巻
灰原薬
コミックバンチKai
菅原道真と在原業平がコンビを組むなんて!
菅原道真と言えば、学問の神様もしくは日本三大怨霊の一人として有名。 在原業平と言えば、伊勢物語の昔男のモデルとも言われ平安時代きってのプレイボーイ。 生没年が幾らかかぶっているとはいえ、あまり共通点も接点もなさそうな二人がコンビを組み、京の都で起こる事件の解決に乗り出す…というなかなか意表を突く設定の物語ですが、二人のキャラクターも秀逸で現代に置き換えるとしたら「気難しい天才少年(道真)に事件解決のアドバイスを求める女たらしの刑事(業平)」という感じで結構面白い。 博識ではあるけれど経験値の少ない道真が、挫折や社会の理不尽を知る業平に出会ってどう変わっていくのか…まだ始まったばかりですが、先が楽しみな作品です。
12投稿日: 2014.11.22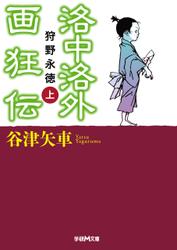
洛中洛外画狂伝 狩野永徳 上
谷津矢車
学研
若さ故の勢い
導入部は、後に狩野永徳を名乗る若者が織田信長の持つ虎図屏風に対し、「こんな生きていない画で満足するのか?」と挑発するシーンから始まる。その後、『洛中洛外図屏風』を描くまでの若者・源四郎の半生が語られるのですが、この展開はズルい!一気に物語に引き込まれます。 『洛中洛外図屏風』は将軍・足利義輝の求めに応じて描かれた物ですが、その足利義輝との出会いや狩野家惣領としての葛藤、絵を描く事への情熱、若いが故の未熟さ等、勢いあふれるエピソードが多くあっという間に読んでしまいました。 ただラストは、冒頭の挑発に対する信長の反応が肩透かしを食らった感じがします。下巻に収録の書き下ろし短編まで読んで、やっとカタルシスが得られた感じ。 それでも、著者はまだ20代と若い事を考えると、これからが楽しみです。
8投稿日: 2014.11.17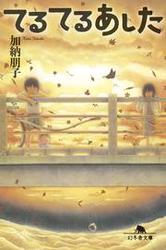
てるてるあした
加納朋子
幻冬舎
魔女と暮らして
親の夜逃げにより、佐々良に住む遠い親戚の久代婆の元へやって来た少女・照代の成長記。 かなりダメな親の元を離れ、元教師の久代婆と暮らし、周囲の人々と触れあうことで人間的に成長する照代の様子も良いのですが、密かに魔女と呼ばれる久代婆の抱える秘密や分かりにくい愛情表現に気付いた時には、残された時間の短さも相まって涙腺がヤバかったです。 登場人物は前作『ささら さや』と共通しているので久代婆達の人物像をよく知りたいなら読んで置いた方が良いですが、ストーリーはこちらが断然オススメ!
15投稿日: 2014.11.17
環八イレギュラーズ
佐伯瑠伽
中央公論新社
これ、映像化希望!
憑依生物(というかプログラム)の逃亡犯を追って地球にやって来た同じ種族の刑事が、乗り移った相手の女子高生らと協力して、逃亡犯が乗り移った相手が誰かを突き止める話。 1950年代SFのハル・クレメント作『20億の針』を現代日本に持って来て、登場人物に知的障害者を加え、頭脳戦あり、アクションありで盛りだくさんな内容なのにラノベ感覚で読みやすい文章。これがデビュー作とは、凄い新人が出てきたもんだ。 直接言葉を交わせない憑依生物の刑事が主人公たちとイメージカードで意志疎通するシーンや終盤のアクションは映像化したら面白そう。無理目なテーマかもしれないけど。 オタクでコミュ障な少女の中に、知的障害者だけど意欲的な美少年の人格が同居することで起こる二人の変化の描き方がうまい。あとがきで触れられていますが作者自身、障害者のご家族がいるそうで、障害者自身が誰かを幸せにする話が書きたかったとの事。難しい題材だけど深刻にならず、エンターテイメントとして楽しめる作品でした。
7投稿日: 2014.11.01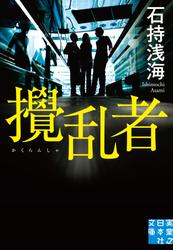
攪乱者
石持浅海
実業之日本社文庫
九つの文藝作品とテロリストたち
社会を攪乱させ日本政府の転覆を企むテロ組織メンバー3人が受けた奇妙な任務と、その任務によって引き起こされる結末を描く9編の連作短編集。 コードネーム「久米」「輪島」「宮古」のテロリスト3人が組織から言い渡される任務は目的がよくわからない奇妙なものばかりで、不可解に思いながらも実行する彼らにもう一人のメンバー「串本」が任務の目的を解説するというのが各話の基本的な流れです。 暴力や流血沙汰になるような方法は採らない、実行部隊に任務の意図を知らせないという組織上層部の方針が優秀な3人のテロリストの関係や運命を変えていきます。 各短編のタイトルは「檸檬」「一握の砂」「蜘蛛の糸」「みだれ髪」「舞姫」など学校の授業でも習うような文豪の有名作品がずらり。タイトルの雰囲気だけを用いたものもあれば、作品の内容が短編のストーリー展開を示唆しているものもあり、それぞれの文藝作品がどう絡んでくるのか深読みするという楽しみ方もあります。 暴力は用いないとは言え、他人を駒のように扱い、不安を煽るような彼らの行動・考え方に共感は覚えませんが、いつかこんな人たちが出てきてもおかしくないと思えてちょっと背筋が寒くなります。
6投稿日: 2014.10.25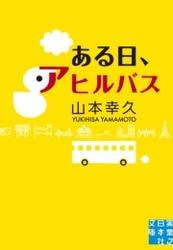
ある日、アヒルバス
山本幸久
実業之日本社文庫
はとじゃないよ、アヒルだよ♪
観光バス会社「アヒルバス」のバスガイド・デコが主人公の笑えて元気になれるお仕事小説。 どう見ても「はとバス」がモデルな「アヒルバス」ですが、定番の東京観光ツアーに加え、『ディープな東京でドキドキ!旦那様にはナイショでナイト』なんていうイロモノツアーも行っている楽しげなバス会社です。 そこの中堅ガイドのデコ(秀子)も本人はわかって無いけど、ちょっとズレてる感じが楽しい。個性的なツアー客のグループや新人に対するあだ名のネーミングセンスといい、同僚たちへのツッコミといい、思わず笑ってしまうキャラクターです。 かつては数々の失敗を起こしていたデコも新人教育を任されるようになったものの、尊敬する三原先輩のようにはできないことに悩みますが、彼女が自分なりのやり方を見出すシーンには「仕事ってそういうもんだよな」と共感できます。 仕事ガンバロって思えて、元気になれる一冊です。 それにしても、デコが通勤に愛用する自転車のロゴには笑わされた。ヤッターマンかよw
9投稿日: 2014.10.25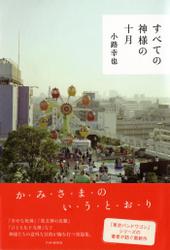
すべての神様の十月
小路幸也
PHP研究所
十月だから、神様を思って読んでみた。
八百万の神がいる日本だから、いろんな神様がいて当たり前。そんな神様達の優しい6編の短編集。 初めの3編は死神、貧乏神、疫病神とあまりお近づきになりたくない方々だけど、誰かに憑き淡々と仕事をする彼らは逆説的に人々の幸せを導いてくれる。 他に、交通誘導員の道祖神、九十九神となって喋るお釜さん、自分がどんな存在か忘れてしまった福の神。 人間の中にいると神様達も人間臭くなってしまうけど、導く側の存在である事は変わらない。 「人間の前に姿を現す時は偽名を名乗り、対象者が亡くなる(貧乏になったり、病にかかったり)のを見守るだけ」という神様達のスタンスは伊坂幸太郎氏の「死神の精度」から設定を拝借したそうですが、飄々とした死神・千葉と味わいは違っていて、こちらの神様達はみんなお人よし。 この優しさが小路さんらしいです。
9投稿日: 2014.10.02
sabachthani?さんのレビュー
いいね!された数515
