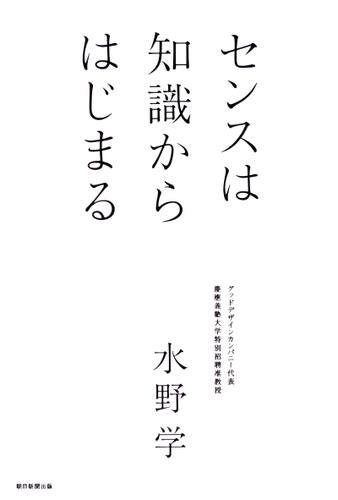
総合評価
(403件)| 91 | ||
| 161 | ||
| 93 | ||
| 12 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスを磨くには知識の集積と客観的視点の醸成、努力で身につけるもの。 あまり目新しさは感じなかったが、数年前に出会っておきたかった本。 場所や距離に関係なく非日常を味わうことは「旅」である、という考え方が好き。
0投稿日: 2023.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センス無いのでやりません」って言ってWebデザインを避けてきた自分に響く内容。センスがあることはマナーであり、勉強を怠っていることを公言してるだけだった。 流行を取り入れることが「センス良い」と考えていたけど違った。オーバサイズの服がトレンドだけど、体が小さい自分にはでかすぎて似合わない。トレンドのものや、自分が好きなものを選ぶのではなく、客観的に最適化されているものの方がセンスが良い。商品デザインをするなら、色や字体、王道など、歴史から勉強していく。センスの良さは突然やってくるものではない。 まずは、アイコンを描くところから始めたい。王道、色、字体を勉強していく。
0投稿日: 2023.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスがないと諦めることへの叱責ともとれた本 アイデアもそうだけど、何もないところから生まれることはほぼなく、様々な知識や情報や感情をしっかり蓄積することの大切さを説明してくれている本。 普通を知る、というところはなるほどなという感想。何がベーシックなのか、それより上と下、のものさしができると。 社会人10年以上やってると、新卒の時よりずいぶん発想力が豊かになったなと思うが、きっと経験と知識の積み重ねによるものなのだろうと改めて実感する。
0投稿日: 2023.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「センスのよさ」とは数値化できないよし悪しを判断し、最適化する能力である。 「普通」こそ、「センスのよい/悪い」を測ることができる唯一の道具である。 センスとは知識の集積。 センスとは知識に基づく予測。 効率よく知識を増やす3つのコツ。1)王道から解いていく2)今、流行している人を知る3)「共通項」や「一定のルール」はないかを考えてみる。 精度の差。デザイン&ブランドは細部に宿る。 服選び 1)ターゲットの表面的な「特性」を正確にはあくする。2)ターゲットの内面的な「特性」を把握する。 3)最適化の条件を設定する。 4)最適化に向けた機能を設定していく 5)時代環境を考えて調整する。
0投稿日: 2023.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ天才に対して失礼だが、共感できる部分が多数。 私自身、なんでそんなアイデア思いつくの? と言われることがよくあるが、色々インプットしてるからアウトプットできるんだよということをロジカルに説明してくれている。 水野さんの著書は他何冊か読んだがこれが一番水増しが少なく、好き。
0投稿日: 2023.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルである「センスは知識から始まる」の意味がよく分かった。 自分にはセンスがないから。これは彼に比べたら苦手な分野だからもう手を出したくない。などと避けていた分野について、そんなことを言う権利があるほど君は勉強したのか?そう問われるような内容だった。 何かをやりたいなら、センスを持ちたいなら、まずはそのジャンルと付随する周辺分野の「知識」を得ることから始めたいと思う。
1投稿日: 2023.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは後天的に得られる能力であり普通を知った上で成り立つものである。 日常会話の中で「センスない」と使いがちだが、それは思い込みで自分を納得させる為の言い訳に過ぎなかったと反省させられる一冊だった。 それと同時に色んな事を知りたい欲が前より強くなった。
0投稿日: 2023.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ仕事で直接デザインに携わっていなくても、普段のちょっとした行動や思考で誰もがセンスを磨くことができる。 刺さる部分が多くて、たくさん付箋を貼りました。何回も読み返そうと思います。
0投稿日: 2023.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ・センスの神様なんていない ・センスのよさとは、数値化できない事象の良し悪しを判断し最適化する能力 ・まず普通を知り、基準を作ることが重要 ・本当に簡単なことをこれが重要だと認識し、日々実践を繰り返すことが難しい ・センスの最大の敵は思い込みであり主観性 ・効率よく知識を増やすには、1 王道を知り、2 流行を雑誌などで掴み、3 共通項や一定のルールがないかを考える ・感覚的に良い、ではなく、ほんの少しの差が何かを見つける ・知識を加えて消費者へのベネフィットとする ・自分の好きと感覚がどこから来ているか知識で測って説明する ・好き嫌いではなく、誰がどんな時にどんな場所で使うのかを思い描くこと ・いつもと違うことをし非日常を体験することで、思い込みの枠を外す ・書店を5分で一周して気になったものを確認すると、一年で365の知識が増える ・人生の先輩と話してセンスの底上げをする
1投稿日: 2023.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰の言葉だったか、「センスは情報量に比例する」を大事にしていたから、タイトルだけで楽しみにしていた一冊。 「センス」は、数値化できない事象に対して使われる表現であると定義したのには納得した。 ただ、具体例の羅列とか、細切れのセクションとか、中盤は間延びした印象。 彼女が喜ぶプレゼントも知識の集積から。
0投稿日: 2023.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ『センス』という目に見えないものの定義、その定義に基づくと『普通』を知ることが重要になり、『普通』を知るためには定番と流行を知ることと、日頃から自分の興味の範囲外のことに興味を持っていく必要がある。という本。 『センス』という言葉を聞いて自分には遠い話だ、と思う人ほど読んでみると心が軽くなるような本。1時間ちょっとで読めます。
0投稿日: 2023.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり残るものはなかったというのが正直な感想。 知識というものはそれそのものが言語化できるもので、それを掴めればアウトプットとしてのセンスが発揮できる。というのはわかる。 だけど、何かを見てそこから知識として吸収できるかは、また違った意味でのセンスだと思う。 センスは知識から始まるのなら、その点についても言語化できてていいのでは?と思った。
1投稿日: 2023.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルの通り、センスのなさというのは、知識がないところに原因があるというのが主張。 確かに何も知らないところから良い発想が生まれるはずもない。 絵画でいうと、たとえば苦悩を表現した絵を何枚も見てれば、自分が苦悩を表現したいときのヒントになる。絵を1枚も見たことない人は、よほどの天才でない限り「苦悩」を表現することはできない。 そしてその知識の吸収は、意識を少し変えるだけでよくて、誰にでもできること。 言われてみればそうだよねって思うことが多かったけど、それを実行できていたかどうかと言われると…。 読んでよかったです。
0投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センスがいいもの」の正体を知るためには、まずは「定番」を知り尽くす必要がある。 誰もが最初は初心者で、定番なものを通って行って、自分好み、友達好み、変わり種を理解していくのだと、なんだか勇気づけられました。 私はセンスがないからなあーと避けていたものも、とにかく調べまくって体験しまくっていけばいい。 センスとは知識、というのがとても腑に落ちました。
0投稿日: 2023.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ以下、覚えておきたい文言。 「第一に、調査だけに頼っていると、自分は何がいいと思い、何がつくりたいのか、自分の頭で考えなくなります。」 「本当に簡単なことを、「これが重要だ」と認識し、日々実践していくこと。その繰り返しを続けることが難しいのです。」 王道から解いていくこと
1投稿日: 2023.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識をつけること、思い込みをできるだけ無くすこと。 分かりやすく共感でき、そして私にとっては自己肯定感の高まる水野流のセンスの身につけ方。 2023年の一発目に読んでよかった。
1投稿日: 2023.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の頃からイヤでも耳にするセンスとほ、100%先天的に身についたものではなく、物事の本質を理解した上で適切な努力をするからその人に備わっているように見えるもの。なるほど。
1投稿日: 2023.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
タイトルの通り、センスは知識から。そして、その為にはインプットが必要だという事が繰り返し語られる。 そしてインプットは幅広に。書体やレイアウトに関する知識、雑誌から得られること、お店での観察、など日常生活の至る所にインプットすべきことは転がっている。 常に観察すること、感じること、これが大切なのだと思う。
0投稿日: 2022.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルの通りで、自分はセンスがないなぁなんて思ったりすることも多いけど、単に勉強不足なんだなと感じさせられる本。面白かったです。
0投稿日: 2022.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
市場調査ありきだと新しいものは生まれない?? センスとは知識 誰でも見たことのあるものという知識を蓄える そしてそれを組み合わせていく センスの敵は主観性。客観情報を集めることでセンスは良くなる。 王道を知り、流行を知り、共通点やルールを見つける。 感覚を頼らない。フォントひとつにも知識があると選択が変わる。 好きを深掘りする。 →自分の土俵に持っていくのもあり。方向性。 誰がどんなときにどんな場所で使うのか →センスの最適化
0投稿日: 2022.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書を読む前、「センスがいい」や「勘が当たる」というものは膨大な経験と知識からなるものだという自分の考えを持っていた。本書にはまさにそのことについて述べてあり、自分の考えと一致することがわかった。「センスは知識に基づく」くらいの認識しかなかったが、本書ではどのような知識をいかようにして集積するか述べある。 数値化できない事象を最適化することがセンスであると定義されており、それが意味するところも読み進める中で理解できた。センスを磨く上で、「不勉強」と「思い込み」は敵であることも学んだ。 センスを磨くには知識が必要だが、知識を吸収し自分のものとしていくには、感受性と好奇心が必要。感受性(感じる力)を育むために、日常から離れて非日常な所へ行ける旅をやってみたいと思う。 ジャンルごとの普通とは何かについて知識を集積することと、旅に出ることを本書から学んだことから行うアウトプットとする。
1投稿日: 2022.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ○センスはまず普通が分かること。普通が分かって良い、悪いが分かる ○センスとは知識の集積 ○普段自分の触れないものにあえて触れてみる。 ちょっとした冒険をしてみる
0投稿日: 2022.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログひたすら 『よく考えろ』 と書いてあります。 思い込みや感覚的な物言いを捨てて。 穏やかに読ませる本でしたが、 グッとくる本ではありませんでした。
0投稿日: 2022.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログPrologue センスは生まれついてのものではない 1 センスとは何かを定義する 2 「センスのよさ」が、スキルとして求められている時代 3 「センス」とは「知識」からはじまる 4 「センス」で、仕事を最適化する 5 「センス」を磨き、仕事力を向上させる Epilogue 「センス」はすでに、あなたの中にある
0投稿日: 2022.11.08 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスのいい人間になりたい。 生まれ持ったものでしょ?努力しても手に入らないと思っていたそのキラキラふんわりした言葉が、実は豊富な知識をベースに構築できるとは。 まずは知識を蓄えていこう。一生に一度は言われたいもん。 センスいいねって。
3投稿日: 2022.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは才能や感覚的な物と考えてしまいがち。何もないところから突然ひらめく訳ではなく、知識の裏付けが必要となる。スタンダードなもの、その歴史的背景も知っておく。
0投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去に読んだことあったけど、 最近WEBデザイナーを始めたこともあって再読。 何度読んでも気付かされることがある。 センスって感覚じゃない 全てに理由がある デザイナーたるもの、その理由を説明できなきゃ! さあ、今日もデザインに励みます
1投稿日: 2022.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔書店でタイトルを見て、なるほどなぁと思ったまま読まずにいたのですが改めて読んでみました。内容はタイトルの通りです。勉強しなきゃという気にさせられます。
2投稿日: 2022.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書に書かれてあった通り、センスは才能ある人のものだと思っていたけど、センスは知識の蓄積から生み出せるものとのこと。 センスとは数値化できない事象を最適化すること。 まずは知ることが大切。 知識を蓄えることなら自分にもできそうなので、色々なものに触れてみようと思った。
0投稿日: 2022.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスという感覚値を言語化している本。 知識があってこそ、 最適な選択ができる。 確かに知らないよりは知ってる方が 選択肢があると思う。 内容はよくわかるが、 センスを感覚でずっと捉えていたので 腹落ちがなかなか進まず。 同じ人多いと思う。 それくらいセンスに対して、 考えることになった本。 おすすめします。
0投稿日: 2022.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログとても参考になる本でした。 「センスは持って生まれた才能ではなく知識の集積がセンスなのだー!」という要旨でした。 なるほどー!と思える箇所が多々あり、参考になりました。 ぜひぜひ読んでみて下さい。
11投稿日: 2022.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識によって磨かれる、というとても勉強になる本。 自分は無知であるということを頭に、常にいろんなことへアンテナを張って吸収していこうとする姿勢がやっぱりなにより大切なんだなぁ。
1投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスを良くするには客観情報を集めること。瞬時に物事を最適化する人がいたとしても、それは膨大な知識の集積。知識を集めるには、まず王道のものは何なのか紐解く。次に、雑誌で流行を抑える。最後に、王道や流行以外も見ながら、共通項はなんだろうと考えること。知識を融合することができたなら、細部にこだわる。このプロセスがデザイン。
1投稿日: 2022.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分では言語化できなかったことが的確に説明されており圧倒される。ここ数年読んだ本の中で最も得るものが多かった。
1投稿日: 2022.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
くまモンのデザインを手がけた水野学さんの著書。 この本ではセンスの良さを「数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力」と定義している。ナルホド。 ざっくりいうとあらゆるものに触れて知識を蓄積し、良し悪しがわかるようになり、求められたものに対して知識の引き出しからこれじゃなかろうかというものを選べることがセンスがあるということらしい。たしかにそうかも。 また、新しいアイデアは特定の分野の知識×別分野の知識から生まれるとのこと。 私は浅く広い知識しか持っていないのでセンスを深めねばなぁと思った。 本をたくさん読むことも勧められていたので、素直に実践してみる。 言葉のセンスを磨いてフリースタイルできるようになりたいな〜
1投稿日: 2022.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 一つ専門の知識を持ちその周りに多分野の知識を絡みつかせる。知識は膨らんでいきやがてその人の独自性を形成する。センスとはその人らしさのこと。
1投稿日: 2022.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログKindleUnlimited センス=知識を元にして物事の善し悪しを判断できること 色の組み合わせにも理由があり、気をてらった商品が売れるわけじゃない
1投稿日: 2022.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ世間一般で言われるセンスというワード そもそもセンスというのは何なのか 生まれ持った感覚的なモノではなく 知識を集積することでスキルとして向上させることが できるものだということを教えてくれる その方法は? 考え方は?? 普段の生活の中で少しスパイスととして 取り入れていこうと思える。 繰り返し読みたい1冊。
2投稿日: 2022.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ結論、全てのセンスは知識から始まるという本だった。 平たく言うとほとんどの人間はゼロベースから始まり生き方から手に入れることができる知識でセンスが決まっていくとのこと。 これからセンスを上げるためには知識を得る環境を手に入れることとどんな物にも興味を持てるような好奇心を育てて必要があると思った。 上記の目線を手にする為の振る舞い等は、先人の意見を参考にしてこれから学んでいきたい。
3投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログどんなにいい仕事をしていても、どんなに便利なものを生み出していたとしても、見え方のコントロールができていなければ、その商品はまったく人の心に響きません。
1投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアウトプットのセンスの良し悪しは、結局のところ知識の量と質に依存する。だから、センスの問題は知識をインプットしないとはじまらないよということ。
1投稿日: 2022.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスがいいとか悪いとか、よく耳にする言葉ですが、なんだかぼんやりとしたもののように感じていました。 「センスって一体何?」 この本は一つの答えを示してくれています。 センスとは数値化できない事象を最適化することであり、知識に基づく予測である。 センスの最大の敵は、思い込みと主観性。 ということは、最大の味方は圧倒的知識量と客観性といったところでしょうか。 読書に落とし込んで考えるなら、ジャンルや著者にこだわりすぎず「広く深く」読んでいくべきなのかなと。 何もかも知りたくてたまらない自分でいたい!!
3投稿日: 2022.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこう言う本は、今まで意識してなかった日頃の行いに初めて気づく事が多いから読んだら面白く感じると思う。作者の意見を参考に自分なりに行動してみようと思った。
1投稿日: 2022.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識ということが非常にわかりやすく説明されている本。クリエイターの方なので、センスの組み立て方を商品開発を例に説明されているが、商品開発に限らず、全く違う分野でも行かせそう。 何かを新しいことに取り掛かるとき ・まずは王道を調べる ・いまの流行り、最先端を調べる ・王道と流行りの共通点をみつける ということをされているらしいが、 例えば、コンサルにおいても題材に対して↑をやろうとすれば効率的にクライアント+業界理解したうえで3点目で自分の意見も形成する癖をつければ十分に力がつくであろう。 どの分野のプロと呼ばれる人たち、第一線を走っている人たちにとっては↑の手順なぞ、ほぼ無意識に行なっているだろうが、この思考回路を著書で教えてくれるのはただただ有難い。
1投稿日: 2022.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログまったくタイトルの通りだと思います。ただ、付け加えるならば、センスは知識からはじまり知識で補強されていく。この補強が少し厄介で、同じ価値観・志向のものばかり集まってきがちで、結果として偏ったセンスが醸成された方もちらほら。そうなると、もはやセンスとは言えない。 知識は広くあつめたいものですね。
2投稿日: 2022.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識が少ない→自信が持てない→意見を言えない というループにハマっていて、色んなことをもっと知れば自信を付けられるかも!?と思っていた時にこの本を読めて良かった。 「センス=知識の集結」、「言葉で説明出来ないアウトプットはあり得ない」など、まさに!と思っていた内容で、特に目新しいことがあったわけではない。けれど、具体的にどうしたら良いかの具体的な方法や、考えてはいたけれど言語化出来なくてモヤモヤしていたことが分かりやすく書いてあって、参考にしやすいと感じた。
2投稿日: 2022.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは特別な人に備わっているものではなく、知識を蓄積することで磨くことが可能、。 知識も単に浅く付ければ良いわけではなく、やはり考える力が大切になる。
1投稿日: 2022.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Prologue センスは生まれついてのものではない 1 センスとは何かを定義する 数値化できない事象を再t系か 普通を知る 子どもは自由にセンスを発揮 2 「センスのよさ」が、スキルとして求められている時代 次の利休 技術がピーク→センスの時代 経営者のセンス どんな職業にもセンスが不可欠 3 「センス」とは「知識」からはじまる 知らないはフリ 閃きを待つ<知識を蓄える イノベーション=知識×知識 センス=知識にもとづく予測 客観情報の集積→センスを決定 4 「センス」で、仕事を最適化する アウトプットの制度↑・シズル感を最適化 5 「センス」を磨き、仕事力を向上させる 思い込みの枠を外す 人生の先輩と話してセンスの底上げ Epilogue 「センス」はすでに、あなたの中にある
1投稿日: 2022.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「くまモン」の生みの親である著者がセンスとは何なのかを綴った本。タイトル通り、知識からセンスは生まれるとのこと。つまりゲシュタルト形成である。
1投稿日: 2022.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは生まれながらにして備わっている訳では無い。豊富な知識を蓄え、その知識を正しく使って分析することによって、センスが良いと思われる回答を導き出している。 知識を蓄えるためには時には自分が興味を持っていない分野に手を出してみることも必要。 自分は色々なことにセンスがないと諦めていた部分が有ったが、知識を蓄えることでセンスのある考えができるという筆者の意見に少し勇気付けられた。 自分がいいな!嫌いだな!と感じることを何故そのように感じたのか?と言うことを言語化できるようにしていく。
1投稿日: 2022.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログーーー センスが知識の集積である以上、言葉で説明できないアウトプットはあり得ません。 自分のセンスでつくりあげたアイデアについて、きちんと言葉で説明し、クライアントなり消費者なりの心の奥底に眠っている知識と共鳴させる。 ーーー まさにそう!言葉にできるというのは本当に大事なことだと思ってる。 言葉にできないってことは、なんとなくの理解でしかなくて、知識や思考が足りてないんだよな。 そして、この後半部分が仕事をしていて自分の力不足を感じる部分でもあるからこそ、これからも知識の精度を高め、アウトプットの精度を高めていけるように精進するぞ。
1投稿日: 2022.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログクリエイティブディレクターでgood design companyの水野学さんの本 斬新なアイデアを出すときにはセンスが求められるように勘違いされるが知識の積み重ねが重要。 ▼センスとはなにか センスは数値化できない事象の良し悪しを判断して最適化する能力。 「日本で一番売れている服」はデータを取ればある程度考えられるが、それを着ればセンスがよくなるわけではない。 センスのいい/悪いは「普通」を知ることが何より。 坂本龍一が「ビートルズはすごい」といえばすごそうに感じるのは坂本さんが古今東西の音楽を知っていると感じるから信頼感を持てる。 一方でビートルズしか知らない人が「ビートルズはすごい」といえば説得力が高くはない。 いいものも悪いものも両方がわかるからこそ一番真ん中が判断できるようになる センスは知識。 フランスのブランドをデザインするのに、フォントの起源がフィンランドのフォントだとどうなのか。 そういう知識を持っているかどうか。それでセンスの良し悪しが決まる。
1投稿日: 2022.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題の通り、センスとは普通を知り、知識を蓄え予測することが大事だと分かった。何度も読み直したくなるような、とてもわかりやすい本だった。 市場調査の結果や、ロジカルシンキングだけを頼りにしてもクリエイティブなものは生まれない、これからはセンスを生かすことが大事なんだなと思った。
1投稿日: 2022.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題がすべて。センスは知識の集積。所有している知識の数が多ければ多いほど、くだされる判断の精度も高くなるからだ。表題と、知識を効率的に集めるための方法だけ覚えていればよいと思う。 美味しいトマトを買いたいとき 例) 知識レベル0:とりあえず目についた赤色が鮮明なトマトを手に取る 知識レベル1:表面に張りがありみずみずしいトマトを手に取る。 知識レベル2:張りがあり、手にとってずっしりと重く、皮にムラがなくヘタ部分が濃い緑色のトマトを手に取る。
1投稿日: 2022.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ目的 センスをみにつけたい 内容 情報にふれる 自分を知る 知識があるとセンスが磨かれる 知ろうという姿勢があるとさらに磨かれる これから
1投稿日: 2022.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルで言ってることを納得させるための一冊であった。 知識が多いほどセンスの精度が高まること、 センスは知識の集積であること、 センスが知識の集積である以上、言葉で説明できないアウトプットはあり得ないということ… 自分の仕事や暮らしに生かせそうな話や、確かにと共感できる話がたくさん。
2投稿日: 2022.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログデザイナーじゃないんで、という言い訳はもうしない。センスを磨くとは、知識を蓄えて使ってみることだとわかったから。勇気をもらった。
1投稿日: 2022.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさんのもの、それも 自分の好き嫌い興味関心如何に関わらず 意識して見て聞いて 知識と経験を蓄積していき アウトプットの練習をして 生きていきたいと思いました。
0投稿日: 2022.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://jinseilog.com/sense/ 経験からも納得 私の場合にはファッションやメイクについて、昔していたメイクは似合うよりも流行を追いかけて新作・限定を買い求めていた。 今みると昔していたメイクは若干「似合う」とはずれているなと思います。 パーソナルカラー診断や骨格診断を受けてから、似合うかどうか目安がわかるようになった。 一方でセンスの良し悪しを全部忘れて、自分の好きなおしゃれを貫くのも素敵。 場面に応じて使い分けたいところなので、それができるのは自分の似合うがわかってこそ。 アンテナを立てて興味を持つ 一見全然関係のないことがつながっているとも思っていて。 ブログをやりたいと思った時に、デザインの知識がないことでこれでいいのか?と思いながらアイキャッチを作成したり。 自分がいかにアンテナを立てないで目の前のデザインに触れてきたかということ。 興味ないことに対してもアンテナ立てていきたい。
2投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ3年前に読んだ本の再読。センスの定義「数値化できない事象の良し悪しを判断して最適化する能力」。王道を知り流行りを知って知識を持ち、共通項など分析して、普通を知り、最適化、ゴールを目指す。前に読んでいたのに忘れてました。
11投稿日: 2022.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自己啓発本の皮を被ったデザイン本。 「センスは後天的につくスキル」「センスがないから、は学びを怠っている言い訳」と切る、著者の知識の深さよ…。
1投稿日: 2022.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰にでも「なんか良い」って思うことはある。 その「なんか」を言語化するのがセンスで 言語化するためには知識が必要で 知識の習得は誰にでもできる。 これからは「センスが無いから」では許されない時代。 「センスを磨く努力をしてないから」と言われる時代。 自分も商品開発に携わっているので 水野さんの考え方を取り入れて センスのある商品を作りたいと思った。
2投稿日: 2022.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
普段の建築の仕事をする上で「センスがないからわからない」と言われることが多く違和感を感じていたが、この本に「知識に基づいて予測することがセンス」であると書いてあり腑に落ちた。 以下自分の好きだった内容を抜粋。 ・みんながへぇーと思うものは、ある程度知っているものの延長線上にありながら、画期的に異なっているもの。「ありそうでなかったもの」 ・ものをつくる人間は、新しさを追い求めながら、過去へのリスペクトも忘れないことが大切なのではないか。 ・はるか遠い未来に飛んでしまっては、消費者は未知のものへの恐怖心や違和感を覚え、ついてきてくれない。 ・「感覚」という言葉に逃げずにデザインの説明ができなければならない。感覚とは知識の集合体。 ・好き嫌いでなく例を挙げてセンスを磨く。 好き嫌いとは、客観情報と対極にあるもの。 ・センスを磨くには、センスを活用する技術を持つことも大切なのではないか。 ・「いい企画を出してやろう」と悩みすぎて時間ばかり食っているなら、自分が得意な分野から考えてみることをおすすめする。 圧倒的に楽しくて効率も上がる。
4投稿日: 2022.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログクリエイティブディレクター向けだけど、ファッションセンスも仕事のセンスも知識によって磨かれることは面白い。ファッションについて頑張って勉強してみよう。 ・日常と異なること=旅をすることで様々な経験を積んで、知識を得て、センスを磨く。 ・毎日本屋を5分で一周して、気になる本がないか、全く興味がない本を探す。
0投稿日: 2022.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
売れるものが「何っぽいか」分類していくことは大切。 斬新に見えるものも分類できる。 尖っている企画と売れる企画は違う。後から尖らせることができる。 アイディアではなく精度が大切。 ひらめきの神様などいない。 センスは身体能力と同じ。日々のトレーニングで磨くことができる。 まず「普通」を知る必要がある。 普通とは、良いものと悪いものがわかるということ。 普通を知れば、普通を基準にあらゆる位置のものが作れるようになる。 日本は現代の利休を求めている。 知識はあればあるほど自由度が高くなる 風水はもともと都市計画 しずる=そのものらしさ まずは定番、王道を知る。その過程で幅広い知識を得る。次は流行。雑誌が最適。 売るためには精度が必要。 センスとはマナー。 情報の集め方も上手くなる。 相手によってチューニングする。 良さが何なのか、細分化していく。 好き嫌いではなく客観的情報で判断。 思い込みを外す。 自分の枠組み(当たり前)を変えるために、環境を変えてみる。 普段と違うこと、方法、向きにしてみる。 初めての場所、興味のない場所に行ってみる。 剥き出しの自分になる。 先輩や年上の人を誘う。 たくさん冒険しよう。 自分のフィールドを広げること。自分がいつも感じていることだった。
1投稿日: 2022.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「確かに」と思うことが多く、よし!実行してみよう、と取り組みやすいことが書かれてるので視野が広がった気がする。
0投稿日: 2022.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
センスについて一冊かけて紐解いたもの。 センスとは知識の集合体、知識に基づいて予測することがセンスだと書かれている。 読むと「まあそうだよなあ」と思いつつ、とはいえすぐ真似しモノにできるかといわれるとあまりにも難しい。 センスについて開けたものにしているように見えて、センスの習得は誰でもできる可能性はあるが、けして簡単ではないのだなと改めて痛感した。
0投稿日: 2022.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹かれて手に取った一冊。 デザインを例にとっているものの、書かれていることは各業界、各職種に通じるものがある。 "センスに自信がない人は、自分が、実はいかに情報を集めていないか、自分が持っている客観情報がいかに少ないかを、まず自覚しましょう。" (本編より引用) もっとも刺さった一文である。 仕事で結果を出せているのは関連知識が他より豊富だからであり、自分はインテリアやファッションはセンス皆無だと思っていたのは、実はただ無知なだけであったのだ。
1投稿日: 2022.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ王道を知る 流行りを知る 共通項を探す 仮説を立てる これだけ覚えていればいいでしょう。 自分の全ての選択に対して、何となくではなく、理由付けできれば良いですね。
1投稿日: 2022.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センスは知識からはじまる」 自分も同じ考えを持った時、たまたまこの本に出会い読んでみました。 自分は、「色々知っていないとそれ以上のものは創られない」と本を読む前に考えていました。水野さんも同じようなことをおっしゃられてて、すごく共感できる部分が多く、今までにないくらい熱中して読めました。 熱中して読めたのも、「センス」かなと思いました。この本を書くにあたり、読みやすい文字のサイズや空白などを知識やペルソナなどを用いて作成されていたのかなと。 本屋で気になった本を取るという習慣、自分もつけていこうと思います。「知りたい!」を増やしていきたいです。
0投稿日: 2022.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分にはセンスが無いのかもしれない、と仕事で悩んでいた際に読みました。 センスにつきての捉え方が変わり、この本を読んでモチベーションも変わりました。 読みやすく、一気に読んでしまいました。 他の水野さんの本も読んでみたいです。
0投稿日: 2022.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは先天のものではなく、知識の集積によって生み出されるもの。仕事で思い悩んでいた時期があったが、凄く励みになった。みんなにおすすめしたい。
0投稿日: 2021.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識に基づくもので努力して身につけられるという主張は頷ける。こういう本は大抵そうなんだけど、ビジネスに近づけて説明を行おうとせず、ひたすら専門性に走ってほしいと思う(そういう本を読めばいいだけなんだけど)。
0投稿日: 2021.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは先天性のものではなく知識の集積によって導き出されるロジカルなものである事がよく分かった。普段から興味の範囲外の物に対する興味関心のアンテナを立てることの重要性を感じた。
0投稿日: 2021.12.25 powered by ブクログ
powered by ブクログテーマ自体に考えさせられると言う意味で良書。しかし、作者もまた思考の途中にあり、記述自体が個人的感覚の枠内、つまり、一意見に過ぎない。 センスとは何か。 ユニクロで衣服を揃えた若い男性でも、センス良いなと思わせる人と、そうではない人が存在する。裏付けとなる知識が説得力を増し、ある種の崩しや外しとして、錯覚させられればセンスを感じる。しかし言葉や説明が必ずしもあるわけではないので、知識が必要かというとそうではない。ワインの蘊蓄を長々喋るような人もセンスがあると言えない。知識がセンスを成り立たせるのは、一部の事例だ。 センスとは、必要十分な、適切さだと思う。 言葉のセンス、対人関係のセンス、ファッションセンス。適切か否かを判断するのは、経験であり、知識、観察力、対人思考。手作りのプレゼントは、センスがあるか。ある人には重たい、ある人には、センス輝く贈り物。 別に作者も知識の一点突破ではないが、ちょっと浅い感じがしてしまった。
0投稿日: 2021.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログわたしの大好きな「THE」や久原本家もブランディングしてはるとは!くまモンだけではない。ただモノではない…! ○アウトプットの前段階においては、知識にもとづいた方向性の決定が大切。センスを磨くには、いろいろなことを知っていることが大前提!センスは研鑽によって身につく。 ○「長年の勘で…」というのは膨大な知識と経験を備えており、それをもとに予測、判断を行なっているのだ。一連の思考プロセスを言語化するのが難しいため「勘」と答えているだけ。 ○非日常を過ごすことで、思い込みの枠を外す。それは特別な旅でなくとも良い。いつもと違うことをするだけ。行ったことのない場所に行く、違う職業の人と話す、浴槽に逆に入る…などなど。他の本で「アーティストデート」と言っていたことかな?ワクワクしながらできそう!
0投稿日: 2021.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021.10.26 107 オーディオ。 知識がセンスにつながる。普通を知ることで、普通じゃないを知る。知識を組み合わせる。どのようなものがどんな反応になるのか勉強する。5秒で選ぶようなもの。 客観性を知る。自分にあったものを選ぶ。 感受性をぶち拡げる。 幅広くなる。専門性もあれば、あらゆることを結びつけられるかも。ビートルズで全てを語るなど。世界を広げる。いろいろ聞きまくる。旅は非日常に行くこと。冒険心、探検心。 フォント、歴史、ロゴ。見せ方、売り方。ストーリー、イラスト。
0投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ尊敬するデザイナーさんから著者を教えてもらって読んだ本。 会社の先輩も言っていたシズルの話、判断を積み重ねることで主体性が養われると考えていた自分の経験とも符合することが書かれていて、自分の知識体系に照らし合わせて比較的スムーズに読み進めることができた。 何度か手に取り直して2、3周したいタイプの本だと感じた。 新しく学んだこと ・知識に基づいた判断を積み重ねる ・王道、流行、共通項 ・フォントの歴史(成り立ち)を考えて選ぶ やはりなと思ったこと ・判断の根拠を明文化する ・敢えていつもと違うことをしてみる ・違う分野の人、年上の人に話を聞いてみる 事前知識 ・感覚を言葉にしていって明確化する 「どうして美味しいのにイマイチだと思ったんだろう?そうか、手がベタベタして気持ち悪かったからだ」
1投稿日: 2021.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ2021年10月「眼横鼻直」 https://www.komazawa-u.ac.jp/facilities/library/plan-special-feature/gannoubichoku/2021/1001-10739.html
0投稿日: 2021.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログNTTドコモ「iD」やくまモンのデザインで知られるクリエイティブディレクター、水野学氏に学ぶ「センス」学。 あまりビジネス本や自己啓発本は読む習慣はないのですが、デザイン関連や好きなクリエイターの書いた本はたまに読みます。 以下、読書メモ。 ・センスとは、誰にでも備わった身体能力。生まれ持った特別なものではない。 トレーニング法さえ学べば、センスを鍛えることが出来る。 ・「センスの良さ」とは、「数値化できない事象の良し悪しを判断して、最適化する能力」。 ・センスの起源に関して。安土桃山時代の千利休はハイセンスのレジェンド。 「いいものを使おう」と訴えた18世紀イギリスの産業革命は「センス革命」 ・日本企業のクリエイティブセンスはまだ海外に比べると劣る。 どれだけ新しいスマホを作っても、iPhoneには敵わない。 技術ではなくセンスの問題。シンプルなデザイン、ユーザーインターフェイスの気持ち良い動き。ユーザーに徹底的に気持ち良さを提供しようと言うセンスが、何よりもiPhoneの魅力。 ・クリエイティブディレクターは企業の医者。 失敗を恐れず縦割り構造の会社組織に横櫛を刺せる人こそがクリエイティブディレクター。 ・センスは知識の集積。 イノベーションは知識と知識の掛け合わせであり、ゼロペースで何かを作ることはない。 ・「あ!」より「へぇー」にヒットは潜んでいる。 新しいものに接したとき、過去のものや過去の知識に照らし合わせて考えることが自然。 ある程度知っているものの延長線上にありながら画期的に異なっているもの、ありそうでなかったもの。 ものを作る人間は新しさを追い求めながら過去へのリスペクトも忘れない。 ・流行っているもの=センスが良いではない。 流行っている商品のうわべだけ真似ても競合商品にはなり得ない。 センスは知識、経験と繋がる、ということがよく理解出来たし、共感もした。 吸収しようという姿勢で知識を取り入れれば、引き出しも増えるし、それがセンスを育てる大きな武器になる。 でも、やはり、芸術やスポーツの世界などでは特に、世の中ですごいと言われる人は生まれ持った才能と言うのは確実にあるとは思う。 あと、年上の人を誘って食事に行く、とか、異業種の人と繋がって知識を取り入れていく、とかは、やっぱり人によって向き不向きもあるし、読んだ内容を全部取り入れなくても良いかな、とは思った。 (こういうビジネス本は、いいとこ取りだけして、結構飛ばし読みしてます) 水野さんが共同運営する、商品の定番を揃える「THE」というブランドに今後着目してみたいと思った。 ジャンルが違えど、定番と言われる商品には、共通した「強み」があるはず。 丸の内KITTEの「THESHOP」でその商品が見れるそう。何気なく見ていたけど、今後改めてしっかり見てみよう。
0投稿日: 2021.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ水野さんの本はなによんでも当たりのものが多い気がする。グッドデザイン賞をつくったデザイナーがセンスとはなにかを語る本。タイトルの通り、センスは知識である。センス=先天的に得られる才能のニュアンスで語られる言葉が多いけど、知識をつけることで自分なりのセンスを身につけていけるようになるんだよ、という目から鱗なお話でおもしろかった
0投稿日: 2021.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ題名通りの本 "センス"と言う抽象的な言葉を論理的に説明されていて、腑に落ちた ●普通を知ること ●技術がピークを迎えるとセンスの時代がやってくる ●センスとは知識の集積 ●はやりを知る ●共通点や一定のルールを知る
0投稿日: 2021.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ見せ方・アウトプットの作り方は感覚ではなくて知識を総動員して狙うもの、という考え方がとてもわかりやすかったです。 もともと美術やデザインも興味はあるが彼岸のものという感覚もありましたが、自分に近いところにあるんだなというのがよくわかりました。 なんのためにどうやって知識量を集めるのか?というのを読みながらわくわくしました^^
0投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「え?ホント?」という本のタイトルがそのまま本の主題になっていて、「なぜ知識なのか」の理由が具体的事例を交えながら書かれている良書。 知識を得るために必要なのはとにかく調べること。知識を得る努力を日頃から続けること。 センスは生まれ持ったものではなく、ひらめきが降りてくるようなものでもない。 限られた人だけが持っている、手の届かぬ才能ではない。 徹底して調べ尽くすこと。その量が著者は一般人の比にならない。 それをわかって、できるかできないかが差を分けるのだと感じた。
1投稿日: 2021.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
自分を「センスない」と思っている社会人には是非読んでほしい内容だった。 特に企画書などを書き始めた人にとっては参考になる進め方が書かれていた。また社会人としての「仕事や知識への前向きな姿勢」が強調されており、忘れかけていた初心を思い出すビジネス本でもあった。 途中、ゴレンジャーやリネンの話は筆者本人の経験中心のためピンと来ない部分もあったが、総じて「センスのよい仕事、成果物を出したいが出せていない」と悩む人にとっては良書だと思う。 ※具体的な調査方法だったりイメージだったりのクオリティアップをしたい人にとっては物足りないかも 最後に私がいいなと思った文言をいくつかメモ ・センスとは数値化できないものの最適化であり、普通を知ることが大事 ・過去の知識が新たなアイディアに役立つ、知っているものだけどなかったものがセンスのあるもの ・知識を増やすには「王道を知る」「流行を知る」「共通項やルールを考える」 ・日常から離れる旅をしてみる ・感受性+知識=知的好奇心
0投稿日: 2021.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログデザインを作り出す力を向上させたい目的があった自分に適した良書。 具体的には自分は感覚でロゴを作ったりしていたが、それだけではなぜその形にしたのか?を説明するのに限界がありました。 そもそも、感覚だけでは作る幅が狭くなりがちで、そもそも美的センスが偏っていることもあり、些細な表現の良し悪しもわかりませんでした。 そのため、私に必要な要素は感覚の反対である「論理」でした。 「論理」こそが、感覚だけの私を成長させる要素だと思えたのです。 そこでこの本の一節、「まず、普通を知ること」が参考になりました。 普通=王道とされているデザインやものを扱う、知る。 それも知識を得れば得るほど知識は増えていく。 そうした知識がセンスを磨くことに繋がり、良し悪しを見極める審美眼が身についていく。 感覚派の自分が論理的になるために必要な要素は、知識にあることを教えてくださった内容でした。 私が読んだ経験から以下の人にお勧めできそうです。 1.美術における「センス」とは何かを具体的に知りたい方。 2.感覚でデザインを作っている方。 3.美術にコンプレックスがある人で、それを克服したい方。 以上となります。
0投稿日: 2021.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログp.18 「センスのよさ」とは、数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力 良し悪しを測定するには「まず普通を知ること」が必要 普通=良いものがわかり、悪いものがわかり、その両方を知った上で「一番真ん中」がわかること p.74 「センス」=「知識の集積結果」 センスが良くなりたいなら普通を知ることが必要 普通を知る唯一の方法は知識を得ること p.79 過去に存在していたあらゆるものの知識を蓄えておくことが、新たに売れるものを生み出すために必要不可欠 p.84 「ありそうでなかったもの」=ある程度知っているものの延長線にありながら画期的に異なるもの p.88 知識に基づき予測をする⇒センスを磨くことにつながる p.92 センスの最大の敵は「思い込み」と「主観」 思い込みを捨てて客観情報を集める⇒センスUP p.98 「流行っているもの=センスがいいもの」ではない p.102 効率よく知識を増やす3つのコツ 1、王道から解いていく 2、今、流行しているものを知る 3、「共通項」や「一定のルール」がないかを考える p.119 「感覚的にこれがいい」は禁句 センスが知識の集積である以上、言葉で説明できないアウトプットはNG p.153 好き嫌いで判断するのはNG 好き嫌いは客観情報とは対極にあるもの 「誰が、どんなときに、どんな場所で使うのか」というように対象物を具体的に思い浮かべて議論すること p.168 センスを磨くには知識が必要だが、知識を吸収して自分のモノとするには「感受性」と「好奇心」が必要
0投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは研鑽によって誰でも手に入れられる。感覚は知識の集合体。といったことが繰り返し述べられています。 ものを作れば(ダサくても)売れた高度経済成長期と異なり、今はデザインやセンスの力が必要だなと日々感じている。娘が少しでも生きやすくなるためにも、いろんなものに日々触れてほしいなーと思う。
0投稿日: 2021.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは数値化できない事象を最適化すること。 「普通」を知ること 知識を得ることでセンスは磨かれる 1、王道 2、流行り 3、共通項のステップで効率よく知識をインプット シズル感の最適化 企画書は読み手に価値を伝える手紙 新しい感性を大切に
0投稿日: 2021.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、タイトルで言ってることを思ってたので読んでみた結果、「やっぱそうですよねー!」ってなりました。 センスがある、ってその物事に関したことを知ってて、それを応用できるから、初めてでも「比較的質の高いアウトプット」が出せるんだと思います。 「あれはあーだから、これもこーしたら上手くいくんじゃない?」的な。
0投稿日: 2021.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「くまモン」などの数々のヒット商品を手掛けたグッドデザインカンパニー代表、水野学氏による著作。 私は自分がセンスの無い人間だと思っている。何をやってもダサいと。 本書のタイトルを見て、「えっ、センスは知識からはじまるってことは勉強すればセンスは磨けるの?」と思って手に取った。学校の勉強は主要科目はコツコツ勉強すればいい点が取れるけど、芸術系や体育系などの副教科は天性の才能が影響し、持って生まれたセンスのある無しによってどうしようもないものだと思っていた。だから、センスと知識はどちらかというと相反するものだと思っていた。 著者がクリエイターとしての経験や学生に教えた経験から述べられているには、「誰も作ったことのないようなものを作ろう」として、ゼロから良いものが出来ることは殆ど無いということ。ヒットする物を産み出すには、「普通」や「王道」を良く知り、そこから今、プラスアルファ何があれば売れるだろうと考えることだという。だからといって、むやみやたらと市場調査をしても意味はなく、市場調査に頼りすぎるのが「日本人はセンスが無い」と言われる一因だという。 要はセンス良くなるためには常にアンテナを張り、人の話をよく聞き、常に勉強し、やったことのないことを時々してみたり、話したことのない人と話してみたりして、自己研鑽すること。「私はどうせ、センスが悪い」と俯いてばかりいてもセンスは悪くなるばかりだろうと思った。 ただし「流行っている=センスが良い」ではないから、むやみやたらと流行を追う必要は無い。けれど、「王道を知る」のと同時に「流行っているものを知り」「それらの共通項や一定のルールがないか考える」ことは大切だ。流行を追うことは疲れると考える私にとって、流行も含めてもっと高いところから見渡すことが必要だと分かり、ボチボチやってみようと思った。 講演会で聴いたら良い話だと思った。ただ、この本自体、あまりにもスルスルと読めてしまったので、書籍としては物足りなかったかな?
20投稿日: 2021.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ【もうセンスがないからできないなんて言わないよ、ぜったい】 「センス」は知識で身につける「スキル」である。という問題提起をテーマに書かれた本 「センスは選ばれた人が持っている特別なもの」みたいな感覚を持っている人は多いと思うが、著者によればセンスとは特別なものではなく、知識の集積による判断基準(スキル)だと定義しているところが非常に面白く、また論理的に説明しているのが納得できる。 例えば、「ファッションセンスが良い人」は長い時間や多くの経験をファッションの研究(服の組み合わせや雑誌の閲覧)などに費やしているため、良い組み合わせが瞬時に判断できるようになっている。 悪いー普通ー良いを判断できるほどの知識の集積の有無がセンスの有無となっている、というのが論理的で面白い。 「センスがないから…」と諦めて手付かずになっていることがある人には一度読んで欲しい。 ネガティブな思い込みを外すきっかけになる本だと思う。
1投稿日: 2021.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは、知識の集積によって、だれにでも手に入れることができるってわかった!知識の豊富さが大事。 センスがない、これはできない分野、って決めつけずに、まずはそのことについて進んで情報を得て自分の知識にしていこ〜 コミュニケーションは話す以上に聞く力が大事。 好きなことのマインドマップも作ってみよ〜〜 メモ✍
0投稿日: 2021.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ[江東区図書館] 息子の先輩が興味を持ったのでどんな本かと追読。 漠然と予想していた本とは趣が異なり、ドコモの「iD」m熊本県公式キャラクターの「くまもん」などを生み出した、「日本を代表するクリエイティブディレクターによる発想法と仕事術」だった。 ただ、Part3の題名は自分の認識に近く、その点からは読んでいて興味深かった。 また、「ひらめきを待たずに知識を蓄える」などの知識という土台ありきでの「普通」や「流行」などを知った上でのひらめき、決定というのは読んでいて感覚的すぎずに良い。たとえ感覚的に感じたとしても、その「理由」を突き詰めて体系化しようという姿勢には共感を感じた。 ■Part1 センスとは何かを定義する ■Part2 「センスのよさ」が、スキルとして求められている時代 ■Part3 「センス」とは「知識」からはじまる ■Part4 「センス」で、仕事を最適化する ■Part5 「センス」を磨き、仕事力を向上させる
0投稿日: 2021.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ膨大な知識から『売れる』仮説を作る。ヒット商品は闇雲に当てずっぽうに閃いてるわけではない。という主旨。 凡人な私からすると、その『売れる仮説』がもう既に『センス』であり、仮説すら思いもつかない場合はもうどうしようもない。 仮に仮説を思いついたとて、果たしてそれが正解なのか自信が持てないだろう。 つまりはその仮説がそもそもセンスなのであって、言い換えれば、想像力やイマジネーション、発想力といったところだろうか。 これらをふまえ、子育てにおいて ・自分で考えることができる ・想像力や発想力をフル稼働できる ・かつ膨大な幅広い知識と経験 が未来に活躍できる子供を作るのかもしれないなどという考え方湧いた。 しかしやるべきことが多すぎて、今どきの子供たちも大変なもんだと思い至る。 まさか見当違いな子育てにまで想像が及んだということは、刺激的な本だったのでありましょう。
0投稿日: 2021.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスに自信がないので手に取りました。主旨はタイトルそのまま。学校教育での音楽や美術の扱いについて触れていて、著者の主張に納得しました。 自ら学ぼうという気持ちの背中を押してくれる1冊。読んでよかったです。
0投稿日: 2021.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ☑️企画書をつくるセンス ☑️営業するセンス ☑️もの選ぶセンス 色んなセンスは元々持ったものではなくて、知識で作ってくものだという『気づき』を得られる本でした。 どんなことでもやはり『勉強』すれば出来るようになると再確認できたような気もしました。 センスというフワッとしたものを体系的に理解できた気がします。
1投稿日: 2021.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは無から生まれるのではない。 知識によって与えられた選択肢の中から、“それらしいもの”を選ぶ。 こうしてピタッと当てはまるものがセンスである。 「センスが良いお店」も「センスが良いパッケージ」も「センスが良い服装」も、雰囲気やシチュエーション、人にピタッと一致しているから。 センスとは独創的なものだけを意味するのではない。 王道を知り、両極端も知り、幅広い選択肢の中からピタッとくるものを選べるかどうか。
1投稿日: 2021.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前に読んだ「世界観をつくる 「感性×知性」の仕事術」でとても気になった水野さんというデザイナー(アート・ディレクター)。 という訳で、水野さんの本も読んでみました。 ※世界観をつくる 「感性×知性」の仕事術 https://booklog.jp/users/noguri/archives/1/4022516739#comment 水野さんという方、センスやらデザインとやらふわっとした言葉を言語化するのがとても上手。 一部のプロの専売特許なようなこの概念を 素人でも分かりやすく紐解いてくださいます。 これは助かる! センスってベースに知識があるのか。。 全く考えてもいなかったです。 途中出てくるデザイン例やフォントの話の中で、 挿絵的なものがあれば、もっと読みやすかったですが(あまりに気になって画像検索してしまった)、 それも著者のデザインなのかもしれませぬ。。 (よく分からんけど。) ますますデザインについて勉強(そして、実践)したくなる1冊です。
6投稿日: 2021.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログデザインする仕事とかではないけど、 ものを見る捉え方の幅が広がりました! すごく、わかりやすくてよかった! なるほど、こういう仕組みで世の中のものは生み出されていて、芸術とかの歴史だけじゃなく、色んなことがずーっと時代が変わっても繋がってるんやなあってわかって、おもしろかった! 色んなことを自分でも発見して、活かしていきたいと思えました!
0投稿日: 2021.02.07
