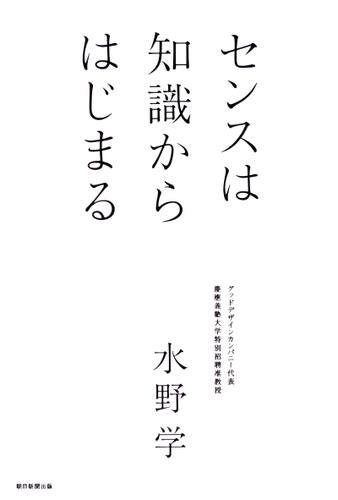
総合評価
(403件)| 91 | ||
| 161 | ||
| 93 | ||
| 12 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、大前研一の本で読んだ「センスは訓練で磨かれる」という言葉によく似ていて手にとってみた。多摩グラ出身でセンスの塊みたいなプロフィールの持ち主である著者がこのように書いてくれると、理屈っぽい僕にも大変分かり易い。 ■センスとは数値化できない事象を最適化すること ■歴史が上手いね、下手だね と言わないのと同じように、美術に上手いも下手もない ■技術の時代からセンスの時代への揺り戻し ■アウトプットの前段階では、知識に基づいた方向性の決定が大切 ■売れるものをつくるには消費者を欺かないための精度が求められる ビジネスにもとても役立つ考え方がたくさん紹介されており、どんな分野の仕事でもベースになる考え方の大切さを痛感させられる。
0投稿日: 2025.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスの本は3-4冊読んだが1番ロジカルに、かつ経験をもとにされているのでわかりやすく、スッと入ってきた。 特に代官山のオフィスを決めた際のエピソードが心に残っている 王道を知りながら自分に合うものを取り入れたい
0投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「普通を知ること」それは知識でしか得られないし、普通を知らないとセンスあるとかないとか分からないよなって共感。 美術の話が面白かった。学校の美術の授業は座学は無くて全部実技だからセンスで評価されてしまう。そのセンスの知識を座学で教えてくれたら良いのに、全く教えてくれないから自分は美術の評価だけ低かったの納得いかなかった。そういうことだったのかと共感した。 センスの授業あればいいな。
0投稿日: 2025.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的に下調べや練習をしたうえで本番に挑む、下準備&計画的人間な自分にとっては、すごく納得感のある内容だった。 自分の実力を把握して、足りない部分を補い、本番(本書でいうアウトプット)につなげるという行為に改めて自信持てた。 個人的にはセンスが歴史的に見てもいかに重要であるかを語るために、近代史に触れられていた部分が面白かった。 ただ、センスは重要である一方、実際にものが売れるための要因としてはささいな要素に過ぎない。全国的・世界的な規模のいわゆる大ヒットは、「売れるまで売る」という企業努力と企業忍耐に支えられている、という視点も現実味があった。 ただ2014年発行なので、IT感覚はちょっと古かったかな。 _______________ *以下自分用まとめ ●センスとは 数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力。他者からも同じく数値で測られないため、結果的に相対評価で判断される。 ●センスを磨くために ⓪まず必要な要素 あらゆることに気がつく几帳面さ、人が見ていないところに気がつける観察力 ①知識を増やす 良し悪しの基準となる「普通=定番王道、流行(一過性のもの)」を知る ② アイデアの土壌を作る 「普通」に共通項や一定のルールがないかを考える ③アウトプット 今あるものから進化した形へとアウトプットしていく ④さらに精度を高めていく ●センスを磨く際の注意点 ・最大の敵は思い込みと主観性。そのフィルターを通して得た知識をいくら積み重ねても、センスは良くならない。 ・ガラパゴス島に閉じこもって生きている自分を自覚する。 ●センスを上げるための日常的工夫・活用アイデア ・自分と全く違う職業の人と話す ・興味ない分野を覗いてみる 例:本屋を5分で一周して気になるものを手に取ってみる、いつも見ない本棚も眺めてみる=知的好奇心の扉が開かれる ・雑誌を眺めて、レイアウトやフォーマットから学ぶ ・企画を考えるとき、自分の得意分野(どんな狭いものでも)に結びつけて考える →楽しいし効率も上がる ●マーケティングにおける落とし穴 ・自分が見たものも、聞いたことも、触ったこともないものをいいと言う人はほとんどいない。 ・現状を100とすると、精々101、110ぐらいになったものをみた時、多くの人が「新鮮だ!欲しい!」と思う。 ・「あっ!」(=「え?」)より「へぇー」(=「ありそうでなかったもの」)にヒットは潜んでいる。 ・つまり、全く新しい製品より''現状より少しレベルのあがった''ものの方が良い反応を得やすい。 ・マーケティング手法としての市場調査では、この結果が得られやすい。しかし、これでは''新しい価値''は創造できない ・市場調査に頼っていると、「自分は何がいいと思い、何が作りたいのか」を自分の頭で考えなくなる(=他力本願)。結果「さらに良くしよう」という向上心を弱めてしまう。 ●日本企業に欠けているもの 「ユーザーに''徹底的に''気持ちよさを提供しよう」というセンス(=追及力?) ●美術について ・『アーツ・アンド・クラフト運動』 日本では1926年に起こった、日用品の中に美を見出そうという民芸運動 ・美術にも体系だった知識が必要(色相環に基づいた色の使用など) ・思い込みを捨てて観察してみることも大切(植物や動物の色、形) ・美術の歴史や知識を学ぶと、日々の選択(ファッション、インテリアなど)に自信を持てるようになるかもしれない ●用語 『ブランド化』 よさが伝わるように、ちょっと情報整理してあげること 『クリエイティブディレクター』 ブランドプロデューサーにイメージ近いかな 『グラフィックデザイン』 賞品や起業の「広告」というごく一部だけに携わるポジション。だが、商品企画も売り方も店頭での見せ方も、全部をトータルにつくりあげていくほうが結果につながるんじゃないか。 →自分もそういう風になりたい! ●デザイン知識メモ ・まずはスクエアに要素(文字や写真)を置いてみて、基本配置から崩していくことで面白さや躍動感が生まれる ・上下左右の余白は統一 ・文章の並びはどこかの行だけ飛び出ず揃える ・文字を普通に入力しただけでは文字間の余白は一定ではないので、余白が均一に見えるように微調整する「文字詰め」 ●その他と感想(本筋と関係のないもの) 「すべての仕事は価値を想像していくことで対価を得ています」 「人間という生きものは、自分のいる場所を肯定しないと生きづらいもの」 「時代は、次の利休を探しているのです」 →今は選択肢が多くて豊かで、個人が尊重される素晴らしい時代だけど、逆に基準がぼかされて善し悪しの判断が簡単にできなくなった。 百0の基準を作ることは前時代的であるのは間違いないけど、明確な基準があった方が楽、生きやすいという感覚はあるよなぁと。 「学校にもセンスを教える授業があったらいい」 →これは現実的じゃないかな。 土台となる客観情報の集め方を教えるのに効率的、と筆者は言うけど、客観情報にそぐわない個人を否定してしまうことにつながりやすいと思う。 センスUPの底上げにはなるかもしれないけど、個人尊重が重んじられる現代の学校では厳しい。
1投稿日: 2025.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログAudible で聴きました。センスのせの字もないんだよなぁと自分のことを思っていたけど、あぁ知識に向かう姿勢が違うんだと気づきました。そこから他の本も読み始めて、今は美術に関して興味も持っています。 子供ながらの好奇心も忘れずに自分のペースで興味を深めていきたいです。
5投稿日: 2025.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今、読んで本当に良かった本。 最近本の引き寄せが強くて(笑)運が良い。 私は基本的にクリエイティブ欲は一切なく、 人の話を聞く、一緒に考える、サポートする、ということに大きな悦びを感じるタイプの人間なので、 この本はご縁が無いかな~なんて思っていたけれど、読み進めていたら、そういう人の方がむしろ伸びるよって書いてあってなんだか嬉しかったな。 まさに、なフレーズが2箇所大きく出てきたので、読書ノートに必死で書き写した。 書いてあることは大枠はタイトルの通りの繰り返し(笑)で、とにかくセンスっつーのは先天的なもんじゃねぇからな、知識だからな、努力しろ、吸収しろ、天性とかそんな甘ったれたもんじゃねぇぞっっ、ってずっと作者が喝を入れてくる(ように私は受け取ったw)本。 中盤で、同じことが繰り返されるから、こりゃ途中で飽きるかな…と思った矢先に、ファッションや奥様の具体例が来たので、引き込まれて読み切ることができた。 数値化できないファッションセンスは、自分を客観視すること。この本が書かれた2014年は、まだまだその客観視が体系化されていなかったが、 今は骨格診断とパーソナルカラー診断、顔タイプ診断が随分日本で浸透し始めた時。まさにだな、と思う。 自分なりの強みを活かしながら、この体系化された技術をモノにして、私らしい「センス」を仕事として確立してみせる、と覚悟ができた本。
0投稿日: 2025.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスという、目に見えないモノについて考えたくて読んでみました。 センスは生まれつきのものではなく、後から身につけられる(ただし、本人の努力次第)ということがわかりました。 そしてセンスとは、一個人の感覚ではなく、必ずロジックがある。 だからこそ、机に向かう勉強ではなく、“学ぶ姿勢”さえあれば、誰でもセンスは磨けるというのです。 “センスは知識の集積である。” この本では、このフレーズがすべての核になっています。 情報をどう集め、どう扱うのか。 プロの視点から「センスを磨くための情報の扱い方」が具体的に語られていて、例えもわかりやすく、すっと頭に入ってきます。 印象的だったのはこの言葉。 “普通こそ、「センスのいい/悪い」を測ることができる唯一の道具なのです。” 「普通って何?」と思う方も多いはず。 でも、この本には“普通”の定義や、その見つけ方も丁寧に説明されています。 普通を知るためには、さまざまなものに好奇心をもって情報を集めること。 大人になると子どものような好奇心を持ち続けるのは難しいけれど、その心構えについても書かれています。 情報を集めたあと、「なぜそれを選んだのか」「なぜ選ばなかったのか」をロジカルに考える。 そのためには、知識――つまり“自分でかみ砕いて血肉にした情報”が必要になります。 センスは一朝一夕で身につくものではありません。 日々アンテナを張り、勉強を積み重ねる努力が必要です。 日常の努力がセンスの良さをつくる。 つまり、センスのある人とは、努力を怠らない人なのです。 やらなければ磨かれない。 言い換えれば、センスの差は努力の差でもあるのだと気づかされました。 読むほどに、文章そのものにも「センス」が感じられました。 きっとそれは、言葉の選び方や構成にもロジックがあるからだと思います。 そう考えると…センスって、もはや生き方そのものなのかもしれません。
37投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章が柔らかい感じがして読みやすかった。作者はセンスを先天的なものではなく知識の集約から作り出されるものと捉えていた。デザインの世界やマーケティングの話は自分の仕事とは全く関係がなく、実務に役立てられるかは分からないが面白かった。根性論ではなくて体系的に、番人に向けてセンスの磨き方を教えてくれている。基本的にデザインやビジネスのセンスの話が多かったけど、水野さんは文章についてもセンスがある人だと感じた。
5投稿日: 2025.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ美術の授業で画家の歴史や作品を深堀り (歴史でその人物について学ぶように、美術もそれと同等のことをするべきでは?) 構図や色の知識。 美術の授業ではそういった知識ではなく、とにかく手を動かす、作業するといたことしかしない。そこで「センスの良し悪し」を決めてしまうのはおかしい。 センスは数値化できるものではないからこそ、客観情報が大切。 客観情報を集める⁼センスを良くする大切な方法。 センスの最大の敵は思い込みであり、主観性。 好き、嫌いは主観を外し「どれが相応しいか」という客観性。 センスの良さと情報量の多さは比例する。 どれだけそのことについて考えたか。情報を得たか。(センスは先天的なものや才能ではなく後天的なもの。) センスを磨くには? ①王道を知る。 ②今、流行しているものを知る。 ③共通項や一定のルールがないか考える。 全ては基礎、原則、ルールが前提。基礎知識があるからこそ応用が効く。 デザインを「好き・嫌い」で判断しない。 検索すればすぐに答えが出てくる世の中だからこそ、本質を見極める目を養っていきたいと思った。 (みんながいいって言ってるからではなく、自分のポリシーを持って判断する) いつもとは違うことをしてみる。 日常から逃れること⁼非日常 「デザインはセンス」「才能」だと思っている人こそ読んでほしい一冊。
0投稿日: 2025.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館で借りて読むうちに、あまりにも面白く。 この内容をぼんやり忘れていってしまうのは勿体ない!!と思い、改めて書店で購入しました。 センスとは何か?生まれ持った才能とか、備わっているもののように思いますが、 タイトルにあるとおり、センスとは知識から始まる。 『知識が紙の大きさで、センスが絵だとしたら、紙が大きいほうがのびのびと絵を描ける。』 そんなような表現で説明されていましたが、この本を読み終わった時に僕は、努力すればセンスも手に入れることができるのかも!と自信をもらうことができました。
7投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読。センスは知識であるとは、厳しいながらも希望のある言葉だ。もしもこれをもっと若い時に知っていれば、と思わないでもないけれども、そんなことを言っていたって時間は戻ってこないし、いまできることをして知識経験をためて、自分の中のセンスというものさしをチューニングして行くしかないのである。 それと、以前読んだ時はそこまで気にならなかったけど、見た目のデザインが整っていることがいかに大切か、というのを改めて気付かされた。見た目が洗練されているかを無意識のうちに人は見ているのだと。大事にしなければならないな。 定期的に読み返して、気を引き締めていきたい。
0投稿日: 2025.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは生まれつき備わっているものではなく、知識に基づいたものであるーーというのが本書の主張は明快で、とても印象的でした。 たしかに、知識が経験があることについては、自分でも評価ができるし、「センスが悪いから」と諦めることも少ないなと気づかされました。 もちろん、知識を集めるだけで実践が伴わなければセンスのある仕事はできないとは思います。しかし、センスが努力によってセンスは磨けるものだと知り、とても励みになりました。 今後は知識を集めることも意識して、日常的にセンスを磨いていきたいなと思いました。
1投稿日: 2025.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
著者の本は初めて読んだが、要所要所に人柄がにじみ出ているように感じた。 著者は 多くの センスに飛んだ作品を世に出してきた実績があるが、それを鼻にかけることもなく、どの人もたくさんの知識を身につけることによってセンスなるものを習得することができると本心から訴えたい気持ちが伝わってきて胸を打たれた。 私の周りの最もセンスがあると思う人も知識の泉であり、著者の考え に大いに納得した。実践法も現実的で大変参考になった。
0投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスが良いというのはどういう事かを言語化した本。知識をつけることや、普通を知ること、尖らなくても少し新しさを付け加えるだけでもセンスは良くなる。 自分が何かを企画して運営する際にプロデュースの視点をもって考えられる本。 感受性+知識=知的好奇心
0投稿日: 2025.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初めはセンスは才能で感覚的なものだと思っていた。しかし、さまざまなジャンルの知識を蓄えることによってセンスは磨かれることを知り、センスゼロの私でも少し希望の光が見えた。 しかし、知識をつけるために学習しても、右から左に抜け落ちて行っては意味がないから、知識を定着させることも考えなければならないかも知れない。 ・センスは生まれつきではなく、知識を蓄えることで誰でも磨ける能力 ・「普通」を理解し、良し悪しの基準を持つことあるセンス向上の第一歩 ・王道と流行を学び、それらの共通点を見出すことで、自分のセンスを言語化・体系化できる ・継続的な知識の積み上げが、創造的なアウトプットと予測力(センス)を育てる
1投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識の集積でセンスは磨けるもの 基本的に言いたいことはそれだけ わかる気がする 私の場合インプットはめちゃくちゃするのだけど 知識を引き出すことが限定的になる どうしても分野?の壁を取っ払って考えることができない 頭が固い感じ どうすれば?それを教えてほしい…
0投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログマーケティングに囚われないこと、通勤ルートを変えたり歯磨きする時違う歯から磨くなど非日常を体験するなど、センスを磨くコツについて載っている本。センスとはなんだろうと壁に当たっている人に。
6投稿日: 2025.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスという言葉を抽象的なものと感じており、"センスが良い"という状態について納得のいく定義をするのもが出来なかった。 この本には「センスとは数値化できない事象のよしあしを判断し、最適に運用する力」とあった。そしてセンスというのは個人の内在的な特徴ではなく、後天的に取得可能な能力であることもわかった。 自分の選択に対して、明確な理由を付与する;この服が何となく似合いそうではなく、自分の体型や着ていくシチュエーションに対してどういった理由でマッチするのか、という具体まで考えることでより自分のセンスが測れるようになる。 そして、センスを後天的に取得するには知識の取得が必要で、自分のフィールド外から取得しに行く姿勢が、+αとして求められるということも理解できた。 よい推察を引き出すには対象分野のみならず全く関係の無いことからも着想(アプダクション)が得られるということは別の書籍で読んでいたので繋がったように感じた。
0投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログセンス、欲しいなっていつも思っています。 洋服選び、インテリア選び、人に何かを説明する時、お料理する時、 ああ、センスないなぁってしょんぼりするから。 「センスがいい文書を書くには、言葉をたくさん知っていたほうが圧倒的に有利である。これは事実です。 文章というたとえを使いましたが、これは仕事や生きるということにおいても同様だと思います。知識があればあるだけ、その可能性を広げることができるのです。」 「センスの最大の敵は思い込みであり、主観性です。思い込みと主観による情報をいくら集めても、センスはよくならないのです。」 「思い込みを捨てて客観情報を集めることこそ、センスをよくする大切な方法です。」 「センスを磨く上で、好き嫌いでものを見るのは禁物です。好き嫌いとは、客観情報と対極にあるものなのですから。」 「そんな思い込みを外す方法とは、いつもと違うことをしてみること。」 「やったことがないことを試してみましょう。」 「見たことのないものを、意図的に見ましょう。」 センスは知識を学ぶことで、養える能力なんだ! そんなことをわかりやすく、丁寧に教えていただけ、なんだか勇気と希望がわいてきました。 あえて、興味の範囲外のことをやってみる。 好きなことをとことん深掘りしてみる。 いろんな学びが自分の武器になる。 センスを磨く努力、頑張ってみよう。
15投稿日: 2025.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ・必ずしも「尖った企画=売れる企画」ではない。企画はアイデアではなく「精度」が重要。ちょっと面白いアイデアを緻密に改良すれば尖ったものにすることが出来る。 ・「センスの良さ」とは、そのシーン、その時一緒にいる人、自分の個性等に合わせて良しあしを判断して最適化できること。良いもの、悪いもの、その一番真ん中を知ること。真ん中(普通)を知ることが出来れば何でも作れる。 ・美しいという感情は未来でなく過去に根差す。技術とセンス、機能と装飾、未来と過去、この対を時代は行き来している。過去を知ることはセンスを磨くうえで重要。 ・市場調査至上主義ではせいぜい100が101になるような改善しか生まれない。市場調査をベースに会社の総意として他力本願で動くのは危険。 ・センスを磨くためにはあらゆることに気付く几帳面さ、人が見ていないところに目が行く観察力が必要。良いセンスを維持することも向上することも研鑽が必要。ひらめきを待たず、知識を基にした方向性の決定が重要。 ・イノベーションは知識と知識の掛け合わせであり、世の中に既にあるAと自分が見たことのあるBをくっつけてCというイノベーションを創出する。そのためにD,E,F、、、という知識を蓄えておく必要がある。「あっ」よりも「へえ~」にヒットは潜んでいる。 ・「へえ~」と思う「ありそうでなかったもの」はある程度知っている延長線にありながら画期的に異なる。新しさを追い求めながら過去へのリスペクトは必要不可欠。 ・自分自身の経験、社会知、感覚を取り出す。人種、時代、性別など自分の属性に基づく知識を重ね合わせて正解にたどり着ける。正解だと思っても「この感覚はどこから来たのか」を徹底的に確認する。 ・「誰が、どんな時に、どんな場所で使うのか」を思い浮かべることはセンスを最適化するために最も必要な三原則。 ・思い込みは敵。非日常を自ら作り出すことで思い込みの枠を外す。
0投稿日: 2025.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・「センスのよさ」とは、数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力である。 ・クリエイティブディレクターは企業の医者である ・ひらめきを待たずに知識を蓄える ・誰も見たことのない、あっと驚くヒット企画:2%、あまり驚かない、売れない企画:15%、あまり驚かないけど、売れる企画:20%、あっと驚く売れない企画:63% ・技術とセンス、機能と装飾、未来と過去の行ったり来たり ・もしチョコレートの商品開発担当者になったのなら? ・福沢諭吉って、スゴイよね
0投稿日: 2025.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは生まれ持ったものではなく定番をよく知って次に流行を知って共通点を見つける努力をすることでセンスは磨かれるらしい。 ※水250mlを冷たくひやしたグラスに氷をいれて水を入れレモン果汁を加える。はたまたマグカップに常温のまま水をいれただけ。同じ条件の水でも雲泥の差。
0投稿日: 2025.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ普通を知ることが大切 普通とはいいものがわかるということ。 悪いものがわかるということ。 センスを磨くステップ 王道を調べる(過程が大切) 流行りを調べる 共通項を見つける
0投稿日: 2025.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
10年前の本なので現在では当たり前に考えられている話も多いが、改めて自戒することもでき発行当時色々な人が進めていたのもよくわかる1冊であった。(当時は忙しすぎて読めず…) ・センスのいいものを作るには「普通」がわかることが大事。普通が分かれば、「いいもの」と「悪いもの」もわかる。 ・「技術」がピークに達すると「センス」の時代が来る ・「美しい」は過去に根ざす。ノスタルジー ・知識はこうして増やす (1)王道を知る、(2)流行しているものを知る、(3)集めた知識の共通項やルールを探す
0投稿日: 2025.04.13 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは何か?という答えを答えられるようになりたいと思いこの本を読みました。 内容は、センスは生まれ持ったものではなく様々な知識の上になりっていることをわかりやすく説明されていました。 センスがいい人になるために憧れるだけでなく、今後も本を読んだりやったことないことへチャレンジしたりして、知識・経験を増やしてセンスがいい人に近づたらと思います。
12投稿日: 2025.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは何かをわかりやすく説明している。ズバリ、タイトル通り、日頃からの知識の積み重ねが大事。使用するフォントの歴史的背景まで考慮に入れているのは驚く。
0投稿日: 2025.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センス」が欠如している現状を打破すべく読む。 佐藤卓「塑する思考」と内容が近い。 以下のような流れで日常で接することや物と対峙すると、全ての経験が旅のようになり、いろんなものに愛着を持つことができる。そしてそれがセンスになり、自分を助ける。 ①外界との扉を開ける ②自我を捨て、客体をありのままに受け取る ③良し悪しなど自分なりの価値判断をつける
10投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『センスは知識からはじまる』は、センスという一見捉えにくい才能を、実は「数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力」として捉えています。 私自身、この本を通じて、センスは単なる生まれつきの才能やひらめきではなく、知識の集積と経験の豊かさから育まれるものであるという考えに深く共感しました。 センスの定義と実生活への応用 本書では、ファッションを例に、「おしゃれさやかっこよさは数値化できないが、シーンや自分の個性に合わせて服装のよし悪しを判断し、最適化することはできる」と説かれています。 この視点は、私たちの日常生活における選択や判断にも通じるもので、たとえば、仕事や人間関係においても「普通」という基準―良いと悪いの中間地点を知ること―が、より良い結果を生む鍵となるのだと感じました。 普通という感覚の重要性 「普通」という感覚は、本書の中で重要なテーマのひとつです。 著者は、商品開発などの場面において、「普通じゃないアイデア」を無理に追い求めるのではなく、まずは「普通」が何かをしっかりと理解することの大切さを説いています。 普通が分かるということは、結果として良し悪しの判断基準が明確になること。 これは、どんな分野においても、成功への土台となる重要な視点です。 知識の集積が生み出すセンス また、著者は「センスとは知識の集積である」と力説します。 仮に「あいうえお」しか知らない人と、「あ~ん」まですべて知っている人を比較すれば、後者の方が遥かにセンスのある文章やアイデアが生み出せるという例え話は、非常に印象的です。 iPhoneやAKB48も、過去に存在していたものの延長線上にあるという考え方は、既存の知識や経験の積み重ねが、新たな創造の源になることを如実に物語っています。 総評 『センスは知識からはじまる』は、センスを「特別な人にだけ備わっているもの」や「天から降ってくるひらめき」として片付けるのではなく、日々の知識の蓄積や経験の深化が、確実に人の判断力や創造力を磨くと教えてくれます。 日常生活の中で「普通」を理解し、見たこと・知っていることを増やすことで、私たち自身のセンスも自然と磨かれていく―このメッセージは、仕事、趣味、そして人間関係すべてにおいて、実践すべき価値ある指針だと感じました。 知識と経験の積み重ねこそが、真のセンスを生み出す原動力であるという水野さんの説得力ある論考は、私自身の考え方に大きな刺激を与えてくれる一冊です。
0投稿日: 2025.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
センスがいい、というのが知識に裏付けされていることが体系的に理解できました。確かに仕事をするにしてもプライベートで筋トレをするにしても知識を得てからの方が圧倒的に効率的でセンスのいいことができている気がします。もっともっと知識を身につけたいと思うようになりました。また客観性を出すために日常とは異なる行動をしてみるというのはすぐにできる範囲からやってみたいと思います。例えば、風呂を逆方向に入るとか、食べる順番を変えてみるとか色々あることに気付かされました。
0投稿日: 2025.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識である。後天的なものであると言いきっている本。 自分はセンスの良い側の人間ではないと感じていたが、努力で何とかなるのでは!?という勇気をもらいました!
0投稿日: 2025.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ”センスとは、知識にもとづく予測である。” 「センス」について、先天性のものではなく、誰しもが磨くことができる後天性のものであるということを語った本。 感覚的に選んでいるようでも、その実、その人の経験や知識に依っているというようなところは、確かにと。 言われてみればな内容ではあるものの、それを自覚して活かせるかどうかこそが、センスの有無と言えるように思えた。 センスは作れる。
1投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かにセンスには、ある程度の知識、経験の集積が必要だと思います。水野氏の発想が、数々のヒットや再生に繋がつていますね!
5投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログセンス=知識量を増やし適切な選択をすること。本を読んだことで新味な考えは特になかった。しかしながら、知識は紙のような物でありセンスは絵のようであるといった表現は気に入った。筆者は様々な分野での知識を習得しながら仕事の幅を広げてきた。自分自身も物事に対して川上から川下までの全体を通して生活していけるような人物になりたい。
0投稿日: 2025.02.15 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスを磨くには知識の集積が大事。知識の集積には感受性や好奇心が大事。感受性や好奇心を磨くにはルーティンを外れた行動が大事。
0投稿日: 2025.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025.02 読了 ・タイトルに惹かれて購入 ・著者の考え方が少し偏っているように感じた ・自分の中で壁が出来てしまい、内容が入ってこなかった
0投稿日: 2025.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログおしゃれなインスタにしたいので写真の基礎を学ぼうと思った。図書館で自分の趣味嗜好と真逆の雑誌を読んでみるのも楽しそう(釣りとか麻雀とか40-50代男性向けの生活雑誌とか) センスで作り上げたものと思われるものには実は全て根拠があって(あるべきで)、そのためには知識が必要ですよ、ということ。 著者はすごい人なんだろうけど、例えがわかりにくいしたまにミスってる……右のページと左のページで微妙にずれていることを言っている箇所がある気がした。
0投稿日: 2025.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ多種多様な知識から、求められるシーンに合う最適解を出力すること。普通を知ること。センスとは何かをわかりやすく言語化されている。
1投稿日: 2025.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1878731061213213146?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識の組み合わせで、良いものは論理的に制作されているんだナァ… 奥様の事例や、実際に水野さんだったらどうするかなど、例があってわかりやすい! 凡な知識から非凡なプロダクトを作るというプロセスが見えた
0投稿日: 2025.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
3. 売れる商品はどれも、その製品らしさ(シズル)を内包しているとのであり、そのシズルが人々の心を掴んでいる。売れるための的確なシズルを見つけ出すためには、その製品が「何っぽい」のかを分類しながら絞り込んでいく作業が有効である 5. 誰も見たことがなくても、狙ったターゲット層にちゃんと「売れる」企画でなければ社会からは求められないんだ 5. 企画とは、アイデアではなく「精度」こそが重要なんだよ 18. 「センスのよさ」とは、数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力である 19. センスがいい商品をつくるには、「普通」という感覚がことのほか大切です。それどころか、普通こそ、「センスのいい/悪い」を測ることができる唯一の道具なのです 22. 多角的・多面的にものごとを測った上で「普通」を見つけ出し、設定する能力が必要 41. 本来の日本は、センスが悪い技術だけの国ではありません。江戸時代までは、むしろ研ぎ澄まされた独自の美意識をもつ「センスの国」でした 45. 人間というのは技術がその時点の限界まで進歩すると、ノスタルジックな思いに身を寄せ、美しいものを求める傾向があると僕は思っています 48. 僕の持論ですが、「美しい」という感情は基本的に未来ではなく過去に根差していると思っています 52. 大塚製薬の「ポカリスエット」。今の20代であれば「脱水症状にはポカリスエット」と知っていますし、子どもの頃から「風邪を引いたらポカリスエット」という環境で育っています。しかし、1972生まれの僕にとって、80年に登場きたポカリスエットは「よくわからない、変わった飲み物」でした。消費者にとっては、ジュースでもお茶でもない、それまでに見たことのない商品であり、同業他社にとっては、思い切ったアイデアの「あっと驚く企画」だったと思います。 2008年に300億本まで売上を伸ばしたのは、ポカリスエットが「誰もが飛びつく新しいアイデア」だったからではありません。「売れるようになるまで、絶対に売る」という大塚製薬の信念と体力が、大ヒット商品に育て上げたのです 56. 日本企業を弱体化させたのは、市場調査を中心としたマーケティング依存ではないでしょうか 63. 企業の美意識やセンスが、企業価値になる。これが今の時代の特徴です 68. 商品というアウトプットは「もの」であり、視覚に左右されます 70. どんなにいい仕事をしていても、どんなに便利なものを生み出していたとしても、見え方のコントロールができていなければ、その商品はまったく人の心に響きません 74. センスとは知識の集積である 76. すべての仕事は価値を創造していくことで対価を得ています 80. アウトプットの前段階においては、知識に基づいた方向性の決定が大切だということ 81. 「あっ!」より「へぇー」にヒットは潜んでいる 84. みんなが「へぇー」と思うものは、ある程度知っているものの延長線上にありながら、画期的に異なっているもの。「ありそうでなかったもの」です 86. 知識にもとづいて予測することが、センスだと考えているのです 92. センスの最大の敵は思い込みであり、主観性です。思い込みと主観による情報をいくら集めても、センスはよくならないのです。 思い込みを捨てて客観情報を集めることこそ、センスをよくする大切な方法です 98. 「流行ってるもの=センスがいいもの」ではない 99. 「クリアアサヒ」はそれまでの新ジャンルといえば他社製品が独走状態でしたが、このパッケージを見た瞬間、「これは売れる!」と確信しました。 「クリアアサヒ」はまさに「シズル」そのものでした。いまにも缶から溢れ出しそうな泡の表現は、「ビールらしさ」に満ちていました。それでいて上質感のあるデザイン。実際にはこの商品はビールではなく、第三のビールと呼ばれる新ジャンルです。しかしそれこそがこのパッケージの肝。「本当はビールが飲みたいんだけど、仕方なく新ジャンルで手を打つか」の思っている人々の心に、刺さるだろうと感じました 100. センスには「賞味期限」がある場合もあり得る 102. 王道のものには、その製品らしいシズルが必ず含まれています。王道としての地位を確立するまでに、改良され、洗練されて、「そのものらしさ」が磨かれているからです 106. その商品が王道たり得る根拠を求め、調べるプロセスにおいて、いくつもの取捨選択をします。「王道」が見つかるまでには、数多くの「王道とは認定できないと判断したもの」との出会いがあるはずなのです。 大切なのは、王道のものを「ひとつに決めること」ではなく、それを見つけ出す「プロセス」にあります 108. 「共通項」や「一定のルール」がないか考えてみる これは知識を集めるというより、分析したり解釈したりすることで、自分なりの知識に精製するというプロセスです 110. 人一人が歩ける通路の幅は、どんなに狭くても600と言われています。900あれば譲り合うことで人とすれ違うことができ、1200あれば支障なく相互通行できるとされています 113. デザインを構成する要素はざっくり考えた場合、①色、②文字、③写真や絵、④形状に分けられます 117. ここから先は「精度」です。僕は、現代は「精度の時代」だと思っており、積み重ねた知識による検証を、あらゆる角度から繰り返していくことで、精度とクオリティを上げていくことができると考えています 119. 「感覚的に、これがいいと思うんです」は禁句。センスが知識の集積である以上、言葉で説明できないアウトプットはあり得ません 121. ありそうでなかったものをつくりだす時、しばしば「差別化」という言葉が使われます。これは本来、「ほんの少しの差」を指すのではないかと僕は解釈しています 132. 僕がしたことは、新しいものをつくることではなく、すでにあったものをほんの少し飾ってあげることでした 137. 「Helvetica(ヘルベチカ)」。ヘルベチカとは「Confoederatio Helvetica」というスイス連邦をあらわすラテン語からきているから。スイス人とアメリカ人の書体デザイナーが生み出した書体なので、そう名付けられたのでしょう。「あえてヘルベチカを使う」という理由をきちんとプレゼンテーション出来なければ、使うべきではないでしょう 139. 感覚とは知識の集合体です。その書体を「美しいな」と感じる背景には、これまで僕が美しいと思ってきた、ありとあらゆるものたちがあります 142. 知識が豊富な人とは仕事ができる人です。知識が豊富な人であれば、上司やクライアントとの会話の際に相手の専門性を感じ取ったり、自分に照らし合わせたり、「チューニング」がうまくできることは多々あります。チューニングがうまくいけば、理解の度合いは深まるでしょう 147. 企画書とは、市場へ商品を出すにあたって最初のアウトプット、いってみれば「消費者への手紙」です 153. 好き嫌いとは、客観情報と対局にあるものなのですから 154. 「誰が、どんなときに、どんな場所で使うかのか」を設定しましょう 156. 狭い分野で豊富な知識を持っている人は、すべての事象を自分の得意分野と結びつけることができる、そんな特異なセンスの持ち主なのですから 163. 僕にとっての旅の定義は、日常から逃れること。つまり非日常であること 169. 「感受性+知識=知的好奇心」
2投稿日: 2024.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは、普通の延長だったり、割とロジカルなことである、と解説している。正直、なにか驚くほどの内容が書いてあるわけでもなく、ちょっと物足りない内容だった。
0投稿日: 2024.12.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ- センスは誰にでも身につけられる - センスは事象を最適化する能力 - センスを磨くには知識が必要 - センスは感覚ではなく論理である - いつもと違うことをして枠を広げる
0投稿日: 2024.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センスとは集積された知識に基づく予測である」という言葉に全てが凝縮されていると感じた。 真に新しいものなど無い。数多の事象や知識を蒸留して得られたものがセンスであり、センス同士の掛け合わせがイノベーションになる。 センスを閃きと呼ぶ人は、事象同士に共通性を見出せないだけで、それは知識や洞察の不足に起因する、と。 知識をどのように獲得してセンスを磨いていくかの例もあり、「一段上の知識を得たい」人におすすめ。
7投稿日: 2024.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センスがないからできない」は恥ずかしい事なのだと感じた。 「センスがない=知識がない」だと著者は述べる。 センスという言葉が使われる科目、例えば、美術は義務教育において実技をメインに学ぶことが多い。 センスを育む為に必要な知識が疎かにされがちである。 その結果、美術に興味のある生徒とない生徒の間で授業時間外に得られる知識量の差がセンスとして表れる。 それを知らずに、自分にはセンスがないと思い込んでしまうというのは恐ろしい事だと思う。 自分の可能性を無下にしないためにもまずは知識をつけたい。
1投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現在の義務教育の美術が実技に偏っていたり、受験に必要とされないためあまり力が入っていかないことや、そのそのことが現在の日本企業のプロダクトの魅力の弱さに繋がっているのではといった点はとても腑に落ちました。 また、美術も学科として美術の歴史や技法について学ぶことが出来ることも、自分自身は親の影響で休日に美術館に行ったり、大人の美術教室に通う経験があったため、とてもその通りだと思えました。 センスをひらめきのような、特別な才能とみなすのではなく、アウトプットしたい対象についての知識をしっかりとリサーチし、細部までこだわって考え抜いていくことでセンスの良いアウトプットをすることが出来るのではというメッセージを受け取りました! 読んで良かった本です。
0投稿日: 2024.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ売れるものとは1秒で判断されるものとすれば、その1秒に訴えかける技術は知識で十分補える一冊。美術、音楽、体育などは実技でなく理論を教えるべきという点では非常にに共感。仕事にも活かせるし人生も豊かになること間違いなし。
5投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.10.27-2024.10.28. 学生時代に買って読みかけたまま、片隅にあったこの本。引っ張り出して呼んでみて思ったのは、やっぱり学生時代の「あの時読んだ方が良かっただろう」という気持ちだ。 一方で、「デザイナーではない人たち」に向けて書かれているこの本は、自分がなんとなしにやっていたデザインプロセスを大変わかりやすい言葉に落とし込んでくれてある。そのため、デザインに触らない人たちとの共通認識点として非常に使いやすい言葉が盛りだくさんだと思った。 「ここって、あんまりやらない人もいるんだ」という部分や、反対に「こんなことやってるのか?!」といった部分もあり、自分を客観視して「普通」を素直に知るにはとても便利な方んだと思う。
0投稿日: 2024.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログたまにセンスがいいと言われるので、そのセンスの正体って何なんだろうと思って読んでみた。 よく他人に対して「服のセンスがないな」「仕事のやり方のセンスがないな」と思うことがあってなんとなくセンスという言葉を使っていたけれど、オブラートに包まずに言うと『普通』と比べて良く見えない・効率の悪いやり方ってことか!と再認識した。そして、その判断ができるのも『普通』(平均)を知っているからできることだと言語化されて改めて発見することができた。確かに、量産系の服(普通)を着てる人たちってセンス良いって言わないよなぁ。 私自身もよくある事柄に対して「自分にはセンスがないからできない」と制限を設けていることがある。例えば写真を上手に撮ることが苦手だったけど、構図の法則をある程度知ってからはそれっぽい写真は撮れるようになった。 「自分にはセンスがないから」と考えるのを避けてる人はいっぱいいる。美術的なことはわからないと言って切り捨てるのは簡単。でもそれは単にその問題から逃げているのだと気付いている人はこの世にどれくらいいるんだろう。 美術が専門科目として放置されていることや、センスには精度が大事だという話もうんうんと共感しながら読めた。仕事だとこだわることを邪魔、時間の無駄とされてしまうのは悲しい。 センスとは知識であり言語化できるものだなと私は思う。デザインと言葉の意味が似てるなと思った。 この本は特に、「自分はもう〇〇歳だから」「自分の職種は〇〇だから」と言ってしまう人やアートとデザインの違いがわからない人、そして多くの社会人に教養として読んでもらいたい!
1投稿日: 2024.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ数値化できないセンスを磨くためには普通を知ること、旅をすることだと。階段1段飛ばしの勇気を持って行動していきたい。
0投稿日: 2024.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログものを開発したり考案する仕事に携わっていますが、センスを身につけるためというよりも「結局センスだよね」と言われたときの釈然としない気持ちの正体を考えたくて読んだ本です。 センスという言葉の定義ももちろんですが、一般的に「センスがいい」とされる力や行いがどのような流れで構成されているのかを、こんなに明確で誰でもわかりそうな言葉で言い表せるのは本当にすごいです。 自分はまだまだ「徹底的にできていない」のだなあと思えました。 もっと何回も読み込んで考えたい本です。
0投稿日: 2024.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスを良くするには普通を知ることが必要である。ハッとしました。センスの良さはてっきり、特別な感性の有無に依拠すると考えていた。しかし、普通こそセンスの良しあしを判断する唯一の道具である、そのため、まずは各分野の基礎をインプットすることが重要。 すべての仕事において、知らないことは不利。センスとは知識の集積である。ひらめきを待たずに知識を蓄えておくべき
0投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識を蓄積させることを楽しんで継続できれば、何歳からでも変わることができると勇気づけられました。 センスは既に自分の中にあり、センスを磨く旅を楽しむ事ができれば知らず知らずのうちに何事かを成すことができることが解った。
0投稿日: 2024.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは生まれついてのものではない。 「センスのよさ」とは、数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力である。(本文より) とにかくたくさんのインプットが必要で、『普通』を見極める。 『普通』を基準として、そこからあらゆる知識を元に肉付けしていく。 自分の『感覚』で判断しない。 なぜこうしたのか、言語化できることが必要。 美術はこれらと同じ、もしくは非常に近しい学問であると僕はとらえています。 「この絵が描かれた背景について、どれだけの知識があるのか」 「どうしてこのような作品が生まれたのか、体系立てて説明できるか」(本文より) これはデザイナーに共通して求められるスキルです。数冊読んだデザイン本には当たり前のように書いてありました。 デザイナーに限らず大切なこと。 『チョコレートの商品開発担当者になったのなら?』 チョコレートに関する情報を集める。定番を知る。パッケージの色は?デザインは? なぜその色を選んだか。 以前読んだ『解像度を上げる』の内容と共通していると感じた。 終盤では、『普段しないことをしろ』と書いてあり、以前読んだ『前頭葉バカ社会』を思い出した。 やはり大事なことは共通しているんだな。
12投稿日: 2024.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログオーディブルで視聴。 センスがある、センスがないというのはこの時代さまざまな分野で言われ、兎角持って生まれた才能的な意味合いで語られることが多いけれども、それを真っ向から否定している本。センスは膨大な知識量やインプットの成果としての後天的なものであるとのこと、とても同感しました。要はセンスがないというのは、センスを得るための努力量が足りない=自分は頑張っていないと同義ということです。誰でもセンスは身につけられるという意味で勇気を与える本だと思います。 その上で具体的に何をしたら良いのかというと、色々な分野について体系的な知識をつけること。非日常を日常的に体験すること。例えば、男性であれば女性雑誌を読んでみる、雑誌を数冊眺めてみる、降りたことのない駅で降りてみる、デパートで普段入らない店に行ってみる、年上の人と話すなど。自分も、日常に新たな気づきを得られる瞬間を積極的に取り入れていきたいと思います!
0投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024.8.12読了 ◯◯さんはセンスがいいから、と少しでもデザイン性を求められる仕事を職場のおじさんから押し付けられることが最近よくあり、センスってなんだろうとモヤモヤしていたので手に取った本だった。 “センスとは、特別な人に備わった才能ではない。” “センスとは、知識の集積である。” この本を読んで、自分の知識の集積にフリーライドされているような感覚があって違和感があるのかもと気づいたし、本書に書いてあるようにアップデートをし続けて、自分のセンスを気持ちよく仕事に活用できるようになれたらいいなと少し気分を変えることができた。
0投稿日: 2024.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識さえ得れば後天的に身につけることができると教えてくれる本。つまり誰もが勉強すればセンス良い人間(≒結果を出せる人間)になれるということ。 何かを目指すにあたってまずは勉強する、という自分の基本姿勢を形作ってくれた本です。 仕事や趣味に対して向上心ある方々全般、商品企画等のアイデア勝負な仕事を生業にされている方にぜひとも読んでいただきたい一冊!!
3投稿日: 2024.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログデザイナーとしても参考になった、特に後半。 ・ファッションも好き嫌いだけで選ばない ・新しい体験を絶えず、好奇心と幼児性 ・調査結果の深掘りをする必要がある
0投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
飲みやすくてあっという間に読んでしまいました。 「不勉強と思い込みはセンスアップの敵」 今の私の心にとても響いた言葉でした。 階段を◯段飛ばすくらいの勇気を持ってどんどん冒険し、様々な知識を蓄え続けていきたいなと思います。
0投稿日: 2024.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスのよさとは、数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力である。この言葉になるほどと感じた。またセンスは知識から始まるというタイトルもよく理解できた。僕は写真が好きだが、なぜこの写真がいいのかを理解するためには、構図やカラー、光の入り方など様々な知識が必要となる。また、服装に関していうとあの人なんかオシャレだなあと思うのにも理由がある。サイズ感のバランスなのか、素材の質感の組み合わせなのか。これらは全て知識からくるものであるので、これからもいろいろなことに好奇心を持って知識をつけていきたい。
0投稿日: 2024.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログTHEもくまモンも中山政七商店も。全くジャンルは異なるのに、幅広い人に刺さっているのは、幅広い知識の集大成によるもの。と、実績を見るだけで腹落ちする。 1番の学びは 王道を知り、流行りの理由を見つめ、共通項やルールを自分の中に落とし込む。 このルートによる思考法。やってみよう。
0投稿日: 2024.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分のセンス・才能に自信がなく コンプレックスになっている人にとって 悩みを解決するための重要なヒント をもたらしてくれる 一冊だと感じました。 センスとは 生まれついての才能ではなく 作成者自分の持つ多様で深い知識の中から いかに自分の伝えたいことを 相手にわかりやすく 感じやすいように 情報を最適化するかについて 論理的に解説されており とても 参考になりました。 ファッションやイラストなど 作品の見た目(特にビジュアル面)を考える仕事に 就きたいと思っている人に ぜひ オススメしたい本です。
0投稿日: 2024.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「センスの良さ」とは、数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力である。 普通こそ、「センスのいい/悪い」を測ることができる唯一の道具 今までは質✖️量だったが、コモディティ化しているためセンスが求められる。 技術力はやがて頭打ちになり停滞する。 センスのある企業、センスのある人間が求められる時代になりつつある。 アップルの商品は革新的 市場調査などはしても意味がない やるのであれば、1秒1人の直感 スティーブ・ジョブズ 自身が本当に欲しいものを作る 商品力が良くても見せ方が悪いと売れない センスを磨くには、あらゆることに気がつける几帳面さと人が見ていないところに気がつける観察力が必要。 効率良く知識を増やす三つのコツ ①王道から解いていく
0投稿日: 2024.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ10年前の本 センスを磨くにはまず知識をつける 王道を学ぶ→流行りを学ぶ→共有項を見つける 過去を知ることの大切さ 新しいものを広めるには時間がかかるというスタンスでいく。 目上の人を飲みに誘おう、勇気がいるけどこれができる人が少ないらしい
0投稿日: 2024.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスという言葉からイメージするとひらめきになるが、そうではなく知識が必要だという内容。あるものを開発するなら、その物の知識を学ぶことが大切。これは今からでも服を選ぶ際、その人の特徴やシチュエーションによって選べばセンス良い服を選べるそうだ。センスは知識からという本を読んでいると自分の好きなああいうものやこういうものもこうやって開発されたのかな?と現場を見られた気がして楽しく読めた。
11投稿日: 2024.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルの通りの内容。たしかにひらめきとか天から降りてくるようなアイデアって地味な作業とか積み重ねじゃなくてパッとでてくるもの。センスがあるものだって認識されてることが多いかも。言われてみれば確かにだった。 風水の話(推測)は確かにそうだな!と思った。なぜそうなったのかまで考えるところデザイナーって感じがして好きだった。 好奇心旺盛であること、ルーティンから外れて小さな変化に触れることの大切さがわかる。意識すれば簡単にできること。私もやってみよう。
7投稿日: 2024.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識の集積である。 びびっときました。 凡人であるが故に、無形の力である、センスを磨きたいなと心の底から思わせてくれる本でした。 知識を蓄え、それに伴う予測することがセンス。 ストンと落ちた言葉でした。 研鑽により磨き、高めていきたいです。 様々な分野の人に響きやすいように、幅広い事例を挙げていて、確かにとなります。
0投稿日: 2024.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ前職の上司からの推薦で読みました。程度がいいなと思われる人間は博学でユーモアがあり、日々努力している。腰の入った経験があればセンスは自ずとついてくる。しばらくしたらまたパラパラめくりたいです。
0投稿日: 2024.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本企業の製品開発の特徴として、調査ありきの製品開発がある。そのデメリットは、第1、自分が何がいいかわからなくなる。自分の頭で考えなくなる。第2に、調査結果で決めたとなると、責任の所在が曖昧になる。新商品が無理だったら首になるという責任感がなくなる。緊張感のなさは向上心を弱めてしまう。 アウトプットの前段階においては、知識に基づいた方向性の決定が大切。「ワクワクする旅がしたい。」という時、世界の国を知っていなければ大体のイメージがわかない、アメリカしか知らなければそもそも選択の余地がない。色々な国を知っていて、ネパールに行ってみようとなったりする。 僕たちは、過去と未来が引っ張りあっている世界に存在していて、古いものに対して「美しい」と思う感情が、未来へ、新しいものへと進もうとする力に拮抗してバランスを取っている。みんなが、「へぇー」と思うものは、ある程度知っているものの延長線上にありながら、画期的に異なっているもの。「ありそうでなかったもの」です。独創性のみ考えていると独りよがりのものになる。 知識を効率良く増やす際に三段階のアプローチがある 第1、「王道から解いていく」というもの。王道のものには、その製品らしいシズルが含まれており、最適化されている。王道を知ることにより、そのジャンルの製品を最適化する際の指標ができる。さらに、王道を理解する過程で、知識を自然と獲得している。一度王道を見つければ、その後の知識の獲得、センスの獲得も容易になる。基準があれば獲得した知識も整理されやすくなる。 第2に、「今、流行しているものを知る」という方法。流行しているものはたいてい一過性のものだが、王道と流行のものの両方を知っておくことで知識の幅を一気に広げられる。そのために有用なツールとして雑誌がある。 第3に、「共通項」や「一定のルール」がないかを考えてみるというもの。これは知識の集積というより、分析や解釈によって自分なりの知識にしていくというプロセス。
1投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ・センスとは定性的なものを最適化することであり、それは知識の活用によって達成される、という考え方が述べられた一冊。 ・知識を得て、基準を知ることで、最適化のゴールが明らかになる。センスとは、知識に基づいて予測することである。 ・技術(イノベーション)の発展が頭打ちになれば、センスの発揮(最適化)が求められる時代になる、の説明が面白かった。
0投稿日: 2024.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスがない事と単なる不勉強を勘違いしている人が多いと言う主題自体は正しいと思う。ただし、知識がついてきたからこそセンスを痛感する場面は山のようにある。それを努力不足と断じてしまうのはいかがなものか。 またセンスを磨く=知識をつける具体例として出してくる具体例が異常なほどに薄っぺらい。また8割は自慢話なのだが、その自慢話の中にも矛盾が入り込んでくる。例えば「『感覚的にこれがいいと思うんです』は禁句」と書いておきながら、別のところで「カレーうどんのデザイン配色→カレーといえばキレンジャーだから黄色!」とか、「40代の女性はみんなフランダースの犬見てるはずだから商品名はフランダース!」など感覚的な発言を連発していたりもする。おそらく筆者の仕事のやり方としては後者がメインなのだろうし、後者のやり方で成功しているのだから問題はないのだろうが、真逆の事を教えるのは読者の混乱を招いてしまう。 筆者と自分の「センスと知識の線引き」の差は個人の趣向として置いておくにしても、主題と具体例の矛盾の溝が如何ともしがたく、あまり参考にならなかった。
0投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「不勉強と思い込みはセンスアップの敵」(本書159頁)とあるように、一見するとセンス=才能と考えがちな我々に対し、いかに知識の蓄積と客観性が「センス」につながるかを説いた本。 一部に論理の飛躍を感じるが、我々が才能すなわち先天的なものとして捉えがちな“センス”を、万人が会得するチャンスがあり、かつそれを磨いて自らの生活や仕事のアウトプットに繋げられる、そんな可能性に気づかせてくれる一冊。
0投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは主観ではなく、客観的な情報の集積の先にあるもの。 自分なりのセンスの解釈は、広範囲かつ深度のある情報から、その時に求められる目的に合わせて「最適化する能力」
0投稿日: 2024.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは才能である。という思い込みが間違いであると気付かされた。1,2時間程度でサクッと読めて良い。 センスの良さとは、数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力 センスを磨くには普通、いわゆる王道を知るのが重要。そこから流行を知り、共通項を考える。 センスは知識の集積 市場調査では新しい価値を生み出せない。聞いたことも触ったこともないものをいいと言う人はほとんどいない。調査に頼ってばかりだと自分は何がいいか、何を作りないかを考えなくなる。 技術がその時点の限界まで進歩すると、ノスタルジックな思いに身を寄せ、美しいものを求める傾向がある
0投稿日: 2024.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報を徹底的に集め、良し悪しを知る。 そこから解を見つけ出す。 というのはデザインに限らず、どんな仕事にも当てはまる考え方だなぁと思いました。 そして、自分の知識の無さ・偏りに意気消沈。 もっともっと知識を付ける、幅を広げるため、勉強します!
0投稿日: 2024.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の認識の狭さを改めて認識できた本だった。 「センス」という言葉を論理的に、また実に実用的な形でどうあるのかを説明している素晴らしい本だと感じた。 元々は、私自身がデザイナーであることから購入を選んだ本だったが、なにかに悩んでいる人は1度読んで見て欲しいと思える本だった。
0投稿日: 2024.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ様々な事に興味を持ち、学び咀嚼し、その客観的な知識をもとに最適解を予測すること=センス、ということかな。 自分的には思い込みを捨てるのが大事だと思った。 // センスとは、数値化できない事象を最適化すること まず『普通を知ること』が必要 イノベーションは、知識と知識の掛け合わせ センスとは、知識にもとづく予測 センスの最大の敵は思い込み、主観性 思い込みを捨てて客観情報を集めることこそ、センスをよくする大切な方法 流行っている=センスがいい、ではない
0投稿日: 2024.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔からセンスやひらめきに乏しく、少しでもいい意見を出すためにと、情報を集めたり細かな資料調べ、作業を積み重ねて切り抜けることがあった。 はっきりとセンスは知識の積み重ねと言い切る内容は、誰もが努力と意識をみがけばより上質な世界を切り開くことができるというセンスなし自覚者に希望をもたせる。 “知識にもとづいた方向性の決定が大切”とした上で、 “ブラッシュアップしていくときは、あっと驚くものを目指し、最終的なアウトプットは、新しく、美しく、尖ったものであるべき。” なるほどと思った。 最終的なブラッシュアップに手を抜かないということは覚えておきたい。 また知識の集積には主観性は敵。 これらのことは1人の人間力についても言えると思う。客観性のある知識の積み重ね、最終的に見た目の美しさ、尖った部分もあって、魅力ある人間力につながる。 “最終的なアウトプットとは、土台となる知識がいかに優れているか、いかに豊富かで、かなりな部分が決まってくる” 書体について興味を持ったのは初めて。 新たなものを知識として得る一歩を後押ししてくれる書。
1投稿日: 2023.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは生まれ持った才能ではなく、誰でも得ることができる。なぜならセンスは知識の集合体なのだから。ということだそうです。 確かに、一定の分野について豊富な知識を得ておけば、どの場面でどんな目的でどんなターゲットに向けて何を提供すべきか、たくさんの知識の引き出しから選び出せるわけだから、最適なものを提供できるということか~。 iDやくまもんを生み出した著者は最初はグラフィックデザインを専門にしていたとのことで、フォントへのこだわりもひしひしと感じた。普段使っているフォントがどの国でどの時代にどんな理由で生まれたかなんて考えたこともなかった。歴史好きの自分としてはフォントの歴史に興味をそそられました。「この企画書にはこの目的で作られたこのフォントを使おうかしら」なんて考えられたら素敵。
0投稿日: 2023.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスが良い・・・とは自分には無縁のことだと思っていたが、センスを磨くにはコツがある。 当たり前にことが多いものの、目から鱗。 普段何気なくやっていることでも、法則化することで、より最適化され、最速化される。今後は意識的にセンスを磨いていきたい!
0投稿日: 2023.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスと呼ばれるものを理論的に説明してくれている。 ・「普通」を知っていれば、それより少し良いもの、すごく良いものなどのさじ加減ができる。普通とは良いものも悪いものも知り、その真ん中がわかる事。 ・市場調査からは新しいものは生まれない。 ・見え方のコントロールがブランド力を高める ・思い込みを捨てて客観情報を集めることがセンスを良くする ・シズル(肉がジュージュー焼ける様。転じて。美味しそうに見せる、そのものらしさを見せること)が必要 例:クリアアサヒのビールの泡のパッケージ ・誰が、どんな時に、どんな場所で使うのか、と具体的に思い浮かべることがセンスの最適化に必要 ・センスを磨くには知識が必要だが、知識を吸収して自分のものにするには、感受性と好奇心が必要。感受性+知識=知的好奇心
0投稿日: 2023.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分が出来ないことに対して、「あの人はセンスが良いから」と言うセリフで片付けてしまうような人間にならないようにしようと思いました。
0投稿日: 2023.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスというのは知識の集大成。 大人になっても知的好奇心を持つことが大切。 そのためにも、いつもと違うことをしてみる、または好きなものを深めてみる。そこから気づくこともあるなと感じました。
0投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスの善し悪しとは、何とも言葉にしにくいものだと思っていた。しかし、この本ではセンスは知識の集積と言っている。センスのいい人とは元々、感覚で上手くいく人であると思っていた。しかし、知識を効率よく集め、客観的に物事が見れることで誰でもセンスのある人になれる。その知識の集め方には、王道とは何か、流行しているものは何か、それらの共通点を探すことで正しい知識が集まる。
0投稿日: 2023.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは自分の知識の集大成であり、知識をインプットしながら、同時にそれを研鑽し、繰り返しアウトプットして行くことでセンスが磨かれる ということかなと思った。 まずは自分がしたいことの知識を貯めて行こうと思った一冊だった。
0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容としてはタイトルの通りの1冊です。 センスは知識の集積から生み出されるものとして、一見関係なさそうなセンスというものを論理的に導くための1冊となっています。
0投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ話の入り口は芸術系でも知識が有効ということだったが,メインの話題はセンスを形式知化 (言語化) するのが大事だし,形式知化できるという内容だった.個人のセンスだけでなく企業として美意識を醸成するのが大事ということや,センスにも賞味期限がある,ということも印象に残った.
0投稿日: 2023.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは、数値化できない事象を最適化すること。 その判断のために知識を身に付ける。判断の精度や信頼度を上げる(^^)服も好き嫌いは取り払い、体型や肌色などから客観的に検討していくことで なぜそれを選んだかも説得力が出てくる。パッケージデザインと一緒ってそのまま その通り!センスない人って多分に知識不足でー自分を含めてですが オシャレもインテリアも身近なものから情報収集していこう。
0投稿日: 2023.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センスとは数値化できない事象を最適化することである」 センスという一見するとふわっとしていて捉えどころのない概念を紐解いていく。 この本は凡人がどの様にセンスの良い考え方が出来るか?を丁寧に教えてくれる本である。 知識の集積の上にセンスが成り立つことが分かる。
0投稿日: 2023.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
くまもんをデザインした方の著者。 とにかく、知識が必要!そうですよねーと思いつつ不勉強な私には耳が痛かった。 ちょうど、好きな服は似合わないけど、どんな服が似合うのかもわからない…という悩みがあったので、本書の内容を、服選びに早速活用したくなりました。 センスという曖昧に感じていたものの輪郭が少しだけ見えた気がする。
4投稿日: 2023.09.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「センスのよさ」とは、数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力だと定義。 判断するには知識が必要。 最適化するには思い込みの枠を外し、アウトプットの精度を上げることが必要。 なるほど。やはり私は知識不足だったようです。まずは仕事の領域の雑誌で情報収集してみることにしました。 ロゴ作りも苦手だったけど、商品と書体の歴史的な知識も意識してみよう。 やっぱ「センスないなー」って感じる人ってデートにしても服装にしても情報収集と客観視が足りてないんだよなー。自戒込めてですが。
1投稿日: 2023.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
20230903 センスとは特別な人に備わった才能ではない。それはさまざまな知識を蓄積することにより、物事最適化する能力であり、誰もが等しく持っている。 まず、普通を知ることが大事。 技術がピークを迎えるとセンスの時代がやってくる。 なぜ日本の企業にセンスが無いのか。市場調査という落とし穴。 イノベーションは知識と知識の掛け合わせである。 センスとは知識に基づく予測である。 経営者のセンスが企業の底力になる。 流行っている=センスではない 知識のクオリティが精度の高いアウトプットを作り出す。 好きを深掘りしてセンスあるアウトプットをする。 幼児性で新鮮な感性を取り戻す。 服選びは自分を客観視し、最適化する身近な方法。 ガラパゴスで生きている自分を自覚しよう。自分という存在がいかに小さな島の中で、閉じこもった生活をしているか、それを認識するところから、世界は広がっていくはず。
0投稿日: 2023.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ1089 水野学 クリエイティブディレクター/クリエイティブコンサルタント。1972年、東京都生まれ。多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業。1998年、good design companyを設立。ブランドや商品の企画、グラフィック、パッケージ、内装、宣伝広告、長期的なブランド戦略までをトータルに手がける。主な仕事に相鉄グループ全体のクリエイティブディレクション及び車両、駅舎、制服等、熊本県「くまモン」、三井不動産、JR東日本「JRE POINT」、中川政七商店、久原本家「茅乃舎」、黒木本店、Oisix、NTTドコモ「iD」、「THE」ほか。2012-2016年度に慶應義塾大学SFCで特別招聘准教授を務める。The One Show金賞、CLIO Awards銀賞ほか国内外で受賞歴多数 このように考えると、センスというのは数字で測ることができないものである、となります。 「センスのよさ」とは、数値化できない事象のよし悪しを判断し、最適化する能力です。 数字で測れないために、センスというのは非常にわかりにくいものだと思われています。それでも確実にセンスのよい/悪いは存在し、それはどのような環境のもとにあるかにも左右されます。 普通とは、「いいもの」がわかるということ。 普通とは、「悪いもの」もわかるということ。 その両方を知った上で、「一番真ん中」がわかるということ。 「センスがよくなりたいのなら、まず普通を知るほうがいい」と僕は思います。 これは「普通のものをつくる」ということではありません。「普通」を知っていれば、ありとあらゆるものがつくれるということです。 数値化できない事象を測る方法をたくさん知っていればいるほど、センスがよくなります。 しかし、美的センス=実技ではありません。優れた画家を育ててきた画商たちは、審美眼というセンスが非常に優れていました。彼らは絵が描けずとも、美的センスがある者たちでした。 端的に言うと「受験科目でない」というだけで、実技を伴う科目は趣味のもの、どうでもいいものにされてしまいます。「将来の役に立たない」と、よけられてしまうのです。これが大人になっていく過程で起こる、芸術との訣別です。 しかし、美術というのは立派な学問であり、二つに分かれているというのが、僕の意見です。 一つ目は芸術や美術についての知識を蓄える「学科」。 二つ目は、絵を描いたり、ものをつくったりする「実技」。 実技を「うまい/下手」で判断することだけが、美術という学問に優れているかどうかを測る尺度になり得る──僕は決してそう思いません。 複数の色を使う場合に最も気をつけたほうがいいのは、隣り合う色の選び方です。美術の教科書の片隅に載っていた、色がぐるりと円を描いた「色相環」を覚えているでしょうか。隣り合う色には、色相環の反対側にある「補色」を使うか、あるいは「同系色」を使うと、きれいな仕上がりになります。より詳しく色の相性を見つけるには、書店に数多く並ぶカラーチャートの本もお薦めです。 美術の知識が欠落すると、美的センス、すなわち美意識というものにコンプレックスを抱くようになります。服、住まいやインテリア、持ち物や雑貨を選ぶことに自信がもてなくなります。身の回りの些細なことですが、これによって、「センス」という言葉への恐怖心が育っていってしまいます。 しかし、本来の日本は、センスが悪い技術だけの国ではありません。 江戸時代までは、むしろ研ぎすまされた独自の美意識をもつ「センスの国」でした。 たとえば茶の湯を確立した千利休が活躍した安土桃山時代は、センス、美意識というものが花開いた時代です。 僕の目には、この時代と今の時代は非常に似ているように映ります。技術からセンスへ移り変わった時代、それが安土桃山時代だと思うのです。 人間というのは技術がその時点の限界まで進歩すると、ノスタルジックな思いに身を寄せ、美しいものを求める傾向があると僕は思っています。 たとえば戦闘技術がピークを迎えて戦国時代が終わった時、大名たちは茶の湯や芸能に夢中になりました。全国統一で世の中が落ち着き、美に目を向ける余裕ができたという見方もあるでしょう。権力者が富とパワーを誇示するために美しいものを追求したという見方もあります。 一八世紀半ばにイギリスで起きた産業革命で、世の中は劇的に変わりました。ものづくりに工業という概念が持ち込まれ、機械化が進み、大量生産が可能になりました。職人がコツコツつくっていた時代とは比べものにならない生産量でしょう。さらに、蒸気機関車というかつてなかった移動手段が生まれました。 これらは素晴らしい技術の発展であり、進化なのですが、安かろう悪かろうの品が大量にあふれるというマイナス面も伴います。それに異を唱えたのが詩人でデザイナーのウイリアム・モリス。今でもそのデザインは美しい壁紙やプリントとして残っています。 一八三四年生まれの彼は、「工場の大量生産品を使うのではなく、もう一度手仕事に戻ろう。暮らしのなかに美しいものを取り入れよう」と提唱し、さまざまなセンスある商品を生み出しました。これは「アーツ・アンド・クラフツ運動」と呼ばれます。モリスによる〝センス革命〟が起きたと言っていいでしょう。手仕事というなつかしさをフックにしたセンスの時代への変換です。 これも僕の持論ですが、「美しい」という感情は基本的に未来でなく過去に根差していると思っています。ノスタルジーやなつかしさもフックになるに違いありません。 斬新なものを生み出した場合、たとえ成功するとしても、それには相当な時間がかかることを理解し、長期的な視野を持つことが必要です。 わかりやすいところでいうと、携帯電話をスマートフォンに変えるだけでも数年を要しており、いまだ携帯電話を使っている人もたくさんいます。 初代iPhoneの発売は二〇〇七年。この時点ではアメリカ国内向けの機種だったこともあり、使っていたのはイノベーターと呼ばれる革新的な少数派だけでした。 ラガード(Laggard:遅滞者)と呼ばれる保守的な人たちは、どんなにスマホが流行ろうとも決して変えようとしないでしょう。 食品でも化粧品でも、新しい商品をつくろうというとき、圧倒的多数の日本企業はまず、市場調査を始めます。僕は、これが大問題だと思っています。 日本企業を弱体化させたのは、市場調査を中心としたマーケティング依存ではないでしょうか。 ひとつは、悪目立ちするものに目が行きがちであるということ。 なにかを選ばなければならない「特殊な状態」に置かれている調査対象者は、普段の自分だったら毎日の生活の中に取り入れたいとは思わないような、変に目立つものを、気負って選んでしまいがちです。 もうひとつは、新しい可能性を潰してしまいがちなこと。 自分が見たこともない、聞いたこともない、触ったこともないものをいいと言う人は、実はほとんどいません。発売前のiPodを市場調査にかけていたら、「再生や巻き戻しのボタンがないなんて」と非難ごうごうだったかもしれません。一〇〇が二〇〇になったものは欲しくない。一〇〇が一〇一になったもの、せいぜい一一〇ぐらいになったものを見た時、多くの人が「新鮮だ、新しい、欲しい!」と思うものなのです。 亡くなってしまったスティーブ・ジョブズという人は、経営者であり、クリエイティブディレクターでした。 「センスがよくなりたいのなら、普通を知るほうがいい」と述べました。そして、普通を知る唯一の方法は、知識を得ることです。 センスとは知識の集積である。これが僕の考えです。 つまり、過去に存在していたあらゆるものを知識として蓄えておくことが、新たに売れるものを生み出すには必要不可欠だということです。 まずは知識をつけましょう。過去の蓄積、すなわち「あっと驚かないもの」を知っていればいるほど、クリエイティブの土壌は広がります。そのうえで、あっと驚くアウトプットを目指すべきなのです。 センスとは、知識にもとづく予測である よきセンスをもつには、知識を蓄え、過去に学ぶことが大切です。同時にセンスとは、時代の一歩先を読む能力も指している。 過去を知って知識を蓄えることと、未来を読んで予測することは、一見すると矛盾しているように感じます。しかし、僕の中でこの二つは明確につながっています。 知識にもとづいて予測することが、センスだと考えているのです。 さらに占いにはいろいろあり、統計学のように思えるものもあります。僕はあるとき風水に興味を持ち、一〇冊ほど本を読んでみて、はっとしました。 「風水って占いに見えるけど、実は気の流れにまつわる知識の集大成なんだな」 気功の気、霊気の気ではなく、大気の気。風水とは、文字通り水と風、そして湿度や温度といった天候や地質の知識にもとづいて打ち出された未来への指針なのです。 Aくんは実はファッションについてとても勉強していて、洋服やそのときの流行をよく知っています。さらに、自分の体型、個性、雰囲気など客観的な情報もきちんと集積しており、その二つの知識を合わせて服選びをしているのです。 一方、「いつも流行のど真ん中の服装をしていて、ファッションが好きなのはわかるけれど、センスはなさそうだし、おしゃれにも見えない」というBさんもいます。BさんもAくん同様に、ファッションについてとてもよく勉強しているでしょう。しかし、彼女の知識は非常に偏っており、「今、何が流行っているか」という点に絞られています。もしかしたら「モテ服はこれ!」という情報も入手しているかもしれませんが、自分の体型、個性、雰囲気といった客観的情報は持っていません。その結果、自分に何が似合うかという目的にかなわない服装をしてしまうので、センスがよくも見えず、おしゃれにも見えないのです。 センスの最大の敵は思い込みであり、主観性です。思い込みと主観による情報をいくら集めても、センスはよくならないのです。 なかなか自由になれないからこそ、意識して思い込みを外すべきだと僕は感じます。 思い込みを捨てて客観情報を集めることこそ、センスをよくする大切な方法です。 僕は半ば冗談、半ば本気で「学校にセンスを教える授業があればいいのに」と言いますが、これは学校教育こそ客観情報の集め方を教える効率的な仕組みだと考えているからです。歴史の知識、数学の知識は客観情報として与えられるのに、美意識にまつわる知識はすべて自己学習として放置されており、その結果、客観情報を集められるAくんと集められないBさんという差が生じてしまう気がしています。 しかし、パッと見ただけでセンスのいい家具を選べる人は、おそらくインテリア雑誌の一〇〇冊や二〇〇冊には軽く目を通しています。あるいは、お店を回ったり、詳しい人に話を聞いて、それに匹敵するような情報を得ているはずです。勉強のような辛い努力ではなく、趣味として楽しんでいたかもしれませんが、結果、膨大な知識の集積が行われているはずなのです。さらに、「自分の部屋」について客観的に見る目も持っているので、ふさわしい家具が選べるのです。 本題に入る前の前提として、「流行っているもの=センスがいいもの」ではないことを理解していただきたいと思います。ここを間違えている人は、意外と多いものです。 たとえば、ジーンズならリーバイス501。一二〇年以上の歴史を持ちながらいまだ多くの人に愛される、定番中の定番です。 王道をおさえたら、流行のものについての知識収集に着手しましょう。王道の真逆です。 流行しているものの多くはたいてい、一過性のもの。しかし、王道と流行のものの両方を知っておくことで、知識の幅を一気に広げられます。 流行を知る手立てとして最も効率がいいのは、雑誌。それもできれば、コンビニの棚に並ぶありとあらゆる雑誌を手にとってみることをおすすめします。 僕は普段から、女性誌、男性誌、ライフスタイル誌に経済誌と、月に何十冊もの雑誌に目を通しており、ここから得た知識はとても役立っています。インターネットは速報性はありますが、流行に関する情報は整理されきってはいません。しかし雑誌なら、精査された情報が載っています。複数読むうちに流行の流れが見えてくるのです。 時代は常に変化しています。数カ月前に出た新製品によって、それまで不動の地位を得ていた定番商品が大きく揺らいでいることもあり得ます。知識を定期的に更新しておくことは、センスアップにつながるのです。 三人の意見は同じですが、その信用度とクオリティは格段に違います。彼らは自分の意見を述べていますが、その意見は「福澤諭吉についての知識」という土台からなる見識です。センスのある発言をするには、正確でハイクオリティな「精度の高い知識」が欠かせないということです。 これは商品やアイデア、企画も同じだと僕は考えています。最終的なアウトプットとは、土台となる知識がいかに優れているか、いかに豊富かで、かなりの部分が決まってくると思うのです。 僕は本屋さんにいるのがとても好きです。「ここにある本の数の分だけ人の考え方がある」と思うと、わくわくします。著名人一人ひとりに会って話を聞くなど、阿川佐和子さんや林真理子さんでもない限りなかなかできません。違う時代を生きた人や亡くなった人であれば、阿川さんだって話を聞くことは不可能でしょう。しかし、一万冊扱っている本屋さんであれば、一万人の考え方に触れることができます。 書店は素晴らしい知恵の泉です。センスの源となる知識にあふれている場所です。 書店に行くのは一日に一回でいいでしょう。通勤途中にある書店に毎日足を向け、五分で一周してみる。一〇分でもかまいませんが、できるだけ高速で店内を回り、「あれっ」と思ったものを手にとってみてください。 理想的にはもちろん購入し、財布に余裕がなければ立ち読みさせてもらいましょう。この習慣によって、単純に言えば知識が一年で三六五増えるのです。 続けていくうちに「知識を身につけよう」という気持ちではなく、「知りたい」という知的好奇心の扉が開かれていくと僕は思っています。 僕自身が、〝ガラパゴス〟から脱出した経験者です。もともとはグラフィックデザインだけが本業でした。ですが、知識を増やし、センスの幅を広げることで、グラフィックデザインだけでなく商品企画、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、経営コンサルティングと僕のフィールドは広がりました。
0投稿日: 2023.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスという抽象度の高い問題を、「センスとは知識からはじめる」と分かりやすく言い換えて様々な例をもとに説明している。 日頃から「センスがないから」といって諦めていたり、言い訳に使っている人はいないだろうか。そのような人にこそ是非読んでもらいたい。
0投稿日: 2023.08.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ要約すると、このタイトルが全て。 これを何度も例も交えて掘り下げている。身の回りにあるもの(iPhoneなど)を例としているので内容としてはわかりやすいし、納得しながら読み進められる。センスとひとくちに言っても奇抜すぎてもいけない。背景知識や、歴史を知ることは、センスを発揮すべき対象への敬意や愛情とも受け取れた。 好きなものを深く狭く掘り下げるだけではなく、新しい「ちょっと違う」を見つける新体験をも促している本。
0投稿日: 2023.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識からはじまる 著:水野 学 センスとは、数値化できない事象を最適化することである。 センスのよさとは、数値化できない事象の良し悪しを判断し、最適化する能力である。 普通を知るということは、ありとあらゆるものをつくり出せる可能性がたくさんあるということである。 現代においても、ごく身近なところで知識にもとづく予測はできるし、予測する必要がある。それがセンスを磨くことにつながっていく。 本書の構成は以下の5章から成る。 ①センスとは何かを定義する ②センスのよさが、スキルとして求められている時代 ③センスとは知識からはじまる ④センスで、仕事を最適化する ⑤センスを磨き、仕事力を向上させる ほんの数年前までは、センスであったり、リズムであったり、美意識であるというものは、仕事力とは一線の距離を持って捉えられていた。しかし、現代において、その距離は非常に近く、近いどころは仕事力の源泉はセンスであったり美意識と捉えておかしくない環境も存在している。 新たな付加価値を提供する上で、既存の知識の延長線上だけではその価値はなかなか提供できない。顧客があっと驚く感動体験はセンスが良い業務の中で生み出されることは多く、多くの優良企業ではそれがスタンダードになっていると言っても過言ではない。 センスは生まれつきではなく、後天的な努力で身に付けることもできる。知識の集積と確度の高い経験からそれを叶えることがでできる。 良いものに触れ、良い判断を行う機会に触れることでセンスは研ぎ澄まされることになる。 センスがわかっているかわかっていないかは今後も両極化され続けることになる。速くそのことに気付き手立てを個人としても組織としても実行することで救われることも多い。 表現できない世界にこそ先行者利益の源泉は眠っている。
1投稿日: 2023.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ購入した本。 タイトル通り、「センスは知識から醸成される」という説明本。 まず普通や定番を知ること。そこから組み合わせで発展させていく。 膨大な知識を前提として得ていくことが大事。 売れるものについてはシズルがある。「sizzle」 「そのものらしさ」が売れるためには必要。ビールならビールっぽさを! センスうんぬんではなく、まず勉強して知識を得ること。そこから徐々に自分なりに発展させていく。
0投稿日: 2023.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスは知識から始める、ということで、ある分野のセンスを鍛える際には、何がなぜ王道かを知る、何が流行っているか知る、というのを意識することで、センスが育つとのことです。 実践できそうな気がしましたので、読んでよかったです!
0投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスを身につけるには、とにかく知識を蓄えろという内容。 自分はセンスがない側の人間だと思っているため、勉強と題して、調べたり、本や雑誌を読んだり、とにかくインプットを重視してきた。 そのことが間違っていないと、読了後は自信になった。 このまま知識を蓄えることを続けていきながら、そのときに意識をもう少し高める。 それにより、蓄えた知識が結集して、きっとセンスになっていくのだろう。 新しい発見というよりも、大事なことを再確認できた一冊。
0投稿日: 2023.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログセンスとは、知識の集合による予測だということが学べた。 目的に対して、その時代背景やターゲットの受け取り方を予測して作り出す。 知識を増やしていくことで最適な提案ができる=センスが良くなる。
0投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに共感して手に取ったが、思ったとこおりの内容が簡潔に整理されており腹落ちしやすかった。 センスとは知識に基づく未来の予測であり、「普通」を知っていくことがクリエティビティーの向上につながる。 おそらく、筆者の言うセンスを無意識にできている人とそうでない人がいるため、センスは生まれつきのもののように思える。そしてその差は分野によっても出るでないがあり、特定の分野でセンスを発揮する人が他分野でそうとは限らない。ただ、うまいかないときに知識に紐付ける、という打開の鍵を本書が示していると思う。
0投稿日: 2023.07.08
