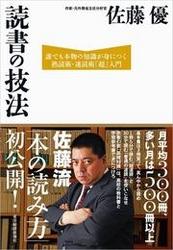
総合評価
(410件)| 90 | ||
| 157 | ||
| 103 | ||
| 17 | ||
| 3 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
佐藤優著「読書の技法」 月平均300冊読む著者の多読法の紹介。 超速読、速読、熟読の3種類の読み方がある。 超速読は読むべき本を見分けるために5分程度で内容をチェックすること。 速読は基礎知識がすでにある本をキーワードだけピックアップして脳内インデックスを作ること(知識が必要なときには本を探してもう一度読む)。 熟読は計算や漢字のように身に付けるために教科書を読むような読み方。ノートに書き写すことを著者は勧めている。
0投稿日: 2018.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ読む必要のない本を選別する。 他人の経験、知的努力を読書によって自分のものにする。 もっともっと本を読まねばならぬ。
1投稿日: 2018.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間は有限。だから読む本を選別すること。 読まなくていい本に時間をとられないようにすること、が、佐藤氏の読書法の基本線ですね。 本にランクを付け、読み込み方にも差をつけるという視点が秀逸。 考え方は、本田直之氏のレバレッジ・リーディングに近いのかもしれないですが、軽薄さが感じられないのは、本人の肉体が物理的に重いからか、それとも本人の人生が重いからか・・・。 予備校講師のバイトをしていたので実感しますが、プライドが高すぎて、自分が躓いていることを自覚できない類の人間が結構いる。 本書の言うように、東大・早慶レベルの学生でも。 そもそも、受験科目に科目選択の余地があるなら、それ以外の科目の知識がごっそり抜けていても、まったくおかしくない、というか、それが戦略的には正しいわけで。 でも、少なくとも大学受験レベルの知識は、教科の偏りなく持っておけよ、と。 敢えて言う人がいなかったこの点に激しく同意。 やっぱりですね。統計がわかってないのに、社会調査とかしちゃいけないと思うんですよ。 あるいは、それができないから、エスノグラフィックな手法で行きます、とか。逃げでしょう。 また、ビジネスマンの間で教養がブームです、とか言われる度に何となく違和感を持ったのも、自分では意識していなかったけれども、このあたりにあったのかな、と。 ベストセラーだからといって、ニーチェの解説本を買うのは良いですけれど、例えば高校の倫理の教科書の内容、アナタ、一通り把握してますか。みたいな。 とことほど左様に、本書も正論が続くのですが、文字通り実行に移す人は、さほど多くないのではなかろうか、という気も。 ビジネスマン向けの哲学本が、流行ってきた背景には、ハウツーものの受けが悪くなってきた出版社側の事情もあるのでしょうが、より本質的な本へとターゲット層の関心を移すことに成功したとしても、果たして読者はそれを吸収できているのか、という佐藤氏の危惧とそれに対する処方が、この本の執筆動機かと思われます。 自身が大学受験レベルの教養講座を受け持つことについては、この本の中でも、自分の仕事ではない、と述べていますが、そういうものが必要だと提言したい、と。 正しいと思います。 という流れで、推薦本として、出口の現代文とか、山川の高校教科書とか、そういったものが前面に出てくるわけですけれども。 問題は、抵抗感なく受け入れられる人がどれほどいるか。 ビジネス書を読む層が、30代から40代の人間だとすると、団塊ジュニア世代がボリューム層として存在していますが、この世代というのは、激しい受験戦争があった最後の世代。 まだまだ幻想としての一億総中流と、「勉強をしていい大学に入れば」、という意識が社会を覆っており、どの階層に属していようと、学歴獲得競争への参加を強要された時代。 受験に対し、全面参加の裏返しとしての愛憎が残る最後の世代でもあるわけです。 もう少し言うと、この世代にとって受験とは、全面参加であるが故に、そこで問われた中身・技術は、無意味なものとして 了解されるわけです。敗者への救済のために。 というわけで、この層の読者。最低限の教養なのだから、と受験参考書を提示されて、大人しくそれを手に取るかなぁと。 まあ、要らぬ心配でしょうか。 実際、アマゾンで、この本と一緒によく買われている本として、出口の現代文が上がってましたし。
0投稿日: 2018.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大人になってから、学生時代に勉強しなかったことを後悔している。しかし、後悔ばかりしていても何も生まれない。何をどう学ぼうかと考えていたらこの本に巡り合った。やはり、高校時代の学習は大人になってから、かなり知識として必要だ。何を知っている必要があるのか、何を読むといいのか、その指針が書かれており、とてもわかりやすい。興味のあることをまずやっていこう。
0投稿日: 2018.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読、熟読の技法はもちろんだが、各分野の知識の欠損を補うために何をどう読むかをまとめた章は筆者がどう読んでいるかも知れ参考になる。
0投稿日: 2018.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読・速読・超速読。 高校の教科書・参考書で 体系知のベース作り。 佐藤優の読書術を語った一冊。 ポイントは2点。 ○超速読・速読・熟読を使い分ける。 1冊5分の超速読、1冊30分の速読で 読むべき本を仕分け。 その読むべき本を3回熟読。 1回目は重要部分、わからない部分に線を引きながら読む。 2回目はさらに重要な部分を抜粋し、 ノートに30分でできる範囲で抜き書き。 3回目は結論を3回読んだ後、通読する。 ○高校の教科書・参考書で体系知の基礎作り。 ①世界史 ・青木裕司 世界史B講義の実況中継 ・これならわかる!ナビゲーター世界史B ②日本史A ・現代の日本史A ③政治・経済 ・詳説 政治・経済 ④国語 ・出口汪 現代文講義の実況中継 ⑤数学 ・新体系・高校数学の教科書 ・もう一度 高校数学
6投稿日: 2017.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当の技法だけ知りたいのならばⅡ部の教科書や参考書の重要性(と言う名のレビュー)を読み飛ばしても構わないと思うが、Ⅰ部とⅢ部はなかなか参考になった。自分も結構読むペースが速いほうなのでこれ以上速読したら確実に頭に入らないと思っていたが、要は工夫なのだと思った。定規を当てて読むやり方は一度試してみたい。
0投稿日: 2017.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ入試問題の解き方 政治書物の読み方 勉学のための読書 など、多岐にわたる「本」の読書方を示している。中には普段何気なく行っていることなどもあり、より意識して読書に向けて取り組もうと言う気にさせる。 ただ読み方を述べるだけではなく、それを如何にして現場のビジネスに取り込んで行くかにも焦点を当てている。
0投稿日: 2017.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ異端の外交官であった佐藤優が、自分の読書術と遍歴を明らかにした一冊。外交官として目を通す必要が速読法を生んだのはわかりましたが、熟読する冊数は大きく変わらないのがわかって、ホッとしています。
1投稿日: 2017.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書術の本が好きで、様々な著者の本を読んできたが、その中でも自信を持っておすすめ出来るのが三谷宏治氏の『戦略読書』と本書だ。読書をする、という表面的な手法の話だけでに終始せず、きちんと前段となる学び方や考え方にも言及している。一読すると、佐藤氏が「スゴく頭の回転が速いんだろうな」と驚嘆するはずだ。
4投稿日: 2017.08.17速読って本当にできるの?
月平均300冊以上読むという筆者の読書術を学べる本である。 速読ってよく聞くけど本当にできるの?と疑問に思っていたが、この本でいう速読は熟読しなくてもいい本に対しては欲しい情報だけをピックアップする読み方のことで、どんな本でも速読できるというものではない。 では、どうやって速読していい本とダメな本を見分ければいいのか、ということについて本書では詳しく書かれている。 この本の最後に本書で登場した本のリストがあり、ここから次読む本を探すのに役立てることもできる。 今までは本を読むときに何かを特別に意識せずにただ読んでいたが、この本をきっかけに読書の仕方を変えたいと思った。 以下にこの本で気になった部分のメモを載せる。 第1章 どうしても読まなくてはならない本を絞りこみ、それ以外は速読する 読書には順番があり、手続きがある。 第2章 速読の技術 本には三種ある 簡単に読むことができる本、そこそこ時間かかる本、ものすごく時間がかかる本 速読術とは、熟読術の裏返しの概念 熟読術を身に付けないで速読術を体得することはできない 自分の知識の欠損部分を知り、そこを補うこと 第3章 速読の技法 ためし読みをしてどのように読む本かを選別する 判断するためには基礎知識が必要 普通の速読をするためには、本の内容を100%理解しようとする「完璧主義」を辞めること 必要とする情報についての明確な目的意識も必要だ 第4章 読書ノートを作る時間がもったいないへの反論 本を読み終えてしばらく経つと、なにが書いてあったかという記憶が薄れてしまう 読書後30分かけて補強作業をするとよい。 読書ノートを作る最大のポイントは、時間をかけすぎないこと。 第5章 基礎知識の欠損部分を埋めるために 高校レベルの教科書と参考書を活用する 国語 出口汪『NEW出口現代文講義の実況中継』は仕事で使う文章の読解力が飛躍的に向上する 第6章 リラックスするための読書は無駄ではない 漫画は「動機付け」には使えるが、知識を身につけるものではない ベストセラーはどんな作品であっても、その時代の雰囲気をつかんでいる
0投稿日: 2017.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄いけどほぼ真似できないなぁ。 読書ノートについてと、高校レベルの学習参考書と教科書を使いこなすという内容は参考になった。歴史や政経、勉強しなおそう。
0投稿日: 2017.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方、ノートの取り方、教科書の使い方、実践しています。 知識がなければ速読はできません。 村上春樹を読み始めたのもこの本がきっかけでした。
0投稿日: 2017.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ情報収集について、読書に特化して書いて有るのだけど、非常に有用なノウハウが多くてためになった。熟読の方法(同じ本を3回読む)というのは、確かにこういう読書のやり方をすると、自分自身に知識が残るな、と思ったので、早速試してみたいと思った。まずはこの本を熟読(再読)することから、はじめてみようかな。
1投稿日: 2017.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「読書の仕方、本の選び方、勉強の仕方」の3点を考える上で非常にためになりました。 記憶に残る読書にするためには、たくさんの本に目を通すためにはという相反するような目的を両方とも実現するためには速読と熟読をしてみようと思いました。さらには超速読と速読が紹介されていますが、それは私にはハードルが高いので、まずは速読で頑張ろうと思います。その速読でもどれくらいのスピードで、どれくらいちゃんと、もしくは雑に読むのかが記載されています。それを参考に私は私のレベルを設定しトライしてみます。 熟読にもさらに上があり、読書ノートを作るということも紹介されています。これはぜひ、トライしてみたいと思いました。 全般的に言えるのは、あくまでも、紹介されているのは佐藤さんの技法です。それと、他にアレンジしてもいいとも言っています。自分のやり方を押し付けるような、もしくはそれが絶対的に正しいというような表現が一切なことが好感を持てました。
0投稿日: 2017.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書籍リリースのペースが驚異的なので、どんな読書を行っているのか参考にすべく本書を購入しました。 しかし著者が読んでいる作品や、書籍個別にどのように整理・咀嚼したのかの具体例の記述部分はすべてスッ飛ばしました。私個人としてはあまり参考にならないので。 『お母さんのハートを打ったJRのレールマンたち』をマルクス『資本論』の "利潤低下傾向" の論理を用いて解釈したり、『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』を『曽根崎心中』や『怪談牡丹灯篭』と絡めて読むといった手法が参考になる人間が、一体どれだけいるでしょうか。 しかしロシア畑で革新思想に触れてきた経歴に反し、読書方法が非常に地道で保守的なので共感がわく。 本に書き込みを加えて汚しながら繰り返し読む。学習は高校レベルの教科書と参考書で徹底的に基礎を押さえる。そして学習内容をちゃんとノートに落として記憶の定着化を図る。時間をかけるべき書籍には何日もかけて熟読する。著者が知識レベルのベースアップに価値を置いていることがうかがわれる。 そのため、記載されているHow to には簡単に実践できるものは少ないです。継続は力なり。習慣化が重要だということでしょう。 著者は1日に約7時間を執筆にあて、読書も1日に4~6時間は確保するという。そもそも通常のビジネスパーソンと割り当てできる時間量が違うので全てはまねできない。エッセンスを抽出し、参考にする程度だろう。
0投稿日: 2017.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わったー。 基礎学力として、高校レベルの知識が必要という事が書かれていて、。確かにと感じた。統計の勉強をする中で、中学レベルじゃできない、せめて高校レベルが必要だなと実感していたからだ。世界史についてもそう。高校で世界史を先行したが、この経験は文学作品を読む中で、大いに役立ってきた。もう一度、高校の教科書・筆者引き合い本を読み直そうと思った。 速読についての本を10年ぶりぐらいに読んだ。本の分類につてはどの速読術にも共通の項目のようだ。久しぶりに本を読み始めようかと思いたった本だった。
0投稿日: 2017.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優さんのことを知りたくて読みました。 他の著書で主張されている内容もありましたが、自分が考えていた原則論とも重なる点があり、共感。 夜より朝、教科書・学習参考書で基礎力を、所詮は基礎力がなければ速度などできない。 さすがです。参考になりました。
0投稿日: 2017.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書法と書いてあるが、それぞれの分野のさわりの教養についても記述があり面白かった ・・・引用や気になったところ・・・ 正しい読書法を身につければ 人生を2倍3倍豊かなものにできる →高校の教科書レベルを身につけるのが知への近道 デタラメな本は読まない 読書量ではなく、その根底にある基礎知識と強靭な思考力とそれを身につけるための熟読法 読書の要諦は基礎知識をいかに身につけるかにある →基礎知識は熟読でしかつかない →熟読できる時間は限られている →選別のための速読が必要 本三種類 ・簡単に読むことができる本 ・そこそこ時間がかかる本 ・ものすごく時間がかかる本 ■熟読 ・本を3回読む →線引く→10/1程度(多くても) →抜き出す →通読 熟読できるのは月6-10程度 重要なことは、知識の断片ではなく、自分の中にある知識を用いて、現実の出来事を説明できるようになることだ。。 大雑把に理解、記憶しインデックスをつけて整理する 判断や意見を書く ■世界史 オバマ大統領 →2009年ノーベル平和賞 →しかし平和主義者ではない →ウサマビンラディンの殺害を実施 ■サウジアラビア →サウード家のアラビアという意味 →サウード王一族と国家が一体となった国 →イスラーム原理主義は国内にとどめた →アメリカ、イギリスと協調 1979 ソ連のアフガニスタン侵攻『社会主義支援の名目で) →国際社会から批判 →アメリカとの関係悪化 →ウサマビンラディンなどがサウジアラビアからアフガニスタンに渡りソ連に対抗 →ソ連を追い出したあと、敵はアメリカであるとタリバーン政権ができた みなさんは受験勉強が嫌いだ、そして受験勉強が意味がないと思っている (重要)国際政治の枠組み作った 1648ウェストファリア条約 →30年戦争を集結させた →ドイツ30年戦争 →最初は宗教戦争だった →途中からハプスブルク家とフランスの戦いになった ウェストファリア条約でヨーロッパの主な国々が互いに平等で独立した主権を認め合った ・・・ ■日本史 ・第一次世界大戦 1915以降貿易は輸出超過に(綿糸・綿織り物中心) 国内では大戦中ということもあり船舶の需要が急増 →アメリカ、イギリスに次いで三番目の造船量だった →世界最高水準の技術に肩を並べていた →船成金(ふななりきん) ・染料、薬品、肥料など化学工業分野でドイツからの輸入が途絶えたのをきっかけに国産化が進んだ。 ・工場の動力も蒸気から電力へ 第一次世界大戦後の不景気で格差が拡大 →三井・三菱・住友・安田のいわゆる四大財閥は恐慌の影響を最小限に抑え切り抜け、経済界への影響力を一層強めた 1929世界恐慌が起こる →輸入品があふれる →まゆの値段が下がる→大打撃 →政府への不満が高まる →満州国の建国で打開しようという軍部を支持する雰囲気が高まる 五一五事件 →テロ 二二六事件 →クーデター 両方とも目的は世直し、手段は暴力 →テロは民間人が暴力を行使 →クーデターは国家機関が授権された範囲を超えて暴力を行使する 日本の政治理解のポイント 1955の55年体制 日本社会党が統一した →焦った保守派は自由民主党を作った 1960年、日本社会党は民主社会党と公明党に別れた 自民党の党是は憲法改正 →55年体制の中では無理だった(1/3はとられてたから) 金権政治への批判から 1994年 政党助成法制定制定 →政党の活動費用の一部を国費から支給されるように →政党の国家への依存を強める(政治家の発想が官僚化してくる) →政党は国家ではなく社会に属する組織なので、国民が出すのが筋では? →企業献金は全面的に禁止すべき →贈賄(見返り求める)や背任(見返り求めない)に当たる可能性のある金で政治活動をすべきでない ■マルクスの考え 資本主義経済確立期 →労働者は低賃金・長時間労働など劣悪な労働条件で経済不平等の下におかれ貧困に苦しんだ →労働力の商品化 →人間疎外の克服 →社会主義の実現が必要 ■マルクスの資本論 一ヶ月の賃金 ・衣食住とレジャー ・養育費(次世代の労働力) ・生産性向上のための自己学習 今、年収200万以下1000万人(2012) →余裕がなく1つ目しか満たせない 実際どうか? マルクスは国家の廃絶を主張していた →レーニンが創設しスターリンが基礎固めをしたソ連の社会主義国家は極端な国家主義的傾向を帯びていた ■政治経済の勉強法 ・テーマを決める →自分なりの仮説を立てる ・事実を知る →図書館行って統計資料など(日本国勢図会、世界国勢図会 ・インタビューをする →詳しい人に聞く(ただし、聞く前に自分なりに調べておく) ・専門書を読む ・アンケートを調査する ・レポートを書く(書き方) →テーマ設定の理由 →調査の方法 →仮説 →調査結果 →結論 →参考文献 ・プレゼンテーションをしてみる ・ディベートをする ■現代文とはどんな教科か? →論理的思考能力を問う教科 入試はどんな教科でも論理と知識しか求められない →数学と一緒 →数学との違いは言葉だということ →個人によって意味が異なる →だから文脈で判断する →文章の中で言葉は、無数の糸で引っ張られているのです。引っ張られて意味が決まる。その働きが文脈の力というものなんです。 ■評論文とは →自分の意見を相手に伝える手段 →読み手は不特定多数 →自分の意見は相手にわかってもらえないというのが前提 →どうするか? →→「論理」的であるしかない。 言葉と事柄の間には距離がある →本当に伝えたければ、「この」と言うしかない →指を刺さなきゃいけない →言葉の限界 →逆に言えば、「この」を理解することが文章理解のコツ 筆者が一度しか言わないことに目をむけろ →何回も言わない →その代わりに自分の主張と同じ引用を持ってくる ・・・ ■数学 体に覚えこませる技術テクネー →実習必要 →脳の別部分に蓄えられる →言語化できない ・・・ 能率が落ちて来たら数学か外国語の練習問題を解く 読書 →線付箋 →理解できない部分は音読する ・・・・ 再読 「 受験 勉強 が 現実 の 社会 生活 の 役に立た ない」 という 認識 は 間違っ て いる。
0投稿日: 2017.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ元在ロシア連邦日本国大使館勤務後、外務省国際情報局分析第一課で主任分析官を務めた佐藤優氏による読書論。氏が外交官時代に培った実践的学習について詳説されており、インテリジェンス技術を応用した読書術となっている。引用ノートの作成法や時間管理法、さらに歴史や民族問題など多岐にわたる専門書の解説を交えた個別的「読み方」が提示される。著者の知見の深さを窺い知ることができる一冊だ。 著者は【一生のうち読める本の数は有限】という原則に基づき、読むべき本を功利主義的観点から分類する必要性を説く。本書が多くの速読指南書と異なるのは、速読とは熟読すべき本を選別する為の一手段に過ぎないとする考え方、すなわち「熟読の為の速読」が提唱されている点だ。熟読によってのみ真の知識蓄積は可能となる。 深く読みこむ必要がない本は、事前に設定した読書目的に沿って要点のみを把握すればよい。但し、未学習分野の専門書を速読することは不可能である。まずは基本書の熟読によって前提知識を得ることが必要とされる。そこで多くの場合、高校教科書レベルの基礎知識が必要になる。本書では科目ごとに使用する教材や学習方法について解説されているので参考にしたい。 ビジネスパーソンを対象に解説されている為、全体的に「インテリジェンスを身につけた社会人同士の競争に勝ち残るには」という論調が目立つ。基本書の熟読と基礎知識の学習を前提としたメソッドなので、本をめくるだけで知識を吸収できるような(胡散臭い)速読術を習得したい者は肩透かしを食らうだろう。しかし、時間を割いて地道に知識蓄積に励むことができる読者には極めて有用な読書論である。
0投稿日: 2017.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優という人については、ほかの著書もいくつか読んだが、大学で神学を学んでその後ノンキャリアの役人になって、鈴木宗男の件だか何かで捕まったマルクスに(たぶん)詳しい不気味なヴィジュアル(失礼)のおじさんという理解。 何かにつけ、「マルクスは~」とか「沖縄が~」とか「特捜部が~」とか言及する人で、何をしている人かはよくわからないけれどもなんだかんだ日本の知識人の枠内に収まっているイメージである。 読書というのは自分にとって趣味の範疇に属するもので、だからここまで勤勉な読書という(付箋やらペンを使うやら)のは目から鱗ではあったけれども、実践できる自信はない。 積読している私としては早期書籍消化の必要から、あまり一冊の本に時間を費やす余裕もないというのが正直なところで、この速読法はたぶん長期的には優れているのだろうけれども、短期的にはあまり気が進まないため、当面は遠慮させて頂きたい。 むろん、速読のために速読法を捨てるというのもおかしな話で、「そりゃお前が面倒くさがりなだけじゃないか」と言われてもやむないこと(だいいちこの指摘は半分当たっているので)ではあるのだが……。
0投稿日: 2017.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ何回も読んでボロボロになっちゃってる。 他の読書ボンのメモもココにまとめている。 速読は限られた時間を有効活用するためのテクニックななのだ。これでだいぶ無駄な読書をしなくて澄ん だ。 高校レベルの教養が必要だそうだ。 自分のビジネスに関係ある読書に集中できそうだ。 高校レベルの知識に不安があるため、並行して埋めていくつもりだ。投資とかの判断にも役に立ちそう。 何度も読み返す。
0投稿日: 2017.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
本のタイトルが超入門となっているが、この読書術は若いことから無数の読書をしてきた著者だからこそ出来る技だと感じた。 ただ、基礎知識が身についていないと、いくら本を読んでも知識が積みあがっていかないというのは、その通りだと思う。 又、基礎知識を付けるための読書に時間をかけないといけない。 私も著者が勧めるように、高校の教科書を使い、世界史、日本史、経済、国語、英語などを学びなおしてみたい。
0投稿日: 2017.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読了。文体も難しくないし特別読みにくいことはないのだが、書いてあることを自分のものにしようと構えてすぎたせいかとても時間がかかってしまった。要再読。読みたい本がさらに増えてしまった。
0投稿日: 2017.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2012年刊行。◆著者の読書法や学習法を、ほんの触りではあるが、解説したもの。高校レベルの知識(ただし定着、ないし手足の如く活用できるまで達すべし)の重要性を感得可能。速読は、読む必要のない本の選別目的とする点は、上手いこと言うなぁ、との感あり。それと、読メのレビュー作成は定着に役立っていると思っているのだが、どうでしょうかねぇ。なお、本論ではないが、著者の鳩山由紀夫評はもっと知りたい。あと、高校学習の意義に触れられているので、目的を見失っていたり、受験科目だけしか学ぼうとしない高校生に読んで欲しい。
0投稿日: 2017.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読、速読、超速読と3種類の技法について、読書の入門書とうたわれているとおりに、活用法を交えながら、かなり丁寧に筆者の考えが紹介されている。 技法の本質的なことは、読書術としてよくいわれているようなことを、筆者が工夫していることを紹介しているだけのことではあるが、本書で読むべきとして紹介されているような書籍のいくつかは、大変興味深い紹介がなされており、早速onlineで注文してしまったくらいのものであった。 読みやすく数時間で通読できるので、本の読み方に興味があるようなビジネスパーソンや学生服には、手頃でオススメかと思う。
0投稿日: 2017.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半の密度の濃さと後半の密度が違ったけれど、その分未消化感はあまりなくすんで、よかった。 本書に記載されているように、もともとの社会の教養が足りなく感じていた私は、ほかの人もそうなんだ、と少し安心。この本のすすめにより、高校の社会科を一気に復習しようと決意した。 また、井上ひさし氏のように、本を活用するもの、としていて、ノートの取り方、速読、熟読の違いなど、高校生の時に知っていたらよかったことだらけだった。
0投稿日: 2016.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ作家・佐藤優氏が、自身の読書術を体系的に余すところなく紹介しきった力作。 読み進めるごとに、著者のインテリジェンスの森に触れて、読みたい本のリストが増えていく。 現代人の情報収集のための、多読、速読、超速読に熟読。 読書ノートの活用。 知識の欠損部分を埋めるための高校教科書や参考書の利用法。 社会人こそ学ぶべき世界史、日本史、政治、経済、国語、数学の優れた学習法に読書案内。 小説やマンガの佐藤氏独特の読み方。 巨人の星、クレヨンしんちゃん、1Q84にこうした見方があったのかとの驚き。 時間の圧縮法、細切れ時間、場所替えの効果。 知の巨人の飽くなき探究心。 膨大な読書量と幅広いジャンルにわたる圧倒的なインテリジェンス。 いわゆる鈴木宗男事件で投獄された際の精神闘争と、膨大な読書量が、更なる知識と問題解決への知恵となって現われる。 学び続ける人、成長し続ける人に触れるのはかくも楽しいものか。 また、本屋へ行こう。積ん読が増えるのを覚悟で。
0投稿日: 2016.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほど『本の仕分け』は必要ですね。 結論として私にとってはこの本は 速読、熟読する本ではなかったなぁ。 超速読で5分で終えるべき本でした(´;ω;`)ウゥゥ ロシア絡みで鈴木宗男さんとプライムニュースに出てて この人何者?と思って見てたので著者を知る という点では少し面白かったかな。
0投稿日: 2016.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読の意義とは、読むべき本とそうでない本とを、せんべつするためだ。確かに人生は短い、時間を有効に使う必要がある。読書ノートは筆者のように細かく作るところまではやらないがあった方が良いのだろう。 筆者は鈴木宗男の関係で捕まり、今は講演活動をしており、かつて外交官時代にはA4で1500枚程度の資料をほんの数時間で読みこなしていたようだ。情報の取捨選択という意味では研ぎ澄まされているのだろう。 しかし速読ではこの程度の内容しか読み取れない。 著者の他の作品を読み込んだ後に再読。 やはり読書ノートは必要だ。しかしどうしても手間なのでブクログで代用する。 時間は有限だ、一生涯に読める本は少ない。本書はこの事実に対して真摯に向き合ってる良書である。しかし、読書を単なる楽しみにしている人には馴染まない考えかもしれない。
0投稿日: 2016.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ〔感想パート〕 【1】p.2の「筆者の読書術について、全力を投球して書いたのが本書である。」にもある通り、佐藤氏の読書の技法が詰まった本だった。 つまり、私のように知識量も教養も経験も、佐藤氏の足元にはるか遠く及ばない者が「今すぐ使える読書法」などと思って読んではならない。しかし「これから知力を強化していきたい」「物の見方を学び直したい」と思う私には、ぴったりの本であったと思う。 【2】私にとって、特に役に立ったのは第Ⅱ部『何を読めばいいか』の第5章『教科書と学習参考書を使いこなす――知識の欠損部分をどう見つけ補うか』の章で、実際の学習参考書からの引用と誤読・誤解しやすいところを解説、そして現在の政治経済や国際情勢との繋がりを示してくれているので、具体的な基礎知識の身につけ方を追って行きやすかった。 【3】「小説やマンガの読み方」の具体例は、まさに目からウロコ!すごく興味深い視点だった! 【4】新しい知識や考えを、しばらく寝かせる(佐藤氏によると「発酵」させる)というのは、戸山滋比古氏も言っている…。やはり、知性の人には共通する方法論があるんだな。学ぼう! 〔ポイントパート〕 【1】速読術とは「でたらめ本」(書かれている言葉の定義がなされておらず、先行思想の成果を踏まえていない、悪い意味での独創的な本)のような、読む必要のない本を早い段階で「読まない」と決断するために必要。 【2】基礎知識がないと理解できない専門書は、なんとなくわかったつもりになってしまい、誤読する危険性があるため、読んでも無駄だ。まず最初に正しい知識・方法論を身につけておく必要がある。 正しい道に沿った読書のために最も確実で効率的な知の道は「高校レベルの基礎知識を正しく消化し記憶に定着させ、身につけること」である。 【3】時間という制約要因を頭に入れておくことで、「何をしないか」「何を読まないか」を正しく選ぶのも知の技法のひとつ。 【4】p.54の『基本書は3冊、5冊と奇数にする』の項目はとてもわかりやすく勉強になった。1つの事柄に対して、定義や見解が異なる時、偏った(もしくは正しくない)知識を身につけたり、素人判断を避けるためにも「多数決」できる奇数が良い。 (ただし、これは自分の日常的な知の技術に限って使える方法であることも忘れてはならない) 【5】p.56『上級の応用知識をつけようと欲張らない』の項目にはドキッとさせられた。 自分が正しく消化できていない事柄に関して、客観的判断ができているか? 基礎知識がまずついているか? 自分の知識の欠損部分を正しく知ることも、知の技法のうちのひとつ。 【6】勉強もしくは必要としているテーマをきちんと定め、レポートを書き、プレゼンをすることを課題として取り組むと、業務にも非常に役に立つ方法を身につけられる。 レポート:(1)テーマ設定の理由(2)調査の方法(3)仮説(4)調査の結果(5)結論(6)参考とした資料や文献 【7】評論を読む際、論理的思考能力・読解力という点で、数学と全く一緒と言って良い。 しかし言葉は「個人言語」(戸山滋比古氏)であり、また時代によっても意味が揺れるものである。 この個人言語を固定するのが「文脈」である。 感情や勘でテキストを読んではならない。 また「言葉の限界」というものについて、正しく理解しなくてはならない。(これはp.188~189を参照のこと) 【8】小説やマンガは「社会の縮図」「人間と人間の関係の縮図」として読むと良い。 【9】短時間睡眠のコツは、二度寝しないこと! きちんと寝る環境(ソファなどではなく)で眠り、「ハッ」と目が覚めたところで、タイミングを逃さずに必ず起きること。仮眠も同様。
1投稿日: 2016.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は言わずと知れた有名人であるが、「月平均300冊」もどうやって読んでいるのかが気になり手にとってみた。 読んでなるほどであった。多くの本を速読・超速読で読み、その中で必要な本だけを熟読しているとのこと。そしてこの著者をしても熟読できるのは月に3冊程度出そうだ。 「速読は熟読に勝ることはない」、「時間は限らなられているので、速読により読むべき本を選別すべき」この考えも納得である。 あと、「本を読み込むには基礎知識が必要で、基礎知識に欠損がある場合は高校の科目を再勉強すべき」というのも至極ごもっとも。 中々面白い本であった。
0投稿日: 2016.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書中心の生活、幅広い知識、、、高校生・大学生のころにあこがれた理想の姿。筆者はその何歩も先に行く驚愕の姿だった。 今は40代前半のビジネスパーソンとなり、かつてあこがれた姿には程遠いところにいるわけだが、それでもヒントは満載であった。 なまった基礎知識を教科書・学参にもとめる。自分の地力を再構築するには確かに最適であるが、全く気付かなかった。 読書ノートの取り方。抜き書き、自分の意見を書くことで知識の定着が図れる。 いかに自分の生活の中に読書を取り入れるか。試行錯誤しながら、自分を高めていきたいと思った。モチベーションが上がった本である。
4投稿日: 2016.07.24 powered by ブクログ
powered by ブクログAsian Reading アジアの活読 『 読書の技法』佐藤優 東洋経済新報社 明日筆者の講演会に参加予定。その前に偶然借りてた熟読の要諦。3回読み、印と囲みとノートへの転記を推奨。当然、全部それをやるわけではなく、そういう本を選ぶ嗅覚関心あり。第7章 時間を圧縮する技法で筆者の仕事と読書を紹介。5時起床、26時就寝という1日で執筆は午前、読書は平均6時間!最低4時間というイーロン・マスクと同じ時間を確保する羨望。自宅の書斎とマンションの一室を仕事場としているこれまた羨ましいかぎり。そこまでやるからいろんなところに連載を持ってるんだなーと。
0投稿日: 2016.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本には「簡単に読むことができる本」「そこそこ時間がかかる本」「ものすごく時間がかかる本」の3種類がある。 人生で熟読できる冊数は限られているので、速読をして必要な本を探しだす。 速読では、100%理解しようとする完璧主義を捨てて、必要なエッセンスだけ学び取る姿勢が大事。 もう二度と読まない、時間は有限という意識で取り組むことで内容の吸収率を上げる。
0投稿日: 2016.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ流行りのビジネスパーソン系な気がして、買ったものの、読む気がしないまま置いてた本。 が、読んでみると、なかなか良かった。 「速読術は基礎知識のある分野のみで通用するのであって、知識のない本を速読術で読んでも意味がない」 「まずは熟読ありきで、その先に速読術はある」 「熟読する本を仕分けする方法として、速読術がある」など、なかなか硬派。 序盤の筆者の読書に対する体験談も面白い。というか、なかなかゴツい。 やはり官僚になる人は能力もさることながら、努力量がハンパじゃない。 具体的に歴史、政治経済、数学など、学術的分野でどの本をどう読むべきかについてページをかなり割いており、お金儲けに片手間に書いた本ではないことも伺える。 また、本作中によく出てくる表現なので、間違いないと思うが、おそらくこの本は「東大、京大、早慶など、それなりの学歴の人」を対象にしている。 多少賢いやり方を知っている人間に、汗をかけと指南する本。逆に、そういう基礎体力がない人にはちょっと敷居が高い内容のようにも感じる。 読んだ後、本を読みたくなる本。
1投稿日: 2016.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の仕方について,具体的な手法や例とともに紹介されている。時間は有限である,から,読むべき本と読まなくてよい本を仕分ける必要がある。そのために「超速読法」を身につけること,そして「普通の速読」で効率よく読書をする方法が書かれてある。著者の経験を例に挙げて,具体的に説明されているところが面白い。例えば,「気になる箇所に線を引く(じぶんのコメントも書き込む)→さらにそこから重要だと思う点を選び→ノートに書き写す」という一連の流れも,実際に読んだ本を例に記されている。 もちろん手間がかかるし,何よりも「超速読/速読」できるようになるか,やはり今の自分では疑問に思うことだらけだ。でも,そもそも,「速読できるようになる」ことを目的にすること自体から見直されるべきで,はっきりと目的意識を持って読書をすることが重要だということが,この本を通してよく分かった。 そして表紙。この表紙の迫力といったら。。余白が際立っていて,さらに迫力が増している感じがした。
0投稿日: 2016.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
凄まじい読書法である。 本書を読んだ人が実際にこの読書の技法を行うのかどうか・・・なかなか真似できることではない。 読書法については、参考になる部分はあまりなかった。 本書を読んだことで、私が実践していることは、高校の教科書をもう一度読むこ とである。 山川出版『詳説世界史』をお昼休みに読んでいる。 古典詳説を読むのは好きだが、時代背景を理解していないと読解できないことも 多々あったため、本書を読んだことで後押しとなった。 作者は、テーマを持って学習をしないとだめだ(「教養を身につけたいから」と いう理由ではだめということ)と主張しているが、まあ、世界史の教科書を読む のと読んでいないのとでは、読んだほうがましだと思うことにして、読んでしまっている。身についているのかはわからない・・・。
0投稿日: 2016.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優『読書の技法』東洋経済 96頁 「情報を整理する時間と情報を探し出す時間は、共に極小にしなければならない。」 171頁 「教養のための外国語とか歴史というような、動機があいまいなままだらだら学習することは時間と機会費用の無駄なのでやめたほうがいい。」 187頁 「(略)…著者の意図に即して読むことが基本だ。そのうえで、批判的な検討を加える。感情や勘でテキストを読んではならないのである。」
0投稿日: 2016.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読すべき本が見つかったときに、改めて熟読の技法を読み返す。ここはスルーしたので。 『現在52歳の筆者は、そろそろ人生の残り時間が気になりはじめている。どんなに努力しても、知りたいことの大部分について、諦めなくてはならない。しかし、そう簡単に諦めたくない。そのときに役に立つのが読書だ。他人の経験、知的努力を、読書によって自分のものにするのだ。』
0投稿日: 2015.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ知力をつける為の読書、その為の最低3回は読む熟読方法と、そうすべきではない本の選別のための、ひたすらページをめくる超速読、その2つより難しい、ひたすら文字を読み続ける普通の速読法の紹介。 その為には基礎知識がしっかりしてないと始まらないという訳で、高校教科書+参考書の利用を提案。多量の本に目を通している筆者の薦める、その具体的な本群に知的好奇心をそそられる。 中盤はその基本書の紹介と、昨年までの民主党政権下の日本の、漠然とした、危うい方向に傾いている集合無意識的状況を、それら引用を利用し意見分析等もしている。その点での賞味期限は今現在では新政権発足で若干切れかかっている。推薦書の美味しい所を抜粋しているとも感じた。 線を引いたり付箋を貼ったりは個人的にも行なっていたが、ITではなく手書きで書き写す所まではしていなかった。実行すると、正にその本をしゃぶりつくすといった具合。 試しにこの本を熟読してみたが、結局その著者の言う普通の速読で事足りる感じのボリュームであった。なので、やはり基本書の熟読が如何に大切か+熟読以外の速読法が無駄を省く為とても重要であるかが体験できた。 ------------------------------ 追記:この熟読方法を為すことで、読む本によっては只読む事以上に理解力、定着率、意識の変容率が跳ね上がりモノ凄い効果を得られる場合があったので、評価を☆5に変更。 (守)
0投稿日: 2015.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
揚げ足取りだが、53pの敷居が高い、 の使い方がおかしい。 まあ、筆者のことだから本当に「不義理をして」敷居が高いのかも 55 本は奇数冊読んで、意見が割れる部分は多数決を 141 日本史Aがいい 195 数学をもう一度 262 陸軍中野学校は「捕虜になれ。そして偽情報伝えろ」 国際政治の原点は1648年のウェストファリア条約 本の真ん中あたりを、まず読む。冒頭・末尾に比べて 力が抜けている部分を見ることで、本の質を判断する。
0投稿日: 2015.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログどのように読書をしていいのか悩んでいた時に出会った本。 人間の能力には限界あり。限界を突破するためには他人から学ぶ必要がある。そのためには効率的に本を読むこと。 テーマが決定したら速読や水先案内人のアドバイスをもとに基本書を3冊選ぶ。基本書の一冊を三回熟読する。残り2冊の基本書も三回熟読し、掘り下げる。 知識の欠損がある場合は内容を理解することができないので高校の参考書で知識を補う。
0投稿日: 2015.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログまず思ったのは佐藤さんの知識量、語学力(いわゆるインテリジェンス)に衝撃を受けた。すげーなと。本当にこんなに賢い人いるのかと。笑 読書術に関してはあまり目新しいことはなかったが、熟読・速読・超速読に関しては勉強になったし、重要な本は何回も読むことを心がけたいと思った。それに読書は楽しまないと意味がない。嫌いで意味のないことは記憶しないのだから。
0投稿日: 2015.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はビジネスパーソンがいかにして読書すべきかについて、以下の観点から紹介している。 ・速読、熟読のための技法の紹介 ・読書ノートのつけ方 ・多読のために必要となる基礎知識の身につけ方 上の説明の合間にちょこちょこ筆者自信が読んだ本の内容についての紹介や考察が挟まれているが、本書の中で言及されていた通り、現時点で理解できないものは読まない、これに尽きる笑 ハウツー本として飛ばし読みすることがオススメ。 勉強したいのに時間がないとお悩みの方にはかなりオススメ。
1投稿日: 2015.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ大量の文書を読み、「インテリジェンス」の世界で闘う著者のノウハウに触れられる一冊です。 手を動かさないと身につかない類の知識を、ショートカットして理解したつもりになってはいけないことを痛感しました。
0投稿日: 2015.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ導入部分の「なぜ速読をするようになったのか」「熟読と速読の緩急の判断基準」等がすごく面白かった。 ちなみに、表紙をめくったところに以下がまとまっている。 ★佐藤流「熟読」の技法 ★佐藤流「超速読」の技法(1冊5分程度) ★佐藤流「普通の速読」の技法(1冊30分程度) 圧倒的な知識量で、ちょいちょい書かれていることが面白い。 鳩山元首相は偏微分の行動様式(現状分析)→積分法を軽視した失敗? ねずみ男から見る処世術、くれよんしんちゃんから見る家庭での閉塞感とみさえの吸引力
0投稿日: 2015.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ教養ブーム 人間が死を運命づけられている存在だから 人間は、制約の中で、無限の可能性と不可能性を同時に持って生きている プーチン 北方領土 カラマーゾフの兄弟 東京・日本橋から、京都三条大橋に到着するには東海道、もしくは中山道をチョイス 概知がいちの部分 刷り込み 「もう二度と読まない」という心構え シンクタンク(think tank)は、諸分野に関する政策立案・政策提言を主たる業務とする研究機関。 現実を虚心坦懐に認め、自らの欠損を早く埋めた者が最終的に得をする。 今あるカードをいかに有効に用いるかがインテリジェンスの要諦なのである。 類比(アナロジー)的に社会や人間を理解する手がかりにもできる 小説は「代理経験」としても読める
0投稿日: 2015.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界を舞台に活躍するインテリジェンスはやはり読書を大切にしている。学生気分でちまちま読み進めていたが効率も考えた自分の読書法を身につけなければならないようだ。人生は短いのだから。
0投稿日: 2015.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさんある本の中から熟読すべき本はどれか判断し、その本をどう読んでいくかという「技法」が書かれており、ためになった。
0投稿日: 2015.03.11基礎知識の重要性
時間は有限であるから人が一生のうちに読める本の数も有限だということは、言われてみればもっともである。 限られた時間の中でどのように本を読むべきなのか、ということが本書のテーマとなっている。 中でも、熟読や速読以前に本を読むためには背景となる知識が不可欠であるとして、その知識を獲得する方法を科目ごとに具体的な書名をあげつつ多くのページを割いて説明している。 これは様々な分野の本を数多く読んできた著者だからこそできることだろう。 本の読み方については、一般人が参考にするにはちょっと厳しいのではないかという部分もあったが、知識を身につけるためにどのような本を読めばいいのか、という面では参考にしやすいのではないかと思う。
0投稿日: 2015.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ知識人・佐藤優の読書方法を紹介した本。時々この手のノウハウ本を読むけれど、冒頭に必ず書かれているのは著者の読書遍歴、現在どれくらいの本を読んでいるかという自慢話になっており、この本も同じ。その上で、著者のように多量の本を読むにはどうしたらよいかというノウハウの紹介、実際の読み方等を事例を使って説明するという流れになってる。本は買え、要点に印を付けよ、意見を書き込め、本選びには超速読を使え、本を理解するにはまず基礎知識を身に付けてから精読せよ等々、著者が実践している読み方のノウハウを紹介している。読書法自体はそれほどユニークはないけれど、自分が決めた読書方法を長く実践することが知識の修得には重要なのだろう。読んだ印象として、この本の内容は読書法というよりも、勉強法のような感じがした。 ちなみに表紙に腕組みをした著者の写真が記載されているが、彼は大きな眼で威圧的に「この本は超速読で済ませてはいけない、精読しろ」と言っているようだ。もしこの本を買う気が無いなら、手にとってはいけない。黙って通り過ぎよう。
0投稿日: 2015.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の読み方を教えてくれたバイブル的存在。佐藤氏ほどたくさん読む事はまだできないが、多くの本を読めるようになったし、内容も頭に残るようになった。実践は難しいけどおすすめです。
0投稿日: 2015.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半部分が非常に示唆にとんでいる。特に読書する前提となる基礎的な知の欠如をどう補うかという考えは秀逸だった。
0投稿日: 2015.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の記録を始めるなら、「最初はこの本」と決めていました。本の読み方をこんなに詳しく指南した本があるなんて、今まで思ってもみなかったし、もっと前に読んでいたら(そもそも発売が2012年ですが)私の人生にももっと影響していたのではないかと思ってしまいます。 佐藤氏のとおりには私は読めませんが、それでもとても参考になります。 やはり、欲張らずに目的意識を持って読むことが大切なのだと再認識しました。
0投稿日: 2014.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ◯読んだ理由 読書した結果、実践に活かせるようにしたいから。学び方を探し中。 ◯概要 ①本の読み方、②要望別どんな本がいいか、ということが筆者の膨大な読書経験から紹介されている。①本の読み方については、本の選び方、速読法、学び方とあり、限られた時間の中で自分の求める知識を効率よく吸収するための「読み方」技法について。②要望別本紹介については、1冊で全てわかるようになりたいという無茶な思い捨てて、本の抜き出しよりどんな読み方や解釈をすればいいかの紹介。 ◯ポイント ・基礎知識が身についているならば、既知の部分は読み飛ばして、未知の内容を丁寧に読む。 →筆者が速読を推奨しているのもこういう理由。「軽く読めるもの、話題だから目を通しておくか」という本であればOK。1冊の本で1つ学びがあれはいい。 ・新聞と同じように本も読む。 →全体を見渡して必要な情報を取捨選択し、取り込んだら自分の記憶にインデックスつけて引き出せるようにする。 速読を実践しようとは思わないけど、読み方は参考になる。 余談:本の紹介で論理的思考能力を養うために、大学受験の現代文参考書があり、早速それで勉強しようと思う。
0投稿日: 2014.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むべき本を定めるための速読法と、知識を取り込んで実際に役立てるための熟読法を紹介している。読書法というより勉強法みたいだ。専門書とか参考書はいいけど、小説や漫画をビジネスパーソン的に役立てるために読む、というのはさすがに無理がある感じがした。どうでもいいけど、表紙を見るたびに「ずんぐりむっくり」という言葉が頭をよぎる。
0投稿日: 2014.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ対露のエース外交官として一線を張っていたものの、検察による逮捕、失職へと追いやられた佐藤優氏の読書術。彼の知識量は尋常じゃない(からこそ第一線の外交官だったのだが)のはわかっているのだが、いかにその知識術を身につけたかがわかる。 …まぁ、なかなかマネできるものではない。内容としては一般的な速読術と、読書の大切さを実例を交えて述べている。これだけである。 一つだけ、彼の述べていることに矛盾がある。 一冊を5分で読む「超速読」であるが、 「最初と最後、目次以外はひたすらページをめくる。中略…めくっている間はページ全体を見て、太字やゴシック体の文字、図表や資料はおのずと目に入ってくる。」 とあるが、読解力を養うために絶賛しながら引用している出口氏の内容、P.185, 193 「文章の中で言葉は、無数の糸で引っ張られているのです。」 「言葉というものは所詮、個人言語であって…状況や場合によっても揺れ動くものである。…とりもなおさず文章の前後関係、つまり文脈から言葉の意味をつかむということである」 ということと矛盾してしまう。言葉だけ見てもその言葉がどう引っ張られているかわからないのである。 ましてや表などは作者の意図でどうとでも視覚的に操作できるため(単純に単位が違うだけでイメージが違う。例えばタウリン1000㎎配合がすごい量入ってると勘違いするというのがより視覚的に勘違いさせられる)、注意深く見なければいけない典型である。 それならば、最初と最後だけ見ている方が、まだ間違えないで済むのでは。 いずれにせよ、知識人の凄さはわかるけど、ためになるかは不明。
0投稿日: 2014.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ20141113読了。 まずは基礎知識をつけること。基本書を熟読し自分のものとして熟成させること。その上でさらなる情報を集めるのだけれど、その時に速読が役に立つ。情報収集するための本は、最初と最後、目次を読み、あとは目を通す。基礎知識はあるので、そこに上積みするための情報をあつめればいい、ということ。 なるほど、と思う方法。参考になる。小説を読むときは熟読になるが、社会人として、世界で何が起こっているかを理解するために必要となるのは読解力、論理力。 高校の知識、そこから身につけたい。
0投稿日: 2014.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読書の技法】 読書は正しい方法で読まなければならない。 ・精読している本は月に4〜5本。 ・読書に慣れている人でも専門書ならば300ページを月に3冊しか精読出来ない。 ・速読は熟読術の裏返しにすぎない。 熟読術を身につけないで速読を行うことは不可能である。 ⭐︎速読の目的は読まなくてもいい本を弾き出すこと。
0投稿日: 2014.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「本書で繰り返し強調するように、読書の要諦は、この基礎知識をいかに身につけるかにある。基礎知識は熟読によってしか身につけることはできない。しかし、熟読できる本の数は限られている。そのため、熟読する本を絞り込む、時間を確保するための本の精査として、速読が必要になるのである。」(45頁) これが基本的な考え方か。確かに。 一口に読書法といっても、本の内容や読書の目的によって複数の手法を使い分ける必要がある。そういう複数の手法を総称して読書法と呼んでいる(フォトリーディングなんかもそのうちの一つと位置付けられそう。)。 そういう目的を考えると、特にあちこちで推薦されている本なら、全部熟読でもいいかな。 それと、基礎知識はやはり経験がものを言うから、筆者の言う速読は、「知らない分野」が多い若い人には難しいのかも。
0投稿日: 2014.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏の読書論。時間という制約の中でいかに効果的な読書をするかという観点で読書術が開陳されている。 高校レベルの基礎知識の習得がまず第一、「読む本」「読まない本」を見極める、読書ノートの作り方など著者の読書術は非常に参考になった。ただ、本に線を引いたり、コメントをつけたりをしまくるという手法は、ちょっと心情的に真似できないなと感じた。付箋やポストイットを活用して直接的な書き込みに代えたいと思う。
0投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
はじめに、にあるように筆者の読書法が体系的に書かれていて参考になる。この体系的、というのがいちばん本書のよかった点。 1章は筆者の読書経験をもとに、多く読むことについて。 2章は、熟読について、筆者の考えが述べられる。 現実の出来事について説明できないと本物の知識は得られていない。 上級の情報を得ようとせず、高校教科書レベルの基礎知識をしっかり会得する事の大切さなどが書かれる。 筆者の熟読の方法は、 1.シャーペンなどで印をつけて読む 2.本に囲みを書いて、それをノートにうつす (迷ったら書き写さない) 3.目次を頭に叩き込み、通読。結論部を3回読み直す これで基礎本を熟読。3冊ないし、5冊読むと、たいていの分野の基礎知識は会得できる、ということ。 3章は速読について。 超速読で本をはじいて、速読するもの(ノートとるもの、とらないもの)熟読するものを仕分ける。 1ページ15秒。目次をみたあとは、ひたすらページをめくる。 4章は、ノートの作り方。 (ぬきがきにコメントを残すというもの。レーニンにならう) 5章は教科書を利用することの優位性。 (教科書購入しようと思った) 6章は、小説や漫画への著者の考え(個人的にこの情報は必要なし) 7章は読む時間について。本によって適した時間がある。(ここは、ほぼスルー)
0投稿日: 2014.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ久し振りに叡智に触れた実感を感じる。まとめ方が素晴らしくサクサクアタマに入ってくる。こんなに読んでいて気持ちがいい本も珍しい。 特に良いのは説教くさくないこと。私は歴史、政治には興味がないがそれでも言いたいことが明確で伝わる書きぶり。多元的な視点でモノを見る事で本質を掴んでいるから難しい言葉を使う必要がないのだ。これは見習いたい。 この本の本質は、見極める能力を高めること、である。益にならない本ははじめから読まない、筋トレの様に自分を鍛えるための本は厳選するし、時間もかけて読み、その間に位置する一般書は奇数冊買って、一番あり得る実態を掴んでいく。 目の付け所の良さ、つまりインプットの良さは、結局のところその人のそれまでの知識と経験によるところが大きい。ハイ・パフォーマンスを出したいならやはり読書とは上手に付き合いたい。そう改めて感じた。
0投稿日: 2014.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読は数少ない熟読できる本を選別するために必要。ノートは一冊に。熟読本はシャーペンと付箋を使って三度読む。基礎知識がなければ速読できない。現実を説明できなければ知識がないということ。高校の教科書等が基礎知識を習得するために優れた教材であること。
0投稿日: 2014.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ①熟読の技法は? ・真ん中は本の一番弱いところなので、本の水準が分かる ・3回読む 1)線を引きながら 2)ノートにポイントを書く(まず囲む→写す) 3)通読 ②速読の技法は? ・読まなくてよい本をはじき出す ・知りたいと思う分野は3-5冊買う 1)ノートにとる(目的を明確にする) 2)ノートにとらない(新聞読み) 3)超速読 ③ノートの作り方は? ・ノートは記憶に定着させるため ④時間を圧縮する方法は? ・昼間15分寝るが絶対に2度寝しない ・場所を変えると効率的 ⑤気づき ・300-500冊/月 熟読4-5冊 超速読(5分)250冊 速読(0.5-3hr)60冊
0投稿日: 2014.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ取捨選択した読み方が重要であるということを、身を持って教えてくれる本。 なるほどな、と面白い記述もあれば、眉に唾をつけて読まねばならない箇所もあり、呆れてしまう記述もわずかだがある。 マンガの部分は、果たして筆者がちゃんと読んでいたのかはなはだ疑問。しんちゃんとか猫村さんとか、どう読んだらああいう結論に至るのか。
0投稿日: 2014.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書物になっているだけで、読まなければいけないという強迫観念を持っていた。 面白くない本は、読まなくていい。 当たり前のことを思い出させてくれたことに感謝。 時間は有限。
0投稿日: 2014.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「超速読」「速読」「熟読」の3段階の技法がのっていた。 超速読は1冊を5分で、速読は1冊を30分で、熟読は最低3回(1回目は線を引きながら通読。2回目のはノートに重要事項書き抜き。3回目は再度通読) たくさんの本の中から今の自分が本当に必要な知識を得るためには効果的な速読法だと思う。 ただし「熟読」は書き込みやノートへのまとめが必要。私は図書館派なので書き込みはできない。なんとか書き込みなしでまとめたいものだ。
0投稿日: 2014.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優の圧倒的な読書の質と量は『獄中記』ですでに示されていたが、本書は著者がその読書という知的活動をどのように効果的に営んでいるのかを記した本である。 著者は、読書を熟読と超速読と速読に分類する。そして超速読も速読も、熟読すべき本を選択するための手段というのが著者の意見だ。「基礎知識は熟読によってしか身につけることはできない。しかし、熟読できる本の数は限られている。そのため、熟読する本を絞り込む、時間を確保するための本の精査として、速読が必要になるのである」というのが著者の基本的な読書に対する姿勢だ。 そのため、超速読や速読の意義については述べているものの、速読の技術についてはほとんど何も述べていない。それは本書の目的ではないのだ。代わりに熟読の技術については詳しい。 ちなみに超速読は、読書というよりもいってみれば立ち読みに毛が生えたほとんど目次による中身の確認だ。そういった超速読も含めているので、月間300冊以上というのは水増しのような気もしないでもない。しかし、最初は「月間300冊以上」という大量の読書量に目を奪われるのかもしれないが、その冊数よりも、著者が毎月それだけの量の本に目を通した上で、熟読すべき本を選んでいるということが本書の主旨に照らしても重要だ。 そして、本書で示された熟読の方法論に照らして自分の読書法を振り返ると、その量は相当違えども、そのアプローチはそれほど大きく違わないと感じた。自分なりの熟読は、大学時代に有名どころの哲学書を読み始めたころから始まったと言える。自分もシャーペン片手に気になったところに線を引き、余白にメモを取り、読書ノートを使って気になるところを引き写すということをしていた。フーコーの『言葉と物』や『監獄の誕生』、柄谷行人や蓮見重彦などを読んでいたが、それらの本は、そのようにしないと理解ができなかったからだ。「言葉の意味がなんとなくわかるということと、テキストの内容を理解することは、本質的に別の事柄だ」とあるが、熟読すべき本に会うとそのことがよく分かる。ここ数年は読書後にはBooklogに、読書ノートを上げているが、このことは確実にその本に対する理解レベルを上げている。必要性と意志から自然と実践した読書法だが、結論としてもあまり間違えていなかったのだと言えるのかもしれない。 今後、電子書籍が一般的になったとき、読書の技法は別の形式を獲得することになるのかもしれない。読書ノートなどは、Evernoteのようなクラウド型のアプリが活用されるべきだということになるだろう。著者は、電子機器は壊れたときにその内容が失われてしまうこと怖れて紙のノートを重要視しているが、現在では紙のノートよりもクラウドでの保存の方が信頼性が高いということが当然ありうる。ただ、そうやって具体的な手法が変わったとしても、超速読、速読、熟読の区別からなる読書の技法はそのまま生き残ることだろう。 また本書では、方法論だけでなく、その方法論を適用した様々な分野の書籍が取上げられている。小説の分野で取上げられているのが村上春樹『1Q84』とミラン・クンデラ『存在の耐えられない軽さ』である。自分の趣味とも合っていて少しうれしい。どちらの作家の作品も大抵読んでいる(そういう作家は多くない)。クンデラがチェコの作家であり、著者の専門の神学で研究対象としたのがチェコのフロマートカであることを考えると、よく知っていることは理解できる。当時の共産圏の知的状況を知る上でも有用なのだろう。また村上春樹は「時代とともに歩いていくことのできる数少ない作家である」と持ち上げる。賛成。ただ、『1Q84』を合わせて出したのは、クンデラの父親が『1Q84』で出てきたヤナーチェックの高弟で、ヤナーチェック音楽大学の学長であったという蘊蓄を実は語りたかっただけなのかもしれないな、とも少し思う。『1Q84』の2つの月の解釈や、鳩山由紀夫の沖縄を巡る右往左往、ゲゲゲの鬼太郎のねずみ男に対する解釈は面白いが不思議。 また、著者は超速読、速読をするためにも基礎知識を身につけることの重要性を説いているが、その基礎知識を身に付けるためには、高校受験解説書が役に立つとして、かなりの紙幅を割いている。ちなみに自分は高校受験で倫理政経を選択したため、日本史も世界史も知識面が非常に弱い。高校での勉強を高く評価しているが、確かにそうだろう。自分でもそのころ身に付けた知識と論理と技法がベースになっている。また高校の勉強は基本的には知識と論理の2つを問い、各教科はその配分が違うだけだと言うが、現代文がほぼ論理の教科だというのは、目からうろこだ。 本書でも紹介されているが、著述と読書を繰り返す著者の生活はある種自分の理想でもある。読書の技法の前に、生活スタイルの技法であるようにも感じた。 ---- ところで、高校時代の同級生が書いた『モスクワの孤独』を佐藤優が読んだとしたら、どういう評価をするのか、とても気になった。サントリー学芸賞を受賞したロシアのインテリの世界を描いたこの本は、著者の熟読の対象なのだろうか。自分の部屋で積ん読状態のこの本の価値を教えてほしい。
1投稿日: 2014.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ多量の必読書類への対処法としての速読という視点と、内容を定着させるための読書ノートの重要性の指摘がとても参考になった。 前者の要点は、新聞と同じように、自分に必要な部分だけ読めばいい、ということ。 後者の要点は、線を引いて抜き書きして3度読むこと。 具体的なテクニックも満載。 日本史・世界史の基礎知識をボトムアップしなければ、と痛感した。
0投稿日: 2014.08.11実践するのは至難!?だが面白い!
とても面白かった。 が、常人にこの読み方ができるだろうか、とも思う(笑) まず、佐藤さんは非常に頭の回転が良い。この速度で回転させるのは頑張っても難しい。 それから、惜しみなく紙の本に書き込める佐藤さんには本を買って収納できるだけのお金とスペースがあるわけだが、 多くの人は毎月何百冊の紙の本に「書き込みをする」というのは難しいだろう。 また、職業や体力の関係で佐藤さんほどの読書時間を取れない人も多いと思う。 だから、本書に書いてあることを「実践する」のは難しいが、 「佐藤優」に興味がある者には非常に面白いし、「技法」の背後にある「姿勢」を学ぶことはできると思う。
2投稿日: 2014.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ圧倒的な読書量と知識を持つ佐藤氏が教えてくれる読書法。 大事なところを囲んでいくというのはやったことないので、勉強書籍を買った際には試したい。
0投稿日: 2014.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログとても読書意欲をかきたてる本です。 私も読書は好きなのですが、たくさんの本を読んでも実際に自分の血肉となってる本は、ほんの数パーセント程度であるのが実感であり、もっと効果的な読書法はないかと感じておりました。 ちょうどそんなときに当作品に出会い、特に熟読法についてはとても参考になりました。 まずは、アンダーラインやコメントを本に書き込みながら読むことと、読書ノートを作ることは実践してみようと思います。
0投稿日: 2014.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本自体が分厚くて読むのがたいへんだが、書かれているとおり、必要な情報(読むときの注意点)だけピックアップして読んだ。 ・自分の学力水準にあわない専門書をよむも、中身を消化できずに時間を浪費しているケースが多い。 ・大切なのは自分の知識の欠損部分を知り、それを補うこと。 ・重要なことは知識の断片ではなく、自分の中にある知識、言葉を用いて現実の出来事を説明できるようになること。 →体系的に習得することか。 ・速読には100%理解しようとする完璧主義は捨てること。また、一方、もう二度と読まないという気持ちで、読むこと。 ・重要なのは、仕事で使うこと、将来必要となることを学ぶこと。同期なしにダラダラ読むことは機会費用の無駄。 ・詳しいことを知っている人に聞くことは大変良い。しかし、聞く前に調べておかないと、大事な部分を聞き逃すかもしれない。 ・大国に囲まれているから、チェコ人は墓にこだわる。 時間は限られているので、ダラダラやらない、時間を区切って、読む。終わりからイメージする、というのも大切だ。
0投稿日: 2014.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでみた感想だが、特に役に立った感じはしない。 速読法も、正直ピンと来なかった。ただ本当に何百冊と本を読む人にはお勧めなのかもしれない。 ただ本を読んだ後のノートのとりかたなどは勉強になったので星4つです。
0投稿日: 2014.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者は月に300冊以上読み、英語、ドイツ語、ロシア語の本も読み、1日3時間しか寝ず、1日6時間読書をするという強者なので、筆者が提唱する読書法を実践できる気がしなかった。 今まで同じ本を繰り返し読むということをしていなかったので、それは実践してもいいかなと思った。歴史小説は興味を持つきっかけにはいいが、どこまでが史実でどこからが脚色かわからないので、動機付けだけにとどめるべしというのは納得。
0投稿日: 2014.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書の技法 / 佐藤 優 / 2013.03.13(7/135) 「この」が示す事柄を正確に理解する。 クレヨンしんちゃん、おすすめ。 存在の耐えられない軽さ 小説は「代理体験」 相手に自分を強く印象づけるために、短い期間(一か月以内)に3回会う。また、重要な人脈を維持するためには、相手と3週間以上の空白を開けてはならない。クンデラ、3の規則 詐欺師入門 騙しの天才たち その華麗なる手口
0投稿日: 2014.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤さんの真似はおそらくできないと思われるが、本の選び方の参考になった。また、勉強や読書の意欲がわいてくる一冊。図書館で借りて読んだが、次回、購入したいと思う。
0投稿日: 2014.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ受験生にはこの本で書かれている勉強法が参考になると思います。また,これから読書の時間がたっぷりとれる大学生はぜひとも手に取ってほしい一冊。 私はこの本を読んで,限られた時間の中でこれからは読んでいく本を厳選していこうと強く思いました。 読んでよかったです。
0投稿日: 2014.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ期待したような内容と異なり、私にはあまり多くの情報を得られなかった。でも短時間で読める本なので、投資した時間分は回収できるかも。
0投稿日: 2014.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ試してみようと思います。 後半の教科書の読み方部分は読書の技法の中に収めなくても良かったんじゃないかなぁ、と思ったが、読書を進めるための基礎知識ということでしょうか。
0投稿日: 2014.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎教育の重要性が強調されており、それが印象的。著者は自分のノート作りを実施している。この本が後押しになり自分も始めた。また「速読」と「熟読」の使い分けが重要だと分かった。
0投稿日: 2014.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログコンクリ殺人事件、名古屋アベック殺人事件。更には、秋田のカルトセックス教団。韓国の歴史捏造アジ。インターネットを通じ、気色の悪い記事に触れた。価値観の違う、到底共観できない身近な世界。人間の価値基準において純粋な悪というのは存在し得るし、対峙し、家族や友人を守らねばならない。そのためには、知力が必要で、読書はそれを高める有効な手段の一つだ。佐藤優は、どのように知力を高めたのか。読む速度は多種あるにせよ、読み流さない事。受肉させるには、メモ、暗記、納得。そして、活用である。本著を読むのは二度目であり、速読した。
0投稿日: 2014.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
デブサミ2014のITエンジニアに読んで欲しい技術書・ビジネス書大賞にノミネートされていた本。 参考: http://thenextbook.jp/award/vote 読書術系の本は眉唾物が多い印象なので、あまり読まないのだが、amazonのレビューを見たところ、そういう類の本ではないようだったので読んでみた。 「時間は有限であり、希少材である。」 この本ではこの考え方が根本にあり、著者がそこから無駄なく知識として定着させる読書法は何かと模索していった過程と結論が書かれている。 結果的に、読書のパターンとして超速読、速読、熟読の3つを上げ、これらを使い分けることで読書量を上げるということが本書の大枠のようだ。 超速読は「自分にとって有益な本か」「時間をかけて読むに値する本か」の仕分けをするために行う。読まなくていい本はこれによって切り捨てる。 速読は「内容を大雑把に理解・記憶して、どこに何が書かれているかインデックスを頭の中に整理して作ることが目的となる。 熟読は自分にとって重要であると感じた本の内容を体得するために行う。 速読と熟読では読書ノートを取るようだ。読書ノートには本の重要事項を抜書きし、それに対して自分の意見をメモする。手を動かすことによって知識として頭の中に定着させる。 以下にそれぞれのやり方をまとめた。 ・超速読・・・5分で序文の一部、目次、結論を読んだ後、全ページひたすらめくる。 ・速読・・・何を知りたいのか、目的を明確にし、1ページ15秒ほどで読む。重要箇所に線引、ポストイットの貼り付けをし、読み終わった後に重要箇所を読書ノートに写す。 ・熟読・・・3回読む。一回目は重要箇所に線引、2回目に線引箇所を絞込み、より重要な箇所だけに囲みをつけ、読み終わった後に読書ノートに抜き書きする。3回目は目次の構成を頭に叩き込んだ上で結論部を三回読み、その後通読。 読書の順番にも言及しており、基礎的な知識が無い分野の応用書を読んでも無駄であること、高校レベルの学力があれば大抵はなんとかなるが、ビジネスパーソンは見栄のせいで自分の知識の欠損部分を見ようとしないことなどが挙げられており、基礎学力を補うことの重要性が訴えられていた。 自分を振り返ってみると、英語があまりできないのに洋書の技術書を読んでみたり、入門書を1冊読んだだけで応用書に移ったりと確かにその傾向がある。 断片的な知識(Wissen)ではなく、体系知(Wissenschaft)として自分の知識を振り返り、欠損部分を探し、欠損部分を埋める。長い目で見た時には結果的にこれが得となる。 ということで早速高校レベルの英語、現代文、論理の参考書を買ってきた。 (本書で「現代文は論理的思考能力を問う教科」だという言葉に見事に刺激された。) 明らかに欠損している部分だけでなく、補強する意味でも一旦基礎に立ち戻ろうと思う。 こういう「基礎が大事だ」というのは分かってはいるのだが、中々行動に表せられなかった。今回、行動に移せる動機付けができた点で、いい本に巡り会えた。読書の仕方だけでなく、何を読むべきか迷っている、もしくはより効率的に知識化する方法を模索している人におすすめの本。
0投稿日: 2014.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『読書の技法』 佐藤優 【読書の技法1】 まず本の真ん中くらいのページを読んでみる。(p59) ★前提として、小説などではなく、難解な本や学術書を読む時の技法。 珍しい読み方。基本書を3冊用意し、真ん中あたりを読み、内容を軽く把握。本をどれから読むか選ぶ。 【読書の技法2】 シャーペン(鉛筆)、消しゴム、ノートを用意する。〈第一読〉(p62) ★その理由として ……重要な記述と思われる部分の欄外に線を引きながら読む。特に重要と思う部分についてはページの橋を折る。ページを折るのに抵抗がある人はポストイットを貼ればよい。(p83) ★とのこと。 【読書の技法3】 シャーペンで印をつけながら読む〈第一読〉(p63) 基本書は、最低3回読む。第1回目は線を引きながらの通読、第2回目はノートに重要箇所の抜き書き、そして最後に再度通読をする。(p83) ★この第1部は大まかに、上記の内容となる。最後の通読は内容に飽きてしまうが、本を把握した満足感と共に読みたい。 本を読みながら、重要と思う部分の欄外に線を引き、わからない部分については「?」マークを記す。重要な部分かどうか迷ったら、とりあえず線を引く。(p64) ★先ほどの【読書の技法2】と合わせて。 【読書の技法4】 本に囲いを作る〈第二読〉 (p66) ……まず、1回目に線を引いた部分で特に重要と思う部分をシャーペンで線を引いて囲む。(p67) ★さらに引用をスリムにさせる。 【読書の技法5】 囲い込みの部分をノートに写す〈第二読〉 (p68) ★重要な所のみ写す。 【熟読の技法6】 結論部分を3回読み、もう一度通読する〈第三読〉(p69) ……もう一度、通読するのであるが、まず目次の後世をよく頭にたたき込んだうえで、結論部を3回読む。(p69) ★p83でも既に書かれている。 まず、2〜3日かけて第一読をする。その際に重要箇所についてはシャーペンで枠に囲み、その部分にポストイットを張る作業も同時進行する。 その後、枠に囲んだ部分のうち、特に重要な内容を1〜2日でノートに書き写す 。(p71) ★2冊目以降の基本書について。最初に述べているが、基本書は3冊用意すること。 筆者は速読を「普通の速読」と「超速読」 に分けている。 「普通の速読」とは400ページ程度の一般書や学術書を30分程度で読む技法である。……「超速読」は、前述の書籍を5分程度で読む技法で、試し読みと言ってもよい。(p76) ★この2つはキーワードとしてこの後出てくるので引用。 ①熟読する必要があるもの ②普通の速読の対象にして、読書ノートを作成するもの ③普通の速読の対象にするが、読書ノートを作成するには及ばないもの ④超速読にとどめるもの(p77) ★本を4つのカテゴリーに分ける。なるほど。そう分けたのは初めて見た。 まず準備するのは、本とシャーペン(鉛筆でも可)とポストイットである。 それから、最初のころは横に時計を置き、一冊を超速読するのに5分以上かけないと固く心に誓う。 まず序文の最初2ページと目次を読み、それ以外はひたすらページをめくる。 (p77) ★「超速読」について。続けて。 原則として、時間がかかるので一行一行、線は引かない。 しかし、何か気になる語句や箇所が出てきたら、後でわかるようにシャーペンで大きく丸で囲むなど印をつけ、そのうえでポストイットを貼る。ポストイットを貼るのが面倒ならば本のページを折る。 そして結論部の一番最後のページを読む。(p78) ★長く引用。とにかく時間をかけないで印象を残すこと。 ……自分の本棚にあえて「積ん読」本のコーナーを作り、5〜6冊たまった頃合いを見て、超速読をしてみることだ。 休みの日に、超速読を用いて30分くらいで全冊、全ページに目を通せば、何らかの発見があるはずである。(p80) ★実践してみたい。 【普通の速読の技法1】 ……本の内容を100パーセント理解しようという「完璧主義」を捨てることだ。(p88) ★本を読む上で大切なこと。 【普通の速読の技法2】 雑誌の場合は、筆者が誰かで判断する(p89) ★雑誌の例として『現代思想 総特集ヘーゲル『精神現象学』二〇〇年の転回』など つまり、著者がその分野で著名であれば買う一つも目安になる。 【普通の速読の技法3】 定規を当てながら1ページ15秒で読む。 (p91) ★同じ箇所を読んでしまうときに。 【普通の速読の技法4】 普通の速読の場合も、熟読同様、シャーペンとポストイットは必需品だ。シャーペンを持ちながら重要な箇所を丸で囲んだり、傍線を引いて識別できるようにし、そのページにはポストイットを貼る。(p92) ★速読でも同じ。p77参考。 【普通の速読の技法5】 本の重要部分を1ページ15秒、残りを超速読する(p94) ★例えば目次、前書きと結び。この「普通の速読」は新聞を読むときと似ているとある。 【普通の速読の技法6】 大雑把に理解・記憶し、「インデックス」をつけて整理する。(p95) ★人間だからこそ、この適当さが生きてくる。頭の中に整理していれば、必要なときこのインデックスにたどり着けるだろう。 ここまでで、読書法は終了。次の章は読書ノートの作り方。 ゆるい形で本を読む習慣が身についてしまうと、いくら本で知識を取り入れても、頭の中に定着していかない。(p101) ★肝に銘じたい。とても大切。 読書ノートを作る最大のポイントは、時間をかけすぎないことだ。30分なら30分、1時間なら1時間と自分で時間を決め、それ以上、時間をかけないようにする。(p101) ★ついつい時間をかけすぎてしまう。間に何か挟んでしまったり。参考にしたい。 大切なのは正確な形でデータを引き出せることと、積み重ねた知識を定着させることで、完璧なノートを作ることではない。(p103) ★知識の定着は繰り返しノートを見ることである。以上読書ノートについて。 小説には「代理経験」の側面もある。人間が個人的に経験できることは限られている。(p221) ★こ「小説やマンガの読み方」より。この本書ではいわゆる小説はあてはまらない。 ……夜中に読むのは、何度でも読み返す基本書や過去に読んだ本など、記憶に定着させたいものが多い。新しく読む本なら、すでに通読しているテーマのものを選ぶようにしている。(p250) ★夜は既読、かつチェックしていない本を読むようにしてみたい。
0投稿日: 2013.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ知は力であり、力は知である。知力をつけるために必要なのが読書。 知は基本的に先人の遺産を継承したうえで成立している。このことを理解せずに高望みだけして、難しい本を力技で読んでも知識は全く身につかない。
1投稿日: 2013.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ非常に興味深く読んだ。 速読にも種類があること、 特に、自分自身不足を感じていた、学生時代の基礎学力。 これを身につける箇所は目に鱗であった。 社会人としてやって行くに当たり、国語力には常に懸念を感じていた。 これを気に身につけたい
0投稿日: 2013.12.30「知の巨人」による読書遍歴と「受験の神様」ばりの受験書指南
むかし立花隆、いま佐藤優。「知の巨人」による読書遍歴を公開と思いきや、途中から「受験の神様」和田秀樹の御株を奪うほどの受験書指南が始まる。 いわゆる「国際的なビジネスパーソン」に向けて書かれた本で、すでに12万部を突破という帯を見て、そんなにこの層は多いのかと疑問に思った。 私は一冊を読むのにも四苦八苦している現状を打破したいと手に取ったが、キリスト神学の本を読んでる時が息抜きで、仮眠は15分程度で切り上げ、日付の変わる0時から自分のための読書に打ち込む著者の姿に、ただただ畏敬の念を感じてしまった。 スマホやネットなどの誘惑をどうやって退けるかなんて悩みを共有してくれるのは、デヴィッド・L. ユーリンの『それでも、読書をやめない理由』の方だったな。ただペンを持ち本に直接書き込むって言う結論は同じだけど。
4投稿日: 2013.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ限られた時間で情報収集を目的として本を熟読するためには、読むべきかどうかを選別しなければならない。そのために、速読、超速読を使うという話。 速読術だけを期待すると、その部分はそれほどクローズアップされていないので少し的外れかも。 個人的には、教科書を使ってビジネスマンとして必要な知識を再習得する項が興味深かった。
0投稿日: 2013.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ大変参考になる。色々と読書法の本は出版されており、自分もその中のいくつかを実践してみたが、どれも続かなかった。しかし、この中で紹介されている方法は1年近く続いている。オーソドックスな内容であり、参考にしやすく、かつ有効である。
0投稿日: 2013.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ熟読する本を探すための超速読(時間を限る) 基本書の熟読(分かりやすいものから,本の真ん中で雰囲気を判断) 高専レベルの数学が重要 読書会をやる 場所を選んで読書する
0投稿日: 2013.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ速読で読む本をふるいにかけ、熟読して読書メモを作って自分のものにしていく、というメソッドは他の読書術と同じ。ただ、高校までの勉強が教養の基礎である、という断言、そしてコミックは動機づけに使い、小説を代替体験に使う、という意見は「なるほど」と思わされた。外務省出身だけに外国語に対する意識も高く、外務省キャリアの激務ぶりも垣間見え、色々興味深い。
0投稿日: 2013.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ目的を持っての読書ならびにその読書からの、インテリジェンスの抽出についてまとめられている。 ノートの取り方などが具体的に述べられており面白い。 著者の言うところの速読で処理したので、評価はこれくらいかと。
0投稿日: 2013.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「筆者が、サーシャやアルチューノフ先生の膨大な読書量から学んだのは、その見た目の読書量ではない。そうではなく、その根底にある基礎知識と強靭な思考力と、それを身につけるための熟読法である。基礎知識があるからこそ、該当分野の本を大量に読みこなすことができるのだ。」p43 「読書の要諦は、この基礎知識をいかに身につけるかにある。」p45 「いずれの形であれ、未知の分野で本を選ぶには、『水先案内人』が必要になる」p54 「基礎知識をつける場合、あまり上級の応用知識をつけようと欲張らないことだ。自分の学力を客観的にとらえることができず、消化できない基本書や専門書に取り組んで時間を浪費している例が多い。特に東大、京大、早大、慶大など難関大学の卒業生で、学生時代の成績がそこそこ良かった人にこういう例が多い。読書法を根本的に改めないかぎり、こういう人が知識を集積していくことはできない。」p56 「基礎学力をつける段階で客観的な自己評価ができないと、間違った読書法をしてしまう。自分の知識の欠損部分を知り、それを補うことだ。」p57 重要なことは、知識の断片ではなく、自分の中にある知識を用いて、現実の出来事を説明できるようになることだ。そうでなくては、本物 の知識が身についたとは言えない。ドイツ語で学問(科学)をヴィッセンシャフト(Wissenschft) という。断片的な知識(Wissen)ではなく、知識を結びつけて体系(‐schaft)になって初めて体系知として学問(科学)になるという考え方だ。戦前の旧制高校で、カントやヘーゲルなどのドイツ古典哲学を学生に徹底的に教え込んだのも、体系知という技法を身につけさせるためだ。物事を体系的に考えることは、エリートとして国家や企業を指導する
0投稿日: 2013.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ誰にでも習得できるという読書の方法論を公開 相当凄そうだが.. やってみる価値は幾分もある だけど何のために? そこがなければ、職業としてやるわけでもない我々は 目的を見失った、否、目的もないまま旅行することによって 己の退屈さを紛らわすだけの無為な徒労に終わってしまうばかりであろう。 現実を虚心坦懐に認め、自らの欠損を早く埋めたものが最終的に得をする。 この部分は私は重々受け入れなければならない。 認識と受け入れ 最初の関門を、 この門はいつ何時も私の前に立ちふさがる。 少しかじって付け上がったとき、 否、自惚れているという認識すら自覚・所有していないとき、 否、自惚れているという認識すら自覚することを体で拒絶しているとき 現状の認識は、問題解決時の問題の把握と同様大にして最も基なるものだ もういやだ
0投稿日: 2013.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ思い描いていた本とはかけ離れていて、蔵書もさることながら読書 量もレベルも違いすぎる中、参考にはなった。 一生で読める本の数 は限られているからこそ速読の目的は読まなくても良い本をはじき出すことと仰る。 歴史小説読むより先ずは教科書を読む事の大切さ なんですね。 教科書も学生時代受け入れられなかったが、今一度読むときっと為になるだろうな!
1投稿日: 2013.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ佐藤優氏の本は以前に数冊呼んでおり、好きな著者ではある。 内容としては、私には難しく、全般を参考とすることはできなかった。 参考となる本も高度なものが多く、紹介されている技法も高度であり、身につけることはできないと判断した。 しかしその中で読書ノートは実践すべきものである。 こうやって書評は書いているものの、読み終わって時間がたつと内容を忘れていることが多い。記憶に残らないものは自分に不要なものであるとの判断もできるが、「あれはなんだったかなぁ?」ということのほうが多い。 今後は、自分に必要と思ったものは簡単であっても読書ノートとして残していこうと思う。
0投稿日: 2013.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで殆ど本を読むことはなかったので、残り短い人生でより多くの本を読む為、自己啓発の為、本物の読書ができる様に購入しました。 ただ読むだけでなく利点を得て吸収出来る様に必ず熟読速読を体得します。
1投稿日: 2013.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校の世界史や数学をやり直したくなる。基礎的な知識がない分野の本を読んでも上滑りするだけだから先ずはその分野の基礎を作るべき、というのは正に的を得ていると思った。
0投稿日: 2013.10.16
